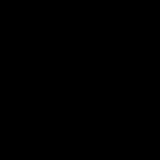国宝のレビュー・感想・評価
全2429件中、61~80件目を表示
恐ろしく美しい映画でした
文芸作品だと思って避けてきましたが、エンタメとしても面白いとのことであり、ようやく見てきました。成程、これは絶賛される分けです。
エンタメとして面白い要素は、所謂、お仕事モノとしての部分でしょうか。あまり一般に馴染の無い歌舞伎界の裏事情や、そこで才能を開花させのし上がっていく主人公の痛快さ等、見ていて飽きません。
美を極める為に人は鬼にならねばならぬ。私のような凡人はそれほどまでにして追い求めなければならない美とは果たしてどういう物か?などと思うのですが、この映画ではしっかりと解答を出してきています。「美とはこれです」と。
それはもう凄まじいものでした。歌舞伎ってこんなにも美しいものだったんですね。ただただ映画に酔いしれていました。
この美を作るために、恐らく、監督も鬼になったことでしょう。ほんの一端しか分かりませんが、例えば、私だったらこのテーマで映画を作るなら、恐らく、歌舞伎役者をメインに据えてしまうと思う。しかし、実際には歌舞伎役者以外を主にキャスティングしている。総合的判断とは思いますが、多分、大きな要素は「顔」だと思います。歌舞伎の演技は後から叩き込めばなんとかなるが、持って生まれた顔だけは如何ともしがたい・・と。これは、ある意味、エゴですね。
そのエゴに付き合わされた役者さん達も大変だったと思います。主演の吉沢亮さんなんて、人間国宝級の演技、普通の歌舞伎役者の演技、未熟な頃の演技(さらには平場の演技を何種類も)を、1つの映画の中で演じ分けなければならないのですから。
全体の感想は、恐ろしいまでに美しい映画でした。テーマ自体は地味なので、この映画を世に広めたアーリーアダプターの皆様のご慧眼に感服です。
当初は観るつもりなかった…
よく行く映画館の外、入口の端っこにぽつんと立っているポスターを貼る小さな看板がある。だいたい公開中の話題の映画ポスターが貼られている。
ある時、とある映画のポスターが貼られた。タイトルは『国宝』というらしい。自分は基本的に映画館に行くとき、ポジティブな気分になりたいので暗い雰囲気、特に実写邦画は殆ど観ない。国宝も自分に合う映画とは思えなかったのでスルーしていた。
ただ1ヶ月半過ぎてもポスターが変わらず、何回も前を通るとさすがに何か気になってしまった。レイトショーで日付が変わる時間だが観に行けるタイミングがあったので家族に遅くなることを伝えて映画館に足を運んだ。
傑作映画だった。吉沢亮さん、横浜流星さんの演技は素晴らしく、次の日本アカデミー賞の主演男優賞、助演男優賞は決まったなと思った。ただ、それと同時に3時間で半分以上は悲しい展開だし、自分が苦手なタイプの映画でエンドロール流れている間に二度と観ないと思いながら家に帰った。
その後、監督や演者、照明さんなどのインタビュー動画を観た。監督による撮影秘話や演者のこの映画にかける想いを聞いたら、また観たくなって本日2回目の鑑賞。今度はエンドロールでKingGnu井口さんの歌声、坂本美雨さんの書いた歌詞を噛み締めながら聴けた。
この時代にこの映画を見れて幸せだと思った。製作に携わったすべての方に感謝。
久しぶりのスクリーン
話題になって大分経ちました。
映画は好きで若い頃は一人でも観に行ってましたが。
今回は、朝イチの回で、日頃の疲れもあり、寝てしまうんではないかと思っていましたが。
寝てる暇なんてありませんでした。
歌舞伎は、高校生の時に一度観てあまり魅力を感じませんでしたが。
歌舞伎の裏側に興味をそそられました。
そりゃ隠し子いてもしかたない。
そして、吉沢亮くんが、横浜流星くんの血をガブガブのみたいと言ったシーン。
歌舞伎は血が濃い。結局、血なんだと。
でも、その血が災いになったり。
観た友人から、ガラスの仮面の歌舞伎版みたいだよって、言われたけど。
そんなところもあり、そうでないところもあり。
洋画も邦画も観ますが、邦画好きな私にとって、久しぶりにスクリーンで観た映画がこの作品で良かったと思いました。
あまりの高評価に観に行ってきました。吉沢亮、横浜流星は頑張ったと思...
歌舞伎の世界に限らず
映画館で観ないと、迫力や息遣いやあの空気感は味わえなかったと思う。
綺麗事だけではすまない世界で、人の想いが交差する世界を多角的な視点から捉えていたことで、立場の違うさまざまな人の立ち位置から思いを馳せたり感情移入をすることが出来て楽しめた。
きっと今置かれてる環境の違いや観るタイミングの精神状態で見方(感じ方)の変わる映画だと思った。
半世紀に渡る一代記
174分の上映時間を全く飽きさせません。台詞よりも映像で、極道の息子と御曹司という、対照的な二人の成長が描かれています。とにかく、吉沢亮と横浜流星が本物の歌舞伎役者と見間違えてしまう程に美しいです。李相日監督は。大名跡を継ぎながらも結局は御曹司ではないことに苦悩する喜久雄に、日本に生まれ育ちながらも在日コリアンとしての宿命を背負う自分自身を重ね合わせたのかもしれません。また、喜久雄の実母が原爆症で亡くなったという映画独自の設定には、反核のメッセージが込められているようにも感じられます。クライマックスの曽根崎心中は、喜久雄と俊介の魂が激しくぶつかり合い、まさに壮絶の一語に尽きます。鑑賞直後に、市川團十郎丈の感想動画をYouTubeで見ましたが、投稿欄に非常に興味深い考察が多数寄せられていたので、そちらも必見です。
レスリー・チャンの、さらば我が愛を彷彿とさせる
大河ドラマのような超大作。歌舞伎の演目パートに時間を割かれており賛否両論あるようだ。詳しくない人にも歌舞伎の魅力が伝わって良かったと思う。演出、キャスト、ストーリーどれも秀逸。妖艶な女形を演じられたのは吉沢悠と横浜流星のビジュアルがあってこそ。田中泯演じる人間国宝も貫禄がヤバい。愛人の見上愛、梨園の妻になる高畑充希、幸薄そうでよい。渡辺謙と寺島しのぶはもう役そのもの。3時間なのに集中力途切れず、気がついたらなぜか泣いてた。李相日監督×吉田修一は裏切らない。絶対に映画館で見るべき作品で間違いなし!
類似作品を思い出してしまって
まず褒めます 少年期役 黒川想矢さん 最高に魅力的でした
少年期編はすごい引き込まれ凄みを感じて観ていました
が、青年期編に入ると周りの席のガサガサ雑音が気になりだし
自分が物語から引いている(つまらなくなってる)事に気が付きました
ラストのほうはものすごく駆け足で、キャラクターの行動原理に疑問が多くなり、、、
類似作品に触れます
「昭和元禄落語心中」という漫画原作、アニメ、ドラマ化された作品です
要素にとても類似性が有り 個人的にはこちらのほうが素晴らしい人情劇になっていて大好きな作品です
この類似性を言及されてる方がネットでも散見されますので、知ってる人は思いついちゃうんですね
あまりに類似する(全く同じではない)ので、もっとなにかぐっと来るポイントがあればここまで酷評はしませんでしたが残念でなりません
単に自分には合わなかっただけで演者の見せ方演技努力は一級品で文句はありません
酷評されるべきは監督の力量だけです
歌舞伎の映画かぁ(;´д`)…
今更ながら
「国宝(今頃)観た」
存在も美しさも、リアルの対極としてのファンタジー
家族を失い、親が興行を世話していた縁から名門の歌舞伎役者に弟子入りした少年・喜久雄が、芝居に生涯を賭す物語。
舞台の上の演者たちを、芝居の上手い人間ではなく美しい存在として撮ろうという執念を感じる映像だった。歌舞伎の舞台を観る目的では見られない角度からのシーンが新鮮だった。
半世紀もの時間を扱う本編では、喜久雄と俊介の友情と衝突が中心に描かれる。サブキャラクターたちから垣間見える感情や、彼らもまた同じ穴のムジナであることも面白い。
喜久雄が出世することや彼が役者を続けられる点など、ファンタジーが多いことも含め、昼ドラのような物語だった。悪魔との取引という表現通り、人らしい幸せや良心を捨て芸に執念を燃やし続けたから頂点に立てた、という筋書きは理解できるが、半世紀を描く物語の終盤に向かうほどダイジェスト感が強くなるのは残念だった。
俊介を見送り、同世代のライバルがいなくなったと同時に今後の確かな後ろ盾を失った喜久雄がどうやって頂に至ったのか、終盤とエピローグを繋ぐ部分が気になった。
作中では最高峰の女形として小野川万菊という人物が登場する。名跡に生まれ、喜久雄と同じように芸だけを磨き続けた彼の域に喜久雄は至れたのだろうか。
伝えたい事と映像が少し違うような気がします
全2429件中、61~80件目を表示
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。