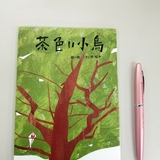「報われぬ覚悟の美学」国宝 こひくきさんの映画レビュー(感想・評価)
報われぬ覚悟の美学
歌舞伎という閉じた世界を題材にしながら、芸術と人間の宿命を描いた力作。長崎に生まれ育った青年が、血縁のしがらみもない名門に身を寄せ、やがて人間国宝と呼ばれる境地に至るまでを3時間近くにわたって描くのは、近年の邦画として異例の挑戦。公開初週こそ空席が目立ったが、口コミが観客を呼び込み、2003年公開の「踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!」以来、実写の邦画作品としては22年ぶりに興行収入100億円を突破した。内容が評価されて伸びていく実写邦画は久しくなかっただけに、観客の支持が数字に直結するという原点を見せつけられた格好だ。
では、なぜこれほどまでに支持されたのか。ひとつには、俳優陣の演技が作品の重厚さを支えている点が大きい。吉沢亮の鬼気迫る表情、横浜流星の葛藤に揺れる佇まい、渡辺謙の圧倒的存在感――舞台芸術の緊張感を映画という媒体に落とし込む力量は特筆に値する。観客は「虚構の中の虚構」である歌舞伎の演目をスクリーン越しに覗きながら、それが同時に役者たち自身の人生の断面でもあることに気づく。その入れ子構造が、単なる芸道ものを超えて、普遍的な人間の営みへと昇華している。
ただし、手放しで絶賛するのは容易だが、いくつか課題も浮かぶ。まず尺の長さである。175分という長尺は、観客に緊張感と没入を与える一方で、中盤の展開の冗長さや説明不足を助長している。原作小説で描かれた人間関係や背景が端折られたために、感情移入できずに置いていかれる観客も少なくない。また、歌舞伎という文化的素養が前提になっているため、芸能に馴染みの薄い層には難解に映る場面もある。興行的な成功と裏腹に、作品の門戸は決して広くはない。
一方で、この映画が日本の労働観や組織観とも地続きである点に注目したい。芸道にすべてを捧げるという姿は、サラリーマン社会における「会社人間」の宿命と重なる。血筋や序列に翻弄され、時に不条理に打ちのめされながらも、信じる道を突き進む。報われる保証もなく、それでも積み重ねを辞めない。その姿勢が、芸の世界でもビジネスの世界でも共感を呼ぶの。『国宝』が単なる歌舞伎映画の枠を超えて社会的な広がりを持ち得たのは、観客一人ひとりがそこに自分の姿を重ねられたからではないだろうか。
総じて、『国宝』は2025年を代表する邦画となる可能性を秘めている。日本アカデミー賞での受賞も視野に入り、海外映画祭での評価も期待できる。課題を抱えつつも、それを凌駕する熱量とテーマ性がある。芸術とは何か、人間とは何か――その根源的な問いを正面から観客に投げかける勇気を持った映画が、ここまで多くの人の心を動かしている事実自体が、この国の文化にとって大きな意味を持つのではないか。
こひくきさま。共感及び嬉しいコメントありがとうございます。
「この映画が日本の労働観や組織観とも地続きである点に注目したい。芸道にすべてを捧げるという姿は、サラリーマン社会における「会社人間」の宿命と重なる。血筋や序列に翻弄され、時に不条理に打ちのめされながらも、信じる道を突き進む。報われる保証もなく、それでも積み重ねを辞めない。その姿勢が、芸の世界でもビジネスの世界でも共感を呼ぶの。」には、なるほどそうだったか!と感動を覚えました。一緒に見た妻があまり感動しなかった理由が、腑に落ちました。
こひくきさま
『宝島』『国宝』に共感とフォロバ、ありがとうございました🙂
レビューアップしていない作品にも、「こくひき文学」のレビューにたくさん共感してしまいました。
他に重なるレビューは『鬼滅の刃』だけなので、遅筆&長文ですが、共感していただけるようなレビューを書けたら…と思っています🫡
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。