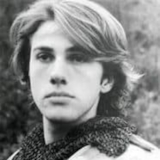「問題提起をしない「歌舞伎」映画」国宝 talismanさんの映画レビュー(感想・評価)
問題提起をしない「歌舞伎」映画
関の扉に始まり鷺娘で幕が閉まるので、歌右衛門(六代目)と玉三郎を想起させられた。田中泯演じる万菊は闇の底からおどろおどろしく出てくる存在で、大昔に見た歌右衛門みたいだった。女形は年取ると性別を超越する、それを田中泯は素晴らしく演じていた。
話の中で特に重要な芝居が「曽根崎心中」なので、近松を復活させた上方歌舞伎の坂田藤十郎の息子の雁治郎が歌舞伎指導&出演で関わり、その息子で、踊りが上手くまだ30代の壱太郎(吾妻徳陽)が日舞指導をしたのはよいと思った。
吉沢亮の白塗りに紅の顔に、レスリー・チャンの類稀な美しさとしなやかな身振りを思い出した。60代になってからの鷺娘では、首の縮緬皺や手の甲の皺が積み重ねた年月を表していた。因縁の「お初」を横浜流星、徳兵衛を吉沢亮が演じる舞台。有り得ないこと続きで驚きつつも、涙なくして見ることができなかった。お初が徳兵衛の覚悟を自分の足で確かめるのが見せ場の芝居。文楽では女形のお人形に足はないが、お初の人形には足がつく。そのお初を左脚がない半弥(流星)が演じる。この芝居の道行きではお初が先導するのに、右足も壊死しているお初が花道で倒れた時、どうなるのか心臓がバクバクした。にも関わらず、或いはだからこそ心中場面も続けると言う徳兵衛・吉沢亮。その血を羨んだライバル・親友のとどめをさす、という演出なのか。
「壊死」で、幕末から明治まで活躍していた美貌の女形の三代目田之助について読んだことを思い出した。田之助は壊死で四肢切断しても舞台に出続けていたが廃業し33才の若さで亡くなったという。血の繋がりは顔かたちや体型や声だけでなく、病も遺伝するとしたら堪らない。芸は血の繋がりというより、生まれた時から親と同じ環境の中で生活し呼吸し見て聞いて、一日中、歌舞伎の空気と稽古の中で育つことを言っているのだと思う。血筋があっても芸や踊りが下手な役者がいる一方で、部屋子や(芸)養子で素晴らしい踊り手でいい芝居をする歌舞伎役者は数多いる。血筋のことばかりいうようになったのは、一体いつからなんだ?クラシック・バレエの世界では、血もどこの生まれの人間かも関係ない。頭の大きさや手足の長さ含めた外見で不利であっても日本人ダンサーは世界で活躍している。あるのは才能と努力と周囲からの援助のみ。音楽の世界も同様だ。
歌舞伎興業を担当する竹野を演じた三浦貴大が、ぽろっと口にする台詞がよかった。彼と吉沢亮が絡むシーンがもっとあったらと思った。
演じた本人も共演者なども高く評価している、汗と涙で顔のお白粉と紅がぐちゃぐちゃの屋上シーン。「さらば、わが愛/覇王別姫」のシーンを思い起こさせる。でも全く異なる。レスリー・チャン主演のその映画は、貧困と孤児に始まり、かつての仲間やパトロンが裏切られ密告され、多くの人々が糾弾され殺され翻弄された中国の歴史を批判的にとりあげた作品だ。その映画からの引用が浅薄で表面的でしかないのは、「国宝」というタイトルを冠したこの映画が世襲含めた「日本の伝統」というものに切り込まず、無批判のまま、個人的・私小説的お話の枠から一歩も出ていないからだ。映像は顔アップが極端に多い。立役の存在感がない。官能もない。全てが薄い。期待し過ぎた自分が悪いんだろう。
おまけ
1)父親=大旦那が亡くなった途端に跡継ぎを孤児状態にする歌舞伎の世界ってなんなんだ?でも名家の○○屋の跡取り息子は大旦那=父親を亡くしたら先輩方に頭を垂れて教えを請わなくては。年老いた大旦那の課題は一つ:踊ることも立って歩くことも座ることができなくなっても舞台に出ること、自分の息子&孫息子の為に。そんな家庭内興業で、役者の妻は男子を生むことが強烈に求められている歌舞伎はいつか滅んでも仕方ない。一方で「血筋幻想」と世襲が日本の芸能界や政治の世界でいまだ幅をきかせているが、歌舞伎の修行のように孤独な勉強と思考をしているのか?
2)原作を読んでいないのでごめんなさい。歌舞伎役者は踊りの稽古が何より大事。加えて鳴り物や三味線の稽古。女形の「国宝」なら、「阿古屋」を演じるレベルか、廃れてしまった演目を掘り起こすなどしていなければ説得力ない。
3)半蔵門にある国立劇場の楽屋入口が映った。正倉院を模した美しい建物をなぜ壊すのだ?建て替え工事を請け負う業者も決まらず使わないままでいたら、建物によくない。エレベーターもエスカレーターもある劇場だから、楽屋や舞台関連をリフォームすれば済む話では?ホテルを載っけて高層ビルにするなんて愚の骨頂。もう既に、文楽、通し歌舞伎、踊りや長唄の会などに多大な損害を与えている。建築物含め、文化と歴史と教育に無関心で無知な国に嫌気がさす。
4)この映画見てからずーっとモヤモヤしている。何故、今、このような映画が制作され大々的に宣伝され、信じられないほど高く評価されているのかわからない。歌舞伎を見たことがない人にとっては新鮮だった、は想像がつく。かつて「芸道映画」は、時代がきな臭くなり社会批判的なリアリズムの映画は検閲されたりと厳しい状況だったから作られた(ということは、今、そういう状況なのだと考えてもいいと思う。いや、もっと悪い。検閲どころか映画制作側の意味不明な忖度を感じる)。「芸道もの」の主人公は若気の過ちで封建的社会から追放され、苦しい放浪生活の中で人格と芸を鍛え、結局は許されて元の封建的秩序の地位に戻る。監督の手腕の見せ所は恋愛だが、女は自分を犠牲にして男に尽くし男は女の犠牲の上に芸の修行に励むという封建的な制限内に留まる。この映画では、多くの女性達が現れては消え、いつのまに?が多く雑だった。
🌟この映画で歌舞伎に関心を持ったら、一幕見(ひとまくみ)席や三階席で見て(切符は高くないし、どんな服でも大丈夫)、何度も足を運ぶ人が一人でも増えたら、いろんなことを考えるだろうし見えてくると思う。今、歌舞伎の世界は、20代~30代の若い役者が綺羅星のごとくひしめきあう、稀に見る時代だそうだ🌟
2025.8.29.の新聞で、大阪松竹座が閉館との記事を読んだ。なにやってんだー!劇場を大事にしてくれよー!
作品を観て、歌舞伎シーンは絢爛豪華ですごかったですが、
何か物足りないものを感じたのですが、talismanさんのレビューを読んで納得しました。
折角、血筋伝承ではなく才能伝承を選択したのに、
そこは茨の道・・・。結局は血筋伝承にエールを送っているストーリーだったので物足りなさを感じたんですね。
ありがとうございました。
「国宝」というタイトルを冠したこの映画が世襲含めた「日本の伝統」というものに切り込まず、無批判のまま、個人的・私小説的お話の枠から一歩も出ていないからだ。
↑
共感いたします。
ただ、自分にはほんのわずかながら
歌舞伎界の世襲制等の問題提起と受け取りました。
だから、
よく歌舞伎界が撮影等を許可し協力したものだとちょっと思いました。
が、全体を美でまぶしたから、
OKが出たのでしょうね。
^_^
覇王別姫へのコメントありがとうございます。実は私、『国宝』への貴レビューが好きで、特に覇王別姫との比較に触れている箇所には膝を打ったものでした。覇王別姫のレビューを書きたくなったのもこのレビューがあったからかもしれません
共感ありがとうございます。
さすが、talismanさん、歌舞伎への見識がすごいレビューなんで感服しました。歌舞伎は、愛之助の鯉つかみしか見たことがないので、もっと勉強します。
talismanさん、大丈夫ですよ。豊富な知識が視点を増やし、より深い解釈や切り口鋭い批評が映画の観方を多様にすると思います。そこに映画愛があるから、共感も理解も得られます。映画も21世紀になって扱うジャンルもテーマも複雑になって、新しいことを知る機会が増えました。talismanさんのレビューは、常に勉強になって参考にさせて頂いてます。
私の自作格言の一つに、美しさが全てを凌駕する、があります。他に(無知は罪、信じる者は救われない)知らないことがいけないことではなく、知ろうとすることが大切。信じて裏切られて憎むより、自分が信頼される人になること。そして見た目の美醜に囚われず、心の美しい人は魅力的である。社会人の経験と色んな映画を観て来て、辿り着いた自分への戒めです。
この映画にも美しさに潜む残酷さと厳しさ、そして到達する人間だけの喜びと悲しさを感じました。どんな職種の芸術家も、その生き方含め、私にとっては先生の位置づけです。
talismanさんの古典芸能文化への深い造詣と熱い想いに、改めて敬服です。素晴らしいレビューを拝見して、とても勉強になりました。ありがとうございます。この映画化は、素人の立場から、よく挑戦してくれたと思いました。歌舞伎をじっくり観る環境にいない者として、いい機会を得たと感謝する自分がいます。映画鑑賞後、いくつかの歌舞伎の映像を観ましたが、玉三郎の女形の凄さに久し振りに感銘を受けました。(昔々NHKホールのロビーでタキシード姿の玉三郎を見ましたが、そのスマートさと気品のオーラに度肝を抜かれたことがあります)
レビューに付け加えると、メーキャップと美術、それに音楽が良かったと思います。東一郎が人間国宝のインタビューを受けるシーンのメーキャップが自然でした。映画を演出最優先で観てしまう私の限界、特に溝口健二の演出力と比較してしまう悪い癖で、このような男女の愛憎劇では、どうしても不満が出てしまいます。talismanさん、「マリアのお雪」をご覧になったのですね。山田五十鈴、梅村蓉子、原駒子の女優陣が印象に残っています。二十歳の時、「滝の白糸」「マリアのお雪」「虞美人草」「浪華悲歌」「祇園の姉妹」「愛怨狭」と観てきて、「残菊物語」の男と女のドラマが圧巻でした。今回の映画化は、歌舞伎の舞台と男の人間ドラマが均等に扱われて、その良し悪しでした。印象としては舞台に重点が置かれていましたね。
次のシネマ歌舞伎は、
「鷺娘」2005(平成17)年5月/「日高川入相花王」2005(平成17)年10月
上演劇場:歌舞伎座
になります。これも観に行こうと思います。
振りつけも所作も身に染み込ませるのは大変ですね。
talismanさんの推しのおかげで「京鹿子娘二人道成寺」観る事ができました。シネマ歌舞伎にもう少し注目して行こうと思います。
talismanさん、私のレビューに共感とコメントありがとうございます。
talismanさんは歌舞伎に精通しておられるようで、深い知識と理解のあるレビューには感服いたしました。
talismanさんの濃厚な知識に、映画が追いついてなかったのですね、そーゆー時ありますよね。でもtalismanさんが満足する内容だったら、私パンピーでは理解が追いつかなくなるでしょうねー😂
えー、単衣着て映画館てシャレオツー❗️
自分も近所に和服の古着屋があるのを最近知ったので、そこで甚兵衛が作務衣でも買って、また「国宝」級の映画観に行こうかな😜
今、東劇で「シネマ歌舞伎 二人道成寺」を上映しているので観に行こうかと思っているのですが、いつもはガラガラなのに「国宝」の影響で日曜日はほぼ満席だったそうです。
共感ありがとうございます。
現在の日本の矜持は、古典芸能とインバウンド客の賞賛しか無いのかもしれません。微妙に海外への目配りも感じますね、女性陣の早々退場も深掘り恐怖と言うか。
おはようございます☀
今日も暑くなりそうですね。
そのうち、1年の半分は夏になってしまいそう。
お体気を付けてくださいね。
猿之助の復帰については、私は肯定できませんが、裏で貢献して欲しいと思います。
名前は残して欲しいし。
ほんと、悲しいです。
返信ありがとうございます。
私も原作読もうかな。
吉田修一はいくつか読んでいて、この人ならまちがいない、って思いますね。
阿古屋は、こないだBS松竹東急で放送したのを観たので、原作でどんな風に表現されてるか楽しみです。
talismanさん!
私も猿之助を好きだったんです〜。
あの事件以来、歌舞伎熱は冷めてしまいました。
あんなに才能があっても、つまづくと脆いですね。
頭では、おもだか屋を応援しなければと思いながら、なんか無理なんですよね。
この映画は観たいと思いながら、まだ観てないですが、とても参考になるレビューでした。
歌舞伎役者は踊りの稽古が何より大事、ほんと踊りの下手な役者は観たくないですね。
でも、前は新春浅草歌舞伎とか観に行ってましたが、最近歌舞伎に対して、関心が薄くなってきました。
幸四郎とかがんばっているんですけどね…。
talismanさん
劇中で、どんどん消えてゆく容貌も境遇も似た女たちが、見分けがよくつかないほどに消費されて、その個々の存在が軽んじられている事は、僕も気になりました。
けれどそこもそういう姿で、あの世界の暗部を上手くさらった作りだったかも知れませんね。
そして、“終わりかけの日本の古典芸能”を、仮面ライダーを使ってでも再起させたい思いは、恐らく文化庁の若手官僚たちの内からの願いとも感じました。
・・・・・
それにしても!talismanさんのレビューを探すのに凄い時間がかかったんですよ😭talismanさんまでどっかに流されて行っちゃったのかと思いました(笑)
せめては「フォロアー同士のレビュー」はレビュー欄の前のほうに掲載してもらいたい!
なんか映画ドット・コムのレビュー配列が無茶苦茶です
😱💦
コメントありがとうございます。
原作では、映画では出てこなかったキャラクターも沢山出てきて、群像劇的な雰囲気もあります。歌舞伎の演目紹介もしっかりしてます。歌舞伎疎いのでいい入門書になりました(取材の量が半端ではありません)。映画とは違った印象を受けると思います。
でも、描いているのが梨園と極道の世界なのでもう必然的に「封建的」「男尊女卑」な世界です。そこはどうか目をつぶってください(笑)
読んでみると、映画では多分伝わらなかった「国宝」の意味も少しは分かるかも知れません(私は原作も掘り下げが足りない気がしました。あ、ちなみに阿古屋やってるのは最後の最後です)。
長いので、読むのにちょっと疲れますけどね(笑)お時間あれば是非。
国宝のコメント興味深く、頷きながら読みました。
映画はヒットすることで次回作(希望・製作費など)に繋がるので、国宝の大ヒットは喜んでいます。
お引越しが愛おしい作品ならば、もしかすると、ひょっとしたら、ルノワールもありかも、しれません。
主役の女の子はお引越し田畑さんをちょっと意地悪にした感じですが。
そんな映画もありましたね。勘九郎(勘三郎)は松竹映画にも出てたし。松坂慶子と共演した映画がありましたね。
医療過誤で亡くなるなんて惜しい事をしたものです。
今晩は^ ^
3代目田之助さんて方が実際にいらっしゃったんですね、芸者との間に娘がいても芸の為に悪魔にお願いしたんだ。と娘に説明するシーンは観ていて辛かったです。
伝統、技術、文化、そして建築物…
利益や効率ばかりが優先される世の中で、姿を消してしまうものは本当に多いですね。
国土も人口も少ない国では、それらを守る方が長期的には有益な気もしますが。
とは言え自分も歌舞伎には興味を示してきませんでしたが。
でもだからこそ、国が庇護しなくては余計に立ち行かなくなってしまうのでしょう。
コメントありがとうございました。物凄いレビュー、勉強になります。当方は伝統芸能にも疎いのですが、この映画の田中泯は当方の知る範囲の梨園の方々とは全く違う雰囲気で、その為に逆に映画が深まっている様に感じました。
おはようございます☀
コメントありがとうございます。
なんだか本作モヤモヤしますね。ソレを描きたいのだろうけど。
吉沢亮さんと横浜流星さんだけを観ていたらいいのかもしれない、けど。
さすがtalismanさん、興味深くて為になるレビューです。
おまけ4)に共感します。本作での歌舞伎界を観ていて、芸の為ならニョウボも泣かす~という歌を思い出していました。三田寛子さんが以前、女遊びを「芸の肥やし」なんて私は認めません、とおっしゃっていたので、男尊女卑思想も変わって来るかなあと思いましたが、中々変われないみたいですね。
専門家のようなレビューに感服!
歌舞伎を見たことがない自分にとっては、慣れないクラシックのCDを買った時に読んだ解説のようです😭
国立劇場のことも知らなかったのですが、文化や芸術や古典芸能や基礎研究の世界にも効率やコスト削減というモノサシが幅を効かせるようになってしまったのだと思います。
短期的な視点で、成果(黒字)が出せない分野に回す予算はない、という官僚が芸術や大学の基礎研究の予算をカットしてるのかもしれません。
コメントバックありがとうございました!
原作小説(文庫版)の下巻最後に素晴らしい解説があり、そこに阿古屋についても書かれてました。戦後、六代目歌右衛門と玉三郎しか演じなかった阿古屋を継承すべく、玉三郎さんが中村児太郎、中村梅枝のお二人に稽古を付けているようです。
おはようございます。
talismanさんは歌舞伎にもお詳しいのですね!
レビューに驚嘆です。
私もレスリーチャン連想しました。
talismanさんも触れていらして嬉しい!
レベルアップした気持ち(^。^)b
特におまけ3には共感の嵐!
国立劇場、閉場から1年半以上?経ちますよね。
伝統文化への国の理解の乏しさを痛感します。
このままでは日本の伝統文化へ関わる全ての人々にとって(ファンにも)大きな損失になりますよね。
文化庁には一刻も早く整備計画を進めて頂きたい。
吉沢亮さん、流星君、田中泯さん、とてつもなかったです。
共感ありがとうございます。
今回も、広い見識と鋭い視点に脱帽のレビューでした。
おまけ2)で「阿古屋」に触れられていますね。流石です。
原作には阿古屋を演じる場面が出てきます。それも相当重要なシーン。原作ネタバレになるので詳しく書けないんですが、映画で「阿古屋」を出さなかった理由は、役者(吉沢君)のキャパをオーバーしてしまうことと、そもそも原作小説の阿古屋シーンを映像化することが無理(下手すると映画自体が台無しになるリスクがある)為だったと素人ながら勝手に解釈しています。観たかったけど、出さなくて正解だったのではないかと今、思っています。
原作が長編大作すぎて、重要人物が完全に消されていたり、脇役達に纏わるエピソードが大胆カットされて薄味感は否めないんですが、原作既読でも、未読でも、1つの映画作品として、とても完成度の高い作品だと思いました。
長文失礼しました。
おはようございます。
流石、talismanさん。凄いレビューですね。歌舞伎お詳しいのですね。私は、昔読んでいたある作家の作品群のお陰で、ギリギリついて行けました・・、が女性陣達をもう少ししっかりと描いて欲しかったかな、とは思いました。ではでは。良き週末をお過ごしください。
共感ありがとうございます。永六輔の「役者その世界」なんかを読むと昔はやくざ者上がりの役者なんかは幾らでもいたようですね。確かに血筋一本になってしまったのは何時からでしょうか?
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。