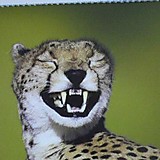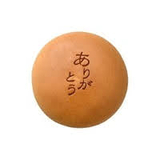35年目のラブレターのレビュー・感想・評価
全314件中、21~40件目を表示
長く連れ添った夫婦がお互いを深く愛する物語です 観て良かったと必ず思って頂けると約束できます お薦めします
35年目のラブレター
2025年公開
これはよい映画です!
沢山の人に観て頂きたいです
ポロポロと沢山泣きました
心が温かくなりました
実話だそうです
これを最初テレビで取り上げられた時に司会をしていた鶴瓶さんと、主人公本人の西畑保さんとの交流も実はあったそうです
お話の舞台は奈良市です
興福寺の五重塔、平城宮跡の朱雀門、奈良公園、浮き御堂、猿沢池、法隆寺などの観光名所もチラチラながら色々映ります
1999年の年末からはじまり2020年の春までの期間ですが、途中
主人公の回想シーンが挟まります
1964年に結婚するところは長めにあります
というかそこが前半の山場になります
35年目というのは、この西畑さん夫妻の結婚期間のことと言うわけです
西畑保さんを鶴瓶さんが熱演されます
しかも奈良はもちろん関西ですから関西弁です、多少おっとりしてますがお笑いノリは大阪と共通ですので、色々な人物との会話も面白く笑いがタップリです
妻役は原田知世さんです
57歳だそうですが、大変に美しいです
美し過ぎで嘘っぼく見えてしまうなあと始めのうちは思ったのですが、見終わってみるとこれで正解だったと納得しました
美しいことより驚いたのは、彼女が、大変自然に関西弁を話して、関西のオカンを好演していたことです
こんな役もできるなんてとビックリしました
知り合った頃の若い時の妻役は
上白石萌音さん、彼女も関西弁を自然に話して、関西ノリで笑わしてくれました
沢山泣いて、感動もしました
ラブレターがタイトルにあるように、本当に胸が熱くなる純愛の物語でした
長く連れ添った夫婦がお互いを深く愛する物語です
観て良かったと必ず思って頂けることを約束できます
お薦めします
何で??
つくづく思うが、どうして邦画は、ハッピーエンドで感動させることができないのか?
なぜお涙頂戴になるのか…
韓国映画や、アメリカ映画は、キレイにハッピーエンドで泣かせてくれるし、スッキリできるが、邦画はこじつけられたり、最後まで描かずエンディングを想像させられたり、蟠りが残ったり、爽快な気分になりづらいし、切ない気持ちにさせられる…
この映画も、内容として悪い訳ではないが、なぜ2度目のラブレターを読める3日前に嫁が死ぬ必要がある?悲しませのタイミング良すぎ…泣かせにかかられて、冷める⤵️⤵️
あのタイミングで、原田知世は死なずとも、感動させられるし、生きていても、良い話になるのに、むやみに死なせ、やるせない気持ちにさせる…展開が読めてしまうし、『なんじゃそりゃ、やっぱり死ぬんかい』と思ってしまった…
残念…
やはり、邦画は、観ないに限る
皎子って名前、難しすぎるやろ、と思ったら実話だったんですね。 若き...
最初から最後までスッと心に響く。努力と温もり、支え合い。
実話であることのみを知った上で鑑賞。
タイトルと予告映像を見た時は、読み書きができなかった保さんが奥様の皎子さんにラブレターを結婚35年目にして書き届けることが叶いました。という風な結末だと思っていました。
まさか皎子さんが2度目に書いたラブレターを読まずに若くしてお亡くなりになられていたとは…
しかし保さんが喜んでもらえていないのではと気落ちしていた1度目のラブレター。
皎子さんにとって本当に嬉しい贈り物であり、宝物だったんですね。
自分が病気でどれだけ苦しい状況でも、決して贅沢ができなくても、最後まで保さんに愛を届けた姿に感動しました。
そして保さんの長い努力は、年齢や境遇など関係なく、全ての人に様々な可能性があることを教えられました。
キャストの皆様も素晴らしく、とても良い作品でした。
気持ちよく泣けた。脚本も演技もすばらしい。
「泣かせよう」という、わざとらしさあるかもと心配して観たけど、それを感じることなく、気持ちよく泣かせてもらった。「そろそろ、ここが泣かせどころか」と思う場面で、いったん”フェイント”が入り、皎子の病気などで動揺させられたあと、最後の方でドカンと来た。とてもうまい脚本だと思う。
鶴瓶と原田知世も良かったが、若い頃を演じた重岡大毅と上白石萌音が良かった。西畑保という人の誠実な人柄が伝わってきたし、読み書きができないことをなかなか言えないのもわかる気がした。皎子さんが「あなたの手になる」と言う気持ちになったというのも、同じ気持ちになれた。
実話だということが感動的。
西畑保さんのインタビュー記事を読むと「兄弟のために貯めていたお金をなくし、それが見つかったのに、自分のお金だということを信じてもらえなかった」とあった。このエピソードは映画にも出てきたけど、これが原因で学校に行かなくなるのは「そりゃ、そうだろう」と思う。映画で「ひどい話だ」と思ったが、実際に起こったことだとは・・ そんなひどい体験をしているのに、誠実で実直な人柄に育って、立派な人だと思う。
最初「わざとらしさがあるかも」などと疑って、ごめんなさい。
とても良い映画でした。
時を超えたラブレター。。
ストレートな感動、とてもいい話
肝心なのは家族の健康
ルーフトップバーのように想いを重ね続ける経営的愛のかたち
『35年目のラブレター』は、一通の手紙をきっかけに時空を越えて心がつながるロマンティックな物語だが、経営者としてこの作品を観たとき、単なる恋愛映画にはとどまらない「本質的な価値の積み重ね」について深く考えさせられた。
物語は、現代に生きる女性が、古い机の引き出しから偶然見つけた“過去からの手紙”をきっかけに、手紙の送り主と文通を始めるところから動き出す。物理的には決して交わることのない2人が、手紙というシンプルなコミュニケーション手段によって、時を超えて心を交わす姿に、まさに“時代を超える信頼の構築”を見た。
経営においても、即効性を求めがちだが、実際に価値を生むのは“積み重ね”だ。たとえば「ループトップバー」のように、毎日同じ動線で目にする小さなスペースが、いつの間にかブランドの記憶としてユーザーの心に定着していくように、目には見えないが繰り返し届ける想いや誠実さが、長期的な信頼や関係性を築いていく。
主人公たちが送る手紙も、いわばループトップバーと同じ。少しずつ少しずつ、確実に相手の心に残っていく。これは、商品やサービスを「一回限りの売り切り」ではなく、「日々使い続けられる体験」に昇華させる思考と極めて似ている。
また、たとえ時代や場所が違っても、人の想いや言葉には届く力があることを教えてくれるこの作品は、「誰に何を届けるか?」を常に考えるマーケティング視点にも通ずる。
『35年目のラブレター』は、愛をテーマにしながらも、時間を味方につけて“想いを積み重ねる”という、ビジネスにも人生にも通用する普遍的なメッセージを持つ珠玉の作品だ。想いを信じ、丁寧に伝え続けること。その姿勢こそが、人の心を動かし、未来を動かす鍵なのだと教えてくれる。
人は本来優しいのです
丁寧に描かれた実話
実話を元にしている映画をスクリーンで観たのは初めてでした。ド派手な展開も、お涙頂戴演出もなく、ただただ、主人公夫妻の人生がとても丁寧に描かれています。だからこそ、俳優陣のとても繊細な演技力が試されると思うし、その繊細な演技力に心を揺さぶられて涙が止まらなくなりました。
例えば若かりし頃の主人公保が、悔しくて悲しくてやるせない時は、重岡大毅さんの表情、声色、セリフのない間から見える感情といった繊細なお芝居にすぐに見ているこちらが容易に感情移入していき、同じ気持ちになって悲しくて泣けるのです。
そして、忘れかけていた何気ない幸せ。
物事に挑戦するには遅いことなどない。
羨ましいほどの理想の夫婦、お互いの愛情。
全てが丁寧に描かれていて、たくさんあたたかい涙が流れ、あたたかい気持ちで映画を観終わりました。全部で6回観に行きました。全部新鮮に泣きました。
そして、ただ泣ける映画じゃないんです。つい声に出してクスクス笑ってしまうシーンの多いこと。面白おかしいやり取りがこれまた絶妙に上手く、関西人のつっこみっていいな、と思わされました。泣いて笑える最高の映画でした。
質高い作品と感じ、大変面白く観ました。
(完全ネタバレですので必ず鑑賞後にお読み下さい!)
(レビューが溜まっていたので数行で短く)
結論から言うと、今作の映画『35年目のラブレター』を面白く観ました。
予告の印象から言うと、感動の押し付けがあるのかな?と思われたのですが、意外にも描き方は抑制が効いていて、感動ありながらも質高く描かれていると思われました。
その理由は、主人公・西畑保さん(笑福亭鶴瓶さん、重岡大毅さん)、妻・西畑皎子さん(原田知世さん、上白石萌音)を演じた4人の演技の素晴らしさがまずあったと思われます。
また、主人公・西畑保さん、妻・西畑皎子さんだけでなく、登場人物それぞれの人物造形も確かで、例えば、夜間学校の谷山恵 先生(安田顕さん)も、自身も夜間学校で再スタートするという、生徒と同じ目線の人物造形も、上から目線でない、それぞれの人物背景を疎かにしない作り手の志の高さがあったと思われました。
妻・西畑皎子さんの描写も、現代から考えればやや主人公・西畑保さんにとって都合の良い妻を強いられていたと見れなくもないですが、戦時中にやけどを負った姉・佐和子さん(江口のりこさん)との関係性など、時代を生き抜いて来た時代背景により、西畑保さんと西畑皎子さんとの2人の関係性にも必然の説得力があったと思われます。
西畑皎子さんの内職のタイプ仕事が、時代の流れの中で必要とされなくなる描写も、時代の流れで変化して行く私達の仕事に関する普遍性を表現していて、深く心に刺さる場面だったと思われます。
今作は実話を基にした作品であるので、やや淡々とした展開ではありましたが、逆にその劇的にしない誠実な構成表現により、各登場人物の深みある人物造形と合わさって、質高く優れた作品にしていると、僭越ながら思われました。
癒やされました✨✨
この映画は高齢の母と観に行ったのですが、鶴瓶さん演じる貧しく学校も行けなくて読み書きができずそのまま大人になった主人公が支えてくれた妻の為に定年後学校に行き直し、感謝の手紙を書くというものでしたが、このご夫婦のお互いを思いやる心が優しく温かく、母も私もとても癒やされました✨
実話ベースと考えると3.8くらい
優しいお話
全314件中、21~40件目を表示