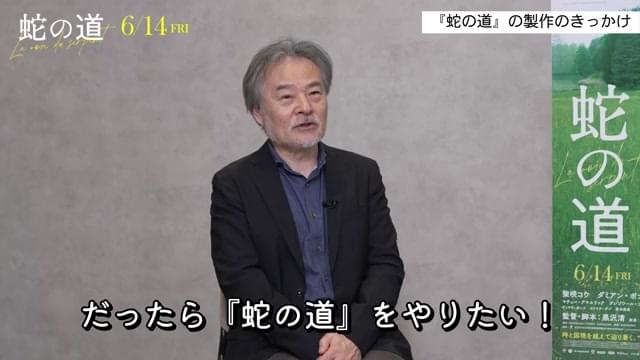「終わりなき復讐譚」蛇の道 ジュン一さんの映画レビュー(感想・評価)
終わりなき復讐譚
1998年制作の自身の監督・脚本作品のセルフリメイク。
その時の舞台は日本、
主役は『哀川翔』『香川照之』の二人だったよう。
今時の人は蛇が通った跡を、
見たことなどそうはあるまい。
自分は昔の人間で、
しかも田舎育ちだからそこそこ目にしている。
太い一本の線が縦に伸び、
鱗の跡が波紋のように横線を描く。
一目で蛇が通ったと判る痕跡。
本作の舞台はフランス。
幼い娘が惨殺遺体で発見され、
父親の『アルベール(ダミアン・ボナール)』は犯人への報復を誓う。
自身の治療のために訪れていた病院で
精神科医の『小夜子(柴咲コウ)』と知り合い、
彼女の助けを借りながら一人また一人と
容疑者を割り出す。
とは言え、やはり素人コンビの稚拙さ。
相手が体力の持ち主であれば
時として圧倒され、窮地に追い込まれる。
が、そうしたピンチも乗り越え、
二人は真の黒幕に近付きつつあるようにも見えるが
その後には死体がいくつも重なる。
しかし、傍から見ていて、どうにも腑に落ちない違和感が。
報復の主体である『アルベール』は全体的におよび腰で、
アシストの立場である『小夜子』の方が積極的にコトを運ぶ。
それは容疑者に対する尋問の場でも明らかで、
亡くなった娘の在りし日の姿をビデオで見せ、
死体検案書を淡々と読み上げるばかり。
こんなあっさりした手法で、
(実際に殺人を犯していたとしても)ホントに自白するか?と
思ってしまう程度の生ぬるさ。
一方の『小夜子』はパートナーの『アルベール』を時として出し抜き、
したたかなネゴシエーターぶりを見せる。
弱気ぶりを叱咤する場面すら見られ、
彼女のモチベーションの高さは、いったいなぜなのか。
とりわけ『小夜子』が、
先を見通したような振る舞いをすることの不可解さ。
この違和感の正体は、
終幕のエピソードで明らかに。
『黒沢清』は、なかなかに手練れの脚本を紡いだもの。
悪の彼岸と此岸の曖昧さを再認識することになる。
もっとも、全ての真相が明らかになっても、
鑑賞者の側は通常の復讐譚で得られるカタルシスを
微塵も感じない。
それどころか、「蛇の眼」に見つめられたような
ざらっとした不快感だけが残る始末。
『柴咲コウ』の演技の賜物は、
既に狂気に囚われた者の表情を
余すところなく体現する。