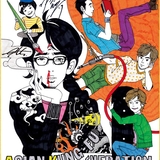ぼくが生きてる、ふたつの世界のレビュー・感想・評価
全66件中、41~60件目を表示
劇的なBGMが流れなくても美しさに涙することができる
ろうの両親に生まれた青年の物語。
誕生から幼稚園、小学生、中学生、20代、そして今を追いかける物語。
主演の吉沢亮が中学生から今を演じる。30歳の彼が中学生を演じてしまうのがすごい。
また、幼稚園、小学生の時の男の子が吉沢くんにすごく似ていて、かなりびっくりした。
CGじゃないよね、なんて思うほど。
ドラマの中心は彼とお母さんの物語。
お母さん役の忍足亜希子さん、お父さん役の今井彰人さんもろう者の役者さん。
障害者の夫婦に生まれた子供としての葛藤。反抗期。
ドラマティックな展開はほとんどない。
ある意味、違いはあってもどの家庭にもありそうな親子の間のすれ違いと心の触れ合いにも思えた。
「産んでくれ」と頼んだわけじゃない。そんな言葉を吐きかける少年時代は障害者の親の下に生まれなくてもあるような気がする。
ただ、最後のところのシーンのような、楽しそうな親子の買い物やご飯や会話。
そんなごく当たり前な普通な時間を母親がとても喜んでくれている、そんなことに気づいた時、今までの自分に気づいて涙が滲んでくる、そんなことは分断された特別な世界でなくても、起こっていることのように思う。
15の夜、十七歳の地図から卒業していく姿のように思えた。
ラストになって映画の中で一切、BGMが流れていなかったことに気づかされた。
冒頭はろうの方の世界を表現するために音のない世界。
そこから彼が生まれて音がある世界に変わったけれど、現実の世界は劇的なBGMなんて流れやしない。
それでも僕たちは現実の世界の美しさに涙することがある。
Coda日本版と、言ってはいけない。
邦画を字幕付で観ると、字幕なしで観た時と違う印象を持つ場合がある。
聞き取れなかった言葉や台詞が文字で表された事により視覚と聴覚に二重に訴えるからかも知れない。最近は字幕付上映もあるので、邦画でも可能な限り字幕付で鑑賞している。今回は内容からも、あえて字幕付版の回で鑑賞。五十嵐大の自伝的エッセイの原作は未読。
9月24日(火)
新宿ピカデリーで「ぼくが生きてる、ふたつの世界」日本語字幕版を。
「Coda あいのうた」に触発された作品かと思ったがアプローチが違った。
この映画は大が生まれたところから始まる(背景音は無音)。宮城の港町、誕生祝いに集まる人々。両親は耳が聞こえない。赤ん坊の大が泣いても泣き声が聞こえない。小学生になった大は親と手話で会話するので同級生から奇異な目を向けられる。そんな状況に母親を疎ましく思い始める。授業参観日を母に教えない。奇異な目で見られたくないからだ。
高校受験のための三者面談でも耳の聞こえない母親は上手く相談に乗れない。塾にも通うが第一志望の高校には入れない。
20歳の大はやりたい事を探すため東京へ旅立つ。しかし、パチンコ店で働くなどしている。壁には上京する時に母が買ってくれたスーツが掛かっている。母から送られてくる荷物、食料品と封筒に入った五千円札。大は東京でも手話サークルに入り、聾者と交流する。
スーツを着て出版社の面接を重ねる大。やっと調子の良い編集長(ユースケ・サンタマリア)に採用され、編集の仕事を始める。しかし、その編集長も逃げ出し、大はライターとなる。父が病に倒れて見舞いに宮城に戻る。東京に戻る大を母は駅まで見送りに来る。その後ろ姿に上京する際の母の後ろ姿を重ね、過去の様々な母の姿を思い出し泣き崩れる。
無音世界から東京へ向かう電車は暗闇のトンネルを抜ける。それは別の世界に出て行く大の姿を現しているように見えた。
大は、母を疎ましく思いつつ、東京でも手話サークルに入り聾者との繋がりを続けて行く。サークルの飲み会で注文を耳が聞こえる大が行い、聾者でも出来るから余計な事をするなと諫められる(聾者の気持ちが理解出来ていない事を現している)。
少年時代を演じた子供たちが吉沢亮に似ているのは良かったが、さすがに中3を本人が演じたのはきつかった(似ている中学生はいなかったか)。両親を演じたのも、その他の聾者の役にも聾者の俳優を使ったのも良かった。祖母が烏丸せつこだったのがビックリだった。
本作にはユーモアはあってもエンタメ性はない。劇映画なのでその点が不満。(Codaにはあった)
Codaでは、大学に旅立つ娘を家族全員で見送り、娘は愛していると表現する。
上京する息子は、母親に愛する事を表現出来ない。
今日観た2本は、上京する息子を見送る母親(本作)と上京する娘を見送る父親(ごはん)が描かれていた。子供は親を疎ましく思っても、子を思う親の気持ちは変わらない。
そして、その思いを知った時に、子は親を思い涙を流すのである。
小さな物語の大きな感動
予告編の吉沢亮君が無性に気になり、鑑賞する事に。
物語としては普遍的な親子の愛情物語なのだが、構成に一切無駄がなく過剰な演出もせず、でも描く所はしっかり描くという呉美保監督の手腕がはっきり見て取れる作品だったように思う。息子の誕生から始まり、前半部分では息子の成長と共にろうあ者の日常生活で生じる不便や困難、危険などが描かれ、さらに息子(吉沢亮)のコーダとしての葛藤や苛立ちもリアルに伝わってくる。この辺のさりげない自然な見せ方が実に上手く、しかも本当に無駄がない。最小限の表現で最大限の効果を発揮している。呉美保作品を観るのは初めてなのだが、前半だけで「この監督すごいかも」と思わずにはいられなかった。ろうあ者の日常生活において起こる様々な出来事はあらゆる困難や不安に満ちており、それらの多くが彼らにとってはあるある話なのだろうが、僕にとっては驚きの連続だった。
三浦友和に似てる似てないのバカ話、カレーの隠し味に味噌を使ってボロクソ言われる、パチンコ屋でどの台が出るか聞いてみたりする。まさにどうでもいいような「会話」を、彼らだって僕らと同じように日常的にしている事にすら僕は気付かずに今まで生きてきた。そんな自分を恥ずかしく思うが、それと同時に僕は基本的に「聞こえる世界」の住民であり、だから「聞こえない世界」というものを実は何ひとつ分かってない、という現実を思い知らされるのだ。最初は「ふたつの世界」って何だろう?と思っていたのだが、上映が始まってすぐに「なるほど、そういう事か」となる。
登場人物はみな素晴らしい。母は息子の全てを受け止め、信じ、寄り添い続ける。補聴器を20万で買い、ろくに会話出来てないにも関わらず「これで大ちゃんの声が聞ける」と嬉しそうに言う。それを聞いて泣かずにいられるかっつーの。父は地元で働くと言う息子に「東京へ行け」と背中を押す。たったひと言だが、父の思いがしっかり込められている。またフルーツパーラーのエピソードだけでも両親がどう生きて来たかをしっかり想像させてくれる。
じいちゃんとばあちゃんも素晴らしい。荒くれ者のじいちゃんなりに孫に何かを伝えているし、ばあちゃんは大にとって家庭内で貴重な「話し相手」だったわけだ。彼らの果たした役割(家庭としても映画的にも)は実に大きいと思う。また大の成長する姿だけでなく、彼らが年老いて行く姿を通じて、家族の「時間の流れ」というものをはっきり感じさせてくれた。2時間に満たない尺でこれだけ深みのある物語を作り上げた呉美保監督には本当に驚かされる。
また上京してから知り合う河合(ユースケ・サンタマリア)も非常に印象深かった。大(吉沢亮)の採用を決めるくだりも面白かったし、大がライターと喧嘩した後に河合が「大はどこでも生きていけそうだな」と笑いかける。それまで「何者」でもなかった大が東京に来てしっかり成長している様(さま)を河合の何気ない言葉が的確に表現しているように感じ、非常に深く刺さる言葉だと思った。そして偉そうな事言ってると思ったらタモリの言葉を丸パクリだったり、しまいには結局飛んでしまうという掴みどころのないこの男は、実は大の成長において(この作品においても)かなり重要な立ち位置だったのではないかと個人的には感じた。
そして最後。
これはもう完全にやられた。駅のホームで母からの「手話で話してくれてありがとう」という言葉に、不意を突かれた大は思わず泣き崩れる。ここでまさかの「無音」という演出かいっ!これは見事としか言いようがない。この静寂の瞬間、僕にはふたつの世界が「ひとつ」になったような、たまらなく愛おしい時間に思えた。もう本当にマジでやられた。母にとってはたわいもないひと言でも、この言葉がその後の彼を支え続けたんじゃないかと思うし、こういう小さな出来事ってきっと誰の人生にもあるはずなのだ。だから大のくしゃくしゃの泣き顔に、誰もがどこかで自分の人生と重ね合わせたのではないだろうか。そして大の心を表現してるかのように、真っ暗闇の奥に見える微かな光が大きくなりながら眩いトンネルの出口へと向かっていくラスト。もうただただ号泣です。最後に流れる歌(手紙の歌詞)も良かった。
やはり予告編で感じた直感は間違っていなかった。吉沢亮君の表情がとにかく素晴らしい。かつて「青くて痛くて脆い」で闇深い青年を演じて非常に良かったのだが、今回はさらに更新してくれた。ちょっと大げさに言えば、これで主演男優賞とか獲れないかなと本気で思ってしまう。この作品はシンプルなのに奥行きがある。基本はろうあ者のお話なのに、最後はそんなの関係ないと思えるほどの親子の物語であり、一人の青年の物語なのだ。
この作品は多くの人に強くお勧めしたい。
※追記
終盤スーツを買いに親子で洋服の青山へ行っていたが、さりげなく三浦友和ネタを回収していた事にあとで気付いた。なぜ三浦友和?と思っていたのだがそういう事かと感心した。
可もなく不可もなく🙏
健常者と障がい者との間に「壁」はない。
そんなきれい事はいくらでも言えるのです。
手話出来ないし、なんなら口話ですら
(唇の動きで会話読み取る)
めちゃくちゃ難しい。
壁とまでは言わないけど、やはりどうしても
隔たりがあるのが現実ではないかと思う。
喫茶店でパフェを食べている時
カウンターに座ったカップル。
あんな感じの無神経さ。往々にあるのです。
なんでも口に出す、それを正義と思っているし
なんなら何が悪い?と開き直る。
障がい者じゃなくても生きづらいいまの世の中。
大が「こんな家に生まれたくなかった!」の言葉は
確かに、両親がろうあ者であった事の苦労から
来るものでもあるけれど、
個人的には「ふたつの世界」ではなく
「ひとつの世界」での子供の成長日記と
親の深い愛情を思い出させる、とてもセンチメンタルな気持ちになる作品だったと思うのです。
点数5点は、作品云々ではなく
自分の素直な気持ち、可もなく不可もなく🙏
ぼくらが生きてる、ひとつの人生
前半の浮き沈みが激しく、それだけで、もう…
大の誕生による幸せムードから、聾者による子育ての難しさで一気に胸が苦しくなる。
差別的な意味ではなく、祖父母のサポート無しでは実際問題立ち行かなかったかっただろう。
(手話を憶えず明子を育てきったのもある意味凄い)
それでも愛情に溢れた家庭で幸せに育っていたところ、友人の「変」の一言で世界との隔たりを意識する。
手話で人気者になれそうなときにも、茶化す阿呆が…
しかし、花壇荒らしの濡れ衣を着せてきた女性含めて、悪意なき悪意が非常にリアル。
中学時代(サスガの吉沢亮でもムリがある)からの反抗期は、みんな身に覚えがあるのでは。
正直、観てて居た堪れなくなった。
だがそれに対し悩み、相談し合う両親の姿は、これも一般的なそれと何ら変わりない。
プータローからの上京暮らしは、両親の出番が減ったこともあり、うだつの上がらない平凡な日常。
大は、成りたいモノはないけど成りたくないモノはある。
だから面接で口では嘘をついても表情で自らバラすし、理不尽なライターには決して謝らない。
この辺は自分に似てて複雑な感情になった。
そんな半生を描く中で、言葉以上に物語る吉沢亮の表情や佇まいの奥行きが凄い。
両親はじめ脇もみな素晴らしいし、複数の子役が悉く吉沢亮っぽい上に演技もちゃんと出来るという。
サークルの酔って記憶なくした一人っ子女性が好き。
聾者同士の会話にユーモアがあって楽しかった。
誰にとっても人生は自分のもの一つきりだし、父も母も一人きりで、その中で生きていくしかない。
世界をいくつに区切ろうが、それは等しく変わらない。
キングダムの吉沢亮とは全く違う演技と母親役の忍足亜紀子の演技に泣いた
聾唖者の両親のもとで育っ五十嵐大にとって、幼い頃は母の“通訳”をすることも日常だったが、成長と共に特別視されることに戸惑いや苛立ちを感じるようになり、明るい母を嫌い東京に逃げる。
その母が駅のホームに息子を送り寂しく去る後ろ姿に自分の母親が重なり泣いてしまった。
そう言えば私の田舎に暮らしていた母も私が帰省から都会に戻る時、姿が見えなくなるまで手を振っていたことを思い出しました。
母役の忍足亜希子や父役の今井彰人をはじめ、ろう者の登場人物にはすべてろう者の俳優を起用しているが、特に忍足亜紀子の演技は素晴らしかった。
優秀作品賞へ推し! 聴こえない母へ、産んでくれて育ててくれて ありがとう!!
耳の聞こえない両親から育った一人息子コ-ダ(聴者)が今思う、
音のする世界と、静寂の世界。
普通の両親の元へ生まれたかった。・・・この思い。
貧しいし、塾にも行ったけど進学にも失敗、人生の道が開けない、
親が耳の聞こえない聾唖者だから・・・・そう思う 主人公の大。
母さんと一緒に歩くの嫌だ!、学校に来ないで!、皆の前で母と話しもしたくない! ・・・多感な少年期 彼の心に芽生える葛藤が少しずつ心に歪みを生む。
今日は 聾唖の両親を持つ青年の話「ぼくが生きてる、ふたつの世界」の鑑賞です。
感想からまず述べると、全て実話でしょう。偽りな表現は感じられませんでした。
どうしてもこの様な作品にありがちな 不要な脚色をし見栄え的展開流れを組んでしまってる事が結構有るのですが、そういった点が無く、誰の心へも等身大で奥底へ感情が入ってきます。
貧しさや、介護、祖父の暴力、孤独、進学失敗、上京そして一人暮らし、チャンスと挫折・・・誰にでも起こりえる視点と展開です。
両親が障害者だからと言って特別な人生が待っている訳ではありません。
ですが、生まれてから 生きてきた今までに与えられた運命みたいな物はあったでしょう。それに自分が向き合って いつそれに気付く事が出来るかだと思うのです。
貧乏も、介護も、両親が障害者も、自分以外の人でも有るわけで。
だから 健常者と同じように悩み、それを生きていくのが人生でしょう。
そう思います。
二つの世界の中を渡り歩く彼。でも見ていて、厳密には彼は健常者であって障害者では無いなと思うのですよ。でも 聾唖の方々の悩みや苦労は 人より遙かに理解が出来る。手話で意思が通ずることは 健常者からすればそれは素晴らしいと思いますね。 結局その思い、長けた能力を何に使うかだと感じます。
コ-ダである彼の人生も表現の一つでもあると思いますが、やはり母子の関係性が一番の魅せ場だと感じますね。
結局の所、一般的な母親との関係を描く事で、耳が聞こえない母、父を持った彼から見えた世界が一番のネタなのでしょう。
-----
(その他 思った事)
・吉沢さんの高校生姿って無理有るかなと思ってたが違和感なく見れたと思う。
・手話にも場所によって違い、方言がある事が分かった。
・仕事は常に自分の出来るレベルより少し上のレベルが遣ってくる。
・両親が聾唖者だと、赤ちゃんへの育児は相当大変であったであろうと理解した。
周囲の人達の助けが無いと多分無理だと感じる。
・耳が聞こえない両親でも大きな愛が有って、育てて貰えたから良かったと思う。
健常者の両親であっても我が子への愛が無く、虐待され放置されてしまう子もいる。不幸か、幸福かは つまりの所、愛がある家族であったかどうかだと感じますね。
-------
何とか東京で仕事をやって暮らして行く息子。
父が病で倒れて急いで帰郷。
祖母の介護と、父の看病。
母の事が心配で 家へ帰ろうかと・・・母へ申し出る息子。
”大ちゃんは東京で、頑張って~”
東京へ戻る列車待ち、駅のホームで、 昔 上京する時の事を思い出す彼。
母と列車内で手話で話した 役者になる話・・・
笑う母の顔。やがて列車を降りた母が 一言息子へ言う・・・・
”列車の中で 手話で話してくれて ありがとう~ ”
母がホ-ム端へ歩いて行く 後ろ姿を見て、
その時、今までずっと自分に話しかけてくれていた 母の声が聴こえた!
自分は何も母の事を分かってはいなかったんだと、
心から聴こうと、話そうとしていなかったんだと。
今 それに気がついた・・・
その事に 彼は深く号泣する・・・ そして母への感謝。
この場面、 メッチャ泣けましたわ。
本当に良い場面表現だったと思います。
-----
原作:五十嵐大氏「ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと」
脚本:港岳彦氏
監督:呉美保氏
-----MC
・五十嵐大(主人公コーダ)役:吉沢亮さん
・五十嵐明子(母)役:忍足亜希子さん
・五十嵐陽介(父)役:今井彰人さん
・鈴木康夫(祖父)役:でんでんさん
・鈴木広子(祖母)役:烏丸せつこさん
俳優陣は皆さんとても素晴らしく、本当の家族の様に思えました。
本物の赤ちゃんを使う事でリアリティがあり
特に百日祝い「お食い初め」の習わしが微笑ましかったです。
是非、ご家族揃って
劇場でご覧くださいませ!!
鑑賞動機:呉美保監督9割、あらすじ1割
『そこのみにて光輝く』『きみはいい子』でハードルが凄まじく上がっていたのと「私の一週間」に感心したことで逆に欠乏感が増していたこともあって、「うーん、期待していたほどでは…ない?」と鑑賞直後は感じていた。
1日寝かせてから改めて考えてみると、CODAだからどうこうではなく、普通の男の子の成長物語で、『6才のボクが、大人になるまで』がチラリと頭をよぎる。
地元から出て初めてある程度客観的に自分(の状況)を見る事ができて、それまで嫌だと思っていた事が、実はそんなに大したことではないのかもしれないと思えること(実際大してことではあるのだけれど)が、必要だったのかな。時系列順に進んでいたのが、終盤に入る回想シーンによって、こちらも気持ちの整理がついたように思う。
お父さん役の今井彰人が吉沢亮とあんまり年が違わないのにびっくり。
うーん、タカノフルーツパーラー? 千疋屋?
音のない世界
冒頭と最後に音のないシーンが挟まれます。
永遠の静寂…自分の声も聞こえない。
大切な人の声も聞こえない。
聞こえない人にしかわからない世界…なのかな。
字幕付きの回を見ました。
聾唖の方がたくさんこられていて、
手話でお話しされていました。
横には親子連れの方も。
吉沢亮さん、素敵な役者さんです。
お母さんに反抗する高校生からホームで涙する大人になった息子まで、自然に演じられていました。
フラッシュバックで思い出せる「笑顔がある人生」は素晴らしい
2024.9.23 一部字幕 MOVIX京都
2024年の日本映画(105分、G)
原作は五十嵐大著作のエッセイ『ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して考えた30のこと(幻冬舎)』
コーダとして生きてきた青年の成長記録を綴るヒューマンドラマ
監督は呉美保
脚本は港岳彦
物語の舞台は、宮城県のとある町(ロケ地は宮城県塩竈市)
ろう者同士で結婚した五十嵐陽介(今井彰人)と明子(忍足亜希子)は、25歳の時に待望の第一子を出産した
大(乳幼児期:有馬麦、幼児期:横山るい、4歳時:畠山桃吏、青春期〜成人期:吉沢亮)と名付けられた男の子はスクスクと育ち、耳も普通に聴こえる状態だった
育児は、明子の父・康雄(でんでん)、母・広子(烏丸せつこ)、姉の佐知子(原扶貴子)がサポートにあたり、大は何の問題もなく育っていった
その後、小学校に上がった大は、祐樹(嶋田鉄太)と仲良くなり、自宅に遊びにくるようになった
祐樹は大の母が辿々しく話すのを聞いて、当初は日本語が喋れないのかと思っていた
大にとってはそれが当たり前の日常で、その日以降母親を恥ずかしく思うようになり、授業参観のことも隠すようになっていった
物語は、前半が大の成長物語、後半になってから、東京で一人暮らしをする中で、過去を想起するという構成になっている
志望校に落ちた大は、そのまま不本意な高校生活を送り、卒業後は東京に出て役者をしようなどと考える
だが、その根本は母親の元を離れたいというもので、俳優になりたいという熱を相手に伝えられない
それでも、東京で生きていくことを決めた大は、母親にスーツを買ってもらうことになった
そして、それを片手に「自分探し」を始めるものの、やりたいことが見つからないまま、パチンコ屋でアルバイトをして生計を立てるようになっていた
映画は、このパチンコ屋にて、ろう者の客・智子(河合祐三子)と出会い、そのつながりで手話の会に参加する大が描かれていく
ろう者の彩月(長井恵里)たちとの交流を経て、智子から「私の話を書いてくれない?」と冗談混じりに言われるようになる
彼女たちとの出会いによって、大は出版の道を目指すようになり、ある零細編集プロダクションにたどり着くのだが、そこは劣悪な環境で、社長の河合(ユースケ・サンタマリア)や社員の上条(山本浩司)も逃げてしまう
そこから、フリーライターとなり、医療に関わる現場を取材するようになっていくのである
ほぼ成長日記という感じで、吉沢亮が登場するまでに半分ぐらい過ぎてしまう印象
まさかの中学生役から登場には驚いたが、反抗期時代から、やぐされる社会人時代まで違和感なく見れるのは凄い
ラストは少しだけ時系列が変わる内容になっていて、祖母のために帰省するシーンが描かれる
そこで母親に言われた言葉で「かつての対話」を思い起こすことになり、目を見て話すことの尊さなどを再確認していく
そして、本書の原作にあたる原稿を書き始める、という流れになっていた
このシーンにおける母親との対話のシーンはとても印象的で、そこからエンドロールに向かう流れは神掛かっているように思えた
いずれにせよ、コーダを取り扱った作品で、その半生がどのように動いていくのかがリアルに感じられる内容だった
両親が大について話すシーンにて、「どこの家庭にも色々と問題はあるものだ」という趣旨の言葉が出てくるのだが、この物語で描かれる内容はコーダだけに訪れるものでもないと思う
母親が自分の進路に相談に乗ってくれないとか、両親との対話や生活のために自分が犠牲になっているという感覚などは、いろんな家庭にもあるものだろう
相談すべき存在がいない家庭もいれば、日本語を話しても通じない親もいるし、家族の特異な部分がからかいの対象になることも多々ある
少年時代のように、自分自身が確立していない頃は「家族が自分のステータス」みたいな部分があるので、それをどのように捉えるかで考え方が変わってくるのかな、と思った
大は違う世界に出て初めて、そこまで特別なことではないと考えるようになっていて、自分が捻くれていた時間の貴重さを感じたのだろう
そう言った意味において、親に反抗した時期がある人ならば、刺さる部分が多いのではないだろうか
優しいお父さん、お母さん。
ろうあ者を両親に持つ五十嵐大の成長物語です。
この映画は大と両親の日常を描くドキュメンタリー作品のようです。何か事件が起こる事はありません。ヤクザ者の大の祖父が賭け事に負けて暴れるぐらいです。といっても誰かが傷つくことはありません。
大の母親はとにかく優しいのです。自身の事で大に迷惑を掛けているという引け目もあって、大が何をしても決して大を叱ることはありません。とにかく「大ちゃん、大ちゃん」なのです。この子だけは幸せになってほしいという想いが伝わってきます。
大は幼い頃はお母さんが大好きな想いだけで進んでお母さんを助けようとしますが、成長するに連れ自分の両親が周りの両親と違うことを自覚し、両親を疎ましく感じるようになります。母親を授業参観に呼ばなかったり、自身が上手くいかないことを両親の障がいのせいにしたり…。
20歳になった大は父から東京で生活することを勧められます。父親自身がろうあ者同士の結婚を周囲に反対され東京に駆け落ちした過去を語ります。東京に出て、大にもっと大きな世界を知って欲しかったのだと思います。
東京で暮らすことになった大は自活することの厳しさを知ることになります。そして、大と両親との関係だけでなく、広くろうあ者の実情を知ることになります。
初めて帰省した時、実家に着いた時の大はとてもいい顔をしていました。東京に行く前の表情とはまるで違っていました。そこには成長した大の姿がありました。
ラストの大の回想のシーンで、東京に行く前に母親は大の為に一緒に大のスーツを買ったり、食事をします。最後に母が「今日はありがとう」、「何が?」、「皆の前で手話をしてくれて…。」、大が今まで母親を傷つけていた事に気付き号泣します。このことが無ければそれから東京に行く大が成長することはなかったように思います。
何かが不自由であることがこんなにも繊細な親子関係を育むのなら、世の中の全てが大のような親子関係なら、もっと優しい社会になるのではないか、そう思いました。
シビアな現実を生きながらも、根底には愛が満たされている
コーダとして生まれた僕の、半生の物語。
出生したときの家族の様子、父母の思い、子どもの思い‥。自分にもあるある、と見につまされるエピソードがたくさん💦
幼少期にパフェを食べたときの笑顔、小学生の時に友達に自慢げに手話を披露するところ、大人になっても自然と聴覚障害者を先回りして助けてしまうところ(それを真っ直ぐに指摘されるところ)、電車の中で周囲を気にせず手話で笑いあうところ、印象的で、胸が熱くなりました。
ラスト、無音の中で思い出される数々の母の姿もよかったですね。吉沢亮の演技もピカイチでした。
観て良かった。
生まれた時から抗えない現実に、虐げられて来たと感じる少年が大人になってゆく過程のお話。
家と外との違いに戸惑い、恥ずかしがり、その全てを親のせいにしてしまうどこにでもある話。ただその少年の両親は耳が聞こえないだけ。
実際そうでない自分が感じることの出来ない感情が入り交じっていると思うので簡単に共感したり共鳴したりすることは出来ないが、そこに重きを置くのではなく、誰にでもある悩み・挫折・若気の至りに焦点をあて淡々と物語を進めていく内容が深く刺さった。
最後に『なんか、ごめん』って言った瞬間、そっと泣いた。
観て良かったと思える作品でした。
凄く面白かったです。
不運ではあるけど不幸ではない
母親明子の生涯を思ったら胸が締め付けられます。
ヤサグレ者の父親、宗教かぶれの母親、自身は聾唖者でありながら中1まで普通学級に通わされており、結婚や出産には親類中に猛反対され、思春期とはいえ生まれた我が子に「生まれてこなければよかった」といわれ。。。
映画館の帰りのラーメン屋さんで、思い出したら思わず落涙していました。
親の気持ちは親になってみて初めてわかる、手垢にまみれた言葉ですが、自分も親になって初めてその言葉を実感するにいたりました。
お父さんの生い立ちはこの映画では描かれていませんが、それなりにご苦労はあったのだと思います。
おそらく、わたし自身の両親もこの映画の両親並みの苦労はあったんだろう。
健常者の家庭だろうとCODAだろうと、経験が財産になるような人生を歩んでいきたいものです。
(祖父母のヤバさを話したら採用されてますしね)
「恩返し」を含んでの「恩送り」
そう思ったらたのしい人生を送れそうです。
親が、子を思うのはいつも同じ
両親が、ろう者で子供が聞こえる。コーダだね。
なかなか大変だ。おじいちゃんは、元やーさん、おばあちゃんもいて、子供の頃は大変。いつか治ると思い、聾学校には、入れてなかったんだ。大ちゃんはそんなお母さんが、恥ずかしい。まあ思春期だからね。パチンコ屋さんでの出会いや東京での苦労 ユースケサンタマリアの雑誌屋さんに雇われて少しづつ好転するんかな。
烏丸セッコさんが、びっくりしました。
吉沢亮は、ハンサムだね。
ろう者の育児とその子どもの“感動する話”で終わってはいけない
両親、とりわけ母と息子の無償の愛の物語は古今東西、多くの人の心を揺さぶり感動させる。今作は同じ親子の物語でも少し違う。
耳の聞こえない両親と耳の聞こえる息子(コーダ)が、その家族や自身の半生を描きながら、母の深い愛情を再確認していく物語。
元ヤクザという破天荒な祖父、宗教にはまる祖母、耳の聞こえない両親という個性的な家族と大の成長の物語でもある。
2022年・第94回アカデミー賞で作品賞、助演男優賞(トロイ・コッツァー)、脚色賞の3部門にノミネートされた「コーダあいのうた」も同じコーダを描いた作品だけど、作者が生まれた1983年から現代までの時代背景も感じられる本作は日本人にとってより身近な作品である。
主人公で原作者である五十嵐大さんの誕生から幼少期、少年、青年期と成長していく描き方もよかった。愛情いっぱいに育ててもらった幼少期、外の世界を知るようになり、自分の両親が他とは違う、そして自身はその二つの世界の狭間にいることを知る少年時代。鬱々とした思春期ではその境遇に苛立ち、時には母に当たってしまうことも……。
一筋縄ではいかない障がいを持った人たちの子育ての苦悩や難しさ、差別なども随所に描かれている。
補聴器を20万で買い「何か喋って」っと嬉々として話す母に当時流行っていた「だっちゅーの」で返す部分はおかしかった。
「東京に行け」という父の言葉に背中を押されて、突然上京することを告げる大に最初は相戸惑いながらも、一緒にスーツを買いに行ってやる母の愛の深さにも涙……。
上京前の買い物帰りの電車の中、大勢の乗客がいる中で手話で話す息子にお礼を言う母のシーンでは嗚咽しそうだったし、ここが本作のハイライトだと思う。
ずっと無音の世界にいる母を遠ざけていた大が自分を責める姿に、胸が痛かった。
「母の愛は海よりも深い」その言葉を改めて思い出す作品だった。
ただ、この作品は「感動する」「泣ける」だけで終わらせてはいけない。“マイノリティー”の人たちがどのように感じ、どのように生きるか……そこに本質があると思う。
五十嵐さんのご両親が本作を観てどんな感想を持っているのか聞いてみたいな。
それにしても今年の邦画は良作が多い。
伝えられない思い
…久しぶりの吉沢亮の作品
期待大・・
吉沢の役は五十嵐 大
耳が聴こえない両親から生まれ
耳がちゃんと聞こえる(いわゆるゴーダ)
生まれた時から両親に愛され
屈託なく育つ。何時しか…
自分のことを(気持ち)を
…伝えても
分かってもらえないことが
苛立ちに変わり
母のことをうっとしく感じて
反抗してしまう
家を出て色々な職に着くが
いま一つ続かない
耳の聴こえない両親から生まれたことの
苦しさや遣りきれない思いが
なかなか拭いきれない
そんなとき聾唖者のサークルで
手話で自分の気持ちを話すことは
自然な行為として特別視しないこと
と知る
危ないときとかは助けが必要だけど
手話で伝われば
それでコミュニケーションはとれる
吉沢亮の大の知るふたつの世界
音のない世界と
音のある世界が
少しだけ体現できる
吉沢亮の演技もよかったし
子役たちも吉沢に似た子供たち
だったので特に吉沢になる前の子役
の子が吉沢の演技にそっくりでした。
母親役の忍足亜紀子さんが
息子を包み込む優しさが
とてもよかった
電車の中で母が
大が人目を気にせず
話してくれたことが嬉しいと
言った言葉に感動が込み上げました。
余談…私も
父親が三浦友和さんに
少しだけ似てると思いました
生まれた時から
両親が耳が聞こえなくても、それが普通だとしたら、特に思春期には大きなショックが来るでしょうね。でも、社会人になっても、聾唖の人との関わりは切らずに続けて行っているのはやはり彼の根底にそれがあると言う事ですね。いずれ宮城に戻るのでしょうね。
久しぶりに
胸の奥をぎゅっと締め付けられる、そんな映画でした。
特別しょうがいのある身内などのいないので
当事者感のないまま見ていて、時折はっと
苦が付かせられるシーンがあったり(良かれと思って
やっていることがそうでは無かったり)と漫然と見ていましたが
クライマックスで一気に持って行かれました。
特に子育て経験のある親御さんにとっては身に染みるのでは
ないでしょうか?(私自身は子育てに苦労した父おやです)
しょうがいという部分を除いてもいい映画でした。
障がい者の世界と健常者の世界を「ふたつの世界」として区別する必要はあったのだろうか?
せっかくCODAを題材として取り上げたのに、聴覚障がい者の両親と健常者の息子の家庭ならではの特殊性が、ほとんど伝わってこないのはどうしたことだろう?
息子が母親の通訳をする様子が描かれるのは、幼い頃に魚市場で買い物をする場面の一度切りで、それ以降は、息子が両親の助けとなっているようなシーンは出てこない。
息子は、「親が障がい者で可哀想と思われたくない」と言うが、そんなエピソードが具体的に描かれることもない。
小学生の息子が、うまく話せない母親を恥ずかしく思う気持ちは分からないでもないが、彼が、近所のプランターを壊した犯人として、あらぬ疑いをかけられたのは、別に、両親が障がい者だからではないだろう。
思春期を迎えた息子が、両親を疎ましく思うのも、普通に反抗期だからだろうし、受験に失敗した彼が、「何も相談に乗ってくれなかった」と母親を責めるのも、手話でちゃんとコミュニケーションが取れているので、単なる八つ当たりとしか思えない。
東京で暮らすようになった息子が、俳優のオーディションや就職活動に失敗したり、パチンコ屋でバイトをしたり、雑誌の編集部で働いたりするようになるのも、両親の障がいとは関係がない。
息子は、東京で、聴覚障がい者の手話サークルに参加するが、手話に方言があることや、必要以上の通訳が障がい者の自立の妨げになることを知るものの、そのことが、彼の人生や両親との関係に大きな影響を及ぼすということもない。
ラストで、息子は、公衆の面前で手話で話してくれたことを母親から感謝され、それまでの母親との接し方を悔い改めて涙するのだが、これは「現在」のことではなく、「過去に上京する時」の回想なのだ。
どうして、このような時系列にしたのかは定かではないが、「だったら、東京に出てきた後の話は何だったんだ?」とも思ってしまう。
もしかしたら、作り手には、CODAの特殊性を殊更強調しようという意図はなく、むしろ、障がい者だとか健常者だとかにこだわらない普遍的な物語を描きたかったのかもしれない。
ただ、そうだとすると、どうして、タイトルで、障がい者の世界と健常者の世界を「ふたつの世界」として区別したのだろうか?
結局、そこのところは、最後までよく分からなかった。
全66件中、41~60件目を表示