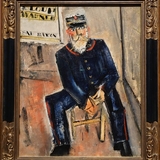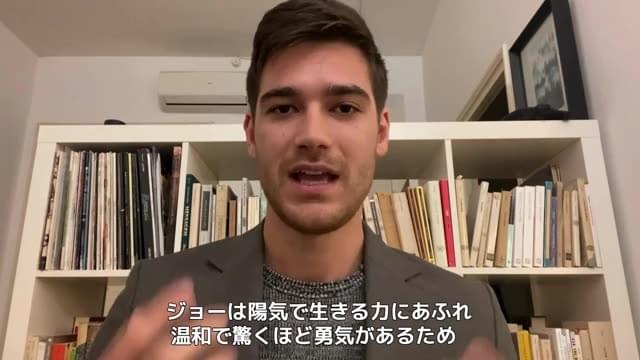弟は僕のヒーローのレビュー・感想・評価
全41件中、1~20件目を表示
障害者の家族がいると恥ずかしくて隠したくなる気持ちは分からないでも...
障害者の家族がいると恥ずかしくて隠したくなる気持ちは分からないでもない。
ただ、この少年は越えてはいけない一線を越えてしまった。
両親は「親だから許すしかない」という感じだし、少年自身も心底反省したというよりも、大騒ぎになって隠しきれないと観念しての告白で、すっきりした感じがない。
新時代のドリーム?
アリアンナ曰く「政治家は大企業に逆らえない」
世界中どこの国でも同じですね
悲しくなる現実
そして自分の頭で考えてる人は、高校生でも分かっている!
嬉しくなる現実
彼女は、学生団体を起ち上げる
その行動力に拍手!!!!
嘘をついてしまうことって、誰にでもあるよね
映画の中でも、両親は子供達にジョーのことで嘘をついたし
彼女のアリアンナも本心を言わずにブルーネが好きだと見栄を張ってたし
ジャックは嘘をつき通すために、どんどん嘘の上塗りをしてしまう負の連鎖と罪悪感
まるで自分が嘘をついているかのような感覚に陥り、感情移入してしまった
でも、1番ビックリしたのは皆の態度
確かにジャックはしてはいけない最低なことをしたんだけど
集まった町の大勢の人々の前で自白したじゃん
なぜそれを皆、受けとめて誉めてあげないの???
物凄い勇気だったと思う
ディスカウントショップ駐車場での、ジャックのセリフに熱い物がこみ上げてきた
弟が大好きで、将来のことを本気で心配してる・・・・
最後は許す両親や、ちゃんと批判する親友やバンド仲間の存在に
イタリア文化の良さを感じた
Youtubeから始まった小説化に、映画化に、新時代の到来も感じた
イタリアンドリーム?
そして何よりも感動したのは、ジョーの役をダウン症のロレンツォ・シストが演じたこと
何の予備知識もなく観た映画だったけれど、それが逆に更に感動を深くしたと思う
お年頃だからね
3月21日は「世界ダウン症の日」。 子どもは常に好奇心に突き動かさ...
3月21日は「世界ダウン症の日」。
子どもは常に好奇心に突き動かされている。健常者とそうで無い人も。
映画の中でジャックの嘘が招く事態が笑い事では済まないレベルなのだが、映画で描かれる大騒動はフィクションで実際にはジャコモさんはやっていない。
実話を元にした本人とその家族と友人達の物語。
主人公ジャックのモデルは、原作者にして本作の脚本にも参加しているジャコモ・マッツァリオールさん。ダウン症の弟ジョヴァンニと一緒に製作し、2015年3月21日に合わせてYouTubeに公開したショートムービー『ザ・シンプル・インタビュー』が話題を呼び、翌年19歳のときには、弟や家族との日々を綴った本『弟は僕のヒーロー(原題:Mio fratello rincorre i dinosauri)』を発表。
本作はその映画化で、実際にダウン症でもあるロレンツォ・シストが弟ジョーを演じる。両親の意見が分かれるがどちらの言い分も好感出来て、長女と次女も魅力的。と言うか悪い奴が出てこない素敵な映画。
色々と考えさせられる作品
配信(DMM)で視聴。
色々、考えさせられる映画だった。弟は障害を持っている。
お兄ちゃんのジャックは弟を大切にしてYoutube動画に紹介するほど。
しかし、思春期に好きな女の子に嘘をついてしまったことが街、家族
街で大騒動。お兄ちゃんの嘘もわからなくはないが、やはり嘘はだめ。
しかし、家族のフォローが温かいし、後味がいい作品。映画館で観ようか
迷って見逃したが配信で観て良かった。
My brother chases dinosaurs が大切
【本当はダウン症の弟が好きなのに、世間体を気にして兄が付いてしまった嘘。彼はその為に多くの友人を失いそうになるが家族の支えで、弟の素晴らしき個性に改めて気づき、世間にメッセージとして発信する物語。】
■ジャックは、小さい頃は初めて出来た弟に大喜びするが、両親から弟のジョーは”特別な子”と言われる。ジャックが成長する中で、”特別”の意味を知り、思春期を迎えたジャックは”弟は死んだ。”と嘘を言ってしまう。
ジャックはジョーが取ったYou Tubeの再生回数が2000回を超えた事から、更に赦されざる嘘を付くが、直ぐにバレて彼は高校で独りぼっちになってしまう。
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・今作が響くのは、ジャックが幼き時はダウン症の弟ジョーの事が好きなのに、思春期を迎え弟の存在を”恥ずかしい”と感じ、”弟は死んだ。”更にジョーが取ったYou Tubeの再生回数が2000回を超えた事から更に嘘を付いてしまい、好きなアリアンナを始め、家族や友人から軽蔑されるも、彼の真意を知る器の大きい両親及び2人の姉から掛けられる、温かい言葉と態度である。
・そこからは、ジャックの家族の絆が感じられるし、ジョーに対してもジャックの両親は決して悲観的な態度は取らず、逆に”ヒーロー”であるジョーの存在及び個性を尊重する姿が描かれている。
ー ダウン症の少年の姿と彼を支えるゲイのカップルとの関係を描いた哀しき名作「チョコレートドーナツ」とは今作は真逆の作りをしている。
何しろ、実話がベースである事が嬉しい。-
<幼き時から思春期に至る過程で、ジャックがジョーの事が好きなのに徐々に世間の目を気にして、ジョーの存在を否定する言葉を発する複雑な表情が、何とも切ない。
そして、ジャックは自身が付いた嘘で追い込まれて行くのだが、彼を救ったのは懐の深い両親と二人の姉が両親が一緒に成るきっかけとなった駐車場で行ったキャンプで、(雨が降って来たので)車の中で彼に掛ける温かい言葉であった。
そして、ジャックは自らの過ちに気付き、昔から抱いていたジョーへの真意”ヒーロー”と言う言葉を思い出し、ジョーの肩を笑顔で抱いたYou Tubeを撮るのである。
今作は、思春期の少年、ジャックを演じたフランチェスコ・ゲギの繊細な演技の魅力溢れた、且つ家族愛に溢れた作品であると思います。>
きょうだいがいるってこんなに素敵なことなんだ!
産まれてきた弟がダウン症で、弟を大切にしつつ、周囲の人々とどう接す...
兄ちゃんがヒーローになるまでの成長物語
ジャコモ・マッツァリオールが記した《自身の弟と自分のついての著書》を、ステファノ・チパーニ監督が映画化。
映画が終わって、館内が明るくなってお客さんたちが立ち上がったとき、
(僕以外には2人ずつのお客さんが二組、つまり館内には5人の客がいたわけだが) 、
みんな無言で立ち上がって顔を見合わせていた
面白かった?
わかった?
うーん・・
という表情。。 僕も含めて。
予告映像や、観に来た我々の期待に反して
弟くんの出番よりも兄ジャックの心象風景が、たくさんのエピソード群となっていたからだ。
《兄ひとりの物語》が、この作品の中心を占めている。
兄の姿に映画のほとんどの尺が費やされている。
弟よりも兄が描かれている。
なるほどと思った。
そこが終演の瞬間、あてが外れて本作のテーマがよくわからなかった理由であり、意外ではあるのだが、
そここそがこの映画の(原作の) 主題なのだと、あとから判った。
この映画、弟はほとんど出演しないのだ。
・・・・・・・・・・・・・
「迷った時期」、これは僕ら誰しも覚えがあるだろう。
ダウン症の弟と距離を取るために、町の高校には行ってみたものの、まったく馴染めずに相当の無理をしている兄ジャックの様子が、この映画の「核」。
街での彼は「心、ここにあらず」で、
「ただ弟からも、両親からも、姉たちからも距離を持ちたい」と願うだけの、兄の心象風景なわけだ。
たぶん原作者ジャコモ・マッツァリオールは、自らの実体験を家族小説に著したのだろうけれど、文才としては少し未熟かな。
そして長編映画は今回初めて手掛けたという、ステファノ・チパーニ監督も、映画作りの編集の腕としてはまだまだなのだろう。
・
でも
観終わって、ひと晩たってから映画の構造がわかった
①導入:弟の誕生
②主題:回避と逃亡
③副主題:両親
④結:ジャック
で、
②の《主人公の街の高校での生活》が、
尺が長い。とてつもなく長い。
だから観客は戸惑った。
しかしある意味ではそのエピソードなんてどうでもいいことなのだ。
主人公ジャックの《目》は
・マリファナに奪われ、
・初めて見るタイプのガールフレンドに目を奪われ、
・ロック・バンドの世界に奪われ、
・環境破壊への抗議活動に奪われている。
あの時間は冗長で散漫で、観る側は疲れるし、飽きてくる。
でもその個々の内容はどうでもいいことなのだ。
あれは思春期独特の、ジャックの目に映っていた光景だから。
だから
観客は目を閉じていても良いし、薄目で流し見して飛ばしてしまっても構わない。
要は、目の焦点が合わなくなっていて、自分がどこに居るのか分からなくなっているひとりの高校生の、永遠に続くのかと思われる、「終わらない迷いの時間の塊」がそこにある。
・・・・・・・・・・・・・
ジャックを見つめる両親と叔母がいる。
「大人になったな」とジャックに告げる父親。
「許すのは親の義務だ」とも。
よく出来た両親だけれども、あの大人たちも、実は、成人した僕たちレビューアーがここまでかかってようやく体得してきたように
あの両親もたくさんの試練と挫折に鍛えられて、やっと「大人になった」その境地に至っているはずだ。
逃げた過去も、逃げたかった辛い現実も、嘘をついたことも、迷ったことも、
両親たちも経てきたはずなのだ。
親として、
ジョーの誕生や、
上の娘やジャックへの配慮や、
必ず思春期の成長過程においてはその人生に躓くであろう息子の成長を受け止められるだけの広い胸。
それが培われてきたのだ。
そういえば
僕が高校生のとき
「僕にはなんにも無い、僕は空っぽなんだ」と悲痛に叫んだとき、母が
「そうかも知れないが、お前には『無』が満ちている」と言ってくれたことを思い出す。
「大人になったな」とジャックに告げる父親。
「許すのは親の義務だ」とも。
演説をして自らの嘘を告白する息子に呆れ果てて失望し、息子を独り置いて帰ってしまった両親が
またスタンスを整えて息子の元へ戻ってくる。
見落としてしまいそうだが、親たちの物語としても優れている。
ジャックも大人になって親になった時、この言葉を子供たちにかけるに違いない。
ドキュメンタリーではなく、あとから味わい深く、観客の共感が湧いてくる「青春文学作品」だったのだね。
ダウン症の家族を持つ家族が、その心持ちをわかり合う映画。
ダウン症の弟がほとんど出演しない不思議な映画。
·
素晴らしい家族愛に感涙!
ダウン症の弟を持つお兄ちゃんが主人公で、
お兄ちゃんの成長物語が軸となって展開していく。
このお兄ちゃんが思考・行動がきっかけで、
痛烈なバッシングを浴びてしまうのだが、
お兄ちゃんの気持ちもわからなくもない。
そして、お兄ちゃんが悪いのではなく、
お兄ちゃんにそう思わせた&行動させたのは、
大人によるところが大きいと思った。
やはり子どもは育った環境や教育によって、
人となりがつくりあげられていくのだと感じた。
しかし、間違いを本人に気づかせることができるのも
大人、特に家族であろう。
ただ、本作のお兄ちゃんはダウン症の弟が
ヒーローだと自身で気づくし、
そこには本当の親友の存在も大きかった。
全く期待せずに観たが、観てよかった。
泣けた!
ステキな家族
ともだちはとてもいい奴だった
24-017
イタリア語ってトーンが明るい
原題を直訳すると
家族っていいな
アレッサンドロ・ガスマンが演じる父親がとても素敵。家族をあたたかく見守り、支え、包みこむ。こんなお父さんだから、ジャックもジョーものびのびと成長するんだなと納得。
もちろんイザベラ・ラゴネーゼの明るくてチャーミングで力強い母親、ロッシ・デ・パルマの演じたジャックの恋の相談役でパワフルな叔母、どちらも大人としてきちんと子どもたちに向き合っている。
ジャックが小さな嘘をついたことから始まった裏切りも、お父さんの愛情がしっかりとフォロー。大好きなお兄ちゃんのためにジョーが鉤十字のTシャツを見せたときが一番良かった場面。
実話を元にした物語。YouTubeに公開されたショートムービーが反響を呼んで小説の執筆につながり映画化された作品。
全41件中、1~20件目を表示