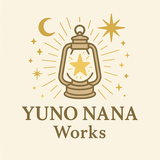あんのことのレビュー・感想・評価
全576件中、1~20件目を表示
どうしたら彼女を救えたのか
彼女がひとつひとつ立てた自分の居場所や、やりがいや、自尊心が、ドミノ倒しのようにバタバタと倒れていく残酷さや無慈悲さに、胸が苦しくなる作品だった。これが実話だなんて…。
彼女を地獄から救ってくれたのも、突き落としたのも、彼女に関わった人々。
学ぶこと、考えることを幼少期の虐待によって奪われた彼女にとって、他人からの影響で簡単に人生を左右されてしまう。それが悲しい。
多々羅刑事が杏を救いたい、助けたいと想う気持ちには嘘は無かったと思いたい。誰かにとっては良い人でも、誰かにとっては悪い人、人間ってそういう生き物なんだと思い知らされた。
コロナ禍を過ごした今、あの時期を振り返ると確かに異常な日々だった。
人と人との繋がりで成り立つ社会で、感染防止を名目に人と人とのコミュニケーションを断ち切ろうとする社会だった。けれど人間は、身体の健康と同じくらい心の健康も大事。身体の健康だけを重視し、心の健康をおざなりにした結果招いた悲劇のように感じた。
あの時、杏のような想いであの日々を過ごした人は、たくさんいたんだろうな。
どうしたら彼女を救えたのか、映画を見た後そればかりを考えてしまう。
ヤッパリ観なければよかった。
2024年上半期の邦画で非常に評価の高い作品ということで、果たしてあまのじゃくのオレが見ていい映画かどうか迷ったが。
「あんのこと」
・
・
・
ヤッパリ観なければよかった。すまん。
お客様が入ってなんぼ、という意味では大成功で、この映画は「あの花が咲く丘で君とまた出会えたら」と同じく、その成果にはとても感服する。
おそらく製作陣が意識したであろう、過剰に哀れな描写はしないという姿勢とは全く真逆の演技と生活描写が目につく。一方、今生存している人類が二度と経験しないであろう、世紀のコロナ流行に、対処している団体、自治体は描かれない。
各キャラクターそれぞれに深みを持たせない設定、描写は理解するが、カラオケで「ランナウェイ」を歌わせるには、その意味が唯一見出せるであろう歌詞の一節を歌わせなかったり、あえての浮世離れの役者起用で、存在感を薄く設定したキャラクターが、思いっきり腰から崩れる。
ごみ捨てはできないが、児相に電話でき、本人の都合通り対処できる母。児相がその家を訪れた描写がないのは、あえて省略したのだろう。主人公を追い詰めないといけないので、そんな脱線はできない、ということだろう。
ラストの母子家庭の廊下のワンカットに希望を見いだせた人は、素晴らしい人で、うやましい限り。
面会シーンでいうと、両者ともに「良心もあるが等しくクズ」で、言い訳、言い逃れ、といった自己弁護、罪悪感のぶつけ合い、という意味があるなら、成功しているかもしれないが、当時を舞台にするならば、いっそそこだけはコロナのせい、と言ってしまったほうがよかったような気もする。
といったように、本作の各キャラクターに関して、「なぜ」の理由は要らないとは思うが、彼らの「背景」には「なぜ」そして「なぜそうなったか」の問題提起を匂わす描写、あるいは問いかけは絶対に必要だと思ったが、よけいなことは入れずに、「主人公熱演」、「救いのない」といった感想にあふれる結果となったのだから、大成功ですね。
伝えたいのは絶望か希望か?この映画が伝えたかったもの
なんの情報もなく、予告編を観て観ようと決めていた作品。始まりからどんよりとした映像と心重くなる内容に、この先への腹を括る。
草薙くんと慎吾ちゃんは騒動後も活躍しているイメージがあったが、久しぶりにスクリーンで観た稲垣吾郎ちゃんがとても新鮮であった。あまり丁寧な説明のない登場であったが「あなた誰よ?」とはならない自然な溶け込み方で主張しすぎることもしなすぎることもなく、ちょうど良かったと思います。そして、メインの多々羅刑事役は佐藤二郎さん。最近ではもっぱら福田雄一監督の作品に、なくてはならない曲者役者として活躍されています。今回は普通(失礼かな😅)の役どころで、物語のキーパーソンでした。それでもやはりいつもの佐藤節は健在で、クセはあります。一癖も二癖も…。でも彼の演じる何者かは、いつも現実社会のどこかに存在していそうなキャラなので、そこまでの違和感はないのです。そして、主人公のあんちゃんを演じた河合優実ちゃん。今回初めて彼女の名前を覚えました。並々ならぬ覚悟で今作に臨んだ彼女の決意が感じられる渾身の演技で、心をえぐられました。他の役も観てみたい、今後が楽しみな役者さんです。
さて、内容はというと…
非常に重いです。
ただ救いのないラストにそこまで引きずられなかったのは、この映画が観る側になんの感情も強要することなく、それぞれの立場の登場人物たちに起きた出来事をただ淡々と伝えることに重きを置いていたからだと思えます。
観終わった後すぐに調べたのは、この映画が事実なのかどうかということ。そして本当の衝撃はそこから…。コロナ禍という未曾有の有事の中、ノンフィクションでないにせよ、このような現実があったという事実に、もはや重い宿題をもらったような胸苦しい気分になりました。絶望する者、手を差し伸べるもの、事実を追い求めるもの、それでもそう生きるしかなかったものたちの圧倒的リアルな物語。
伝えたかったのは、絶望か希望か?
目を逸らすことなく
しっかりと胸に刻む。
杏の希望と絶望を分かち合う
河合優実演じる杏の生々しい実在感に終始圧倒される映画。佐藤二朗の熱さと個性、稲垣吾郎の静かな佇まいが、杏の過酷な人生を見守る私たちのいたたまれない気持ちを少しだけ和らげる。
事前に読んだネット記事には、本作をコロナ禍の物語であると評するものもあった。ただ、個人的な印象としては、そのように括るほど単純な話ではないように思える。
杏は、新聞記事に載った実在の女性がモデルとなっているそうだ。入江監督は、コロナ禍の空気を記録しておきたいという思いもあったものの、「コロナ禍と社会的弱者というテーマがあったわけではなく、むしろ記事に書かれていたひとりの女性について、より深く知りたいという動機が先にありました」と語っている。
そして確かに、この映画は杏(ひいてはモデルになった女性)の心に分け入り、彼女の痛みと希望、絶望をひたすら分かち合う映画になっていた。多々羅の罪やコロナ禍でコミュニケーションが分断されてゆく様も描かれるが、それらの描写に何かを断罪するニュアンスはあまりない。杏の人生があのように進んでいった原因について安易に単純化するような決めつけをしないという、彼女へのリスペクトが感じられた。
河合優実に、元になった記事の女性が憑依しているような錯覚を覚えた。
もちろん直接彼女を知っているわけではないし、またあそこまで酷いDVが起こっている家族に現実に接したことはない。それでも、杏の感情の動き、弱々しくも少しずつ立ち上がり、どうにか前を向いた心がまた折られてゆくさまは生々しいリアリティをもって胸に迫ってきた。見知らぬ彼女に出会ったような気持ちになり、気づけばその行く末を心配しながら見守っていた。
彼女を力強く救い出す多々羅にも心を揺さぶられた。彼があの熱さとちょっとしたユーモアで杏の人生に介入したからこそ、彼女に希望の光が差したことは疑いようのない事実だ。行方をくらました杏を多々羅が見つけて抱きしめるシーンには心を打たれた。
一方で、自助グループの世話役という立場を悪用し、参加者の弱みにつけ込んだ犯罪を犯すというアンビバレントな一面に困惑した。これは実話で、杏のモデルの女性を親身に助けた元刑事が、実際に別の相談者への性加害容疑で逮捕されたという。
そういったエピソードがフィクションにアレンジされる時、こういう行動をとる人物は、得てして「間違いを犯したけど本質的にはいい人」あるいは「実は悪い人だった」といった感じで単純化されがちな気がする。一見相反する行動に何らかの説明をつけ、わかりやすいように描かれる。
しかし、多々羅の描写にそんな辻褄合わせはない。でも、物語を邪魔するような矛盾は感じない。むしろ人間はそんなものかもしれない、とさえ思わせる。この辺の説得力は佐藤二朗の力量も大きいのだと思う。
物語においては、コロナ禍の孤独も確かに杏にはきつかったが、それより多々羅が杏の前から消えたことが彼女の絶望を後押ししたように見えた。それくらい多々羅の存在は杏にとって大きく、唯一のよすがだった。
ただひとつ押さえておきたいのは、多々羅の犯行を報じた桐野が最後に後悔の念を見せていたが、彼は仕事をしただけで間違ったことはしていない。杏と多々羅の縁を断ち切ったのはあくまで多々羅の行動である。
杏の母親を演じた河井青葉の迫力もすごかった。あの容赦のなさがないと、杏の絶望は観客に伝わらない。母親はなぜあのようになってしまったのか。母親が杏をママと呼ぶことに、祖母との母子関係の歪さが透けて見える。現在は一見穏やかそうな祖母と母親は、親子としてどのように過ごしてきたのだろうかと考えたりした。
気になった点もあった。
ひとつは、後半で杏に無理矢理預けられた子(この子のエピソードと、杏を取材した記者と多々羅の告発記事を書いた記者が同一人物、という部分は創作だそうだ)を演じた子役の扱いだ。杏の実家で母親の剣幕に晒される場面も心配になったが、オムツ替えの時に股間をしっかり映してたのがちょっと……。実の親の許可は当然取ってるんだろうけど、本人はそれが映像に残ることについて理解できない歳だし、見てしまっていいのだろうかという気持ちになった。
ブルーインパルスをあの場面で出すこともちょっとひっかかったのだが、監督のインタビューを読むとブルーインパルスそのものがどうとかいうより、その時それを眺めていた自分たちへの自省がこめられているようだった。
「自分たちがブルーインパルスを見ていた一方で、こういう事件が起こって、こんな女の子がいた。地続きのところにいたにも関わらず、そういった事件に対して全く想像力を働かせてなかった自分に『一体何をやっていたんだ』とショックを受けましたね」
なるほど、と思いつつも、あの描写でそれが伝わるのだろうか、という気もした。
杏に子供を押し付けた母親(早見あかり)も、初登場時は随分勝手な人間に見えたが、最後に出てきた時は物語の締めの台詞のためかすっかり殊勝な態度になっていて、キャラがぶれたように見えた。行動の辻褄合わせの描写がないのは多々羅と同じだが、脚本上の人物描写の精度と役者の力量の差だろうか。
とはいえ、河合優実の全霊の演技でスクリーンに立ち現れた杏の実在感は揺らがない。悲しい最期を憐れむより、彼女がドラッグを断ち、あの実家から脱出して仕事を始め、学校に行くようになった、その頑張りを尊敬し、彼女の姿として覚えていたい。彼女の生きた軌跡を見て、そんな気持ちになった。
河合優実は今年を代表する役者
いつもの入江監督のスタイルとは異なるテイストの作品に仕上がっている。できるだけ監督自身の采配を芝居に入れずに観察・記録に徹するようなやり方を今回は選択している。そのやり方が成立するのは、役者への信頼ゆえだが、その信頼に120%役者たちが応えている。主演の河合優実は本作と『ナミビア砂漠』と『ルックバック』で、今年を代表する俳優となると思うが、本作の鬼気迫る芝居は観る人全てをくぎ付けにする。非常に辛く悲しい物語を現実感ある手触りで描いた作品なので、見るのがしんどいと感じる人はいるだろうが、それでも目をそらさせないだけの芝居を彼女がやってのけたおかげで、観客はこの理不尽な現実を受け止めるしかない。
佐藤二朗も善人とも悪人とも決めかねる存在を見事に演じているし、稲垣吾郎の週刊誌記者役もじつにはまっている。母親役の河井青葉もすごい。
実話をベースにしているが、映画のアレンジも加えている(早見あかり関連のシーン)。現実を捻じ曲げたいからではなく、現実の理不尽さを際立たせて伝えるために的確なアレンジだったと思う。この現実にあった理不尽のその本質は何かを真剣に考えたからこそ、生まれたアイディアだったと思う。
目を開かせ、意識を突き動かす秀作
あんの人生は過酷だ。その少なからず痛みを伴う物語を、いかなる語り口で観客に伝えるか。作り手の腕の見せどころはそこにあるわけだが、本作は巧みにハードルを超え、観客の心を一度掴むと離さない。彼女の人生に触れると誰もが他人事ではいられなくなる。この子が少しでも前へ進めますように。ささやかなれど確実な幸せが訪れますように。そう切に思わせるのが河合優実という人の凄さだ。加えて、佐藤二朗や稲垣吾郎演じる役柄が存在感を添える。すべての人が敵ではない。彼女を守ってくれる人はこの世に存在する。そう思える、信じられる幸福。ただし、この映画はやがて意表突く展開を提示すると共に、誰しもが経験したコロナ時代を無慈悲に突きつける。せっかく積み上げてきたものが音なく崩れ落ちていく無念さーーー。我々は日々、どれほど多くの声なき声や慟哭に気付かぬまま生きているのだろう。閉じた目を開かせ、視野を広げ、意識を突き動かす秀作だ。
コロナ禍の“日本人像”を記憶にとどめる営み
どちらかといえば娯楽作の印象が強い入江悠監督が脚本も兼ね、コロナ禍である若い女性の身に起きた実際の出来事に着想を得て映画化した、真摯で重苦しい社会派ドラマだ。近年の邦画では、時代背景と人物らの設定で近い部分が多いのは2021年の石井裕也監督作「茜色に焼かれる」だろうか。またコロナ禍とは直接関係ないものの、2020年の大森立嗣監督作「MOTHER マザー」、2023年の工藤将亮監督作「遠いところ」なども社会の底辺でもがく人々の可視化を試みた点で共通する。
本作の杏のように家庭環境に恵まれず社会経験も積めないまま困窮している人々に手を差し伸べる人も、支援する制度や組織もあるにはある。そうしたセーフティネットの脆弱さがコロナ禍によって露呈した面は確かにあったが、すべてをコロナのせいにするのもきっと違うのだろうと、本作を観て痛感させられる。長いものには巻かれる(上が決めたことには異を唱えず従う)、都合の悪いことや面倒なことは見て見ぬふりをしてやり過ごすといった日本人に染み付いた傾向のせいで、想定外の天災に直面して社会的な機能不全を起こし、結果として杏のような存在を追い込んでいったのではないか。
映画鑑賞後にモデルになった女性や出来事に関心を持った方は、「ハナ(仮名) コロナ 朝日新聞」で検索すると2000年6月の記事が見つかる(有料記事のため無料で閲覧できるのは一部のみ)。本作を観る前に記事を読むとネタバレになるので要注意。河合優実の熱演も含め、「あんのこと」を、そしてハナさんのことを忘れるべきではないし、日本人の脆さと弱さを自問し続けなければならないと思う。
佐藤二朗さんの退場が痛かった💉
シャブって連呼しており俗称ではと思いましたが、覚醒剤(メタンフェタミン)の事ですか。グループセラピー等は海外作品にありそうだなと思いました。折角、生活が上向きになって来た所で、いつもより頼もしい佐藤二朗さんが退場し、お母さんとの生活に戻ってションボリしました。真偽が怪しいコロナ禍の要素は、要らなかったと思います。
観るのを躊躇っていた作品ですが。
希望がない
事実を元にした作品ということが悲しすぎる
希望が削がれ
ある女性の記録として捉えた
全576件中、1~20件目を表示