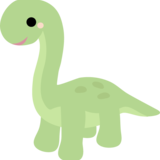「「事実に基づく」は要ファクト・チェック(追記有)」TATAMI ブログ「地政学への知性」さんの映画レビュー(感想・評価)
「事実に基づく」は要ファクト・チェック(追記有)
◇ 映画に対する共感とその印象
映画『TATAMI』は、国家からの抑圧に苦しむ選手の姿を描き、観客に強い感情的な共感を呼び起こす。試合の視界の狭さやモノトーンの映像は、選手の精神状態や国家の閉鎖性を象徴しているとも読み取れる。
◇映画の背景とモデルとなった実際の出来事
映画の舞台は2019年の柔道世界選手権だが、劇中の設定(女子60kg級)は実在せず、実際には男子81kg級のイラン選手サイード・モラエイがモデルとされる。映画は事実を大きく改変しており、観客の印象に影響を与える作りとなっている。
◇ 映画の脚色と現実との乖離
劇中ではイスラエル選手との対戦が実現しないが、実際にはイスラエルのサギ・ムキが優勝しており、対戦の可能性は現実的だった。さらに、イランはすでに世界選手権で金メダルを獲得しており、「初の金メダル候補」とする描写も事実と異なる。
◇イランの対イスラエル政策の背景
イランがイスラエル選手との対戦を拒否する背景には、イスラエルを国家として承認しないという一貫した外交方針がある。これはイスラエルの建国経緯やパレスチナ問題、欧米主導の国際秩序への不信感などと深く結びついている。
◇ 国際政治とイランの対外姿勢
イランの頑なな姿勢は、欧米の干渉や制裁への反発、イスラム革命の歴史、英米の石油利権確保に対する記憶が影響している。こうした背景を無視したままイランを一方的に非難するのは表層的な理解に過ぎない。
◇主人公がパレスチナ人だったら
イスラエルの徴兵制やガザへの攻撃を踏まえると、イスラエル選手の「無邪気な対話」も再考が必要であり、友情美談には疑問が残る。
◇必要なのは体制批判ではなく対話
柔道に対する外国人選手の尊敬の念に学び、体制批判ではなく対話を通じた相互理解が求められると筆者は主張する
◇ 演出の限界と柔道描写の不自然さ(評価対象外)
俳優の柔道の動きは緩慢で、ウォーミングアップもリアリティに欠ける。試合シーンの完成度は低く、柔道に詳しい観客には演出の甘さが伝わってしまう。
全文はブログ「地政学への知性」で
◇追記
多くのレビューが映画の内容を無批判に飲み込んでいるように感じます。この代表がパレスチナの選手でも同じように受け入れるのだろうか?イランがイスラエルを国家承認していないことを承知しているのだろうか?善良なな多くのイラン人がイスラエルを支援する欧米諸国の経済制裁で市民生活が圧迫されていることも踏まえているのだろうか?国の圧力を擁護するつもりはないが、批判ばかりされて態度をあらためるって人間関係でもう難しいこと。国家だったらなおさらだと思います。