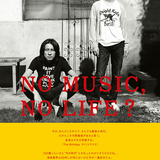小学校 それは小さな社会のレビュー・感想・評価
全110件中、1~20件目を表示
シンプルに面白かった!
感謝します
ワイズマン、想田和弘のような観察映画ではあるが...
特に大きな事件が起こるわけではなく、ナレーションなし、BGMも極力抑えた作品で、ドキュメンタリーの中でも「観察映画」と言えそうだ。
私はフレデリック・ワイズマンの作品はあまり観ていないが、想田和弘監督の作品はそれなりに観ているつもりである。
本作と想田作品、そしておそらくワイズマン作品との大きな違いは、場面設定のレア度だろう。
海外では本作が広く観られているようだが、彼らにとって日本の小学校の日常風景は貴重に映るに違いない。
しかし私にとっては想定内の光景が多く、新しい知見が広がる感じはなく、正直なところ深みもあまり感じなかった。
例えば、えんどう先生が「教育に向いていない」「何度か無理だと思った」と語る場面があるが、個人的には、そうした部分にこそ、もっと焦点を当ててほしかった。
作品には、優しく助け合う児童、熱心で温かい教師たち、どこに出しても恥ずかしくない日本の学校の姿が、徹頭徹尾描かれる。
唯一、シンバルを叩く女の子の存在には、人間臭さがあって良かった。
本来、学校にはさまざまなタイプの子どもがいるはずだが、悪く言えば、この作品(あるいはこの学校)には、あまりにも「優等生だけを集めました」という印象が残った。
そこを「さすが世田谷!」と言えば、嫌味になるだろうか。
また、見た目が外国籍と思われる児童がほとんど登場しない点も気になった(ハーフらしき子は1人いた)。
その一方で、ハーフの教師が登場するのは珍しく、彼の生い立ちや、なぜ日本の小学校教師になったのかが知りたくなった。
さらに珍しいものとして、ルンバ掃除機、卒業式でのモニター演出、公園で遊ぶ子どもたち(実際「初めて公園に来た」と語る子もいた)など、いずれも今の時代ならではの風景だろう。
小さい女の子のことばに心が動く
子供達の心迄届くように
ー 小学校では色々な決まりがあります ー
初めて学校生活を迎えた子供達の何気ない日々を、まるでその場で見ているかのような映像で綴られた作品。
笑ったり、走り出したり、戸惑ったり、目にいっぱいの涙を浮かべたり、何気ない子供達の姿はずっと見ていたいほど (^^)
六年生の児童達の大人びた会話に驚かされる。
「 日々闘いです。」と語る教員の皆さんの熱い思いと踏ん張りに支えられているからこそ成り立っている、改めてそう感じました。
本当に頭が下がります。
ー 足はぴたっ
ー 皆んな優しい子
ー 子供のままでいたい
Eテレを録画にて鑑賞
小さな「日本人」
「敵」を見に行ったときに予告編を目にして気になっていたのですが、タイミング合わず見逃した映画がありました。
2024年公開の「小学校 それは小さな社会」です。
先日偶然NHKEテレで放映するというので、やっと見ることが出来ました。
東京世田谷の小学校に1年間密着したドキュメンタリー。
ナレーションもなく、ひたすら生徒と先生を追いかける。
新入学の1年生は、「小学校」という集団生活に徐々に溶け込み馴染んでいく様子や、6年生は1年生を世話したり係の仕事をしていくなかで、成長していく姿を見ることが出来ます。
子どもが「学校」の中で成長する瞬間を見ることが出来るのは教諭だけであり、親と言えども成長した後の姿しか確認することが出来ません。
その意味でも非常に貴重なドキュメンタリーです。
しかし、タイトルにあるように子どもたちは、「成長」というより、手の挙げ方にまで細かな「きまり」のある小さな社会に適応せざるを得ない、ようにも見えます。
こうして小さな「日本人」が誕生していく。
ほんとに小さな社会
見ていると、小学校1年生はまだ幼児だなと思う。それに比べると、6年生は物の道理がわかり、社会性も身に付いた大人に見えた。1年生も6年生も、日々成長している。まぶしいくらい。
コロナの時の先生方は、本当に大変だったね。全力で子供に向き合う姿に、涙が出た。先生だって一人の人間、葛藤があって当然だ。
サブタイトルの小さな社会というのがその通りで、ひとつの集団の中で、自然に役割が定着していくところはおもしろかった。人が何人かいれば、こうやってうまいこと付き合っていくんだなぁ。
しかし、小学校の卒業式って今こんな派手なの? 私の頃は中学の制服着たりしてたけど、ずいぶんお金かけてるね。都内の富裕層なのかしら。ちょっと驚いた。
Eテレの放送を視聴。
タイトルなし(ネタバレ)
小学一年生担任のわたなべ先生は最初は言い方がきついと思っていたけど言っていることはわかる
🙂↕️
手裏剣を教えて作ってあげてる一年生の男の子が「係とか他にやることあるのにこれじゃできないよどうしよう😨」と戸惑っていた男の子に対し「手裏剣教えてあげるけど作るのは自分でやってくれる?って言ってもいいんだよ?」とわたなべ先生が提案しててそれをやるかやらないかは本人次第だけどあーそれも言っていいんだなって教えてくれる先生だったので良い先生だなと思った
6年生修学旅行先を事前調べで女子児童が
「先生部屋にドライヤーがない部屋があるだってどうしよう💦」
先生「自然乾燥で乾かせばいいじゃん!犬みたいにブルブルって笑」
児童「私は犬じゃありません!」が印象的
もし本当にドライヤーがなかったらフロントに借りるのか?本当に自然乾燥だったのかそれはデマだったのかはわからないけど先生冗談で言ってたのかな?
来年2年生になる児童が新1年生に歓喜の歌(第九)を演奏することになり来年度2年生になる女の子がオーディションに受かってシンバル担当になって朝練で楽譜を忘れて先生に怒られて大泣きしてしまった場面で閉じた
これ以上は自分はのりこえられないと思ってしまった
けど気になっていたので音無しで見てわたなべ先生がいいさんの一番の味方になっていたので視聴を再開しました。
私も一緒に怒られてあげるという言葉に救われました.
なんて愛にあふれた先生なんだ!!!と思った。いいさんに叱った先生も体育館での全体練習で失敗せずできたらほめてくれてとホッとした😮💨
昼休み練習しようねの後忙いでわたなべ先生に走って抱きつきに行ったところを見て本当に先生が大好きなんだな〜落ち込んだ時に抱み込んで
くれる存在がいいさんにいてよかったな☺️
小学校というセーフティーネット
なんとなく違和感‼️❓
タイトルなし(ネタバレ)
東京・世田谷区の公立小学校の1年を撮ったドキュメンタリー。
図らずもコロナ禍の2021年の撮影となり、コロナ禍下での小学校生活の記録となった。
リモート授業の様子が興味深い。
映画は、はじめは探るように様々な生徒を写していくが、そのうち数人の生徒に焦点があてられるようになる。
六年生の放送部員の男子生徒と、この年に入学した女児。
小学校生活を切り取ると、どうしても年中行事にカメラを向けることになる。
放送部員の男子生徒は、運動会・体育祭での集団での縄跳び演技が苦手で何度も失敗、自宅での練習を重ねる。
1年生の女児は、次の4月、新たに新入生を迎えるにあたっての音楽隊でシンバル担当をオーディションで勝ち取る。
が、勝ち取ったはいいもの、なかなか上手く演奏できず、ベソをかいてしまう。
こういうあたりを美談的にまとめていて、日本の小学校教育が集団を第一にしているのがよくわかる。
が、やはり観ていて、息苦しい。
型にはめることが最善、というのは、60歳のわたしが小学生だったころより、強固になっているのかもしれない。
英語タイトルは「The Making of a JAPANESE」。
日本人は、こうやって成型されるんですってね。
三学期制をtrimesterというのは初めて知った
日本の公立小学校の(コロナ禍における)日常をとらえたドキュメンタリー。いや〜観ていて気持ちが悪かった。何に対しても指導かハラスメントか境界線の見極めが難しい社会生活の中で、小学校教育においては未だにアレがまかり通るんだ…と不思議な気持ちになった。そして教育という名のもとに先生たちのものの言い方がいちいち聞いてて気持ち悪い。悪気がないのはわかる。でもその言い方、職場で同僚や部下にしたら一発アウトよ、今。
(抜粋)
>イギリス人の父と日本人の母を持つ山崎エマ監督は、大阪の公立小学校を卒業後、中高はインターナショナル・スクールに通い、アメリカの大学へ進学した。ニューヨークに暮らしながら彼女は、自身の“強み”はすべて、公立小学校時代に学んだ“責任感”や“勤勉さ”などに由来していることに気づく。<
監督とは逆の経歴を持つ自分。
幼少期はインターで、小5から日本の学校。
確かに、掃除や給食の配膳などを子どもたち自身が行う日本式教育「TOKKATSU(特活)」はインターではなく、転校したばかりの時にはかなり戸惑ったのを覚えてる。
インター時代のクラスメイトは全員(自分も含めて)多かれ少なかれ映画の中に出てくるゆうたろう君みたいな部分を持っていたなー。周りと違うことを一切恐れない。違うことこそが個性。それでいい、みたいな。だから先生が『ちゃんと普通にあ歩こうね』とか言ってるのを聞くと「なんで?別にいいじゃん?」ってなる。
自分自身が教育者ってわけではないから小難しいことはわからない。日本の(もしかしたら日中韓かな?)学校教育の独自性についてのドキュメンタリーだというのであれば欧米と比べた時にどこが独特なのかナレーションを入れてほしいと思う。この日本的教育こそが責任感と勤勉さの由来だとするには映像を垂れ流すだけだと説得力に欠ける。なんだかとにかくモヤモヤ続きの作品であたしには全然合わなかったなー。
箇条書き👇️
・小学校の先生は大変なお仕事だということがよくわかった。え?あーゆーことも全部先生達がやってくれてたんだ!と気付かされる場面が多々ある。
・小学校の卒業式で当時のあたしの担任(24歳男性)も「初の卒業生」であるあたしたちクラスを送り出したときギャン泣きしてたなーと思い出した。
・公立小学校の卒業式で羽織袴を身に着けたりするんだねー
都内の小学校での、普段の生活模様。 1年生と6年生にフォーカスを当...
都内の小学校での、普段の生活模様。
1年生と6年生にフォーカスを当てて、1学期から3学期まで。
4月、ランドセルが重たそう、落ち着きのない新1年生、その子らを手伝う6年生。
徐々に集団生活や規律を学び、
年度末には、新2年生として次の新入生を迎える準備とか、卒業式の準備とか。
授業の合間には、給食とか掃除とか靴箱整理とか etc.
日本で生まれ育って、確かにかつて通った道なのは間違いないのですが
あらためて体系立てて紹介されると、すごく規律を訓練されていたのだなあと、再確認になる映像でした。
本作の英語題がまた刺激的で…
"The Making of a Japanese"
劇場公開は、日本より他国が先だったそうですが。
映画中でも、日本の教育体系は "諸刃の剣" だと指摘されていたとおり、
集団ありきで、皆が平均に近づく、よほどの乖離は減る、でしょうね。
自己主張より全体調和。
久しぶりに日本に戻った人から
"日本は、下がひどくない"
(平凡な人でも、そう悪いわけでもない、の意味)
のような言い方をされることが、しばしばあります。
一方で、飛びぬけた人が日本では出づらいことにも納得です。
スーパー人材が少なく、トンデモ犯罪も少なく。
耳と胸が少し痛くなる映像記録でした。
日本の社会に関する新たな視点を与えてくれた作品。
日本人は、小学校で、「日本人」になるらしい
録音技術にただただ驚かされる
確かに、カットの長さは短く、BGMや(ごくわずかな)テロップもある。けれど、ナレーションはなく、結果、映画の解釈を視聴者に大きく委ねようとしてくれている「感じ」がして、それが視聴していてとても心地いい。
ただ、編集者の意図はおそらくかなり明確で、まるで台本でもあるかのようなテンポの良さと物語展開。
そして、その意図を表現するのに大きな役回りをはたしたのが、この撮影ユニットの録音技術だと感じた。なぜなら、「よくこれ、録れてたな」という場面がいくつもあったから。映像ももちろんだったけど、編集でどうにもならないだろう録音の方がびっくり。
いずれにせよ、何回も視聴して、自身の解釈の移り変わりを楽しんだり、昔の同級生や同年代の誰かと語り合いような作品。
教育従事者なら違う視点で観れたかも
なぜか自分の卒業式より泣けた
全110件中、1~20件目を表示