リンダはチキンがたべたい! : インタビュー
片渕須直監督、「リンダはチキンがたべたい!」は「僕たちを自由にしてくれる映画」と独創性を評価 来日した監督陣と対談
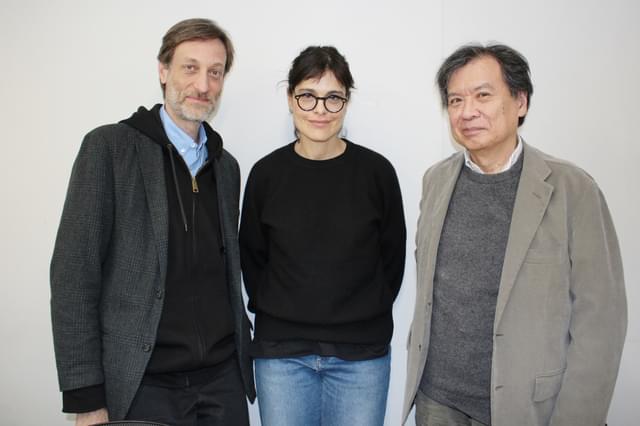
アヌシー国際アニメーション映画祭2023の最高賞にあたるクリスタル賞を受賞した「リンダはチキンがたべたい!」が公開された。
気鋭の映画作家キアラ・マルタが私生活のパートナーでもあるアニメーション作家セバスチャン・ローデンバック(「大人のためのグリム童話 手をなくした少女」)とともに共同監督した本作は、8歳の少女リンダがかつて一緒に暮らしていた父が作ってくれたチキン料理を食べたいと懇願する。街じゅうがストライキで、どんな店も閉まっているなか、母のポレットは思い出の味を再現しようと奮闘する……という物語を、実写映画的な演出と、カラフルな色彩設計、ワイルドで大胆な描線のアニメーションで表現する。
このほど、両監督と交流のある片渕須直監督(「この世界の片隅に」)が対談した。

(C)2023 Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films, France 3 Cinéma
――ローデンバック監督の前作「大人のためのグリム童話 手をなくした少女」とは、だいぶテイストの異なる物語ですね。
セバスチャン・ローデンバック(以下、セバスチャン):自分は1度作ったものと同じようなものはもう作りたくないのです。いつも違う作品を作ろうと考えますし、今作の原案はキアラで、すべてキアラと共同で監督、脚本執筆をしました。
片渕須直(以下、片渕):僕もセバスチャンの作品には、「手をなくした少女」のような重厚なイメージをもっていましたが、今回の宣材のビジュアルからわかるように、そういった話ではなさそうだったので、一体どんな新しさが生まれたのか、非常に期待していました。そして実際に鑑賞し、この作品の自由さを楽しみました。今度はキアラのほかの作品を見たくなりました。彼女の作品をいくつも見ることによって、この作品が特別なものだとわかるのだと思います。

(C)2023 Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films, France 3 Cinéma
――本作のキャラクターたちには「1人1色」が割り当てられ、リンダは黄色、母ポレットはオレンジといったように全編通して1色で描かれるという独特の手法が取られています。肌の色も様々、異なるルーツを持つ人が住み、市民が社会問題解決を求めてデモをする……フランス映画らしい設定だと思いました。
キアラ・マルタ(以下、キアラ):物語の舞台は団地ですが、子どもが自由に移動できることが必要だったので、パリのような大きな都市を避けようと思いました。地方都市のそばにある郊外の、架空の街です。そして、現代ではありますが、いつの時代とは明言していません。最初の方でデモについて流れるラジオは、60年代の実際のニュース音声を使って、敢えていつの時代かわからないようにしています。
一目で見て誰かがわかるよう、1人1色と設定しました。実は、それは絵をきちんと描き込む必要をなくすところからの発想なのです。アニメーターにも、キャラクターの絵を正確に書く必要はない、と指示しました。実写の俳優もシーンによって全然違う顔をしたり、出演する作品によってあの同じ俳優だとは思えないような顔をします。しかし、アニメーションはいつも同じキャラクターが、同じような顔に固定されてしまう。ですから、この作品ではそんな制約を取り払ってみました。また、群衆シーンになった時に、様々な色があると楽しく、カーニバルのような、紙吹雪を飛ばすような明るい雰囲気も出せると思ったのです。

(C)2023 Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films, France 3 Cinéma
片渕:お話も完全にリアルなことではなく、こうあってほしいという願望が物語によって実現される作品ですね。なのに、絵も描きこみは少ないけれど、見終わった時に確実にその人物が存在した印象を覚えました。それは、キアラが声の録り方も工夫したのだと思うし、そこにセバスチャンのアニメーションで、リアルにそこにいるような人の佇まいや動きを作り上げていたと思います。それは、最初の役割を超えて、複雑に絡まり合っていって、それぞれの人物たちが1枚の絵だけで表現できないものになっていったのではないでしょうか。
キアラ:今作は子どもに向けた、子どもについての映画ですが、都市を舞台する中で政治的な要素を入れました。デモを語ると、どうしても子どもたちが不在のまま語られることが多いので、ちゃんとそこに子どもも参加していることを表す、そのこと自体が政治的な行為だと思っています。
セバスチャン:実は、フランスでも子どもと政治が繋がる作品はそれほど多くありません。ただ偶然にもこの映画を作った同じ年に、別のフランス映画のアニメーションの新作で、工場がストをしている描写がありました。それを見ると、やはりフランス的だと思いました(笑)。

(C)2023 Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films, France 3 Cinéma
キアラ:フランス映画ではありつつも、私はイタリア人なので、イタリア的な要素もある作品だと思います。私は今フランスに住んでおり、日本の皆さんよりはフランスを外国とは思わないくらい、両国は近い関係ではありますが、伝統は違います。イタリアではデモなど政治的な話をする時は、アイロニーを込めて話されることが多いですが、やはりフランスでは、より真面目に捉えられていると感じます。また、イタリア人の方が、自虐的なギャグを言う傾向がフランスより高いかもしれません。
セバスチャン:フランスとイタリアは隣り合っていますが、文化的には全く異なると思います。アニメーションについてはフランスの方が圧倒的に制作数が多いです。長編はイタリアではなかなか作れません。フランスではアニメーションの有名な学校もあり、アニメ制作はとても盛んです。今回、かなりの人数のイタリア人のアニメーターが参加していて、制作期間はフランスに住んでもらいました。1人1人のアニメーターにシーンごと全部任せるという形をとったので、1人1人が責任を負う形です。その分、自由な作り方ができたので、途中でこのカットを付け足そうとか、これはやめようとか、そういう変化が常にありました。

(C)2023 Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films, France 3 Cinéma
例えば、本編の中でヘリコプターが飛んで、俯瞰で団地を見下ろし、カメラが下がっていくと、霧で何も見えなくなるカットがあります。あれは制作が始まって、もう4分の3ぐらい全体ができていた時に、キアラが現場にやってきて、「こういうカットがあったらいいんじゃない?」と提案したものです。もともと絵コンテにも描かれていなかった、そういうアイディアも取り入れられました。
キアラ:でも、セバスチャンには、「いきなりそんなこと言うなんて、自分がリドリー・スコットのような巨匠だとでも思ってるのか?」なんて言われてしまいましたが(笑)。技術的に難しい提案をしたことで、私はアニメーターたちから嫌われたと思います。しかし、制作がスタートしてからすぐだったらもっと早く嫌われていたでしょう(笑)。4分の3時点まで終わっていたので良かったのです。
片渕:あの俯瞰のカットはものすごく大変なのがわかります……(笑)。霧のシーンは、その正体が何であるかということより、団地の広場にいた人たちを全部包み込んで、それまでの人間関係が全部洗い流されて、また新しい人間関係が築かれる瞬間だったのですよね。それまでずっと人々の間にあったカメラアングルが、突然空から別の客観的なアングルになったのは本当に効果的です。あれは必要なカットだったと思います。
キアラ:私は、創作においてはいろんなものがごちゃ混ぜになっていることが面白いと思っています。同録のリアルな音はドキュメンタリー風ですし、そこに完全なイマジネーションも混ざって、夢のシーンもある。こういう風に進むのかな……と思わせて、まったく違うようにレールから外れてしまうような連続が面白いと思って制作に臨んでいます。

(C)2023 Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films, France 3 Cinéma
――アニメーションのみならず、音や音楽へのこだわりを感じました。
キアラ:音響監督のエルワン・カルザネとの仕事が決定的でした。彼が、この映画のサウンドのコンセプト、全体像を作ってくれました。レオス・カラックス監督の「アネット」の音響にもかかわっていて、彼から作曲家のクレモン・デュコルを紹介されました。クレモンはニーノ・ロータやミシェル・ルグランのように、作曲のみならず作品の色を作ってくれる、そういう仕事をしてくれました。映画の背景画はアニメーターではなく、画家にお願いしたことも良い結果をもたらしたと思います。
▼国際共同制作など、アニメーション人材の国際交流について
――本作はフランスのスタジオで、イタリア人アニメーターとともに作られた作品ということですが、日本のアニメーションも国際的な協業が進んでいる印象を受けます。
片渕:日本のアニメーション業界でもさまざまな国のスタッフを交えての仕事が盛んになっています。実は、僕も2019年の11月にフランスに行ったとき、今手掛けている新作をフランスの若い人たちと一緒にやりましょうと話していたのですが、コロナの感染拡大のためにできなくなってしまいました。フランスの方々と一緒に作品を作る機会を失ってしまったのは残念でした。
フランスにはゴブランという国立のアニメーション学校があって、世界各国からの学生が集まっています。そこで、何人かのグループにわかれて作品を作っているんですが、コロナ禍では、学生たちはそれぞれの国に帰ってリモートで制作しました。リモートを使うのなら、完成作の講評も、フランスの講師だけではなく、外国の人にもしてもらおうとなって、僕も講評したことがあります。国境を越えていろんなことが近くなっています。だからこそ、この「リンダはチキンがたべたい!」が日本でも公開されるのでしょう。こういった世界のアニメーションが見られる機会が増えるといいなと思っています。

(C)2023 Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films, France 3 Cinéma
ひとつ残念なことは、ゴブランで日本人の学生に出会えないことです。日本人は若い人も年を取った人も、世界のいろんなものに興味を持つべきだと思います。そうやって視野を広げることが、その人を自由にすると思うんです。「リンダはチキンがたべたい!」は、僕たちを自由にしてくれる映画です。日本のお客さんにもこんな面白いものがあるんだって、知ってほしいですね。
――片渕監督との友情を通して、アニメーション監督として共鳴する部分はどのようなことですか?
セバスチャン:「この世界の片隅に」をはじめ、片渕監督の作品を何度も見ていますが、自分と共通点を感じるのは、片渕監督もキャラクターを通して、世界をありのままに描くことを大事にされているところです。リアルではない表現でも、真実を伝えることができると思います。私たちは、アニメーションや実写と分けて考えないのです。おそらく片渕さんもそうなのではないでしょうか。

