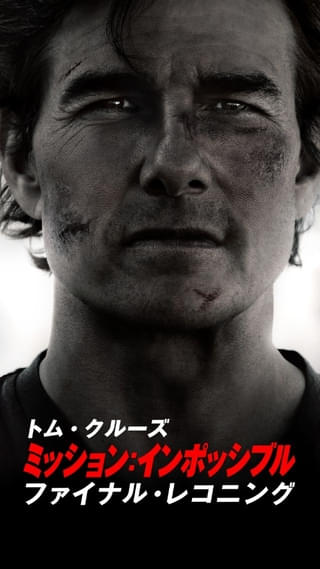コラム:メイキング・オブ・クラウドファンディング - 第11回
2017年11月6日更新

松原保監督の「被ばく牛と生きる」にドキュメンタリーの神髄を見る
10月28日より映画「被ばく牛と生きる」がポレポレ東中野にて公開されている。本作はこれまで数々のテレビ番組のドキュメント制作を手掛けてきた松原保氏の映画初監督作品である。松原監督は、4年間にわたり40回近く毎週末福島に通い、警戒区域の中に住んだり、数十キロ離れた避難先の仮設住宅から通って被ばくした牛の世話を続けている人たちを取材した。その膨大な映像を映画化した作品は、監督が愚直に人々に向かい合って作られた。
20分のコンテスト応募作品が映画化されるまでの経緯やドキュメンタリー映画を撮る意味、クラウドファンディング達成に至るまでの努力について、松原監督と、《いのち》をテーマにしたドキュメンタリー映画の監督として知られ、本作ではプロデューサーを買って出た榛葉健氏のお二人に伺いました。

■偶然の再会から映画作りがスタート
大高 そもそも映画を作ろうと思ったきっかけは、どのようなことだったのですか?
松原 映画を作ろうとは思っていなかったんですよ。もともとテレビ用で、海外に向けて、というアプローチをしてきたので、ドキュメンタリーとはいえ、番組的なものを作ろうとねらっていました。日本の民放での放送は無理だとわかっていたのですが……。
榛葉 そんなことないよ(笑)。民放が原発問題についての敷居を高くして、放送しないというわけではありません。ただ、松原さんのラッシュを見た時、これは映画にした方がいいと思ったので、僕の方から映画にすることを勧めました。彼の思いもそれに近かったですし。
大高 「テレビで海外」というのは、海外の放送局で放送しようということですか?
松原 もともと震災は関係なく、海外でのドキュメンタリー放送に活路を見出そうとしていたのです。
榛葉 私が大阪でやっているドキュメンタリー映画祭があるのですが、今から2年前の2015年の夏、松原さんがそこでのコンテストに、今回の映画の原型になっている20分の短編を応募してきたのです。私は審査する側でしたが、10年間審査をしていて初めて満点をつけたのがこの作品でした。
表彰式が終わった後で、松原さんが挨拶に来られました。若いころに一緒に仕事をしていたことがあったのですが、25年ぶりくらいの再会でした。私がまだテレビの仕事を始めて3年目くらいで、関西で情報番組のディレクターをやっていた時に、彼は外部プロダクションのディレクターでワンコーナーを担当されていたのです。それ以降は一緒になることがなく、まったく出会わずにいて、応募者の名前を見て「見覚えがある名前だな」とは思ったのですが、「榛葉さん、大変ご無沙汰しております」と言われてようやく「あれ?」と思い出しました。
そこで、「実は今日の作品は20分なんですけど、4年間撮りためた膨大な量の映像がある。発表する場はどうしたらよいか」「映画化にもチャレンジしてみたい」という相談がありました。だけど、松原さんには映画の経験はありません。テレビのドキュメンタリーも1時間くらいのものは作られているけれど、2時間スケールのものを作ったことはなかったのです。
一方、私は阪神・淡路大震災の時にTBS系列で特別番組のチーフディレクターをしていて、長編ドキュメンタリーをいっぱい作っていました。他にも、ヒューマンドキュメントやスポーツドキュメントなどをテーマにするなど、いろいろなことをやってきていて、テレビの経験はいっぱいあります。映画の方では2001年から「震災といのち」をテーマにした2本の映画を制作し、国内・海外で上映してきました。ですから、お役に立てることがあるならと思い、「1度ラッシュを見せてください」と、1か月後に松原さんの事務所に伺いました。
2時間半ほどのラッシュは、このままでは映画にできないようなものでした。けれども随所に、ものすごく研ぎ澄まされた、長期間取材をしている人でないと記録できないような、当事者の声や映像がありました。これはどこかで発表しなくてはならない、じゃあ映画にしましょうということになったのです。そこから1年がかりで編集と追加撮影を行いました。足りないシーンがいくつかあったので、こういう映像を撮ってください、こういう当事者の思いをちゃんと引き出してきてくださいなど、いくつかリクエストさせていただきました。
■会社が危機に瀕しても取材を続けるドキュメンタリスト魂
松原 4年半以上もずっと自分で全部資金を出していたので、ここからさらに映画化にもお金がかかるのかと。これ以上自分の懐からお金を出すと会社が本当に危なくなってしまうこともあって、クラウドファンディングで資金を募ることにしました。1回目は制作資金でした。
榛葉 最後の福島ロケでは皆さんからのクラウドファンディングにご協力いただきました。この撮影は私が指示を出したんですよ。「こういうシーンがないと、絶対映画の終わりにはなりませんよ」って。もし撮影のためのお金がなければ僕が出すつもりでした。「お金がないから…」と松原さんが福島取材を渋っていたので「ダメ!」って言いました。そうしたら、松原さんがご自分でMOTION GALLARY さんを探してこられて、「クラウドファンディングでやります」って仰ったんです。
大高 その最後に撮られたシーンというのは、映画の最後のシーンですか?
松原 そうです。一番最後に撮ったのが、映画でもいちばん最後のシーンです。
榛葉 追加の撮影にあたっては、二つのことを指示しました。一つは技術的なことで、ドローンでの撮影です。タイトルバックになっているシーンも、ドローンでの撮影です。もう一つは、すべての出演者の方の5年間の想いを総括するインタビューを撮り直すことです。インタビューにどういう答えを期待しているかについては、僕は言いませんでした。ありのまま、5年間の想い、正直な5年間の気持ちをちゃんと撮って下さいとお願いしました。
そうしたら、松原さんは、ちゃんとその二つを撮ってきてくれました。これは大きかったですね。
松原 資金がちゃんと確保できるのであれば、ドローンだってへっちゃらだし、私も自分の力で行ってやりたいという気持ちはあります。しかし、自分の手持ちの資金を出して、何とかしのいだり、やりくりしたりしていたので、どれだけお金を出さずにできるかというところがありました。お金がないと発想は縮こまってしまうものです。
大高 製作と制作を兼務すると大変で人格分裂のようになってしまいますよね。
松原 分かっているのに出来ないもどかしさが、自分の中でジレンマとして存在しているんですね。
榛葉 私がドローンでの撮影を必ずやってほしいといったのは、原発の位置と登場人物の牧場の位置関係をワンカットで分からせることのできる構図を持った映像が必要だからです。また、本来牧場だった場所が、雑草だらけの荒れ地に変わっているという話を聞きました。であれば、それがラストシーンになります。遥か遠くでもいいから、ちらっとでも構わないから、原発の建屋が見える関係性をワンカットで表現できたら、そのシーンには大きな意味が生じます。そのあとは見てくださる方々が、ここで何が起きているのかを感じていただければ十分です。ですから、その画は撮ってくださいとお話ししました。
これらの実現に、クラファンのおかげは大きいですね
松原 あとは車ですね。警戒区域の中を自由に動こうと思ったら車が必要なんです。しかし、レンタカーでは許可証が発行されないので、事前に車のナンバーを登録しておかなければなりません。自分の大阪の自家用車のナンバープレートを登録して、それに対する許可を得る仕組みで、自由に動くにはその車でなくてはならないのです。だから、しんどいのですが、車で大阪から自分で運転していかねばなりません。
榛葉 週末行って、月曜の明け方に帰ってきて、月~金曜日はプロダクションの仕事をして。大変なことです。松原さんが自分では言いづらいと思うので代わりににお話しすると、福島での撮影のために、松原さんの会社は潰れかけているんです。小さいとはいえ、ちゃんとしたプロダクションです。ですが、社員の方が「このまま社長と付き合っていたら、この会社危ないのでやめます」といって辞めちゃったんです。でも辞める人が悪いわけではなくて、普通に考えればそうなるでしょう。
わずかな人数でやっている会社の社長が、会社の経営よりも、ご縁のあった福島のことを必死でやっているのは、尊いけれども経営者としてはだめです。でも、彼は福島の方々のことを放っておけずに通い続け、結果倒産寸前のところまでいって、社員がやめ、奥さんと2人だけになり……。大阪の映画祭のコンテストに応募してきたのはその頃で、会社の窮状も聞きました。映画作りを仕事として請け負うこともできますが、そんな状態ではなかったのです。本当にお金がなかったのです。
それでも何とかしないと、せっかく4年間撮りためた福島の映像が埋もれてしまうのです。埋もれるということは、松原さんの努力が無に帰するということでだけはなくて、彼を信じて取材に応えて下さった福島の方々の思いも無に帰することになってしまいます。それならば、私にもドキュメンタリストとしてやるべきことがあるなと合理的に思えたのです。
世の中には、伝えたい思いがあって、それを語りたいけど語れない人たちがいます。その人たちの想いを、僕たちプロの表現者が、世の中への架け橋となって届けるのは当たり前のことです。これはドキュメンタリーの役割でもあります。採算は関係ありません。松原さんの思いに何とか応えたいと思いました。こうやって頑張っている人たちが潰れちゃったら、日本の映像文化は途絶えてしまいます。合理的な人だけが映像作家、映画人、制作者として生き残って、松原さんのような愚直な制作者が消えてしまったら、本当に伝えるべきことが伝わらなくなります。
仕事ではないところで私がこれまで応援してきたのは、戦場で映像を記録しているようなドキュメンタリストとか、採算性を目的にせずに、心に響くドキュメンタリーを世の中に届けたい、と努力してきた映画監督たちです。福島でも同じで、こういう人たちを本当は大手のメディアが守らなくてはならないのです。少し補足をすると、私が普段働いている毎日放送は、日本の放送局の中で最もドキュメンタリーをきっちり作る会社の一つです。レギュラーのドキュメント番組もあり、極めてきちんとしている放送局だと自負しています。
松原 一銭のお金もない中、知恵を使って時間を使って、プロデューサーがここまで許してくれる会社はありませんよ(笑)。今はそれに甘えています。
榛葉 映画の製作は、個人の立場で協力させて頂いているのですけどね。
■テレビと映画でドキュメントはどう違う?
大高 ドキュメンタリーをテレビで公開するのと、映画にするのとでは、良し悪しなど違いはありますか?最近でいえば「ヤクザと憲法」など、もともとテレビ用に作ったものを映画として再編集することも増えてきているように感じます。その線引きといいますか、どういうものをテレビにすべきで、どういうものを映画にすべきというのはありますか?
榛葉 実は、日本でテレビのビデオドキュメンタリー番組を初めて映画化したのは私なんです。いまでは東海テレビの阿武野勝彦さんなどが有名になられて、定期的に映画化されていますが、最初は私が始めました。1本目の作品の「with…若き女性美術作家の生涯」はもともとテレビ番組で、阪神・淡路大震災で被災した神戸の女子大生の生きざまを描いたドキュメンタリーです。テレビ放送のたびに再放送のリクエストが殺到して3回放送しました。さすがに再放送はもうないなと思っていた時に、国際的な賞を受賞して、映画化のオファーがありました。それで映画のプロデューサーに「制作費を出していただけるんですか?」と聞いたら「あなたが出すんですよ」と言われました。「なんだそりゃ」と思いましたけどね(笑)。
当時、テレビはまだハイビジョンではなかったので、画質が粗いのです。映画界からは「画質の粗いものを大スクリーンで流しても誰も見やしない」とバカにされ、会社からは「ドキュメンタリー映画は採算が取れないから無理だ」と言って止められました。それでも登場人物との信頼関係など、いろんな思いがありました。テレビ番組のままでは倉庫に眠るだけになってしまう。主人公の生きざまを後世の人に届けるためには、映画にする必要がある、十年先の人にも見てもらえるコンテンツとして、世に出しておく必要があるとの気持ちから、制作費を自己負担で映画を作りました。
すると、会社も私の思いに応えて、著作権の部分を穏便に見てくれ、映像を出してもいいということになり、制作・著作に毎日放送を残したままで映画化できたんです。それが最初のドキュメンタリー番組の映画化です。この「with…」は、ほぼテレビ版と近い関係でした。
2本目の「うたごころ」は東日本大震災で被災した宮城県南三陸町の女子高校生が主人公の映画です。その頃私は会社では管理職になって、報道の現場からは離れていたので、休暇をとってボランティアで現場に入っていました。その時、避難所で出会った高校生の気持ちに触れて「この子はまちがいなく主人公になる子だな」と思ったので、持っていたビデオカメラで2年間撮影しました。その途中で、テレビにしようか映画にしようかを当然ながら考えました。やはり私の本拠はテレビなので。
けれど、テレビでやるとどうしても短くまとめなくてはならなくなります。1時間のドキュメンタリーでも2時間のドキュメンタリーでも、数十万~数百万という不特定多数の人に分かりやすく伝えようとするという仕組みがシステムとして働きます。これはテレビという媒体の持っている特性です。ケーブルを含めるとチャンネルは何十もあります。地上波だけでも同じ地域に6チャンネルとか7チャンネルとかあって、スイッチ一つですぐにチャンネルを変えられてしまいます。だから、今のテレビはじっくり見るものではなくなっています。瞬間的な訴求力などに左右されるので、テレビ番組を作る時は「間(ま)」を削っています。
大高 余白をどんどん削るんですね。
榛葉 どんどん削ります。余白を作ったらその瞬間にザッピングされて、ピュッってチャンネルを変えられてしまうから、そこを埋めます。どんどん削っていって、余白がありそうな所には音楽を入れて煽ったり、ナレーションで状況の描写をしたりして、手取り足取り全部やってしまうんです。
松原 ラッシュの連続ですよね。そうでないとチャンネルを変えられてしまいます。
榛葉 その恐怖心があるんです。
大高 全体の尺の問題ではなくて、ひとつひとつラッシュしていく感じですね。
松原 映画館っていうのは、その場所から逃げられませんよね。
大高 退室できないから、作品全体を考えた上での演出的な布石が打てますね。
榛葉 じっくり見ていただけるでしょう?そこがポイントです。「うたごころ」を作った時に、テレビ番組でも映画でもいい、どっちにでもできると最初は思っていたのです。しかし、ずっと取材していて、主人公の女子高校生の肉声を聞き書きのようにして長時間撮影をしているうちに、「この子の感情の起伏や揺れのようなものを表現するのはテレビでは不十分だな」と思い始めました。
映像を短く刻めば刻むほど、分かりやすい言葉だけが残ります。そうすると、極端に言うと「被災をしたけれど、この子は頑張っています」などと単純なステレオタイプにまとまってしまうのです。でも、その子の2年間って、頑張っている日もあれば、深く沈んでいる、沈殿しているような日もあるのです。そうした感情の起伏をちゃんと表現しようとすると、ロングインタビューをありのままに出したほうがご本人の感情に近いのです。そうすると映像を切ることはできません。例えば息継ぎをする瞬間も、「一滴の涙を流すまでの2分間」といった時間も、ずっと残したいんです。
テレビだと涙が流れるまでの2分間を待てません。最後の10秒間の涙を流す瞬間だけしか放送できません。それでも、その子の涙を流す心理状態は2分前から始まっているのです。だからそこを残す表現法を考えなくてはなりません。あくまでも当事者主体で考えて行った時に、どの媒体で表現をするかは後から決まってくるのだということを、私はその時に学びました。
その経験があって、全国で劇場公開した後で「榛葉監督、次はぜひ福島の映画を撮ってください」と言われて、「がんばります」とはいったものの、それまでに福島に私が入ったのは1回か2回しかなかったんです。その時点で、既に大勢の方が福島でドキュメンタリーを撮られていましたから、これはちょっとレイトカマー(=遅れて来た人)の私にできることは殆どないな、何かはしたいけれど……と思っていたのです。
そこに松原さんがコンテストに作品を応募してきて、「長編を作りたいけど、何とか力を貸してもらえませんか?」と言われました。だから、これは私の役目だと素直に思えたのです。彼の経済的な困窮も勿論ありますが、福島を舞台にしたドキュメンタリーを作るという、私のファンになって下さった方からの思いに応える一つの道だとも思えました。私は松原さんの映画として立てながらも自分にとってもやるべき主体性があると考え、「ゴースト監督(笑)」みたいになって一緒に今回の映画を作りました。
大高 面白いですね。テレビの「詰め込んでしまって、ある種の結果だけをバンバン並べる」ような感じよりも、映画では曖昧というか明確に言い切れない部分を表現しているのでしょうか。
松原 そうですね、空気感というか、考える間ですね。映画館というというのは閉じ込められた環境の中に置かれるので、見る人たちが、心情をどれだけ映画の中に入って行かせられるか、試みのできる表現の場です。テレビでは持てない間を作ることができます。
榛葉 お客様にそれを感じ取って頂けるように、どれだけ設(しつら)えておくかということです。
松原 特にテレビでは、最後に大きな結論というか、締めが必要です。映画にもそうした部分はありますが、見せて考えさせて、相手にボールを投げかけたままで終えることが可能です。今回の映画は、投げかけて、考えてもらえるような結論にした方が良いと考えました。
大高 それで、今回は映画というフォーマットになったのですね。
松原 自分の言いたいこともありますが、それを極力押し付けないで、考えてもらいたい、自分の持っているものを削ぎ落として、ありのまま、素のストーリーで考えてほしいなと思います。
コラム