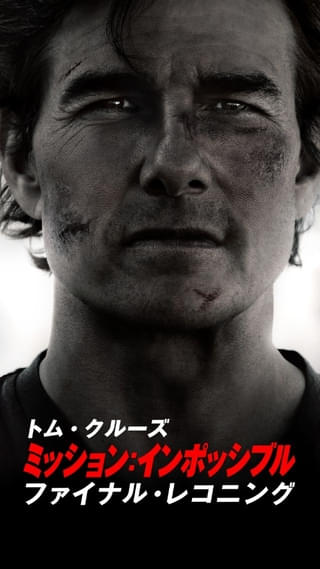コラム:若林ゆり 舞台.com - 第66回
2018年4月6日更新

第66回:長塚圭史が「スリー・ビルボード」のマクドナー戯曲でブラックな笑いを引き起こす!
「スリー・ビルボード」で多くの映画ファンを魅了したマーティン・マクドナーは、元々は劇作家だということをご存じだろうか?(ついでに言うと彼はアメリカ人ではなく、イギリスとアイルランドの国籍をもつロンドンっ子)。マクドナーの戯曲は2000年代前半、ロンドンやニューヨークの演劇界でしばしばセンセーションを巻き起こしたが、ロンドンでは2003年の「ピローマン」以来、ブロードウェイでは2005年にアメリカを舞台にした「スポケーンの左手」以来、長きにわたり彼の新作戯曲が上演されることはなかった。彼自身の希望によって演劇界から離れ、映画に軸足を移したためだ。そんなマクドナーが2015年、ついに10年ぶりに発表した新作戯曲が「ハングマン HANGMEN」だ。
この「ハングマン HANGMEN」が、いよいよ日本でも幕を開ける。演出を手がけるのは、劇団「阿佐ヶ谷スパイダース」の主宰で、これまでにマクドナー作品3本(「ウィー・トーマス」「ピローマン」「ビューティ・クィーン・オブ・リーナン」)の演出経験を持つ長塚圭史。彼が初めて演出した翻訳劇が2003年の「ウィー・トーマス」であり、これは気鋭の演出家として長塚の名を広く知らしめた意欲作だった。その長塚に、マクドナーの魅力について語ってもらおう。まず、マクドナー作品との出会いとなった「ウィー・トーマス」を振り返ると?

「これは、マクドナー作品の中でもとくに凄惨なタイプの異色作で、ロンドンでめちゃめちゃ話題を呼んでいた作品なんです。アイルランドのアラン諸島にあるイニシュモア島を舞台にした、アイルランド国民解放軍の話で。トーマスっていう猫が、飼い主でクレイジーな解放軍中尉、バドレイクの留守中に死んでしまう。パドレイクはその猫をものすごくかわいがっていたから、帰ってきてそれを知ったらみんな殺されると島のやつらが怯えて、近所の猫を黒く塗ってごまかそうとするんです。とにかく舞台に死体がいっぱい出てきて、お父さんが息子の殺した死体を解体するというとんでもない舞台なんだけど(笑)、これが、イギリスで大当たりした。ところがこの作品を、僕が小劇場の俳優たちを集めて日本でやったときは、なかなかお客さんが入らなかった。でも舞台上に死体がゴロゴロ転がるようなかなりのブラックコメディで、生きた猫も出ている、というので話題にはなって、ちょっとずつお客さんが増えてきたのはよく覚えています」
この日本初演時にはマクドナー本人が見に来て、一緒に痛飲した思い出もあるという。
「マクドナーは、けっこうワイルドな感じがありましたね。終演後には一緒に飲みに行って、全然帰ろうとしなかった(笑)。面白かったなぁ。僕が28歳くらい、彼は30歳過ぎかな。『ウィー・トーマス』は残酷さの表現がかなり重要な要素なんですけど、そこを彼は評価して、喜んでくれましたね。仕掛けが満載なんです。鉄砲を撃つにしても、あまり嘘っぽいとつまらないのでものすごい量の火薬を仕込んだ。見事だった、と言ってもらえました。日本のスタッフの優秀さに感嘆してくれたし、『作品の本質は突いていた』と面白がってくれました」

暴力的で凄惨な場面なのに、笑えてしまうユーモアの妙。これは、クエンティン・タランティーノにも共通する魅力だ。
「まさに。たとえば『パルプ・フィクション』で、ジョン・トラボルタがサミュエル・L・ジャクソンと車に乗っているときに間違えて若いチンピラを撃っちゃって、掃除しなきゃならなくなるシーンとか。ああいう笑いの感覚って世代的に共有しているものなんですよ。あのときマクドナーと飲みながら『映画のフェイバリットは何だ』という話になって。そのとき僕らが共通していたのは、サム・ペキンパーでした。ペキンパーの暴力のあり方は、おかしみとはちょっと違うけど、唐突性も含めてタランティーノにも引き継がれているものだと思うんですね。『ウィー・トーマス』も、韓国映画の本当にリアルで恐いようなのとはちょっとまた違って。舞台だからこそ本物らしいものを使うと、かえってほどよく嘘が強調される、舞台の特性をわかってやってるな、と思いますね」
長塚は、翌年(2004年)も「ピローマン」の演出を手がけるが、その後、マクドナーはパタッと新作の芝居を書かなくなってしまう。
「僕としては演劇の素晴らしい才能が映画に流れてしまったことが、けっこう不満でした。彼の『ヒットマンズ・レクイエム』という映画を見たときに『ふぅーん……、こういうのがやりたくて映画に行ったのか』と、ちょっとだけガッカリしたんです。でも『スリー・ビルボード』は、大いに納得しました。『戯曲を書く人間が本気を出したら、映画でもこれくらいやれるんだよ』って(笑)。誇らしい気持ちも湧くし、長い間、芝居から離れて映画界に行っていたことに対しても頷けるような、嬉しい映画でしたね」
筆者紹介

若林ゆり(わかばやし・ゆり)。映画ジャーナリスト。タランティーノとはマブダチ。「ブラピ」の通称を発明した張本人でもある。「BRUTUS」「GINZA」「ぴあ」等で執筆中。
Twitter:@qtyuriwaka