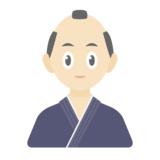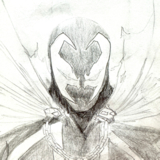悪は存在しないのレビュー・感想・評価
全78件中、61~78件目を表示
わかる人にしかわからない映画
人間はもろく弱く愛おしい。くだらないことだらけで何も爪痕残していない人生だとしても魂はみんな懸命に生きている。
映画に理屈を求める人にはたぶん向いてない映画。
高橋のあのラストシーンをつくった監督に脱帽。傷ついた鹿のように思えたのは私だけだろうか。あのシーンだけでももう一度観たい。
後で色々思い出す映画
最初は森の木の光景が延々続くが、途中から濱口監督の面白い会話劇となり、劇場内でも笑いが起こっていた。個人的にはコンサルとの会話がおかしかった。ラストシーンが衝撃的であとで色々思い出している。悪は存在しないというタイトルも効いている。
悪は存在しないが
狂気は人間にはいつでもどこでも存在する。主人公の最後の行動は普通ではない。どう考えても狂っているとしか思えなかった。悪は存在しないけど、善も存在しない。
鹿に襲われそうな子供を助けようとした人間を、おそらく殺した。殺された(ように見える)人間は生き返ったように立ち上がったが、また倒れたのが、不気味だ。殺した方の男に無表情に抱えられた子供もおそらく死んだだろうし、生きていたとしても、幸せな暮らしが待っているとは考えられない。殺人を犯したように見える主人公は何を考えているかよくわからない人間として描かれていて、子供を迎えに行く時間も忘れる。いつも子供を危険な目に合わせても、本気で反省していない。自然が好きなのかどうかもよくわからない。グランピングの話を持ちかけらたせいでそのようになったようにも解釈できるが、そうではないと思う。というのは、グランピング説明会の地元住民もみんな変だ。住民の意識自体が変。自分たちは本来の地元民ではないと言いながら、地元の利益だけを主張する。
一番変なのは自治会長?のじいさん。上(自分たち)がしっかりしないと下(下流の大多数の住民)が困る、と言い出す。自分たちは上だと思ってる。地元住民はその異常さに気づかない。上が下をグランピングで一時的に受け入れればいいだけの話なのに、排除する。
主人公は何が真実か、何が現実か、探し求めているのか、さまよっているのか、よくわからないが、正気と狂気との境界線をうろついている。グランピングのことを気にしているようにみえて、一心不乱に描いている絵はグランピングの説明をする男女。子供の相手もせずに、男女の無表情な姿の絵を鉛筆で描く表情には狂気を感じた。一生懸命にグランピング問題を考えているのか、どうか、怪しい。木を切り倒して、薪をくべる自分の生活を悔いているのかもしれないし、悔いてもどうにもならないことに絶望を感じていたのかもしれない。答えはないだろう。人間が自然に干渉せずに生きることは不可能だ。どこかで、人類は狂ったのである。
前作では、人類の中でのコミュニケーションの問題を多言語を扱って映画にした。今回はコミュニケーションの問題を人類と自然との関係に広げようとしたのだろう。しかし、人類内の問題の延長で自然との問題を解決できるはずがない。その結論を提示した映画だ。
「ドライブ・マイ・カー」でも、自分の写真を撮った人間にひどい暴力を振るった(と推測できるシーンがある)男の表情が狂気をはらんでいるように描かれるシーンが印象的だったのを思い出した。このような狂気をはらんだ人間の衝動に動物(自然)とは違う人間の本質を見ているように思う。本作のラストもその映像の展開に息をのむ。
映画は音楽と騒音が効果的に使われていたり、映像の焦点が定まらずにカメラが回っていたりして、緊張感を切らさずに見ることができた。前作と同じく、不気味さというか不安定さが映画全体に持続するので、時間を忘れて映像を凝視し続けられる。映像が切り替わる直前に次のシーンの音がかぶるのは、構成上必要なのかどうかよくわからなかったが、少し気になった。「ドライブ・マイ・カー」と同じく、車の運転シーンが多いが、後方や側方の場面が多い。車が見られているような感じで、観客が見られているような感じになる。これも不気味な感じだった。
比較する対象がない。映画史に刻まれる傑作だと思う。
悪とは?を本質的に問う映画
長野県水挽町の住人と東京の芸能事務所によるグランピング建設計画を機にコンフリクトが起きていく
のが話の軸です。
冒頭の長い森の風景・圧巻の自然を美しい映像で見せることで、鑑賞者へ本作の世界観をインプット
しようという試みであろうと感じました。そのくらい長い。長いと感じるくらいの長さです。
そこから主人公 巧と住人たちとのコミュニケーションから、巧と住人の関係性などがわかるように
描かれていきます。
そうすることで、まずは巧及び住人たちへ鑑賞者は感情移入していくこととなります。
そんな中でも、巧の娘である花が纏う不穏な雰囲気は、割と冒頭から気になるところではありました。
グランピング計画の住人への説明から、ますます住人への感情移入が深まるわけですが、
芸能事務所の黛が真摯な対応をすることに好感を覚えたと思えば、
住人説明会で苦労していた高橋と黛が、実は東京では、社長&クソみたいなコンサルにも辟易している
ことがわかり、ここで高橋&黛にも感情移入していくこととなります。
そうすることで、“悪”とは、その人の立場によって、また、観る人がどの視点で観るかで変わり、
また、絶対悪は存在しないのでは?という気づきを得ることになり、
なるほど、タイトルの『悪は存在しない』とは、言い得て妙だなと思いました。
本作最大の事件、花が行方不明になってからの展開がまた面白いと言いますか、読めない展開になるのですが、
花と鹿🦌が対峙している場面(割りかし鹿の顔のドアップが長いです)から、
巧が高橋へスリーパーホールド!!
えっ!?って感じです。何が起きているかわからないくらい動揺しましたが、
次の場面で花が倒れていて、鹿はいない。なるほど、花が倒れているところを巧は高橋に見せたくなかったんだろうと思いました。
一瞬、高橋は死んだ!?と思いましたが、起き上がっていたので生きていますね。気絶していただけということがわかります。
一方、花は死んでいるかもしれないし、生きているかもしれない。
巧が花の鼻に手を当てて、呼吸をしているかどうかを確認するやいなや、すぐに抱きかかえて歩き出すことから、
私は、花は生きているんじゃないかと捉えました。
このラスト以前に、巧は高橋&黛に対して車のなかで「人間を襲うのは、手負いの鹿ならあり得るかも」的な話をしているので、
花は鹿に襲われたであろうことは想像に難くありません(鹿の顔のドアップがその示唆かと)。
とどのつまり、動物も含めて皆生きることに必死であり、誰も悪いことをしようと思っているわけではないんですよね。
だから「悪は存在しない」というタイトルなんだろうし、ただ、答えはひとつではないと思うので
本作を観た人が、この映画を通じて色々な事に思いを馳せてほしいというのが、濱口監督からのメッセージなのだろうと解釈しました。
実に深い作品です。時間が許せばもう一度鑑賞し、理解を深めたいと思いました。
オチが分からなーい。
巧と花は鹿なんかな?野生の鹿?
それとも花が怪我した鹿に襲われたってだけでええのかな?
花が行方不明になって、近所の人たち総出で探して、夜になったまではわかった。
で、高橋と巧が平原?原っぱ?に出た時には、なんか明るくなってたから夜通し探してたんかな?
で、花見つかって、花の近くに怪我した鹿がいて、怪我した鹿は人間襲うかもというフリが前に提示されてて、なのに花は帽子とって怪我した鹿に近づこうとする。
それを止めようと走り出した高橋を巧が絞める。あれは本気で殺すつもりのやつ?よく分からんけど高橋は白い泡?吹いて気を失う。
で、鹿がもういないけど巧が花に近寄ると、花は鼻血出して気を失ってて、巧は花を抱き抱えて原っぱを去る。
取り残された高橋もフラフラと立ち上がるけど、再度倒れる…これは?死んだ?
この後は誰かの走る息と森の木々の映像でおしまいとなる。
オチに来るまでは特に謎もなく、ふんふんと進んできたのだけど、このオチをどう解釈すれば?となりました。
面白かったんだけどもね。
タイトルの意味は、悪(だけの存在)は存在しないってことかなぁって思った。完全な善も、完全な悪もないという意味かなぁと。
関西では5/3は公開初日で混んでた。多分満席。でも一番大きいスクリーンじゃなかったし、1日2回公開。まぁ、監督の名前以外で観にくる動機の薄い作品だもんね。
そして、映画には全く関係ないけども。
多分隣の人が、うっすらドブ臭い・うんこ臭い口臭・体臭の人で、このうっすら臭いの、昔の恋人の口臭と同じで、彼のことが頭に浮かんで仕方なかった。
においの記憶、強いわぁ。口が近すぎる訳でもないのに薄いけどちゃんと香るあのにおい。鼻が全然バカにならず、ずっと香り続けるから途中からハンカチて鼻を覆うしかなかった…あーなつかしくさかった…
悪は存在しなくても、衝突も罪も存在する世界
冒頭から映像と音楽を贅沢に味わい、自然の恩恵と不穏さにゆっくり浸る。
ストーリーとしては八ヶ岳でのグランピング施設のための説明会、それに携わる二人の心情が語られ、無機質な悪でもなくどこにでもいる自然体な存在だなと感じる。
やはりこの物語はまさしく「悪は存在しない」なのだと思う。手負いの鹿が稀に見せる凶暴性、嫌悪感や怒りはあっても普段は抑え振るわない暴力の存在。それは悪とは言い難いはず。仕事で担当だからと結果的に水を汚してしまう人も、手負いだから興奮して人を襲う鹿も、悪ではない。ということは、なされた罪の多くは悪の問題ではなくて。
自然体な物語だけど、ラストの展開はまさに手負いの鹿の豹変のような、起きないはずのことが起きたと感じさせられた。ただ、ここの解釈がここまでブレるのは想定内なのだろうか。
私としてはどちらとも解釈できるような曖昧さとか、そこをはっきりさせることは重要じゃない描き方というのは、基本的に嫌いじゃないほうなのだけど、この作品については、ラストの展開とその語られなさはあまり好みじゃなかった。映画は答えを提示するものであるとかその答えが関心事だとは思っているわけではないけど、あまりに解釈のブレを招いてしまう突き放し方で。答えを求めるのは貧しい考え方だという指摘は、監督の知性からすれば酷くブレる解釈をする層はおよびじゃないということなのかなと思うけど、うーん…
悪は存在しなくても、相互理解は容易じゃない。
自分の解釈としては、たくみのあの行動は悪がゆえではないよ、でも罪ではあるねってことかと。悪じゃなくても罪はおかされる。手負いの鹿の暴走のように、声を荒げることのないたくみが暴走をしてしまう。なぜ暴走したのかは、娘を失ったことを東京から来た薄っぺらい男に結びつけたか、それともただやり場のない怒りが彼にむいたか、その原因はたくみにもわからないかもしれない。ただ、たくみはずっと怒りをためていたはず。黛と対比するかのように、高橋は、無責任で無神経でしかも結果的に罪を犯すであろう人間として描かれていたし。
どこかで響いた銃声によって手負いとされた鹿がはなを傷つけ、はなは死に、そして遠目でもそうと確信したたくみが暴走をする。
ラストシーンは、はなを抱えたたくみなのかな、息遣いのみ聞こえる。映画冒頭の雄大さと不穏さのコラボがここでも。無力で不穏でちっぽけな、それでいて必死な息遣いで幕が閉じられる。
うーん。
唐突過ぎ!
惹き込まれて面白い作品だなと思いながら観ていたのに、唐突な終わり方に呆然とした・・・
なぜ、失神するほど羽交い絞めにする必要があったのか。
全く理解できないという思いだけが強く残ってしまって、何か台無しになった感じです。
「上(上流)」を目指し迷子になった監督は存在する
スパイの妻やドライブ・マイ・カーは良かったからあえて点数を低くする。
出口が見えないから適当に作ってお前ら自分で考えーみたいな監督メッセージ。
そもそも二項対立を崩すようなタイトルこの題材にした時点で、面白くなるのはキャンプ地建設の成功とか失敗とかそういう予想のつく円満な話じゃなくなり、
監督の表現ともっと奇抜でもいいから観客を驚かせる何かの結末が肝心になる。
それを意識しながら答えを求めた果てに放棄した監督の姿がどうしても目に浮かぶ。
後味の悪い映画だ。
そのせいで前半の森に誘い込むような空ショットも台無しになり、
リアリティを追求してるかのような奇妙な角度からの撮影も、観客を揶揄うような作者の狡賢さを示唆してるみたい。こんな悪意で考えてしまいとても残念だった。
現実的かと思いきや!
現実的な作劇かと思いきや、神の領域を描いた快作!
●生きる場所、立場が違えば善悪の見え方が違ってくることが伝わってくる。その描き方がリアルで面白かった。
善悪の判断は神の領域。だからこのタイトルなんだろうな。
●会話がいい。少なくとも社会人なら身に覚えがあるような内容が共感できる。
そうそう、自分やまわりもそうだよな…と。
●キャラクターもいい。こういう人、現実にいるよなぁ…と思わせる。
●ラストは意味不明…というか監督が観客に仕掛けた時限爆弾と思う。
これ、いろいろな解釈ができる。主人公は娘の死を隠したかったのか?楽園の存在を隠したかったのか?矮小な自分を自然に紛らわせたかったのか?
人によって解釈はわかれるだろうな。
社会派ドラマであると同時に重層的に人もあるがままの神域の住人であると描いていると思う。面白かった。
サブミッションの名手
映画祭の箔が付いているからか、有難がっている方が多いのに驚きました。
アート的な画をテンポのろく繋げば芸術風映画の出来上がり。濱口さんの映画は初見なのですが過去作もこんなもんなんですかね?去年の東京フィルメックスがこの手の映画ばかりでウンザリしたのですが、自分には本作も同列にしか見えませんでした。
とはいえ無名の俳優を使い、雰囲気で書いた第一稿をそのまま撮れ、それでも監督の名前で客を集められる、本当に素晴らしい事ですね。観客に向き合い、表現に腐心している名も無き監督たちが気の毒に思えます。
唯一の救いはチョークスリーパーで笑いが起こっていた事です。信者でない一般客もチャンと高い金を払って見に来ているんだな、とホッとしました。
さすがにわからない
分からないのは全然いいんだけど、これ、創り手も分かってねえんじゃねえのかって感じがすんの。だから最後ぶん投げて終わりにしたんだろっていう。
もちろん、そんなことないと思うけど、そう観えるんだからしょうがないね。
最初の説明会まで長いんだよね。寝た。
たぶん水挽町の美しさを描いてたんじゃないかと思うけど、そこまで映像美しくなかったでしょ。
あの辺の美しさというか良さって、肌にあたる空気の感じとか、音が高い空に吸い上げられてしまったような感じとか、視覚より触覚、聴覚さらに嗅覚みたいなところにある気がすんの。
それを映像で表すって、難しいね。表せなかったら、その辺の山だし。
グランピング場の云々かんぬんは、「調べたんだな」って感じはあったね。だからどうした感もあるんだけど。
《悪は存在しない》ってことで、グランピング場を推し進める側にも色々あるんだよってことにしてるけど、これ推し進める側がハッキリ悪だろ。
本業のタレント事務所がうまくいかないからって、思いつきでグランピング場に手を出して補助金もらっちゃダメでしょ。
どんな理由があったって、地元の人を喰い物にしちゃ駄目。
地元の人も開拓三世で、自然破壊してきたことには変わりないからって理屈だけど、変わりないわけないだろ。田舎をナメてんのか。
その辺のヌルさが「最後にぶん投げやがった」っていう感覚につながるんだろうな。
最後はなんで都会から来た人を殺したんだろうね。
『お前が来たから』ってことなのか、殺したオジサンは実は森の精だったのか、あるいは鹿だったのか。
「これ、このあと事情説明してもグダグダするだけだから、ここでスパッと終わりがいいな」と思ったら終わりになったので、そこは良かったよ。
面白いは、面白いんだけど、少し腹立つところもある。
レビュー書いてみて、それは創り手側の田舎蔑視を感じてしまうところにあると気付いたよ。
自然に悪は存在しないが、人に悪は存在する 自然への謙虚さを忘れたとき、その報いは訪れる
何か悪いことが起きるのではないかと、ドキドキしながら観ているのは少し嫌なものです。
その顛末を見せるのが映画の一つのパターンだから。
(たまに、何も起きない平安の安らぎを見せるパターンもある。)
娘が一人で歩いて帰宅するのもどうかと思って観ていると、案の定行方不明に。
銃声が2発聞こえたのは、鹿が撃たれたのだろう。
帰宅途中、ぶらぶらしていた娘は、手負いの鹿と遭遇し、愛でるつもりで、不用意に触ろうとしていた。
そこで、娘を見つけた主人公は、一緒にいた高橋が声を出して鹿を驚かせ、娘に怪我させることが無いように、必死で羽交い絞めにして押さえつける。
その後、見ると鹿はおらず、娘が横たわっていた。
途方に暮れた男は娘を抱いて、去るのだった。
「悪は存在しない」とは、鹿のことか。
鹿が人を襲うのは悪意からではないから。
グランピング場開発で助成金を無理にでもせしめるのは悪である。
自らは出張らずに通り一遍のコンサルをして強引に進めるコンサルタントも悪。
自然の怖さも忘れ、つい娘を迎えに行くことを忘れてしまう父。
手負いの鹿は襲ってくることを、東京の人間には偉そうに説明する反面、娘には言って聞かせていない。
何をおいても最大限の努力で、子供の命を守るのが親の務めだ。
それを怠ることこそ、最大の悪だ。
説明会では、住民側に立ち、それでも自分たちも以前はよそ者だったと言いながら、いつしか謙虚な気持ちを忘れ、自然をわかった気でいた。
その報いがあったのだ。
ラスト20分の変調
中盤までは長野県水挽町で暮らす人々と、そこにグランピング場を建設しようとする東京の芸能プロダクション社員との人間関係が中心に描かれる。その延長線でストーリーが進むと思いきや、終盤の20分で展開は大きく変化する。
芸能プロダクションの社長が煙草を吸うシーンや淡白すぎるエンドロールなど、面白い演出はいくつもある。また、作品を通して水挽町周辺の風景が美しく描写されているため、見応えは充分にある。
しかし、ラストシーンが唐突かつ衝撃的すぎるため、見終わった後はその意味を理解することにしか意識が向かなかった。
考察させるためだけのラスト?
最初の30分間は環境ムービーか?と思うほどの、自然と水汲み薪割り映像。自主制作映画か?と思うようなぶった切りの場面切替。ムビチケもない正規料金でこれはキツい、ランチ後腹一杯状態だったら間違いなく「落下の解剖学」のように寝てた。午前に見に来てまだ良かったと思ったところで、物語が動き出す。
コロナ禍での補助金欲しさにグランピング施設を作ろうとする芸能事務所と、計画が杜撰すぎるので検討し直すよう求める地元住民。漸く映画における対立軸が見え、それぞれの登場人物の背景も見えてきたところで、大事件が起こり、えっ?これで終わり?というぶん投げエンディング。
分かりやすくしろとは言わないし、観客に考察や解釈の幅を与えるのはありだと思うのだが、監督や脚本家は自らの中で、この人の行動はこういう理由、この人の結末はこうなっているという帰結を持っているのだろうか? もし監督の中にそれがなく、結末どうすればいいか分からなくなったから観客の解釈で、という投げ出しの作り方をしているとしたら、有名になったのを良いことに手抜きした駄作としか言いようがないし、見終わった直後の今はそのように見えてしまう。
友人は監督の傲慢さというか、偉そうさ、観客を見下してる感があるとすら言っていました。
以下ネタバレです。
※※※※※
濱口監督のエンディングに対する以下のコメント。
「ただ単にそれが起きた、ということが第一です。それを受け止めていただきたい。主人公の側にもいわゆる悪意は存在しないという解釈でいいと思います、たぶん(笑)」
「わかりやすい対立構造みたいなものがあって話が進むなか、主人公はずっと誰とも対立する立場にはいないんです。議論が紛糾する場面でも、実のところ中立的なことを言っています。そんなキャラクターの最後の行動が観客を驚かせるわけです」
この監督コメントからエンディングを勝手に考察すると、
・花は死んでいる
・死因は不明だが、鹿の角で刺されたり、銃で誤射されたような跡はない
・(鼻血が出ていることから)手負いの鹿に襲われ頭を強打するなどしたように思える(巧と高橋は実際は鹿を見ていない)
・巧は花の遺体を高橋に見せたくなくて高橋を襲った?
・巧が、見せたくなかった理由は不明(鹿は人を襲わないと断言しながらも、例外として手負いの鹿は人を襲うことがあるかもと話しているので、自分の見解が間違ったことを隠したいわけではない。また、そんな理由で死体を見せたくないと思うような男ではない)
・花を失った悲しみと怒りが暴発し単に目の前の高橋に向かって、首を絞めた?
・高橋は死んでいない(1度起き上がって再度倒れるが、死んでいるなら1度起き上がる描写は不要)
花が何らかの事故で死んだのは事実として、巧が高橋を襲う理由が分からず、監督も脚本家も自分たちの中で帰結はあるのか?と大いに疑問。
「聖なる鹿殺し」のように、高橋は花を取り返すための生け贄だという考察を拝見し、自然をないがしろにする高橋(鹿はどこか別のところに行くんじゃない?と軽く発言したり、薪割りを1本やっただけで1番スッキリした、管理人やろうかなと軽く言い出す)を受け入れるわけではない、だから花を返してくれという表れなのかとも考えてみたが、監督自身が中立的という巧の行動に、そこまで自然崇拝のバックグラウンドは見いだせない。
濱口監督は以下のように言う。
「彼自身が生きてきた人生と、あの瞬間の偶然みたいなものが、彼にああいう行動を取らせているんじゃないかと考えています。あの瞬間に、タイトルと物語の緊張関係がもっとも高まります。劇中の高橋のラストのセリフは観客の疑問でもあると思いますが、その答えは与えられることはなく、高橋も観客もなぜこうなったのか自問するしかない、という構造です」
濱口監督の「行動の前に感情があるわけではない」という棒読みメソッド、そして、上の「あの瞬間の偶然みたいなものが彼にああいう行動を取らせている」からすると、花が死んだ怒りを突発的に目の前の高橋にぶつけただけ?とすら思えてしまう。
高橋同様「何でだ?」と思わずにいられないし、観客は自問するしかないという構造を作り出すためだけに、うやむやにしているように見え、考察させるための投げ出し、話題作りのための投げ出しのようで好きになれない。監督自身の伝えたいことはないのだろうかと思ってしまいました。
タイトルが持つ意味を考えている…
観賞後ずっと、タイトルに込められた、濱口監督の真意を図りかねている。
自然そのものに悪は存在しないということか、社会で対立する人間のなかにも悪など存在しないということか。
山でしか生きられない生物にとって、人間は単なる「侵略者」でしかない。
昔から住んでいようが、新たに「仲間」に加わろうとするものであろうが、彼らからみれば同じ「エイリアン」に過ぎない。住民の環境云々はただの言い訳にすぎず、すでに「完成」されたコミュニティに加わろうとする新参者を排除する構図があるのみ。劇中のグランピング建設の説明会は、さながらケアサービスの施設建設に反対する近隣のマンション住民の構図と同じ。
海辺で生まれ育ち、山を多少なりともかじった身としては、山は恐ろしい存在だ。陽が沈み漆黒の闇に包まれた山中に取り残される恐怖は体験したものでないとわからない。
山に優しかろうが、汚す存在であろうが、関係なく、時として無慈悲に自然は牙をむく。悪い行いをしようが、善行を積もうが、自然の行為そのものに意味はなく、因果論の入る余地もない。
人々の対話を作品の中に重きをおいているところは、濱口監督らしい世界観。
たとえ解決に至らずとも、コスパ・タイパなどの効率世界の対局にあろうとも、人間が対話を重ねることの意味を考える。
最後の場面をどう理解したらいいのか。そもそも理解しようとすることが人間の傲慢さなのかもしれない。
それだけのこと?
いまさらですが、〝自然〟って何?
辞書に書いてある通りに理解するならば、
『人の手の加わっていないありのままの状態のこと』
とするならば、開拓三世である巧もその他の集落住民も、別に自然と共生しているわけではない。都会に住む人よりは山川森林に近い場所に住んでいて、都会の人よりは人の手が加わっていない燃料や水資源を利用する機会が多いだけである。山や川や森林との距離が遠いか近いか、電気や水道などの公共インフラを利用する度合いが高いか低いか、つまり都会に住む人とはその使用方法において、程度が違うというだけのこと。
こういう映画を見るときに、気をつけなければいけないのは、自然側に属する人間と都会的な現代人との対立構造のように捉えてしまうこと。
劇中で語られた〝上流に住む人間の義務〟〝それに相応しい振る舞い〟というのも同列の人間同士に成り立つ話であって、本当の自然にとっては、どうでもいいこと。汚染されようがなんだろうが、自然にとっては、どうぞご勝手に、なにしろ我々は何万年だって待てるのですから。
放課後の学童クラブに迎えにいくのを忘れてばかりの親だと、こどもに及ぶリスクが増大する。
鹿と間違われて猟銃に撃たれてしまう確率は、都会に住む人よりは、鹿の住む山の近くに住んでいる人たちの方が高い。
それだけのこと。
あれ?
自分、なんだかおかしいかも。
この映画を見た後の印象が、『人間なんてみんなクズなんじゃないか』
それしか残ってない。
どうしよう!
ラストの突き放し感
冒頭の長回しの森林を見上げるという俯瞰ショットは一旦誰の視点なのかワクワクしながら観ていたが、ラストでそういうことか!も腑に落ちた。
グランピング施設の説明会は住民側も開催側も不快感MAXで、みんな嫌いだわ!と思いました笑
が!!物語の中盤、開催側のタカハシとマユズミの2人のドライブーシーンの会話劇リアリティと面白さで、ドライブが終わる頃にはみんなこの2人のことが好きになっていると思います笑
ラストは衝撃的な展開だが、タカハシの「オレの居場所らここだわ〜!」の安易な台詞を踏まえると、「お前の居場所がここなわけねーだろ!」と自然代表のタクミに拒絶されたのでしょう。
自然代表と言っているが、あくまでも本物の自然の恩恵を受けている存在であって、住民と自然、東京から来た部外者2人と住民、それぞれ悪でもないし正義でもないのだが、交わってはいない一定の距離感を常に感じる。
個人的には村長の「水は低いところに流れる」という水を人間社会の構造に例えた言葉から、タカハシとマユズミがタクミと水を汲みに行く一連の流れが好きでした。笑えるシーンも挟みつつ、マユズミが一生懸命水を運ぶ姿に何故かグッとくるものがあった。
ドライブシーンとうどん屋のシーンさ濱口監督本人的には笑いを狙いに行ったわけではないそうだが、フランス公開時も爆笑だったそう。
全78件中、61~78件目を表示