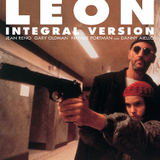マエストロ その音楽と愛とのレビュー・感想・評価
全14件を表示
マエストロと生きた女性の心の旅路
伴侶としてレナード・バーンスタインを見守り続けたフェリシアの物語。夫婦の内情が話の中心で、クライマックスの演奏シーンを除けば、レナードの晴れ舞台がじっくり描写される場面は意外なほど少ない。フェリシアに寄り添って観てしまう作りだと思ったらクレジット上はキャリー・マリガンが主演になっていた。内容を踏まえて「マエストロ」というタイトルを見ると、フェリシアが複雑な感情をこめて夫にそう呼びかけているような気がしてくる。
終盤を除いて物語の起伏が少なく、少し地味めな印象。バーンスタインの音楽が聴けるのはよいが、特定の曲をじっくり聴けるシーンは少なかった気がした。フェリシアが病に冒されるくだりで涙を煽るような描写を避けていたのは好感を持てた。
私はバーンスタインの仕草をよく知らないので、顔はよく似てるくらいの認識しか出来なかったが、実際の映像での彼をよく知る人が見ればまた違った感想になるのかもしれない。彼の音楽家としての履歴や功績についての初心者向け説明はほぼなく、その辺は観る側が知っている前提で描かれた、妻の目に映る夫バーンスタインの物語。
冒頭で大写しになった、老いたレナードを演じるブラッドリー・クーパーの顔に目が釘付けになった。クーパーっぽいけど本当の老人のようでもあるし、別の俳優なのか?という考えもついよぎるほど、顔だけでなく首や手の皮膚もリアルに年老いていた。それもただ老人っぽいというレベルではなく、レナードの歩んできた人生までも感じさせるような、時間の重みをまとった生々しさがあった。クーパーの演技もさることながら、やはりカズ・ヒロ氏の特殊メイクの力は大きい。俳優の演技と同等に雄弁に、レナードという人物を語っていたように思う。
確か彼は現代アートに軸足を移して、映画の特殊メイクを手がけることは少なくなっていたはずだ。そんな彼の起用に、晩年のレナードの描写に対する製作側の気合を感じた。
(実際のバーンスタインの風貌に合わせて鼻を大きくした特殊メイクに対し、一部のSNSや映画評論家、ユダヤ人差別と闘う団体が「ユダヤ系に対する侮蔑的ステレオタイプ」と批判しているそうだが、アホらしい。バーンスタインの遺族は問題ないと言っている)
前半は、モノクロ映像で2人の蜜月時代が描かれる。部屋を出たらスタジオだったり、庭から室内に移ると劇場だったりと、ちょっとファンタジックな場面転換も恋に落ちた2人のうきうきした気持ちを上手く表している。彼らの仲が深まること以外大きな動きがないので、この辺のくだりは若干冗長なようにも見えた。モノクロ部分の後半で、遠回しな台詞ではあるが、フェリシアがレナードの性的指向を承知していることが示される。
話が大きく動くのは、中盤でカラー映像に変わってからだ。夫婦の顔立ちには年齢なりの貫禄が表れ(これが実に絶妙)、子供たちは成長している。一方で、フェリシアはひとりで深い葛藤を抱えていた。彼女のレナードに対する感情の爆発と和解、病と死が描かれる。
自分の伴侶が他の人間と性的関係を持つのが嫌なのは当たり前の感情だ。しかもレナードはきちんと隠す気がなさそうだし。そりゃ寝室から締め出しますって。
でもフェリシアは、最終的には改めてレナードと彼の音楽に向き合い、彼を許した。演奏から伝わる彼の魂の根源的な美しさへの敬愛が、嫉妬や葛藤を乗り越えたのかもしれない。レナードの芸術家にありがちな性的奔放さは残酷で、肯定的に捉える気はないが、彼女の決心は美しい。
映画の中で、マリガンとクーパーは夫婦が段階的に年齢を重ねるさまを演じたが、年をとってゆく演技の足並みが綺麗に揃っていた。さらっとやっていたが難しいことではないだろうか。
フェリシアの台詞は説明的ではないが、マリガンの目の表情が彼女の幸福感から嫉妬や悲しみまで全て語っていて、さすがだと思った。がんに蝕まれて生気が抜けてゆくフェリシアの姿には胸が締め付けられた。
「マエストロ」と題してタイトルロールの人生をたどりながら、フェリシアという女性の生き方を浮き彫りにする。マリガンが演じたからこそそういう作品になったと思う。
監督二作目にして映画で遊びまくる。
監督二作目でこれをやってのけるブラッドリー・クーパーがスゴい。あの手この手を繰り出しながら、映画づくりをめいいっぱい楽しんでいるのが伝わってくる。ガシガシ放り込まれる音楽によって、レナード・バーンスタインがいかに攻めた音楽家だったかもわかるし、突然ミュージカル調になったりしてリアリティラインとかを平気で飛び越えてくる暴れ放題な構成もワクワクする。そしてキャリー・マリガン! 存在感が圧倒的に強いし、痰をティッシュで拭く仕草のリアリティには震えた。演技だってわかってるのに、命の炎が消える寸前って残酷だけどマジでアレだと震えた。震えたって二回言った。それくらい震えた。
ブラッドリー・クーパーがアカデミー各賞を取りに来た作品。 ★2.9
アカデミー7部門ノミネート作品だが、
各シーンが断片的過ぎて、全く見入ることなく終盤へ。 音楽家としての表現が僅少で、バイセクシャルな夫に嫌悪を増す妻・・。 そんな物語を期待しました?
会話シーンから突然舞台になったり、ドアの隙間から描写だったりと見せ方は工夫あるも、各シーンがあまりに日常のワンカットで、ドラマになっていないと思う。
ちと細かい指摘・・。↓
序盤のワンシーンにも強い違和感。 台詞稽古を真似るシーンでお互い顔の距離がグンと近くなる。 が、次の瞬間クーパーのタバコの煙がマリガンの顔に覆いかかる・・。
私も40歳まで煙草を吸っていたが、デート中に例え相手が喫煙者であっても、顔に煙りを吹きかけた事は一度もない。 横を向いて吐く場合がほとんど。
それは好意を持った相手に自然な配慮。
細かい事だが、リアルを追求する監督なら、絶対にしない描写。
クーパーも容姿はバースタインに似せているが、その時黙っていても心情が伝わる様な深い演技はないと感じ、アカデミー候補になるも、レミ・マレックが「ボヘミアン・ラプソディ」で主演男優を獲った時にの様な違和感が湧く。
マリガンは演技としては上手いのだが、彼女はなぜか人物的に好きになれる役をあまりやってなく感じ、損をしていると感じる。 今作の前日に見た、「アメリカン・フィクション」の家政婦役と好意を寄せる警官の二人など、わずかなシーンだけでも、見てる方が好きになれる役は多々あるのだが・・。
ほぼ再生速度を速めての視聴だったが、終盤の演奏シーンにやっと通常再生に・・。 ややオーバー気味にタクトを振るのはバースタインそのものだが、「あれっ再生速度がまだ速い・・。」 というより演奏されている曲の拍子より、クーパーのタクトが早く感じる。 演奏の終盤では早いというより拍子が合ってないぐらいに感じる。
(私は軽音楽・特に洋楽には多少詳しいが、クラシックは素人なので、このタクトの振りが拍子と合っているのか、是非演奏家の方に聞きたいものだ。)
と不満ばかりのレビューに・・。
(他の方レビューも高得点なのに、面白く感じてない場合が多い)
「監督がカリスマになりたいだけでは」や「ものまねと演技は別物」との意見もあり、的を得ていると感じた。
今年のアカデミー作品賞には、「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング」は入ってない。
なぜなら、アカデミー基準のマイノリティ要素を含んでないから。
が、私がこの1年で見た作品で、開始からの1時間を最も引き込んだ作品でした。
が、今作は再生速度を速めて、早く見終わらないかと思ったぐらい・・。
もし今作がネトフリ配信じゃなく、通常の劇場公開のみで収益を得る作品だったら赤字作品だろうと・・。
↓ネタバレ含む
終盤、マリガンが病床に苦しむシーンでやっと感情移入するかと思いかけたところで、また若い指揮者志望の黒人男性との描写に・・そしてエンド・・。
エンドロールでバーンスタイン本人がタクトを振る映像が映るが、BGMが実際に指揮している曲とは違うようだ・・。
これって本当に音楽を愛した者の映画と言えるのだろうか。
私にはブラッドリー・クーパーが顔を似せ、アカデミック要素を加味して、賞レースを獲りに来た・・その様な作品に感じてしまう。
逆にトム・クルーズは、アカデミー賞対象作とはならない作品だと百も承知で、観衆が本当に見たい物を追求する姿こそ本当のスターだと・・。
アカデミー作品賞候補がこの様な作品ばかりになっては、
日本国内では益々、洋画離れが進むのではないかと危惧する事に・・。
彼の作品を聞き込んでからもう一回観たい
主役兼監督を務めたブラッドリー・クーパーさんが、しょっぱなからバーンスタイン本人にしか見えない!
若いころから老年期まで、一人で演じきって、なんの不自然さもなく、特に老年期のバーンスタインはドキュメンタリーを観てるような気分になってしまった。
また、バーンスタインの奥様のフェリシアを演じたキャリー・マクガンさんも、子供が3人いるのに、まさかの夫が結婚前、交際前からゲイだったという現実を静かに受け入れて、寂寞とした感情を抑えながら、凛として生きる大人の女性の品格を見事に表現されていました。感情をおしころした人を演じるのは演技の中でも難しいと聞いたことがあります。
なんとなくバーンスタインの方が主役の前提で最初は見ていたのですが、途中で移される彼女の美しい後ろ姿—―シルクの水色のワンピースを着て(西洋では水色は幸福な結婚を象徴する色だと聞いたことがあります)、すくっと伸びた背筋が凛々しくて、寂しげでもありセクシーでもあり、この映画の主役はバーンスタインではなく、フェシリア夫人の方だったんだなと後で気が付きました。
世界的指揮者で小澤征爾さんや佐渡裕さんがバーンスタインに弟子入りしていたそうですが、夢見心地で踊るように指揮をして、魔法使いのように美しい音楽を生み出す、バーンスタインさんのとけそうな笑顔にハートを射抜かれてしまいました。「音楽の神様に愛され、祝福された人」がバーンスタインで、奥様がどことなくさみしそうだったのは、彼は音楽の神様に選ばれた人だから、家族が彼を独占してはいけないずっと奥様はがまんしてたんじゃないかなと思いました。奥様は芸術家の彼を愛していたから、彼に自由に好きなことをさせて、自由を謳歌する彼の自由の中には、ゲイの恋人との逢瀬が含まれていたり、音楽に関することなら欲張りに何でも挑戦する、嫁の自分が彼にリミッターをかけてはならないという覚悟をして、彼の妻の役割を果たしたんだろうなと思いました。
ボヘミアンラプソティでも、女性と結婚しているフレディが実はゲイだったという衝撃の展開がありますが、こちらの作品では、衝撃的というよりは、天衣無縫に生きる夫の性的志向も、すべて神様が決めたことで、奥様は静かに受け入れるという、大人の女性の物語でした。この作品が悲劇にならずに、美しい家族の愛の物語が成就したのは、バーンスタインはバイセクシュアルで、奥様のことも本気で愛していた、という真実がきちんと描かれているからだと思いました。
日本でも江戸時代から同性愛の男性は意外に多くいたんだといわれていますが、結婚は子供を作るために男女間で行われて、夫婦は親友のような関係に変化して、恋人は別にいるという人も、実際は多くいたのかもしれません。この作品の中で鮮烈な印象を与えて心をゆさぶるのは、バーンスタインの「音楽」で、夫婦の問題はごくごく静かに穏やかに描かれています。
いい映画だなあと思いました。
大音楽家LBの音楽と夫婦愛を凝縮した傑作
※2023.12.24 Filmarksに投稿した記事です
再見した感想を文末に追記
《初見2023.12.8 イオン桂川》
レナード・バーンスタインは、「アメリカの」という限定抜きに20世紀後半を代表する作曲家兼指揮者にして音楽指導者であったが、本作は音楽家レニーの紹介映画としては不親切極まりない。
【以下ネタバレ注意】
例えば、アメリカ音楽史に欠かせないコープランドやクーセヴィツキーといったビッグネームも登場するのに、丁寧な説明はないから気づけた人の方が少数派だろう。(町山智浩氏は「父親がイヤな奴で」と話してたが父親は画面に登場しない。嫌味な小言を繰り返す師匠クーセヴィツキーのことを勘違いしたのではないか。)
ミュージカル界の巨星ジェローム・ロビンズも序盤そこそこの尺で出てくるが、愛称のジェリーで呼ばれているせいで、すぐにはわからなかった。
後半のヤマ場、マーラー「復活」の演奏シーンも曲名のクレジットなど出ないから、劇中で作曲シーンが印象的なレニーのミサ曲と混同しているレビュアーも少なくない始末ではある。
ただ、一見不親切な、そうした説明不足の小ネタの数々や、相当ひねったレニー自作曲によるBGMの使い方の面白さに気がつくと、実に含蓄の深い作品だと思えてくる。
(もちろん見過ごしたネタもきっと多いに違いない。)
なかでもいちばん感心した仕掛けが、終盤で最初はフェリシアによって発せられ(「復活」演奏シーンの直前)、2回目はレニーによって繰り返され本作を締めくくる ” Any questions? “ のセリフだ。
これ、エンドロールで心浮き立つ序曲が流される、レニー作曲のもう一つのミュージカルの傑作「キャンディード」の締めのセリフであり、それを引用しているのだ。
「キャンディード」は、ヴォルテールの原作による哲学的ピカレスクロマン(破天荒な冒険譚)。
ストーリーは支離滅裂で、しっちゃかめっちゃか(ゲイの人物も登場し重要な役割を果たしている。1956年初演にして驚くべき先進性!)。
だが、作品全体にわくわくするエネルギーが満ち、鑑賞後は多幸感に包まれる。
大団円では合唱が「僕らの畑を育てよう」と高らかに歌う(本作でも練習シーンが登場)。
「何か質問は?」と問いかける、あるいは「何か問題でも?」と開き直って見せるレニーその人も、破天荒な生き方を貫きながら新たな地平の開拓者たることをやめない。まさしくキャンディード流ピカレスクロマンの主人公だった、とクーパーは言いたかったのだろう。
《再見後の感想追記》2024.2.10
12.8劇場公開日に鑑賞し、拾いきれなかった情報をNetflixで確認して最初のレビューをFilmarksに投稿。
しかし、配信では、どうしても見方が細切れになってしまい作品の真価が味わえないことを痛感。
このため宝塚シネ・ピピアで再見した次第。
結果は、初見時よりも、一層密度の高い技巧を凝らした作品だとの感慨を深くした。
まず全体の構成だが、モノクロからカラーへ、1.33:1から1.85:1へのアスペクト比の変化から3部構成と見立てる説明が多い。
だが、物語の内容から見ると、下記のように、プロローグとエピローグ付きの5部構成と見たい。
プロローグ:冒頭のインタビュー
第1部:レニーの指揮者デビュー
第2部:レニーとフェリシアの出会いと蜜月
第3部:2人のいさかいと不和(別居?)
第4部:関係修復と闘病する妻への献身的愛
第5部:妻との死別後の教育活動
エピローグ:冒頭のインタビューへの回帰
こう見ると、第3部を折り返し点として、ちょうど前半と後半(内容で分けたので時間的長さは等しくないが)とで対照的に折り重なる構成になっていることがわかる。
(ちなみに、こうしたアーチ型の5章立て構成は、バーンスタインが得意としたマーラーの交響曲の第7番に典型的に見られ、「大地の歌」や未完の第10番にも受け継がれていることも、偶然ではないかもしれない。)
そして、本作のテーマが
「レニーとフェリシアの愛=出会い、葛藤、別離」
であることは、プロローグのインタビューのなかで、レニーが、
“ I miss her terribly. “
と、フェリシアを失った悲しみが強いことを述べて本編に入ることで明確に提示している。
小生は初見の投稿で、本編のキーワードがレニー自作の『キャンディード』から引用したと考えられる
“ Any questions ? “
であることを指摘した。
が、ここで、
“ I miss her terribly. “
というセリフについても同様に注目してみると、
まず本編第1部に入ってすぐ、カーネギーホールの屋根裏部屋で、電話でワルター病欠を知らされたレニーが、
“ Well, that’s terrible news ‥ “
と口癖なのか “ terrible “ と返している。
さらに、第3部の二人の不和から関係修復のきっかけとなるフェリシアのセリフが、
“ I miss him, that child of mine. “
と、彼女の方からレニーのことを失って恋しく思うと(死別後にレニーが言った同じ言葉で)告白しているのだ。
そして、そのあとが、かの
“ Any questions ? “
のセリフで締めくくられるのだから、あたかもシェークスピアの戯曲のように、キーワードによる呼応関係で見事に構成された台本だと感嘆せざるを得ない。
次に、レニーの同性愛についてだが、
本編第1部冒頭で屋根裏部屋のカーテンを開けるとベッドにデヴィッド・オッペンハイムが半裸の姿で現れ、一夜同衾していたことがわかる上に、ニューヨークフィルの指揮台に立てる喜びを、彼の尻をドラムよろしく叩いて表現することで明白に印象付ける。
おまけに、この部屋にはミュージカルの名振付師ジェローム・ロビンス、アメリカ発の大作曲家アーロン・コープランドらの著名人が出入りしている。調べれば、すぐにわかることだが、彼らも「ゲイ」である。
つまり、デビュー前から、レニーはニューヨークの「ゲイコミュニティ」の一員として芸能活動を始めたことが明示されている。
すでに、この部屋には、本作では終生のレニーのマネージャーとして登場するハリーの姿も見える。映画後半(第3部)に至っても、ハリーは、私生活でもレニーの至近にいて、若いレニー好みのハンサムボーイを付き人として斡旋したり(コカインパーティーにも加わったり)してフェリシアの不興を買う原因ともなっている。言うまでもなく、このハリー本人も「ゲイ」、ゲイコミュニティとの仲介役、いわばレニーのための女衒の役を買って出ているのだ。
フェリシアとの夫婦愛に満ちた介護と別離を見せたあとの第5部で、若い黒人の教え子とロックバーで身体を密着させて踊るレニーの姿に、嫌悪感や不快感を示す向きが多い。
しかし、全5部が対照的に構成されていることに注目すると、これはフェリシアと出会う前のレニーが耽っていたのと同様に、彼女の死後、彼の「地」である同性愛志向が健在であったことを示す意図があったと考えたい。
そもそも、フェリシアは、結婚前に、レニーからデヴィッドを紹介された折に、はっきりと彼が同性愛の相手であることを認識していた。
また、第2部後半のジェイミーにレニーが言い訳する前のフェリシアとの会話で、「自分が同性愛をやめられないこと」を了解した上で結婚したらしいことが示されている。
再見すると、2人の恋愛の主導権は、常にフェリシアの側にある。「4年も躊躇していた」レニーに対して、結婚を積極的に進めようとしたのは彼女の方なのだ。
つまり、彼女は、レニーの同性愛を重々承知の上で、さらにはそれを認めた上で、結婚を選択したのだ。
ならば、なぜ、2人は別居を選択するほどの「不和」となったのか。
これも、第2部後半で描写されている。
本稿では再々登場するレニーの傑作『キャンディード』の大団円の合唱 “ Make our garden grow “ の練習シーンで、レニーはスペイン語の歌詞の部分がフェリシアの発案だと明かす。それを聞くフェリシアは満更でもない笑みを浮かべるが、横から若い男性の助手が
「そんなセリフはヴォルテールの原作にない」
と指摘すると、途端に不快な表情に一変する。
その前のエド・サリヴァンショウで、レニーの業績を自慢げに語るところからも、フェリシアは、レニーの音楽家としての才能に惚れこみ、自分がその創作に関与していることに生きがいを見い出しているのだ。
この合唱練習シーンに続くのが、レニー畢生の大作『ミサ曲』の作曲及び初演のシーン。
この初演は、別の指揮者が行ったらしく、レニーはフェリシアと隣りあって客席で聴いている。ところが、曲がクライマックスを迎えたところで、レニーはあろうことか、彼女ではなく、逆隣の若い助手の手をグッと握りしめる。音楽がさらに高まるなか、フェリシアは、その様子に凍りつくような冷ややかな視線を投げかける。
そのあと、「LB」の刺繍のあるレニーのナイトスリッパ、枕、歯磨き一式を、フェリシアが廊下に投げ捨てるシーンが続く。
こう見ていくと、彼女が我慢ならなかったのは、レニーの同性愛そのものというより、彼の重要な創作活動において自分をないがしろにされたことだったと言えるのではないか。畢生の大作初演の喜びを、愛する妻であり終生の伴侶であるこの私とではなく、若いツバメと手を取って分かちあっている現場を臆面もなく見せつけられて「キレた」のである。
フェリシアと決別して、レニーの私生活は、姉のシャーリーが言うように「自分を見失い」、アバンチュールにコカインパーティーにとすさんでいく。
だが、上記した
“ I miss him, that child of mine. “
のセリフが彼女によって発せられたことからも明確だが、「折れた」のはフェリシアの方だったのだ。
以上、まとめると、本作の主題は、同性愛者であった若き天才音楽家レナード・バーンスタインがフェリシアという女性と本気の恋愛をして結婚、おしどり夫婦となり、一時期不和ともなるが、病に倒れた彼女に献身的な愛を注ぎ、死後も terribly 寂しく想うほど愛し抜いた物語、ということになる。
さて、技法面だが、とにかく情報量が多い。
「音楽家バーンスタインの伝記」を期待したのに、音楽活動はほとんど描かれていない、
というのが大半の下馬評のようだ。
しかし、BGMのすべてがオリジナル曲ではなく既成曲。それも、9割以上がレニーの自作曲か彼が指揮した演奏曲だ。
サントラ盤のセトリを見るだけで、レナード・バーンスタインの主要な作品群をほぼ網羅し、メルクマールとなる演奏曲も要領よく押さえていることがわかる。
本編冒頭シーンだけで、デヴィッド、ジェローム・ロビンス、アーロン・コープランド、ハリーが姿を見せ、会話のなかにはワルターやロジンスキーといった大物が出てくる。
初見レビューでも書いたが、ほとんどの視聴者は、これらの情報を初見では看取できないだろう。
冒頭シーンは、レニーの動線に従い、屋根裏部屋から、カーネギーホールの客席へ、ステージへ、そして満場の聴衆を前にしての「マンフレッド序曲」の演奏シーンへとシームレスにつながっていく。
いささかトリッキーだが、少しの無駄もない、相当の時間経過とさまざまな場面転換を一瞬のうちに見せる意図のもとに編集されている。
クーパーは、本作制作にあたって、夫婦愛に焦点をあてながら、同時に、音楽史の巨星たるLBの音楽と業績の全てを凝縮する形で見せようとしたのではないか。
初見では全て汲み取れなくても、再見を繰り返したり、視聴者が自主的に調べたりすることで感得できれば良い、と考えたのではないか。
そのため、再見することで、おのずと発見の要素は増え、スコアも上げたくなる。
やはり、傑作である。
※Filmarks 2023.12.24投稿記事に追加したものを一部省略して投稿した。
8割ほどの幸福
ブラッドリークーパーが主演と見せかけて、話の本筋はどちらかと言うとその妻にこそ当たっている
偉大な音楽家
結婚を渋った挙句実は男色家だった
ただ妻へ向ける愛はやはり確かなものがある
また音楽への愛も確かなものがある
素晴らしい旦那、素晴らしい音楽家だけれども、どうしても満たされない
性の嗜好を超えた愛
だけどどこか完全には受容できない
果たして完全に納得した状態で亡くなったのか
心の内に虚無を抱えた亡くなっていったのか
それを考えながら見る闘病シーンはかなり胸に来るところがある
糞しかしない鳥の下で生きている、みたいなセリフが頭に残る。
また、
創作者と演者は方向性が対照的だという印象的なセリフ。
前者は内面へ向いていて、後者は外面に向いている
作曲家と指揮者のバーンスタイン
監督と俳優のブラッドリークーパー
米史最高のエンターテイナーの一人。
レナードバーンスタインは、個人的にはヨーロッパ偏重なクラシックの世界から、アメリカなりにクラシックをやって解釈し直し、エンターテインすることで全世界が認めた、かつてない、そして不世出のコンダクター。今回の作品を観ても、その思い込み?先入観?は間違いなかったと思う。
その中でも、刮目に余りあるほどの演技は、英イーリー大聖堂で振ったマーラーの交響曲第2番「復活」。私の先入観通りの彼そのもの。指揮台で笑い、歌い、仰け反り、そして跳ねる。それに呼応するかのように、ボーイングは変わらずだけど、バイオリニストたちがどこぞのロックライブかと思わせるほどのヘッドパンキング。そりゃ盛り上がるよ。更に更に、このシーンがキャリーマリガンの’I miss you’からの舞台袖でサンドイッチされていることの演出の憎らしさたるや。だからこそ、この後の展開が沁みるわけで・・・。
今後ブラッドリークーパーから目が離せないのは間違いないな。
今年一番
ドキュメンタリータッチの佳作と思いきや、
スピルバーグやスコセッシがプロジューサーに名を連ねる
ハリウッド超大作でした。
監督・主演のブラットリー・クーパーは、ありとあらゆる
レニーの写真・映像を研究しており、各シーンは、Lifeや
Magnamのカメラマンが撮影した写真から飛び出したようで
アメリカ写真・映画芸術の王道を踏襲したものでした。
(ちょっと古臭い感じするかも)
白黒の前半部分は、古き良きハリウッド映画の夫婦愛を
彷彿させる。(ジューン・アリソンとジミー・スチュアート
が出てきそうだ?)
しかし、カラーの後半部分は、自由奔放(自堕落?)な生活を
謳歌するレニーと家庭を守ろうとするフェリシアに亀裂が
生じる。
とてつもない才能に、魅了され、時には戸惑った、比類
ない人生を送った夫婦の愛情物語なんだろう。
レニー役のブラットリー・クーパーは、ルックスをかなり
研究しているが、クライマックスのLPOと「復活」を
振るシーンの指揮は、実際のバーンスタインの演奏に接した
ものにとっては、正直、ヘタクソである!!!
フェリシア役のキャリー・マリガンは申し分ない立派
演技である。でもチリ人だからスペインなまりじゃないの
フェリシアは・・・
フェリシアの看病のために、コンサートをキャンセルされた
ものより
音楽ファン、特にクラファンやミュージカルファンの方のために
結構いろんな感想・評が多く、まだ観てない方たちを躊躇わせてるように思うので、音楽ファン、特にクラファンやミュージカルファンの方のためにひとこと書きます。
ネタバレになるかもしれないですが、この映画の全編にわたってバーンスタイン自作の有名曲が適所に使われていて、マーラーなどの楽曲も効果的に出てきて、音楽好きにはとても素晴らしいです。特筆すべきは、ブラッドリー・クーパーがバーンスタインになりきって指揮するマーラーの第2交響曲”復活”、第5楽章フィナーレの場面です。レニーの1970年代頃のコンサートを、英国のどこかのカテドラルで再現しているのですが、延々約6分間にわたって終曲まで聴けて思わず拍手したくなるほど。それとバーンスタインとフェリシアが”オン・ザ・タウン”の世界に入り込んで、ブラッドリー・クーパーがジーンケリーばりに踊るところも良かったな。またレニー自作のミサ曲の”平和:聖餐式(シークレット・ソング)”の練習シーンも良かった。
楽曲の詳細をお知りになりたい方は、Deutsche Grammophonから出ているサントラの紹介を見てほしい。それによると基本ネゼ=セガンとロンドンSOの演奏だけども、一部はバーンスタインがウィーンフィルやNYフィルに遺した音源も使われているようです。
なお、この映画はフェリシアとの愛の軌跡を中心に描いているので、バーンスタインの様々な業績や活躍を具体的に見せてくれる場面は多くない。インタビューを受ける場面で語られる方が多いようです。いわゆる伝記的な部分がもう少しあったほうが、音楽ファンには嬉しかったかもしれない。また、レニーの奔放な生き方とかフェリシアや子供たちとのかかわりの場面で、物語の説得力とかフェリシアやレニーへの共感も増したかもしれないかな。
なお、以上は私の感想です。これからの方は、惑わされず、あまり拘りなくフラットな気持ちで観てほしいです。また、NetFlixだけども映画館の音のよいところで観たほうがいい。
まあまあだった
若い指揮者がどんな評価でどのようなパフォーマンスで出世していくのかと思ったらそこはばっさり端折られて、奥さんとの出会いが描かれる。それがとても普通でつまらない。裏に同性愛があるくらいだ。
後半カラーになって、奥さんと猛烈なけんかをする。うちでそれをやったら一発で離婚だ。余程の理不尽がない限りこっちは平謝りなので、あんなふうに対等に言い合えるなんてすごい。関係が壊れることが怖くないのだろうか。本当の信頼関係で結ばれているのか。一方で男性との浮気は暗に認められているような、芸術家だから仕方がないという理解を奥さんがしているのだろうか。すごい場面だったけど、別にこの題材で見たいのはそれじゃない。偉大な指揮者だって人間だみたいなことかもしれないけど、もっともっと偉大さを見せて欲しい。
終盤に素晴らしい演奏が見られる。また、後輩への指導も指揮で演奏が見事に変わるのがすごい。そういうのがもっと見たかった。音楽や指揮の分量が3倍くらいが望ましい。
バーンスタインの響き
レナード・バーンスタイン。
アメリカを代表する指揮者で作曲家。クラシックやミュージカルなど多くの音楽を手掛けているが、やはり私は『ウエスト・サイド物語』の映画音楽で知る。
そんなバーンスタインをブラッドリー・クーパーが演じる。若年期から特殊メイクを施した老年期まで熱演。
主演のみならず、プロデュース・脚本・監督まで兼任。『アリー スター誕生』で監督デビューながらその手腕が絶賛されたクーパーが、監督第2作の題材に。バーンスタインを敬愛し、兼ねてから伝記映画を構想していたとか。
プロデュースにはスコセッシやスピルバーグも名を重ね、そのリスペクトぶりが窺える。
現在賞レースで軒並みノミネートに連ねる注目作。今年のNetflix映画でも特に期待の一本。
“映画監督ブラッドリー・クーパー”は一発屋ではなかった。
演出面・映像面で冴えを感じ、『アリー スター誕生』の時より堂に入った印象。
特に映像面は秀逸。カメラワークも巧みで、若年期をモノクロ、老年期をカラーで分け、その映像美はクラシックの名画を醸し出す。
偉大な音楽家の伝記。その輝かしいキャリアにスポットが当てられるのが通例。勿論本作でも若くして代打でオケの指揮を執り名を馳せたエピソードから始まり、音楽論や音楽家の卵たちへの指導なども描かれる。
しかしクーパーが主軸に据えたのは、妻との愛。
妻は女優のフェリシア・モンテアレグレ。
演じるのはキャリー・マリガン。
クレジットではクーパーより先に名が出、それも納得の名演。
もっと音楽家としての伝記を見たかった人には期待してたのと違うかもしれないが、音楽家としてよりも一人の人間=バーンスタインにクーパーが迫り、寄り添う。
とあるパーティーで出会った二人。
二人でバーンスタインの楽曲の世界へ体感するなど、瞬く間に恋に落ちる。
子供も3人。仕事も順調で、幸せな日々。
…ただそれだけなら描く必要はない。
幸せと並行する複雑な関係。
バーンスタインが同性愛者であった事を知らなかった。知人に私は夫とも妻とも寝たなんて言ったり。
パーティーで出会った若い男性とイチャイチャ。妻を愛し、同性も愛し、愛に自由奔放。
が、フェリシアの胸中は…。夫が他の女性と関係を持つ事は浮気だが、同性と関係持つのも性的マイノリティーだからと言って寛容される事ではないだろう。これも浮気。
夫に尽くした自分の人生を“鳥のフン”に例えたフェリシアに心痛。
程なくして、フェリシアの胸に腫瘍が…。
愛に奔放だったバーンスタインもさすがに妻に献身。
紆余曲折あったが、何かを前にして、愛を再認識する。
綺麗事と思われるかもしれないが、それでもその愛の営みに心打たれる。
文字通りそれを支えた。キャリー・マリガンの苦悩と病魔と闘病と息を引き取る演技は、圧巻。
バーンスタインが指揮を執る演奏シーンは高揚感満点。
劇中の音楽もバーンスタインの楽曲を使用。正直そこまで詳しくはないが、『ウエスト・サイド物語』の音楽はすぐ分かったね。
特殊メイクはカズ・ヒロ。鼻を強調した特殊メイクに一部批判的な声も出ているようだが、バーンスタインを見事再現した特殊メイクはさすがのもの。3度目のオスカー、狙えるぞ!
伝記映画や夫婦愛のドラマとしてオーソドックスな作り。
『アリー スター誕生』もそうだが、好き嫌い分かれるかもしれないが、これが監督クーパーのスタイルなのだろう。
そこから浮かび上がらせる光と影を包み隠さず。
音楽と愛を奏でて。
バーンスタインという響き。
今年はモリコーネのドキュメンタリーやバーンスタインの伝記。
いずれはジョン・ウィリアムズ(まだ亡くなってないけど)や伊福部昭題材の伝記が見てみたい。
あー、バーンスタイン❗
レナード・バーンスタインの伝記映画が公開されると知って楽しみにしていました。
バーンスタインといえば、70年代にカラヤンの次に人気がある指揮者で髪型もカラヤンに似てリーゼント?で恰好良く、カリスマ性もピカイチ。当日小中学生だった私も知っていました。また、彼が指揮したクラシックアルバムは結構所有しており、現在でもSACD化したアルバムが発売されれば買い求めてしまいます。
さて、本映画の出来はどうかと言うと70点くらい。確かに、バーンスタインを演ずるブラッドリー・クーパーがスクリーンから微笑むと、それはアルバム表紙にポーズを決めるバーンスタインその人であり、会話にも早口で巻くして、凄く知性を感じる。もっと、バーンスタインが好きになり、彼が指揮したクラシックアルバムを聴きたくなりました。
但し、バーンスタインの内面の引き出し方は薄いし、同性愛者であるとか、麻薬らしき物を鼻から吸引したり、ディスコで踊りながら恍惚(ラリっている様な)した表情を浮かべたりしているのは、イチファンとしては観たくなかった。そこが減点。あと、有名人の名前が映画で登場していない。ブルーノ・ワルター(大作曲家マーラーと親交があり、映画でも交響曲2番と5番が印象的に使われてきた)の名前が出たくらいかなぁ。
しかし、バーンスタインのCDを手にとった人、指揮した音楽を聴いた事のある人は一見の価値あり。
しかし、題名は「マエストロ」ではなく、「バーンスタイン」の方がいいなぁ〜と思った。
bravo 👏 👏 👏 👏 👏
朗らかで社交的なバーンスタイン( ブラッドリー・クーパー )が、後に妻となる女優フェリシアと出逢う。
仕事に追われる中、バーンスタインが愛する妻や子供達と対話を重ねる姿が印象深い。演じるブラッドリー・クーパーの愛情溢れた眼差しに魅了された。
時に目を潤ませ、時に声を荒げ感情を露わにする美しい妻フェリシアをキャリー・マリガンが熱演。
この素晴らしい作品を是非、映画館で。
映画館での鑑賞
偉大すぎるパーソナリティの不幸
バーンスタインの再現度が半端ない。カズ・ヒロの特殊メイクあってのことだろうが、ブラッドリー・クーパーの立ち姿、指揮ぶり、それ以上に声質と話し方の寄せ方は凄い。クラシックファン以外に伝わると嬉しい。この映画は音楽映画ではないし、アメリカが生んだスーパースターの英雄譚でもない。どちらかいうと女優でもあった奥さんフェリシアを演じたキャリー・マリガンに感情移入する人の方が多いだろう。バーンスタインのバイセクシャルを正面から捉えているが、それが彼の偉大さを少しも損なわない。一昔前ならスキャンダラスに思われたかもしれないが、むしろバーンスタインの自分でも持て余す才能と人類愛が家庭人としては妻や娘を苦しめる姿が胸を打つ。マーラーも交響曲2番「復活」は見ごたえがあり感動的だが、映画の終わりではないところがより夫婦のドラマを深いものにしている。
全14件を表示