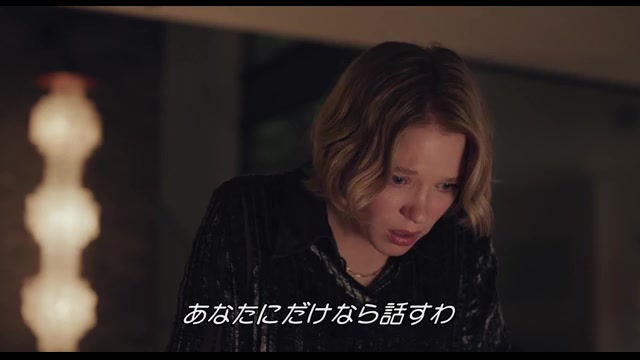「スローターハウス5×マトリックス×D・リンチ風が錯綜する迷宮世界を、レア・セドゥとバッドトリップ」けものがいる 高森 郁哉さんの映画レビュー(感想・評価)
スローターハウス5×マトリックス×D・リンチ風が錯綜する迷宮世界を、レア・セドゥとバッドトリップ
初見でまず、主人公がいろいろな時代に移って異なる人生を体験する筋がカート・ヴォネガット原作のSF映画「スローターハウス5」っぽいと感じた。デイヴィッド・リンチ風味も複数あって、ロイ・オービソンの楽曲が印象的に使われているのは「ブルーベルベット」、2014年のLAで売れていない女優志望の女性がくすぶっているのは「マルホランド・ドライブ」、ダンスクラブ内のカウンターバーがある一画のインテリアは「ツイン・ピークス」などを想起させる。
観終わっても謎が解決されずに残り考察を促す感じ(それがまたリンチ監督作に似ているポイントでもある)があって、英作家ヘンリ・ジェイムズの原作小説に手がかりを求めて野中惠子訳「ジャングルのけもの」(審美社刊)を読んで、茫然とした。映画とは別次元の難解さというか、男性主人公のジョン・マーチャーとヒロインのメイ・バートラムが長い年月にわたり延々と禅問答のような会話を繰り広げ、劇的なことはほとんど何も起こらず、いっこうに2人の距離が縮まらないままなのだ。原作における「けもの」とは、主人公が自分の人生にいつか起きると予感する何かしら重大なことの比喩。訳者あとがきで紹介された、原作者ジェイムズによる主題の説明では、「彼は定められた通りの運命に出会っていた――それはおよそどんな事件も起こることのない人間という運命だったのである」。
とはいえ、いくつかわかったこともある。ベルトラン・ボネロ監督を含む映画の脚本チームは、主人公と運命の相手の性別を入れ替え、主人公をガブリエル・モニエ(レア・セドゥ)、運命的な異性であるルイ・ルワンスキ(ジョージ・マッケイ)を配置。序盤の1910年のパリの屋敷で2人が再会するシークエンスでの状況や会話の内容に原作小説の一部が反映されたほか、2044年の指導役のAIとの対話でも、ガブリエルが「破滅的な何かが起きる予感があり、たとえ怖くてもその場に居合わせるべきという根深い感覚がある」と告白する台詞が原作から引用されている。一方で、それ以外のパートのほとんどが映画オリジナルであり、原作の禅問答のような会話劇を、よくもここまで映画的なメリハリの多い重層的なストーリーに翻案したものだと感心させられた。
幸い、試写で2度目の鑑賞ができ、また原作とプレス向け資料の助けも借りて、全体の見通しがだいぶよくなったことで気づいた点もいくつかあった。
映画「けものがいる」の前提はこんな感じだ。2044年、AIが人間を管理している社会で、単純作業でない知的な職業に就くには、DNA浄化センターでのセッションを経て不合理な人間の感情を消去する必要がある。セッションを受けることにしたガブリエルは黒い粘液で満たされたバスタブ風の台に横たわり、ロボットアームの先から伸びる針を耳に挿入され、1910年と2014年の2つの前世を訪れる。それによって前世で潜在意識を汚染した古いトラウマを消去できる、と説明される。
2044年現在のパリ、そして前世の1910年のパリと2014年のロサンゼルスでも、ガブリエルはルイと出会う。それ以外にも、ナイフ、人形、鳩、予知能力者/占い師、ダンスクラブなど、複数の時代に登場する思わせぶりな要素がちりばめられている。これらの要素は、ガブリエルの現世と2つの前世が個々に独立したものではなく、相互に何らかのつながりがあることを示唆している。
先に映画の前提として書いたが、指導役のAIが語る前世とDNA浄化についての説明は、そもそも素直に信頼していいものだろうか。ミステリ小説などのよく知られた叙述トリックで「信頼できない語り手」というのがあるが、2044年の人々(と映画の観客)に対してAIが全知全能のガイドのごとく語っていることが実は真実ではなく、人間への支配を維持強化するための巧妙な虚構という可能性はないだろうか。
いくつかの気になる点から推論し、こんな仮説を立ててみた。AIが説明する「DNA浄化セッション」の実態は、AIに備わっておらず厄介な人間固有の特性である感情を調査研究するための「人体実験」であり、同時にその実験から得た知見を利用して人間から感情を奪う「洗脳」なのだ、と。セッションで前世を再訪するというのも表向きの方便で、仮想現実(VR)とブレインマシンインターフェイス(BMI)を組み合わせてリアルな夢を見させる未来技術によって、AIがシナリオを書いた「1910年の悲劇」と「2014年の悲劇」を被験者に疑似体験させて感情のデータを収集して分析し、洗脳に役立てているのでは。
複数の時代にいくつかの要素が繰り返し登場する点も、それぞれの時代に現実に起こったことではなく、すべてAIが書いたシナリオだと推論する根拠の1つになる。さらに、時代を超えたある2つのシーンの類似性も気になる。2014年にダンスクラブを訪れたガブリエルが、3人組の女性客から同席を却下される。そのセッションを終えた2044年の晩に訪れるダンスクラブでも、やはり3人組の女性客から同席を拒否される。この反復から、もしかすると2044年の「現世の体験」すらもAIに見せられている「夢」なのではと想像してしまう。
そんな仮説に立つなら、映画「マトリックス」との類似性も明白だろう。ますます高度に、便利になっていくAIに依存しすぎることに警鐘を鳴らす意図も確かに認められる。2044年のガブリエルも悲劇的な結末を迎えるように見えるが、感情を奪われなかったからこその悲劇だと思えば、AIによる洗脳に屈しなかったガブリエルは勝利したとも言える。
技術革新が進む20世紀初頭にジェイムズが書いた原作小説は、劇的なことが起きる予感を抱いたまま何も起きないのが自分の運命だったと悟り絶望する主人公の話だった。これをAIの普及が進む2020年代に翻案したボネロ監督は、AIに管理される社会でいくつもの悲劇を経験しながら感情を失わなかった主人公を通じて、感情こそが人間らしさの源なのだと訴える。ままならないことも含めて人生を、そして悲しみも含む感情を、受け入れて肯定する点で小説と映画は響き合っているのかもしれない。