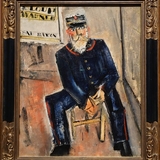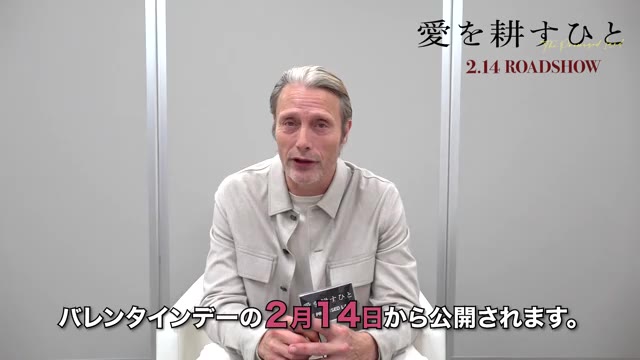愛を耕すひとのレビュー・感想・評価
全152件中、81~100件目を表示
邦題のイメージとは違うかも
一部にショッキングなシーンもありますし、「愛を耕すひと」というイメージで観るとこんなはずじゃなかったと思う人もいるかもしれません。
歴史好きな人、人間ドラマ好きな人、北欧好きな人、色々楽しめると思います。
ケーレンとデ・シンケルって真逆の存在のようで、本人がこだわってる部分は重なってるよなと感じました。
それが原題の「Bastarden」に繋がるのでしょうか。
Till
マッツの最新作、近年は大作やアクションものが多かったですが、久々に人間ドラマな作品がやってきたのでいざ鑑賞。
思っていたものとは違いましたが、史実に沿った重厚な人間ドラマが味わえました。
ジャガイモ作りに励むケーレン大尉とその土地までに出会った人々とのハートフルものかと思いきや、早い段階から不穏な雰囲気漂う感じで、思った以上に血生臭い展開もあったりとで驚かされました。
ケーレンも良い人なのかなーと思っていたら気難しく、最初は人を道具のようにしか見ない感じでいけ好かなかったんですが、人々との交流を得て人としての成長をしていくっていうシナリオが活きていたなと思いました。
ケーレンと関わりのあった人の死がダイレクトに突き刺さる展開が多く、救いのある展開よりも鬱屈とした展開がオープンで進んでいくので中々に重いのは好みが分かれそうです。
デ・シンケルが底無しのクズ野郎だったのもとても良かったです。
自分に敬称を付けることを要求しながらの登場シーンが嫌なやつだなと思いましたが、煮え湯の拷問シーンの容赦のなさと高笑いでまずフラストレーションが溜まり、怒りのあまりメイドを窓から突き飛ばして殺したり、残飯をわざわざ渡しに行ったりとバカだけど変に頭が回って権力があるから厄介というこの手のドラマ作品の中でも一級品のクソムーブをかましていました。
その分シンケルがアン・バーバラにギッタギタのボッコボコにされるシーンはテンション上がりました。
薬入りの酒を飲ませてぶっ倒したあとにブッ刺しまくりからの男の一物をかっ割いたところはヒャ〜となりつつもスカッとしました。
アン・バーバラの目がギラギラしていてゾワゾワしっぱなしでした。
地味にシンケルの部下を殺すシーンが暗殺者じみた隠密っぷりでしたし、どの行動も隙がなかったのが面白かったです。
思想によって差別的な要素が生まれるのも時代背景と照らし合わせて見ても納得いくものがあり、アンマイ・ムスを手放す展開は仕方がないとはいえ中々辛いものがありましたし、アン・バーバラの逮捕後も物悲しいものがあったりしました。
終盤はちと駆け足な感じがあり、アンマイ・ムスとの別れがあっという間すぎてどこか見逃したのかな?と思いましたし、アン・バーバラとの再会も無理くりすぎないかなとは思いました。
映画館でじっくり味わえて良かったです。
濃厚な演技を大スクリーンで堪能できるのはいいな〜と劇場を後にしました。
鑑賞日 2/19
鑑賞時間 13:25〜15:45
座席 C-6
ヒース
原題:Bastarden=ろくでなし
日本語題は誰が考えたのか知らないけれど、原題の方が作品の内容には
合っていると思った。
*追記*一度投稿してから、他のレビュアーさんが「私生児」の意味もあると
書いておられたのを読んだので拝借してここに追記します。
ろくでなしとは作品に登場するフレデリック・デ・シンケルを
指すのだろう。退役軍人のルドヴィ・ケーレン大尉(マッツ・ミケルセン)
が荒野を開拓して農地にしようとするのを邪魔する極悪非道の男。
その地域を仕切っている有力者だけに質(たち)が悪い。権力を
持っていて周囲の人間は逆らえないから好き放題だ。
グラディエーターII 英雄を呼ぶ声(原題:Gladiator II)に登場する
双子の皇帝に匹敵する。
そんな奴の妨害に遭う一方で自然の脅威やら人的資源の問題やらが
障害となり心が休まる暇などなかったに違いない。だから「愛を耕すひと」
というロマンス的な雰囲気の題はちょっと合わないと思った。
誰かを愛するのは間違いないがそれだけがこの映画の主題ではないはずだ。
ケーレン大尉自身もただやられるだけではなく彼なりの方法で
解決しようとする。不利な状況を打破するには綺麗ごとでは済まない。
彼が取った行動もなかなかのものだった。
18世紀のデンマーク。アメリカの西部開拓時代のような、ならず者が
蔓延る世の中では自分の身は自分で守ることも必要だったに違いない。
ぶれない自分軸を持っていて信念を貫こうとする人はやっぱり強いし
必死の努力の先に得られるものは大きいと感じた。
史実に基づく歴史小説が原作。この映画では予備知識がなくても
時代背景や人物の成り立ちが分かりやすく描かれていて良かった。
小説用の創作や映画用の脚色は当然あっただろうが、とても
ドラマチックな内容だった。壮絶という言葉が本当にふさわしかった。
デンマーク・ドイツ・スウェーデン合作。デンマークが舞台の
デンマーク語の映画は普段観る機会があまりないから貴重だった。
おそらくデンマーク映画界の最高峰のスタッフ・キャストが集結して
製作されたと思われ、質の高い映画を観た充実感が得られた。
マッツ・ミケルセンの渾身の演技が良かったが他の出演者たちも
それぞれ印象に残った。
(余談)予告編を見た時、日本語字幕の「決して違う」という表現に
違和感を覚えた。「決してーーではない。」という使い方が普通では?
その部分は本編ではまともな翻訳になっていた。
今ひとつ主人公の心境がよく分からないのよ。
重厚な歴史ドラマ。デンマーク語(だよね)であるところが好感持てる。最近は大市場のアメリカを意識してかヨーロッパが舞台であっても全編英語っていう映画が多く違和感を抱くことが多い。ナポレオンが英語喋っている作品もあったよね。
舞台はデンマーク領ユトランド半島。「バベットの晩餐会」と同じ土地です。あれは海っぺりだったけど本作は内陸の荒れ地(ヒース)。時代は「バベット」のちょうど100年前です。
まずこの時代感というか主人公の生活環境の過酷さがいまひとつ表現できていないと思う。かたや仇役のシンケルの暮らしぶりのキンキンさ。デンマーク王国は全盛期はかなり豊かだったと聞くけど片田舎の荘園領主があんなウィーンのど真ん中みたいな生活していたかなあ。
映像は確かに美しいけどどうも土にまみれて大地を耕しているという感じはしない。小綺麗なんです。
最大の問題はルドヴィ・ケーレン大尉の人物表現。この映画の原題は「Bastarden」私生児です。原作にあたっていないのではっきりは言えないがこれは彼が周りからそのように呼ばれ蔑まれていたということでしょう。人格形成に影響がないわけがない。そのような経験は、上昇志向がありながら卑屈であり、時として優しく時として冷酷で暴力的な人間として、すなわち二面性のある複雑な人間を生み出すと思う。冷酷なところはならず者たちに罰を加えるシーンに表れているがその他、基本的にはこの作品はルドヴィ・ケーレンという人物の心の中には分け入っていない。全てマッツ・ミケルセンの重厚な演技で覆い隠されていて単に鈍重な我慢強い人にしか見えず今ひとつ心の陰影が見えてこないのです。演出のせいではもちろんあるのだが、ミケルセンの演技プランにも問題がなかったといえるのか?素晴らしい演技だ、名優だともてはやす声があまりにも多くて、天邪鬼の自分としては疑問を呈してしまうのです。マッツ・ミケルセンの最高演技は007のル・シッフルだと思っているひとなもんで。すいません。
男爵の由来じゃないよ
あんまり話題になっていないけど、マッツがでてるとつい見に行っちゃいます。
マッツはやっぱり、期待を裏切りません。それでも、誰でもわかる主演作があげれない、ライダーズ・オブ・ジャスティス?重賞もとっていないんじゃないかなぁ?
地味なこと以外は減点ができません。
史実を元に脚色していると思うけど、現代人の視点では結末も合格です。
原題はBastardenで英語から考えると「クソ野郎」なので、むしろこういう邦題を付けるとかえって敬遠するひともいるんじゃないかな。
作物の育たない荒れ地を開墾する話し。全く笑わない「クソ野郎」のマッツと作物がちょっとだけ生長するのを眺める作品。封建制を敷いている国であれば、どこでも成立するストーリー。空き地とお屋敷があればお金をかけずに撮影できそう。日本でも頑張ってリメイクしてみて下さい。
本作やイニシェリン島の精霊、燃ゆる女の肖像みたいな寒くて風が強そうな所は、食材のバラエティーがなくて、実にメシマズに見えますね。現代においてもそういったところの食事は単調ですもの。ビタミンなんて単離されてないとは言え、あのような食事をしていれば寿命は短くなるよね。それに比べると、同時期の江戸の町民の食生活は恵まれてるし、文化が発展する余地があるんだなと、見ながら思いました。あと、あの領主はフルーツゼリーがよっぽど好きなんだろうね。ケーキは手を付けてなかったけど。
配信で上がっていても気付かなそうな作品なので見ましょう。
ずっと見ていられる!
凍てつく心を耕したのは?
マッツ・ミケルセンの演技に圧倒された約2時間だった。
「007カジノ・ロワイヤル」や「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」しか映画ではお目にかかってないが、存在感がある俳優とマークしていた。
だからこそ、期待して「愛を耕すひと」(原題「BASTARDEN」の意味である「私生児」とはかけ離れているようであるが映画の結末から納得した)を鑑賞したのだが、期待以上の感動をもらった。
とても嬉しい❗
不毛の大地を独りでも開拓しようとするルドヴィ・ケーレンが、襲い掛かる自然の脅威と地主であるフレデリック・デ・シンケルからの非道な仕打ちに抗いながら、彼のもとから逃げ出した使用人の女性アン・バーバラや家族に見捨てられた少女アンマイ・ムスとの出会いにより、ケーレンの凍てつく心に変化が芽生え、愛するようになっていく。
アンマイ・ムスとの別れと修道院で再会のシーンには涙が溢れた。
演じたメリナ・ハグバーグは初めての映画出演だが難しい役をこなしていた。
フレデリック・デ・シンケルのシモン・ベンネビヤーグの徹底したサイコパスな演技がこの作品をさらに見応えあるものにしている。
結末が予感できたためスコアを「4.5」にしたが、初めてのデンマーク映画、重厚な色彩の映画を観て良い時間を過ごした。
是非とも観るべき一作。
2509
不毛の大地で育まれた愛
貧しい退役軍人ながらも、古びた一張羅の軍服を着て馬に乗る姿はどこか中世の騎士を思わせる気品とストイックさを兼ね備え、無表情で不愛想でもその内に秘めたる温かみのある表情を時折垣間見せる。そんなマッツ・ミケルセン様の魅力全開の中世愛憎劇。
貴族の私生児として生まれ、不遇な人生を強いられた男は戦場に赴き殊勲を得るも、このまま年老いて退役軍人として人生を終えるつもりはない。貴族の称号を得るために彼は国が断念した土地の開拓に一人挑もうとする。
自分を息子と認めなかった貴族の父への思い、そんな父を見返したいという思いからなのか彼は己の名に「フォン」を刻み込むため、貴族の称号を得るために未開の地の開拓に挑戦する。
荒涼とした大地は50年もの間あらゆるものを寄せ付けず開拓者たちを頑なに拒んできた。あまりに厳しい気候、何ものをも受け入れようとしないその頑強な土壌を持つ大地にいま一人の男がくさびを打ち込む。
長年愛を知らず、ただ戦いに明け暮れたケーレンの心には荒涼とした大地と同様に冷たい風が吹きすさんでいた。すべてのものを拒絶し孤独の中で生きてきた男の姿はまさに何ものも受け入れようとしないこの大地の姿と被る。しかし逃亡小作人の妻のアンやタタール人の少女アンマイとの交流を通して彼の乾いた心は次第に湿り気を帯びていく。
彼ら家族同然のいとなみが固く閉ざされたケーレンの心にくさびを打ち込み乾ききった彼の心を潤わせていった。彼らが力を合わせてこの乾ききった大地を農場に適した湿り気のある大地に変えたように。そして彼らの間に強い絆が芽生えた時、頑なだった大地も心を開くかのように小さな一つの芽を芽吹かせる。
開拓地を自分の領土と主張するシンケル卿の様々な妨害を受けながらもついに彼らは力を合わせて苦難の末に開拓に成功する。しかしいまだシンケルによる執拗な嫌がらせがやむことはない。ようやく心を開いた大地、しかしそこには悪魔が巣食っていたのだ。
シンケルによって囚われの身となるケーレン、王室にも見放されもはやこれまでかと思われたときアンの捨て身の行動が彼を救う。
シンケルは死に、すべての脅威は去った。しかし領主殺害の罪を負ったアンは終身刑に、けして生きて逃れられない運命となる。開拓民も去りケーレンは一度手放したアンマイと再び暮らし始め、月日は流れた。
ついに待ち望んだ貴族の称号を手に入れたケーレンだったが彼の心はどこか寂しげだった。年頃になったアンマイは恋に落ち、彼の元から去る。再び孤独の生活に戻った彼はその時気づく、自分が人生で本当に求めていたものがなんであったか。それは貴族の称号などではない、それは彼が生まれて一度も手にしたことのなかった家族のぬくもりであり家族の愛だった。彼がこの大地の開拓によって育んだもの、それは愛でありその愛こそが彼が本当に求めていたものであった。それに気づいた彼は貴族の称号を投げ捨ててこの地を去る。本当に自分が手に入れたものを取り戻すために。
ルドヴィ・ケーレンはけしてその名にフォンが刻まれることはなかった。彼にはそれよりも大切なものがあったことに気づいたのだった。
とても見ごたえがある作品であり、主人公たちに次から次へと降りかかる試練など見ていて気が抜けません。終始安心して見れなかったので結構疲れます。どこまでが史実かわかりませんが映像がとても美しく、中世を舞台にした貴族たちによる愛憎劇はドロドロした昼ドラのようで奥様方にも喜ばれるかと存じ上げます。劇場はマッツ様目当ての女性で埋め尽くされていました。
特筆すべきはシンケルの悪役っぷり、近年まれに見るものがありました。アカデミー賞悪役大賞受賞は間違いないでしょう。ここ十年で一番の悪役ぶりではないでしょうか。
舞台が絶対王政の時代で人権なんてあってなきがごとしなだけにバッドエンドを予想しましたが、シンケルが死んでくれてやっとそこから安心して見れました。
ほんと観客をも欺くあのエレル嬢に成りすましての馬車での登場は映画史上類を見ないほどのもの、私も見事に騙されました。
土地開拓の話としか前情報入れてなくて、まさかこんなに娯楽性高い作品とは。鑑賞は疲れますがそれだけに見ごたえある大作です。劇場の女性客同様私もマッツ様にメロメロです。
やり遂げたい事と家族
愛する家族を護るには、選択肢が少なくて…
選べないどちらかを1つ選ぶのは残酷だと思うけれど、それが現実なんだろうなぁ。
土地を開拓し終えたけれど、家族はバラバラ。
何のために自分の土地を手にしたのか切ない。
ゼレンスキー大統領も、正義を掲げて国を国土を国民を守るための戦争のはずが、蚊帳の外とは、切なすぎる。
映画の醍醐味から、現実世界に引き戻された。
愛憎渦巻く濃密なドラマ
私生児
原題のデンマーク語のBastardenは、英語のbastardのことで、私生児やロクデナシという意味。邦題の「愛を耕すひと」も英題の「the promised land」もなんか違う感じ。原題の「私生児・ロクデナシ」が一番しっくりくる。
主人公のケーレンは貴族の使用人の子供で、25年間、軍で働き大尉の地位に就く。彼は軍を退いた後、貴族の称号を得るために荒地の開墾を始める。つまり、ケーレンは、自分が私生児であることに劣等感を感じていて、それを、爵位を得ることで埋め合わせようとしている。
敵役のシンケルは生まれながらの貴族でありながら、非情なロクデナシで、自分を権威付けるために「デ」シンケルと自分を呼ぶように命じる。そして、ケーレンが王権の下に自分の土地を開墾することを恐れている。
つまり、二人とも敵対していながら、どちらも欠落感や劣等感を抱えているという意味では同じなのだ。
開墾と敵対の過程で、ケーレンはタタール人の子供を引き取り、逃亡した小作人の妻を愛し、貴族のシンケルのロクデナシ振りを知る。苦労して開墾に成功した後に爵位を与えられるが、それを拒否する。ケーレンは、身分や財産以上に重要なことに気付いたのだ。
壮大なデンマークの荒地の撮影が素晴らしい。セットや衣装なども当時の様子を忍ばせる。マッツ・ミケルセンをはじめ役者陣の演技と役作りにも説得力がある。
是非、映画館で味わってほしい重厚な作品。
マッツ・ミケルセンの最高傑作。
「アナザー・ラウンド」も「ライダーズ・オブ・ジャスティス」も面白かったし、「007」シリーズ、「インディ・ジョーンズ 運命のダイヤル」も見事にエンタメを楽しませてくれたが、今作品はマッツ・ミケルセンの代表作となる大傑作だ。ただし、敵役の地主の人物造形は客を呼ぶエンタメ要素としては仕方なかったのかもしれないが、ちょっと安易ではあるが、それでも全体を通しては許せる範囲だ。ここ何年かでもお目にかかれないレベルの名画だと思う。私は勝手に脳内変換をして、舞台を日本の明治初期・屯田兵で北海道の開拓に従事したドラマとして「高倉健&倍賞千恵子」のコンビ、もう一つ「三船敏郎&新珠三千代」のコンビで想像して楽しんだ。きっとこれらも名画になっただろうと勝手に思いを巡らせて興奮している。
凍てついた心を溶かす純真
18世紀のデンマーク、不毛の荒野(ヒース)が広がるユトランド半島の物語。
アメリカの西部開拓物語は山ほど観てきたが、デンマークの開拓史とは今回初めて出会った。ただ、ハリウッド的な白黒はっきりした勧善懲悪とは趣がかなり異なり、絶望の中にわずかな光を見出し、耐え忍んだ先にようやくほのかな希望を得るのがせいぜい。「不幸でないこと」と「幸福であること」は決して同義ではないが、それでも、多くの人々の人生にとっては、「不幸でないこと」をもってよしとするしかないのも現実だろう。
だからこそ、北欧の厳しい凍てつく冬を乗り越え、春にジャガイモが一つ芽吹き始めると同時に、凍てついたケーレンの心も少し溶かして周りの人々への優しさを見せ始める様を見ている観客たちの心も少し暖まるのだろう。
もちろん物語の主人公はケーレンなのだが、彼を突き動かしているのはアンマイ・ムスの存在だろう。原題である "Bastarden" というデンマーク語の単語は英語の "bastard" に相当する。罵り言葉として使われたりもするが、「私生児」や「雑種(白人と黒人のミックス)」などを意味する語だ。まさにアンマイ・ムスを指したタイトルで、肌の黒い、南方の血が混ざっている遊牧民族出身の彼女は忌み嫌われ、露骨に差別も受けるのだが、真っ直ぐで純粋な心根こそが逆に人々を繋ぐ救いとなっている。
そして、アンマイ・ムスに限らず、身分や性別、人種などによる差別が当然のように横行する時代背景があるにも関わらず、手を携えることで差別を跳ねつけようとする姿が見られることもあったのであろう。あたかも不毛な荒野に果敢に挑み、なんとか収穫を得ようとするかの如く。
羊の解体もお手のものなので、アレをスパッとできるのも納得できてしまう
2024.2.19 字幕 MOVIX京都
2023年のデンマーク&ドイツ&スウェーデン合作の映画(127分、G)
原作はイダ・ジェッセンの小説『Kaptajinen og Ann Barbara』
不毛の地の開拓に命を賭けた退役軍人と奇妙な縁で結ばれる擬似家族を描いたヒューマンドラマ
監督はニコライ・アーセル
脚本はアナス・トマス・イェンセン&ニコライ・アーセル
原題の『Bastarden』は「私生児」、英題の『The Promised Land』は「約束の地」という意味
物語の舞台は、1755年のデンマーク
戦争を終えて役割を解かれた退役軍人のルドヴィ(マッツ・ミケルセン)は、財務省に出向いて、不毛の地の開拓を申し出た
だが、宰相のパウリ(ソレン・メーリング)は無駄だと断罪する
それでも引き下がらないルドヴィは、私財を投げ打って、その事業に取り掛かることになった
デンマークの北部にあるユトランド半島には、ヒースと呼ばれる不毛な土地が広がっていて、国も50年近く開拓を試みるものの、誰もが成し得ていない事業だった
だが、デンマーク王フリゼリク5世の念願でもあり、財務省はルドヴィを派遣することに決めた
ルドヴィは単身その土地に乗り込み、家と倉庫を建てて開拓を始めていく
地元の牧師のアントン(グスタフ・エイン)は協力的で、近くの荘園から逃げた小作人のヨハネス(Morten Hee Anderson)とその妻アン・バーバラ(アマンダ・コリン)を秘密裏に雇わないかと打診する
ルドヴィは二人を雇い、アンには家事係として働いてもらうことになった
だが、ある夜のこと、物音がして倉庫に出向くと、そこには盗みを働くタタール人の少女アンマイ・ムス(メリナ・ハグバーグ、15歳時:Laura Bilgrau Eskild-Jensen)がいた
彼女を捕まえて、集団のところに出向くものの、タタール人を雇うのは犯罪行為だと言われてしまうのである
それでもルドヴィは彼らを雇い入れて、開拓を始めていく
だが、その様子は偵察隊によって、軍裁判官のフレデリック(シモン・べネンビヤーグ)の耳に入ってしまう
さらに、彼の元を逃げ出したヨハネスのこともバレてしまい、ある夜の宴席にして、熱湯炙りの処罰で殺されてしまう
フレデリックの暴挙はそれだけに止まらず、その土地の権利は元からフレデリックのものだったという書類にサインをしろと迫る
ルドヴィは頑なに王の領土だと跳ね返し、それによって、フレデリックの横暴はエスカレートしていくのである
映画は、史実ベースとのことで、ルドヴィもフレデリックも実在の人物とのこと
ルドヴィの方の行方は不明だが、フレデリックが狂人であったことは資料に残されているらしい
ドイツ人入植者やデンマーク人がタタール人を拒むのには色んな理由があると思うが、一番わかりやすいのは宗教なのだと思う
ドイツ人やデンマーク人はキリスト教徒だが、タタール人はムスリムであり、さらに流浪の民としての生活様式にも違いがあった
それだけではない何かがあると思われるが、映画ではそこまでは描かず、不幸を呼ぶ者としての象徴として描かれていた
その後、ルドヴィは家族と目的のどちらを選ぶのかという決断が迫られるものの、彼は後悔の残る判断をしてしまうのである
映画の見どころは、フレデリックの横暴に対抗するシーンで、彼を良く思わない人々が阿吽の呼吸で「計画」を遂行していく様子が描かれている
いとこで一方的に結婚を迫られているエレル(クリスティン・クヤトゥ・ソープ)は、アンの用意したワインをフレデリックに飲ませるし、彼女が中に潜入していることを使用人のリーセ(Nanna Koppel)は黙認し、さらにフレデリックをエレルのいるところまで誘導する役割を担っていた
その直前に使用人のアン(Anna Filippa Hjarne)がフレデリックによって転落死させられていたこともあって、フレデリックの執事のボンドー(Thomas W. Gabrielsson)ですらドン引きしていたりする
そんな中で、フレデリックの狂気だけが突出し、それがアンの復讐へと結びついているのだからすごいことだと思う
ボンドーは財務省にフレデリックの悪事を全て話し、それによってルドヴィは解放されるのだが、それと引き換えにアンが投獄されてしまう
何度も嘆願書を送っても受け入れられず、とうとうコペンハーゲンの職業刑務所へと移送されることが決まった
この時、ルドヴィの功績は王室に認められ、貴族の称号を手に入れることになったのだが、彼はそれらを全て捨てて、ある行動に出た
映画は、そこを詳しくは描かないが、それが却って哀愁を漂わせている気がした
いずれにせよ、かなり重たい話で、良き人も悪しき人も不遇の死を遂げる映画でもあった
動物の殺傷シーンもある(CGらしい)し、なかなか絵作りは強烈なところもあるので、後半はなかなかスプラッターな作りになっている
それでも、前半の鬱屈とした圧政などが不穏さを増長しているので、アンの復讐劇はなかなかスカっとするものがあった
刺してなお足りずからの「アレ」はなかなか強烈で、生きながらえても地獄しか待っていない
ある意味、介錯にも思える部分があるのだが、それを見たエレルの笑顔も秀逸で、その後の執事たちの掌返しもなかなかのものだなあと思った
こんな世界打ちひしがれるわ、ほんとに。。。 しかし素晴らしき大傑作...
全152件中、81~100件目を表示