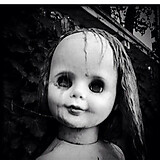哀れなるものたちのレビュー・感想・評価
全673件中、581~600件目を表示
完全に好みが分かれる映画。 物語はすごく面白いけど性描写が多い。 ...
完全に好みが分かれる映画。
物語はすごく面白いけど性描写が多い。
男の人も露わ。
まぁのめり込む時期もあるかもしれないけど。赤ちゃんの頭の中だったらもっと面白い事もたくさんあるだろうに。その内他に目覚めていくのは良かった。
白黒からカラーに変わる辺りはきっとベラの中を映してるんだろう。
全体に魅力的な背景でベラの衣装も素敵だけどあの足を出した服はどうなんだろうね、時代的に。
あのおばあちゃんとの絡みがもっと続くともっと良かった。
貧困や戦争、女性の割礼等、色んなメッセージを込められているんだとは思う。
最後あのダンナの頭の中は博士になるのかなと思おうとしたけどやっぱりそうしたのか…気持ち悪!
自分でも何点つけて良いかわからない映画だった。
エマストーンすごい
後追いの成長。
天才外科医によって蘇生し生まれ変わった女の話。
橋から身投げしたヴィクトリア、橋の下で天才外科医ゴッドに拾われ、お腹にいた胎児の脳を移植され蘇生した体は大人で精神年齢は子供なベラ・バクスターのストーリー。
物心がつき好奇心旺盛なベラ、子供の様に駄々をこねやりたい放題、性に目覚めては盛りのついた動物の如くセックスだったけど…セックス、裸描写は結構あったけどエロさ全然感じずで、どちらかといえば始めましての人とのやりとり、急にビンタ、蹴りあげるみたいな描写の方が笑えた。
月日が経つにつれ片言な言葉や歩き方、考え方などが徐々に成長して、ホントの自分を知り元の家に戻るも、なぜ自殺をしたかが分かり蘇生した場所へ戻ったけど…実験の経過観察はどうなった?
変人天才外科医の「あ~」って唸りながら口からだすあの空気玉は何すか?(笑)
笑っちゃった。
「ラ・ラ・ランド」よりも個人的には「クルエラ」が好き、エマ・ストーンは好きな女優さんだけど、本作は体張って裸体を晒したけど、役やストーリーとはいえ裸体を晒す女優さんって他の作品でもいるけど、晒す=その女優さんが安く見えてしまうのよね個人的に、なので女優さんの裸は見たくない。
作品は飽きずに観れたけどちょっと時間を感じてしまった。
とても不思議な物語
とても不思議な物語。これまでの知識と経験をもとに理解しようとしてはダメです。
何故に?何が?どうなった?とツッコミながらも物語を素直に受け入れましょう。
長編と難解に対峙する大いなる覚悟をもって鑑賞に臨んでください。
それぞれのシーンで映像と音楽、衣裳や動きが魅力的に作られています。そして物語にどんどんと引き込まれていく感じです。
大きなテーマとして『「自己実現と知性」と「本能と性」が人間の根源なのだ』と語りかけてきます。
ラストに向かって「なんですと!」という展開が訪れまして「あぁそうするんだね、それが良いよね」と自分なりにハッピーエンドを想像したのですが遥かに想像を超えてきました。そうくるかぁ。それは思いつかんかった。
映画についてまだまだ未熟だなと思い知らされます。
う〜ん、難しい!
いえ、ストーリーが難しいという意味ではありません。この作品をどう感じるか、どう評価するか、悩みどころです。
エマ・ストーンの演技は幼児脳からだんだん成長していく様を表情やしぐさを通して見事に演じられ主演女優賞で問題なしと思います。
作品全体的に美しい映像と独特の音楽、雰囲気に圧倒されることも間違いありません。
ベラ(エマ・ストーン)が胎児の脳からものすごい勢いで進化していく、その過程で色々な人々と出会いながら影響を受けてある意味成長物語とも言えるこの作品。しかしながら万人に受け入れてもらえるかどうかは???でしょうか。テーマとして性描写は必要かもしれませんが見方によっては『エログロ』と捉えられても仕方ない感もありますよね。
確かにここのレビューをざっとみても女性ウケはすこぶる悪そうです。海外では随所で笑いが起きていたらしいですね?日本人には老若男女笑えないかもしれません!
明るく例えてみましょうか?ゴッドとベラはブラックジャックとピノコ(あっちょんぶりけ!)、再生したばかりのベラはシザーハンズのエドワード、ダンカンは量産されるインド映画に掛け持ちで出てる役者、ゴッドの執事(?)のオバ様はハイジのロッテンマイヤーさん、娼館の主人は『ばるぼら』のママ、ゴッドは空飛ぶグリーンゴブリン(これは例えじゃないか?!)てなところでしょうか?何の脈絡もない話になってきました。
とにかく問題作で色々評価が分かれて賛否両論ではありますがエマ・ストーンさんに3000点、いや3択の女王竹下景子さんに全部でお願いします。(わかんないだろうなあー)
変態監督の冴え。
歪
ファーブル昆虫記やシートン動物記の人間版
フランケンシュタイン、アメリ、マイフェアレディを混ぜた感じ。マッドサイエンティストなんだけど、Lovelyとコメディ(ブラックユーモア)が入っているので、大人のディズニー的な?変態ってバッサリもあり。
寝るかもと思ったけど全然眠くならない。ファンタスティックな映像が-0.5、キレイにまとめ感のあるラストが好みじゃないので-0.2、⭐️4.3なので切り上げて⭐️4.5。
好奇心と自由と寛容
久々に劇場に駆け込みたくなる話題作は期待を裏切らなかった! 驚嘆の世界観、寓話性、芸術性に加え、アイロニックな笑いを誘う楽しさもあり、常識はずれの主人公の言動や行動にはある種の爽快さもある。ただ奇妙奇天烈なだけなく、好奇心を持ち自由に生きることを賞賛する一貫したテーマがある。
映像からたくさんの刺激を受け、たくさんのことを考えたくなるし、物事の表層ではなく根源を見つめさせてくれる。重厚で高次な映画芸術の最高峰だと思う。
勿論、お下劣なところがあるからこそ、より興奮するというのも事実。高尚と下品のバランスが実に丁度いい。
とにかくベラの強烈な生き様に目が行きがちなところで、ベラの父親的存在ゴッドウィン・バクスターについて一つ。クライマックスで彼は肉体を入れ替え不老不死のハッピーエンドに進むのかと思わせるカメラワークののちに、予想を裏切り安らかな死を迎える。私には印象的なシーンの一つであった。
冒険してもいい頃
よくよく考えてみたらエロ漫画のテーマではないですか。
俳優陣の名演に騙されるところでした。
ただ生と性の問題は人生のテーマですので哲学的にも捉えることができそうです。
エマさんとゴッドが素敵な映画でした。
奇妙な世界に没入
ゴシックホラー、SF、童話、実験的アート、シュール・コメディ、ファンタジーといった言葉が思いつくが
感想がうまくまとめられない。
しかし映画自体は演技、演出、音楽、美術が素晴らしく融合しており、奇妙で怖くて美しくてなんとなくクセになりそうな五感に響くゾワゾワする感覚をもたらしてくれた。
登場人物の倫理観やエログロ行為など眉をひそめるようなシーンはあるが、そもそも狂気から始まる超現実的なワンダーランドなので何でもありかと。
よくこのスケールでこの世界観を作り出せたものだと感嘆。モノクロもカラーの切り替えも美しかった。
ラストは優しくて残酷だが収まる所に収まった?と妙に満足。
最初から最後まで謎の没入感に包まれた時間だった。
不適切にもほどがある
娘が××してしまう・・・
ベラ・ルゴシのフランケンシュタイン、
ドラキュラだけでなく、
古今東西、映画の設定で最多である、
比較文化研究。
モンスターと人間、
カッコーとひと、
宇宙人と地球人、
魔法使いとサラリーマン、
昭和と令和、
バービーとケン、
トランプとジョーカー、
クイーンとダイアナ、
king&metoo、
東と西、
北と南、
右と左等々、
we didn't start the fire・・・
前作は女王と側近の、
王室や側近たちのゲスっぷりを、
ギリギリ崖っぷちでレディとして保つのはカメラや照明機材をほとんど使用しないライティング(一部使用してましたね)。
頑なにフィクスのカメラに固執してきたランティモスもワイドレンズ使う使う、
魚眼も辞さないローアングルショットがほとんど。
その理由とは?
ウェス・アンダーソンと
ランティモスは筆致が正確無比、精密機械のようなので、
前作同様下記のようなことがぴったりはまってしまう・・・。
話しは脱線、
カメラフレーミングとその内容を世界地図の図法を例にして。
〇メルカトル図法
地球全体を平面にして描く、ただし極地は正しく描かれない。
カメラをフィクスで真正面から描く。
プロット運び、物語重視、芝居や感情に興味薄。
例えばウェス・アンダーソン。
〇モルワイデ図法
魚眼レンズのように歪んでみえるが、極地も正確。
ワイドレンズを使用してパースを駆使してでも人間の内面を描く。
芝居運び、感情重視、昼メロみたいに突っ走る内容。
ヨルゴス・ランティモスは今まではメルカトル図法が多かったが前回同様、
突っ走る。
機材やフィルムを作品の質に併せて新作してしまうキューブリックや、
タランティーノもこちらに近い。
以上勝手な図法解説は全くのデタラメです。
強調したい所は顕微鏡並みのピント解像度魚眼、ローアングルショット。
どうでもいい所はどうでもいい。
その理由は、すばらしい衣裳、背景に豪奢な部屋、荘厳な建物、盛者必衰、格差表現のアイテムを全部入れ込んで権威や品位を上げたり下げずんだり、
バックアップ担保(嘲笑有)しとくかって感じか?
たまに上からのアングルもあるんだけど、
単なるだだをこねる腐女子は見るに堪えない。
でも、それこそがおもしろいつくりでいつものヨルゴス・ランティモスの手口だ。
船のシークエンスが無駄に長い。
知識を得るおもしろさに気づく、
大事な場面だが、
映画的には退屈なセリフ以外にも、
手法は取れただろうが、
尺を使いたくないのもわかる。
考えてみれば、
シネコンで観る映画ではなく、
アート映画、
無駄に長いは、
あたりまえ。
自由や人権以前の、
脳は単なるハードディスク、
OSはDNAのような、
ケダモノベース、
ギンズバーグ、アーレント、
自由、権利、開放、
ジェンダーベース、
小さなアイデンティティを、
皮膚感覚マッハ50で拾い集めていくような、
ピノキオベース、
サリバン先生が、
手に水を当ててwater!
ヘレン・ケラーベース、
I have seen THE LIGHT !
ジョン・ベルーシベース、
それぞれテーブルを分けて、
テーマ別にも話せるが、
物理的ロジックより、
精神的ロジックより、
感情剥き出し、
いつものランティモスベースで、
なめんなよベース、
または、
ツッコまんかいベースで、
話すのが妥当か。
公房『密会』の溶骨症の少女のように、
ベラのココロを、
グズグズの真っ黒とみるか、
イノセントな真っ白とみるか、
は、
あなたしだい、
いや、
あなたの状況、タイミング、
マインドしだい。
【蛇足】
強調、ピント外しは、
絵作りだけでなく、
実は昨今の役者や物語にも反映されている。
それは100年強の歴史の浅い映画よりも、
400年続く歌舞伎の世界の方が顕著だ。
例えば、
役者でいうと、
16代目ロバート・デ・ニーロとか、
シナリオでいうと、
1シーン、いや1カットを拡張して表現する連獅子の舞とか、
強調する所は前後左右関係なく強調する、
ベスト盤のような、
あるいは、
今日のスーパーゴールのような・・・
400年継続する為の映画のありえない強調と、
映画のあるべき文法を比較して考える。
しらんけど・・。
何をどう判断して、どう理解すべきか難解
自ら命を絶ったベラ。しかし、天才外科医ゴッドウインにより脳を移植されて新生児として蘇生する。ゴッドウインはベラに知識を与え一から育てる。ゴッドウインの閉ざされた屋敷内での生活から更に外部の世界へ好奇心を持つベラ。放蕩者ダンカンの誘いに乗り、外の世界を旅する。ベラは現実世界に衝撃を受けながらも自分がどうあるべきかを模索していく。とあらすじを語れば単純ではありますが、この過程に絡む人物達、世の中の偏見、不条理などが様々あります。ある見方をすれば純真無垢な脳を持つ大人の女性が真の自由と平等を求めた話となります。ある見方では、男性の女性に対して、ある者は純真無垢な女性を束縛したいことを求め、ある者は性欲を満たしたい時にはいつでもできる対象と考えている。という男性の本性を描いているともとれます。またある見方をすれば、女性はどのような境遇になろうともその中で進むべき方向を見出すが、男性は立ち止まり嘆き、絶望してしまうものである。等等様々な感想を持つ作品です。
無垢な脳のベラは映像は白黒、目覚め好奇心が高まるとカラー映像になる演出、また様々な国々での映像、デザインは見事です。エンドロールではなく映像を駆使するのも流石です。
万人受けする作品ではありませんが、ストーリーのモヤモヤ、なぜベラは自殺したのか、移植された脳は誰なのか、ベラは何者なのかまでスッキリさせてくれます。
18禁となっているとはいえ、パリの売春宿でのさまざまなセックスシーンはもう少し短いもので良かったのではと思います。
エマ・ストーンの全てに驚き
橋から飛び降り自殺を図った若い女性のベラは、天才外科医のゴッドウィン・バクスターによって、自分の胎児の脳を移植され生き返った。そして、ベラは貪欲に多くのことを学んでいき、もっと世界を見たいと思うようになった。そして、ベラは弁護士のダンカン・ウェダバーンと駆け落ちし、大陸横断の旅に出た。大人の体で新生児の目線から世界をみるベラは、時代の偏見から解放され、平等と解放を要求し、成長していく、という話。
胎児の脳が生きていたのならそのまま育ててはどうかと思ったけど、目的が違うんだから仕方ないか、と途中から思った。
色々な男を経験するベラだが、さすがR18+だけ有ってなかなかのもんだった。エマ・ストーンの弾けたセックスシーンや幼児がヨタヨタ歩く姿など、彼女の演技全てが驚きだった。
あまりエロく感じなかったのは、愛のあるセックスに見えなかったからだろうと思った。
自殺を図った理由も伏線回収されてたし、最後も良かった。
面白かった。
未来のイヴ
フランケンシュタインの怪物のように甦ったベラ。ベラを甦らせたゴッドはさながら理想の女性像を求めるピグマリオンといったところか。
確かに体は大人の女性、心は赤ん坊で従順、これほど男にとって理想的で都合のいい女性像はないかも。
まだ幼い彼女は好奇心から広い世界を見たいといい、駆け落ち同然で家出をする。そして性的快楽や美食に目覚め、世界のすばらしさを知る。
それを与えてくれるダンカンに依存していたベラだが、世界の醜い部分を知ってショックを受ける。彼女の中でこんな社会を変えたいという気持ちが芽生える。そのためには多くを学びたい、とりあえずそのための生活資金として売春宿で働き始める。そんな彼女に未練たらたらのダンカンは帰国もせずに娼婦館の下で地団駄踏んでおります。
印象的だったのは彼女が娼婦として働きだしたころから見違えるようにきれいで知的な女性に見えたこと。今まではどこか男に依存して生きてきた無知で愚かな女性というイメージがガラッと変わる。自立して革新的な考えに啓発された彼女が本作で一番輝いていた。彼女は男性優位の娼婦館でもそのシステムに疑問を感じて意見したりする。女性に相手を選ばせるべきではないかと。
同僚の女性と社会主義者の集まりに参加するという彼女たちの後ろでなんとまあ無様な姿をさらすダンカン。ダンカン、この野郎。
ベラは純粋無垢なので世間体とか気にしない、売春をやることにも何の躊躇もない。むしろそれを責め立ててる男の方が滑稽に見えてくる。男社会では売春婦、娼婦といえば蔑みの目で見られたりする。でもそれは男目線、結局男が女性に貞淑を求めるのは己の独占欲を満たしたいがために過ぎない。俺だけのものになれ、俺にだけかしづけ、俺以外の男とするな、である。なにか道徳的倫理的に売春を責めているような顔をして結局は自分の独占欲を満たしたいだけなのである。それはダンカンや元旦那の姿を見れば明らか。
本作では観ているものに明らかに不快感を与える性交シーンが延々と描かれる。立派な身なりをした男たちが変態的な行為を要求したり、子供の性教育とばかりに行為を見せたり、そしてそれを真剣にメモる男の子の姿。ここまで男社会をこけおろしてるのもすがすがしいほど。
そして娼婦という仕事がそもそも恥ずかしい仕事なのか蔑まれる仕事なのか、ということにも投げかけてくる。やはり自分も心のどこかで娼婦を見下している。憐れだと、ほかに仕事がないから仕方なくやらざるを得ないのだろうと。そんな考えにも純粋なベラは投げかけてくる。そもそも憐れんでる時点で見下してるのではないかと。そんな風に本作は我々の価値観にもゆさぶりをかけてくる。
本作のタイトル、「哀れなるものたち」の正体は作品の最後の最後に分かる。この男社会を変えるには革新的な外科手術が必要ということなんだろうか。男が追い求める理想的で都合のいい女性像として創られたベラがその男社会を変えていくことを予感させるラストには思わず膝を打ってしまった。
ちなみにエマ・ストーンがエマーソンを読む、しゃれでしょうか。一人で女性史を演じきったのは素晴らしかった。個人的には「バービー」のマーゴット・ロビーと賞レースを競い合ってほしかった。この監督らしいファンタジーでグロテスクな怪作。
「経験」よりも「教育」が大切だと考える自分は、社会的な常識や既成概念に囚われているのだろうか?
確かに、人間の成長には「経験」が必要だし、だからこそ、父親代わりのゴッドは、娘のようなベラを、世界を知るための旅に送り出したのだろう。
実際、ベラは、リスボンで性欲に溺れ、船上で知性と理性を身につけ、アレクサンドリアで慈愛の心に目覚め、バリで勤労と対価を理解し、ロンドンに戻って自分の過去と対峙することによって、自立した女性へと成長していくのである。
だが、ベラの脳が新生児のものであるならば、「経験」よりも「教育」の方が先なのではないかとも思ってしまう。
確かに、自由奔放な彼女の言動には、世の中の常識や既成概念に風穴を開けるような破壊力があり、そこが、本作の面白さにもなっているのだが、それでも、彼女に必要だったのは、「観察者」や「記録者」ではなく、赤ん坊を育てるような「教育者」だったのではないかと思えてしまうのである。
ただ、こういった感想そのものが、常識や既成概念に凝り固まっている証左なのかもしれないが・・・
それから、いくら本能的で根源的な欲求だからといっても、新生児の脳を持つ女性が、強烈な性的欲求を持っているということにも違和感を覚えざるを得なかった。
ただ、これについては、終盤で、蘇生する前のベラが相当に淫乱であった(らしい)ことが明らかになり、蘇生後も、そうした性分が残っていたのだと解釈すれば、なんとなく納得することができた。
それでも、性的な描写が不必要に多かったという印象は拭えないのだが・・・
ラストの、将軍の顛末についても、あれをハッピーエンドとして片付けてしまうことには抵抗感がある。「殺していない」という事実のためだけに、人間としてではなく、ヤギとして「生かし続ける」ことは、単なる「偽善」なのではないかと思えるのである。
その一方で、父親に人体実験の材料にされたという生い立ちを持つゴッドが、人生の最後に、愛する者たちに囲まれながら息を引き取る姿には、素直に胸が熱くなった。エンディングは、このシーンだけで十分だったのではないだろうか?
いずれにしても、いかにもこの監督らしい奇妙奇天烈な物語で、VFXや魚眼レンズを駆使したビジュアルも楽しめるのだが、それでも、話としては、「ロブスター」や「聖なる鹿殺し」の方が面白かったと思えるのである。
これぞ映画!
「女王陛下のお気に入り」で大手配給によるメジャー入りを果たしたギリシャのヨルゴス・ランティモス監督が、今回はサーチライトピクチャーズ配給によってインディ系映画にカムバック!そしてゴリゴリの作家性を出してきました。
やはりこの監督はやばい!笑
フランケンシュタイン、メトロポリスはとても分かりやすいオマージュですが、原作のゴシックホラー調の世界観がヨルゴス・ランティモス監督によってファンタジーなんだけど色使いや衣装がエッヂが効いたデザインになっていてモダンでかっこよかった。
相変わらずの魚眼レンズで普通の画がひとつもない。
巨大なセットといい映画作りをものすごく楽しんでいる感じが伝わってきて、観ているこちらも楽しくなります。
エマ・ストーンはやる子だというのは「女王陛下のお気に入り」時点でわかっていたのだが、マーク・ラファロ演じるダンカンのクズっぷりにやられました。完全にハマり役。
やはりクズキャラが魅力的な映画はいいですね。
パリで浮浪者になってロンドンまでしつこく追いかけて来る執念には参りました。最後ダンカンがどうなったのかとても気になるのだが映画では描かれなかった。
ただし、本作の日本配給は相当頑張っており、これだけエッヂの効いたアート作品(男性器もボカシなし!)を大手のシネコンで観れる日が来るとは思っていなかった。
私が観た109シネマズのほぼ満席の劇場ではエンドロール(これもかなり凝っていた)中も誰も席を立たたなかった。私のように圧倒されていたのか、ララランドのエマ・ストーンを期待して来てとんでもないものを観せられ呆然としていたのかはわかりません笑
性への目覚め、知の目覚め、そして自己解放という精神の大きな旅路をまさに船旅という画で分かる冒険劇に落とし込み、その冒険を渾身の舞台セットと衣装と音楽でデザインし尽くしている。これぞ映画。
ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を獲得したランティモス監督の最高傑作!今年ベスト確定!
なかなかの衝撃作。エマ・ストーンの熱演に拍手!!
妊娠中に自殺した女性。たまたまその新鮮な遺体を手に入れた天才外科医によって蘇らせられる。どこの誰だか分からぬまま彼女は実験体として生きていく。
不自然な動きにおぼつかないしゃべり。
脳に障害を持ってしまったが故かと思いきや、蘇生のためにお腹の胎児の脳を移植していたという衝撃的な設定。
その為か知能の発達は早く、少しずつ言葉も覚えていく。
体は大人であるが、知能が伴っていない為何をしてかすか分からない怖さ。
閉じ込めておきたいが徐々に芽生えていく好奇心。
やがて彼女は旅立っていく。
人間も動物。本能のままに生きるとこうなっていくのかといった感想。
倫理的に容認できない内容も多々あり、決して気持ちのいい作品ではない。
しかし、映画でしか表現できない世界であり、だからこそ映画は面白い!
久しぶりに観るような重厚な作品でした。
あの難しい役柄を見事に演じきったエマ・ストーンには脱帽です。
それにしても、グウェンにグリーンゴブリン、ハルク。
主要人物が揃ってマーベル出演者だった事にビックリでした☺
不協和音の不思議な世界
全673件中、581~600件目を表示