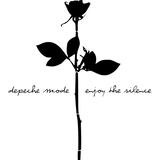哀れなるものたちのレビュー・感想・評価
全673件中、561~580件目を表示
全く先が読めない展開に引き込まれる!
芸術的?奇抜?奇想天外?
フランケンシュタイン?
などなど、どの言葉を当てはめれば良いのか?
迷うストーリーだが、全てかな?
エマ-ストーン主演なので
期待して鑑賞。
妙に美しい背景や
美しく派手な衣装など
見応えあるシーンがありながら、
人体の解剖シーンや過激な性描写シーンなど
見てはいけない様なシーンが多く出てくるので、評価が分かれるかな?
ダンカン男子はリアルに結構いっぱいいるww
すっごくすっごくすっごく好き💕💕💕
そして好き過ぎる作品の場合に、何がそんなに好きなのか上手く言語化出来ないから結果的に箇条書きになってしまう自分の能力の低さ、なんとかなって欲しい……
2024年に入ってから観た映画は割と多めに4.0点台を付けるのが続いていて自分の中での映画の良し悪し基準が少々崩壊気味なのでは⁉️と心配してる部分も少なからずあったけど、コレは間違いなく大好き❤好きだけでなく観てる間中ずっと『次は?次のは?どーなるの??』とワクワクしっぱなしだった(((o(*゚▽゚*)o)))
初めの20分くらいのナニコレ?どーゆー設定??を紐解く時間が進むにつれて感じたのは『あ!オトナ版“初めてのおつかい”!!』と思ってみんなでベラを全力で応援する映画だと思っていたけど、全然違った。トンデモナカッタ。
なんかいろんなものが盛り沢山で楽しませてくれるけど、全体的なバランスはしっかり取れていて『幕の内弁当〜起承転結編〜』みたいな映画だった。
【好き💜ポイント】
・ストーリーそのものが飽きさせずワクワクしっぱなし!
・映像や衣装の天才的な色遣いに圧倒!(特にベラの心の状態が身に着けるものの色に反映されてるのがすごくわかりやすかった💕)
・予告でも何度も流れていたあの象徴的な不協和音が映像と合わせると不協ではなく聞こえてくる不思議!
・本来子供の頃に経験する生(の目覚め)、性の目覚め、自我の目覚め、という成長過程に生じる様々な目覚めポイントがオトナビジュアルなお子ちゃまベラたそが経験することで、デフォルメされているようにみえても実はそれこそが真理なのか?と気付かせてくれた点。
・目覚めシリーズのあとにやってくる『世の中のために何かしなきゃ病』までちゃんと描かれていて納得。
・フュリアスジャンピング!フュリアスジャンピング!フュリアスジャンピング!ww
・あたしの大好物、父娘愛❤ ❤ ❤
・マックスの献身的な愛とダンカンの破滅的な愛
・アルフィーの件とか「ん?コレいる?」となってたけど、起承転結の何度目かの『転』にはやはり必要✨そして綺麗に『結』に繋げてくれて良き😊
登場する男の人たちはいろんな側面からクズなんだけど、単純に『クズ男は要らない!自立した女性として生きて行くの!!』と片付けるわけではなく、結局のところ世の中には男と女しか居ないんだからお互いに支え合ってより良い地球にしましょうよ🌏ってな愛情深いメッセージが1番のお気に入り。
あたし自身が理想とする世界を目指す作品❤ ❤ ❤
でもでも情報量が多かったのも事実!まだ消化仕切れてないからもぉ一回観たい!そしてこの先きっと何度だって観たくなる作品💜
エマが素晴らしい
デフォーのげっぷ??
エマ・ストーンの脱ぎっぷりが破天荒で大胆にも全然セクシーじゃない、そんな衝撃とある意味での落胆は『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』でのスカーレット・ヨハンソン以来か!?
冷たくて無機質な印象のヨルゴス・ランティモスだった筈が壮大に思える世界観はレオス・カラックスの『アネット』のようで奇形の動物なんかはティム・バートン的なテリー・ギリアムなんかも、とにかくらしいようでらしく無いような少し戸惑ってしまう感覚と原作は知らないがあれだけ場面が多いと溜まってんのかランティモス、まぁ監督に全幅の信頼を寄せている女優って説得力だけは大いに。
帰らない?帰れない?まだ居たのかマーク・ラファロの短期間での落ちぶれた姿に笑える、あれはゲップなの?雄叫びのような苦しそうに悶えながらパッって口から気泡みたいに浮遊させるウィレム・デフォーに笑いを堪えるのが大変で、インパクトのある姿が奇妙にも虐待でしか無い父親の教育的実験から悲しい気持ちにも、何だかわからないままでハッピーエンドに無難な着地をしたヨルゴス・ランティモスに対してのコレじゃない感!?
エマ・ストーンの体当たりの演技に脱帽
エマ・ストーン演じるベラ・バクスターの、ある意味成長の物語であり、愛の物語であり、
人生観・死生観にも関わるような、実に深い作品だと感じました。
倫理的・道徳的な観点からは到底ほめられるような作品ではありませんが、
この映画(原作も)は他に類を見ないオリジナリティがありますし、
何よりこういう発想はなかなか生まれないでしょう。
主人公ベラは、体は大人、脳は胎児。でも恐るべきスピードで学習していき、
オープニングとエンディングではまるで別人かと思うくらいの成長を遂げています。
そのように演じているエマ・ストーンの演技がすごいのです。
表情・歩き方・所作など全然違うのですよね。本当にすごいなと思いました。
R18+の理由は、セクシュアルな表現がふんだんに盛り込まれていることと
人間の脳や臓器などもビジュアル化されていますので、その点に留意いただき
鑑賞いただければと思います。
私はヨルゴス・ランティモス監督作品は、本作が初鑑賞ですが、
今までにない衝撃を受けましたので、他の作品も配信で鑑賞しようと思います。
第96回アカデミー賞へのノミネートが11部門というのも納得な作品でした。
面白いと言ってしまっていいものか
原作ありの作品だけど、どうすればこんな世界が思いついたのかと感心する反面、嫌悪感を覚える部分も多々あり終始、好きと嫌いを行ったり来たり。
『ロブスター』でも同じような薄気味悪さを感じたので、おそらく自分は、ヨルゴス・ランティモス監督が好きなんだと思う。
エマ・ストーンは、中盤まであまり美人には見えなかったけれど、終盤に向けて覚醒して、ロンドンへ戻った後の凛とした姿は美しかった。
素晴らしい演技ではあったけど、これで主演女優賞を獲るのは如何なものかとも思ってしまう。
他は『マエストロ』しか観てないからなんともいえないけれど。
プロダクションデザインはすごく素晴らしいし、豪華とチープの混ざった衣装も良い。不安定な世界観に合った不安定な音楽も良い。
将軍の結末も見事な着地だと思う。
ただ、パリのパートは下品でまるまる嫌いなので減点1。
【現代にも通じる深淵テーマ】
奇才ランティモス監督にこの原作ときたら鑑賞前から相当な癖凄作品だと予想はしていたが予想通りの癖凄。
ランティモス監督作品は『聖なる鹿殺し』以来の鑑賞。氏が醸し出す寓話性、19世紀ヴィクトリア時代の建築様式、奇抜なコスチューム&色彩、独特のカメラワークとモノクロを意図的に多用した、他にない世界観を創作。
エマ・ストーンの身体を張ったSEX &マスターベーションシーンに、屍体解剖シーンに、エログロ演出は好みの作風じゃない(良し悪し云々抜きに作品評価よりその印象が際立って残り過ぎる⁉︎)が、封建社会における個人或いは女性の自立の象徴的且つ比喩表現としての描写は案外深淵で終始一貫した普遍的なテーマ性を感じる。
エンディングは少々グロい⁉︎が痛快、メェーー🐐🐐
ひとは「はじめて」を経験していくことで成長していく。そんな「はじめて」はどんなことでも美しく、尊重されるもの。
赤ん坊の脳みそを成人女性に移植する。
この奇妙な設定ひとつだけで、ストーリーがこんなにも豊かに広がっていくとは感心しながら鑑賞していた。
この設定によって、描かれる成長により、ハッとさせられるメッセージが鋭く迫ってくる。そんな瞬間が何度もある。
キャストの演技を含めたトータルのアートディレクションは圧巻で、その世界に吸い込まれていく体験ができる。
グロさのある表現があるが、その部分で敬遠してほしくない。それ以上に美しい映像に溢れている。
ひとは多くの「はじめて」を体験することで成長していくのだということを感じられる作品だった。この作品はそんな「はじめて」の瞬間はどんなことでも美しく尊重されるものだと感じさせてくれる。
それくらいひとには「はじめて」が重要なものであり、それは年齢を問わず重要なものであるのだと学んだ。
女性版フランケンシュタインの自立
女性版フランケンシュタインの怪物が偏見のない目で世界を見て男性が作ったルール・モラルを無視して経験を積み、自分の意志を作っていくお話。自殺した妊婦に胎児の脳を移植して作ったヒロインベラ。
幸福感に包まれた少女時代は世界がおとぎ話のようなフワフワした映像だったのが、だんだん成長していくと現実に即した色合いになっていくのは見事であった。
男が作ったルールを無視して世界を知り、良いことだけでなく不幸も知ることで、大人になった。最後に妊婦が自殺する原因となった妊婦の夫=男性中心主義の権化を倒してベラは自立の道を歩み始める。
良い映画であるけど、ベラに都合の良い世界だな。終わりまで見たとき、ちょっとポリコレ臭を感じた。夫マックスもベラが長い旅行をしている間ずっと待っててくれる都合のよい夫。これが逆だと、男が外で遊んでいる間ずっと家庭で待ってくれる嫁か。長らく男が女に求めていた都合の良い女を逆転した状態だ。男が自分に都合の良い女を求めるなら、女が自分に都合の良い男を求めても問題ない。が、結局自分を抑えて我慢してくれる人が必要なんだなぁ。結局は弱肉強食か。ポリコレは自分が強くなって搾取する側になりたいというのが本音だろう。そう見ると大して正当性があるわけじゃないわ。まあ映画だからいいか、現実だと長い間放置された夫は夫で別の女と付き合うだろうし。
それにしてもいつまでベラが変人で行動が理解しにくくちょっと苛ついたわ。あと、この映画は釈迦が生老病死を知って悟りを開く物語の変形だと思った。
個人的には星4は多すぎだが、星3.5では少ない。星3.8ぐらいにしたい映画だった。
エマちゃーーーーん
クソオモロかったやんけ!
美術とか、衣装とか、エマちゃんの芝居とかも凄えんだけど結局描いてるメッセージの重厚さよ。
上映終わり横席の若い女子が「むず。」って立ち上がって、階段降りてたら前の若者が「宗教とアートと哲学をー」みたいな事言ってたぞ。
そいやここ近くに多摩美有ったわ。
そう言う事なんだろうな、俺も学生時代はトリュフォーとかゴダールとか解ったような顔してマウント取り合ったわw
で、若者よ、そんな難しく考えるな、難しい解らんトコは後回しで構わん!多分君らが知ってる映画だとバービーと同じテーマだぞ。
大人の肉体に無垢な脳味噌、世界を知り自我を知り個を確立する物語だぞ。
映画とする事で観客にも加害性と成長の意義を突きつける、男はやっぱ女性たらばあーなんだな、どの世界でもどの環境でも女を消費し支配したがるんだな。
でもこの映画は優しいな、娘が父や家庭に帰って来てくれるんだ、エマちゃん良い子だな可愛いなー。
シナプス大量形成
成人の体に赤ん坊の脳を持つ女性が、この世界をみて成長する話。
ロンドンブリッジから身投げして亡くなった妊婦の遺体を天才科学者ゴッドが発見し、胎児の脳を移植して蘇らせるという人体実験を行って誕生したベラ。
最初は言葉も拙くよちよち歩きでお漏らしもしてという状態だったけれど…あっ、みつけちゃいましたね〜。
記録係として連れてこられたマックスと結婚?と思ったら、立会人である筈の弁護士ダンカンと冒険旅行へ。
熱烈ジャンプは入り口で、人間の心理や本質を覗き見て、そして哲学を語り考え…って人の汚さや世の中の不条理をみても恐れず戸惑わず何でも欲しがるベラだからこそですね。
終盤はオールドボーイ的復讐か、ゴッドアルフィーかなんて思ったら、まさかのそんなドストレート?それはそれで良いけれどw
白黒混濁でコミカルな描写も結構あるけれど、かわいーとかおもしろーいというよりも、常にどこか不快感がついて回り、それの対象が変化して行く様な感覚があって面白かったけれど、設定以外にぶっ飛んだものが少ないし、落とし方がコント過ぎて、もっと行けるんじゃ?と物足りなさも感じた。
リスボンでベラ達が食べたポルトガル風タルトを頬張りたくなる
18世紀が舞台?のゴシック・ファンタジー・SEX・自分探し映画。
それでいてシュールなSFラブコメ成長物語でもある。
ロンドン、リスボン、アレクサンドリア、パリの無さそうで多分無い所を旅する主人公ベラ。服装から奇天烈で上は肩のフリルが大きなドレス風なのに下はミニスカート風で、他にも無さそうで無い乗り物が美しくて さらに絵画の様な建物や装飾が沢山見れるのも楽しい。
見応えはベラの成長と、ウィレム・デフォー演じるゴッドが語たる過去だろう。
またマーク・ラファロ演じる遊び人弁護士ダンカンのキャラが良くてベラの成長を刺激、加速させる。
R18+の理由は予告編で想像出来るだろうから 一緒に観に行く人は慎重に選ぼう。
最終的に
笑えるツボが違う…?
上映前日にこの作品のCMをみて
オモシロそうだったので観てみました
序盤は
ベラに凄く興味があった
まあ、旅に出て彼女の奔放さ
人間本来の欲望のままに生きるところ
グイグイ引き込まれていったけど…
中盤以降は
眠くはならなかったけど
お腹いっぱい。笑える所もなかった
…退屈な感じ
結婚式で…あ~これでハッピーエンド
終わりかな
と思ったら先があった
そこからもstoryがあった
時間は短いと思うけど長く感じた
最後のころは
音と音楽の爆音に頭が痛くなった
私には笑えるツボが違う…のね
2月2日記
☆再度。観てきました
前回途中で頭が痛くなって
最後がオボロゲだったので…
別に笑う映画ではありませんでした
重くならずライトに描いています
…女性が男性に縛られない社会
というメッセージ
…全世界の
女性が自由に生きられる未来を
ということですね。
最初はわからなかったけど
メッセージはあって無いようなもの
エンタメ作品だから
いかにその…世界観を
楽しめるかどうかですかね
再度、観てよかったです
…でもやっぱり
やぎ人間は笑えないし
性描写が多いのもどうなのかな
評価は変わらないです
哀れなるものたち…とは
★エマストーンの
体を張った演技が見所ですね
…スゴイとしか言い様がありません
♪この作品はファンタジーと
思ってみるとベラが愛しく思える
現代のフランケンシュタインなのか?(的外れ笑)
エマストーンの演技も中々ぶっ飛んでていいね。
頭と身体が噛み合ってない感じが上手い。特に表情とか。
子供が性欲に目覚めちゃうんだから仕方がないよね。あーゆー風になるのは。しかも初めてでもないわけで。
映像もなんか独特な雰囲気を出していると思った。
1番すごいのは、BGMだな。あの何とも言えない不快感というか不安感はいいね。そのままエンドロールに突入したのも良かった。あのエンドロール、秀逸だよ。芸術性を意識したのかな?あーゆーのあんまり好きではないけど、本作にはあってた。
ただちょっと性的な描写がしつこい感じもしたな。あれはもうエロスではなく獣性な色合いに近づいていったような。まあ、男としては拒否反応はしないけど、エロさが少ないのはね、ちょっとなあ。しかし、映倫も通すようになったんだなあ、あーゆーの、と思った。
マークラファロってやっぱハルク役がなければここまで躍進してなかったよなあって思いつつ、演技はちゃんとしてて役にハマってると思った。
最後は、博士と将軍の脳を入れ替えちゃえば良かったのになあ。まあ、流れであの展開は既定路線だけど。
現代のフランケンシュタインとして考えると、社会にある一定のテーゼを主張してる点なんかからもなんかあるのかなあと。こう言うのって大抵メッセージ性あるからね。
まあ、エマストーン、迫真の演技であったのは間違いない。「ゾンビランド」の頃が懐かしいね。
とんでもなくビザールでエクスペリメンタル
ピアスと脇毛
オール50点
物語・芝居・画、"名監督"と呼ばれた方々の作品には、そのどれか(または全て)に特出した才能を感じ取れたのだが、最近のぱっと出監督にはそこまで特出した才能を感じ取れる方が居ないのですよ…
で、本作。
画は一見美しく見えるのだが、カメラアングルが悪い所(カメラマンの問題?)が有り、せっかく美しい背景・セットも脳に焼き付く画…とまでならなくて残念。
エマ・ストーンが寝転がる固定ショットとか、良い画は有ったのですけどね…
そんなエマ・ストーンが脇ツルツル、時代設定的に脇毛は有るべきだと思いますけど。
あと、ピアスの跡も消して欲しかったですね、時代設定的に。
物語は…永い、要らないシーン・要らないセリフが有るよなぁ、中盤以降あくび連発。
ラストのヤギは安易、アイツの脳を女性遺体に移植して強制娼館送り、キモ親父達にナブり倒されて娼館の窓からダイブ…の方が。
どーでも良いのですが、娼館のシーンは五社英雄作品を観てるようでした。
エマ・ストーンの体を張った演技は見ものだが…?
エマ・ストーンが主演のベラ役を務め、体を張った演技で、ベネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞し、アカデミー賞にもノミネートされている話題の作品。ホラー、ミステリー、サスペンス、ファンタジー、エロチシズム、ヒューマンドラマの様々な要素が盛り込まれ、一つのジャンルには、到底、分類できない不思議な作品。
大人の体を持ちながら、胎児の頭脳しか持ち合わせてないベラが、次第に頭脳と体の釣り合いの取れないセクシャル・ディスティニーに目覚めていくシーンは、極めて生々しく描かれている。エマ・ストーンが、全てを曝け出して、ストレートでエログロなセックス・シーンを惜しげもなく披露し、女優魂を見せつけてくる。
また、前半部分は、スクリーンがモノクロで映し出されていたのが、途中からカラーとなる演出は、ベラの自我からの目覚めや心の開放を、演出していたのかもしれない。背景も19世紀のヨーロッパを思わせる街並みの中に、どこか近未来も思わせるような色彩と佇まいが美しく印象に残る作品となった。
物語は、身ごもったベラが自ら命を絶つところから始まる。しかし、風変わりな天才外科医のバクスターによって、胎児の脳を女性に移植され、体は大人、脳は幼児のちぐはぐな女性として蘇る。次第に自我か芽生える中で、バクスターの館から出ることを禁じられていたべラは、「世界を見てみたい」と、弁護士のダンカンとヨーロッパ大陸への逃避行に出かける。その旅で、ベラは純粋な欲望と視線で世界を見渡し、成長していくのだが…。
当初は、フランケンシュタイン的な悲哀の作品かと思いきや、ベラの奥底から突き上げてくる性欲に対する衝動と共に、『女性の自由や解放・平等』がテーマとして根底にあるようだ。「ここまで映していいのか?」というようなシーンも盛り込まれ、海外での各賞を受賞しているが、日本では、賛否両論の作品になるだろう。
出演は、主演のエマ・ストーンの脇を固める、天才外科医のバクスター役をウイリアム・デフォーが演じ、相変わらず怪演振りをみせている。また、逃避行の相手ダンカン役には、『アベンジャーズ』の『ハルク』を演じたマーク・ラファエロが演じたが、エマの相手なら、もう少し若手でも良かったように思った。そして、ベラの婚約者でバクスターの助手をテレビドラマに良く出演している、クリストファ・アボットが務めている。
全673件中、561~580件目を表示