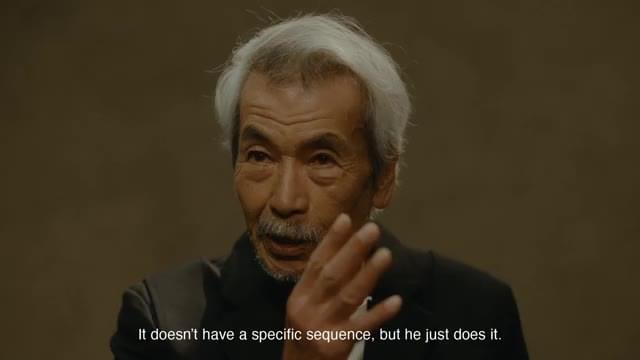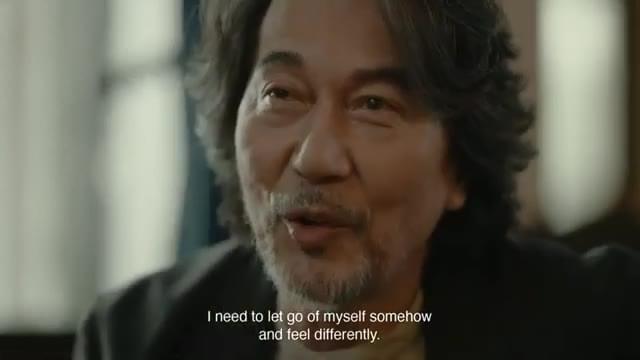PERFECT DAYSのレビュー・感想・評価
全790件中、621~640件目を表示
日常を噛み締める、優しい微笑み
一般人のドキュメンタリーのようで、日常に心揺さぶるような出来事はそう起きないけど、何故か退屈ではなかった。大きな緩急のない中、役所さん演じる主人公の表情を見ているのが微笑ましい。
寡黙で日常生活と仕事を丁寧にこなし、小さな幸せを嚙みしめ、自然の木々と人を愛している主人公をとても愛しく思った。
裕福で恋人や家族や友人に囲まれ楽しく過ごしていれば皆幸せと定義するのは、とんだ勘違いでしょう。主人公の生き様もきっと幸せのかたちだから。
本当の豊かさとは
期待を裏切らない素晴らしい映画だった。
役所広司演じるのは、大都会東京の片隅で、トイレ清掃員として暮らす無口な男。毎朝夜明け前に目覚める規則正しい生活。お気に入りの音楽をカセットテープで聴きながら車を走らせ、キビキビ仕事をこなした後は、銭湯で汗を流し、行きつけの地下街の飲み屋で晩酌をし、文庫本を読みながら眠りにつく。ただその繰り返し。小さな苗木を育てること、お昼休憩のときに木漏れ日の写真を撮ることをささやかな楽しみとして、生活を送っている。
日々の小さな喜びや感動を大事にするその姿は、いわゆる孤独とは無縁のように見え、心の豊かさとはこういうことなんだろうと感じさせてくれる。
自分一人で完結しそのサイクルの中で安定した、正に完璧な毎日だ。
その一方で、他者との関わりが、その「完璧さ」に波風を立てることがある。不確実性が生み出すストレス、心のザワツキ、消せない過去の記憶、憧れや愛情、喜びと悲しみ。
生きていく上でそれらを避けては通れないこと、個人の世界から一歩踏み出して、人とつながりを持つことの重要性を示唆しているのかなと思った。
毎日眠るときに、夢が映像化されるのが印象的だ。白黒の残像、記憶の断片。良い目覚めもあればそうでない日もある。こうやって1日1日リセットをしながら、日々の営みを繰り返していく。決して表には出さないけど、心の奥底に積み重なり、今もなお背負い続けているものがあるんだろう。
単調な映画なんだけど、驚くほど感情が揺さぶられた。
願わくば、こういう大人になりたい。
ほんの一瞬の笑顔
そもそも、「PERFECT DAYS」という曲を知らなかった。他の60年代ポップスは結構聴いてきたのに、この曲は完全にノーマーク。歌っているルー・リードという歌手も初めて知った。それどころか、主人公の清掃員がカセットテープで流すコレクションを一曲も知らないという事実。
自分の思い出と交錯できない事実が結構ハンディキャップで、主人公に今一つ感情移入が
できない。
ところが、清掃員演じる役所広司の圧巻の演技で、いともたやすくマイナスがプラスに転じる。
来る日も来る日も、公衆トイレ、銭湯、コインランドリー、写真屋(趣味のカメラのフイルム入替)、行きつけの飲み屋の繰返し。飲むものはいつもレモンサワー、ランチはいつもコンビニのサンドイッチ。
変わり映えもなく、一点の狂いもない毎日。なのに愚痴なし、しかめっ面なし、でもきちんと笑顔あり。
これは、フェイスブックやインスタで、自分の日常はドラマチックと常にアップする輩たちに向けた、完全なるアンチテーゼなのか?。見せる必要もない自分の日常をイイネで飾り立てた輩たちに向けた強烈なメッセージなのか?
いや、おそらくそんなたいそうなものではないような気がする。よく言われる幸せの在り処とも違う気がする。
人は生きてる限り生活し続けるってことかな。働いて食べて寝て、笑顔は絶やさなくてもいいから、笑顔になれる一瞬があればいい。そんなとこかな。
もしかしたら、日本人監督が描くともっとメッセージ性が浮き出るのかもしれない。だが、そこはヴィム・ベンダース。そうは問屋を下さないはず。
と思いきや、「すばらしき世界」とはまた一味違う、役所広司の一瞬の笑顔がそこにはあった。
ほんの一瞬の笑顔が、ダイヤモンドに見えた。
おっさん理想の日々
平山の日常の所作を繰り返すショットが誠に映画的で、さすがにベンダースは上手いと今さらながら唸る。
なぜか主人公は「底辺の仕事をする貧乏な老人」であるという勘違いをよく目にするが、そんなことはない。裕福な家庭に育つも親と絶縁し、まともな仕事でそこそこ稼ぎ結構浪費家でもある50代後半くらいの設定。
寡黙ではあるものの表情は豊かで趣味は豊富。女の子にチューされればにやけるし、バイトがバックレたらプンスカ怒る。惚れた女性(石川さゆり)の前ではめちゃくちゃ饒舌だし、初対面の男(三浦友和)に積極的に絡んでいったりもする。
寡黙だがよく笑う主人公。これを役所広司はアンミカの「白は200色あんねん」を地で行くように、繊細に笑いの機微を表現する。本当に素晴らしい演技。
平山が車内のカセットデッキで聴く音楽はいかにもベンダース。金延幸子「青い魚」がかかったのは嬉しい驚き。同僚の友達の女の子がパティ・スミスを好きになるのはありきたりなシーケンスかもしれないが、オッサン的には何か嬉しい。カセットを鉛筆でクルクル回したり、フィルムを現像したり、毎日居酒屋で一杯だけ飲んだり、おっさんが落ち着くショットは数多い。
とにかく、多くのおっさんにとっては理想的な日常が描かれたファンタジックな映画。公共トイレを掃除しているだけで社会問題をテーマにしていると思い込む諸兄はご注意を。
あと、役所広司と三浦友和の絡みは最高ですね。今撮ってくれてよかった。
公共トイレの清掃員を生業としている中年男性の平山。 平山の毎日はだ...
公共トイレの清掃員を生業としている中年男性の平山。
平山の毎日はだいたいがパターン化されているが、それでも毎朝、新しい気持ちで生活を営んでいる。
人によっては、取るに足りない人生に思うだろうし、トイレの清掃員という仕事は社会の底辺の仕事と思う人も居るだろう。
全く世界を意に介さず、独自の世界を形成する平山の生き様に、少し重なる部分があって、少ない台詞や少ない他人との関わりが愛おしくて、ラストに流れる『Feeling Good』で泣きそうになった。
私も業種は違うが、低所得なエッセンシャルワークに就いている。
たとえコロナで世界が激震していても、仕事を休めず社会で働いていたが、今だに、同じ仕事を、どこかで誰かと繋がることもあろうと思いながら続けている。
私も平山の言う、沢山の世界の1つなんだ…と思ったら、まるで人生を肯定されているようで、嬉しいことも辛いことも起こるけど、それでもこれからも生きることを続けていこうと思えました。
こんな、センスの良い、素敵な作品を世に送り出してくれたヴィム・ヴェンダース監督に感謝します。
淡々とした日を過ごしていく、同じ暮らしの繰り返し
人生を美しく生きるのは自分次第
古く汚いアパートのきれいに片付いた部屋に住む平山の日常を描く。何の事件も起きない。それだけなのになぜ引き込まれるのだろう。
まさに人間は内面で勝負だ。いい家に住んでいてもSNSで人を攻撃しているだけの人もいるだろうし。
役所さんのヘアスタイルが素敵なのでアデランスかと思ったら銭湯で洗髪していた。髪が豊かでうらやましい。
三浦友和。なんでいつまでも声が若いんだ。二人のシーンは近年まれに見る優れものではないでしょうか。
住んでいるのが下町なのに、掃除するのが渋谷の特殊なおしゃれトイレだったり、実は富裕層の勘当された息子っぽかったり、思春期の姪が信じられないほどいい子だったり、多少の嘘くささは漂う。しかし見ていて気持ちのよい、人生を大切にしよう、美しく生きたいと素直に思える映画だった。
あんまり好きではない。
好きか嫌いかで言うと嫌いだけど、
ヴィムベンダースがナチュラルに東京と撮ってるのがすごいと思う。
小津安二郎へのオマージュが言及されていている今作。
小津映画数本しか観れていないけれど、ものすごい完成度の映像だと思う同時に日本的家族感やお節介的人情味や男の身勝手さがやや苦手な私としては、
日本の日本家父長制的な家族を良いものとしては撮ってないと思うと言っていた黒澤清の言葉を思い出すまで(たぶん東京映画祭)、だーいぶモヤモヤしながら居心地の悪い気分で観てたが
この映画ストーリー、人物を“良いもの”として観なくてもいいと思ってから安心して観ることができた。
主人公のトイレ掃除のおじさんは
質素な生活をしているけど、結局まぁまぁ裕福な実家をもつ人がやっている選択的貧乏であって
きっとこの人のお父さんが死んだら死ぬまで困らない金額が口座に入るんだろうな。と思った。
食うや食わずの切迫した人とは違うから、
あの若者が飛んでシフトパンパンになったとたんイラつき出すのは自分の優雅な質素生活が乱された怒りだと思う。
同じく役所広司主演の「すばらしき世界」は、ほんとうの本当にぎりぎりの生活に追い詰められたおじさんを描いていて、同じ質素な部屋に住む日本人のおじさん同じ役者を使って撮った作品としては、話は雲泥の差があると思う。
結局この映画はおじさんが気持ちよくなる作品なんじゃないかなーっと思ってしまったのが私の感想です。
そう思うと、オタールイオセリアーニ監督の作品は
満ち足りたように見える裕福な人物と何も持たず貧乏ではあるがある種の優雅さがあるような人物がグラデーションでクロスしていく描写が多いけど、嫌味がなくとても美しいのはなんでだろう。ただの好みの問題もあると思うけど、違いはなんだろうと思った。
「素敵な歌と舟はゆく」はけっこうそこが主題な気がするのでまた見直してたい。
人生はPerfectでなくても、 Perfectな日々を送ろうと思った。
いつトミー・リー・ジョーンズが出てくるのかと思って観てた。エンドロールの後に、あの自販機の中から出てきたら面白かったのになぁ。(冗談です)
ひとつひとつのエピソードや登場人物、時々インサートされるモノクロームの夢、どれもがつながっていくわけでない。なのにどうしてこんなに惹きつけられるんだろう。
いっそもっと何も起こらなくてもよかったと思うくらいいつまでも観ていられる。(若い人たちには物足りないのかな)
役所広司演じる平山という男のバックグラウンドは想像するしかないけれども、観ている自分も平山と同じ気持ちになって微笑んだり、ちょっと嬉しくなったり、泣いたりしてしまう。
役所広司さんは唯一無二の俳優だなぁ。
例えばこの役を、三浦友和が演じてたら。
中井貴一だったら、佐藤浩一だったら、真田広之、渡辺謙、小林薫、、。過去に遡って、笠智衆、志村喬、三船敏郎、渥美清、高倉健、、、。
いろいろ想像しても役所広司さん以外に考えられない。(高倉健、いいかな。いや洋楽似合わないな。)
大谷効果で日本の人気が上がってるということでなくても、作品も含めてアカデミー賞は間違いない。
と期待したい。
帰りに幸田文の「木」とパトリシア・ハイスミスの「11の物語」買ってきた。持ってるのに。
もちろんBOSSも。
非常に単調ながら、何故か観ていられる。
主役 役所広司
ヴィム・ヴェンダースによる東京映像詩
今の私には合わなかったですね
全790件中、621~640件目を表示