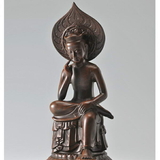エドガルド・モルターラ ある少年の数奇な運命のレビュー・感想・評価
全55件中、1~20件目を表示
ゆったりした語り口で語られる、不条理なまでに翻弄された人生の物語
1858年にボローニャで起きた事件を題材にした歴史劇である。仲睦まじいユダヤ人一家に育つ少年がとある理由によって親元から引き離され、カトリック教徒としての生活を余儀なくされる。ストーリーの柱には、現代でもあらゆる争い事の火種となりうる「宗教上の違い」があり、教義のため、宗教上の権威のために是が非でも事を為そうとする、優しい顔をした非情さが本作を不気味な闇で覆う。その一方で、これはいたいけな少年の瞳を通じた年代記でもあるのだ。己の理解がまったく追いつかぬところで全てが目まぐるしく移ろうお伽話のような感触すら持ち、彼は数十年のうちに大きな精神的変容を辿ることになる。ベロッキオ監督曰く、この事件はイタリアにとって重要な歴史的瞬間だったとのこと。なるほど、描かれるのは、宗教的支配が近代史のうねりによって変わりゆく過渡期。ゆったりした語り口ながら、当時を生きたあらゆる人々にとっての激動の物語なのだ。
最近、親族の納骨があり翌日、親族のお葬式がカトリック教会で会った。...
最近、親族の納骨があり翌日、親族のお葬式がカトリック教会で会った。
全く違う様相ではあるが若干の違和感を感じるも平然とどちらも参列した。
ほとんどの日本人がそうであるように宗教には寛大というか「無関心ではないがそのときそのときの都合によって神様を代えれる多様性を持ち合わせている」と良いように思ってしまう。
この映画は全くそうではない。
母親の死に際で改心させようとする息子にがんとして断る母親。
子どもだったから長い年月を経て改心できたのだろうし、他の家族は家族を連れ去られた悲劇を背負い生きてきたのだから改心するという選択肢はなかったに違いないし。
ただ、つれさられたエドガルドには何の罪もない。権力者のエゴに巻込まれただけなのに。
母と死別した後もキリスト教宣教師として立派に生きられたという史実もこれまた感動の余韻を残した。
子どもから改心するまでの10年間が描かれていなかったのは残念だった。それを描くと3時間以上の大作になるかも。
それにしても司教のエルガルドに靴をなめさせたり地面に舌で十字を書かせたり、完全なるハラスメントである。実際にはないと思うが
今風で言うなれば宗教ハラスメント、宗ハラである。
権力者のいやな一面でメチャクチャ腹立たしく思ったシーン。
これも史実に基づいていたのかなあ。多分、そやろなあ。知らんけど。
胸が張り裂けそうな思いです
理不尽!
だから宗教は信じないのよ!と思わせるお手本のような話。全然関係ないけど直前に見た悪い子バビーの最後の方で世界の宗教をものすごい単純化して説明してたのは秀逸だったな。実際それくらいしょうもなくて単純なことで争ってるんだよねー。さてそれが実話だとしてもこれは映画です。薄ぼんやりと事実を並べてもダメなんだよ。社会の受け止め方とか家族の活動とかを描きたいのかと思いきや、途中からパタっと家族が出てこなくなって、あっという間に10年後みたいな乱暴な流れのあとにすっかりカトリックへ帰属しちゃったエドガルドくん、おいおい社会側を描かないなら心情を描きなさいよ、中途半端な教皇の罪悪感感じてなくはないんです描写とか、何もかもが薄ぼんやり。題材は強烈なんだからどこかに焦点絞って描けばよかったんじゃないかしら。とにかく薄ぼんやり進んで折れるように終わった映画。イタリア映画の現在地だなこれは。
宗教が絆を断つものであってはならないと思う。
理不尽極まりなくて、腹立たしい。
この映画の不思議な点は、エドガルドの目線が殆どないこと。大人になっても彼は帰らない。これを、大概の人が洗脳もしくは、ストックホルム症候群と思うのだろうけど、親の元でユダヤ教であれば、洗脳ではないのかというと、これもわからない。
そして、彼は成人した後も、司祭として従事した。これは彼の判断だったのではないのか?その点の取材は明かされない。彼が明かさなかったのか、またも教会側の力が働いたのか、これも解らない。
理解はできないけど、彼の生きるための選択の一つということはわかる。でもそれは、誰でもそうなのではないだろうか。
理不尽でもブラック企業で社畜になる人も生きる為だ。だからこそ、雇い主や権力側の人は、思慮深い人格者であってほしい。
これを観てて思ったのは、近年の虐待に対する児相や警察などの対応の鈍さも、この視点で考えると頷ける。罷り間違えば連れ去りになるのだから。
警察だって権力組織だもの、一見すると正しく見える。それなら、この時代の教皇配下の警察のする事であれば、やはり抵抗するのは難しいということになると思う。
時代によって、立場によって正しいは変化し続けるけど、本当の意味での、宗教の持つ対話と寛容さを今後は実践してほしい。
たったそれだけで
怖い映画だった
家庭に持ち込まれた宗教戦争
永遠の宗教二世問題
1858年のイタリア。ユダヤ教一家の7歳の息子を「この子は赤ん坊の時に洗礼を受けたキリスト教徒だ」とローマ教皇が拉致したという歴史的事実に基づく物語です。現在からさほど遠からぬ時代にこんな横暴が許されていた事にまず驚き、イタリアの人々に及ぼしていた教皇の権力は斯くも甚大だったのかと知りました。でも、本作の訴えを本当に理解するには、イタリアの歴史とキリスト教・ユダヤ教の背景を知っていなくてはならないんだろうな。と、またまた自分の不勉強を恥じる。
「でも・・」
と、不信心な僕は思います。無責任な事を言ってはいけないし、教皇の行為は許されないのですが、子供に何を信仰させるのかと綱引きする姿は、現在の日本で取り上げられている「宗教二世問題」にそのまま被さって僕の目には映りました。
人間らしい
権力者の言動に嫌悪感を感じた。
どうして?生きてる内は答えがでないコトでは
24-053
宗教めんどい。
教会/世俗のイタリアの断裂線を描く妙
熟練の作品
自由と平等を推し進める民衆と、それに対抗するカトリック教会。イタリア統一に一役買ったのは、広場の銅像になるような立派な英雄ではなく、無学な家政婦がきっかけだったという不合理で残酷な実話。
冒頭。ヘブライ語で赤子に祈りを捧げる父母。赤子の瞳は遠くを見通すように澄んでいて、まるで飼い葉桶に生まれ落ちた赤子のように特別な存在だった。それを覗き見る家政婦の視線は、その後の数奇な運命を示唆する重要なシーンだった。
ユダヤ人迫害、権力乱用というカトリックの傲慢さと凋落をあぶり出しながら、マルコ・ベロッキオは犠牲者の少年の痛みを現代社会に提示してくれた。
かくれんぼ遊びが家庭と教会で二度描かれる。イタリア統一という歴史の中で隠れてしまいそうなエドガルド。彼自身も自分がどこに居るのか分からない。
そんな彼を置き去りにせず、「あなたはどこにいるのか。どこにいようと我々はちゃんと見つけ出しますよ」とマルコ・ベロッキオの声が聞こえるようだった。
印象的なシーンは数多く。母のスカートの中、寝台のシーツの中、教皇の法衣の中、母との別れ。たった一枚の布切れが、少年の残酷な断絶を浮かび上がらせていた。
そして十字架から釘を抜いてキリストを解放するシーン。キリストは〝受難の象徴〟いばらの冠を捨てて歩いていく。
ユダヤ人でありながらユダヤ人に殺されたキリスト。キリストが磔になることで信仰者は罪から解放されるのに、キリストを十字架に掛けた責任はユダヤ人が負うべきだというのなら、ユダヤ人の僕がキリストを解放してあげるよ。
現実では宗教の和解は困難だが、少年の無垢な夢が、同腹の兄弟(ユダヤ教とキリスト教)をなんなく和合させたみたいで面白かった。
全55件中、1~20件目を表示