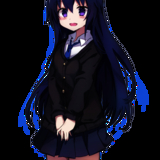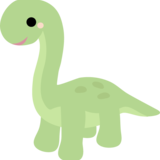関心領域のレビュー・感想・評価
全571件中、121~140件目を表示
セカンドオピニオンを
こわい
「ナチスの残虐行為の断罪」ではない
この映画の核心にあるテーマは、我々の「関心領域」と「無関心領域」の対比だ。舞台となるアウシュヴィッツ収容所の隣にある豪邸は、実際には家族にとって壮絶な現実から切り離された場所だ。ヘートヴィヒと彼女の家族は、ナチス体制によって与えられた豪華な生活に浸りながら、収容所での恐怖や苦しみを「関心領域」として扱っていない。この態度は、現代における私たちの無関心にも通じるものがある。
この映画は、単にナチスの残虐行為やその恩恵に浴した人々を断罪するものではなく、我々の「無関心」を批判している。戦争や人道的危機、気候変動といった地球規模の問題に対して、私たちは知識を持っていても、それが日常生活に直接影響を与えない限り、行動を起こすことは少ない。この「無関心領域」の存在が、映画を通して浮き彫りにされ、我々の社会的・倫理的責任を問いかけている。
「ホロコーストを知っている」ことが重要ではなく、我々が自身の「無関心」を直視し、世界の問題に対する意識を持ち行動することの必要性を訴えている。そのように思えてならない。
全文はブログ「地政学への知性」でご覧ください。
現在の関心領域
アウシュヴィッツの絶滅収容所から塀一枚隔てた豪奢な家で穏やかに暮らすルドルフ・ヘス所長一家の日常を淡々と描いた皮肉で恐ろしいホーム・ドラマです。収容所で起きている事は全く描かれず、収容者の姿すら殆ど見られません。ただ、塀の向こうに見える煙突からは止むことなく煙が立ち上り、銃声や人の悲鳴と思える「音」が微かに聞こえるだけなのです。家に集まるドイツ婦人らは、収容ユダヤ人から巻き上げたドレスや宝飾の品定めに余念がありません。
収容者の中から選んだのであろうユダヤ人家政婦に対し「夫があなたを灰にして辺りに撒き散らすから」と冷静に言ってのける夫人の穏やかな暮らしの直ぐ隣で進んでいる現実に対する想像力を観る者は試されます。安易な手持ちカメラは用いず、構図を決めた固定カメラの映像が冷ややかな美しさを湛えます。2月頃、本作の上映情報が出た時、「『関心領域』なんて日本語として座りの悪いタイトルだなぁ」と思ったのですが、今となってみればこれ以上にない選択に思えます。
本作を観ていると、文字通りの塀で閉鎖され「天井のない監獄」と称されるガザで進行中の現実を嫌でも連想するのですが、現ドイツ政府は完全にイスラエル側に立ち、パレスチナ問題を塀の向こうの「関心領域外」としている事を一体どうとらえたらよいのでしょう。
この映画を観て重い心を引きずったまま市の図書館に寄ったところ、本作の主人公のひとりでもあるルドルフ・ヘスが書き残した『アウシュヴィッツ収容所』を見つけました。彼が戦後に本を書いていたなんて知らなかったので、早速読み始めました。でも、「なぜ彼は?」を知ろうとしても、アイヒマンの場合と同様に凡庸な答えしか得られないのだろうな。
終始作中に蔓延する不快感こそ無関心の罰
作中で描かれるのは、ナチス幹部の一族の華麗なる生活である。ホロコーストの惨劇は少しも描かれない。それでいて、ホロコーストの悲劇を、ナチスの罪を、民主主義の欠陥を、なんと克明に描いた作品であろうか。
終始感じる不快感の正体は音だ。ヘス一族の何ら変哲のない生活の中に、人の咽び泣く音、無機質な機械音、不穏な爆発音が止めどなく流れ同化しているのだ。
不快である。不穏である。充満しているのだ。
かのホロコーストの惨劇の最中、当時の人々は、ヒトラーに手を掲げ忠誠を叫んでいた人々は、どんな気持ちだったのか。積極的にナチスを指示し、ユダヤ人に蔑みの視線を向けていたのか。当時最も洗礼された民主主義の体系を持っていたドイツでなぜ史上最悪の指導者が誕生したのか。
無関心である。このことはポピュリズムが蔓延する現代に間違いなく通づる教訓を与えてくれるはずだ。
終始背筋が凍るばかりだった。映画館で見るべき映画とはこう言うものではないだろうか。
関心なのか無関心なのか
最初はBGMのように流れる不穏な雑音。
ああ、多分それがあの音なのだろうと
耳を研ぎ澄ませていると、
だんだんと輪郭が明確になってくる。
銃声、怒号、悲鳴、煙、そして臭い。
奥様は、ユダヤ人が着ていた高級毛皮を身にまとい、
ポケットから出てきた口紅をさす。
赤ちゃんは泣き止まず、
妹は夢遊病を患い、
男の子たちは、抜かれた金歯を宝物にしている。
壁の向こうで何が起きているのか、
知っていて平然を装う。
時折「無関心」でいられなくなり、
壁の向こうの子どもに向かって
「次はしくじるなよ」とつぶやく。
そりゃ、壊れますよ、精神が。
最後は現代のアウシュビッツ収容所が映し出され
淡々と、機械的に、施設の中を掃除をする人たち。
ガラス越しに見える大量の靴の山には、
まるで関心がないようです。
まさに、あななたちのことですよ、
ということなんですよね。
壁一枚隔てて描かれる、天国と地獄
1945年、アウシュビッツ強制収容所の隣。壁一枚を隔てた家で、幸せに暮らすヘス一家。壁の向こうからは、昼夜を問わず聞こえるホロコーストの“音”。しかし、彼らはその音を物ともせずに、“無関心”の果て、豊かな“楽園”を築き上げていた。
本作を鑑賞する前に、事前予習として2022年のドイツによるテレビ映画『ヒトラーのための虐殺会議』を鑑賞したが、本作を理解する上で非常に役立った。ナチス親衛隊や事務次官らが、如何に効率良くユダヤ人を“処理”するかについて議論を交わす作品なのだが、本作のアウシュビッツ強制収容所はまさにその答えとなった舞台。ガスで一度に400〜500人を毒殺し、そのまま焼却炉として遺体を焼却するのだ。
本作中では、ルドルフと役人達との設計図を用いた会話により、より具体的にその内容が語られている。炉を左右に分ける事で、片方で焼却処理をし、もう片方では炉の冷却と灰となった骨の排出が行われる。焼却と冷却を交互に繰り返す事で、一定のペースで決まった人数を処理し続けるのだ。焼却炉が稼働する様子は、絶えず収容所の煙突から立ち込める煙で表現される。
そう、本作では強制収容所で行われる全ての行為が映像では一切示されない。地獄の様子は、“音”によって表現される。それは、平穏なヘス一家の生活の中に、常に流れ続ける。
しかし、彼らに収容所にいるユダヤ人達の“痛み”や“叫び”は届いていない。
本作を通して1番に感じたのは、【好きの反対は嫌いじゃなく“無関心”】とはよく言ったものだなという事。“嫌い”という感情は相手に対するベクトルが向いているが、“無関心”はそもそもベクトルすら存在していない。それはまさしく、本作におけるヘス一家の生活態度そのものだ。
収容所とヘス家の間にあるのは、僅か一枚のコンクリート製の壁。そんな壁一枚隔てただけの場所であるはずなのに、そこに自分達の楽園を築き、何不自由ない生活を送っている。壁一枚隔てさえすれば、その向こうにどんな地獄が存在しようと、築き上げた楽園での生活を謳歌出来てしまう人間の恐ろしさ。そして、一度手にしたその悦楽から離れる事は出来ないのだ。
そうしたヘス一家の歪んだ生活を、色彩や左右対称の構図等、拘りを持った画面構成で鮮やかに表現してみせる。
冒頭のタイトルシーンは、最初こそ白く光り輝いていた『THE ZONE OF INTEREST』の文字が、次第に輝きを失って燻んで行き、やがて消えて行く。その様子は、まさしくヘス一家の収容所内への“関心が薄れて行く”様を表しているかのよう。
また、ヘス家の面々が穏やかな日常を過ごすシーンは、ポスタービジュアルにあるように彼らは多くの場面で画面の中央にいる。それはまるで、「自分達が世界の中心である」という彼らの傲慢な心理を映したかのようだ。しかし、そんなシーンのどれもこれもが色彩豊かで美しく、穏やかに映るというのが皮肉。まさか、鮮やかな色彩や計算された画面構成に一種の嫌悪感を抱く日が来るとは思わなかった。
音楽も非常に大きな役割を果たしており、暗闇にゴォォと不気味に響く様子は、まるでホラー映画のよう。この曲は要所要所で耳にする事になるが、終盤ではあの音の奥に収容所のユダヤ人達の怨嗟の声すら聞こえた気がした。
ヘス一家の中でも最も醜悪に描かれているのが、ルドルフの妻ヘートヴィヒ。ユダヤ人から接収した衣服やダイヤを当たり前の如く身に付け、夫がアウシュビッツ強制収容所の所長である事から“アウシュビッツの女王”と呼ばれている。彼女は自分の母を家に招き、拘って作り上げた家庭菜園を見せて、自分が今どれだけ満たされているかを見せる。
しかし、そんな生活の裏で、夜中まで行われる収容所の“焼却処理”。夜空を真っ赤に染め上げる異様な光景は、ヘートヴィヒの母を家から離れさせる。翌朝、ヘートヴィヒが見つけた母の書き置きに何が書かれていたのかは何となく察しが付くが、彼女は母が黙って家を離れた事に不満を漏らし、使用人に当たり散らす。無関心の極地に達した彼女には、最早自らの生活の歪さに気付く事は出来ないのだろう。
ルドルフの転属によって住居を変えねばならないかもしれないと知った彼女の台詞は強烈だった。
「ここが私の楽園なの。昔からの夢だったの。ここを離れるくらいなら、あなた一人で出て行って。」
しかし、私が作中最も恐怖し、同時に悲しさで一杯になったのは、幼い次男のある日の姿だ。収容所内のユダヤ人達の為、夜中に林檎を埋め込むレジスタンスの少女の姿が映し出されていたが、その林檎が発端となって収容者が暴れ、看守によって鎮圧される。
その“声”を、その“音”を聞いた彼は、窓ガラスに向かって一言。
「二度とするなよ。」
まるで親が子供を躾けるかのよう。幼い彼にとっては、今生きている場所こそが世界の全て。親や周囲がユダヤ人を差別し出した後の世界に生まれた彼にとっては、それはごく自然な発想、自然と漏れた言葉だったのだろう。だからこそ、それは途轍もなく恐ろしく、同時にあまりにも悲しい。“人間の悪意の再生産”が詰まっているこのシーンは、間違いなく本作の白眉だろう。
終盤、ヘートヴィヒの要望を聞き入れ、ルドルフは一人転属地で過ごす。再びアウシュビッツに戻れる事になった彼は、階段を降りる際に嘔吐し、現代のアウシュビッツの博物館の姿を見る。展示されている積み上げられた収容者達の履き物や、当時の品々を。
パンフレットによれば、あれは監督にとって“未来の今”なのだという。彼らの行為の果てに今がある。我々はそれをちゃんと見つめているのか?と。
何故、あの瞬間ルドルフは嘔吐したのか。もしかすると、あの嘔吐は地獄の隣にある楽園から離れた事で、僅かばかりでも良心を取り戻したルドルフの本能が告げたSOSのサインだったのかもしれない。しかし、彼は再びあそこに戻る。そして、あの生活が始まるのだ。
アウシュビッツのホロコーストは確かに過去の出来事だ。しかし、監督の言うように、我々は常にそうなる可能性を秘めているはずだ。いや、既になっているのかもしれない。壁一枚隔てただけで、地獄の隣に楽園を見たヘス一家のように。
また、ヘス一家の生活は“誰かの犠牲の上に成り立つ幸福”だ。しかし、それもまた現代の我々に通ずる問題かもしれない。
現代を生きる我々は今、誰の“犠牲”の上に生活し、何に対して“無関心”なのだろう?
何も起こらないのにずっと緊張を強いられる
知っていることの責任
256 そんなに見つめないでよ
オープニングの画面でいきなり睡魔が。
レビューを見てあーそういう意味ね。
人間の業が出まくりなのは笑った。
だって大きな家の方がいいもん。
プールに滑り台でっせ。
転勤?!イヤよ、あんただけ行って、
あんたは好きだけど。
オカン凄い家でしょう。え?実家に帰った?
なんで?
まあ、拙は人間ってそんなもの。
同調圧力って跳ね返せない、とも思っているので
作品としては素晴らしいと思うも
人間的にはなかなか改善改革は困難なんだよねー
とどこか冷める。
A24作品なのでどこまで攻めるかと興味が
あったがなかなかなものであるのは事実。
監督のジョナサン・グレイザー
「アンダー・ザ・スキン 種の捕食」でも我々の
認識を一歩ずらす演出で
本作も一筋縄ではいかない様子。
70点
2024年8月13日 京都シネマ
今の世界中に繋がる無関心という恐怖
この作品は、音とアウシュヴィッツ収容所の隣で暮らすごく普通の家族を通じて、無関心という事が本当に恐ろしい事を訴えています。
ヘートヴィヒがベッドに隠しているコートを自分の物と思い込み、着こなしてかつ、ポケットに入っていた口紅を塗る場面、ルドルフ司令官とその子供が川でレジャーを楽しむ内に沈んでいた処刑された人の骨が当たり、あわてて家に戻り、シャワーを浴びる様子、赤ちゃんが泣き叫び、誰も止めず、隣接する収容所の環境に耐えきれず、実の母親がいきなり出ていく所、銃声、怒鳴り声、悲鳴が最初から最後まで途切れる事なく響いている状況、仕事と家庭で起きている軋轢、命懸けでりんごを置いて行く姿、塀の外でまかれる人骨の灰、最後に出てくるアウシュヴィッツ収容所記念館のおびただしい受刑者の遺品、ガス室、司令官が吐き気をする所等...阿鼻叫喚です。
紛争、格差、気候変動等ポリクライシス=複合危機が世界中でリアルになっている中、この映画「関心領域」は無関心がいかに自分自身の生活へ跳ね返り、リスクを背負う事への警告を訴えています。
私にもあるヘスとの共通性
8/15が今年もやつて来る。毎年、この時期には戦争とヒトとの、戦争と国家との、戦争と民族との関係性を考える機会として来た。昨日、山口市で「関心領域」という映画を見た。
映画を見に行き途中で寝てしまった事や途中で退出した事はあったけど、昨日は途中退席し、しかし意を決して再び戻り続きを見た。そうした体験は初めてだった。
退席した直接的な理由は緊張感のあまり尿意を催し、それが最大尿意に達したからだけど、一度外の空気を吸わずにはいられなくなったからだ。
映画はアウシュビッツの所長を務めたルドルフ・ヘス家族の日常を綴ったものだ。壁を隔てた向こう側には生存率10%と言われるユダヤ人等絶滅収容所がある。壁のこちら側ではヘス所長家族らが一見すると優雅で贅沢な日常を送っている。映画Schindler's Listとは違い、ユダヤ人に対する虐殺の直接なシーンは一切ない。しかし煙突から上がる炎、川に流れてくる白い灰、それを浴びた子どもたちが不浄なものを拭うように風呂場でゴシゴシと擦られる場面、何度も何度も出てくる汽笛、射殺音、ユダヤ達の悲鳴とむせび泣く様な声、そうした音の通低音として鉛を流したような音。こうした環境でも正気を保つていた様に描かれていたのは妻のイルセ・ヘスだ。女は強し。
私は2017の夏にアウシュビッツ、第二アウシュビッツと言われるビルケナウ、チェコのテレジン収容所を訪れている。アウシュビッツでは日本人の公式ガイド員の中谷剛さんに案内してもらった。同じコースの英語のツアーにも参加した。行くにあたっては事前に何冊もの関連書籍を読み、DVDを見た。だからこの映画中のユダヤ人虐殺の場面が直接的に分かるというか感じられてしまうのだ。
私が退席した理由と再び鑑賞した理由はこの映画の映像と音が現地で見てしまったものを呼び起こし、でも最後までやはり見ないといけないと判断したからだと思っていた。
映画の後、アフターアワーカフェが行われ、話さずにはいられない私は参加した。話すとまた2017年に見たアウシュビッツを思い出す。映画のラストでは現実のアウシュビッツ博物館を清掃作業するシーン、その後にヘスが階段で吐き気を催しゲロを吐こうとするシーンが連続してた。カフェ参加者はあれはヘスのゲロを片付ける事の示唆ではないかとか、いやいや清掃員の日常はアウシュビッツで死体処理やその後の灰と骨の搬出をさせられたユダヤ人達の姿ではないかとか、清掃員にとって展示品は日常の光景で無関心になるのは当たり前だとか、そんな話が出てた。私はNIVEAの缶が展示してあった事を思い出した。
映画はヘスが螺旋階段を降りていくシーンでほぼ終わった印象がある。ヘスは自分がやってる事、この先待ち受けている事を理解しいたのだと思う。しかし私は何故、退席したのか、何故あそこまで緊張して映画を観たのか、今ひとつ合点がいかなかった。
山口からの帰りに私はセローのバイクで高速を走った。90km以上のスピードでトンネルを走ると、高周波帯の風切音となる。それは正に先程見た映画で聞いた人の悲鳴や慟哭だ。酷似した音だった。セローの様なバイクで高速を走ると風圧をまともに受けハンドル操作を誤ると死ぬ。しかしトンネル内はオレンジの光に照らされ他の情報がなく、正にゾーンに入っていた。一点だけ見つめて危機感は薄れ、狂気染みる。
アフターアワーカフェで私が話したことは壁の存在、壁を隔てた向こう側は想像でしか補えないことだ。情報は遮断され、加工されて、こちら側に都合の良いものしか届かないシステムとなっている。
私を震撼させたもの、私に緊張感を強いたものの正体は私の中にもあるヘス長官と共通する都合の悪いものは見ない様にする事や自己の保全を第一に考える脳機能、私の中にもある他者への残虐性なのではないかと思った。そう思えたのは高速道で体感したあのゾーン感覚だ。
関心領域をThe areaとは言わず、The zoneとタイトルしたのは、ゾーンに入れば他者への関心などなくなるからだ。それは私だけでなく、ヘスと同様、全人類のDNAに深く刻み込まれている人の属性なんだと私は思っている。シンドイ映画だった。
知らない現実もある。
いままでアウシュビッツの収容所の悲惨さしか知らなかったが、そこに勤務している側の生活もあったという現実。
しかも、となりに住んでしまうということ。
時には川に流れてきた骨を見て、子供を洗っていた場面で、毒殺した毒が川の水にながれているのかと思ったり。
妻は現実よりも、自由とお金のある生活を望み、遊びにきた母親はとなりの残酷さに耐えきれずに帰ってしまう。
子供たちもそれぞれ。
林檎をおいてまわったのはヘスの娘だと主人はいうのだけど、そうだったのか…?
いままで考えたこともなかった映画に触れて、私は良かったと思う。
現代と当時の狭間で人の関心を描く
終始、隣の収容所で行われていることは全く映さず、音(人の叫び声など)や煙だけでその情景を映し出す。
その中で、将校夫婦に起きる出来事だけを映し出し、夫婦の問題を描いているように物語は展開するが、後半、将校がふと現代のアウシュビッツの状況に気付くかのような描写が描かれる。
将校は現代の状況に気付きそうでいながら、また自身の日常に戻っていく。
第二次大戦下と現代の狭間で、人が関心を持つということの重要性を訴えているように感じた。
余談だが、仕事仲間の人にこの映画の話をしたところ、リンゴを地面に置いてくる少女の描写などわからないことが多く、パンフレットで真相を知ったようで、もっと説明描写が必要だったのではという感想だった。
確かに、私もリンゴの少女の描写は分かりづらかった。
侵攻した軍は非人道的行為に走ってしまうものなのだろうか(追記)
8月6日(火)
夏風邪で3週間映画館に行けず、観賞予定が大幅に狂った。やっと第96回アカデミー賞で作品賞、監督賞、脚色賞、国際長編映画賞、音響賞の5部門にノミネートされ、国際長編映画賞と音響賞の2部門を受賞した「関心領域」をTOHOシネマズシャンテで。
ナチス親衛隊がポーランド・オシフィエンチム郊外にあるアウシュビッツ強制収容所群を取り囲む40平方キロメートルの地域を表現するために使った言葉が「The Zone of Interest(関心領域)」だそうだ。
「The Zone of Interest」タイトルが映し出されて1分か、それ以上そのままで、その後黒味の画面が続く。映写トラブルかと思う位だ。だんだんと音量が上がって来る。
家族ののどかな川辺でのピクニック風景から映画は始まる。収容所の司令官ヘスの家族である。
しかし、映画の中盤で同じ川へカヌーで子連れで出かけた時、川上から濁った水が流れて来るとヘスは流れの中で人骨を手にする。濁り水の量はどんどん増えて来る。
川上で焼却灰でも処理しただろう事が容易に類推出来る。ヘスは慌てて子供を家に連れ帰り風呂で子供達の体を使用人達にゴシゴシ洗わせる。
ヘスの妻ヘートヴィヒ(ザンドラ・ヒュラー)は、庭に温室を作り、花壇にはバラやダリヤ数々の花が咲き乱れ、滑り台付きのプールもある。私が設計したのよ、と訪ねて来た母親にこれらを紹介する姿の誇らしい事。
母親も素晴らしい家だと思っていたが、絶える事無く立ち上る煙、焼却炉の燃焼音、夜空に煙突から吹き出す炎(当然匂いもするのだろう)、これらを観て、感じて、母親は翌朝置き手紙を残して去ってしまう。
暗視カメラで表現されるユダヤ人作業者にリンゴを差し入れる少女は実在したらしい。
「奴らは何をしていた?」「リンゴの奪い合いです」アウシュビッツでは腐った野菜や肉で作った水分が多いスープしか提供されていなかったそうだから奪い合いにもなるのだろう、少女の善意も死に繋がるのか。
ヘスが転属になる事を告げるとヘートヴィヒは怒りまくる。自分と子供達は、ここにどうしても残るから、あなたは単身で行って。使用人達にも当たりまくる。
ラスト、転属先からアウシュビッツに戻る事になったヘスは嘔吐する。その時、廊下の先に彼が見た物は・・。
現代のアウシュビッツの博物館の清掃風景と展示品が映し出される。焼却炉の中をはき掃除する清掃員、通路に掃除機を掛ける清掃員。ガラスの拭き掃除をする清掃員。ガラスの向こうには、おびただしい数の収容されていたユダヤ人がはいていたであろう靴、靴、靴。山積みの無数のボロ靴が展示されている。
暗闇の階段を降りて行くヘスの姿で映画は終わる。ヘスがダークサイドの闇に消えたように見えた。
本作の舞台となったアウシュビッツ第3強制収容所は1942年10月に開所され、1945年1月にソ連軍により解放された。
劇中でも「一度に500人、7時間で焼却出来ます」という台詞があった。アウシュビッツ収容所全部の被害者は100万人を超えるという。
観るのが遅くなったために「ONE LIFE」を先に見る事になった。ロンドンへ行く列車に乗れなかった子供達の中には、あの煙をはいてアウシュビッツに来る列車に乗せられた子供達もいたのだろう。
アウシュビッツの博物館には行った事が無いが、中国で南京大虐殺記念館(南京大虐殺の追悼施設)には行った事がある。日中戦争で1937年の南京侵攻時に日本軍に虐殺された中国人の遺骨が土中に層をなす程大量に発見されて(「関心領域」の靴の山のように)遺骨の山がこんなにも層をなす程あったのですよと展示されていた。侵攻した日本軍は2万人をレイプし、20万人の軍人と市民を殺害したと言われている。(一説には30万人)
当時南京にいたデンマーク人シンドバーグは、ユダヤ人を救ったシンドラーのように中国人を日本軍から救ったと掲出されていた(その後、施設は拡張されて私が行った頃の倍の広さになったようだ)。
ロシアも、ドイツも、日本も、侵攻した軍は非人道的行為に走ってしまうものなのだろうか。今日も世界のどこかで人間同士が血を流しあっているのだ。ため息が出てしまう。
今日は広島に原爆が投下された日だった。
追記:
カメラはFIXして動かない事が多いが、ヘスやヘートヴィヒが邸内を移動するとき等それと相反して、えらく細かくカットが割って有る。また、昼間の庭園や屋外のシーンは抜けが良く明るい画になっているが、夜間や夜の室内等は暗めの画作りになっている。雪が降った庭などは、春~夏の明るかった庭とは一変した庭の風景になっていた。監督が何を意図したかは良く判らない。
この映画に負けて「PERFECT DAYS」がアカデミー賞国際長編映画賞を取れなかったのは残念だ。
嫁
サラリーマンの鬱
音響のすばらしさは他のレビューで語られていると思うので、ここではお仕事映画として徹底して主人公の鬱に焦点を置いた映画であった点を強調したい。
毎日人を殺して、効率的な始末の仕方を考え、肉の焼けた臭いを嗅いで鬱にならないでいられるだろうか?
作中漂ういたたまれなさの原因は、収容所に対する登場人物たちの白々しさもさることながら、誰も主人公のヘスの精神状態に対するケアがないことにも起因する。
妻は生活のことにしか、子供と犬は自分の不快にしか、部下や上司は第3帝国のことにしか興味がない。ここが地獄であると自覚し、ここを離れたいと思い、それを言葉にしているのは主人公だけである。
しかし、その言葉は最愛の妻に届かない。小川の前で妻に単身赴任を勧められ、性欲を自分の手で処理する主人公の精神状態は、おそらく世界中の勤め人がいつもどこかで感じているものだろう。なんという孤独だ。
ドライな映像は客観的にも主人公を突き放す。製作者と登場人物、両方からここまで疎外される主人公はそういない。いやな気分にさせる映画として本年度No1になりそうだ。
全571件中、121~140件目を表示