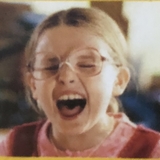関心領域のレビュー・感想・評価
全570件中、321~340件目を表示
十分な教養と予習ないのでムリ、かなり退屈
はっきり言ってしまうと。 私の鑑賞中の関心は「当時の西洋中年女性の...
はっきり言ってしまうと。
私の鑑賞中の関心は「当時の西洋中年女性の肥満前なのに肥満後を予見させる足取り」に吸い寄せられてました。
モデルのウォーキングや女優の映像で見せる動きはまさに「見せるに値する」動きなのだなと。
この映画での妻であり母であり使用人対する雇い主であり訪問してきた母にとっての娘である女性を全くのプライバシー無しにその底の底まで「覗き見」したのがこの映画だと思うのです。
だから、この、不細工なほどの中年感あふれる肥満未満の歩き方が、説得力を持たせる。
塀の向こうだけではない。
子どもにも、夫にも、使用人にも、自分がどんな生活をしてるかってことにすら意識を向けない。望むのは「羨ましがられる私」。
身につまされたか?
彼女の生き様を人ごとに見えた私もまた、
いろんなものを見ないようにしてるのかも、しれないですね。
そして、戦中のドイツ軍本部の業務連絡が極めて整然としており、本人たちがいかにも優秀で知的で理性的な集団だと自負してる様が、「間違いは、その間違いが大きいほど渦中の人間には気づかれないのだな」も、思いました。
人間にはあれが出来る
開始直後、スクリーンは真っ黒のまま数分鳴り響く不穏な音。なんとも不安になるその音を逃げ場なく浴びせられ続け、映写機壊れてない?と不安になってきたあたりで画面は長閑な自然の風景に切り替わります。
その時点で、ああなんか…アート系の映画なのか〜と思いました。
エンタメ的な親切さのない映画を見たのは結構久しぶりで、劇場で見たのはもしかしたら初めてだったかもしれないのですが、こういう映画はむしろ劇場で観るからこそ意味があるのだなと学びました。
特殊な体験として心に残るし、その場に居合わせた観客同士で妙な連帯感さえ湧く(正直いびきも聞こえたけれど)。
一時停止ボタンや早送りボタンを押す自由がない状況で見るべきものなんだなと思いました。
肝心の内容ですが、とにかく劇的さがないのが特徴だと思います。
ホロコーストという、被害者であれ加害者であれ、どこを切り取ってもドラマチックにならざるを得ないような題材を扱っているにも関わらず、です。
物語的な文脈の存在しない他人の日常生活を隠しカメラでただ覗いているだけ、みたいな退屈なシーンが続き、だからこそ異常なまでのリアリティがある。不思議と、塀の中の悲劇を生々しく描いたどのホロコースト映画より、あれが現実に起きたことなのだと生々しく実感させられた気がしました。
だから、特に何も起こっていないのに、とにかく恐ろしい。
ホロコースト映画を見て、『こんな酷いことを人間ができるものだろうか』と思ったことは何度もありますが、『人間にはこれができるのだ』と確信させられたのは今回が初めてかもしれません。
人間にはあれが出来るし、かつあれをやりながら我が子を愛し、妻や夫を愛し、食事をし、娯楽を楽しみ、生活をより良くするための努力をし、現実的な職務上のノルマにプレッシャーを感じたり、夫の転勤で生活が変化することに悩んだり出来るのです。
この映画について、無関心というものがよくテーマに挙げられますが、私はルドルフとヘートヴィヒについては無関心で済ませられないほどに塀の中の出来事に主体的に関わりすぎていると思っています。
ルドルフは毎日塀の中の光景をその目で見て、かつ運ばれてくる彼らをいかに効率的に絶滅させるかの決定に主体的に関わっているわけですし、ヘートヴィヒは囚人の持ち物を平然と収奪し、気に食わない使用人に『お前も灰にしてやる』などと暴言を吐いています。しかも、あの状況に耐えられなくなった母親が挨拶もせずに逃げ帰ってしまったことで、『あの状況で平然と暮らせることは異常である』という現実を認識させられてもいるのです。
無関心の罪で済ませられるのは、あのヘートヴィヒの母くらいまででしょう。
それでもなお、彼らは単なる職業上の義務としてだけでなく、それを肯定し、それを行う自分たちも肯定できるだけの思想性を持ってあの場所に暮らしているのだろうと思うのです。
具体的には、彼らは間違いなくナチズムとか反ユダヤ主義の熱心な信奉者ではあって、ルス家が子だくさんなのもアーリア人種を増やすためナチスがそれを推奨していたからでしょうし、ヘートヴィヒが東方における生存圏とかいう概念であの生活を肯定していたのも、その表れだと思います。
ユダヤ人を絶滅させるという高尚な仕事の末端の汚れ仕事を担うことに対して、自己犠牲を払っているのだというような陶酔感すらあったかもしれません。
ルドルフたちは単に役割を果たしていただけの平凡な人たちでなく、あの時代の異常な思想を支持していた人たちとしても見るべきなのだろうと思うのです。現代に置き換えても、無関心に並んであらゆる属性への差別感情や排他主義は間違いなく現在進行系の問題ですし。
でも同時に、別に大して異常な思想性を持っていなくとも、ただ単に無関心であるだけでも人って結構酷いことを見過ごすし、無かったことにするし、なんならなし崩し的にその実行犯として巻き込まれてしまったとして、それに抗うことなんか出来ないのかもしれないよな、とも思わされ…そしてそのほうがより救いようがないし、邪悪かもしれない…。
そういう、人間というものそのものの『嫌』さ、どうしようもなさみたいなことについて、映画を見終わってから何日もずっと考えさせられています。
本当に何も劇的なことの起こらない映画なのに、これだけ重たいものを人の心に残すのはすごい。
映画というものの可能性や真の価値みたいなものも教えられた気がする、個人的に忘れられない作品になりました。
これ、お前のことだからな。
改めて映画の奥深さを感じる
映画はよく“総合芸術”なんて言われたりしますが。
私はむしろ映画の“大衆娯楽”な一面を愛しているので、“芸術”なんて言われると「そんなに敷居を上げなくても…」と怖気付いてしまいますが。
でも“総合”については、本当にその通りだと感じています。
いろんな要素が合わさって一つのシーンが出来上がっている。
プロフェッショナル同士の表現の結晶のようなシーンに出会うと、言葉にできない感情が揺さぶられます。
『ようこそ映画音響の世界へ』で丁寧に説明されていますが
私たち観客は音によって奥行きや距離を感じ取っていることを改めて体感しました。
カメラのフレームの外側にも世界が広がっていると感じる。
そして、平面でしかないスクリーンの映像を立体的な空間として感じるのには、劇場によるサウンドデザインも重要。
この没入感は、映画という作品を届けようとする全ての人の技の結晶なのだなぁ。
聴覚に集中した状態から、一気に情報量が増えるファーストシーンだけでも劇場で体感してほしい!
貴重な映画体験でした。
そして、チャレンジングな映像表現に刺激を受けた方には『映画(窒息)』もおすすめ。
映画への挑戦状でありラブレターです。
サンドラ・フラーさんの品のない歩き方が素晴らしい。
どんな役どころでもリアリティを持って演じ分けられる役者さんですが、立ち姿やちょっとした仕草から、その人物がどんな人生を歩んできたのかが想像できるところがすごい。
『落下の解剖学』に続いて自分の考えを主張する強めな役どころでしたが、またコメディもみたいなぁ。
子供の頃にアウシュビッツ展に行った時の恐ろしさを思い出しました。
実際にアウシュビッツを訪れたことのある方には劣るでしょうが、再現されたガス室を通るだけでも怖くてたまりませんでした。
靴はもちろん、髪で編まれた毛布や入れ歯に石鹸。壁いっぱいに貼られた犠牲者の写真も展示されていました。
これは決して過去の物語ではない。
まさに今ジェノサイドが起きているなかで生活をおくっている私自身に「これ、お前のことだからな。」と突きつけられました。
おぞましさの上塗り
ノイズ
試される映画
想像できなければできないほど、
意味がわからなければわからないほど、
いかに僕が無関心だったかがわかりますね。
淡々と流れる日常をずーと観てると
最初ずっと気になってたはずの銃声や悲鳴やらが
いつのまにか聞こえてなかった自分がいました。
無関心
文才がないので「この映画に込められた反戦のメッセージがどうたらこうたら」という感想を書けば、たぶんありきたりで陳腐になっちゃうだろうからそこには触れない。
「人間はどこまで無関心になれるのか」という点で興味深い映画でした。
人間ってほんと怖いよね。
私ふだんはニコニコヘラヘラ暮らしてるけど、頭の中は政治に対する怒りでいっぱい。
赤木俊夫さんを自殺に追いやったお役所、伊藤詩織さんの尊厳を踏みにじった司法、能登の瓦礫の下にいる被災者を放置して新年会をハシゴした首相、国民が生活をすり減らして納付した税金を海外にばらまく国、もう全部なんでそんなに他人の苦悩を無視できるのか理解できない。本当に理解できない。
でももっと理解できないのは、その政治家たちを支持して投票する人。
次に瓦礫の下で見殺しにされるのは自分かもしれないのに。
私には、この映画の登場人物が身の回りのそういう人たちと重なって見えました。
でも自分も「そう」かもしれないんだよね。
世間の出来事全てに対して無限に関心を持ち関わることはできない。
私が関心の外に捨てたこと。それはそれでいいのか、どうなのか。そういう自問自答をやめてしまったら、私もあなたもヘス一家のようになってもおかしくない。
映画では昼夜ずーっとごうごう、ごうんごうんと何かの音が鳴り響いているんですが、あれは焼却炉の音なのかな?噂通り、もう音が不穏で不穏で。
お話は淡々と静かに進行するわけですが、裏で起こっている出来事を探ろうと頭がフル回転する映画でした。
イチャイチャインキャラカップル
皆なにをそんなに絶賛してるの?
何人かに勧められたので見ましたが、伝えたいことは分かるけどとにかくつまらなかった
予告以上の情報はそんなにないです。
内容が辛いとかじゃく、つまらすぎて早く終わらないかなーと思ってました。
あまりにも日常すぎて、それなら短編でも良かったのではと思うくらいの内容量。
そもそもアウシュヴィッツ収容所がどんな所で何が行われてたのか良く知らないので、知識不足なだけかも。
銃声も途中までずっと軍の訓練の音だと思って見てまし
た。
隣から聞こえる叫び声も残酷とか怖いってレビューが多いけど、なんて言ってるのか分からないから特に何も感じない。字幕が付いてる叫び声は残酷さが伝わった。
映画マニアの人が「好きな映画」として発表したする用の映画みたい。
怪物だ~れだ?
恐ろしくおぞましい映画
この話しは事実を知っていれば知っている程、恐ろしい筈だ。監督はあえてアウシュビッツの中は映さない。しかし音は聞こえて来る…
これがこの映画の視点だ。現代社会もある意味、ガザの惨状やウクライナの状況をテレビ画面やSNSで遠い所の様に眺めている。監督は正しくこれを言っているのだ。。
この物語の妻は今の幸せな生活を手放したく無い。聴いているが聴こえないふりをしている。もしくは本当に聴こえなくなっているのかも⁉︎(現代人の我々の様に)これがまさしく恐ろしくおぞましい事だと監督は訴えかけているのだ。知っているのに知らないふりをする。聞こえているのに聴こえて無いふりをする。それは淡々と流れる現在の今を失いたくないから…まさにこの映画の妻と二人が話す時に、写し出される河の流れの様に次々と流れていく…
おそろしい…
表現のセンスよ!
ホームドラマ
土曜日にMOVIXで
アカデミー賞の何だかを獲っていて
すこぶる評判がよかったのでリストアップしていた
この手の作品はいつもの映画館で観るのが通例なのだが
公開予定になく油断していたら何と始まっているではないか
MOVIXと利府のイオンシネマで上映されていると
イオンシネマ シルバー料金は魅力だが利府は遠い
ん 今日は1日なので安い日だ
普段はあまり行かないMOVIXとなった次第
アウシュビッツの収容所 ホロコーストの話なのだけれど
直接描かない手法 そういう手もあるんだな
では何を描いているかというと 軍人一家の日常なのだ
オヤジが転勤するとか出世するとか妻は転勤イヤだとか
妻の母親を家に住まわせるとか家政婦がアル中とか
娼婦 庭師 息子の彼女…岸辺のアルバムみたいなホームドラマ
隣地はユダヤ人の収容所
汽車で機械的に運ばれてきて殺されて燃やされる
川遊びをしていると骨が流れてきて
オヤジが子どもたちに上がれ~と言う
風呂で淡々と汚れを落とす
血の付いた靴底を洗い流す作業員
暗視カメラの映像は最初は夢の中の風景か何かだと思った
いまだによく理解できないが
リンゴがどうしたとかいっていたなぁ
何もないところから家を作ってきた妻にしてみれば
日常の音とか景色なのだが ある日家に入った母親は
最初はいいところねぇなんて言っていたのに
その環境の異常さに耐えられない
ブラックコメディでありホラー
最後の嘔吐シーンは何だろう 未来からの復讐か
関心領域というタイトルは秀逸だ
目の前の景色が円形に明るくなっていて
その他はシャドウがかかっているイメージ
明るい部分はホームドラマ 夫の昇進 転勤 不倫 単身赴任
シャドウの部分では常軌を逸した大変なことが進行している
妻役は落下の解剖学のひとだっけ
いやぁすごい作品だった 先週のあぶ刑事との落差ありすぎ
早くレビュー読みたい
ただ観るだけ
すごいタイトルつけたなぁ
映画が始まった途端にこれはちょっと違うぞと思い始めて気持ちが引き締まる。まず英語のタイトルが前面に出た時、そうだ、この映画はそういう映画なんだと意識する。
始まってみると予想に反して、幸せな家族が淡々と描かれていた。事件もない。揉め事もない。でも、みんな聞こえないの?あの音が。あの声が、と言いたくなるのだ。音響の効果も抜群だった。
ヒトラーのユダヤ人虐殺は本当に色々な映画になっている。側近が主役だったり、ユダヤ人を救った人が主役だったり、様々だ。
この映画は、そういう戦争の悲惨さというより、人間の本質みたいなことに焦点を当てていた。隣で何が起きてるか知ってるはずだけれど、なんていうか、本当に普通に気にせず暮らせちゃうんだなぁ。それは彼らが悪いわけじゃない。interestは人によって違うんだ。あの母親は出て行った。彼女のzoneにはあの音が入ってきたんだなぁ。
気が付かないうちに自分にもzoneができていて,見えてないことがあるのかもと思えて、怖い映画だった。
別方向からの収容所
環境に適応してしまうことの罪
可能なら何の予備知識もなく出会いたかった映画です。
おそらく描かれていることの半分も受け取れていないと思います。それでいて、阿鼻叫喚の地獄の隣りで幸せそうに暮らす家族を見せつけられるだけで、人間が持つ業のようなものを嫌というほど見せつけられる作品です。
川から急に逃げるヘスや突然姿を消すヘスの義母、精神崩壊するメイド、さりげなく背景に映る焼却炉とその煙など、はっきりと見せないが確実にある悲劇をこれほど婉曲的に描き続けた作品もないでしょう。
いくつか理解できてないシーンも多いため、またみたいと考えています。
全570件中、321~340件目を表示