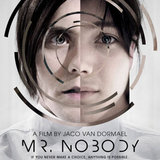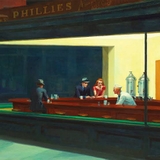関心領域のレビュー・感想・評価
全571件中、181~200件目を表示
アウシュビッツ収容所の隣で幸せに暮らす家族がいた
人の背ほどの壁一枚を隔てて収容所の隣に暮らす家族。
広い家に家族や使用人、豪勢な庭や温室まで揃う一見理想的な暮らしをしている。
そこに暮らす全員が無関心でいるようで、収容所から受ける潜在的な影響が少しずつ見えてくる。
子供たちはスタンフォード監獄実験を思わせる描写が描かれ、妻の母親は(恐らく)異様な雰囲気に耐えられず手紙を置いて去る。
幸せに見える妻も執着と二面性が垣間見え、夫は着々と心を閉ざす。
映像が途切れても音声が続いたり、響くような音が漏れ出して消えるような演出が印象的。
視覚的に遮られても確かに届くその音に、作中の人物や観客の関心はどれほど作用するのか。
現代の収容所は観光地となり、淡々と清掃を行う姿が映される。
時を隔ててもその領域は確かにそこにある。
様式美と靴の生々しさ
ホロコーストをアートに描くことの是非はあるが、その様式美との対比で、最後の靴の生々しさが際だった。
庭園、家庭菜園、壁紙一つとっても、ドイツの一般的な美しい家庭はこうあらねばならないという硬直した強迫観念が感じられる。
関心を持つことが危険で、なんの得にもならないと思えば、人間は簡単に無関心でいられる。口では人権がなんだのといいながら、町のホームレスのことは“自業自得”だと簡単に切り捨ててしまうし、移民を犯罪に結びつけて排除しようとする。
それはこの当時のドイツ人が、ユダヤ人は劣等民族であったから排除しても仕方がないと考えていたことと、なんらかわらない。
この当時の一般的なドイツ国民の多くは、大量虐殺が行われているのを知らなかったという。それを知ったときは驚いたものです。当時のナチがヨーロッパの地の下にユダヤ人そのものの歴史と存在を封じ込めようとしていたのだなと…。そんなことはできやしないのに。
ヘス一家の多くは、塀の中に無関心でいるようで、影響は受けている。息子たちには暴力的な一面があるし、赤ん坊は泣きやまない。意識にあがってくる死や殺戮というおぞましいものを、意識的に無関心の領域に押し込めている。その強いストレスの中にいてさえ、自分の夢見た家庭だけが全てで、夫の心にさえ寄り添わない妻が一番強烈な自意識を持っている。なぜなら夢を叶えてくれたのはユダヤ人の死体だから、彼らの死に同情などするわけがない。
私の視力ではよく見えない席に座ってしまい痛恨のミスだったが、真夜中に長女はなにを置いていたのだろう。一回目のリンゴはわかりました。二回目がよくわからず。とにかく一家の中では長女が正面から「事実」に向き合った人間だったことはわかった。事実、のちにレジスタンス活動に加わったという。
実際に収容所とナチ将校の家が同じ壁を共有していたことは流石にないだろうけど、あえて狭い画(え)の空間に押し込めることで、舞台のような演出に感じられた。
見て見ぬ振りは誰でもできる。国がそういったから、仕事だから、みんなそうだったから、と責任転嫁できる。ヘス一家は特別残虐なのではない。
最後のルドルフは画面の中からお前もだぞ、とこちら側に問いかけている。
新たな角度で迫る反戦映画
まさにタイトルを地でいく映画でした。
隣にあるアウシュビッツ収容所で恐ろしい出来事が日々起きているにも関わらず、まるでその存在すら知らないのが如く、(所長)家族の優雅な暮らしが淡々と描かれていきます。定点観測的なカメラワークでまるでその家族の様子を覗き見しているような感覚に陥ります。
でも、時々、収容所の様子が映像ではなく、間接的に「音」を通じて観客に聞こえてきます。でもそこに住む人々は気づいている様子はありません。そもそも「無関心」といった方が近いのかな?そのギャップに恐怖を感じていきます。
途中で妻のお母さんが訪ねてきますが、夜の焼却炉をみて、そして、それに無関心で熟睡できる娘をみて、突然いなくなります。翌朝、おそらくお母さんの置き手紙になにかしらアウシュビッツのことが書かれていたと思いますが、それをそっと捨てた?しまいました。ちょっと怖かった、、。
とにかくなにも起こらないが、終始なにかが起きるような不気味な感じで物語は静かに進んでいきます。
そしてラストシーン。
所長の内面が唯一垣間見れる階段を降りていく場面。突然、現代のアウシュビッツ収容所の場面とシンクロします。このシンクロさせたシーンの意図はなんだったのか?その他、敢えて間を与えて我々の想像力を試す工夫がいくつかあります。この映画の良心的な存在、りんごを隠す少女のアニメのシーンも印象的で、監督の巧みな演出で最後まで飽きることなく観賞出来ました。
昨年個人的ナンバー1映画だった「pefect days」を破ってアカデミー外国語作品賞を獲ったときいて観たが、インパクト考えると妥当な選択かな、と。ありとあらゆる手法で出尽くし感があった戦争モノに新たな角度を付けて反戦映画を作った監督に拍手👏
怪作也。
「軍用靴で表現」
ある意味で「無関心領域」ともいえるが
今年231本目(合計1,323本目/今月(2024年6月度)31本目)。
(前の作品 「アニマル ぼくたちと動物のこと」→この作品「関心領域」→次の作品「」)
他の方も多く書かれているのですが、いわゆる収容所をへだてたところに一つの家があり、そこの家の住人(うすうす気が付いていたはずですが…。描写からもわかる)を描いた作品で、収容所それ自体のシーンはほぼ出ないという映画です(いわゆるガス室のことも「荷下ろし」などと言葉を変えて表現される)。
確かにそういう観点でみれば、それは「関心領域」であると同時に「無関心領域」であるとは言え、ここをどうとるか(かつ、この点に論点があたるため、ナチスドイツのこの政策については是とも非ともあまり述べていない)といったところです。
この時期になるとナチスドイツを(否定的に)扱った映画があると思いますが、その中ではストレート球であると同時に「視点が少し違う」ように描かれていて、それは当然「そういうみかたでもみてほしい」というメッセージがあるものでしょうが、こうした作品「も」公表されること、それ自体に意味があるかなと思います。
採点に関しては特に気になる点まで見出せずフルスコアにしています。
観終わったあとに改めて。
関心領域
現代と何ら変わりない
世界で戦争、殺戮、差別が続いていることを横目で見ながら、いわゆる「豊かさ」を享受していると錯覚しているのは誰なのか。収容所の壁は、現代でいうメディアである。壁から音声が聞こえてくるが、自分事とは現代人は誰も感じてない。そして勘違いしてはいけない。収容所の壁の内側に生じていることが間違いだとは映画は語ってない。収容所の外側にいる現代人が、狂っていると喝破している。今日も食事が美味しいし、映画が楽しいが、きっと誰かの犠牲の上に成り立っているのでないか?最後の「嘔吐」は哲学者サルトルの、あの嘔吐だろうか?嘔吐できないのなら、なおさら問題である。
仕組みや日常となる恐ろしさ
「愛を読むひと」を観たときにも感じた、仕組みや日常の一つになる恐ろしさ
今ある「自分にとって」の幸せを手放したくない妻と多少なりとも違和感を感じていそうな子ども、子どもが成長して思想が固定化されていくさま、
驚いたのがアウシュヴィッツを博物館のように手入れするシーンが急に挟まれたこと
急にすべてが自分ごとに…
関心領域とは、もともと映画で感じるような意図とは別の意味でナチス下で使われていたようです
どこまでいっても、いつの時代も、自分のおかれた環境、周囲を1番に考えてしまうのは仕方ないことなのかもしれませんが、その環境はどういった仕組みで成り立っているのでしょうか、
考えなければ同じことが繰り返されても気づかないのかもしれません。
今の自分を突きつけられる物語
この映画のテーマ、設定、評価などを全て事前に知った上でなお、映画を鑑賞している最中に、不覚にもよくある家庭内のエピソードと思ってしまう瞬間が、何度もありました。あの不穏な音楽が聞こえているにも関わらず。
まさに、今の自分の「関心領域」を突きつけられているようで、ぞっとしました。
今の自分に、できることを始めようと改めて思いました。
メンタルに直接響く恐怖
恐ろしい作品だ。広い庭と素晴らしい家、仲の良い家族、誰もが羨む生活を淡々と写しているが、直接的な違和感を感じる。スクリーンには、エグ味があるシーンは何一つ映らない。しかし、背景の生活音の中にそれは紛れ込んでいる。悪名高きアウシュヴィッツ強制収容所の隣に住む家族の話である。何千人と直ぐ真隣でユダヤ人たちが虐殺されているにもかかわらず、この家族には全く関心が無い。その恐ろしさは今の日本の根底にもある恐ろしさだと気付く。決して他人事ではない恐怖。現在、日本人にもヒタヒタと迫り来る恐怖だと、どれだけの国民が知っているのだろうか?これは私たち日本人の近い将来の姿にも思える。政治に関心を持たない私たち日本人の未来を写した映像だとも言える。
奥さんメッチャ腹立つ
歴史的な考察や撮影方法だったり語れる要素が無限に湧いてくる映画だし記事や考察を見る意欲が湧いてくるすごい映画だと思う。
ただ自分は頭の悪い自分が思った事は奥さんメッチャ腹立つってことだった。
あの異常な空間で奥さんだけがイキイキといしている何故かというと、あの立地に住む際の負担を他人に肩代わりしてもらってるからだと思う。
窓際の部屋は母に、赤ん坊の面倒や家事は使用人に
夜の焼却炉の明かりと赤ん坊の泣き声を他人の肩代わりして自分窓のない部屋でぐっすりと寝る。
毎日快眠でスッキリしてるからあの環境で受けるストレスが少ない。
コレは旦那にも言えてること。収容所の仕事も家のことも電話一本で済まし仕事におけるストレスが皆無に近い。
だから夫妻はあの異常の環境で平然とできる仕事や家事におけるストレスがないから生活の妨げになる騒音を許容できるようになってしまってる。
自分が背負うべき責任や負担を他人に背負わせると人間驚く程人に対して無関心になるんだと学んだ現場から嫌われたくなかったら生涯現役で現場に足を運ぶべき。
女王の宮殿
見る回数ごとに恐怖が増していく!
ドキュメンタリーの様な定点観測的カメラワークや、
どこの生活でもありうる日常会話を綴ったセリフなど、
1度目は、自分が何かを見過ごしてしまったんじゃないかという恐怖が過って
2回目に足を運ぶことになった。
案の定、それで味わう恐怖はこれまで経験したことないもの。
なんの外連もない描き方で、これほどまで斬新な表現があったのかと!
日頃、答え合わせを作品に求める鑑賞者には全く向かない深淵さがそこに。
映画とは平面に描かれるものだけではないと分かる。
日常会話に恐怖を味わう訳は、自分の中にもそれと同じ芽が
あるのではないかと気付いたとしたら、
その恐怖を取り払うことに必死にならざるを得なくなる。
音がフィーチャーされがちな作品だが、
味覚以外の全感覚が侵されてしまった。
淡々としながら、
これまでに無い斬新な体験を味わわせてくれた作品。
無関心であることの罪悪
第二次大戦中、アウシュビッツのユダヤ人収容所と塀一枚隔てて、暮らしていた収容所長一家の平凡で幸福な生活を描く強烈な作品です。収容所の中は一切見せず、遠くから叫び声や銃声が聞こえてくるだけでホロコーストを描く実験的な演出方法がポイントです。とは言え、ドラマらしいドラマもなく、短いカットと効果音だけで淡々と進行していくので、演出の意図は分かるんだけど、睡魔に襲われるのもしばしば。一方で、一枚の塀の向こう側で行われていることを知りながら、あえて目をつむり日々の暮らしに埋没していくのは、所長一家だけではなく現代に生きている私達自身のようにも思えてきます。塀ではなくTVやネットの向こう側で毎日行われている世界中の悲惨な事件も、所詮は他人事であり、やがて関心を失ってしまう。関心のない事は報道されなくなり、報道されない事はやがて実際に起こってない事になってしまう恐怖を感じました。役者では、『落下の解剖学問』に続いて、サンドラ・ヒュラーが嫌な感じの女性役を好演。
私は、この映画と自分との間に高い壁を建てるか?
無関心領域
冒頭から野音をやけに拾うなぁと思いながら観ていましたが、他の場面でも同じだったので、なるほど環境音をあえて取り込んでいるのかと理解しました。
なんか叫び声みたいなのが聴こえるなぁと思っていたら、アウシュヴィッツ収容所のすぐ隣が舞台だと気付いてゾッとしました。
異常な環境に居るのにふつうの、むしろ裕福な暮らしをしていて、子供たちも元気に遊びまわっている。この対比は辛辣で新鮮。
ただそこから物語が動かない。
異常な環境でも慣れてしまう。慣れてしまう適応能力を私たちは持っているのを知っているから。
アフリカの子供が毎日たくさん餓死しようとも、侵略戦争で命を落とそうとも、私たちは贅沢な悩みに真剣に苦しんで生きていく。
テレビ画面越しに伝えられる海の向こうの出来事に時折胸を痛めることもあるけれど、何ができる訳でもないし明日も仕事だし突然大雨は降るし、麻痺して生きていくしかないから。
だから次の展開が欲しかったなぁと思います。
もうひとつ物語自体に仕掛けがあっても良かったのではないでしょうか。
たっぷり寝たあとに観たのに猛烈な眠気で途中寝落ちしてしまいました。
アウシュビッツ収容所を主題とする映画の新たな貌
1所長一家の日常生活を通して、アウシュヴィッツ収容所のホロコーストを描く。
2映画は収容所の隣に住む所長一家のピクニック場面から始まる。そして一家の豊かで秩序だった生活描写が続く。しかし、そこに収容所の実像を示すショットが次第に挟み込まれていく。収容所から運び込まれた服飾小物や貴金属を使用人たちと楽しげに分け合う場面。釣りや川遊びの最中に不気味に濁って来る川。濁りの原因は焼却された遺骨や遺灰である。圧倒的なのは、昼夜問わず聞こえ来る所内の怒号や悲鳴、銃声などの音。そして煙突からの黒煙。所内の行状を一切見せずにそこで何が行われているのかを如実に示す。とても効果的であり、斬新な手法であった。
3 所長と妻の関心は、手にした権限や暮らしを守ること。収容所から聞こえる音や眼に入る煙、そして恐らく洩れてくる臭い、すなわち日常的なホロコーストの証には無関心。所長は現場の責任者として、国策を実現するため効率的な施設運用を実行している。その点では当時の価値観に照らせば優秀な組織人であり、仕事として割り切っている。強権的な所長像を想像していたが、冷静な軍人であった。それゆえ最後の場面では、ハンガリーを対象とする新たな抹殺計画を担う重責が作用し吐き気を催したと思う。
一方、その妻は家や庭は我が城であり、主として仕切る中で、収容所は暮らしを維持するための必要条件として捉えるようになったのではないか?
4 遊びに来た母親が一晩で黙って消えた。収容所で行われていることに想像が及びその恐ろしさに気づき忌避したと思う。また、地元の名も無き女性が夜陰に紛れて食べ物を運んだ姿は神々しい輝きを放った。映画は、歴史の記憶を残す博物館として、丁寧に維持管理されている現在の姿を示して終わる。この映画を通し、歴史を学ぶと同時に何に関心を向けるのか個人の度量を試されるように思えた。
全571件中、181~200件目を表示