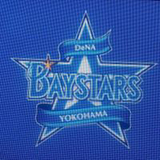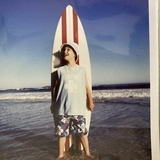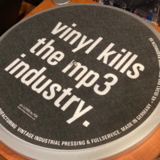クラブゼロのレビュー・感想・評価
全71件中、21~40件目を表示
「オートファジー」
典型的な北欧作品
まさに北欧映画らしい作品。終始気味の悪さ不快感を与え続け結局最後もバッドエンドの胸糞悪いストーリー。
洗脳をテーマにした作品だが、巧みに導く姿を描くというより子供たちが洗脳された状況でどうする事もできずただただ悪い方向に一直進していく姿を淡々と見せつけられる。
鑑賞者も少しは洗脳されるような巧みに破滅に導くストーリーみたいなのを期待してたがその辺りは全くなかったのは少し期待はずれ。
まぁ洗脳にはいろんな形があるけど、結局の所環境下が大切な事を強く思い知らされ、いつで誰しもが被害者になり得ることを知らされる。
雰囲気としてはA24っぽい作品ではあるが内容は典型的な北欧作品。
北欧作品が好きな人には勧めたくなる作品であり個人的にもまずまず楽しめた作品であった。
ポップコーンは持ち込まない方が…
意識的な食事を指導し生徒達を心酔させて行く栄養学の教師を演じるミア・ワシコウスカ
シュールさ満開なハマり過ぎの表情と演技に意識が集中!
個人的には正直ヤマなしオチなし意味無しの
やっちまった系ジャンルか…な印象でしたし
一週間近く経ってもあの不気味な「むぅ〜むむぅ〜む🎶」が頭から離れないのでございます
ゲ◯シーンは不快感がマックスに押し寄せるわぁだし💧
子供達の不審な変化にすぐに気付かず
心も身体も健康でいられない子供達を育ててしまった親達も胸糞だし
ただ裕福な家庭の子供達の住む家は全てがキチンと整いカラフルな色彩の家具や何だかよく分からないけど😆興味をそそる手の込んだ食事…
肌にフィットする鮮色やパステルカラーのミアの装いや生徒達の制服のオシャレ偏差値は抜群にいい!男子のハイソックスがめちゃキュート!
途中退場されていた方もいらっしゃいましたが
奇妙な感情ががひと回りして蘇ってくる様な
クセ強で異色なスリラーでございました
…ただこんな作品の後でもしっかりお腹は空いてデッカいドーナツを美味しく頬張りました!
いろんな角度から見られて面白い
カルトの怖さや滑稽さが描かれている点で「ミッドサマー」やランティモス諸作のようでもあり、
食べないことが体制へのプロテストに結びつく点でハン・ガン「菜食主義者」のようでもあり。
「食事への過度なこだわり、金持ちの道楽としての」を笑っているかと思うと、最後「信心」ということばが出て来てエンドクレジットが「最後の晩餐」の構図になってたりして、ひとすじ縄ではいかない、なかなか知的な映画です。
音楽が個性的で面白い。ピアノ発表会で女の子が弾く変な曲、最高!
終盤、食事に関して思わず目を背けるほどグロいシーンがあり要注意。
ハリウッドを離れたミア・ワシコウスカが素晴らしく、彼女がカルトリーダーなら若者が付いていくのも仕方ないと思わせる。
これ、どうやって撮ったの?
めっちゃありそうな話。
カルトにはまっていくんだけど、その過程が思春期にありがちな、コンプレックスやプレッシャーや孤独、からのー、摂食障害(本人たちは多幸感)
最初から最後まで気持ち悪い。たしかにブラックユーモアの現代ホラー(摂食障害の女の子の母親がダイエットしてるとかね)
それはそうと。
痩せていく少年たち、どうやって撮ったのか途中からそれが気になって。明らかに初めと顔つき違う。メイク?CG?
Eat Me
飯を食べない事が健康の第一歩的な触れ込みで、まずそんな訳ないじゃんと思いながら観ましたが、想像以上にカルト的な方向へ進んでいったので困惑しながらの鑑賞になりました。
食事に何やら悩みを抱えている生徒たちが赴任してきた教師に倣って意識的な食事をしようとしていたのにだんだん不穏な雰囲気になっていく…といった感じでまさにハマるとヤバいクラブのキャッチコピーに嘘偽り無しでした。
ただそれが好みの面白さになっていたかというと微妙なラインで、生徒たちが少食な理由を親に話さないからどうしてもトラブルが起きてしまうし、親もそれに対して気付けないのかともなってしまいましたし、どちらもコミュニケーションが不器用なのが祟ってしまっていて、その弱みに漬け込んだ教師の戦略勝ちでズルズル洗脳していくもんですからある種家族ものの成れの果てなのかなと思いました。
摂食障害の描写は中々にキツく、少しの食事でも嘔吐してしまう、一度リバースしたものをまた口にする、食事が好きだからこそ嫌悪してしまう部分もありつつ、こういう症状を持つ人も実際にはいるんだよなと関心を寄せるきっかけにもなったのは良かったです。
最初から最後まで先生の計画通りに進んでいくので、物語的な起伏は薄く、大人たちの滑稽さが際立ってしまったがゆえに個人的には歯痒い感じ止まりでした。
金無しですが美味いもん食って生きたいタチなので、あのポテトは山盛りいただきます。
そして今日の晩飯はツナマヨうどんなので腹が空いてます。
鑑賞日 12/11
鑑賞時間 12:00〜13:55
座席 F-1
BRAINWASHER‼️
キモキモグログロ🤮キモキモゲロゲロ🤮🤮🤮
(初めて観るタイプのグロに目を背けるほかなかった……)
映画鑑賞直後の印象は、★3.4。
自分もEXTREMEな食生活に走った経験があるから気持ちはわかる。でも今の学生たちはあたしの頃と比べて情報過多というかフェイクも含まれる過剰情報の世の中で何が正しく、何が誤りで 、また何が自分に合うのか合わないのかを判別するのが難しくなってると思うから生きるのが大変だと思う。
結局この映画があれこれ考える触媒となってるからただの気持ち悪いスリラーではない問題提起作だったんだなー、と考え改め、★3.8に。
『食べ方の異常』を大人たちがアレコレ言うけど、ベンのお母さんが外出する時は黄色を身にまとう『謎のこだわり』とか先生と生徒が一緒にいるところをみたという事実が一人歩きして『風評被害の温床』となっていたり、世の中にはよくわからないけど何かおかしいが溢れてるのに自分に都合の悪いことには蓋をする。
表向きはconsious eatingの必要性を謳ったヤバいクラブの話。
でもよくよく考えると、クラブの内部と取り巻く外部環境は一般的な政治/社会の縮図のようなものに思える。
いずれにせよ気持ち悪っ😅
分かるけどねえ
カルト宗教団体
ノヴァク先生のどこかヤバそうな人という異質感が終始気味悪かった。
生徒達がだんだんと洗脳されていく様が、見ていていたたまれない。
最初は食事法なんかに全く興味も無さそうだったベンですらあっさりと染まっていく絶望感。
最後、生徒達は集団自殺でもしたのか、もしくは先生と一緒にクラブゼロの施設に移っていったのかな?
ノヴァク先生の目的や、自宅の祭壇で「母よ」と祈っている対象の正体が最後まで意味不明で、そこがまた不気味だった。
先生はあくまでクラブゼロの会員だから、組織の中には幹部とかもいて、
作中に描かれていないもっと壮大な宗教的思想があるんだろうな。
カルト集団の怖さを描いていると思った。
クラブゼロの内部を描く続編があれば観てみたい。
クラブゼロの笛吹き女
まさかのクリスマスムービーでした。
導入段階でのノヴァクの教えは何の問題もない。
必要以上の摂取を控え、身体に悪いものを避けることで、環境にも自己の心身にも良い影響がある。
断食についても、期間や手順など正しいやり方であれば本当に効果的だと聞いた。
しかしこれを段階的に極端な方へ、しかも悪意なく導いていくところが非常に厄介。
まぁ実際、“餓死”という無数の前例を意志の力ひとつで覆せるハズはなく。
親たちは頭ごなしに否定せず、放置した上で管理下に置いておけばよかっただけだとは思う。
(ぶっ倒れたところで栄養点滴ぶち込んで、説得)
親として難しいとしても、全家庭あれはちょっとなぁ。
この辺は宗教よりは簡単に感じもするが、盲信相手には無力というのは共通したところか。
シュールな笑いも嫌いじゃないが、後半よく分からない要素が増えてきた。
グレンがチョコバー食べてた件はほぼ触れられない。
そのグレンとキス寸前までいったフレッドは、何事もなかったようにノヴァクとキスするし。
教えを拡大解釈して「母親をガンにも出来るし午後に雨を降らせることも出来る」とか言うエルサが怖い。
ベンの急転換は逆にリアルなのかなぁ。
フェードアウトしたと思ったヘレンがラストカットで重要な役割を担うのは上手かった。
エンドロール中まったく身じろぎしないのも凄い。
(合成かと思ったら、まばたきはしてた)
構図は最後の晩餐っぽかったけど、そしたら2人足りないし、意味深にずっと映して役者さん大変だなぁ。
食事シーンはなかったけど、ノヴァクは本当に食べてないの?
後味の悪さが堪らない魅力
持続可能な社会を目指し、健康的な生活をするためにも、食生活を変えなければいけないというのはある意味で事実。しかし、それも突き詰めすぎれば、健康的な生活を阻害するし、生きていくことの喜びもおかしな方向に行ってしまう。
寮で暮らす子供たちに、「意識的に食べる」ことを推奨し、やがて「食べないこと」にエスカレートさせ、社会や家族から引きはがし、現代社会や親こそが間違っていると刷り込むことで、生徒から信者に変えていきます。
この物語に明確な解決はありません。正しいことと正しくないことのグラデーションの中で生きていく人間にとって、どこで立ち止まるべきか判断することはなかなか難しい。
本作でノヴァク先生が主張する内容を嘲笑することも可能でしょう。しかし、その態度がまた地球や子供たちの将来をより悲惨なことに繋げかねないわけで、我々は決して目をそらしてはいけない作品の一つだと思います。
ハネケより意思は明快
ノヴァク先生は、
生徒たちを巧妙に統率し、
洗脳的な手法でその心を操る。
ハムハム
彼女の「教育」とは、単なる指導に留まらず、
心理的な操作を含んだ支配的な側面を持っている。
ハウスナー監督は、
映像によって観客の視覚と感情を巧みに操作し、
その心を徐々に統率していく。
圧倒的に多用されるズームアップ、ズームバック、
今までのハウスナー作品で,
多用されていたドリーアップ、バックのカメラワークは、
本作では数カットのみである。
その技術的な選択に強い意図を感じさせる。
ハムハム
登場人物たちの心情を神のように俯瞰し、
また悪魔的に一瞬でヨリ、ヒキ、
切り替えることで、観客を不安定な状態に追いやる。
ズームによるヨリ、ヒキの使い方は、
特に大きなスクリーンで観ると映像がチープに感じられる。
スクリーンが大きければ大きいほど、
ズームアップ、ズームバックはその効果が過度に目立つ、
映画では多用されない理由のひとつだ。
(アルトマンは逆手に取る、効果的に使う事に長けている。
マネをする監督、カメラマンもたまにお見掛けするが・・・)
しかし、ハウスナーはあえてその手法を選んだ。
この選択は、ハネケやオストルンドとは違い、
観客を不安にさせ、
感情的に揺さぶることだけを狙っているのではなく、
その映像的意図を明確に伝えようとしているように思える。
ハムハム
また、本作における色彩の使い方は、
特に前作『リトル・ジョー』から一層明確に表れている。
学校や家庭の壁、床に至るまで、
さらには登場人物の衣装にも一貫した配色が施されており、
その色調は単なる視覚的な装飾にとどまらない。
ウェス・アンダーソン作品に見られるような、
色彩の単なる遊び心とは異なり、
ここではそれぞれの色が物語や登場人物の心情、
さらには社会的なメッセージを強調するために用いられている。
一方で、音楽もまたこの映画の重要な要素だ。
奇抜な弦楽器の音や、不意に鳴り響く打楽器の音が、
物語の進行に合わせて奇妙に響く。
その音の使い方には、
まるで観客の神経を逆撫でするかのような不穏さと、
変な心地よさが漂い、
観客はそのリズムに引き寄せられていく。
ハムハム
音楽と映像、色彩が一体となり、
子供たちがエクストリームな異物に引き込まれていく様子が描かれる。
これこそが、
ハウスナー監督なりの観客に現実を突きつける方法なんだろう。
映画全体を通して、統制と調整が繰り返し行われ、
その中で登場人物たちと観客自身が少しずつ「洗脳」されていく。
しかし、それが単なる精神的な支配を意味するだけではなく、
むしろ現代社会のさまざまな問題に対する洞察を提示している。
最後の晩餐のようなラストカット、
静止画のような動画では、
そのすべてが集約され、
観客は自らが「ゼロだったクラブ」のメンバーに入信する、
あるいは、
拒否する、
または、
家族が入るとどうなるんだろう・・・
そこから何を思い、
どう感じるかは、観客一人ひとりの問題として残されるのだ。
ハムハムハム
『クラブゼロ』は、ただのサスペンス映画ではない。
それは、視覚的、音響的、そして色彩的に観客を巧みに誘導し、
心理的に揺さぶりをかけることで、
現代社会の深層(or浅層)に迫る作品となっている。
モヤモヤ映画
ベンが可哀想だった
全71件中、21~40件目を表示