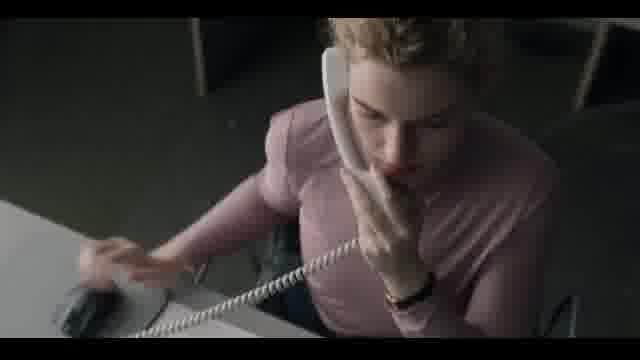アシスタントのレビュー・感想・評価
全51件中、21~40件目を表示
伝え方だったり
権力者による搾取、ゆるやかに加担する人々
映画業界を舞台に描かれていますが、働く人なら業界分野にかかわらず、どこかで似たシチュエーションに遭遇したことがあるのではないでしょうか。
自分がその場に居合わせているかのように、体がこわばって動悸がする感覚を味わいました。
作中では気分がよくなる出来事は起こらず、救いがありません。
体調のよいときに鑑賞することをおすすめします。
本作で焦点が当てられているのは、ハラスメント被害の当事者ではなく、周囲の人々です。
権力者が搾取しやすい組織の構造を強化するように、周囲の人々が自覚なくゆるやかに加担している様子を淡々と突き付けてきます。
主人公ジェーンに対して、同僚たちはやさしい言葉をかけながら、事を荒立てるなと圧力をかけます。
女性すら味方ではないことも描写されます。
本作で行動を起こしたジェーンですが、そのうち彼女もゆるやかに加担する人々になってしまいそうな未来を暗示しています。
何度も観たくないし、人にすすめるのも難しいですが、目を背けてはいけない問題を提起する社会派ドラマです。
鑑賞後にパンフレットのインタビューやレビューを合わせて読むと、この問題について考えを深めるよい機会になるかと思います。
性格もあるよねぇ...
「慣れる」恐怖
眠い凡作
普通やん、と思った自分が怖い
静かな物語でした。
あるアシスタントの、ある一日を追った物語。
しかし、このアシスタントにとっては特別な一日が、周りの人にとっては普通の一日であるところに、この映画の本質がある。
最後のお父さんとの電話のおかげで、(私にとって)深く心に残る映画になった。
重たく分厚い壁
登場人物は1人を除いて基本的にはいい人。極端な人はいない。しかし誰もが無機質。自分の手が届く範囲の事に誠実に生きている。だから主人公の様に次のステップのために手を伸ばした人が分厚い壁にぶち当たる。
それは絶対権力者の問題であることは間違いないが、それ以上に長い間培われてきた構造の流れに向き合うことを放棄してどんどん無機質になっていってしまう。
最後に主人公は父親と電話する。父親は暖かく優しい言葉をかけるが、父親もかつてはその大きな構造の中で身を置いていたことに娘は気付いてしまい何も語らず静かに1日が終わる。
本当に向き合わないといけないのは人なのか、それ以外の何かなのか結論は観客に委ねられる。
顔が見えない会長は不気味さを増幅させる。
業界の闇を淡々と静かに。
「SHE SAID」以前にあった、これが映画業界の平凡な日々
主人公のジェーン(ジュリア・ガーナー)は一流大学を卒業し、憧れの映画業界に就職した。
プロデューサーを夢見るが、いまはまだ入社して5週間の新人アシスタント(正式雇用の前にインターン期間があったらしいが)である。
本作は彼女がまだ暗いうちに家を出て深夜に帰路に着くまでの、ある1日を描いている。
劇中、ほとんど抑揚がなく、淡々とストーリーは進む。
カメラも映画制作会社のオフィスからほとんど出ない。
だが本作は終始不穏な雰囲気に満ちている。
いまにも、何か事件が起きそうだ。
だが、何も起きない。
アシスタントのジェーンは大量の雑用をこなし、その間、権力者によって“何か”がおこなわれている。
でも誰も声高に問題を叫ばない。
誰も被害に遭ったと騒がない。
そう、描かれるのは“平凡な日”だ。
つまり、ここで起こっていることは“事件”ではなく、“平凡なこと”だ、と本作は述べている。
だが、本作を観る僕たちは知っている。
スクリーンにはハッキリとは描かれないが、何がおこなわれているか。
この不穏な雰囲気の果てに何が起きたか。
そう、本作は「SHE SAID」の“前日譚”なのである。
あの映画には巨悪に挑んで勝利したカタルシスがあった。
だが、そのドラマチックなストーリーの前には“平凡な日々”が延々と続いていたのである(エンドロールに出る本作への情報提供者への謝辞が、このことを裏付けている)。
日常に、ぽっかり開いた闇を見つけたとき、どう行動するか?何が出来るか?
本作は観る者に問いかける。
闇は大きく深い。
本作の「会長」は決してスクリーンに映し出されることはない。
そして課題は構造的だ。
見て見ぬフリをする同僚(女性社員すらも)、人事部の相談窓口も機能してない(ぜんぶ会長に筒抜けである)。
このようなことを引き起こしているのは、特定の誰か(例えばワインスタイン)「だけ」ではなく、ここには構造的な問題があるのだということを本作は語っている。
ジェーンはささやかな抵抗を見せるが、それは不調に終わる。
周囲も見て見ぬフリ。
騒ぎ立てないほうが身のため。
何より、自分が傷ついたわけではない。
本作が描くのは「映画みたいな逆転劇」ではなく、そこで給料をもらって暮らしている「平凡な日々」だ。
ジェーンは答えを出さないまま本作は終わるが、彼女を責めることは難しい。
彼女は「正義のヒロイン」ではないし、誰もが映画のようなヒーロー/ヒロインになれるわけではないのだ。
「正義のヒロイン」ではないからこその、怒りや悲しみ、心配、戸惑い、そして迷いをたたえたジュリア・ガーナーの演技が光る。
父の誕生日を忘れた
エンタテインメント企業に就職した女性の、日常業務を映し出すところから始まりますね。
数分台詞がないので、結構シリアスです。
主役のジェーンは、雑用的な業務が多い模様ですね。
そうこうしてるうちに、若い女性が受付に現れて‥。
会長の行動に気付いたジェーンが、社内のカウンセラーみたいな人に相談するところがハイライトっぽいです。
相談を受けた男性の、なかなかひどい態度でジェーンはショックを受けてましたね。
この辺はジュリア・ガーナーの演技が光ります。
他の方も言ってますが、この映画は彼女の抑えた演技が功を奏してると思いますね。
内容は、考えさせられます。
ただ、こういう事は、誰かが声をあげなければ解決には向かっていかないのではないかと思いますね。
最初に声をあげるのは、大変な勇気がいりますが、やる価値はあると私は思っています。
一度声をあげれば、誰かがそれに賛同してくれるかもしれないですしね。
最初は1人でも、時と共に増えていく可能性は充分にあります。
何かの被害にあっている方は、諦めずに声をあげ続けてほしいと思いますね。
諦めなければ道は開けると信じてほしいです。
私も、その1人なので。
こういう事が減ることを願います。
※ファーストデイで1200円で観れたので、お得な気分でした🎬
男女同権思想に関心がある方はぜひ。
今年222本目(合計873本目/今月(2023年7月度)8本目)。
(参考)前期214本目(合計865本目/今月(2023年6月度まで))。
※ 男女同権思想(フェミニズム思想)に関しては色々な考え方がありますが、一般的な解釈によるものとします。
いわゆる男女同権思想を扱った映画…と思いきや、このレベルに達する女性への冷遇さはもはや女性嫌悪思想(ミソジニー)の域に達するのではなかろうか、と思えます。
結局のところ、1つの(超大手でもないだろうと思われる)会社として1人の女性が提起した男女同権問題を「消極的に」黙殺したのではなく「積極的に」そうさせた点、人の(女性の)思想良心にまで踏み込む(謝罪メールの内容をこうしろ等と関与する)等の点があり、これらの点は結局、「男女同権思想のなさ」を超えて、もはや「女性嫌悪思想」の域に達しそうなレベルです。
ところで、あらゆる仕事においても男性が優位なところもあれば逆なところ、あるいはほぼほぼ男女同権思想が達成できうる職場というのがありますが、この映画で描かれている映画業界(エンターテイメント業界)において、「積極的に」男女同権思想を阻害する思想は成立しえないことはわかります(いわゆる「男性向け」映画等を作っている、といった特殊なものは除いて)。つまり、職業の性質上、積極的に男女同権思想を達成するべきと解釈できる業種において、映画内で描かれている企業がそうなっていないのは、「この業界」全体で「多少の」ひずみがありうるとは言えても、「この業界」全体として極端にそうだとはどう考えても理解できず、映画内で描かれる「この会社」だけが極端に変なのだろう、ということになります。そして、(日本とは違うので一概に比較はできないものの)いわゆる終身雇用が当たり前な世の中はとっくの昔であり、こんな無茶苦茶な会社とはさようならの世界であり、何がどうあれマスコミ等に暴かれれば、合理性のない差別ないし女性嫌悪が過ぎるものであり袋叩きにされるものでしょう(ただし、それも私人制裁に当たる行為であり、積極的に褒められる行為とは言えない)。
換言すれば映画内で描かれている「この映画」で描かれている一つの会社は、程度の差はあれどこにでも存在するようなものであり、それが現在(2022~2023)の人権感覚でまかり通っている、というある意味「極端な状態」になっているという点が論点であり、その点は映画内では直接的な言及はないものの(映画自体、発言が少なく各個人とも淡々と話すだけで比較的字幕量は少ない映画です)、「ほぼ直接的」ないし「間接的」にこのような業界ないし会社に対する人権喚起の映画なのだ、と解釈するなら(通常はその解釈)、今日の人権感覚ではおよそ通らない(まだ平等な男女同権思想が達成できていない、ならともかく、意味もなく女性嫌悪思想を取ることの意義がおよそ見出しにくい)理論であり、それはここ日本においても、少なからずコンプライアンス意識が低い一部の中小企業においてみられることは容易に想定できることまで考えると(すべての中小企業がそうだ、というのではない)、この「男女同権思想のなさを超える、女性嫌悪思想の意味のなさ」をよく考えてほしいという点を述べている点はかなり評価可能です。
採点にあたっては特に減点対象まで見出しにくいのでフルスコアにしています。
2023年年の下半期ではベスト10には入りそうな良い映画なので、ぜひ多くの方に見ていただければというところです。
静かな語り口が良かった
すごく惜しい作品。ただしすごく良いなと思う台詞もあった。
MeToo運動が本格化するきっかけを作ったハリウッドの大物プロデューサー、ハーヴェイ・ワインスタインの性的暴行事件にヒントを得て作られたんだと思いますが、日本の芸能界も某大手事務所創業者のしでかした性犯罪がようやく社会問題化したし、園子温や榊英雄や木下ほうかなど映画業界の枕強要問題もあったので、芸能界における性的暴力問題は題材がすごくタイムリーで良いなぁと思いました。
ところが、作りがとてもドキュメンタリーチックといいますが、セリフも少なくて画や編集が良くも悪くもルーズなんですよね。音楽もほとんどない。
これを良いと思う人はたくさんいると思いますが、私は逆で、もっとドラマチックに描いて欲しかったと思います。
ドキュメンタリーチックが良いなら、それはワインスタイン問題を取材したドキュメンタリーを見ればいいだけなんで。
せっかく映画にしたのにドキュメンタリーらしさを最優先する必要はあったんですかね?
だから、映画にエンターテインメントを求めている自分にはすごく惜しい作品になってしまいました。
取材で得た事実でも映画にまとめて俳優に演じさせた時点でもうフィクションなんで、中途半端にリアリティーを求めるよりもドキドキハラハラするサスペンス映画にでもしてもらったほうが良かったですね。
ただ、ラスト付近にすごく良いなと思う台詞もありまして。
それが、女性キャラクターが主人公に言った「大丈夫。彼女は賢いから彼を利用するわよ」みたいな台詞です。
これが芸能界における性的暴行事件問題の本質なんですよね。
メリットの方が大きいから性交渉を受け入れる人も少なからずいるんです。
被害者は必ずしも利用されたんじゃなくて、利用したパターンもあるんです。
監督さんもこの本質に気付いているなら、ここをもっと掘り下げてくれれば格段に面白い映画になれたんだと思います。
ただ、フェミニストからはボロカスに叩かれますけどね。
女性はいつだって被害者じゃなきゃいけないから。
淡と淡々と
映画業界の闇を描く…みたいな宣伝文句を頼りに観に行きましたが、主人公が所属している会社のブラックさをまじまじと見せられる作品でした。それが故に主人公と主人公周りの様子を淡々と見せられるだけなので、映画としてどうかと聞かれると面白くはなかったです。
序盤の会話で、「休日はどうだった?」の返答に「出社してました」という開始早々ブラックを匂わせる強烈な出だしにおっ!と思いましたが、そこがピークだったかもしれません。
同じ部屋にいる同僚の奥さんの文句を電話越しに聞かされますし、会長からこれまた電話越しにいびられますし、知識はないけれど体と顔で良い役職に採用された若い女の子がきますしで、主人公にとって悪環境でしかないんですが、声を上げずらい状況はとても辛そうでした。
主人公が偉い人に意見をぶつけますが、それを見事にはぐらかして、その上悪意のないセクハラ(君は偉い人の好みの顔ではないなどなど)をぶつけられたりと、かなり胸糞でした。しかもまた会長からいびり電話が
かかってきたりと、もう主人公辞めても良いんじゃない?と思ってしまいました。
淡々と見せすぎているせいか、大きなアクションが無かったのが残念でした。フェイクドキュメンタリー的な楽しみ方は出来るかもしれませんが、会社の闇を暴いていくものを期待していただけに肩透かしでした。上映時間の割にかなり長く感じてしまいました。なんだか惜しい作品でした。
鑑賞日 6/27
鑑賞時間 17:20〜18:55
座席 F-9
声にならない静かな悲鳴が聞こえる
映画予告を初めて観た時から絶対観たい!と思わせてくれました。日本ではなかなか撮れないようなジェンダー問題。声高に勢いよく進む内容ではなく、静かに淡々と進む内容が逆に現実味があって信頼できる。アルアルな職場パワハラ、セクハラ。最初の父の誕生日の件からはじまり、最後の父の電話で締めるやり方が、上手いなぁ…と。散々な1日の最後に「自慢の娘だよ」なんて…。
いたたまれなくて、泣けてくるわ。自分の味方はどこにいるの?と…
さて、主人公は職場の不愉快な圧力と親からのプレッシャーから、どう自分の人生選択していくのかな?続きが気になりました。
なんとも辛い、やるせない。
憧れの映画会社で、プロデューサーを目指してアシスタントの仕事をしているが、雑用や会長の奥さんの愚痴や、超過労働。あげくは、どなられ、始末書メールしろ。
仕事させてもらってるだけ感謝しろ!ついこないだでもこんなんや。社内カウンセラーのやるせないしうち。
記録するんか?どないする?1番信用できないね。
不実の点描画
The Assistant
主人公は頭が良く、アシスタントとしても優秀なことは疑いがない。それは男の同僚が茶化しながら仕事を押し付けながらも、謝罪文の添削は手伝ってくれるところに皮肉にも見て取れる
だからこそ彼女は映画業界に(とって) 残るべきだ、残るべきなのだけど
フィルムに紡がれる1日の後の日々を想像して哀しくなる、去るか、同化するのか、正しく導くor導かれる日を待つか
民衆に夢と正しさと教訓を紡ぐ上で、実生活の正しさは必ずしも必要とされていない。虚構と同時に、不実な環境を皮肉にも生み出しているシステムをただ眺める。
全51件中、21~40件目を表示