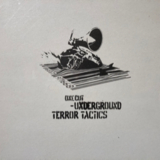映画 窓ぎわのトットちゃんのレビュー・感想・評価
全252件中、161~180件目を表示
黒柳徹子さんの大切な思い出
・人の成長は係る人によって全然変わってくるんだと感じさせられます。(黒柳徹子さんが黒柳徹子さんになることが出来た素晴らしい方々。)
・校長先生が素晴らしい人柄。
・イメージはこの世界の片隅にですが、そこまで重たくないので、見やすいです。
まじで観てよかった
観た人も含め、作品に携わった全ての人たちにとって愛おしいもの
観終わった後は、自分の心の中にある毒が浮き出てくるような感覚になりました。
まず、何というか、全てにおいてすごく丁寧に作られている印象を受けました。
絵本のような描写、子供や大人の表情、汗の浮き出るシャツ、指の末端の色の違い、小児麻痺の子の足の色の違いや動き、汲み取り式便所のシーン、オーケストラの演奏、駅員さん、お葬式の後にトットちゃんが走っていく中でのすれ違う景色との対比、チンドン屋の音が聞こえた瞬間の赤ちゃんの表情、タバコ等々…
そういった細かな作りからだけでも、作品全編を通して、原作や黒柳徹子さんへのリスペクトや愛情を感じられました。
過去にゲームやアニメの実写化で、監督が原作を知らずに作られたものがいくつかありましたが、この映画は制作が決まった直後に、制作に関わる全てのスタッフに「原作をまず読むこと!」とお達しがあったのではと思うほどでした。
また、子供の喜怒哀楽なんかは、本物の子供とジブリのいいところを随分と参考にしたのではとも思いました。(特に泣くシーン)
映画本編では、小児麻痺の子供が出てきますが、どこかの1日テレビのような「障害」で無理矢理感動を作ろうとしているところがないのもよかったです。
あくまで主人公は「トットちゃん」で、そこがまったくブレていなかった。(トットちゃんは見た目では見えにくい障害)
そんな風に、原作を大切にしつつイチから丁寧に愛情を持って作られているので、制作スタッフにとってこの作品はとても愛おしく、我が子のようなものになったのではないでしょうか。
そして、観た側にとっても愛おしくなるものでした。
個人的には、やっぱり校長先生の人間味がすごく良かったです。
黒柳徹子さんにとって、とても大切な人をとても大切に描いていたのではないでしょうか。
校長先生役の役所広司さんもピッタリで、校長先生は「となりのトトロ」のサツキとメイのお父さんに通ずるものがありました。
校長先生は、子供たちが大切にしているものは何か、常に思っているような人でした。
よく「人を大切に」「親を大切に」「友達を大切に」「自分を大切に」と大人は言うけど、実は「いい大人」に見られる為の綺麗な言葉として投げっぱなしになりがちです。(大切にする方法は???)
でも校長先生は投げっぱなしにならず、子供が大切にしているものを大切にされていました。
「人を大切にする」ということは、「人が大切にしているものを大切にすることなんだよ」と、全編を通して見せてくれました。
そして、それをメッセージ性として観た側に押し付けるようなことはまったく感じられなかったことも心地良かったです。
長くなりましたが、この映画は是非とも多くの人に観てもらいたいです。
基本的に、上映期間中に2回以上同じ映画を観に行くことはありませんが、この映画は最低でもあと2回は観に行きたいと思いました。
オススメです!
トットちゃんの束の間の日常と変わってゆく世界
地味さが逆に眩しい
いのち
ちょうど小学生の時に原作を読みました。私は公立の小学校に通学していたので、トモエ学園の電車の教室に憧れていました。また、「海のもの」「山のもの」も原作で知りました。しかし、この歳になってみれば、トモエ学園の自由な校風が一番魅力的ですね。トットちゃんは今だったら、ADHDの診断がされたり、集団から排除されますから。
子供の時はそれなりに楽しかった学校ですが、今になって思えば、優秀な労働者を作る場所でもあったのかな?と思います。誰とでも仲良く、時間を守って、模範回答を暗記する。
とっとちゃんのお父さんも食料よりも自らの精神性を選んで、軍歌は弾きませんでしたよね。会社で鬱っぽくなっている人は、安定した給料より自分の気持ちに正直になった方がいいと思った瞬間です。
原作を読んだのが小学生の時なので覚えていないのですが、こんなに命を尊んだ作品だったのかと、大変驚きました。ラストに向かって、やすあきちゃんの亡くなった命と戦地に行かされる兵隊のこれから亡くなる命が重なりました。兵隊もトモエ学園に象徴される子供達も、全ての国民はこの戦争で死んではいけなかった。やすあきちゃんの様に病気で早く亡くなる子供がいる一方で、300万人の国民がこの戦争で死にました。戦争がなければ死ななくて済んだ子供達や若者達もです。
劇中に出てくる桜も樹々も街の風景も子供達も生命力に溢れてきらきらと輝いていました。だからこそ、勇ましく流れていた軍艦マーチや死を美化していた当時の国家に怒りを覚えずにはいられませんでした。やはり、国家権力は無責任ではないかと。子供や若者を死に追いやる戦争は、過去の日本だけに限らず、世界中で今現在も起こっています。
残る名作になるポテンシャルはあった
トットちゃんの可愛らしさを表現することには成功している本作ですが、ビジュアル、物語の進行、演出のいずれにおいても一貫性に欠けているように感じてしまいました。
【序盤~教育編】
序盤部分。ADHD的な個性を持つトットちゃんの豊かな発想力と突飛な言動、そして校長先生の温かい心遣いについては原作に忠実に描かれており、素晴らしい出来です。トットちゃんは一見してわかり辛い困難を抱えている児童です。そのため本人にとって悪意のない振る舞いでも周囲から誤解され、咎められてしまいやすい。だからこそ校長先生は鋭い洞察によって「君は本当は良い子なんだよ」と微笑みかける。この言葉は生涯を通じてトットちゃんの心の支えになります。このパートは原作の魅力を見事に映像化しています
【中盤~泰明君と反戦描写】
しかし中盤から泰明君と反戦描写がメインになるにつれ、本作は紋切り型のアプローチが増加し、テーマがぶれていきます。泰明君のケア描写にせよ、トモエ学園を差別する軍国主義児童に反撃するシーンにせよ、トットちゃんが善なる少女という「ストーリー上のステロタイプ」を演じているように見えてしまう。泰明君の死に関しては、障害児の死を利用しているという批判が刺さるまであと一歩のレベルです。直接関係がない子供の死を戦争に接続しようとする演出、そして感動を誘うための過度の強調、どちらも不誠実だと思います
【社会階層の描写について】
本作は教養のあるトットちゃんの周囲の大人=反戦思想、対比される一般国民=軍国主義者の差別主義者、という構図に終始しており、いささかバランス感覚に疑問を感じました。現実にそういった傾向があったにせよ、あまりにも一辺倒過ぎる。鑑賞者を「軍国主義に染まる日本が怖い」という感想に誘導するために、軍国主義者の顔を描かない等の手法で非人間化して恐怖心を煽るのは「子供の視点だから」で言い訳出来る範囲を超えています。格差問題に自覚的なら敵対的と受け取られかねない演出プランは採用しなかった筈です。それこそ高畑勲であれば厳しく戒めたのではないでしょうか
また泰明君~軍国主義日本パートは過剰に演出される一方で、トットちゃんの家族のその後は「明確には語らないが察してください」方式になっており、このバランスも不統一に感じました
(一応フォローすると、中盤以降でも駅員さんの顛末や「尻尾」の話の配置等、優れたパートは複数ある)
画作りについて。背景美術は大変素晴らしいです。キャラデザについても、戦中~戦後の児童漫画のような赤い唇は結構好きなセンスです(ただし子供の顔が歪むシーンだけはやり過ぎに感じます。デフォルメ絵に口紅を入れたからと言ってリアル調と地続きにはならないのでは・・・)。また数回挟まる幻想演出はシーンごとに画風が変わるのですが、オムニバス的で一貫したものを感じられません。幻想演出を入れたいというプランありきで唐突に感じる場面もままあったと思います(どれもシーン単体で見れば素晴らしい出来です)
【まとめ】
原作がエッセイであることや、監督がドラえもん出身である事を考慮すると、作品にストーリー性を与える為に泰明君の準主役化と反戦テーマが盛り込まれたのは理解出来ます。しかしその調理があまり上手ではなかったというか原作の実話ベースの強度と含蓄に比べて脚色が紋切り型で浅いんですね。特に反戦描写は原作から逸脱し、児童視点の中立性を損ねてしまっている点で残念です
もっとトットちゃんの個性と子供視点の中立性を大事にしてほしかったかな
面白かった。
ヒヨコと腕相撲の心理描写に涙
原作未読。ヒヨコが出てくる辺りから感動の連続でした。
トットちゃんは、ヒヨコとの突然の別れで生き物の尊さを学びました。実はこれが物語の大きな伏線だったのです。
トットちゃんと小児麻痺の泰明ちゃんが腕相撲する場面があります。トットちゃんは、泰明ちゃんの小児麻痺による踏ん張れない足を見て、わざと負けます。
泰明ちゃんは「ズルするな」と憤り、この場面でも感動しました。皆と遊ばず読書にふけっていた泰明ちゃんの本心が表れた瞬間でした。
泰明ちゃんは、トットちゃんとの特訓の結果、不可能だった木登りができるようになり、障がい者ではなく、他の小学生と同じように対等な立場でトットちゃん達に接してもらいたかったのだと思います。登場人物の心理描写が巧みでした。
一点だけ気になったのが、米英の攻撃のニュースが入る辺りから敵性語である英語は禁止になるのですが、雨降りの中でトットちゃんと泰明ちゃんを怒鳴ったおじさんが「カレーライス」等と書かれた食堂に入っていった場面です。ライスは英語だよなと思ったのですが、公に禁止になったわけではないので、敵性語は使わない風潮があったという解釈にとどめました。
アニメーションや黒柳徹子さんのナレーションも素晴らしい感動作です。
窓ぎわのトットちゃん
昨今話題の戦争を扱った年末映画4連発。太平洋戦争開戦前夜〜戦中を描いたアニメ映画『窓ぎわのトットちゃん』、戦中末期を描いた実写映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』、戦後を描いた実写映画『ゴジラ-1.0』とアニメ映画『鬼太郎誕生ゲゲゲの謎』。やっと全て観ました。
トットちゃん原作小説は昔から知ってはいましたが未読。こんな話だったのか…と色々びっくりしました。
とっても元気で個性的な女の子トットちゃんが見る世界は、とてもキラキラしていてカラフル。楽しみと喜びに溢れた世界が、じわじわとにじり寄ってくる戦争の気配により静かに彩度を失っていく。戦争ものの映画はどれもそういう色合いですが、太平洋戦争が本格化するまでの日本の街(都会)はこんなにもカラフルで活気に溢れていたのかと。昭和前半の日本というと薄暗いイメージしかなかったけど、たしかにあの華やかな明治を経ているんだからずっと灰色なわけじゃないんですよね。
そんなことを思わされつつ観ていました。子どもの目で見た開戦前夜と戦中。子どもたちに二度とこんな思いをさせてはいけない。と同時に、今海の向こうでまさにこのような中で生きている子どもたちを思わずにはいられない。
やはりキャラデザが…
シンエイ動画の子供描写の積み重ねが反映された
シンエイ動画は「ドラえもん」の制作会社で、特に劇場版では子供たちの躍動や芝居に定評がある。本作では、その技術が惜しみなく使われている。
芝居も動きも圧倒的な物量で、物語も昭和回顧的な予告に反して、ADHDやLDの普通の学校になじめない子供たちの教育(実在した「トモエ学園」)の話で、今日の興味に即するものだった。
また、色彩設計も柔らかく、作中当時のの「童画」(たとえば、松本かつぢなど)の線や、血色の良い肌などが採用され、美術はキャラクターに合わせて水彩の手書き(+取り込みごデジタル加筆)が使われている。
戦争の描写が後半でやや主張しすぎるようにも思うが、
洋服などの色彩、子供たちの動き、音楽合わせのイメージシーンなど、2023年に傑出したアニメーション映画であり、子供たちにもオススメだ。
トモエ学園いい学校!入ってみてもいい学校!
トモエ学園いい学校!入ってみてもいい学校!
暴力を使わず因縁つけてくる奴らを追い払ったトモエ学園のみんなの言葉は本心だろ。
こんな学校が実在したということに感動を覚えた。
小林校長はあたたかいまなざし、ひとりひとりの子どもをちゃんと見ている。時に失言した教師に厳しく指導する姿もリアリティがあってよかった。
夜に電車を搬入するのを見たがっている子どもたちに、ダメだと言わず寝巻きと肌掛けを持ってこいと言える大人がどのくらいいることだろう。
あの戦前戦後の時代に、時間割もなく自由な課題をさせて、物事を探究させるモンテッソーリの学校があったなんて素晴らしすぎる!
小児麻痺のやすあきちゃんを木に登らせる手伝いをするトットちゃん。
木の上からの景色はやすあきちゃんにとって宝物になったと思う。
やがてやすあきちゃんの死と直面する時は縁日のひよこのシーンが重なることでよりトットちゃんの気持ちに近づけた。
父親がヴァイオリンで軍歌を弾きたくないと決意した時の家族の表情も良かった。
建物疎開で素敵な赤い屋根のお家も崩壊。建物疎開などというものがあったということはこの映画で初めて知ることが出来た。
エンドロールの最後にパンダが出てきたのがまた微笑ましいではないか。
黒柳徹子さんのその後の人生にも思いををはせることができた。
黒柳徹子さんの幼少期の事がよく解るアニメ。 本年度ベスト級。
ぶっちゃけ感動も涙も無し。
予告編で観たいと思わなかったけど、本作の舞台となったトモエ学園が自分の地元と言う事で鑑賞。
当時と今の違いを比較したかったけど、今の面影は一切無し(笑)
だけどトットちゃんが住んでる大井町線の千束駅や洗足池公園。
田園調布の街路樹。
田園調布から自由が丘までの線路脇の道。
隣街の九品仏(クホンブツ)浄真寺の天狗の足跡等、自分が行ったことがある景色が登場!
テンションが少し上がる。
黒柳徹子さんと同じ景色を見ていたと思うと何だか感慨深い(笑)
本作は黒柳徹子さんの幼少期の出来事を描いてるけど、ストーリーに繋がりがなくイマイチハマらず。
どうせならエピソード毎のチャプター仕立てにした方が良かったのかも。
そして自由奔放なトットちゃんと思いきや、心の優しい女の子だった。
トモエ学園の小林先生のCVは役所広司さん。
低音で喋るセリフが素敵!
小林先生の教育方針も素晴らしかった。
トットちゃんのお父さんは音楽家なんだけど、予想外に裕福な生活をしているのが不思議(笑)
焼夷弾によりトモエ学園が焼失するんだけど自分が今住んでいる場所にも焼夷弾が落ちたのかと思うと、色々と考えさせられる。
トモエ学園の跡地は今、イオン系の高級スーパーになったけど、値段が高い商品ばかりで買い物に困ってます( ´∀`)
映画的な時間の飛ばし表現が良かった
シーンのテンションが上がった決定的な瞬間に、何かを想像させるインサートを使い物語の時間を飛ばすのはとても映画的でこの物語を語るには効果的だと思った。
主人公のキャラクター造形もとても可愛らしく、色彩に溢れてまた、洋服や家具など当時の主人公の社会的な状況をさりげなく色々な状況を説明しているのがとても秀逸だと思った。まぁ、実際に黒柳さんがそういう生活をしていたということでもあるが。
物語の語りとして、黒味を入れることでどうしてもエピソードの羅列感が出てしまい、全体としての物語的強度が落ちていた。
エピソードにすれば、わかりやすいし、感動もするし、自伝的側面もあるのでそうしたことはある種の語り方だとは思うが各エピソードが全体として機能的だったかというとそうではない気がする。徐々に戦争に巻き込まれいく空気感もいいんだけどね。
でも、なんか見たことによる新しい何かはなかった。
隣のおじさんは凄く号泣してたので、私の心の問題かもしれないけど。
私は何に響いたのか…
原作が発売された当時、母親に勧められて読まされた記憶があるが、内容はほとんど忘れてた。
カラフルで活気に溢れた子供達の生活に、静かに忍び寄る「戦争」と「死」。
自分と異なる他者に対する寛容さ。
「みんな、一緒だよ」
それは「同一」というより「共同体」という意味だ。
校長先生が強く大石先生を叱責したのも、高橋くんに言った言葉が「あなたは私たちと違う」というメッセージになることを懸念したのかも知れない。
最近また「ザ・ベストテン」での黒柳徹子の差別に対する涙の訴え(1980年)が話題になった。
当時、南アフリカの人種隔離政策の中で日本人は「名誉白人」などと呼ばれて優越感を持っていた人々も多かった時期(今思えば、これこそ蔑称だろう)。まだまだ日本人にとって黒人差別が他人事に感じられていた時代に、自らメッセージや具体的な活動を起こした著名人の先駆け。
今や国内の「ユニセフ」は彼女の活動こそが真の姿だと言われるほど。
そんな彼女らしい、可愛らしくてまっすぐで、そして切実な思いが込められた作品。
でも決して説教くさくない。
純粋な子供たちの姿を描いているかと思うと、実は「信念を貫ける大人」と「時代の流れに飲み込まれた大人」の話でもある。
途中で差し込まれるアニメーションもすごく印象的。
原作のいわさきちひろさんの挿絵のイメージにも共通するシーンがあったりと、絵本の様にながめてみたり。
全体通して具体的に「どこで」「何に」と聞かれるとすごく困るのだが、エンドロールが始まって、気付いたらボロボロ涙がこぼれていた。
★は5個でもよかったのだが、個人的には大人のキャラクターの顔(特に「目」)に馴染めなかったのと、もう「役所広司」「小栗旬」。(造形ではなく)そのまま本人がイメージされてしまったので、若干のマイナス。
なぜこれだけ売れた原作の映画化に42年もかかったのか、パンフレットを買ったけど明確には書いてなくて、内容的には物足りない。
でも、間違いなく今年一番涙が出た映画でした。
つくり手の視点
「この世界の片隅に」を超える傑作に
正直スルー予定だったけど、信頼筋の絶賛の多さに慌てて映画館へ。見逃さなくて本当に良かった。
「この世界の片隅に」と並列に語り継がれてほしい名作。戦争シーンはほとんどないのに、日常の中から、おしゃれの自由を奪われ、食品が減っていき、兵隊礼賛になっていく様が説教臭くなく、でも子どもたちが見ててもわかる塩梅で入っている。
小学校を退学させられる黒柳徹子(トットちゃん)にあまりにも共感できなかった原作だった(子供の頃に読んだからこそそう感じていたのかも)けど、トットちゃんが見ている世界と世間一般が見ている世界を、要所に『窓』を活用して見せてくる。何なら大人は視野が狭くなっている、理想を押し付けてくるともさえ言ってくるよう。戦争も大人都合でトットちゃんの人生には必要なし。
学校が素晴らしすぎる。職業柄身につまされる。校長先生は「話をしよう」と声をかけるのに、傾聴の姿勢を忘れない。子どものやることを尊重する。それでも危険な場合は代替案を提示する(相撲→腕相撲)。
小児麻痺を背負うキャラクターも戦争と関係なく…というのが憎いというか上手い(黒柳徹子の体験談なので)。
運動会のシーンから基本的にずっと泣いてた。二人三脚のシーンだけじゃなく、鯉のぼりも先生の見つめ直し含めて良かった。
ラスト15分はただただ怖かった。アニメーションでしか描けない終わり方だったと思う。
黒柳徹子のナレーションが最初と最後に。何度も実写化のオファーを受けたらしいが、この座組でアニメーションで映画化したことにリスペクト。
全252件中、161~180件目を表示