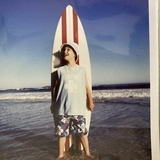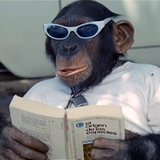映画 窓ぎわのトットちゃんのレビュー・感想・評価
全252件中、121~140件目を表示
話の本筋が見えない…
今年ラストのプレビューはトットちゃん
【加点ポイント】
天真爛漫で自由奔放なトットちゃんには好感がもてる
【減点ポイント】
脚本が酷いのか尺の関係でカットしたのかわからないけども、主要の登場人物なのに補足エピソード一切なかったり突然フェードアウトしたりする
ただ尺の関係だとするとちょいちょい余計なエピソードも盛り込まれているからやっぱり脚本でしょう
【総評】
結局何を観客に伝えたいのかわからない作品になってしまったので、脚本変えて作り直したらもっと評価されそう
命と音楽
泰明ちゃんの葬式から飛び出して、出征の列を逆走するトットちゃん
戦争ごっこする子供達、四肢欠損した兵士、戦死した子供のお骨を抱えて泣いている母親、それらを振り払うように必死で走る
特にセリフはないが痛いほどトットちゃんの気持ちが観客に伝わってくる
反戦映画として本当に誠実な描写
また音楽が持つリズムの楽しさを学校で教わってからの、リズムによる全体主義社会への反撃
お父さんの音楽家としての矜持等、音楽演出もとても素晴らしかった
個人的な話になるが、祖母の兄が学校で教師をしており学校に爆弾が落とされて亡くなったという話を思い出さずにはいられなかった
昭和初期の時代
実話の持つ圧倒的な説得力 小林先生の教育への情熱 演じる役所広司、大野りりあが素晴らしい
大ベストセラー「窓ぎわのトットちゃん」40年ぶりのアニメ化作品。
メジャーすぎるので観るのやめようか迷っていましたが、やはり観て大正解!
著者が在学していたトモエ学園での生活と、その小林校長先生の教育への情熱が、実に生き生きと描かれています。
導入から、今では失われた素朴な昭和初期の生活や子供たちの行動に泣いて、中盤は小児麻痺だった泰明ちゃんとの交流で泣いて(特に泰明ちゃんが服を汚して帰ってきたことが嬉しくてなくお母さんのシーン!)、終盤はひたひたと迫りくる戦争の影に恐れ、小林先生の教育に対する無限の情熱に感動しました!
黒柳徹子の実話の持つ圧倒的な説得力、今¥ばやし先生の人間力に感動しました。
小林先生を演じる役所広司のどこまでも広く暖かい心と秘めた厳しさ、トットちゃんを演じた大野りりあが素晴らしかった。
素晴らしかった
今だからこそ映画にしたんだね。 重いわ。。 上映が終わって言葉少な...
今だからこそ映画にしたんだね。
重いわ。。
上映が終わって言葉少なな時間に歩き出しながらなんともまとまらず話したことばはそれくらいでした。
観る前は絵が苦手に感じられて行くか悩んでいた映画。本は子どもの頃に読んでいたはずなのだけどトモエ学園の景色は頭の中では電車が一両だけで、最後まで読まずにいたのか戦争前〜戦中の肌感や経済的なことなど想像もつかないまま印象的なシーンだけを記憶していたのを実感した。
校長先生の教育は、全体主義への単なるアンチテーゼに過ぎないのだろうか
原作未読です。
なので、原作を読めば作者の真の意図が理解できる可能性があるので、僕の勘違いであった場合は申し訳ありませんが、幾つか気になった点がありましたのでレビューします。
まず、①果たしてともえ学園の教育(校長先生の教育といっても良いかもしれません)は、その当時の時代背景を考慮しても手放しで賞賛するべきものでしょうか。
一人一人の子供の「個性を活かす教育」「誰一人置いてゆかない」は、実はなかなか実現できない難しいものなのです。不可能ではないにしてもそのような教育は、とにかく手間とお金(環境ともいえますが)がかかります。
子供が大勢いた戦後から団塊の世代などの時代は、ともかく子供が社会に適応して生きていくように社会に送り出すことを最優先にしなければならない時代でした。いわば溢れかえるひな鳥のような子供たちを養鶏の「ブロイラー」のようにギチギチに「檻」に閉じ込めて、とりあえず社会に最低限適応できるように、次々と送り出さなければならない。
先生たちも人間ですから、そのような状況にもちろん疑問を持ち悩みながら、でもそうせざるを得ない時代背景があったのです。よくないと誰もがわかっていながらも、「効率」を第一にするしかなかった不幸な時代が長かった。もしかしたら、今もその名残が残っているかもしれません。
そういう時代であったので「檻の狭さに収まりきれなかった」とっとちゃんは、公立の尋常小学校という「ギチギチの養鶏場」から弾き出されてしまったので、私立の学校に行くしか選択肢がなかったのです。
ともえ学園の校長先生は、とっとちゃんの取り留めの無いを4時間興味深く聞きました。確かに素晴らしいことですが、公立の先生にそれができる余裕があるでしょうか。
最先端の外国の教育理論も取り入れて、素晴らしい教育環境も実現できて(電車の教室とか)、人格的にも素晴らしい校長先生は、理想を実現した素晴らしい方であることは確かです。国民的スターなどを生み出したことは確かに賞賛に値することですし、素晴らしいことであることに間違いありません。
しかし「貧弱な」公立教育であったとしても、無数の名もない教師たちが大勢の市井の人々をなんとか生活できるように社会に送り出す仕事を担ったおかげで、このともえ学園と言う「恵まれた囲いの羊たちの奇跡的な教育」が存在できたということは、見落としてはならないポイントだと思います。
そういう視点がないと、「ともえ学園・校長先生は素晴らしい。それに比べてウチの子の学校は・先生は」という勘違いの批判・不満を持ってしまうのではないかと危惧しました。
それから、ともえ学園の校長先生の言葉に引っかかった部分がありました。
「とっとちゃんは、本当はいい子なんだよ。」という、言葉です。
自分を卑下することなく、自分に自信を持って良い、という意味で言われているのだと思いますが、それまでの経緯を考えると、またともえ学園の役割から考えると、果たして適切な言葉なのだろうかと思いました。
「いい子」とは何でしょうか?それは、「大人にとって都合のいい子供」です。
尋常小学校で求められるのは、そういう子供です。限られた時間・限られたリソースで、効率よく子供を社会に最低限適応できるように「仕上げる」のに「都合のいい子」です。そこに、きらめくような個性・感性は必要ない…むしろ押し殺すもの・捨て去るべきもの、であるはずです。
僕ならとっとちゃんにこのように言ってあげたい。
「君はとっとちゃん。他の誰でもない。ここでは、君はそのままでいて良いんだよ。大人にとって都合のいい子になる必要はないんだ。君は君のやりたいことを君のできる範囲でやって大丈夫だよ。」と。
そして、②「戦争」に対する自虐史観的な全体主義への通り一遍の批判めいたものに違和感を感じました。
映画の中では「ともえ学園の「個人(尊重)主義」」と対立する図式で「戦争・全体主義」が対比されていたように感じました。
これも、あの当時の時代背景を考えなくてはならないと思うのです。
この映画を見ると、校長先生の言うように「見ても・聞いても、理解しない。自分の頭で考えない。」ことが戦争を引き起こし、ひいては戦争協力へと人々を駆り立てていった。と言うふうに描かれているように思えます。自虐史観的な。
しかし異論は認めますが、あの当時の日本は外国の圧力のもとで、いやでも戦争をせざるを得なかった状況にあったし、もし日本国民の全てが「私は人を殺したくないので戦争に参加しません」と兵役を拒否したら、すぐさま日本は植民地になっていたでしょう。
今の日本を礎いたのは誰でしょうか。国民のうちごく少数は無批判に妙な愛国心に燃えた「自分の頭で考えない人」であったのかもしれませんが、大多数はただただ日本の国の将来を思い、家族を思い、自分を捨てて命をかけて戦った大多数の名もない人たちだったと言うことを忘れてはならないと思います。
私達はいつも目立ったスターを賞賛します。
TVの向こうには、そういう人たちがいつも輝かしく映し出されています。
とっとちゃんも、もちろんご自分の弛まぬ努力の故にだと思いますが、日本でもナンバーワンのTVのスターになりました。ご両親や、ともえ学園の素晴らしい環境、ともえ学園の校長先生、その他、いろいろなことに恵まれて、「困った子」がスターになりました。
しかし、僕たちのような平凡な市井の人々は、TVに写ることのないのこちら側の人、です。
TVに輝かしく映し出され・賞賛される「スター」と比べて、恵まれない自分を惨めになったりします。
しかし、社会は「スター」だけで成り立っているわけではありません。
社会の大部分は、恵まれた環境で生まれることがなく、教育にお金をかけることもできず、チャンスにも恵まれず、いい仕事にも就けなかった、その他大勢の人によって成り立っているのです。TVに惑わされず、そのことに心から気づいた時、人はありのままの自分を受け入れることができる。そう思います。
子供も楽しめる楽しくて明るい作品かと思ってみましたが、後半は暗い雰囲気かつダークな内容で(ホラー的要素はありませんが)、子供はあまり楽しめない作品ではないでしょうか。しかし、大人は教育論について考える良い機会になると思いました。むしろ大人に観ていただきたい作品です。美麗な映像と、人物の独特のアニメ表現(唇が明るい)は、良いと思いました。
滝沢カレン=全力!脱力タイムズ
アニメーションは美しく、音楽だって素晴らしい。役所広司演じる校長先生には癒され、学ばされ、グッときた。「小林先生と子どもたち」にタイトル変更した方がいいと思う。総じていい作品ではあったんだけど、木登り辺りから間延びしているし、ラスト際はなんか締まらない感じでスッキリしない。しかも、肝心なトットちゃんの描きが薄い。
裕福な家庭なだけに、戦争が激化していくと生活が一変し、ものすごく悲しい気持ちになる。ここら辺の描写はピカイチ。それなのに、長いと感じてしまうもんだから泣けないんだよね。杏、小栗旬に至ってはエンドロールまで分からないレベルで上手かったし、役所広司も言わずもがな。だけど、滝沢カレンは滝沢カレン過ぎるぞ。脱力タイムズ始まったかと思ったわ。
※Filmarksより引用
アニメらしさを活かした独特な世界観
芸術作品的な映画!!!
トットちゃんから日本社会・地球規模のメッセージ
幼少期の徹子さんの人一倍ピュアな女のこの目で描かれた物語
マスクびしょ濡れ😭
切符切りの駅員さんが懐かしい
昔、家にあって読んでたはずの「窓ぎわのトットちゃん」ですが、大まかな筋しか覚えてなかったので改めて鑑賞。
映像になると、駅員さんの切符を切る姿が懐かしいなぁ、と思い。駅によって切られた時の形が違うのも味わい深かったのに、いつの間にか自動改札が◯にしか穴を開けなくなり、
いまや交通系ICでは切符の存在自体が無い。
たまに訪れる旅行先でICが使えない駅だと久しぶりに切符を買う感じで、切符1つにも時代の移り変わりを感じる。そんなことを思い出させてくれる映像でした。
*****
トットちゃんや、ヤスアキちゃんが当時としては裕福な家の子ども達だったんだな、と改めて思い、
また黒柳徹子さんが芸能人として自分の特性を活かせる仕事に就けて良かったと思いました。
黒柳さんの逸話で今も覚えているのが昔のテレビ番組「笑っていいとも」のテレフォンショッキングで、ゲストとして出演するも、1時間番組なのにそのほとんど、多分40分か45分くらい??だったかとにかくおしゃべりがあまりにも長すぎてでも司会のタモリさんが遮ったり途中で切り上げさせることすらままならない脅威のおしゃべり故、番組のほとんどのレギュラーコーナーが出来ず〜〜!!という、生放送ならではの、そして黒柳さんならではのハプニングで番組が放送されたというもの。
黒柳さんのおしゃべり好き、自由奔放さ、他の人とは違う行動や考えをするところが幼少期の一般的な学校では「問題児」とされるところ、
大人で芸能人であればそれは「個性として面白い!」となって評価されるというか。。伝説にもなる。そんな長時間話すゲスト、後にも先にも多分黒柳徹子さんしかいなかったんじゃないかと思うし、面白さを追求するテレビ番組という舞台であればそんな奔放な行動も良しとされる(スタッフさん達は進行が滞り、焦りまくりだったかもしれませんが)。
小林先生のような、子どもの個性を受け止めてくれる教師やそんな学校があって本当に良かったと思う。
映画を見ながら、「もし自分がトットちゃんのような性格なら?」とか「もし自分がトットちゃんのお母さんの立場なら?」とか色々考えました。
話を聞いてあげる、って大事なんだなと思い、また戦争でトモエ學園も焼けて無くなってしまいましたが、本にしたことでこうして映画化され、多くの人の目に残る形になり、とても良かったと思います。
校舎は無くなっても、小林先生のような考えを知ることが出来て良かったです。子ども時代にこの本を読んでいてもあまりよく分からなかったこと、感慨深くは思わなかったことが、大人になって実感することが出来て、見て良かったと思いました。
*****
私も子ども時代にお祭りでヒヨコを買ってもらったことがあって、その子は羽が白く成鳥になるまで育てられましたが、とても可愛いヒヨコだったことを思い出せて嬉しかったです。
磨き抜かれたクオリティ
期待外れ
知り合いからのすすめだったが、いまいちピンと来るシーンもなく、「泣いた」「感動した」というレビューを目にして、いったいどこの辺りが泣き所なのか私には不明。
作中の時間の流れが速くなったりゆっくりになったりするのも作品に没頭できない部分のひとつ。
トット助
もっと早く観に行けば良かった
原作は未読。可愛らしい絵でトットちゃんとお友達の友情ほっこりストーリーかなと思っていましたが、心に沁みまくるお話で、めちゃめちゃ泣きました。
楽しかった日常が…毎日会っていた人たちが…
毎日普通に暮らせることに感謝。映画を観てから黒柳さんがテレビで平和のことについて話されてるのを観てまた涙が出ました。
トットちゃんのお家にいたロッキーのことも徹子さんのナレーションで聞きたかったなあ。
原作読んでまた泣こうと思います。
あっという間に上映回数が減ってしまってるけど、もっと長くたくさんの人に観てほしいです。
心の成長物語
黒柳さんが自分で話しているとおりADHDだと人目でわかる少女時代。
小学校を追い出され、たどり着いたトモエ学園で出会った校長先生が彼女の人生を大きく変えた。子供のあるがままを受け入れ、子供の自主性を育む教育は、画一的な教育とは対象の理想の教育像だと思いました。それを嫌味なく対比的に描いた序盤は成る程と思いました。
小児麻痺のヤスアキ君が自身の障害を気にして後ろ向きだったのを、黒柳さんが引っ張ることで前向きになっていく描写もすごく良くできてました。
縁日で買ったヒヨコが死ぬシーンで号泣し死というものを理解したシーンは、その後、ヤスアキ君が死ぬシーンと繋がっていたのかと思い、良く構成されているなと思いました。
ヤスアキ君との関わり合いを通じて、黒柳さんの心も成長していったのが分かりますし、最後に青森に疎開する際に弟が愚図り抱いているシーンで、小林校長先生が自分にかけた言葉、『良い子』という言葉を発するのは少し大人になったというシーンを現していたんだなと思いました。
全体を通じて絵が綺麗ですし、作画も素晴らしかったです。それもあって、華やかであった生活が戦争によって暗い影を落としていくところも際立っていて、色の基調も華やかさがあるものから暗いものに変わっていくのも考えて作られており、戦争の愚かしさも表現されていたなと感じました。
黒柳さんの自伝ではありますが、とても考えられた作品で秀作だと思います。今の子供たちにも見てほしい作品でした。
モンテッソーリ?校長先生と子供たちが生き生きしている
絵と世界観は5、ストーリーが前半と後半で分離した印象のため4、校長先生を主役にして描くともっと分かりやすかったかも。
子供が見たいと言ったので見てきました、前半は笑いながら見ていて楽しかったそうです。後半の戦争の描写は怖かったそう。
トットちゃんが友達を笑わせていたところが面白かったとのこと。
わたしとしては戦争というものを教えるのにちょうどよかったかなと、食べ物が無くなったり、配給制(お金が役に立たない)、疎開、日本が敗戦国で独伊と同盟国、戦いは良くない、侵略される可能性も0ではない、とか。
トモエ学園、わたしモンテッソーリ教育の学校だとずっと思いこんでいて、さっき調べたらリトミックの学校だったのですが、いやどう見てもモンテッソーリにしか見えない。
子供の自主性に任せた教育は素晴らしいと思ったけど、なかなか時間などの問題もあり現実には難しいかな。
あるがままを受け入れてもらった子(愛された子)は強いなと改めて思った。最後に言う台詞は自分が子供のときに言ってもらった台詞。
人は良くも悪くも自分がされたことしか本当の意味では理解できない。優しくされた子は人にも優しくできる。
リアルタイムで読んだ本、話すことがなくなるまで校長先生に話したエピソードは覚えてる。母が私に読めと言いましてね(自分が読んで良かったからと言われても当時低学年)。あんまり覚えてないからまた買おうかな。
子供って、そおゆうとこあるよね~と、うなずいてしまいたくなる場面がいっぱいで微笑ましい。大人向の映画です。子供には少し難しいかな。
クリスマスプレゼントが足りないとのクレームが先ほど娘からあり、明日買い足すべきか悩む、トモエの校長先生ならどうするのか?。(昨日一緒に買ったよね?サンタからの分が足りないそうでね、サンタの分…)
全252件中、121~140件目を表示