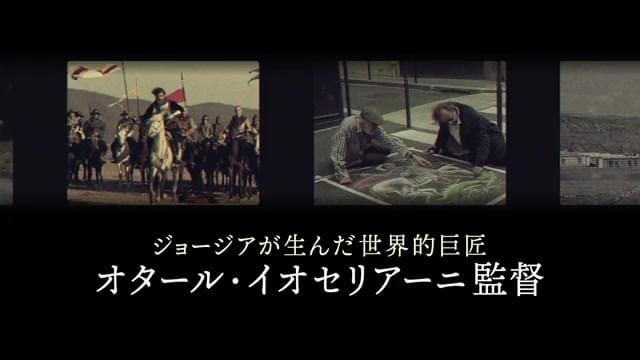鋳鉄のレビュー・感想・評価
全3件を表示
【ジョージア出身のオタール・イオセリアーニ監督がジョージアのルスタビ冶金工場で働く工員たちの日常を捉えたドキュメンタリー映画。そして、NOBUの若き時の、鋳造経験を記すの巻。】
ー 私が働く会社にも、鋳造工場がある為、面白く鑑賞した作品。-
■ジョージア南部のルスタビ冶金工場で働く工員たちの日常を捉え、溶鉱炉での過酷な作業や、休憩時間に喫煙しながら談笑する姿などを映し出した作品。
◆感想
・驚くのは、作業環境の過酷さである。飛び散る火花どころではない、花火の様に作業者の身体に降り注ぐ火花の中で、平気な顔をして、炉から流れ出る湯(鋳鉄を溶かしたものの事を湯という。)の道を砂で作り、型に流し込んでいる。
・今では、殆ど機械化されている鋳造の過程が、ほぼ手作業で(もちろん、道具は使うが)行っているシーンはとても面白い。
・けれども、あの作業環境だと、塵肺になると思ったし(誰も、マスクなどの保護具を付けていない)現代だったら、労働基準監督署から指導されるレベルの環境の悪さである。
だが、工員たちは平気な顔で働いているのである。
故に、冒頭でオタール・イオセリアーニ監督は工員に対して、敬意を込めたテロップを流すのである。
<今作は、ジョージア出身のオタール・イオセリアーニ監督が、ジョージアのルスタビ冶金工場で働く工員たちの日常を捉えたドキュメンタリー映画である。>
■私が新入社員だった頃、上司から”現場に行って、職制たちの生の声を聞いてこい。”と言われ、全工場を三カ月かけて回り、職制たちに作業環境の問題点や、人事制度(特別作業手当等)に対する意見を聞いて回った事がある。
何故か、何処の工場の職制も優しく色々と教えてくれたが、特に鋳造工場の職制たちは”○○君みたいに、現場に来る人事の若い奴は、初めてだ!”と言って、鋳物のイロハから教えてくれたモノである。
驚いたのは、特に皆に慕われていた親分みたいな職制は(付き合いは、その後20年近く、その方が定年になるまで続いた。)湯の表面を見て、湯温を±50度の範囲で当てた事である。”簡単だよ!””と言っていたが・・。その方を、後年に愛知の名工に推した事は言うまでもない。
そして、鋳物工場に配属された新入社員に手込めで簡単な製品を作らせる”鋳物道場”で、”○○君、家を建てたんだろ!家の表札作るかい。型は俺が作っておくからさ。”と言って、後日そこで自分で砂固めから、湯口を切り(結構難しい。)型を入れてから型抜きをし(これも、難しい)湯を入れた(怖い)モノである。
そして、後日“出来たよ!”と連絡が入り、イソイソと我が家の鋳鉄製の表札を取りに行った。当然、その見事なずっしりと重い黒光りする表札は、今でも、我が家の玄関に鎮座しているのである。
月曜に乾杯の
巨匠イオセリアーニによる、製鉄所での鋳鉄のようすを描く短編ドキュメンタリー
イオセリアーニ映画祭にて視聴。
『エウスカディ、1982年夏』他、短編1編と同時上映。
ルスタヴィ冶金工場で働く工員たちの姿を描いた短いドキュメンタリー・フィルムで、まだイオセリアーニがグルジア時代の作品。
1964年ということは、監督は30歳。
ちょうど『四月』の2年後、『落葉』の2年前といった時期にあたる。
監督はこの作品を撮るために、なんと身分を隠して4カ月もこの工場で精錬工として働いていたらしい(!!) 同じ日に彼の半自伝的映画『汽車はふたたび故郷へ』を観たけど、若い頃のイオセリアーニって結構脱法的というか、かなりめちゃくちゃやってるんだよね……(笑)。
内容的には、ロジカルなカメラワークとモンタージュが縦横に駆使されており、まずは「短編映画」としてきちんと成立している。イオセリアーニが、若い頃から「技術的」にすぐれた映像作家であったことが確認できるはずだ。
コンテの組み立ては、どこか「音楽的」だ。
まず第一楽章にメインテーマとなる「鋳鉄」がガツッと呈示され、中間楽章で冷えて固まった鉄鉱石をこそげとる単純労働と工員たちの束の間の休息が描写され、終楽章にふたたび派手で豪快な溶鉱炉の作業がドカーンと出てくる。そして、工員たちが帰途につくエピローグ。
もとは作曲家だったイオセリアーニらしい、絶妙の感覚だ。
(そういえば、僕はブルックナーの8番や9番のスケルツォ楽章を聴くたびに、なぜか夜の鉄工所で巨大な機械が製鉄している様子を思い浮かべてしまう。)
フィルモグラフィ上は、ジョージアの風土・文化と名もなき民を称揚し、フィルムに焼き付けるという傾向の強かった初期イオセリアーニにとっては、「家族」を描いた『水彩画』、「自然」を描いた『珍しい花の歌』、「古い街」を描いた『四月』に続いて、名もなき工場労働者の姿を刻印した作品ということで、きわめて重要な位置を占める。
このあと、「民族音楽」を記録した『ジョージアの古い歌』、「ワインづくりの職人」の姿を描く『落葉』、「農村の生活」の様子を描く『田園詩』と続けていったうえで、彼はフィルモグラフィとしての「ジョージア探求」に、いったんの区切りをつける。
そして第一次パリ滞在を経て、総括的なドキュメンタリーとしての『唯一、ゲオルギア』と、イオセリアーニ的群像劇の形式でジョージア(グルジア)の暴力史をまとめあげた『群盗、第七章』を結実させることになるわけだ。
『鋳鉄』には、どこかホモソーシャルでインティメットな男どうしの醸し出す空気感や、黙々と完遂される「労働」における身体言語の美しさなど、イオセリアーニの作品を貫く核心のようなものが、ちゃんと備わっている。
これ単品で観てもしょうじき仕方ない気はするが、イオセリアーニの業績を考えるうえでは無視できない作品だと思う。
全3件を表示