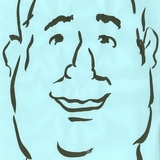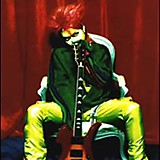君たちはどう生きるかのレビュー・感想・評価
全762件中、401~420件目を表示
君たちはジブリから何を学ぶのか。
様々なこの映画に対する批評があるけど、「君は石を持ち帰れるのか、そうでないのか。」それだけだと思う。
それさえも分からないという人はそこまでなのだと思う。
意見が分かれるのは分かる。けど・・・。
鈴木敏夫プロデューサーの「いままでいろいろな情報を出しすぎていて、観る方の興味を削いでしまっていたのかもしれないと思ったんです。最初は通り一辺倒の宣伝だけでもしようかなと思っていたのですが、一切宣伝しなかったらどうなるのか興味があった。これだけ情報化された時代に、情報がないことが、エンターテインメントになると思ったんです。」との意向がある以上、情報が入り込んでしまう前に観たかったので急いで(それでも公開から6日も経っちゃったけど)。
映画自体の内容はさておき。
これまで宮﨑駿監督が作ってきた映画のエッセンスが、あちらにもこちらにも散りばめられていて、これまでの宮﨑映画の回顧録のような感じがした。
その上で、宮﨑駿監督の「君たちはどう生きるか」に込められた意図を自分なりに酌むと、”(監督である)僕はこう生きてきた。で、「(観ている)君たちはどう生きるのか」”と問われていると感じた。
拡大解釈なのかもしれないけど。
監督の”こう生きてきた”の部分が、これまで監督(やジブリの方々も共通して持っている?)が映画に込めてきた”反戦の思い”や”危うい世界を変えていきたい”という根底の部分を作品を通して表してきたことならば、その意思を受け取って受け継いでいってほしい、との願いが”大おじ”の言葉そのものだったのかもしれない、と思う。そして、主人公の牧眞人(ここでは監督自身の分身)は、”大おじ”とは違う方法でそれを達成したい、とも。
までも、色々と詰め込み過ぎたので、内容の1つ1つを理解するには膨大な時間が必要な気がする。その意味で、この映画自体の意見(賛否)が分かれるのかな、と思う。
ジブリファンは絶対に見るべき
恐らく、宮崎駿の遺作となる作品。
「難しい」「分からなかった」というレビューがされている当作品だが、個人的には物語のテーマとしては極めて単純だと思っている。
戦時下で極めて裕福な家庭に育ったものの幼い頃に母親を亡くした主人公。
その後、父の再婚をきっかけに田舎に引っ越す事になった彼は、受け入れられない母親の死、新しい母親の存在、あまりにもお金持ちすぎて子どもの愛し方がズレている独善的な父親等、鬱憤を抱えていた。
本作は、そういった悩みを「塔」というファンタジーの世界での経験を経て乗り越えていくという、主人公と周りの人たちの成長を描くストーリーである。
(本質的にはトトロや千と千尋の神隠しと変わらないのではと個人的には思った。と見せかけて、もっと深いテーマがあるのかもしれないが)
そんな、不思議な世界での成長物語であるが、演出が素晴らしく(作画、気持ち悪い、怖い、不安になる表現)この表現は、宮崎駿にしかできない、宮崎駿は天才なんだと改めて感じた。
ポスト駿が誰になるのか議論され続けてから何年かたつが、改めて宮崎駿の圧倒的なレベルの高さを世に知らしめたのでは無いか。
加えて、鈴木敏夫のプロモーションを殆どしないという方針により、これからどのように作品が進んでいくのかという不安感と作中のダークな雰囲気が見事にマッチしているのが見事だなと。
ギャル「駿って鬱なん...?」
『君たちはどう生きるか』の批判者について考えてみた
『君たちはどう生きるか』で言っておきたいこと二つ、三つ。
否定的な意見が多い理由について。
やってることは、宮崎駿のフィルモグラフィーにおいて、『千と千尋…』の頃から同じ、テーマ的にも映像・演出的にも、詰め込めるだけ詰め込んだ「全部乗っけ」の作品。
この作品だけが酷評されるのはおかしい。
でも、この作品が批判される理由は、よくわかる。
作品内容ではない、観る者に原因がある。
なお、私はそんなにまで、ムキになってかばう程のジブリファンではない。
むしろ、ラナやシータやクラリスを苛める、宮崎駿のいじわるロリコンっぷりが嫌いだった。
ロリコンはロリコンを嫌う。
スタンド使いはスタンド使いと引かれ合うとは逆の標語ですね。
さて、…『千と千尋』以降の、『ハウル』『ポニョ』『風立ちぬ』には、全方位に向かって喜怒哀楽を満足させようとしてくる、宮崎駿のスキゾっぷりがあった。
入れるテーマ、モノは全て入れてある闇鍋カオス状態みたいな内容だった。
でも、ちゃんと面白かった!
では、『君たちはどう生きるか』はどうか?
その違いは、鈴木敏夫プロデューサー主導の、宣伝なし・予備情報なし、の秘密戦略があった。
これにより、これまでの作品の豊富なスポンサーによるヒットを援護する宣伝がなくなった(今作において興行収入的には作戦成功)。
例えばテレビCMなどでの「ハウス食品は、スタジオジブリの新作『ハウルの動く城』を応援します」などがなくなり、つまり、その、CMなどで視聴者に印象付けられる、作品の一部紹介によって醸される【方向性】が一切なくなった。
ああ、これは、こんな話なんだ、と思わされることがなくなった。
⚪︎少女が迷い込む世界での成長
⚪︎おばあちゃんになっちゃった娘を愛してくれる魔法使い
⚪︎海の女王の娘が人間の男の子を好きになっちゃった
⚪︎空に憧れた青年が、航空機の設計士となり、病弱な奥さんとともに、戦争に突入していく
かように、まあ、見る者は、一行で語られるような話の方向性が、CMなど、もしくは作品紹介の数十秒の映像でナレーションとともに植え付けられる。
…だけども、そう言った事前情報がないことによって、映画を「誘導者」なしで観ることになり、自分の観点が進むべき、物語の方向性の道筋を、自ら探す訓練の出来てない者は戸惑ってしまい、つまらなく思えてしまう、のだろう。
いや、先程の一行概略以上に、「千と千尋」以降の宮崎アニメは、凄まじいギミック、サイドストーリー、色彩に彩られる。
そして今回、10年ぶりの宮崎駿の長編新作である。
SNSは、多くの問題をはらみつつも、熟成の時を迎えている。
ホームページ、ブログ、フェイスブックの時代からの意見者は高齢ともなり、批判はあまりしなくなっている。
良いとこを取り出した方が、残り少ない余生を楽しめるからだ。
でも、ツイッター、インスタなどの、比較的新しい、波及力のあるSNSでは、まだまだ、それを活用する者は「若い」「青い」、これは年齢のことではない、批評歴の浅さのことだ、そう言った人は、批判からはじめる。
批判できる自分に優越感を感じている側面もあろう。
巨匠にもの申しちゃう、しちゃえる自分、と言う優越感。
【10年ぶり】の宮崎アニメ新作は、その、恰好のマトになったとも言える。
わからないってことは、なかなか恥ずかしい側面もあるけど、わからないわからないと、それを根拠に批判できちゃう凄さ!
うらやましいほどの、それは「若さ」だ。
で、今回の宮崎駿の新作を見て、それぞれが下した判断こそが、「君たちはどう生きるか」なんだよなぁ。
さて、ちょっと作品内容に触れる話も書いておく。
大おじ様は、不思議な塔の中の世界を左右する、神のような存在であることに専念していた。
異世界に没頭していた。
だが、その世界は終わりを迎えようとしていて、次に、自分の血縁である若い主人公・眞人に、塔の中の世界の管理者を任せよう・移行しようとした。
これは、『エヴァンゲリオン』での、人類補完計画を推進した碇ゲンドウと、現実世界は辛く厳しいけど、そこに戻そう・戻ろうとするシンジ君と重なる。
宮崎駿監督は、この作品でも、まだまだ若く、貪欲で、昨今の流行りの作品に全方位で戦いを挑み、故に、こうしてエヴァも例外じゃなく取り込んでいる。
で、眞人も、シンジ君のように、ファンタジー世界で生きようとはせずに、家族で生きるに辛さもある…、戦争も激しくなる世界に戻って行く。
「君たちはどう生きるか」の答えを出すわけだ。
そして、ファンタジー世界で知り合う、若い頃の母親(不思議の国に迷い込んでいたエプロンドレスのアリスのような美少女)も、確実に死ぬ運命があるのに、【自分が亡き後の世界に希望を見い出し】、自分の現実・時代に戻っていく。
嗚呼、書いていてホロッとしてきた。
この、お母さんのパート、『想い出のマーニー』みたいだし、『まどか☆マギカ』みたいだし、
いや、これだけでなく、凄まじい数の既存作品に、宮崎駿は、若さをもってして、全方位に戦いを挑んでいる。
それは、「俺も、この程度なら同じふうにやれるんだぜ」ではなく、「俺なら、そのテーマをこう表現する、凄いだろ?」の、力を見せつけてきている。
宮崎監督、今作から、宮崎の「崎」の字を改名している。
ザキの右上の作りが「大」の字から、「立つ」の字になっている。
最初みたとき、なんか違和感を感じて、僕は、自分がゲシュタルト崩壊したのかと思っちゃいました。
しかし、これは、うげっ! 😵
新生・宮崎駿の爆誕を意味します。
この人、まだまだ、これから、やるんですよ。
なお、「千と千尋」以降の、混沌混濁した、とっ散らかされた、しっちゃかめっちゃかの宮崎作品ですが、
海外では大ヒットする可能性があります。
それは、海外版だと字幕になるからです。
難解と言いますか、庵野監督の「エヴァ」もそうですが、数々の読み解きを必要とする「千と千尋」以降の宮崎アニメですが、わりと細かいセリフで筋を通してはいるのです。
物語とセリフを詳細に考えていくと、なるほどと納得も出来るのです。
字幕は、その咀嚼により、記憶への定着が深い。
だから、海外での字幕での鑑賞で、評価が高まる可能性がある。
(追記)
と、ここで、新しい情報が入りました。
アメリカなどでは、海外のアニメの上映は、吹き替えが主流なんだそうです。
それじゃ、日本人が日本で鑑賞するのと、まあ、さして変わらない環境なんだね。
ありゃま、俺の終盤の主張が根本から覆された!
宮崎駿のイマジネーションが炸裂
本作は元々は同名の小説からインスパイアされたということだが、基本的には宮崎駿の完全オリジナル作品となっている。
ただ、後で調べて分かったが、元となった小説(未読)は主人公の少年と叔父さんのやり取りを中心とした青春ドラマということである。本作にも主人公・眞人の大叔父がキーマンとして登場してくるが、おそらくこのあたりは小説からの引用なのだろう。眞人は大叔父から”ある選択”を迫られるが、これなどは非常に重要なシーンで、正に本作のテーマを表しているように思った。穿って見れば、それは宮崎監督自身から観客に向けられたメッセージのようにも受け止められる。「君たちはどう生きるか?」と問いかけられているような気がした。
映画は東京大空襲のシーンから始まり、眞人の疎開先での暮らし、家庭や学校の日々がスケッチ風に綴られていく。不思議なアオサギが度々登場して眞人をからかったりするのだが、それ以外は極めて現実的なシーンが続く。
映画は中盤からいよいよファンタジックな世界に入り込んでいく。眞人の不思議な冒険の旅は先の読めない展開の連続でグイグイと惹きつけられた。
ただ、ここ最近の宮崎作品は、前作「風立ちぬ」は例外として、理屈では説明のつかないエクストリームな世界観が突き詰められており、本作も例にもれず。宮崎駿の脳内が生み出した摩訶不思議なテイストが前面に出た作品となっている。そこが人によっては難解で取っ付きにくいと思われるかもしれない。
そんな中、個人的に印象に残ったのは、ポスターにもなっているアオサギのユーモラスな造形だった。鳥のようでもあり人のようでもあり、得体のしれない不気味さも相まって強烈な存在感を放っている。最初は眞人と対立しているのだが、一緒に冒険をするうちに徐々に相棒のようになっていく所が面白い。
また、終盤の大叔父との邂逅シーンには、「2001年宇宙の旅」のような超然とした魅力を感じた。宇宙の誕生と終焉を思わせるビジュアルも凄まじいが、何より”あの石”に”モノリス”的な何かが想起されてしまい圧倒された。
他に、魂と思しき不思議な形をしたクリーチャーが天に向かって飛んでいくシーンの美しさも印象に残った。しかも、ただ美しいだけでなく、魂たちの向かう先には過酷なサバイバルが待ち受けている。これを輪廻転生のメタファーと捉えれば、生まれ変われぬまま朽ち果てていく魂もいるというわけで、その哀れさには切なさを禁じ得ない。
このように本作はファンタジックな世界に入る中盤あたりから、常識の範疇では理解できないような現象やビジュアルが頻出するので、ついていけない人にはまったくついていけないだろう。
なぜトリなのか?なぜ女中と亡き母親の容姿が変わったのか?なぜ積木なのか?等々。挙げたらきりがないくらい多くの謎が残る。
しかし、だからと言って本作がつまらないとは言いたくない。個人的には、その謎めいた所も含めて大変刺激的な2時間を過ごすことができた。
ちなみに、もう一つ本作を観て連想したものがある、それはバーネットの児童小説「秘密の花園」である。これも何度か映画化されており、自分は1993年に製作された作品を観たことがあるが、本作との共通点が幾つか見られて興味深かった。例えば、主人公が親を災害で亡くしたこと。トリに導かれて秘密の場所へ引き寄せられる展開。大叔父もとい叔父がキーマンになっていること等、共通する点が幾つか見つかった。
キャストについては概ね好演していたように思った。ただ、一部で違和感を持った人がいたのは残念である。ジブリはこれまでも俳優や歌手、タレントを積極的に起用し上手くハマるパターンもあったが、今回はそうとも言い切れない。
尚、本作は公開前に宣伝をまったくしなかったことでも話題になった。ジブリともなればタイアップやCMは引く手数多だろうが、敢えてそれをしなかった鈴木敏夫プロデューサーの手腕は大胆にもほどがある。もちろん宮崎駿のネームバリューのなせる業なのだが、この逆転の発想は革新的と言えるのではないだろうか。今の時代、全く情報なしで映画を観る機会はそうそう無いわけで、貴重な映画体験をさせてもらった。
この映画の私的解釈と、感銘
(完全ネタバレですので必ず鑑賞後にお読み下さい!)
この映画『君たちはどう生きるか』を観ました。
結論から言うと非常に感銘を受けました。
しかし、この映画『君たちはどう生きるか』は、宮﨑駿(宮崎駿)監督が分かり易くは劇中で説明していないので、私的な解釈を交えて、なぜ私がこの映画を見て感銘を受けたのか、書いてみます。
この映画『君たちはどう生きるか』は、先の戦争中の日本が舞台です。
主人公・牧眞人は、戦争中に母・久子がいた建物が焼け、母親を亡くします。
その後、主人公・牧眞人の父は、戦争中に兵器工場で儲けます。
主人公・牧眞人は、疎開も兼ねて東京から父の兵器工場近くの母の実家の屋敷に父と共に越して来ます。
その時に主人公・牧眞人は、牧眞人の父が再婚した、牧眞人の新しい母・夏子に出会います。
牧眞人の新しい母・夏子は既に父の子を宿しています。
牧眞人の新しい母・夏子は、後に火事で亡くなった実の母・久子の妹であることが明かされます。
牧眞人が父と共に越して来た母の実家の屋敷には、離れに塔があることが分かります。
離れの塔は、本好きな優秀な大叔父が建てたと新しい母・夏子から説明されます。
牧眞人はこの新しい疎開場所で、学校の周りの生徒と軋轢が出来ます。
牧眞人は学校内の軋轢から逃れるために自分の頭を少し大きな石で打ちつけ、多量の出血をさせ、(口では否定しながら)周りの生徒から攻撃されたと父を含めて暗に伝えます。
ある時、屋敷の中でアオサギが牧眞人の前に現れます。
アオサギは、火事で亡くなったはずの牧眞人の実の母・久子が本当は生きていると伝え、何度も離れの塔に牧眞人を導こうとします。
その後、新しい母・夏子が離れの塔の付近で行方不明になります。
牧眞人は老婆・キリコと共に新しい母・夏子を探すために離れの塔の中に入って行きます。
牧眞人は塔の中でまたアオサギに攻撃を受けるのですが、以前に作ったアオサギが落とした羽を使った矢でアオヤギのくちばしを射抜き、アオサギを無力化させます。
くちばしを矢で射抜かれたアオサギは、サギ男へと変貌します。
映画をここまで見て、私的には3つの疑問が立ち現れます。
それは、
Q1.アオサギとは何なのか?
Q2.主人公・牧眞人が自分の頭を打ちつけ大きな出血をさせた意味とは?
Q3.大叔父が建てた離れの塔とは何なのか?
の3つの疑問です。
この3つの疑問は映画を最後まで見てもしっかりとした説明はなく明確な答えは不明のままです。
しかし、以下に(私的)解釈出来ると思われます。
A1.アオサギとは、世界から離脱したい欲求のメタファー(暗喩)だと解釈されると思われました。
主人公・牧眞人は、潜在的には実の母・久子が生きていて欲しいと願っています。
そして口には出しませんが、実の母・久子が戦争中の火事で亡くなった原因は戦争にあると思っていると感じられます。
さらに、父がその戦争に兵器工場の経営で加担していることも、暗に牧眞人には違和感があると解釈できます。
そんな父が新しい母・夏子と子を宿したことにも、牧眞人には違和感あると思われます。
牧眞人は、そんな世界から逃げ出したい離脱したいと暗に望んでいると思われます。
そして、牧眞人が世界から逃げ出したい離脱したい欲望のメタファー(暗喩)がアオサギであると解釈されると思われるのです。
A2.さらに、牧眞人が自分の頭を打ちつけ大きな出血をさせた理由は、(そんな世界に立ち向かわず)離脱したい行動の現われとして解釈出来ると思われます。
最後に大叔父が建てた離れの塔とは何なのか?
A3.(このことは後に明かされますが)離れの塔とは、世界から離脱した人達が、「悪意」のない理想的な世界のバランスを理論化し実現しようとする場所なのだと解釈できると思われます。
くちばしを矢で射抜かれたアオサギは、サギ男へと変貌しますが、その後、サギ男は主人公・牧眞人と老婆・キリコを離れの塔のフロアより1つ下の階層に導きます。
離れの塔より1つ下の階層には海が広がり、大量の帆船が漂っています。
牧眞人は島に流れ着き、「ワレヲ学ブモノハシス」と書かれた門を、大量のペリカンに押されて開けてしまい、ペリカンに襲われます。
しかし矢についていたアオサギの羽のおかげで、牧眞人はペリカンに食べられずに済みました。
その後、牧眞人は老婆・キリコの若い頃のキリコに出会い助けられます。
キリコは漁を行い、牧眞人と共に大きな魚のハラワタを取るなど解体します。
そして、白く小さいふわふわとしたワラワラにその魚を解体して出来た食料を分け与えます。
また帆船に乗ったのっぺらぼうの黒い乗組員たちは漁が出来ないことをキリコが説明します。
白いワラワラはキリコが与えた食料を食べて空へと飛んでいきます。
ワラワラはその後、上の世界、つまり人間世界に到達して人間の生命として誕生するとキリコは説明します。
しかしワラワラが地上に達する前に、大量のペリカンが飛んで来て空を飛ぶワラワラを食い散らかします。
それを阻止するために、海中からヒミ(若い頃の牧眞人の実の母・久子)が現われ、火でペリカンを燃やし空飛ぶワラワラを助けます。
ただ、その火はペリカンだけでなく、少なくないワラワラをも燃やすことになるのです。
ここで4点の疑問がわきます。
Q4.ペリカンとは何なのか?なぜアオサギの羽を持っていた牧眞人はペリカンに食べられなかったのか?
Q5.キリコが行っている漁の意味とは?
Q6.帆船の黒いのっぺらぼうの乗組員とは何なのか?
Q7.なぜヒミ(若い頃の牧眞人の実の母・久子)はペリカンだけでなくワラワラも燃やしてしまっていたのか?
それぞれの答えの解釈は以下になると思われます。
A4.ペリカンは世界から離脱した(せざるを得なかった)ある一つの行きつく先のメタファー(暗喩)だと解釈出来ると思われます。
ペリカンは世界から離脱し追い詰められ、ついに人間生命の誕生(ワラワラ)をも食い散らかす存在として現れます。
そして、アオサギは世界から離脱したい欲求のメタファー(暗喩)です。
だからこそ世界からの離脱の存在としてアオサギと同類のペリカンは、アオサギの羽を持っていた牧眞人を食べることが出来なかったのだと考えられます。
A5.キリコの漁の意味は、自分たちが生きる為に生命を殺し対峙する、つまり世界に立ち向かう行動のメタファー(暗喩)として解釈出来ると思われます。
キリコの漁の肯定は、実は世界に立ち向かう人々の肯定につながります。
しかしこの肯定の先には、世界に立ち向かうための争いや、その先の戦争の肯定も暗に示しています。
つまり、キリコの漁の肯定は、牧眞人の父が世界に立ち向かい兵器工場で財を得ていることを延長線上で肯定しているのです。
A6.そして、帆船の黒いのっぺらぼうの乗組員は、(世界に立ち向かうキリコの漁とは逆に)世界から離脱した存在の一つのメタファー(暗喩)と解釈できると思われます。
帆船の黒いのっぺらぼうの乗組員は、同じ離脱の存在のペリカンのように追い詰められて人間の生命の誕生であるワラワラの上昇を食べ尽くすことはありません。
しかし帆船の黒いのっぺらぼうの乗組員は、ペリカンと同じ離脱の存在として、(キリコの漁のように)世界に立ち向かえず、生命の殺傷から目を逸らし、ただ漁をしたキリコから食料を買い取る者として振舞っています。
A7.そして、ヒミ(若い頃の牧眞人の実の母・久子)は生命の誕生を守る母としてのメタファー(暗喩)だと解釈されると思われます。
しかし、ヒミ(若い頃の牧眞人の実の母・久子)は、生命の誕生を守る優しい理想的なだけの母という存在ではありません。
ヒミは、時に、生命の誕生のワラワラをも焼いてしまう、苛烈な母としてのメタファー(暗喩)でもあるのです。
映画が進み、牧眞人はヒミ(若い頃の牧眞人の実の母・久子)やサギ男らと共に牧眞人の新しい母・夏子を離れの塔の中でついに発見します。
この過程で新しい母・夏子が、ヒミ(若い頃の牧眞人の実の母・久子)の妹であることが明かされます。
離れの塔の中の新しい母・夏子は(お腹の中の胎児を含め)、牧眞人から拒絶されていることを暗に甘受しています。
そして、新しい母・夏子は、牧眞人の離れの塔からの救出を激しく拒否します。
その過程でも1つの以下の疑問が現れます。
Q8.インコの存在とは何なのか?
A8.その答えは、インコとは、離れの塔の離脱した世界で、新しい理想的な世界を反転的に構築しようとする集団のメタファー(暗喩)であると解釈出来ると思われます。
インコは、帆船の黒いのっぺらぼうの乗組員らとは違って、キリコのように命を殺生することが出来ます。
しかしインコは、キリコとは違って、個々の生命(世界)に対峙しているとは思えません。
インコは、個性を無くした組織的な集団としてオートマチックになることで、個々の生命(世界)に対峙することなく殺生することが出来ているのです。
それが、世界からの離脱を経て、”新しい理想的な世界を反転的に構築しようとする集団”の意味です。
映画の最終盤で、主人公・牧眞人は遂に実際にこの離れの塔を作った大叔父に会うことになります。
そして、大叔父は牧眞人に、絶妙の積み木のバランスで成り立っている離れの塔の理想の世界の、継承者になってくれることを望みます。
しかし牧眞人は、自身の頭の傷を大叔父に見せ、自分にも「悪意」があることを示し、離脱した理想の世界を作る継承者になることを拒否します。
そして現実の世界に戻ることを大叔父にはっきりと伝えるのです。
このことにインコの大王は激怒します。
インコの大王は自分で理想の積み木を立てようと試みますが、すぐに積み木のバランスは崩れ、さらに怒ったインコの大王は自分の太刀で理想の積み木を真っ二つにします。
それによって離れの塔の中の、離脱した理想の世界は崩壊して行きます。
牧眞人とヒミ(若い頃の牧眞人の実の母・久子)とサギ男はそれぞれの年台の現実の世界につながる扉のある廊下へと逃げ出します。
そして、そこに若い頃のキリコと牧眞人の新しい母・夏子も逃げて来ます。
牧眞人と牧眞人の新しい母・夏子とサギ男は離れの塔に来る前の現実世界に戻ります。
そして、ヒミと若い頃のキリコは、牧眞人たちとは前の、ヒミが牧眞人を産むよりずっと以前の世界に、扉を通じて現実の世界に戻ります。
牧眞人と新しい母・夏子は、扉を抜けて牧眞人の父や屋敷の老婆たちと再会します。
サギ男も扉を抜け現実に戻りアオサギとなって飛び立って行きます。
インコたちも崩壊する離れの塔から現実の世界に殺到しますが、それぞれ可愛らしい小さなインコとして現実の世界に飛び立って行きます。
この映画は、牧眞人が世界から逃げ出す離脱する欲求を肯定しています。
また世界や生命の生死に立ち向かう若いキリコ(あるいは牧眞人の父)も肯定しています。
そして、(映画の初めの牧眞人のような)世界の離脱と(若いキリコのような)世界の立ち向かいの、間を取り持つ、ヒミのような時に苛烈になる母を肯定していると思われます。
一方でこの映画は、離れの塔の崩壊や大叔父の理想の継承の拒否で、世界からの全面離脱への疑義も示しています。
そして、世界や生命の生死に対峙する時の残酷さも示していると思われます。
火事で亡くなった実の母・久子の現実での不在の受け入れも示しています。
この矛盾に満ちた現実の受け入れと、離れの塔を通じたヒミ(若い頃の牧眞人の実の母・久子)との関係を含めた経験の記憶と、近しい仲間の存在により、辛うじて現実を生きて行くことに決めた主人公・牧眞人の姿に、個人的には静かな感銘を受けました。
今の現在、国内外を含め様々な場所で訳も分からず暴発している人々の存在があり、彼らを迂回させる一助にこの作品がなれば良いのにとも思われてはいます。
この映画は暗く重いですが、世界を伝え切ったところにも感銘しました。
好みではなかった。
寝た。めちゃ頑張ったんですが、20回くらい寝てた。
導入(中盤まで)と最後おさまってれば、後はストーリー自由だと思ってるようす。
ぽにょと、ハウルを思い出す。行き当たりばったり感。
監督自身がナラティブ的な手法で作っているように感じる。主観の体験という感じで辻褄合わせする気ない。いままでのツギハギにも感じる。
エヴァンゲリオンみたいに、それぞれで補完して考えて想像して欲しかったのかもだけど、上手くいってなくて置いてけぼり。
見たい人は覚悟してみよう。
映画にアートを求めてる人はどうぞ
君たちはどう生まれ、どう生きるのか
輪廻転生、生と死、あちらの世界、こちらの世界、パラレルワールド、人間の持つ心の闇。
私の解釈ですが、あの塔は、闇を表していると思いました。その奥は生と死の境目の場所。
マヒトは何度も闇に誘われます、人は大切な人を亡くしたら、ついていきたいという気持ちにもなるでしょう。
その誘導に何度も勝つのですが、夏子さんを助けにいくという形で入っていくことになります。
そこで、生死の境目で大叔父さんに現実世界を生きるのか、死後(天国)を守るのか選択を迫られます。
これは凄く怖い選択だと思いました。
天国は一見、夢のように美しくも見えるのです。
マヒトが現実世界を選んだ時、とても安堵しました。
そして、どんなに苦しくてもそこで生きるという意思を感じました。
また、夏子さんを通して、人間が生まれることの壮絶さを伝えられました。
夏子さんはつわりが酷く、自ら闇に誘い込まれるように進んでいくのです。
そこで、もがき苦しみます。
一つの命を守るために必死の形相になりマヒトに酷いことを言う。(ここについては、もっと深い見方ができるので何とも言えませんが)
人間が、生まれるのは本当に大変なこと。
それはワラワラなどを通しても伝わります。
私達は現在の、更に生きにくい社会の中で目に見えるものばかりに囚われ、死にたいと思ったり、それを選んでしまう人もいます。
でも、一つの命の誕生の裏には壮絶な物語があること、生み出す母親の忍耐と愛情の強さとはどれほどのものか、ということ。
それが一度見た時点で大きく伝わってきたメッセージでした。
まだまだ解釈の足りないところはあります。書ききれないところもありますが。。
宮崎駿監督が、もっともっと生きて理解すればいい、だから、もっと生きるんだ、と言っているような気がします。
ちゃんと考えましょう、感じましょう。
自分なりの解釈で良いのです。
難しい、とか一言で済ませるのではなく、頭と心を使うのです。
それが何より大切なこの映画へのアンサーではないでしょうか。
この不思議なファンタジーが良いのよね
ジブリの暖かみを残しつつアニメーションとしてクオリティが上がっていて凄く良かった。
どの場面も美しかったなぁ。特に私はジブリの描く森が好き。
今回は冒頭の火事のシーン凄かった。
ドルビーアトモスで観たから音の重圧感も重なって凄く満足感を得た映画だった。
ストーリーも良かった。
大叔父さん?はこの世の中じゃ良く無いと思って新しい世界での生き方を選んだ。
その生き方を他の人にも共有したかった。
ただ、主人公は戦争する世の中や周りの環境の変化にちゃんとついていけてはなかったり嫌な気持ちもあっただろうけど、現実での生き方を選んだ。
自分の生き方は自分で選ぶ。
辛いこともあるけど、何を大切にして優先して君たちはどう生きるのか。
主人公のお母さん、その妹、お婆さん、みんなあの塔の中の世界にどう生きるのか問われて選択していったのかな。
私(宮崎駿自身)はこう生きる事を選んだ。この生き方に続く物はいないかもしれない。宮崎駿のような映画作れる人はいないかもしれない。この自分が作った世界を残して欲しい気持ちもありつつ、
みんな自分の世界を自分で選び築いて行けば良い。
そんな映画なのかなぁと勝手に解釈(勝手な解釈です)
この映画にしか得られない感情があって心が持ってかれた。
この世界にもっと浸りたかった。
お父さんと新しいお母さんが仲良くしてるのを見たり、つわりのお見舞いの時の、お父さんが一緒に寝てる感じを漂わせる感じ良かったな。
本人は感情を言葉には出さないけど、子供からしたら受け入れるのにも時間がかかるし感情を揺さぶられる事だったって主人公目線のこの表現でよく分かるよね。
もしかして新しいお母さんは、主人公のためにあの世界に行ったのかな。
主人公の気持ちは充分分かっていただろうし。
どうなんだろうね。
あとインコの見た目、凶暴だけどピュアさもある感じ良かったな。
宮崎駿自身も分からないと言ったらしいから、個々の受け取り方でこの映画を観てそれぞれの私の世界観を作ったら良いなと思った。
絶賛や批判いろんな意見が出る映画おもしろいよね。
“難解だけど面白い”という所までに至っていない
風立ちぬ以来の新作ということでとても期待していたが、
鑑賞後の感想としては少しガッカリしたという気持ちである。
しかしながら、この作品には褒められるべき点もある。
まずは圧倒的な作画力。これに尽きるだろう。
宮崎駿作品の魅力とも言える疾走感のあるシーンは日本を代表するアニメーター集団であることを顕著に表している。特に前半の火事の中走るシーンは今の劇場アニメでも中々見ることができないレベルである。
それだけの作画力のある作品を低評価に陥れているのはストーリーである。
作品に隠された意図、メタファーを盛り込むのは考察する楽しさがあるしとても良いことだと思う。しかし、本作はそれに特化させすぎて純粋に作品として見た時に単純に面白くない。特に言語化されている場面が少なく観客に理解させようという気すらしない。
制作側が作品に込めたいメッセージと観客が理解できるレベルの塩梅を上手く取るのがプロの仕事ではないのかと問いたい。
結論、今回の作品の評価としては、星3とする。
理由はストーリーは難解であり、作品として面白いというレベルに達していない。しかし、正統なジブリ作品として評価できる作画力や世界観ではあるためこの評価とする。
宮崎駿が考える「君たちはどう生きるか」です。
まずはじめに。
映画を見たあと、本屋に寄り「君たちはどう生きるか」
をパラパラ見ましたが、映画は小説や漫画化された
君たちはどう生きるかとはストーリーも設定も違います。
タイトル、テーマだけがかぶっているだけで中身は別物です。
個人的感想は最後に書いてあります。
おおよその流れを長々と書いておきます。
映画の方は、
舞台が戦時中の日本で、主人公マヒトがある日
大人たちが騒いでいる中目覚め、火事を目撃する。
火事の現場が母親の病院でマヒトも現場へと向かう。
母親を亡くし、戦火のこともあり父親と二人で
田舎へと移り住む。そのさきに母親にそっくりな
女性があらわれ、新しい母親と父親から紹介される。
母親にそっくりな女性は母親の妹ナツコである。
お腹には子を宿しており、大きなお屋敷に住んでいる。
お手伝いのおばあやおじいが身の回りのお世話をしている。
母親の死を受け入れられないでいるマヒト。
マヒトとの距離を感じながらも気丈に振る舞うナツコ。
アオサギがあらわれ、マヒトにちょっかいを出し始める。
アオサギが屋敷の離れにある館に向かうのを見たマヒトが
館へと出向く。館はボロボロで上へと通ずる階段は土で
埋もれている。姿を消したマヒトをおばあたちが総出で捜す。
アオサギの羽が落ちているのを見つけ、
おばあが家に帰るよううながす。
館についてナツコからことの成り行きを聞く。
次の日、父親の運転でマヒトは学校に行く。
帰り道に同級生とけんかをする。そのあと自分の右側頭部に
石で傷をつける。おばあや医者に治療してもらう。
父親から誰とけんかしたか問いただされる。
コケただけだとマヒトは主張する。
次の日、アオサギがあらわれ木刀で向かい打つが、
歯がたたず、アオサギから母親は生きていると言われる。
カエルに飲みこまれようとされるとき、ナツコの弓で
アオサギどもを追い払い、難を逃れるマヒト。
その日からナツコのつわりがひどくなる。
おばあたちからお見舞いに行くよう言われ、
お見舞いに部屋に行き、帰り際タバコとナイフを盗む。
おじいにタバコを渡し、ナイフを研いでもらう。
竹の弓を作り、矢先が釘の矢を作る。うまく飛ばないので
池に落ちているアオサギの風切り羽を矢に取り付ける。
そのときに誤って机の上にある本を床に落としてしまう。
君たちはどう生きるかの本に母親の字でメッセージが
書き記してある。ナツコが森の中へと消えていく。
おばあたちがいなくなったナツコを捜す騒ぎに気づくマヒト。
ナツコが消えた場所をキリコと追う。
道の抜けた先に館の裏手に出る。
館に入ると入口が塞がれ、アオサギがあらわれる。
母親は奥にいるとアオサギに案内され、ソファに眠る
母親を見つける。触れると液体になり崩れる。
ナツコの居場所を問いただすとアオサギが
殺してみろと言い、マヒトは弓を引き矢を放つ。
一度は避けられたが、矢はアオサギを追いどこまでもついてくる。
矢はアオサギの上くちばしを貫通し、飛べなくなる。
館の上に大爺があらわれ、アオサギにナツコの居場所を
案内しろみたいなことを言われる。
アオサギ、マヒト、キリコは下の世界へといざなわれる。
マヒトはある島で目覚める。まわりはペリカンだらけで
金の門があり、門には「我を学ぶものは死す」
みたいな文字が書かれている。マヒトが門の前に立つと
ペリカン達が門に押し寄せ、門が開く。
海から船に乗った若いキリコがあらわれ、島に降り立ち
ペリカン達を追い払う。マヒトを助け、呪文を唱え、
後ずさりして船で島から脱出する。
仕掛けた罠を引き上げ、魚を釣り上げる。
ここは下の世界と説明され、生きている者は少ないと言われる。
生き物を殺生できるのはキリコだけで、他の者はできない。
若いキリコがその役目。若いキリコの家に招かれ、魚をさばく。
変な丸い妖精がいる。内臓が妖精の好物らしい。
机の下で目覚めるマヒト。まわりにはおばあ達の人形が取り囲んでいる。
それには触れるなと若いキリコに言われる。
マヒトはトイレに行き、月明かりがまわりを照らすと
妖精が空へと飛び立つ。若いキリコがあれが人間へと生まれ変わる
のだと説明される。ペリカン達が妖精を食べ始める。
全滅しかけたときにヒミがあらわれ、ペリカン達を追い払う。
寝ているときに外から物音がし、マヒトが外に出ると
トイレの横に傷ついたペリカン1匹がいる。
もう命が長くないとペリカンが言うと、妖精を襲った罰だとマヒトが言う。
ペリカンは下の世界ではエサとなる魚が少なく、
妖精を食べるように進化したと話す。
ペリカンは死ぬ。アオサギがあらわれる。
マヒトがスコップを持って、ペリカンを土の中に埋める。
翌朝、アオサギとマヒトがケンカして風切り羽をマヒトが引きちぎる。
若いキリコが二人をなだめ、ナツコ捜しがはじまる。
若いキリコからマヒトにキリコの人形と石をお守り代わりにもらう。
道中でアオサギの上くちばしの穴を塞ぐためマヒトが
木の棒を削り、いろいろ調整してあげる。
ナツコがいる家を見つけたが、インコが家を占拠している。
インコは人間を食べる。
アオサギがインコの気を引き、その隙にマヒトが家の中へ。
家の中にもインコがおり、丁重に出迎えられる。
ナツコはどこだと問いただすとお腹に子がいるので食べない。
ここにはいないと言われる。マヒトが食べられそうになるところを
ヒミが助けてくれる。ヒミの家へと招かれる。
そこでジャムパンを食べる。
ナツコの居場所を案内するためヒミと一緒に行動する。
父親がおばあ達から館のついての言い伝えを聞く。
館は空から降ってきた石であること。
その衝撃で池の水がほとんどなくなったこと。
石を覆うとしたら、何人も死人が出たこと。
いわくつきの館であること。
城の中に潜入し、番号の付いた扉の廊下に出る。
両端からインコが迫ってきて、扉の向こう側に
一時避難。父親がマヒトを見つけるが、
マヒトは元の世界に戻らず、下の世界へと戻る。
その扉はいろいろな時代に繋がっており、
ドアノブを手から離すと、下の世界には戻れない仕様。
ナツコのいる部屋に着き、マヒト一人で部屋に入る。
ナツコを起こすが、マヒトを拒絶し、マヒトとヒミは
気絶してしまう。
マヒトは夢の中?で時の回廊を通り、大爺の元へと行きつく。
大爺は積み木をしており、世界が一日保たれると言う。
積み木と言っているがそれは墓に使う石。
大爺がことの成り行きを話し、
自分の役目を引き継いでほしいと頼まれる。
マヒトは目覚め、インコに調理されようとしている
ところをアオサギが間一髪で助ける。
マヒトとアオサギが合流し、ヒミの行方を探る。
ヒミはインコに捕らえられ、インコの王様と一緒に
大爺の元へとつれていかれる。
マヒトが引き継がないなら、
ヒミに引き継がせるとインコの王様が言う。
ヒミを助けようとするが、インコの王様に阻まれる。
インコの王様と大爺が少しお話し。
そのあとヒミと大爺が言葉を交わす。
マヒトは役目を引き継がない、
ヒミも一緒に元の世界に戻りなさいと諭される。
インコの王様は時の回廊から出ず、経過を見守る。
マヒトとアオサギが崩れた階段から這い出てくる。
目の前に時の回廊があり、先へと進む。
広間に突如、扉があらわれ、扉の先へと進む。
インコの王様もつづく。そこでヒミと再会。
石を飛び先へ、アオサギもつづく。インコの王様もつづく。
大爺とはじめて対面。
13個の積み木を、3日に1個?1日に3個?積み
世界を導くように言われる。
マヒトは自分はうそをついてきた。頭の傷のことも。
そんな自分は役目を引き継ぐ資格はないと言う。
大爺が良い世界にするも、悪く醜い世界にすることも
できる。このまま元の世界に戻っても辛く、むなしい結果が
まっているだけだ。
しびれを切らしたインコの王様が積み木を適当に積む。
こんな積み木で世界の情勢を決められてたまるか的な事を言う。
積み木が崩れ、下の世界が崩壊する。
マヒト、ヒミ、アオサギが時の回廊を抜け、
番号のついた扉の廊下へと向かう。
若いキリコがナツコを見つけ、番号のついた扉の廊下に向かう。
マヒト、アオサギ、ナツコは元の世界に。
ヒミと若いキリコは過去の世界へ。
元の世界に戻ったマヒトはアオサギから
何で下の世界の記憶があるんだと問いかけられる。
なんか厄介なもの?もってないかと聞かれる。
ポケットからキリコの人形がおばあのキリコに
代わる。積み木の石が出てくる。
記憶は早く忘れろと忠告される。
3年後、戦争は終わり、都会へと戻るマヒト達。
ようは全部のジブリ映画の要素を1つの作品にまとめて
作ったらこの映画ができたということです。
風立ちぬのようなリアリティ要素、
トトロや千と千尋の神隠しのようなファンタジー要素、
風の谷のナウシカやもののけ姫のような自然と人間との共生、
魔女の宅急便やハウルの動く城のような心の成長や葛藤など。
面白いかどうかと言われたら、なんとも言えない。
ジブリ特有の表現や見せ方、話の流れや教訓、
教えや人生哲学等、ジブリ映画をたくさん見ている人
ならあるあるなシーンや場面があり、
ジブリファンなら理解できる表現方法がある。
それを楽しめるかどうか。まわりくどい言い回しや
シーンを許容できるかどうかで
面白いかどうかが別れると思う。
主軸は、マヒトの心の成長物語なので
シンプルだけどジブリなので良くも悪くも
一筋縄ではいかず、わかりにくく作られている。
個性豊かなキャラクターが多く、物語に集中しづらい。
なんの説明もなく新たな重要人物が出てくるので、
置いてけぼり。
重要そうなナツコもそれほど掘り下げず
ナツコをエサにマヒトが右往左往する展開。
マヒト、アオサギ、ヒミ、大爺だけの話を
聞いておけばよいです。
補足
ペリカン 自己犠牲、母性の象徴
サギ 神の使い、再生の象徴
インコ 知性 家族の絆 明晰さ
アオサギの声が太田光かと思ったけど、
エンドロールで名前が無かったので誰だったんだろう?
比喩と暗喩に満ちた場面の連続だが、メッセージは明解だと感じた
映画「メッセージ」とテレンス・マリックの「ツリー・オブ・ライフ」とキューブリックの「2001年宇宙の旅」を足したようなメッセージ性と、背景はルネ・マグリットの絵画や飛鳥の石舞台のような様々なメタファーに彩られた、美しい映画でした。
ただ、監督が伝えたかったメッセージが上手く描き切れたのかというと、消化不良だったのでは…?という気もします。
でも私はこの映画のことは嫌いではありません。
マヒトは、小さな嘘をつく矮小な自分を認めることができて、やっと欺瞞と暴力が渦巻く世界と対峙する決意をしたんですよね。
ナツコはおそらく姉(マヒトの母)に対して引け目があって、姉の授かり子のマヒトと向き合う責任から逃れたかったのではないかな。
ヒミは、自分が死ぬことがわかってても、マヒトをこの世に産むことを選んだ。マヒトと出逢った異世界での期間が、きっと神隠しにあった1年だったんでしょうね。この辺が、子供が死ぬことがわかっていても子供を産む決断をした「メッセージ」の主人公を彷彿とさせました。個人的に。
ヒミは「火は怖くない」というセリフを言いますが、火は生命を燃し、また新しく命を生む役割もあることからでしょうか。
私たちがこの世に命があるのは、絶対ではない。キリコのいた海は子宮で、白い生き物は精子。らせんを描くのはDNAそのものですね。この海での出来事のように、もしかしたら私たちは、あの世にいるときに、誰かに選ばれて生まれたのかしれないし、自分で選んでこの世に産まれたのかもしれない。
陳腐な表現ですが、生命というのは神秘で、人間だけではなく数多の命は全ておろそかにしてはいけないよという、メッセージを感じました。
そこに気がつくまでのマヒトは劇的な変化はみせません。そこにもどかしさや物足りなさを感じる人もいるでしょう。セリフは極力そぎ落とされ、ほとんどのシーンは抽象的です。
大叔父が持つ隕石は、地球に生命をもたらした象徴?大叔父がもっていた13の積み木の数字「13」は、キリスト教でいうところのユダで、すなわち「神に背を向けた男」ということでしょうか。大叔父は、長年行方不明になったままなので、この生命の渦のような世界で、神ではないのに神のような力を持ってしまった者なのかもしれません。戦争を経験した大叔父は、苦しみや悲しみを生む人間界そのものの行く末を、子孫に託したかったのかな?と思われます。
インコは…生命のバランスを欠く、恐ろしい外来種の象徴でしょうか(笑)?
私の推考が正しいのかどうかはわかりません。この映画の背景にある全ては、監督の頭の中だけにあるのでしょう。
ただ、そもそものメッセージはシンプルなものの、そこに至るまでのストーリーが面白いかというと、それほどでもありません。
ただ、最後まで観ることで、じわじわとこみ上げるものがありました。
特に場面場面で思わせぶりな表情を見せるキャラクターの繊細さ、和洋折衷なのに美しい色彩の世界は、もう一度みたいと思わせる中毒性があります。
小中高生より、ある程度人生経験を積んだ大人のほうが、胸に訴えかけるものがあるかもしれません。
今の宮崎監督でゲド戦記を作って欲しい
同タイトルのヒット本とはほぼ関係がないですね。
親(主に父)から離れて冒険に巻き込まれる形、その中で異形のもの達との友情など育まれたりと、おなじみのテイストが健在。
なので集大成と言われてるのかもしれない。
これまでの、ナウシカやもののけ姫のような外へ向かうものではなく、千と千尋やトトロなどどちらかと言えば内へ向かう方向性の作品。
内とはいえ、監督の年齢を思えば次々とめぐり来るイマジネーションの豊かさに驚きを禁じ得ない。
マザコンなのは昔から有名なところで、それを逆手にでもとったような感じもある。男性にとって母親というのは大きな存在なのですね…。
己の中の悪意を認める点から、今の監督にゲド戦記を作り直して欲しいなとチラと考えた。
もちろん現実には無理だろう。
追記で。戦争当時、兄が戦死して兄嫁と弟を再婚させることは珍しくなかったのは知っています。当時寡婦になったからといつても実家に美の置き所もなかったのが実態とも思います。
しかし男女逆パターンはどうだろうか?
嫁は頑丈で沢山子をうみ、よく働くことが理想とされてた時代に、体が弱く亡くなった妻の妹をわざわざ選ぶ。それも妻が死んだ翌年には既に妊娠させてる。ストーカーにも似たものを感じて少しゾッとしましたね…。
ジブリ最強期に子供でよかった……以上。
最初にものすごく感じたのはラピュタと千尋とハウルともののけをMIXしてみた!って印象でした。
シンプルにつまらなかったです。
途中咳が止まらなくなり、他の人のご迷惑になるなと、退場しようかな、この映画ならまぁいいかと思った自分に対し、ジブリ映画なのに?と悲しい気持ちになりました。
私がジブリに出会ったのは本当に幼少期の頃で、TVでナウシカ、ラピュタ、魔女宅、紅の豚、トトロをそれこそ頭おかしいくらいに観て育ち、小学校中学年くらいに友達と友達のお母さんとポンポコ観たのが映画館では初でした。本当にジブリ作品、宮崎駿監督の作品が大好きで生きてきて、嫌な予感と期待を混じえながら久々に鑑賞し、現在動揺しています。
こういう時、力になるのが鑑賞された皆様のレビューを拝見し様々な考察を見ることなんですが「宮崎駿監督自身の事を作品にした」というのをみて納得し非常に腑に落ちました。
だが、しかし、評価としてはコレです。
それは揺るぎません。
意見として庵野監督の影響を受けているとあり「それだ!」と思ったんですが……シンエヴァを観て「酷いな……」って思った方々……おそらく今回のジブリもそう感じたのではないかと思うんですが如何でしょう?
個人的な見解なので賛否両論あるとは思いますがあえて吐き出します。庵野監督が自分の事をエヴァという作品にのせた事に対して「え」ってなりました。ただ、本人にとってはスッキリした事なのはよくわかります。ただ宮崎駿監督がまさかそれと似たような事をするとは…私は庵野監督のファンではないのですが宮崎駿監督のファンなので今エヴァファンで同意見を持った友人の気持ちが少しわかった気がしました。なるほど胃が痛い……
世間や社会にとって大変大きな存在であり、凄まじい渦の中で素晴らしい作品を作ってくれたので否定する気はしないですしずっと大好きですが、スタジオジブリ作品で育った者としてはやはり一個の作品としてはこの評価しかつけられませんでした。
他の方のレビューにもあった通りこれで本当に引退なのだという事を真摯に受け止め、とりあえずジブリパークにでも行こうかと思います。
映画タイトルからのイメージに反して
タイトルの元ネタになっているのは吉野源三郎さんの書いた児童に向けた人生指南書なので、まさか高齢の宮崎駿監督が子どもたちに道徳教育のための映画を作るような心境に至ったのでは・・・と思ったけど、ちっとも説教臭いところのない、爽やかで楽しい映画でとても良かった。
元ネタの小説も少し登場していてうれしかった。
昭和初期の上流階級の家庭の暮らしぶりも面白かったし、主人公が旅する地下の世界の、過去のジブリ映画をところどころ思い出させるファンタジックな世界観もよかった。
前作の風立ちぬは大人が主人公だったけど、やっぱり子供が主人公の映画のほうが宮崎駿監督の作風にあっていて楽しく見れると思った。
インコの軍隊とかワラワラとか、癖があってかわいいキャラクターがたくさんいるのに、映像が内緒にされてるのでキャラクターのグッズがしばらく販売されなさそうなのだけは残念。
いつかは映像公開してもらって、たくさんキャラクターのグッズがほしい。
宮﨑駿のラブレター
端的に言えば、「吾朗、後継ぎはお前!」に尽きると思う。
恐らく、大叔父=駿。「血を継いでいる人間を後継ぎにしたい」という発言は駿から吾朗へのメッセージだと思う。
塔(積み木)=アニメの世界で解釈すると、大叔父(駿)が塔に魅せられ、その世界にどっぷり浸かり、殿様となった流れがすんなり入ってくる。だから、所々に過去作のオマージュが挿入されてるのかも。
そして大叔父の積み木の崩壊は駿(ジブリ)の時代の終焉を意味しているのではないのかなーと思ったり。
真人(吾朗)は、今後自分の積み木を実直に積み上げていくのだと思う。
偉大な人間の後継ぎはいつの世も揉めるんですかね。。
どう生きるか、監督はヒントを遺してくれたのか
初レビューです。映画として、点数をつけなければならないのは難しいですね。
君たちはどう生きるか、観ました、2度。
劇場で泣いてしまったんですが
それは「感動」とかそういうものじゃなく
「宮崎駿の死を感じた」
「これからきっと恐ろしい時代がやってくる。宮崎駿が生きた時代よりもっと恐ろしい時代が。その中を生き抜く覚悟をしなければならない」という
2つの恐怖からの不浄な涙でした。
2,200円と4時間使って理解できたのはほんの僅かです。
少なくとも、宮崎駿が我々に問うのは
「君たちはどう生きるか」
これに尽きるのだと思います。
いや「コレだけなら映画観なくても解るだろ」と言われそうなので、言葉をつけ足すと
「俺(宮崎駿)はもう死ぬけど、
で、これからは俺の時代(戦後)以上の苦難の時がやってくるだろうけど、その荒波を
君たちはどう生きるか」
という問いかけ、ではないかと。
もっと言えば
「覚悟しろよ、焼け野原を知らないガキども」
という脅しのような揺さぶり。
我々ガキどもは、この先の荒れる時代を「どう生きれば」良いのか、勝手ながら考察させて頂きたいと思います。
前提として、観客の教養が試されます。
「戦争が始まって3年、4年」「冒頭の空襲警報ください」「サイパン」などのヒントから作中は1944年なのだと、瞬時に理解できるくらいでないとどうしても置いつき辛い部分があります。
それでいて「感受」のアンテナも常に張り続けなければなりません。意味ありげなシーンは7割は実際に何か意味があり、残り3割は「意味がない」ことを意図している、と感じました。シーンの伸びとは裏腹に、視聴者は考えることが次々起きて非常に疲弊します。
今までの宮崎監督作品は「娯楽としても楽しめる」ラインを守ってこられたように思いますが、今作は娯楽面を一切捨ててます。覚悟無しに観ることはオススメしません。娯楽映画が観たければ、スーパーマリオムービーを鑑賞することを強く推奨いたします。
宮崎駿監督は御年82歳、死がテーマに上がるのは当然の気もしますが、自分なりに根拠もあるつもりです。
主人公の真人が、青鷺に誘われて迷い込む「塔」の中、「海」が広がる世界。
このファンタジー世界では、ジブリファンがどこかで観た光景が手を変え品を変え出てきます。
海で会う「黒い人影」は「千と千尋」の「列車の乗客」のようで、
白く可愛い「ワラワラ」達は「もののけ姫」の「こだま」にそっくり、
真人が塔を登る時、「外壁を這うツタが剥がれ、あわや落下」というシーンは「ラピュタ」でも見られ
(うまそうなパンを食う、もラピュタですね)
とにかく宮崎映画の総決算のような演出のオンパレード。
(個人的には、インコたちの「歓呼三声!」「ラァー!」「ラァー!」「ラァー!」というのが、
まんま「漫画ナウシカ」の「クシャナ殿下と部下達」でツボでした。)
コレは宮崎ファンへの最大級のファンサのように受け取れるのですが、一方で違った見方もできます。
「このファンタジー世界(ペリカンは地獄とまで呼んでいる世界)」は「宮崎駿が作った世界」であり「宮崎駿」そのものだと。
物語のラスト、塔の崩壊こそ「宮崎駿の死」の暗喩ではないか、と。
また、塔の崩壊についてはダブルミーニングだと思っていて、コレは「現実世界」でも、同じようなことが言える気がします。
いや、コレはもっと残酷な現実を突きつけられている気さえするんです。
作中は1944年、第二次大戦末期の混沌の中でしたが、この時でさえ「石の積み木」は「揺れている」に留まっていたんです。
積み木が崩れたことを「敗戦」と読むことも出来ますが、
では「積み木の揺れ」はもう終わった過去の出来事なのでしょうか?
寧ろコロナ以後、世界の「積み木」は揺れに揺れていると思います。
今まさに崩れかかっているとさえ。
宮崎駿監督からの警告のような気がするんです。
「積み木は今まさに崩れようとしている」と。
纏めると
「俺(宮崎駿)はもう死ぬけど、
で、これからは俺の時代(戦後)以上の苦難の時がやってくるだろうけど、その荒波を
君たちはどう生きるか」
という問いに見えてくるんです。
少し悲観的過ぎる気もしますが、我々はこれくらいの覚悟が必要なのかもしれません。
ではその崩れかかった世の中を、我々は「どう生きれば」良いのでしょうか。
答えのない問いです。だから難しい。
でも、宮崎駿は少し、ヒントを遺してくれていると思います。
それが真人の答え「友達を作ります」。
もちろん直接的な意味だけにあらず、この答えは
「結束を深める」という意味に受け取れます。
宮崎駿はいわゆるアカ的な人なのでこういう(団結せよ的な)表現がしっくりきますが、もっと単純に
「他者との絆を大事にしよう!」
と解釈してもいいと思います。
単に「真の友を見つけよ」でも良いんです。
恋人でもなんでも、自分を認めてくれ、自分も相手を認められる相手を。
そしてもうひとつ、大事なのが「ウソつきの青鷺」。
作中では何度も、「この世は正と邪だけではない」ということが描写されます。
自分を襲い、ワラワラを食べるペリカンも「食う魚が無く、生きるためにワラワラを食べていた」こと。
ペリカンを追い払うヒミもまた、ワラワラを燃しているという事実。
恐ろしい「インコたち」にも生活があり、互いに支え合ったり、同じ釜の飯を食ったりしながら、卵を大切に温め、インコの命を育んで生きていること。
そして勿論、「自分を騙して母の死を穢したウソつきの青鷺」と共闘し、最後には「友達」と認め合うこと。
ラストシーンでは色とりどりのインコたちが、フンを撒きながら美しく飛び立って行きます。
これ以上無いくらいわかりやすく、「この世は浄も不浄もある。穢れていて、それでも美しい世界」を描いています。
真人が学んだ一番大きな事は「この世は穢れていて美しい、カオスなもの」だということです。
「人間とは慈しみも汚い嘘もある、カオスな生き物」と言い換えても良いでしょう。
真人は自分でキズつけたこめかみを「自分の悪意の証」と言って「(悪意のないまっさらな石に)触ることは出来ない」と言いました。
そして元の世界、奪い合う穢れた世界で生きる決意をしました。
青鷺は最後、「あばよ、友達」と言って真人の元を去りますが、実は真人の元に残っていると思います。
何故なら「全ての青鷺はウソつき」だから。
勿論青鷺としてではなく、「真人のウソつきの部分」として、真人の中に残り続けるのだと。
真人がついた嘘とは?コレは自分の我儘のためについた「こめかみの傷」のことではありません。
産屋で、夏子に言った「夏子母さん!」のことです。
あれは真人と夏子のわだかまりが解け、真実の家族になるシーンだ!あの言葉が嘘なわけない!
と思う方もいるでしょう。
でも、あれはきっと真人が学び身につけたウソ、方便なのです。
だって最後に時の回廊が崩れ現実世界に帰るその時まで真人は「母さんに生きていて欲しい」と願うのですから。
少なくとも真人の中で「久子(ヒミ、母)と夏子が完全に置き換わる」なんてことは無いんです。
それでも「夏子母さん」と呼びかけたのは、真人からの歩み寄りであり、何より「自分についたウソ」なのです。
そして、「ウソ」こそが真人の一番の成長だったのだと思います。
青鷺は去ったように見せても、真人の中に残る。
「ずるくても、賢く、ウソをつける真人」として。
そして何より、生きろ。
作中で、唯一明確な殺意を真人に向ける存在がいます。インコです。喧しく好き好きな声で鳴くインコは
宮崎視点で言えば観客や批評家のことだと思われます。
でも、単純に自分が感じた鬱陶しさをわざわざ映画に落とし込んだわけじゃないと思うんです。
勝手ながら、自分ごと化してもこのたぐいの輩は存在します。悪質クレーマーや理不尽な上司など。しかし、近年最も数が膨らんだインコたちは「SNSの第三者」ではないでしょうか。彼らは彼らの理屈で武装し、他者を寄ってたかって攻撃します。多様性に富むような色をしていても、色は4色顔は均一の喚きながら包丁を振るうインコです。
「妊婦は食わない」「産屋に入るな」など、こちらには意味不明な理屈でもインコ理論にとっては大罪であり、禁忌侵す者殺すべし、というのは、近年のSNS等で見られた事象であり、つい最近にも悲しい出来事がありました。
現実でも崖際まで追い立てられている人がいたら、この映画を見て欲しいです。
宮崎映画にとって何より重要なのは、生きることなのです。
「この世は美しくもあり不浄でもある。みな罪を背負っているかもしれない。人それぞれ生き方も違う。自分が如何に穢れていても、やはり生きるのは素晴らしい。生きよう」
というメッセージは、1990年代のもののけ姫や漫画版ナウシカ等から風立ちぬ、そして君たちはどう生きるかに至るまで、宮崎氏の中で不動のテーマなのだと思います。
――――――――――――――――――――――
宮崎駿は要するに
「ずる賢くてもいいから、上手く生き抜いてみせろ、そして、真の友を見つけろ」
と、我々に、「どう生きるか」のヒントをくれたのだと思います。
感じ方、考え方は人それぞれです。まだ私も、この映画のすべてがわかったとは到底思っていません。
また、同じく映画を観た方と意見を交えることで見方が変わることもあろうと思います。
なのでぜひ、簡単にでも良いので、一人でも多くの方の感想に触れたいです。
宮崎駿のやりたかったこと全部乗せ!最高!
私は小さい頃から宮崎駿監督が大好きで宮崎駿監督で育ちました。未だにジブリが大好きでこれまでのジブリ作品も何度見返したかわかりません。
映画が始まる前は絶対に1回で理解してやるという意気込みとドキドキ、緊張のしすぎでトイレに2回行きました。何本か予告を見ましたが、何にも覚えていません。そこから上映開始2分で、ああ私はこれからすごいモノを見させられるんだと思い興奮し泣きました。そしてジブリらしいアプローチのストーリー展開にワクワクさせられました。もうこの時点で次の回も見ちゃおうかな?と思わされる。何度も見たいヲタモード発動します。
キリコのキャラ設定も登場序盤から気になる存在になっていて本当に素晴らしいと思いました。また、菅田将暉さん、あいみょんさんの声優は私自身初めてでしたが、本当に素晴らしかったです!ハマりすぎです。
演出的には「あ、今の。あの映画のあのシーンに似てる」と思えるシーンが満載で、あのシーンが今のクオリティで見られることに感激しまた泣きました。そうなるとあのシーンはあれが最頂点なのかなとか思えたり。なかなか沢山のことを考えながら見ていました。最後、アオサギがじゃあな、と去っていくシーンでは巨匠がこれで本当に去っていってしまうという寂しさが押し寄せてきてまたまた泣きましたし、EDでは米津玄師さんの歌を天を仰いで泣きながら聴かせていただきました。最高でした。上映後も泣き止むことが出来ず、トイレにこもって泣きました。
私にはこれが最後の作品にしたいという監督の気迫が終始ビンビンと伝わってきてしまい、宮崎駿監督の集大成をIMAXのハイクオリティで見させて頂けていることにも感激でずっと泣いてしまっていたので本来の映画の楽しみ方が出来ていないのかもしれません笑。
この映画では、主人公眞人がタイトルとなった本を読むこと、キリコに労働を教わること等で自分以外の人の気持ちを知っていきます。芸能人への過度な誹謗中傷などもそうですが、この世の中にはなかなか受け入れられないこともたくさんあるけど、そこまで否定出来るものだろうか?自分は?どう?相手の気持ちに立って考えてみれば分かることだってあるよ、と宮崎駿監督に最後に伝えられた気がしています。ありがとうございました。上映中にあと何度か行く予定なので、また感想を書かせて頂きたいと思います。ジブリヲタの感想でした。長々とすみません。
リタラシーと共感性が試される大傑作
日本アニメ文化を昇華した巨匠のメッセージ性の高い大傑作でした。
ある程度リテラシーや知的素養が無いと作品を完全に消化することは難しい作品だと想いますが、宮崎監督のおそらく最後の作品になることを踏まえれば視聴者はこれを正しく受け止める必要があります。
物語の最初はシリアスな雰囲気で主人公の眞人は空襲の炎で母親を失いますが、疎開先で不思議なアオサギに導かれて異世界に迷い込みます。そこから不思議の国のアリス的な展開で家族のアバター(若いころの姿)などと交流して最終的には、それぞれが深い「理解・共感」と自己肯定にたどり着き、自分の世界に帰っていくという展開で物語が進むにつ入れて明るくポジティブな展開になっていきます。
最後も感動的でまったく無駄のないエンディングでした。象徴的・心象的な表現も多いので理解できないと文句を言っている人が多いですが、ゴミのような異世界転生物が流行っているアニメ業界に対する正統派のアンチテーゼと言える作品でもあります。
アニメーション(作画)のレベルは全盛期にはおよびませんが、そこらへんは全く問題ありません。
「周りの人々を理解することによって世界の見え方が変わる」という素晴らしい映画でした
呼び水
存在する意義 生きてるだけでも尊いけれど自分自身で構築しないと世界は開かないよ若者よ外に出よ的な印象を受けました
昨今、自分に自信がなく価値を見出だせず他人に危害を与えてしまう人が少なからずいます
作品の中では自傷行為として
理由はいろいろ推測できますが
そんな邪悪な心や抱えきれない自分の脆さも包み込んでの人間なんだと
また老いることによる醜さや騙しの世界、食物連鎖など生きることはきれいごとばかりではないといった気持ち悪さの違和感を敢えて加味してある気がしました映像的にはカエル軍団に覆われるとかも
生きとし生けるもの
そこに在るだけでも意味を持つかけがえのない君へエールを送る
生きるも死ぬも自分次第その人次第だけれど…
誰かの気持ちに変化を起こす呼び水となり得る作品でした
全762件中、401~420件目を表示