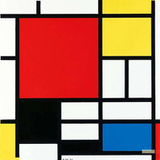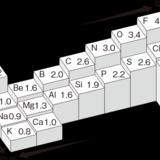君たちはどう生きるかのレビュー・感想・評価
全763件中、301~320件目を表示
タイトルなし(ネタバレ)
まずは、冒頭のマヒトが母の病院へ走って向かうシーンが鳥肌モノです。映像がとてもきれいで、さらに人の死が伝わってくる描写、その最初冒頭何分かだけで、映画の世界に引き込まれてしまいます。
物語はマヒトが母を失ってからはじまります。マヒトは母を失ったことで自暴自棄(?)みたいなものになり、生きる意味を失ったんだと思います。その証拠として自分の頭に石を叩きつけるなどの、自暴に走ったのだと思います。しかし父親は新しい妻ができたりと、マヒトとは真逆です。そんな父親にマヒトは不信感を抱き、新しい母(ナツコ)にも敵対心を見せます。そんなマヒトが異世界へ飛び冒険をします。最終的な異世界の王から「この世界の王を受け継いでほしい」と頼まれます。異世界には若き日の母が生きており、現実世界よりも幸せのはずです。最初のマヒトなら承諾していたかもしれませんが、マヒトはアオサギやキリコさんなどとの冒険により成長したことで、母がいなく、これから火の海になる現実世界に生きる決意を決めたのだと思います。最後の「東京に帰った」というのはその後もちゃんと生きたんだと示したのだと思います。
物語中盤にでてくるインコは、勝手な憶測ですが現実世界の「大衆」だと思います。マヒトや若き日の母は異世界では人間です。それは今の現実世界で言ったら「才能のある人」たちと考えます。それを喰おうとしてるインコは才能のあるものを潰してしまう今の現実世界の「大衆」に当てはまると思います。
この映画は本当に難しい映画だと思います。鑑賞中ずっと考えて見ましたがなかなかわかりませんでした。でも映画は「観客が想像して最後のピースをはめるもの」と僕は考えるので、本当に面白い映画でした。
Y××ooのレビュアーたちはどうイキるか
2023年映画館鑑賞40作品目
7月23日(日)イオンシネマ石巻
6ミタ0円
監督と脚本は『ルパン三世カリオストロの城』『風の谷のナウシカ』『天空の城ラピュタ』『魔女の宅急便』『紅の豚』『崖の上のポニョ』『風立ちぬ』の宮崎駿
原作はあくまで宮崎駿
吉野源三郎の小説『君たちはどう生きるか』はタイトルを借用しただけで中身は全く違う
だからコペル君は登場しないし子供に刺激を受ける無職のおじさんは登場しない
時代は大東亜戦争の日本
母を火事で亡くし父と共に東京から母の実家に引っ越してきた牧眞人少年
父は母の妹と再婚し継母は孕っていた
アオサギの手引きで母の実家屋敷の裏にある廃屋の塔に入っていく牧少年
天から降ってきた物体を大叔父が塔で囲ったのだ
塔の下の世界は異次元
海がありペリカンが人の言葉を喋りインコは擬人化していた
母は少女の姿で大人になった姉を姉だと認識していた
ばあやのキリコは若かった
大叔父は行方不明になり母も子供の頃行方不明になったが一年後帰ったきた
継母は孕ったまま塔の下の世界に
帰りたくない
牧少年が嫌いだという
なんだかよく訳のわからない話だ
単純明快を好む頭が硬い人には向いていない
幻想的な世界は好きだ
令和の不思議の国のアリスだ
あっちは夢オチだけど
全く宣伝をしなかったのはそれだけ宮崎駿に自信があったのだろう
宮崎駿の新作アニメ公開ってだけで十分だと
だからといって宮崎駿の方針を曲解し事前に情報を一切シャットアウトして鑑賞に臨むのは愚かなことだ
声優のメンバーを教えられただけで「ネタバレ」などと抗議する人たちにいたっては笑止
有吉の反論は概ね同意
声優が有名俳優ばかりなのは宣伝無しの保険だというトンチンカンな記事を書く信じられないほど無知なライターが世の中には存在するが実際はまるで違う
宮崎駿は声優専門の人たちの声が嫌いだからだ
「おヨーグルトですわ」みたいな人たちは宮崎駿の世界観にそぐわない
あとアオサギの声に菅田将暉くんのようなイケメンがやるのはちょっと抵抗感
ああいうのは大泉洋でいいんだよ
それにしても口の中にまた顔があるあの気持ち悪い生物はなんなの
ブラックジャックに出てきた人面瘡の一種かな
あれは殺人鬼の良心だったけど
声の配役
母ヒサコを火事で失い父と共に東京から田舎に引っ越してきた牧眞人に山時聡真
体内から火を出し花火を打ち上げたりするなど武器とするナツコの姉の子供時代のヒミにあいみょん
下の世界で漁師をしているキリコに柴咲コウ
シュウイチの再婚相手で孕っている夏子に木村佳乃
眞人の父で軍需工場を営む勝一に木村拓哉
塔の中で行方不明となり本の読み過ぎで頭がおかしくなったといわれる大伯父に火野正平
セキセイインコたちのリーダー格のインコ大王に國村隼
ヒミの花火で瀕死の重傷を負う老ペリカンに小林薫
ばあやのあいこに大竹しのぶ
ばあやのいずみに竹下景子
ばあやのうたこに風吹ジュン
ばあやのえりこに阿川佐和子
上の世界で人間の赤ちゃんになる魂のような下の世界の生き物のワラワラに滝沢カレン
塔の中の世界に誘う案内人のアオサギに菅田将暉
「魂の物語」として素晴らしい
宮崎 駿監督の「君たちはどう生きるか」を息子(小5)と観てきました。上映中息子が何度か横から「おもろない」「つまんない」と囁いてくるのを、「まあ、まあ」と宥めつつの観賞でした。
さて、私個人の感想としては、一言で言い表すのは難しいですが、「自分の奥底で、深いところで、頷くものがあった。」です。
私はラピュタやトトロなど、同監督の初期の作品が大好きです。子供の頃に観たこれらの作品は、セリフを憶えるぐらい繰り返し観るほど私を魅了し、その後の私の人生に多大な影響を与えたと言っても過言ではありません。
それと共にもう1つ、私の人生に大きな影響を与えたものがあります。それは、心理学者の故河合隼雄さんの著作と、そこで紹介されていた様々な児童文学の作品です。河合隼雄さんの著作に「子供の本を読む」と「ファンタジーを読む」という2冊があります。河合隼雄さんは「心」と「体」とは別の領域として「魂」というものの存在を仮定して、人の在りようを考えた方ですが、上記の2冊の中で魂を描いている作品として様々な児童文学を紹介されています。そこにはジブリがアニメ化した作品が「ゲド戦記」も「床下の小人たち(ジブリでは借りぐらしのアリエッティですね)」も「思い出のマーニー」も紹介されていたはずですし、「耳をすませば」のパンフレットでスタッフの方の好きな、あるいはオススメの本として紹介されていた「トムは真夜中の庭で」もありましたので、ジブリとこうした児童文学の関係は密接と言えますし、河合隼雄さんがよいと思われた作品との共通性は否めないものがあります。実際、宮崎駿さんと河合隼雄さんは対談などもされていましたので親交があられたのかなとも(詳しく存じ上げませんが)思います。
私はこの河合隼雄さんの著作で児童文学における「魂」の描かれ方について慣れ親しんでいたためか、今回の「君たちはどう生きるか」は、とてもしっくりと「魂を描いた物語」として観ることができました。そこには、私の忘れられないいくつかの夢で見た景色があり、昔この世のものとは思えない美しい海辺に立った日に感じた風があり、深く感動した児童文学の世界があり、16歳で突然逝ってしまった友人がいた。そういう映画でした。「魂」の世界を描いているのですから、その領域で観なければ訳が分からないのは当たり前だし、難しかったりつまらなかったりしても当たり前かと思います。この映画は主人公の傷ついた魂が癒やされるまでの物語とも捉えられるし、映画全体のストーリーが、宮崎駿さんの魂のお話と捉えることも出来ると思いましたが、(ここで言う「魂」は、「心」とは異なります)この物語を映画という形で作ることを可能にした宮崎駿さんの才能や経済的条件、関わったクリエイターさん達の素晴らしい力、鈴木プロデューサーの理解など全てに拍手を贈りたい。
そもそも、魂のお話というのは、商業的な視点とは相容れない部分がある、ましてや尺も決められ、観客動員数も気にして作る映画などという媒体でそれを作るのはかなり難しいと思います。その難しさは、これまでのジブリ作品で随分感じたところです。魂の世界の出来事は、例えば今回の作品で出てくる石の数が13であることに、いろんな方がいろんな考察をされていますが、魂の世界でそれが13と決められる時、それは作り手が何かを意味して13と決めるのとは違って、魂が13でなければいけないと言ってくるようなものです。それはその魂の器である人でさえ、その理由がわからなかったりします。実際に宮崎駿さんが石の数に意味を持たせていらしたかはわかりませんが、魂の世界のことを例えて表現するならそういうことだと思います。また、魂の世界のことを商業的なものを意識して改変するということをわかりやすく言えば、誰しも不思議な夢ぐらいは見たことがあるかなと思いますが、その夢の中で例えば白い衣の老婆から石ころを渡されたとしますよね?その夢の体験が意味もわからないけど、深く感動して目覚めたら涙が出ていたとして(何らかの魂の体験)、それを作品にする時に、「老婆に石ころじゃ売れないよね」なんて、美しい少女に青く光る石を渡されるように変えてしまうことが、いかに魂の世界から離れてしまうかということだと思います。
そういうのが、「君たちはどう生きるか」には、だいぶ少なかった。それが素晴らしかったです。売れることを目的にしたら実現しなかったはずです。
ですので、この作品の中に出てくる物ごとや台詞を、こういう意味だと考えることはあまり意味がないのかも知れません。それより自分の中の魂の世界とリンク出来たら、深い体験になる映画ということかも知れませんね。
それでは、なんの意味があるの?と思うかも知れませんが、私は魂の物語として必然的に描かれたシーンが沢山見つけられたし、些細なシーンにも魂が癒やされていく過程で意味あるエピソードとして宮崎駿さんが描かれているのを感じましたので、とてもわかりやすく感銘を受けました。
これまでの作品で見たことがあると感じた数々の場面を、焼き直しと捉えた方は沢山あるかも知れませんが、
私にはそもそも宮崎駿さんの中には「君たちはどう生きるか」で描かれた魂の世界があり、これまでの作品にそこから切り取ったものを入れて来られたんだなと感じます。だから、全くそれは気になりませんでした。
だいぶ前から宮崎駿さんは、魂の世界を描きたかったのではないでしょうか?でもそれは映画としてのエンターテイメントを考えたら難しかった、その葛藤の痕跡があり、思いに反して観客にわかる受ける形にしなくてはいけなかったという悲鳴が聴こえていたから、自分はハウルとポニョは違和感が強いということかなと、今回の作品から感じところです(あくまでも、個人的な感想です)。そのあたりの作品では、「人にしたいの?キャラにしたいの?」というのが掴めない登場人物や、これは何かを示すためにだけ描かれているような登場人物だなと感じたことがあり、違和感がありました。
今回はそうではなく、主人公が生きている現実世界での周囲の人達の、主人公に対する愛や思いやりが(それが正しいかそうでないかとは関係なく)きちんと受け取れました。魂の世界に引き込まれていく人が現実世界にちゃんとよい形で帰還するためには、ここをきちんと描かないといけないんだということをよくわかって作られていることに安心しました。千と千尋やハウルでの親の描かれ方ではなかったです。そして、親だって一人の人として苦しみ悩み生きている存在であることをこの映画の登場人物から感じ取ることも出来ました。理想の親を体現するキャラクターでも、現代的な親の何かを象徴させるための登場人物でもなかったです。
長々と書いていますので、鬱陶しく感じられる方もあるかも知れませんが、今回の本作を通して、魂の世界を描いた素晴らしい児童文学の作品に再び光が当てられるといいな、最近書店から消えつつある作品もあるので、そう思います。
もし、児童文学の中の魂のお話なんていうのに、なんぞや?と思い、興味を持たれる方があったら、是非河合隼雄さんの著作を読んでみられるとよいのではないかと思います。
1つだけ、「君たちはどう生きるか」に物足りなさを感じるとすれば、それは非凡な感じがしなかったということでしょうか?もし仮に私が魂の物語を作れと言われたら、勿論こんな完成度にはならないですが、ざっくり同じような構成で同じようなストーリー展開のものを作るだろうなと感じるところです。そのぐらい古典的でオーソドックスな「魂の物語」の雛形みたいなところがありました。ですがそれでも、これをアニメーションで作ったことの意味は大きいし、それは宮崎駿さんの晩年でしかなし得なかったかもしれないと思います。
そして、改めてアーシュラ・K・ル=グウィン(「ゲド戦記
」原作者)や、ミヒャエル・エンデ(「モモ」や「はてしない物語」作者)、フィリパ・ピアス(「トムは真夜中の庭で」作者)といった素晴らしい児童文学を生み出した方々の類まれなる才能に脱帽する次第です。これらの作品を読み、クリエイターとしてこんな素晴らしい作品を自らも生み出したいと願った純粋な監督の情熱が、「君たちはどう生きるか」から垣間見える気がしました。
ある種の方には共感を得られる感想だといいなと思います。
失われた物語の中で
吉野源三郎の同作にインスピレーションを受け,オリジナルストーリーとして制作された宮﨑駿の最新作である今作の評価は真っ二つに分かれることになった。これまでのジブリにあるような「物語」としての側面は大きく後退し,アニメーターとしてのパーソナルな表現が前面に押し出されている結果だろう。『風立ちぬ』で引退を宣言した宮﨑がそれを撤回して監督した今作はあまりに自由で伸び伸びと作られている。次世代へのメッセージを含んだ「遺書」とすら呼べそうである。アニメーター宮﨑の自己開示,それは物語というよりイマジネーションに満ちた混沌だった。フェデリコ・フェリーニが『8 1/2』で撮りたかったものを,宮﨑はアニメーションで表現したように思える。
冒頭では東京が燃えている。ジブリが自家薬籠中の物としている「火」の描写は『風立ちぬ』から地続きである。そしてそれはたとえ空襲による火災であったとしても,「偉大な破壊」(坂口安吾)であるがゆえに美しい。病院にいる母のもとへ走る主人公・眞人はもちろん宮崎駿その人である。履き物を慌てて脱ぐ仕草や階段を駆け上がる動きなど,アニメーションのお手本のようなシークエンスには誰もが目を奪われただろう。しかし,病院の火災により眞人の母は命を落としてしまい,彼は疎開することになる。眞人が東京から離れると画面から戦争の影が消える。まとめると,前半が現実パート,後半が虚構パートというふうに切り分けることができるだろう。そして現実と虚構の往還,すなわち児童文学によく用いられる「行きて帰りし物語」の形式によって物語が展開する。「行きて帰りし物語」では「向こう」へ行くために「通路」が必要である。それらは『となりのトトロ』では「小径」,『千と千尋の神隠し』では「トンネル」として表現されてきた。今作においては「塔」が「通路」であるのと同時に宮﨑にとっての重要なメタファーとなっている。塔は疎開先の森の中にひっそりと建っているがこれは人が作ったものでなく,空から降ってきたものだという。人智を超えた存在である塔はおそらく「物語」の暗喩だ。そしてそれを人が建造物すなわち言語や法体系でコーティングしている。神の言語で書かれた物語を私たちが読むためには,低次元の言語や体系を必要とするからである。眞人が義母を探して通る道はまるで『となりのトトロ』に出てきた場面と酷似している。これだけでなく,『ハウルの動く城』の扉,『崖の上のポニョ』の船の墓場など,過去作品からの引用が多く見られる。それらは「ジブリらしさ」というサービス的な目配せではなく,明らかにコンシャスな反復である。特徴的なのは,眞人が異世界へ進んでいく際,そこに「老女」が同伴する点だ。『となりのトトロ』も『千と千尋の神隠し』も少女の成長譚という性格を持っているため,「大人」は彼岸へは行くことができない(サツキとメイの父親にトトロは見えないし,千尋が冒険している間,両親は意識を喪失している)。しかし,今作で宮﨑は屋敷に侍女として仕える老女を登場させた。もちろん彼女はキーパーソンであり「観測者」あるいは「守護者」としての役割を果たすことになる。眞人を映す「カメラ」であり,物語を受容する「観客」でもある。彼女は塔の奥へ進む眞人に「罠」という言葉を使うが,このワーディングはやや奇妙である。罠というのは,それを仕掛ける主体なしに存在しないためである。老女は「大人」でありながら,異世界への分水嶺で「罠」を仕掛けた何者かの存在を嗅ぎ取っている。また,彼女はアオサギが喋る様子を目撃する。アオサギだけではない。のちにインコも登場するがこれらは現実世界の「大人」たちに「バケモノ」として「認識」されるのだ。ここに従来の作品との違いがあるように思われる。「喋るアオサギ」も「インコの兵隊」も一般人に「見えている」とすれば,彼らは現実世界に存在するなにかしらの存在の表象だと推測できるだろう。序盤のアオサギは不気味な存在だが,その「着ぐるみ」を剥がしてしまえば無能な中年男性(=サギ男)である。翼を奪われたサギ男は粗忽でコミカルな存在,すなわち道化と化す。アオサギは,眞人を異世界へと導くトリックスターなのである。彼は大きな魅力のないキャラでありながらポスターに採用される存在感を持ち,最後には眞人と「トモダチ」になる。敵でも味方でもないトリックスターは「物語」への「水先案内人」なのだ。物語を信じる宮﨑にとって欠かせない存在だろう。
眞人たちが地底世界へ潜り込むとそこにはインコ帝国が築かれている。この「帝国」はおそらく「スタジオジブリ」だろうが,同時にそこは宮﨑駿の精神世界である。そこでは生者と死者が行き交い,過去と未来が混ざり合っている。過去の作品世界が引用としてでなく,メタフォリカルに重なり合いながら存在しているのだ。「わらわら」という存在が地底から「地表」を目指して飛んでいくシーンがある。わらわらはおそらく「受精卵」あるいは「物語のインスピレーション」だ。生命や物語は,厳しい淘汰圧を耐え抜いたものだけが存在しうる。それを食べる「ペリカン」たちは,生命や作品に「カネ」の匂いを嗅ぎつけた資本家であり,批評家であり,一般大衆でもあるのだろう。ジブリ作品にしてはやや造形の書き込みが足りないような気がするが,「創作」に関するプリミティブな考え方に触れることのできる重要なシーンである。地底世界には,「塔」(=物語)の中で姿を消した白髪の「大叔父」が登場する。彼はおそらく宮﨑駿本人だろう。だとするとここで矛盾が生じることになる。観客は眞人を宮﨑本人だと思っているからだ。しかし,実母の「ヒミ」,老女の「キミコ」が若かりし頃の姿で地底世界に存在していることから,その矛盾は特に問題視しなくて良いだろう。眞人は過去の宮﨑,大叔父が現在の宮﨑であるという推論はコロラリーとして容易に成り立つ。インスピレーション源の『君たちはどう生きるか』は「叔父」と「コペル君」の対話がベースとなっているが,本作では叔父が大叔父,コペル君が眞人に翻案されている。宮﨑は脚本をツイストし,叔父とコペル君のアイデンティティをも縫合してしまったのだ。それは「過去の自分」と「未来の自分」の対話でもある。すなわち本作は徹頭徹尾,宮﨑による内面の吐露だ。それは私たちに説教をする内容の映画ではない。むしろ「自分はこう生きた」という宮﨑自身の生の証明になっている。いい画を容易に描けるようになった宮﨑が,あえて背景やパースを崩して表現したかったものは,あまりに個人的実存だったが,国民作家によるそれはあまりに普遍性を獲得している。日本アニメーションの巨匠に許された自由な自己表現は,難解でありながら観客の心奥に訴えかけるものでもあったのだ。本作は児童文学としての性質を持っているため,むしろ子どもたちのほうが純粋に冒険譚を楽しめるのかもしれない。ロジックやクリティカルシンキングに馴染んでいない子どもたちは映画の混沌を混沌そのものとして受け止めることができるだろう。そんな純粋な作品を86歳にして作ってしまう宮﨑駿はやはり天才的な作家である。
終始荒唐無稽↩︎監督自身も意味不明と言及 結論何の意味もない。だが名作
タイトルでも言いましたが、間違いなくジブリ最高傑作です。だが難解。鑑賞後のカタルシスが凄いです。
今までの駿ジブリは子供でも楽しめるが大人も楽しめると言った様なスタンス。今作でも残っていますが、10年前の風立ちぬから若干路線変更しているように伺えます。特に血シーンや難解などストーリー構成でしょうか?
本作も風立ちぬも血シーンが有ります。
お子さんには若干ショッキングに映ると思います。後、本作はネットやら口コミやらで難解だからと言って視聴を控えるのはかなり勿体無いと思います。なので寝ている人が多かったです。前述した通りですが、本作は難解です。しかし難解でも美しいアニメーションや世界観で私を引き込んでくれてとても素晴らしいです。今までほぼ全てのディズニー映画、ジブリを鑑賞してきましたが、ここまで考えさせられる内容の映画はないと感じました。本作はハッピーエンドですが、考え方によってはメリーバットに捉える事も可能です。
ディズニー映画お得意のお涙頂戴的なハッピーエンド映画が苦手、だが、バットエンドも苦手な人にかなりおすすめできます。
以下、ネタバレを含みます。難解な点や面白いと思った所、考察など書いていきます。
①結局本当の母親は死ぬ。
母親は死にます。しかし異母と打ち解け合えた事によりハッピーエンド。義母は戻って来られる。私はいいと思います。2人で本音をぶつけ合うシーンでは躍動を感じました。
②鷺男の正体が謎。
映画を見る前、あらすじを見たので、こいつが大叔父かと思いましたが、見事に違いました。
他の口コミを見ていると弟説が浮上していて、私もこの説を推しています。
この鷺がラストシーンで「あばよ、友達」的な事を言っていました。最初は気が合わない。水と油→キリコに諭され、共に行動&協力し合う様になる(友達になる)→ラストシーンであばよ(別れを告げると共に、友達を辞め、家族になる、二重の意味)
が私の考察です。正直、口コミを見ないとコイツの正体は分かりませんでした。弟説が正しいとは
限りません。
③実母とキリコがなぜ下の世界にいるのか謎。
どちらも若返った状態でこの世界に留まっています。実母は鷺のいった通り、遺体がありません。
なので、成仏できず、この世界に留まっている?
問題はキリコです。キリコは主人公と、同じく下の世界に投げ出され、最終的に若返った状態のキリコから駒?の様な物が渡され、現世で変身しています。若いキリコは若い実母と共に、違う扉へ姿を消しました。実母は若い頃、一度、下の世界に迷い込んでいたが、キリコはその様な事は言及されていなかった。↩︎言及されていたらごめんなさい。しかしなぜ2人ともこの世界にいるのか、さっぱり意味がわかりませんでした。若い頃のキリコさんはせんちひのりんの様な存在でした。しかし実母の死であの様に捻くれてしまったのでしょうか。
④主人公はなぜ自分の頭部に傷をつけたのか
本作のグロシーン。
お父様に車で送迎、おまけに高そうな服。
いじめの標的にされます。
河川敷で格闘しますが、ボロ負け、石で頭部に傷をつけます。自分で。これはいじめられてやり返す事ができないやるせない気持ちを表現しているのでしょうか?キリコにも同じ傷が付いています。又は肉親である父親に構って貰いたい幼さの現れ?トイストーリーのウッディの様に感じた。
結論
自傷行為をする事によって自分の悪と向き合う。
主人公を成長させる為、自分の悪意と向き合う。
これがこの作品のメッセージではないでしょうか
この作品について駿も意味が分からないと語っています。
この作品は一人一人自分自身の物語であり、人により
解釈が大幅に異なる。
衒学と人間讃歌の元、スタジオジブリはどう生きるか
何かと話題の宮崎駿監督の最新作「君たちはどう生きるか」を観てきました。
宮崎駿監督の作品としては約10年ぶり。スタジオジブリとしては約2年ぶりの新作で事前のセールスプロモーションを全くやらない。事前情報も無しと言う前代未聞のプロモーションが逆に話題となっていましたが公開から作品の内容に対しても賛否両論。
その真偽と言うか意見も観ないと分からないとあって、鑑賞をした訳ですが、で、感想はと言うと…個人的な一意見ですが、面白く無い訳ではないが、面白い訳でないw
一言言えば複雑だし、必要以上に難しくこねくりまわしている感がある。
ジャンルとしては冒険活劇ファンタジーらしいけど、正直それだけでは括れない難解さがあると思うし、また説明が不十分な点が多く、哲学的と言うか文学的な側面がある。
吉野源三郎原作で1937年発表の「君たちはどう生きるか」に感銘を受け、直接の原作ではなく、タイトルとして引用されているらしいが観る限りにはやはりその影響は多分にあると思う。
観る側の器量を試されるというか、実験的な作りは嫌いでは無いんですが、まあジブリっぽくはないんですよね。
長年ジブリ作品を観てきた者にすれば老若男女が楽しめる、ある程度明快な作品がジブリの信条かなと思うんですが、人間讃歌と言うテーマは変わっていないと思います。ただいろんな部分が挑戦的で観る側に突き詰めると言う感じ。
その兆候は「風立ちぬ」で庵野秀明監督を主人公の声優に起用された時にもあった訳ですが今回はもう全部がそうなっていて“どうしたこうなった?”と言うよりも”うるせえ〜どうせもう何作も作らないし作れないんだから、たまには好き勝手に作らせろ!”と言う開き直りな感じなんですよねw
いろんな不足点を埋めるように観る側の思考が錯誤するんですが、これって庵野監督が得意とする手法で「エヴァ:Q」でも観られた「衒学」(げんがく)かなと。
衒学とは知識がある事を自慢する事であり、知ったかぶりという言葉が一番近い。
何か裏がありそうな雰囲気を出すための演出であっても実際に裏は存在せず、観る側に衒学を漂わせると言うか。
まあ「お金を出して観る人が好き勝手に解釈していいよ」と言う答えだと思うし、だからこそ一切のプロモーションをしないのがプロモーションとなっている訳ですが、事前のプロモーションをやらないのは今までのジブリブランドがあればこそな訳で、これが普通の作品ならもう大爆死ですよw
作品としては「千と千尋の神隠し」「もののけ姫」「ハウルの動く城」的な感じもあり、今までのジブリ作品のセルフオマージュも多分にありなので観る側にいろんな問い掛けが仕掛けられている。
かと言って今までのジブリ作品のイメージで思い込むと手痛い目に合うので、一切のイメージを捨てて、全くの新作で観るのが正解かと。
それでもなかなか難解な作品ですが、声優キャストは結構ツボにハマるキャスティングでアオサギ役の菅田将暉さん。ヒミ役のあいみょん。ばあやのキリコ役の柴咲コウさんはかなり上手い。特に菅田将暉さんは熱演です。
宮崎駿監督は今後作品を作るのかは不明ですが年齢的な事を考えるとかなり難しく、スタジオジブリとしても新作が出来るのかは不明。2014年公開の「思い出のマーニー」で映画制作部門を解体し、一度アニメ制作から撤退しているので主要スタッフが抜けている分、「無為自然」的な流れになっている。
勿論、ジブリ作品が新しく作られるのは嬉しいし、勿論観に行こうとは思う。
だけど、ある程度のイメージの構築は仕方ない分、スカされた感は残念ではあります。
宮崎駿=スタジオジブリのイメージから結局脱却しきれなかったのは今更言っても仕方ないけど、スタジオジブリのブランドはやはり残して欲しいかなと。
もし、もう一回だけ作ると言うのであれば…庵野秀明監督で「風の谷のナウシカ」の続品を作るのであれば、個人的にはもう大歓迎ですw
私たちは、なぜ生まれ、どう生きるのか、━忘れていた魂の記憶を思い出させる、真の天才による世界で永遠に語り継がれる偉作
観終わって、子供たちの未来のために、自分にできることを精一杯やろう、と思う━。それが、宮崎監督からの問い、「君たちはどう生きるのか」に対する答えである。本作は、表面的な感想、評論、批評を、一切受けつけない。語る者は、監督からの問いに対する、自分なりの答えを見出し、表現してから語るべき作品だと思った。
これまでの宮崎作品のエッセンスが凝縮された集大成であるばかりでなく、今まであまり明確にされてこなかった重要なコンセプトが表現されている。それは、時空を超えたいのちのつながり(縁生)であり、生まれ変わり(誕生と死の循環・輪廻転生)であり、異次元世界(あの世・常世)と現実世界(この世・現世)が、力動的に共振・協働している関係の世界観である。
「君たちは『なぜ』生まれてくるのか」━。この問いに対する答えがあって、初めて、「『どう』生きるのか」、が出てくる。本作は、なぜ、悲惨なこの世に、それでも君は、自ら願って生まれてくるのか、が問われる(あの世は、ある意味、安定しているにもかかわらず)。その答えもまた、宮崎監督は描いている。本作は、私たちが忘れてしまった、なぜ生まれてきたのか、どう生きるのかを思い出させてくれる━いや、観た者が、それを思い出してくれることを願って生み出された作品だと言っても過言ではないのかもしれない。
プラトンによれば、私たちの魂は、生まれてくる前、レイテの泉の水を飲み、すべての記憶(あの世の記憶、過去世の体験と智慧)を忘却して生まれてくるという。しかし、この世にあるイデア(真実・永遠の真理)のかけらに出会うと、魂が震え(感動と呼ぶ)、求めるようになり、忘れていた記憶を少しずつ思い出す(想起する)ようになる━。本作の主人公もまた、忘れた魂の記憶を思い出す、試練の旅に出る。
なぜ、悪は存在するのか。悪の必然と意味もまた、語られる。あらゆるいのちとの共生、自然界の見えるいのちも、見えない異界のいのちも、すべてつながり生かされ、それぞれの役割を果たしている。無駄なもの、不必要なものなど何一つなく、秘められたいのちの可能性を開花し、謳歌し、すべてがダイナミックに調和し共生する世界のあり様を、宮崎監督の世界観とすれば、それは未来からやってきたヴィジョンであり、古代からあった永遠の真理であろう。だから、本作は、これから永く、世界で観られ、語り継がれるだろう。その必然と意味、力が、本作にはある。
宮崎駿は、日本の自然と文化に育まれた、間違いなく真の天才━genius:ダイモン・守護神と協働する「聖なる狂気」の人━である。
漫画「風の谷のナウシカ」から続く宮崎駿先生の「不完全な私たち人間への慈愛」の想いを受け止めた
かつて映画の「風の谷のナウシカ」のエンタメすぎるエンディングに非常に落胆をした者です。漫画の「風の谷のナウシカ」を愛読しています。だから漫画を読むたびに、宮崎先生の「ナウシカ」に込めたメッセージは一体いつ映画で発信されるのだろうとずっと気になっていました。昨日、まったく前情報なし期待無し(すいません・・・)で「君たちはどう生きるか」を観ました。鑑賞後、万感の思いで胸がいっぱいになりました。漫画「風の谷のナウシカ」が形を変えて、ここでつながったのだとすとんと腑に落ちました。宮崎先生、本当にありがとうございます。この不条理な世の中で決して善人でない私(少なくとも私)たちはこれからどう生きるか。深い問いかけに答えることはとても難しいです。しかし、前を向き地に足をつけて限られた一度の人生を歩んで行きたいと考えます。
企画自体が面白い
これまでの作品を「悪意に満ちた13個の積み木」とは。ここまで言いたいこと言うためにジブリ単独出資で宣伝も無しで勝負するとは、宮崎駿作品の集大成として見事な戦略です。
内容より、この企画自体が面白いですわ。
要事前学習/「母の死の受容」と誰もが持つ魔界
吉野源三郎の原作は戦前に刊行されましたが、子ども向けの哲学書として読み継がれてきました。17年に刊行されたマンガ版は空前のヒットになるなど、教養の一つとして浸透しています。
宮崎駿が同じタイトルで映画を作るとなれば、原作を踏襲することになり、そこにどんな宮崎流、ジブリ流の創作が加わるのか? それを楽しみにするのは自然だと思います。
本作で、原作が登場する場面が一ヶ所あります。主人公眞人が、母久子が遺した小説「君たちはどう生きるか」を発見し、それを涙して読む場面です。そこからは、原作に対する肯定的な姿勢が読み取れます。
■母の死を受容するというテーマ
小説「君たちはどう生きるか」は亡き母が遺した、という点がポイントになります。
母の死は、本作を貫くテーマです。この場面で不意に、眞人が求めてやまない母からのメッセージが現れます。それは、まさに眞人が今後、世界を生きるための知恵であり、亡き母からの贈り物です。
その後、眞人は母や、義母・夏子を探す旅に出ます。行き先は魔界(下の世界)。
そこで、母と再会し、夏子やキリコを連れ戻すといった冒険を繰り広げます。原作「君たちはどう生きるか」の拡張を期待した私は、その冒険ファンタジーと原作とのギャップが、鑑賞中に処理できなかったというのが正直なところです。
わかりにくい本作がシンプルにみせるのは「死と生」に対する謙虚な姿勢です。
母の死を乗り越えることが、眞人の人格形成には避けて通れないことです。本作ではその過程を、内面心情や、現実世界の体験から直接描くのではなく、冒険ファンタジーとして置き換えて示してくれています。
母の死を受容できず、義母も受け容れられず、そこに弟が誕生してしまう。「下の世界」に旅立つのは、そうした精神的にどん底状態のタイミングです。そして「下の世界」は単に魔界というより、死と再生(誕生)の場であり、そこでもたくさんの生き物?たちが登場し、再生の物語が紡がれています。
そこで眞人が体験したのは、死と再生の現実です。そこは決して楽天地ではなく、均衡をとるのも難しい厳しい世界として描かれています。いずれにせよ眞人は、現実世界を覆うもう一つ大きな世界を体験しました。
■原作との三つの関連性
改めて、原作との関係を考えてみます。また、問いとしての「君たちはどう生きるか」に対する宮崎の答えはあるのでしょうか。
仮説はいくつか立てられます。一つは、原作が説いた人格形成の不足を補完したという点です。
原作が発表されたのは戦前の昭和12年。大衆文化を背景に、原作は自己形成に「個の確立」が重要であることに踏み込みました。原作は当時、旧制中学校・高校のエリート予備群に対してかなり衝撃を与えたかもしれませんが、現代でそれは常識の範疇で、これを唱えても若者には届かない。
そこで、精神的な「親殺し」に触れていく。もちろん「親殺し」とは親を殺めるわけではなく、親と離別し、親という存在を超えていく精神的な自立過程を指しています。本作でいえば、眞人が母の死を受容し、義母や義弟を受け容れるという精神的な葛藤場面です。
原作ではコペル君の父親が亡くなりますが、そこでの「死」は薄い影でしかありませんでした。本作では、父と母の違いがあるものの、母親の死を一貫したテーマとして、それを受容し超えていくことが、人格形成になくてはならないものと捉えています。
そして、本作において親殺しの葛藤は、死や再生という「生き物の宿命」を自覚する契機になります。それが人格形成に不可避なことだとすると、原作には触れられていませんし、そのメッセージは原作が書かれた時代にはなかなか理解されなかったと思います。
若者に限らず今を生きる我々が「生命」の循環を理解し、考える。これが本作のメッセージと考えるのが自然だと思います。これが二つ目の仮説です。
三つ目は、原作の教養主義的な欠点を、補完した点です。
原作は、戦前に書かれたこともあり、かなり教養主義的です。学問、修養、芸術といった教養の習得によって人格陶冶ができるという核心に基づいています。しかしこれは、知識吸収が得意ないわゆるエリート向けに用意された啓蒙ルートということもできます。
本作は、若者に哲学を促すのには、もっと想像的で、直感的なルートがあることを説いたと考えられます。「生き物の宿命」や「生命」の自覚が必要だということを多くの人々に伝える場合、教養主義的に説得するより、文学的に描いた方が伝わりやすいのは事実だと思います。
■なぜ「下の世界」は崩壊したか?
それにしても本作はわかりにくい。
特に、「下の世界」が突然崩壊する場面は問題です。それも、それは主人公の眞人が継承者として指名された直後です。ただ、そのわかりにくい場面が、物語を読みとくヒントになります。
本作は「上の世界(現実世界)」と「下の世界(魔界)」との二層で構成されています。特に「下の世界」は人格形成の葛藤を描くファンタジー世界であり、生命再生の場として描かれています。
そして終盤、大叔父は眞人に「下の世界」を継承するように勧めます。
われわれ観る者は、「上の世界」同様、「下の世界」は継承すべき価値ある世界だと理解する一方、なぜ大叔父が支配者で、眞人が継承者なのか判然としません。
また、継承するのに眞人は生命を投げ出さねばならないのか、疑問も膨らみます。
こうしたなかで「下の世界」は、いとも簡単に崩壊します。
その崩れ方はまさに積木くずし、あるいは夢の終わりのようです。
ようやく、本作を貫くテーマが母の死の受容であることを理解し、二層構造が持つ意味を考えはじめた頃、「下の世界」は崩壊してしまい、われわれは置いていかれます。
本作の一貫したテーマは、母の死の受容でした。
ようやく眞人が「下の世界」のさまざまな経験を経て、母の死を受け容れられたところで、眞人の旅は終わりました。
そして、その時点で「下の世界」が不要になったといえます。
■誰にでもある「下の世界」
作中で、「どの世界にも塔が存在する」(うろ覚えです)と「下の世界」の秘密が披露される場面があります。
塔とは「下の世界」の入口のことですが、これは、世界中の人間誰もが、それぞれ心の内に「下の世界」をもっていると考えるべきでしょう。想像力が発揮されれば、誰もが「下の世界」を召喚できます。
ここまで考えて、ようやく本作は物語になります。
原作を補完するように、親を失う(親殺し)場面が設定され、改めて「君たちはどう生きるか」が問われる。
そこでは、死と再生という大きな世界を、一人ひとりの想像力を駆使し「下の世界」を経験することで、はじめて理解できる。自分が生きていることを日常生活を覆うもう一つ大きな世界から捉えなおす。
このような形で「君たちはどう生きるか」に応えた物語なのでしょう。
美しい日本式アニメだけど
無広告戦略にダマサレタ。思索的な映画、もちろん有っていい作家映画なれど、たしかにこの内容を広告していたらここまでの集客は無かっただろう。悪い映画とは思わなかったがやられた感を引きずる。
テーマはわかりやすい。でも傑作ではないと思う。
置いていかれるとか、理解できないとか、聞いていたので身構えましたが、テーマはわかりやすいと思いました。本の『君たちはどう生きるか』を読んだことがあって、テーマがリンクしているだろうと推測しながら観たからかもしれませんが。
読み返したわけではないので曖昧ですが、本では「人は成長過程で自分中心のものの見方を離れ、社会を俯瞰して見れるようになる」とされていたと思います。
私が映画で気になったのは「義母が眞人を『大嫌いだ』と言った後、眞人が急に『お母さん』と呼ぶようになった」シーンです。
眞人はここで[義理の親子になったことに義母も苦しんでいる]ことに初めて気がつき、[だからこそ自分のいない異世界に来て出産しようとしている]と理解したのではないでしょうか。そして[義理の親子という関係を築く]覚悟をしたのだと思います。
(なんで妹と再婚?というレビューを散見するのですが、この頃は結婚は家同士でするもので、配偶者が死んだ時に兄弟姉妹と再婚することはよくあったと聞きます)
本でいうと冒頭なので、映画では自分中心の子供時代をゆっくり描いている感じです。
他にもいろいろあると思うのですが、本では最後に「自分で考えて生きること」を訴えていました。
映画でも眞人は「与えられた無垢の石で新しい世界を築く」という用意された道を拒否し「戦時中の混乱した世界に戻って友達と協力して生きていく」ことを自分で決めます。
そしてラストシーンでは、戦争が終わり東京に帰るという変化の時に本を持っていたことから、その後も眞人が自分で考えて生きていこうとしていることが示されました。
テーマが好きだし、全体として嫌いではないけど、傑作という印象ではありませんでした。
その時代がそうだったと言っても男尊女卑を無批判に描くのはどうなのか?と思いますし。眞人がタバコを渡したりクチバシを治したりと男性(らしきもの)には報酬を払うのに、女性には無報酬で助けてもらう、という描き方も気になります。
監督がジブリや自分や後継者を重ねて作ったかはわかりませんが、もしそうだとしたら、プライベートフィルムとして身内で見ればよいものです。
映像もセルフオマージュなのかもしれませんが、過去作を上手く織り込んであるというより、見覚えのあるもののツギハギという印象で、懐かしくて感動するより先に飽きてしまいました。
ザ・ジブリ
映画館に行く機会がなく、とりあえず久しぶりに行こうと見に行った。
最後に見たジブリは本当にナウシカとかトトロとかの時代のしか見ていない。
冒頭から懐かしいジブリの映像があった。BGMもなく、日本家屋の床を歩く音などとても心が落ち着いた。
話が進むにつれ話が雑に分裂していると感じた。母親の死、アオサギ、おばあちゃん、曾祖父、外れにある建物、話がばらばらでいずれ紐解かれるにしても雑に広げている感じがあった。話もリアルよりでファンタジーじゃないのかと思っていた。
そこから話が展開していき一気にファンタジーになり、話の展開的には前半は話がバラバラだったが、幼少期の母親とインコの家で出会ってからは割と楽しめた。最終的には自分が求めていたジブリをしていてよかったと思う。
最終的に特に感じることはなく、まあジブリってよかったよかったで終わるのはらしいから、これで十分な気がした。
ただ、話の展開の仕方の雑さ、面白い部分が後半からしかなかったりと展開が全体的に満足するものではなかったなと思った。
あとは、視聴者からすればメタ的に読み解くことができる部分を登場人物たちがなかなかの速さで理解していたのが結構気になった。まあ、賢ければそんなものかと流しているが、もしかしたら世界が南淳もしていたりなど秘密があるかもしれない。
まあ、ジブリなのでそういった考察は野暮なので特に気にせずジブリを見たという満足感だけで十分よかった。
宮崎流身勝手の極意!
宮崎さんは最後に高畑勲さんみたくわがままし放題をやりたかった。
かぐや姫の物語みたいに金と時間とスタッフを贅沢に使いまくり庵野さんから超有能なスタッフを引き抜きファンにもスポンサーにも忖度しないわがまま作品をつくったんだなと思いました。
その結果はかぐや姫の物語と同じくなんとも言えないつまらん作品に仕上がった。
それでも宮崎さんのコアなファンは評論や分析や解釈のしがいがあって大喜びですかね。
ネタバレなのかな?
主人公の母親は、「君たちはどう生きるか」を大人になった息子へ贈ります。この作品は本来は青年に成長する前の子供向けに書かれた作品。自分で考え行動する習慣を持ちなさいってね。
一般に物語の主人公は作者の分身であり読者の分身でもあります。
つまり宮崎版「君たちは〜」は、これまで忖度しまくった作品を残してきた宮崎さんの過去の自分への決別宣言であり、さらに大人になっても子供向けアニメみたく分かり易いストーリーを期待してわからんぞと憤ってるファン(私)への説教かなと。
マーケティングの勝利
事前情報をシャットアウトしての公開は、宮﨑駿の復帰作だからこそ成立するマーケティング手法ですね。じゃあ映画の中身がそれに伴っているかと言うと、正直言ってあんまり関係なく、単純にファンタジーものとして楽しめました。じゃあ、ファンタジーものとしてどうかと言うと、正直言って過去の宮﨑作品の既視感たっぷりの内容でした。しかし、後半の異世界篇から段々と世界観や誰が何をしたいのかの方向性が分かりにくくなって迷走気味なのが残念。この体験が主人公の少年にどのような影響を与えたのかもよくわからず、パッツンと切ったような幕切れも唐突です。宮﨑駿ファンには悪いけど、監督の心境とか、なんかのメタファーがあるかもしれないけど、ピンときませんでした。役者では、菅田将暉がビックリのキャスティング、全然気がつきませんでした。
難解?いえいえ カへカへ テーマはわかりやすい「コピー」です カへ
7月14日、15日、16日、22日視聴。
映画が、まだ身体の隅々まで沁み入っていない現時点での感想です。
まず、以下『』内、私の7月19日tweetを、ご覧ください。
本稿のダイジェストとなります。
『 ネタバレ注意
インコは声真似。コピー の象徴かと。
大叔父様や彼の築いた世界は、黒澤明監督的な存在や映画界の比喩でしょう。
最終盤「時間がない」のに追い打ちをかけるようにインコ大王(コピー)の心ない行動で映画界は崩壊。
宮崎駿 流の警告?
定めならね 従うしかないんだよ? 』
君たちはどう生きるか のテーマ、「コピー」は2通りあるように思えます。
インコを通して描かれるもの
インコを通さず描かれるもの
今回は、公開後徐々に声が大きくなってきていると思われます、インコを通さず描かれる「コピー」 セルフオマージュ(今までの宮崎駿作品にこんなシーン出てきたでしょ)
については、記述しません。
インコを通して描かれる「コピー」についての記述となります。
まず、君たちはどう生きるか でインコとは何か。
インコは声真似をします。これは「コピー」の象徴かと思われます。
スタジオジブリは、自社映画作品の国内でのネット配信(アマゾン、Netflixなど)を認めていません。これは、一言でいえば行き過ぎた「コピー」を嫌っているからです。
作品最終盤、インコ大王は、心ない行動により大叔父様の築いた美しく幻想的な世界を
崩壊させてしまいます。具体的には、大叔父様が眞人に3日に1個づつ積むよう用意した13個の悪意に染まっていない石を、インコ大王が、まるでファスト映画を表現するような素早い動きであっという間に積み上げてしまい、積み上げられた石は案の定すぐにバランスを崩し~大叔父様の築いた世界はあっけなく崩壊します。
また、インコ帝国にいる無表情な、おびただしい数のインコたちはネット配信など、氾濫する「コピー」のわかりやすい例えでしょう。
つまり、ネット配信やファスト映画など、行き過ぎた「コピー」の横行によって、いまに映画界は崩壊しますよ、という重大な警告メッセージというわけです。
続いて
大叔父様や彼の築いた世界は、黒澤明監督的な存在や映画界の比喩でしょう。
について
「1993年4月、宮崎駿監督は、黒澤明監督と対談します。その模様はテレビ放送され、今もYouTubeで視聴することができます。また書籍化(「何が映画か」)されています。
宮崎駿監督52歳の頃です。対談の様子を一言でいうと、平身低頭。宮崎駿監督は黒澤明監督への敬意を隠そうとせず、聞き手に徹しています。」
「」内は、ー神の隠れる場所 映画「千と千尋の神隠し」のネガフィルムーより
一言でいうと、宮崎駿監督にとって黒澤明監督は憧れの存在です。また、アニメというくくりでなく広く映画界というくくりでは、宮崎駿監督は黒澤明監督の直系後継者という声が散見されます。
さらに、眞人の夢に出てきた、大叔父様が卓上で自分の積んだ石のバランスを確認するシーンでは、バランスを確認した高く積み上げられた方の石は7つ。(それとは別に2つの石が同じ卓上に。)この7という数字は、黒澤明監督にとって芸術全般の「最良の友」早坂文雄氏とともに完成させた「生きる」「7人の侍」「羅生門」を含む全盛期7作品を指していると思われます。
(※映画「千と千尋の神隠し」で釜爺が千尋らに渡した回数券の残り枚数は4枚。回数券は1951年から11枚綴りが定着。使用された7枚の回数券の意味は?詳しくは ー神の隠れる場所 映画「千と千尋の神隠し」のネガフィルムー を)
話が堅苦しくなりましたが、スタジオジブリ公式ツイッターのトップページを、ぜひご覧ください。7月14日公開日以降、かわいいアオサギのキャラクターがカヘカヘ鳴いています(笑)これはアオサギの鳴き声のふりしてモールス信号という声が大きいですが、私はさらに映画のテーマである「コピー」を表現していると読みます。
昔は(今でも)コーヒーのことをカフェと。カフェを単純化してカヘに。
カ→コ、ヘ→ヒに置き換えるとコとヒ、つまり「コピー」が浮かび上がるという仕掛けと
読んでいます。
ぜひ家族連れで鑑賞していただき、観終わった後上記のようなうんちくを、お子さんに。
気軽に本物の芸術に触れるチャンスかと。
面白い。が、鳥苦手な人は見ない方がいい。
とても面白かった。宮崎さんの良いところが出ている。仮にストーリーが分からなくとも作画だけでも楽しめる作品。ネタバレになるが、鳥が苦手ならマジで見ない方がいい。ほぼ鳥しか出てこない。系統的にはファンタジー。
全763件中、301~320件目を表示