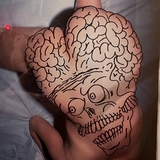君たちはどう生きるかのレビュー・感想・評価
全1336件中、501~520件目を表示
俺はこう生きたけど
頭に「俺はこう生きたけど」と付けると、
今までの作品はこうやって作ったんだ。
俺のこの体験が後のジブリの作品になったんだ。
と言ってるように思えて、
あぁこれが本当に最後の作品なんだなと思えて
感慨深くなった。
全く情報を与えないと言う策略も重なって
宮崎駿監督生きてるよな?と見終わって心配になるほど
集大成的な映画だったように思う。
誰もが、あれ?これあのジブリのあのシーン!
と思うような場面が散りばめられてて、
そのワクワクと同時にこれが最後と言われてるようで
悲しくもなる、そんな映画だったと思います。
ただ、宮崎駿監督の描くキャラクターって、
どんどん何考えてるか分からなくなって来て、
キャラクター同士の関係性も希薄になってるように
思えて、感動するべきシーンで全く心が動かなかった。
どう言う事?なんでそうなるの?
と引っかかる部分が多くて、
昔みたいにワクワクドキドキして
キャラクターたちと一緒に冒険してるような感覚に
なれなかったのが残念でした。
ジブリで育って来たと言うのがあるので、
俺はこう生きたけど君たちはどう生きる?
と言う宮崎駿監督からの問いかけだったとしたら
劇場に足を運ぶしか選択肢はなかったです。
面白いけど面白くないけどつまらなくはない
アオサギ頑張ります!観客の皆さんも大注目です。
ネタバレ厳禁!らしいので鑑賞記録のみを記載します。
8/5土曜日11:35から109シネマズ湘南シアター4で鑑賞。
167席のお部屋でお客様の入りは8割方、夏休みの土曜日の昼間の上映回なので、半分くらいは子供連れの家族客、高校・中学生らしい若者グループも多数。賑やかな感じであったが、始まったら皆さん、マナー正しく、スクリーンに見入っていました。スマホを見たり、お菓子をガサガサする不届き者もまったくなく、作品に集中していました。
私も静かにいつものようにポップコーンセット頂きながら、宮崎ワールドに浸っていましたが、残念ながら、残業続きで相当疲れていたせいもあり、ちょっとウトウトしてしまいました。
もちろん、見る価値十分です!
宮崎駿最後の作品、いやジブリ最後の作品にしたかったのかな?
作品が始まって20〜30分経って、この映画はいつ面白くなるんだろう?と、でも必ずどこかで挽回してくれるはず!だって天下のジブリ宮崎駿作品なのだから!と信じて見てましたが、とうとうラストまでその時は来ませんでした。
もう感想うんぬんよりもなぜこんな作品になってしまったのかを色々考えて見ました。
制作中に宮崎駿監督がなんらかの理由で現場からリタイヤしてしまい仕方なく続きを息子の吾郎さんが勘で完成させた。
ここまで視聴者置いてけぼりにしたのは実はわざとで、過去のジブリ作品のファン達に「ジブリはもう終わり、限界です。いつまでもジブリに幻想を抱かずもっと新しいものを見つけて生きていってください」というジブリファン達にジブリ卒業を促す宮崎駿最後のメッセージだった。
宮崎駿監督80歳を超えて、お年寄りによくある頑固さが抑えきれずに周りが制御できなくなってこんな作品になってしまった。
など。
宮崎駿監督いままで素晴らしい作品をありがとうございました、お疲れ様でした。
自分は紅の豚が1番好きです( ^ω^ )
宮崎駿のもうひとつの集大成。大衆向けではないけど好き
又聞きの評価がどれも「難しい内容だった」というものが多かったので興味本位で視聴。
結論を先走るならば、「なるほど。確かに深い映画だ」、「宮崎駿らしい描写で考える人生論」というものが浮かんでくる。
タイトルにもある通り、“生”が大きく関わってくる作品だからこそ、そのテーマも重く深いものになってる。
“どう生きるか”と考える瞬間は人生の中に幾度と無くしてあるもので、その度に始まる新たな出会いは勿論、かけがえのない存在との別れ。それらを何度も繰り返すことで、人として真っ直ぐに成長をしていく。
それらを宮崎駿風の冒険活劇を通して、映画として見せられていたのではないかと思う。
難解だったという意見に関しては、同情をせざるを得ないのが正直。
上映中にも過去のシーンと今見ているシーンとを照らし合わせて、「このシーンの描写は前のこのシーンと重ねることで意味を成すのか」と思えるような描写が幾度と無くあったこと。
またそれ以上に先述の「どう生きるか~」の考えに至るのも、上映終了後小一時間考えに考え抜いて至り得た感想である。
普段にはあまりない経験だった、からこそ「難しい」といった意見も感覚として理解を深くも思えてしまう。
総じて、自分個人としては面白かったし、知人に勧めるのも憚らない完成度の映画にとは思うが、何分難解さを秘めいているのも事実であるからこそ、映画的「大衆娯楽」性があるかと言われると一考の余地がある。
人生をアニメーションという比喩を通して考えさせられる
ジブリの新作「君たちはどう生きるか」
生と死の厳しさ、戦争、人生の生き方と困難。
この幅広いテーマを一本の映画で、しかも全て比喩で表現されている。
一つ一つの所作や言動に意味があり、どこに感銘を受けるか受け手の見方によって大きく変わる。
そのため全ての人がこの映画から大切なものに気付かされる素晴らしい大作だと思う。
しかし万人にオススメするわけではない。この映画は最初から最後までほぼ比喩で表現されている。だから頭を空っぽにして受け身でも楽しめるジェットコースターのような映画だと思うと意味がわからず退屈な時間になると思う。
目線、セリフ、ワラワラ、アオサギ、積み木、波、、それらが何を表しているのかどんな心情の変化があるかを考えながら見る必要がある。
名作と呼ばれる映画は必ず賛否両論分かれる。ただこのレビューを最後まで読んでるあなたは確実に充実した時間を過ごせるだろう。
僕たちはどう観たらいいのか
ジブリでいちばん好きなのはとなりのトトロ。ネコバスの行き先が「メイ」になるところで落涙必至。それ以外の作品には特に思い入れがない。なので正直、本作が意味するところを考えるのはめんどくさいだけでしかない。
宮崎駿のキャリアなのかジブリ作品群の投影なのかわからんけど、好意的に解釈しなければ、82歳の監督は認知症じゃないかと思ったほど(超失礼)。監督の作品づくりはシナリオが彼の頭の中にしかないというやり方だし、出来上がりを観た鈴木敏夫も宣伝に困って、事前情報を出さない手法を採ったのではないだろうか(暴論)。
仕事疲れもあって中盤はスクリーンを薄目で観つつも度々意識が違う場所へ飛ぶ始末(レビューを見たら寝た人多かったようで…)。それでも客は大入りだしオレ自身観てしまったわけで、あらためてハヤオ&ジブリのブランド力すごい。それははっきりわかった一作。
サギが出てきます もうおわかりですね
宮崎駿監督の作品には駄作はないと常々思っております 今回も少なくとも期待は裏切られないだろうと思って映画館に足を運びました 「君たちはどう生きるか」からは着想をえたらしいです でもサギのキャラクターが出てきて、異世界に主人公が入るあたりから、原作は全くかんけいないことがわかりました それからはひたすら退屈な時間を過ごすことになります
サギってそういう意味なんですね 監督自ら「何か期待してるらしいけど違うよ」ってことですね アニメで哲学的な問答をどう描くのかに期待したのですが、過去に見覚えのある陳腐な”ファンタジー”場面のオンパレードでした 引退を撤回して10年も費やしてまで何を描きたかったのでしょうか
明らかにサギなんですが訴えても賠償はとれませんのであらかじめご了承の上鑑賞を
この物語が何に?
キャンディーズの「微笑み返し」ですな。
つくづく宮崎駿は、商売上手ですな。(悪い意味ではないが、あざとい)
・「魔女の宅急便」では、ユーミンの曲をつかってママ世代に訴える。
・「ハウル・・・」では、当時人気のキムタクを声優に起用。
・「風立ちぬ」では堀辰雄の小説や、松田聖子の曲と同じタイトルにする。さらにユーミン の曲も使う。
本作では「君たちは・・・」の小説や、5年前の漫画版のタイトルを、内容にほぼ関係なく無理やり入れ込む。
映画の内容(映像世界だけ)は、過去の作品のオマージュで綺麗です。
昭和のアイドル・キャンディーズは、過去のヒット曲をオマージュした「微笑み返し」を解散前に発売して大ヒットしました。
でも、この映画はだめでしょ。
・疎開した少年の葛藤や悩みのエピソードが弱すぎる。
・大叔父の世界や、積み木のモチーフが弱すぎる。
終戦前後の少年の葛藤を描いた映画では、高畑勲の「火垂るの墓」の方が100倍染みわたります。見るのがつらくて何度も見たくはないが、1度見れば忘れられない映画に仕上がっています。
さよなら宮崎駿! もう出てこなくて良いよ♪
言い遺したいことがいっぱいアッテナ
宮崎駿の集大成なのでしょう。
過去作品へのセルフオマージュ(と言ったら大げさかもですが)が随所にあって、走馬灯のよう。
大まかに少年の成長物語らしい、というのは分かりました。
時代設定にしても人物設定にしても、必然性があってそうしたんだろうが、何のためなのか、何がしたくて何が言いたいのか掴めない。
アオサギを筆頭として、多すぎる老婆とか、キャラ変するキリコ、妊娠中の継母ナツコ、消えたおじ、とか何かのメタファーらしき存在がたくさんあるけど、何の比喩なのか良くわかりません。したがって彼らのパートのエピソードも同様によく分からない。
で、同一ストーリー上の話として全体の整合性を考えて読み解こうとするのでわけわからなくなるのかも、と思った。
宮崎駿は第一線の職業人としても人としても経験が長いので、思うことや言いたいこと(言い遺したいこと)がたくさんあって、それを集大成として全部、宮崎駿の個人的な表現でぶち込んだために、それぞれのキャラクターやエピソードが分かりにくく、とっちらかったのかも。
つぎはぎで一貫性がないので、ひとつのストーリーの上で動く一本の映画、というよりは「誰それのパート」としてオムニバスみたいに見たら良いか。
考えてみたら人の日常は必ずしも連続線上にあるわけではなく、ひとつひとつ脈絡があるようなないような出来事が集まり積み重なってできているので、案外これがリアルに近いのかも知れない。
それと、制作に時間を掛けすぎたのでは、とも思う。
7年の間に、日本のアニメ界では名作がたくさん生まれている。それらを見てきた観客の目も進化しているはず。なまじ長く時間を掛けたために、他作品を意識してあれこれ取り込んで修正して、それで冗長になったり散漫になったりしていないだろうか。
アニメーションはさすがで、「未来少年コナン」からの宮崎アニメ健在と思いました。
永遠に人に問いかけるテーマ
夢の中にいるような、非現実が現実として理解しているような空間の展開です。
おそらく、この映画が何度も見られる頃には、多くの込められた映像やストーリの仕掛けを見抜く人が多く出てくるだろう。ひょっとしてそれが声優のバックボーンや音楽とも紐づけされているかもしれない。
今は巻き戻しができないから、宮崎駿監督のメッセージは伝わっていないのだろう。
もちろん娯楽作品に難解な解読は、人によっては不要な議論だけど、未来の人類にも問いかけたい作品を目指しているような気がする。
この作品が化石になってしまうほど陳腐なものかもしれないが、それは未来の人々の判断に任される。
ひとりひとりに与えられた人生は、それぞれ時間や空間でまったく違うけど、これから生き抜く僕たちを含めて未来の人々に西暦2023年頃にパンドラの箱が開いてしまったことが言いたかったのかもしれない。
かわいかった
おーって感動しながら観て最後は心がスッキリ
「難しかったね〜」と両脇の座席のカップルさんの正直な感想。そうだよねー展開が早くてなんで!なんで!と思っているうちに終了。
60代のおばちゃんとしては、ジブリアニメを何回も何回もリアル映画館で観てきた人としては、ありがとうー!宮崎監督😍この作品を作ってくれてと感動して涙が出そうになった。作っている時の監督はすごーく楽しかったと思う。過去に作ったあのシーンこのシーンを再度研磨して観せてくれる。ジブリアニメの各シーンが目に浮かぶ。そして終了となってあーしあわせだったと思う。そしてやっぱり頑張ろうと単純に感動する🥹
先程の若いカップルさんたちが『わからないからもう一回観よう〜』と話し合っていたー宮崎駿監督、大成功ですよ🥹わからなくてもいいのですよね🙂
全1336件中、501~520件目を表示