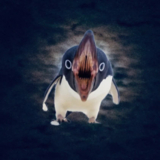君たちはどう生きるかのレビュー・感想・評価
全2100件中、1421~1440件目を表示
宮崎駿監督の新しい作品が映画館で観られることは本当に嬉しい
多くの方が書いているように、娯楽作品としての完成度は高いと感じられず、最後まで期待を大きく超えるような瞬間がなかった。絵もアニメーションも美しいものの、かつてのジブリアニメ、宮崎アニメのスペシャルな何かが欠落しているように思えて。何か寂しい物足りない気持ちが残ってしまった。
私の知性と感受性の無さも多分にあるんだろうけど、そうであれば求められるものが高すぎるし、2回3回と観て少しずつ解釈を上書きしていくマニア的楽しみ前提のようなものも正直辛い。そのような楽しみ方もあって当然だけど、映画は初見1回でも十分楽しめるものであってほしい。なのでこの点数が限界。
全然正しくない気もするけど、私の1回見た限りでの考察は、
内向的で鬱屈した頭の良い少年が、母からの「君たちはどう生きるか」を読んで、世界や周囲の人間に対する新しい自己のありかたや価値観を獲得し、神曲をモチーフにした創作世界(塔)に挑む。
塔の原理を司る石は西洋からやってきた価値観や文化、資本主義や商業主義、消費主義的な、なんというかアメリカンゴッズ的な神だろうか。高畑監督ではなくこっちかなあと私は思った。このままでは崩壊を免れない創作世界(塔)の中で、これまで石の元で仕事をしてきた宮崎監督と宮崎少年が対話し決別した結果、現実と向き合い新しい創造の道を歩む。そんな意志表明のような作品。
もう一つの軸は、やはり母、母性、女性に対する価値観。ここも正直もっと強烈な独特の見せ方をしてくれるはずみたいな。
これらは全く間違っていたり、もっと難しい色々複層的なテーマもあるのだろうけど、すぐに2回目3回目を観に行こうとは今は思えていない。
ファンとして宮崎駿監督の新しい作品が映画館で観られることは本当に嬉しいし、引退を撤回し82歳になった監督がここまで芸術的でパーソナルな作品を出してくることにも戸惑いもありつつ、感動している部分ももちろんあり。
でもくどいけど、娯楽作品としても見られる完成度がもう少し欲しかった。
蛇足だけど、最後のシーンで宮崎少年が積木を一つ持ち帰ってたけど、これって積木は風の谷のナウシカでシン・ナウシカやるよー!的な伏線かなって思いました。
まさかのベックリン❗️
始まってすぐは、動画の動きに違和感を感じてしまいました。
過剰な人物や物の線の動きが、気になってしまった。
もう少しケレン味?省略の快感の様なものが、以前のジブリには、あった筈だと。
動きの過剰さに比べて、背景の密度の無さも気になってしまいました。
もっと緻密さや、世界観を脳内に想起する様な背景だった気がして、薄っぺらい感じがしてしまいました。
大邸宅も、離れの洋館や森、キーポイントの塔も、位置関係がぼんやりしていて、距離感が掴めなかったです。
良作の映画は、何と無くそういう舞台構造が、イメージしやすいモノだと思ってます。
自動車と人物の等身等も、以前の心地よいディフォルメから、微妙にズレてきている気がしてしまい、気になってノイズになってました。
そういう粗を感じてしまって、序盤に宮﨑駿氏の老いからかと思い、少し悲しく見てました。
話に非日常が増え始め、
彼岸?下の国?に入り込んですぐ、まさかの死の島!ベックリンの死の島のオマージュ?で、
びっくり‼️まさかジブリ映画に?
リドリースコットが、エイリアン・コヴェナントで引用した時は、苦笑いしましたが、まさか宮﨑駿が!っとビックリしてしまいました。
そこから先は、なんだか素直に見てしまいました。何も考えず唯々イメージを飲み込む感じで。
私は、千と千尋より本作が好きです。
宮﨑氏の説教臭さを感じる事なく、本作は見れました。
トトロの時の、私の心の琴線に触れるまででは無いですが、とてもシンプルな咀嚼することないイメージの羅列に、ある種の清さを感じました。
巨匠の終末作、黒澤明の「夢」の様な感じもありますが、それよりももっと腹を割った感じがしました。
宮﨑駿自主映画として、好きです。
なんかまとまらない文章、失礼しました。
勢いで、書いてしまいました。
後、宣伝しないとかの仕掛けは、プロデューサーの思いつきなので、どうでも良いですわ。
これで引退せずに、最後に超絶娯楽大作作ってくれたら、カッコイイかな。
パンダコパンダみたいな。
宮崎ワールドの集大成
新作を受け取った喜び
印象 3つまで の中では怖い しか選べなかった。
村上春樹さんの新作も時期が近く、並べて何か書く人が多い。
私も並べたくなった。それは、ご両人とも、もしかして最後の長編かもと考え、自然と集大成のような内容になったかなということ。既視感とても多め。でも批判じゃありません。どの歴代の作品も好きだから確認作業は幸せです。
ただ、最後のつもりかもしれない創造主に反し、次も待ってますから!と思うのは欲しがりな受け止め手の性。
作中のゆるキャラ?ワレワレのように我々も作品を滋養としてふゎーとまた飛びたいです。
無秩序に、宮﨑駿の夢と愛が詰め込まれる
宮﨑駿作品はメディア用の表のテーマと自身が描きたい裏テーマがあるように思うけど、本作は「表のテーマ」が見つけられないほど作品が個人的。ジブリの集大成、スタジオの終幕を示唆するとともに、描かれていたのは現役を支えた仲間家族への感謝と愛と感じました。
半生をなぞったアート色が強い作品でありながら、エンタメとして成り立ってしまうこと自体が宮﨑駿がたどり着いた境地と思う。馴染みのアニメーション、聴き慣れた心地よい音楽、これらを“馴染みの”と思える豊かさにも気付かされながら、冒頭から書き込みの細かさやエネルギーに圧倒されて、この時代にまたスクリーンで宮﨑駿作品を見れること自体が胸にくる。これで育ってるからね!!!
起承転結も秩序もないのに感覚的に理解できてしまう。好きポイントでした。俺の人生を一言で括られてたまるか。そんな声が聞こえる気がするのは、事前開示やプロモーションを削ぎ落とす外側の姿勢や、作中のインコの大群が世の中への皮肉と感じられたから。
きっと天国地獄と比喩されていた下の世界は監督の創作人生そのもので、大叔父は自分自身。自分をはじめ、つくり手たちを呪縛から解き放ち、僕はこの生き方を選んだよ。これからの時代を担う君たちはどう生きる?と、問いかけられるというより、自分の半生をもって未来への裾野を広げてくれた感覚に近かった。
前向きな気持ちになったことは間違いなく、描くぞ、と奮い立っている。ああできればさよならなんて聞きたくなかった。
この夏はもう来ない
物語のある時から、テンポが速くなる。ハヤオが思い出したかのように、得意で大好きなことを描き始める。アクション、異世界、そして少女。夏休みが終わることを悟ったかのように。急ぎ足で。
この映画の制作中に、恩師でありライバルの高畑さんが逝去し、自身にも死が迫っていることを初めて意識したのかもしれない。
過去作のオマージュは、オマージュではなく、締め切りや予算に追われて当時描ききれなかった後悔を総括するための、描き直しなのかもしれない。それは夏休みの宿題だったのかもしれない。
花火大会のフィナーレのように、惜しげもなく繰り出されるあの玉この玉が、公開初日の満員のスクリーンで大爆発していた。
“Animation”
絵に息を吹きこむ喜びを。アニメーションの、原体験を呼び起こさせる、純粋な動機を、好奇心を感じろ。読むのではなく、考えるのではなく、見るのだ。
そこで観客も気づく。
あれ、これはもう見れないの?
夏ってこんなに短いの?
もうこの夏は来ないの?
宮崎駿、好きに生きてくれてありがとう。
【ジブリの奥深さが詰め込まれた素敵な作品】
事前の情報が何もなくワクワクした気持ちで劇場で観させて頂きました。
先に、観終わった時の気持ちとして、胸を熱くさせてくれる作品だと感じました。
これまで観てきた様々なジブリ作品を随所で感じることができる素敵な作品でした。
映画を観終わり劇場を出るために歩いている際、周囲にいた方の話し声が聞こえてきたのですが、あまり内容が分からなかったという方も多いのかなと感じました。
私個人としては、内容もスッと入ってきて、もちろん全てではないですが、宮崎駿さんが伝えたい何かを感じることができ,最後は何故かわかりませんが涙が少し出るような胸の熱くなる作品でした。
人それぞれ捉え方は異なると思いますが、これまでのジブリ作品の中でも私は非常に良かったと感じたので、気になる方は一度劇場で観ても良いのかなと感じました。
梨木香歩の裏庭オマージュ??
小説、『梨木香歩の裏庭』のオマージュ?
(原作宮崎駿と表記されているので、本当に小説に影響されているかは定かでは無いですが私の思い違いかもしれませんが…凄く内容が似ています! )
キャラのデザイン、性別、時代を変え内容は殆ど同じと言っていいんじゃないでしょうか。
一度読まれて影響されたのでしょうか。序盤で気付きました。 その後からは同じだな、、と。
ただ、小説では主人公の感情はとても分かりやすく激動で感情移入して楽しめるのですが、映画では主人公の感情が分かりにくく感動が薄く感じられました。
小説自体はとても内容が濃く難しいので、この2時間に要約しジブリ独特の表現を付けるには時間が足りない、説明不足だと…
小説を知らない方は内容が分かりづらいと思います。
登場人物を深く掘り下げた感動物と選別するよりは、スタジオジブリのもつ背景画や独特の世界観、表現をギュッと濃厚にされた作品だと思います。 評価が二分に分かれるのは、その二つどちらかを求めて観られる方が多いからだと思います。
私は好きでした!内容はともかく…あ〜ジブリだあ!今ジブリ観てるなあと!笑
このレビュー書きたくて会員登録しました。
映画館で宮崎駿監督作品を観ることができた。
よく分からない、監督の老いを感じる、万人受けしない...色んな意見をお見かけしますが、満員近い映画館のスクリーンでこの作品を観ることができて私はとても満足です。祝日最後に滑り込んで正解だったなと思います。
宮﨑駿監督作品を最後に映画館で観たのは20年以上前で、5歳の時に観た『千と千尋の神隠し』以来でした(当時は立ち見販売もされていたけどそれすら埋まるほど人気だったのを覚えています...次の回待つ間にセレビィ観た記憶ある)。
コロナになる以前から足を運ぶことが全くなくなった映画館。観に行こうと思ったのはTwitterで見かけた映画のポスター・事前情報が全くない・宮﨑駿監督作品という3点に魅力を感じたからです。正直、チケット買う時には「今ってこんな高いんかい」とか思っていましたが、見終えたあとは「もう一回映画館へ観に来たい」という気持ちでいっぱいでした。
この映画が伝えたいことは何なのか、自分なりに解釈できたので満足です。でも、あまり深く考えなくてもこの作品の見所・魅力・好きなところはたくさん見つけられるかと思います。良いアニメーションです。
評価が分かれているのをみると、人により求める部分が違うんだな...という感想を持ちます。そりゃそう、確かになと思います。
私個人としては何より、青サギポスターとタイトル以外何も知らない状態でこの映画を映画館のスクリーンで観られた...という一連のことが、映画という思い出において一生のものになるだろうと感じています。
お盆に帰省した際には、20年前に『千と千尋』を観た地元の映画館へ、母と姉と共に観に行こうかと思います(上映されていると信じて)。映画館で観られる内に、堪能したいです。
まさかの〇〇系
よくわからなかったなどの感想が多かった印象ですが、たまたま吉野源三郎著の『君たちはどう生きるか』を、読んだことがあったのでこの映画作品との妙なつながりにハッとさせられました。
小さな子供と見に行くのは少し難ありです。序盤はほぼほぼ怖い表現しかないです。
※ここからネタバレです
まさかのタイムリープ・異次元系でとても楽しかったです。
私は、眞人のお母さんであるヒミの言った(後に焼け死ぬ運命になっても)「素晴らしいじゃないか。眞人を産めるなんて。」が聞けて本当に感動でした。
ヒミが眞人に『君たちはどう生きるか』を渡してなければ、眞人はこんな逞しい決断はしなかっただろうと思わせられました。当たり前ですが無駄なシーンは一切なく、初めから終わりまで物語に引き込まれました。
私も誰かから何かをしてもらったり、何かをしたりお互いが少し関わるだけで後の結果は、良くも悪くも大きく変わっているかもしれないと感じました。もちろんこの映画を見たことで、明日の私は、小さなことでも今までの自分とは違う選択をするかもしれないと思いました。
珍しく説教系じゃなくてジブリでは一番楽しめました。
宮崎駿監督が作りたかった映画をみられる幸せ!!!
キャラクターがとんでもなくかわいいので、あれを公開前に出さない戦略、いいと思います。あれだけを見にもう一度行きたいです(行きました)
それから画面の表現力が尋常じゃないです。
きれいなだけでなく、伝わってくる情報、感情が多すぎて、
気持ちが動きすぎて、どうしたらいいかわからなくなります。
それがなんなのか考えることも楽しいです。
ストーリーも私は大好きでした。
別の世界、新たな視点から世界を見て、今はまりこんでいた世界を抜け出すというような。
でも難しくなくて、ものすごく楽しいし、上滑りの部分は全くないです。
最後にはぼろぼろ泣いていました。
天才の宮崎駿監督とそれをリスペクトして支えるスタッフの方々。
こんな映画を作って下さって感謝したいです。
私は過去作と比べてもかなりこの映画が好きです。
以下ネタバレです。
完全に地獄めぐりとか、ダンテ神曲のイメージで見ました。下は死者の国です。大叔父はそれを司る石と契約して、その国をより良いものに作り変える権利を得、その国の王になった。親族も王族の扱いです。けれど、連れてきた鳥は増えすぎ、飢え、全く上手くいっているようにみえない。悪意の石。世界が崩壊することを恐れているのは大叔父だけで、石はそれも想定内、どうせ人間なんてできるはずないと思っているようにみえました。壊れたら、元の地獄に戻るのかな?
夏子は眞人を守るため、後継者を産むために、自ら死者の国に行きます。眞人が迎えに来たとき、強く帰りなさいと言っていました。夏子は若いキリコや久子にも驚いていなかったので、多少事情を知っていたんじゃないでしょうか。久子と夏子には何の遺恨もないようにみえたし、久子が死んでしまい、眞人を現世に残すために後継者を産むと考えると、姉が死んですぐに義兄との子供を妊娠した理由も納得できます。ラストシーン、産まれた子供はやはり男の子でした(久子や夏子が後継者候補になっていないことを考えると、男でないといけない?)現世では勢いのある単純な(無神経な)雰囲気の眞人の父は初めから終わりまで部外者なのが、皮肉です。
もうひとつ、眞人は前半夏子を嫌い、むくれていたのに、母からの本を見つけたとたんに、ガラッと雰囲気が変わります。あれは秘密書的なものじゃなかったのかなと想像しました。夏子さんは好きで森に入ったんじゃないと思う、とまで言っていたし。
ラストシーンで眞人が石を触るシーンも良かったです。お母さんの娘時代に会えて、あなたを産めるなんて最高って言われて、火に苦しんで亡くなったんじゃないってわかって、良かったね。
全部完全に妄想です。
何の情報もなく映画を観るって、本当に新鮮な体験でした!
輪廻の宮﨑監督流解釈が楽しい
普通におもろい
ジブリっちゃージブリ
冒頭の階段ダッシュ、やたらプルプル動くパンとジャム笑
あれこそがジブリ
ただ、ストーリーはありきたりで他人にオススメするほどではなかったかな。
あっちの世界に引き込まれて、海が広がってて、見えない何かぎ通り過ぎて、人型の黒い何かがいて。
デスストランディングかと思ったよ笑
宮崎駿による宮崎駿の世界の解釈を長編アニメにすること
2023年。宮崎駿監督。宮崎監督が引退を撤回して臨んだ久々の長編アニメ。「引退」とかあたかも自分の人生をコントロールできるかのようなことはやめたほうがいいってことですね。または、「引退」と言ってみたからやりたくなったかもしれないので、それも含めて、なるようになるしかない。
さて、作品はというと、これまた「宮崎駿の引退劇」を読み込みたくなる内容。物語は、第二次世界大戦中、火事で母を失った少年が主人公。軍事工場を経営しているらしい父はその後、母の妹と再婚してその実家の古い屋敷へと疎開することに。そこには不思議な塔があって、母(と新しい母となるその妹)の伯父がそこで行方不明になったとされている。少年は不思議なアオサギに導かれてその塔へと入っていく、、、というもの。この塔のなかではくだんの伯父によって不思議な「世界」の構築が行われており、少年はその世界を受け継ぐことが期待されている。これはもうどう見ても宮崎駿(伯父として表象)が築いたアニメの世界(狭く言えばスタジオジブリ)の後継という話だろう。宮崎駿がいわゆるアニメオタクを遠ざけていたのは有名な話だから、自信がつくった「世界」をそのまま受け継いでほしくはないのだ。少年が「後継」を拒否するあたりにそのあたりの「欲望」が現れていると見るのは自然だろう。
もうひとつ、重要なのはタイトルの「君たちはどう生きるか」。原作は大正から昭和にかけてヒットした小説。思春期の少年が学んでいく実践倫理学的な物語だ。この本を主人公が読むのは、父の再婚相手が母そっくりの叔母であることにもやもやを募らせ、しかも不思議なことが起こり続ける古い屋敷にフラストレーションがたまっている時だ。要するに、自身の内部の感情や道徳観では処理しきれない現実社会を生きるための、倫理的な道しるべとして外部から(死んだ母の残した本に偶然気づく形で)もたらされている。それまで新しい母となる叔母につれない素振りだった主人公の態度が変わるのはこの本を読んだ後だから、物語上の意味は明らかだ。主観的に素朴な感情をいかに克服して「人間」として生きるか。本作の場合、それが母の死を乗り越え、新しい母を救出し、異世界においても生き延びるすべを与えてくれる道しるべとなる。
つまり、片方に宮崎駿が構築してきたアニメの世界があり、片方に内的で主観的な感情の世界がある。「君たちはどう生きるか」という本はその両方を行き来しながら大人になっていく主人公にきっかけを与える重要な本なのだ。しかも、それをさらっと、ほんの一瞬だけ示すというところに、アニメーターとしての宮崎駿の矜持が見えるようだ。アニメはおもしろくなければいけないので、長々とタイトルの意味を解説すべきではないのだ。
ちなみに、細かい演出や映像の断片はどこかでみたことがあるといいたくなるものばかり。意図的な演出なのだろう。「宮崎駿の世界」を描いているのだから。
次世代へのメッセージ
大叔父様から眞人へのメッセージが、そのまま宮崎監督から視聴者へのメッセージとして読み取れた。"これまでの世界は崩れつつあるため、より善い世界を君の手で創ってほしい"という思いは第二次世界大戦下の当時に当てはめることもできるし、2023年現在に当てはめることもできる。そんなメッセージに対し、眞人は美しい世界で生きることより、悪意もあるし殺生も時にはしなければならない世界で生きていくことを決意したように感じた。過去作品よりも、よりリアルで生々しい実際の世界を映し出した綺麗事のない真っ直ぐな作品だと思う。
見る人の視点で大きく変わる芸術作品
「君たちはどう生きるか」
それは宮崎駿が作品を通じて伝えたいメッセージだったと私は思います。
宮崎駿という方は、「仕事人間」だったと私は思います。
その監督が最後に私情も含めた、心や頭の中の思いを作品に投影させた作品ではないかと思いますいます。
「私の仕事はやり切った。さぁ、これから君たちはどう生きる?」
そんな思いを感じました。
他の方の考察で、作品に出てくる物や人物がスタジオジブリのメンバーに置き換えられる
考察はとても共感出来ました。
最後の映画かは、分かりませんが、造りたい人と作りたい物を商業的作品ではなく伝えたい事を全てつぎ込み、そして今回のキャスティングに関してはこれからの世代の人達にも作品に携わってもらい技術の継承みたいな意味もあったのではないでしょうか。
これから見る人に、少し不思議な魔法の言葉をかけるとすれば
「この作品に内容はありません」
この作品の楽しみ方や、内容は、見る人が考える事で想像を膨らませる仕掛けであると私は思います。
のちに答え合わせをしてくれる日が訪れるまで楽しみましょう。
P.S.
推理小説で犯人を知りながら読む作品と、犯人を知らずに読む作品はどちらがおもしろいでしょうか。
普通だった
好きな人以外には薦められない。気になるなら観ておいたほうが。
個人的には、途中で映画館を出たくなった。
君たちはどう生きるか、私はこう生きた。
自伝「ふしぎの国の駿」
青鷺は鈴木さんだよね。
明確には言えないが色んな作品、人が出てる、ような気がする。
全2100件中、1421~1440件目を表示