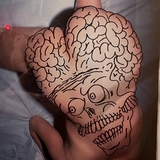君たちはどう生きるかのレビュー・感想・評価
全2098件中、721~740件目を表示
宮﨑駿監督の描く児童文学作品
3回鑑賞しました。
初回に鑑賞した時は、何となく面白いんだけど消化不良気味な感じは否めませんでした。ストーリーがわかりにくいのか、演出のテンポが悪いのか、今回の久石譲氏の音楽が全編通じて静かなトーンだからなのか…色々考えました。
しかし何度も鑑賞していくにつれ、次第に自分の中でこの映画の輪郭をはっきり捉えることができるようになった気がしました。
この物語の主人公を取り巻く現実はとても辛いことばかりです。戦争、親との死別、新しい親との関係、不慣れな田舎での暮らし、イジメ…。
そんな主人公は自暴自棄になりつつも、不思議な鳥(アオサギ)や実母の残してくれた本とのを出会いを経て少しずつ生きる力を取り戻していきます。そこから物語が動き出します。
誘われるように入り込んだ不思議な世界で主人公は様々な出会いを体験をし、少しずつ成長していきます…。
難解…と言われているようですが、難解なのはあの不思議な世界の構造だけで、物語そのものはシンプルで少年の瑞々しい成長譚である…というのが3回目を見たあとの自分の感想です。エンターテイメントというよりは、児童文学という言葉が相応しい映画だと思います。
このようにこの映画の輪郭を捉えてからは、初回にはピンと来なかった演出も、静かな音楽も全てが腑に落ちるようになり、3回目の鑑賞後は含蓄のある素敵な児童文学作品を読み終えたような感じを覚えました。
最後に、個人的にこの映画の好きなシーンは、終盤、ある目的の為に主人公がありえない身体能力を次々と発揮していくところです。非常に爽快なその演出に「未来少年コナン」を彷彿とさせる宮﨑駿監督のアニメーションの真骨頂を見た気がしました。
タイトル詐欺と言いたくなる内容
まずはじめに言っておきますが、私はジブリ映画のアンチではないです。
紅の豚とか大好きです。
ただこの映画はつまらないです。
意味がわかりません。
以下、映画の内容等について思ったことです。
・なぜこのタイトルにしたのか?
事前の情報がなく、予告編もない今回の映画。「君たちはどう生きるか」というタイトルおよびポスターから同名の書籍をジブリ風にアレンジしたものかと思っておりました。いや〜全く関係ないやん。少なくとも自分はそう思いました。そもそも、あの内容なら、このタイトルにした意味が本当にわかりません。
・なぜ予告編などを出さない。
自分は映画を観るかどうか決める時は、予告編を観たり、あらすじを確認したりしてから決めます。なので、今回は非常に困りました。観るかどうか、かなり悩みました。
・意味がわからない。
全体を通して意味がわからなかったです。というか内容がない。その時々で思いついたシーンを繋げましたって感じでした。謎も疑問もほったらかしだし。ラストについては、「はっ?だから?」って感じでした。
以上
この映画の内容について色々な考察がありましたが、そもそも全体の内容を考察しないといけない映画はあまり良くない(悪く言えば駄作)というのが個人的な考えです(考察には明確な答えがないので)
確かに考察が必要だったとしても、良い映画はありますが、そういう作品は結末についてはわかりやすくしっかりとしています(この作品はそれができてないので)
あと、考察の中に監督の人生を描いてるみたいなことがありました。私もその考察については、反論はしませんが、それならこの映画は初めから観に行かなかったと思います。
あっ、だから予告や事前情報を出さなかったのか〜
2023/08/08追記
自分は未熟者なので今回のこの作品は正直、面白さを見出せなかったです。
もしよろしければ、「こういう所が面白よ」と、コメントにて、ご教授していただけると幸いです。
また、ストーリーはどういう所が面白かったということも、ご教授していただけると幸いです。
2回目以降観る時の参考にさせてもらいます。
2023/08/13追記
コメントにも書きましたが、金が絡むなら匂わし、皮肉はダメだと思います。
食事でメニュー(ポスター)から塩ラーメン(映画タイトル)を注文(映画鑑賞)して不味い醤油ラーメン(面白く無い内容)が出てきたら許せないですよね。文句を店(監督他)に言ったらメニュー(ポスター)に鷺が書いてるから察してくださいと言われたら、腹立ちますよね。まぁ、美味しい(面白い内容)なら許せますが(満足しますが)
人生をアニメーションという比喩を通して考えさせられる
ジブリの新作「君たちはどう生きるか」
生と死の厳しさ、戦争、人生の生き方と困難。
この幅広いテーマを一本の映画で、しかも全て比喩で表現されている。
一つ一つの所作や言動に意味があり、どこに感銘を受けるか受け手の見方によって大きく変わる。
そのため全ての人がこの映画から大切なものに気付かされる素晴らしい大作だと思う。
しかし万人にオススメするわけではない。この映画は最初から最後までほぼ比喩で表現されている。だから頭を空っぽにして受け身でも楽しめるジェットコースターのような映画だと思うと意味がわからず退屈な時間になると思う。
目線、セリフ、ワラワラ、アオサギ、積み木、波、、それらが何を表しているのかどんな心情の変化があるかを考えながら見る必要がある。
名作と呼ばれる映画は必ず賛否両論分かれる。ただこのレビューを最後まで読んでるあなたは確実に充実した時間を過ごせるだろう。
僕たちはどう観たらいいのか
ジブリでいちばん好きなのはとなりのトトロ。ネコバスの行き先が「メイ」になるところで落涙必至。それ以外の作品には特に思い入れがない。なので正直、本作が意味するところを考えるのはめんどくさいだけでしかない。
宮崎駿のキャリアなのかジブリ作品群の投影なのかわからんけど、好意的に解釈しなければ、82歳の監督は認知症じゃないかと思ったほど(超失礼)。監督の作品づくりはシナリオが彼の頭の中にしかないというやり方だし、出来上がりを観た鈴木敏夫も宣伝に困って、事前情報を出さない手法を採ったのではないだろうか(暴論)。
仕事疲れもあって中盤はスクリーンを薄目で観つつも度々意識が違う場所へ飛ぶ始末(レビューを見たら寝た人多かったようで…)。それでも客は大入りだしオレ自身観てしまったわけで、あらためてハヤオ&ジブリのブランド力すごい。それははっきりわかった一作。
サギが出てきます もうおわかりですね
宮崎駿監督の作品には駄作はないと常々思っております 今回も少なくとも期待は裏切られないだろうと思って映画館に足を運びました 「君たちはどう生きるか」からは着想をえたらしいです でもサギのキャラクターが出てきて、異世界に主人公が入るあたりから、原作は全くかんけいないことがわかりました それからはひたすら退屈な時間を過ごすことになります
サギってそういう意味なんですね 監督自ら「何か期待してるらしいけど違うよ」ってことですね アニメで哲学的な問答をどう描くのかに期待したのですが、過去に見覚えのある陳腐な”ファンタジー”場面のオンパレードでした 引退を撤回して10年も費やしてまで何を描きたかったのでしょうか
明らかにサギなんですが訴えても賠償はとれませんのであらかじめご了承の上鑑賞を
君たちは死や喪失をどう乗り越えるか
死や喪失に対し「はい!これが苦しいんです!」という明確な主張はありませんでしたが、序盤の主人公の説明できないような行動から、苦しみや喪失感が伝わってきました。
私たちも、身近な人を喪ったり、世の中の不条理や悪意に遭遇したりと、そういった苦しみが誰しもあると思います。
失意といっても色々です。ちょっと「いいな」と思った好意、幼かった頃の、感受性が強い時の、密かな思い。でも、それが思いもよらない形で無惨に裏切られた(と思ったり)、 小さなプライドを守るにはあまりに心にさざ波が立ちすぎる事件が起こるときもある。
と、若くてきれいな義母を主人公が横目でちらっと見た視線から感じました。詳しくは本編。
でもこの映画を極彩色の世界を主人公と一緒に駆け抜ければ、一生懸命になる自分に爽快感があったり、ひそかな思いを暗い恥の感覚としてではなく別の面から捉えることができ、新しい自分になっている事に気づくと思います。
それは何かというと、主人公が意図せずお婆さん・キリコさんたちやアオサギと関わったように、人は当初「この人と」とは思っていなかった人たちと一緒に世界を懸命に生きていく、と思います。大変な目に遭った時、今現在だけの姿や見た目にとらわれず、心の全ての感覚を使って人を判断することを学んでいくのだと。
見る時によってつど姿を変えるアオサギ、キリコさんなどが、そんなメッセージを送ってくれている気がしました。
以下、ネタバレあり
①アオサギ
・物語のトリックスター(予測できない動きで物語を進展させる人物)のような、鍵となる人物。最初はトラウマの引き金を連呼して刺激してくるなど、とんでもなく邪悪で、人の心の聖域にずかずかと入ってくる人物に見えます。しかし油断ならない相手ながらも、物語後半ではその飛行力が必要になってくる人物。
→現実世界でもそういう人たちと協働しないといけない時がありますよね。憎い、嫌い、じゃ割り切れない。相手の力が必要。
②キリコ
・使用人たちの一人のおばあちゃん。はっきりした態度で一際きわだっています。最初は矢と引き換えにタバコをねだるなど、「裏取引を持ちかける」ずるい人物だけのように見えましたが、精神世界のアナザーワールドでは、持ち前の気性のしっかりしたところを生かして主人公を救ってくれ、命を慈むような思いがけぬ優しさを見せる人物。
→ 物語中盤で、主人公がおばあちゃんたちの人形に囲まれながら呟くシーンがあります。
「おばあちゃんたち、ごめんね」と。
なんでごめんね、なのかなと最初は思ったのですが、おばあちゃんたちは最初は戦争中の薄暗い雰囲気の中で、卑しさ、得体のしれなさ、醜さ、平凡さとともに描かれていました。
だから主人公も「所詮自分とは関係ない知らない人たち」「賤しいつまらない人たち」と見下げ、距離を取りたいと思っていたと推測します。
そして、そんな自分の先入観や心の氷に気づき、謝罪したのでは?と思われます。
なんてったって、異世界のアナザーワールドで守ってもらった後に見たおばあちゃんたちの人形には、醜さはなく、慈しみや安心感に満ちていましたから。最初と全然印象が違います。
不条理な悪意にさらされることのある世の中で、おばあちゃんたちは本当に「護ってくれる」よき身内だと本能的に主人公は察知したのだと思うのです。
このあたりから主人公が望みのために闘っていく、という転換点が始まったと思います。
もっと踏み込むと、「君たちはどう生きるか」という生き方の智慧がさりげなく描かれているようになりません。ーー先入観を排し、かつ過去や背景を考慮し、相手のよさに目を向けながら、包括的に理解しようとしていくうちに人間の本質が見えてくる。そうすると、自分の中のここは安全という身内や仲間が決まるので、外の世界に向かっていける、体当たりできるようになるーー主人公も後半では、「警戒すべきもの」と「安心できるもの」とがちゃんと識別できるようになっていました。積み木のあたりで、大叔父の提案を断るのって、こういうところにつながってくると思うのです… 例えば、の解釈ですが。
以上が最終的に仲間になる①アオサギや②キリコから私が受け取ったメッセージです。
まとめると、
・死や喪失、失意を乗り越えて生きていかなくちゃいけない
・そのためには、身近な人たちとの新しい関係をしっかり認めて築いていきながら、今を一生懸命駆け抜ける営みの連続によって、仲間を得て、不条理な悪意を退け、自分の望みを明確にし、生活の中での立ち位置を確立していくしかない
そういうことを、象徴的に繰り広げられる色彩豊かなファンタジーの中に凝縮させたのではないかなと思いました。
極彩色の世界を、説明のつかない出来事のなかを一生懸命駆け抜ける主人公と伴走させてもらい、まとめて自分自身を振り返ったような気持ちでした。言葉にならないで感じてきた思いーーしいていえば、自分の学生時代の鬱積、絶望、そして憧れを、その後の社会人時代でどう闘い、どう昇華していったか、という自分自身の物語をも、映画の中にかいま見た気がしました。
この物語が何に?
王道のロールプレイングゲーム風
「もののけ姫」あたりから「風立ちぬ」まで、ずっと難しめの作品が続いていたジブリ映画。
ひょっとすると「ラピュタ」「魔女の宅急便」以来、わかりやすかったかもしれない。
主人公・眞人のセリフが親切でわかりやすく、会話を丁寧に追えば筋はわかる
久しぶりに少年が主人公なので、小学生くらいの男の子はもちろん、ファンタジー好きの女の子や、男の子のいる母親にもおすすめ。
謎解きロールプレイングゲームのようで、おもしろいシーンも結構ある
ただ、話が凝っており、ちゃんと理解するには宮崎監督の過去のインタビューなどがヒントになるかも
引退宣言以降、なにしろ10年くらい表に出ていないので、若い人が混乱するのは無理もない。
「不条理もいろいろあるけど、とにかくがんばって生きよう」が結局シンプルなメッセージ。
宮崎監督の言う、がんばって生きるとは「現実世界で尊い命や文化をつなぐこと」。
そのことがストーリー、キャラクター、オブジェで全開に表現されている。
ジブリオマージュは総集編という見方もあるが、むしろ過去との決別
間違いなく自伝だが、監督自身が誰に投影されているかは、解釈の分かれるところ。
眞人や大叔父、ラストで生まれてくる子どもの可能性もある
キャンディーズの「微笑み返し」ですな。
つくづく宮崎駿は、商売上手ですな。(悪い意味ではないが、あざとい)
・「魔女の宅急便」では、ユーミンの曲をつかってママ世代に訴える。
・「ハウル・・・」では、当時人気のキムタクを声優に起用。
・「風立ちぬ」では堀辰雄の小説や、松田聖子の曲と同じタイトルにする。さらにユーミン の曲も使う。
本作では「君たちは・・・」の小説や、5年前の漫画版のタイトルを、内容にほぼ関係なく無理やり入れ込む。
映画の内容(映像世界だけ)は、過去の作品のオマージュで綺麗です。
昭和のアイドル・キャンディーズは、過去のヒット曲をオマージュした「微笑み返し」を解散前に発売して大ヒットしました。
でも、この映画はだめでしょ。
・疎開した少年の葛藤や悩みのエピソードが弱すぎる。
・大叔父の世界や、積み木のモチーフが弱すぎる。
終戦前後の少年の葛藤を描いた映画では、高畑勲の「火垂るの墓」の方が100倍染みわたります。見るのがつらくて何度も見たくはないが、1度見れば忘れられない映画に仕上がっています。
さよなら宮崎駿! もう出てこなくて良いよ♪
言い遺したいことがいっぱいアッテナ
宮崎駿の集大成なのでしょう。
過去作品へのセルフオマージュ(と言ったら大げさかもですが)が随所にあって、走馬灯のよう。
大まかに少年の成長物語らしい、というのは分かりました。
時代設定にしても人物設定にしても、必然性があってそうしたんだろうが、何のためなのか、何がしたくて何が言いたいのか掴めない。
アオサギを筆頭として、多すぎる老婆とか、キャラ変するキリコ、妊娠中の継母ナツコ、消えたおじ、とか何かのメタファーらしき存在がたくさんあるけど、何の比喩なのか良くわかりません。したがって彼らのパートのエピソードも同様によく分からない。
で、同一ストーリー上の話として全体の整合性を考えて読み解こうとするのでわけわからなくなるのかも、と思った。
宮崎駿は第一線の職業人としても人としても経験が長いので、思うことや言いたいこと(言い遺したいこと)がたくさんあって、それを集大成として全部、宮崎駿の個人的な表現でぶち込んだために、それぞれのキャラクターやエピソードが分かりにくく、とっちらかったのかも。
つぎはぎで一貫性がないので、ひとつのストーリーの上で動く一本の映画、というよりは「誰それのパート」としてオムニバスみたいに見たら良いか。
考えてみたら人の日常は必ずしも連続線上にあるわけではなく、ひとつひとつ脈絡があるようなないような出来事が集まり積み重なってできているので、案外これがリアルに近いのかも知れない。
それと、制作に時間を掛けすぎたのでは、とも思う。
7年の間に、日本のアニメ界では名作がたくさん生まれている。それらを見てきた観客の目も進化しているはず。なまじ長く時間を掛けたために、他作品を意識してあれこれ取り込んで修正して、それで冗長になったり散漫になったりしていないだろうか。
アニメーションはさすがで、「未来少年コナン」からの宮崎アニメ健在と思いました。
永遠に人に問いかけるテーマ
夢の中にいるような、非現実が現実として理解しているような空間の展開です。
おそらく、この映画が何度も見られる頃には、多くの込められた映像やストーリの仕掛けを見抜く人が多く出てくるだろう。ひょっとしてそれが声優のバックボーンや音楽とも紐づけされているかもしれない。
今は巻き戻しができないから、宮崎駿監督のメッセージは伝わっていないのだろう。
もちろん娯楽作品に難解な解読は、人によっては不要な議論だけど、未来の人類にも問いかけたい作品を目指しているような気がする。
この作品が化石になってしまうほど陳腐なものかもしれないが、それは未来の人々の判断に任される。
ひとりひとりに与えられた人生は、それぞれ時間や空間でまったく違うけど、これから生き抜く僕たちを含めて未来の人々に西暦2023年頃にパンドラの箱が開いてしまったことが言いたかったのかもしれない。
ごちゃごちゃしている
キャラクターが持つ目的や成り立ちが最初の方と最後の方で変わっている気がする。
やりたいことを詰め込んだらこうなったという印象で、あまり整理されていないと感じました。
あと1-2回作り直したら面白くなりそうな気がする。
かわいかった
おーって感動しながら観て最後は心がスッキリ
「難しかったね〜」と両脇の座席のカップルさんの正直な感想。そうだよねー展開が早くてなんで!なんで!と思っているうちに終了。
60代のおばちゃんとしては、ジブリアニメを何回も何回もリアル映画館で観てきた人としては、ありがとうー!宮崎監督😍この作品を作ってくれてと感動して涙が出そうになった。作っている時の監督はすごーく楽しかったと思う。過去に作ったあのシーンこのシーンを再度研磨して観せてくれる。ジブリアニメの各シーンが目に浮かぶ。そして終了となってあーしあわせだったと思う。そしてやっぱり頑張ろうと単純に感動する🥹
先程の若いカップルさんたちが『わからないからもう一回観よう〜』と話し合っていたー宮崎駿監督、大成功ですよ🥹わからなくてもいいのですよね🙂
インナートリップのお話
アオサギは、眞人の嘘が、外の世界に具現化したもの。
本当は、死んだ母が恋しい。夏子は受け入れたくない。
自分の本心を見て見ぬふりをし、覆い隠し、表面上は気丈に振る舞う眞人。
そんな眞人をあざ笑うかのようにこっちを見てくるアオサギ。
眞人は、アオサギが目障りでたまらない。実は、アオサギを生み出したのは自分自身なのに・・・笑
自分の嘘を覆い隠すため、アオサギを殺そうと弓と矢を自作し、アオサギを追う。
アオサギを追いかけるうちに、眞人は異世界に入り込む。
異世界=眞人=宮﨑駿の無意識世界。自分の内へ深く入っていくインナートリップ。
無意識のイメージの世界を日本最高の絵師が、アニメーションに。
見ごたえ凄いです。見に行ってよかったと、思いましたし、是非是非見に行ってほしいです!おすすめです!
意味が分からなかった、つまらなかったと感じた方は、現実世界的な理屈や、辻褄に合わないことが
気になってしまったのではないかと思います。寝てみる夢って、いちいち説明もないし、辻褄も合わないけど
面白いし、よく考えると深~い意味がありますよね。そんな感じで観るともっと楽しめると思います。
最初のお墓のシーンで出てくる「我を学ぶものは死す」は謎ですね。
そもそも誰のお墓なのか、伏線回収もなく、このシーンは何の意味があるのか、謎です。
ただ、直観で思ったのは、もはや日本アニメのカリスマになった宮崎駿が、後進に、自分を目指すな、
自分を崇めるな、宮崎駿がゴールだと思ったら、お前は死ぬぞ!と言わずにおけなかったのではないかと
想像しました。なんか唐突ですが・・・
夏子を取り戻すため、産屋に入り、一緒に現実の世界に帰ろうと夏子に呼びかける眞人に対して、
夏子は今まで見せたことの無い怒りと悲しみの表情で「帰りたくない!、あなたなんか嫌い」と。
その瞬間、ハッと今までの自分か夏子に向けていた心に気が付き、ひた隠しに隠していた本心に気付き、
その感情を認め、癒し、手放し、初めて素直な心で「夏子母さん!」と眞人は言えるのでした。
その時、本当の意味で心が通じ合ったのではないでしょうか?
今このタイミングで、自分の内に内に入っていく映画がメジャー本流の映画でテーマに選ばれたことが
すごい画期的なことだと思いました。
外の現実世界は、訳の分からない感じで行き詰っている風ですが、もしかしたら、これからの人類は、
外の世界ばかりではなく、外側と同じくらい自分の内側を観察して、無意識と意識を一致させることが
調和のとれた、皆が幸せな世界を創るカギになるのではないかと思います。
鈴木さんのプロモーション一切なし、予備情報一切なしは、自分にとってはドンピシャでした。
こういったテーマのお話を見せられて、新鮮な驚きで楽しめました。
全てのイメージに何かしらの意味、メタファーがあり、噛めば噛むほど味が染み出るスルメ映画です。
どのシーンにどういう意味づけをするかで、宮崎駿が何を考えているかを探っているようで、
実は、自分自身を知る映画にもなっていると思います。
「ポニョ」「風立ちぬ」が自分的には、もう一つで、ちょっと迷走している印象があったのですが、
今回、芯を食ったクリティカルヒットで、すごく楽しめました!
おそらく、宮崎駿の一番言いたかったことは、自分の内面に向きあって、自分の中にある悪意にも目をそらさず、
君たちは生きれるのか?それは君たちの選択しだい。
理不尽な現実世界でも、生き抜く覚悟が君にあるのか?(眞人は理不尽な現実世界で生きる覚悟を私たちに見せてくれています)
そして、力強く、生きてほしい。そして、人生を意味のあるものにしてほしいという願いではないでしょうか?
全2098件中、721~740件目を表示