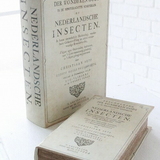君たちはどう生きるかのレビュー・感想・評価
全2100件中、401~420件目を表示
生まれるまでの話。
「見せたいものはもう全部見せたよ、もう終わったよ」というエンディング
良いジブリ作品の、原作があってそこから精製されたような濃さとは違う純米酒みたいなぐちゃぐちゃな濃さがある感じ。
興味深いけど残るものが余りない不思議な異世界感がありました。
好き勝手作ってる感じで精製されたストーリーの筋ってものがないです。ほんと晩節に好きに作った感じ
ストーリーはなんか1回見たらもう十分だって思ったんですが、ストーリーがが完結した後のあの全部終わった感じ、かかっていた魔法がもうどこかに消えて無くなってしまったみたいな、置いて行かれたような辛辣な後味は心にめりめりと刺さりました。
ジブリにこんなストーリーを引っ張らない「ハイおしまい、もう全部終わったよ」みたいな締め方があっていいのかと...
米津玄師のED曲は本当に喪失感を辛いほど感じさせてきます。のめり込める映画を観た後の脱力を曲にそのまましたようで、お店で掛かってると脱力感が蘇ってきます
きっとこの脱力感を胸に刺したくてもう一回観ると思います
過去から引き継いだこの世界の調和を作るのはあなた自身だ。あなたはどう生きるか。
メッセージとしてはおそらくシンプルで、この世界は太古から現在まで、卵子から大人まで、先祖から子孫まで、無数の生命の連鎖で紡がれており、色んな生物や人が絶妙なバランスをとって成り立っている、その調和を維持するのはあなた自身だ、というものかと思います。戦争の時代から始まるのも、その調和(平和)を乱していたことの象徴なのでしょう。
そしてそのシンプルなメッセージが、宮崎駿、ジブリ映画ならではの世界観で描かれてています。
本作をみていると、過去のジブリ作品の要素も随所随所に見られるのですが、それも敢えて「過去の作品があってこその今」という表現のためなのかなと思ったのはかんがえすぎでしょうか。
観なくていいと言うのは待って欲しい
「この世は生きるに値する」がメッセージなんだと思いました。
つまらなかったと言うのはいいと思うのですが、他の人に観なくていいと言うのは待って欲しい。
この映画で救われる人はいると思います。
私もその一人です。
貴方が生まれた意味はあるんだよ、と言われることが必要な人に一人でも多く届いて欲しいです。
命のバトンリレーと血縁者の大掛かりな仕事の後継者選定、時間を超越する為のリアルと並走しているファンタジー。ジブリの今ソノモノ。
誰だってこの映画を初見だけで理解するには難しいのかもしれない、しかし当初から情報を伏せられていて正解だったのかもしれない、広告や宣伝費を払っていたらジブリは間違いなく大赤字だっただろうから。
となりのトトロや火垂るの墓の同時上映を幼稚園児頃に見た世代として、今回の君たちはどう生きるか、は主人公だけでなく、主人公の母も後妻になる母の妹も、それぞれ葛藤があるのが話を難しくしているのだと思います。所々に飛行機製造工場の父のキャノピーを見て美しいと発言したり、前作の風たちぬの匂いも感じました。しかし、アオサギを通じてこの映画は東京空襲で焼け死んだ母親と異世界で年齢を超えて巡り会う物語でもあります。大叔父と言われる人物から異世界の管理者として後継を頼まれ、それを他のインコ王に阻害され、各々の現実世界へ帰る有様は、まるでタツノコプロダクションの終焉、名前通りに皆が育って巣立ちしていった様子をスタジオジブリに重ねて見えてしまいました。
宮崎駿の映画の世界観はコクリコ坂辺りから、WW2前後に軸足を置いているように感じます。もちろんSFでもファンタジーでも面白い映画なら好きに作って欲しいと思う一方で、今回の君たちはどう生きるか、これはジブリの崩壊を見ているような気分になりました。
弟子であった、他の監督達が作るアニメーションの方が面白いと感じるのは何故なのでしょうか。
言論の自由などない時代に書かれた書籍、時代に迎合しない
とにかく、景色が美しい。若干わかり難いストーリーだとは思うが、時系列も生死も越えた世界、
古事記のような多重構造の世界。日本人にとってはそんなに難しく無いと思う。君たち…を送られ、読み終え、母からのメッセージ"どういきるか?"に宮嵜駿の幼少期がかさなる真人が応える
読みごたえがある作品、こんな映画を待っていた。
宮崎駿の表現したいことをいろいろ詰め込んでいるため渋滞感はあるけど...
宮崎駿の表現したいことをいろいろ詰め込んでいるため渋滞感はあるけど、ファンタジーとしてはジブリらしく作られていた気がする。
冒頭の炎の描写は新鮮ささえ感じる。作画や背景はやっぱりさすがジブリといった感じ。これまでの作品のオマージュも観ていて楽しい。
内容に意味を求めてると難しいものがあるけど、展開としてはわかりやすさはあったし、ジブリ作品としては楽しめたので良かった。
観終わったあとに、君たちはどう生きるかについて考える。僕はこう生きた。きみたちはどう生きていく?意味を見出すのは人それぞれ違う。未来へ託し、希望を求めていたのではと。
集大成のように言われている今作品ですが、この内容を80歳で制作していることがすごいし、宮崎駿の中にはまだ表現したいことがたくさんあるはず。長編でなくても、何かしら作り続けていってほしいです。
不思議な世界
ネタバレはなにもしたくなく、公開されても映画を見るまでなにも情報が入ってこないようにしていました。
好き嫌いは分かれると聞いていたが、映画だしそんなの当たり前。
ジブリが大好きだから期待はすごくしていたけど、少しだけそれを抑えて映画館に行きました。
最初が少し長いな?と思ってしまいました。
もっとアオサギとの友情を描いてもいいのでは?と思ったり、眞人の性格なのか、ジブリで感じる丁寧さが少しなかった気がする。
もっと後半の部分の詳細が知りたかったし、これは?ん?と、思うこともあり。
ただアオサギはジブリらしいキャラクターで、とても好きになりました。
また生と死の世界のようでしたが、大叔父様?はなぜヒミを主?にしなかったのか?と少しフェミニストな考えもあったり。
少し反抗的な年頃の男の子には辛い家族が変わることや、学校で馴染めないこと、嘘を親につくこと。
そんなことをしていた彼が映画を通して夏子さんを助けに行くのは少し大人になった瞬間なのかな?
ただやはり謎は多い…
みなさんのレビューをみてみたいと思います。
初日に見て以来、評価を考えていたが…
僕は「風の谷のナウシカ」を劇場で見て以来、すべての宮崎駿作品を劇場で見て来た。
そしてこの作品を初日に見た時 評価に困った。
というのも、今までの宮崎作品は、表面的には分かりやすく楽しめる作品作りをしながらも、その奥にはそれに留まらない深い表現があったが、今作ではそちらを前面に押し出して来たからだ。
僕は20代後半の頃、毎週のように単館上映の映画に通っていた。
もちろん、ただカッコつけて毎週のように通っていた訳もなく、そういった映画が面白いと思っていたのだ。
しかし、その僕にしても今作は困惑する部分が多かった。
なので、評価を後回しにしていたのだが、先日「SAND LAND」を劇場で見て「あぁ、これが見たかったんだ…」と思った。
色々難しい事を考えたけど、単純に宮崎駿作品には、胸踊らされてワクワクして、めちゃくちゃ楽しんで、でも後から考えると「あの場面で言いたかったことは、こうだったのかも?」なんて思ったりするような作品が見たかったわけで、見終わったときに「う~ん、この作品はいったい何を表現したかったんだろう?」とか考えたい訳じゃなかったんだと気付いた。
なので、評価は星一つにしたいと思います。
よくわからんけど面白い?
見終わった後、なんだか不思議な気分になりました。
映画としては、今までのジブリがたくさん入ってるような感じで、ワクワクできる部分がたくさんありました。
でも見終わると「…アレ?」って感じで、「面白かったよ…ね?」みたいな、不思議な感覚でした。
多分いろんなメッセージが埋め込まれていたけど、よくわからず。
また見たいなと思いました。
いつも通りのジブリ作品と思って鑑賞
どの立ち位置で観るかで評価は分かれそう
主人公の母親が入院している病院が火事になり亡くなる。しかし、父親(実業家・恐らく娘婿)と疎開すると、疎開先には母親の妹が…。
しかも、妹(主人公の叔母)は既に妊娠しているという中々ハードなスタート。
確かに、細部にわたる拘りの描写は宮崎アニメだしジブリ作品だが、主人公はヒーローでもヒロインでも無く、1本筋が通った部分が無いので、ストリーが見えにくくわかりにくい感じ。
一切の事前情報が無い。と言うのはスラムダンクの手法だが、あちらはバスケのスポ根という揺るぎないモノがあるので成功しただろうが、宮崎監督の考えに追い付けないと楽しめないと思う。(私もその一人だった)
結局、最後に残ったのは木村佳乃の声だけだった…。
いつものジブリファンタジー
何かと話題になっていたので見てみました。
なるほど。確かに好き嫌いがわかれそうな作品かも。
主人公は戦火を避けて母方の田舎の大きなお屋敷へ疎開してきた少年。
そのお屋敷の池に棲みつくアオサギを見かけたことから物語が始まる。
現実の隣に潜む非現実的な世界が徐々に日常を侵食していき、いつの間にかファンタジー世界へと迷い込んでいく過程はジブリの得意分野。
テーマを感じさせつつもそれをファンタジーで包み込み作品にしてしまうのもお手の物。
そしてファンタジー世界の不可思議で幻想的な景色や住人の奇妙でありながら愛嬌のある描写もさすがです。
逆に評価されない部分は、私もそうですがある程度映画の中に理屈や論理を求めてしまう人には少し好まれないのかもしれません。
詳細は伏せますが一件落着というような終わり方ではなくて少しモヤモヤする感じがして結局アレは何だったんだろう、とスッキリしない気分で映画館を後にしました。
ファンタジー自体は好きで、その世界のルールにのっとって事態の解決が図られれば納得するんですが、それで終わりなんだ……という感覚。
映像は面白みがあっていいと思います。
人に勧めるかはその方の好み次第かなぁ、という作品かな。
ネタバレ避けて前評判確認の上鑑賞
かなり覚悟して鑑賞したということもあり
想像よりはるかに面白かったし、美しかった。
鑑賞後解釈が追いつかない部分が
大半を占めるにもかかわらず
現実に戻るラストシーンで涙してしまった。
母親の精神力に感動したのか、
はたまた脳みそフル回転状態からの解放感なのか(笑)
千と千尋の神隠しやハウルの動く城をはじめとする
ジブリの過去作の要素が強かったのが第一印象。
様々な考察やレビューを落とし込んで
この点数まで上り詰めました。
異世界もの? 引退記念公演?
私は、どう生きるか
必死でついて行こうとして完全に置いていかれた観客の一人です。
宮崎駿アニメに慣れていないからなのか?
いや、想像力が乏しいだけなのかもしれない。監督は何を言いたかったんだ?
分からない。
あちこちの解釈、レビューを読んでみた。皆さん、それはそれは様々に自由に、ときに真逆とも言える解釈をされている。
そこでふと思ったこと。監督は見る人に理解してもらおうとも、メッセージを受け取ってもらおうとも、これっぽっちも思っていないのではということ。
映画監督の想田和弘氏が言っている「『観客のことを考えるのはもういいでしょう』とばかりに、自分のためにやりたいようにやったのだと思う。」という言葉が腑に落ちた。
「巨匠」と崇められる宮崎駿が、最後に自分のやりたいようにやり切ったのであれば、嬉しい。それだけで良いのだ。変だけれどそんな風に思ってしまう。
置いていかれたけれど、今も思い巡らしている。私は、どう生きるか。
これまでのジブリの詰め合わせ
難しいような難しくないような
物語を理解できるか不安を感じながら観に行きましたが、そこまで難解というわけではなかったかなと…
親(先代)から受け継いだ道を選ぶのも1つ、自分で道を作るのも1つ…
色々詰め込まれていて、ハテナ感はありました。
マイナス点として100分くらいの尺に収められなかったかなと。
中盤に間延び感があり、やや退屈しました。
序盤では誰にも心を開けず母を失った寂しさを1人抱えるだけだった眞人が、最後には「現実世界で友人を作る道」を即選んだのには少し驚きました。
新しい母親を受け入れられないながらも、頑なに一緒に帰ろうとする姿から誠実さが溢れていて、彼なら良い世界を作るだろうなと感じました。
自分もとても善意だけでできた人間ではなく、悪意があって嘘もつきます。
それをちゃんと自覚し、認めながらもブレない芯を持って生きていきたいと思いました。
宮崎監督の自叙伝として拝見しました
ラピュタ、トトロ、もののけ、ポニョ。
次々と宮崎ワールドを構成する過去の作品が紹介される。そしてこの世界の創造主、宮崎さんは最上階でこの世界(ジブリ)を維持する後継者を探したが見つからない、という。
インコ王が、我こそはと申し出るが、才能がなく維持できない。
ジブリの後継者を名乗る連中は皆、思慮が足りないこんな凡人ばかり、と監督は呆れる。
監督なき後、もうジブリは維持できない。塔(ジブリ)の中で暮らしてきた多くの人達(観客含)に対して、ジブリ無き後、「君たちはどう生きるか」と問いかけると共に、「僕(宮崎監督)はこう生きた。では君たちは?」と、問うているような気がした。
関係者皆へ挨拶をする本作は、本当に最後かもしれない。
全2100件中、401~420件目を表示