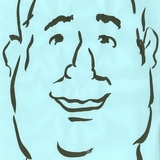怪物のレビュー・感想・評価
全320件中、1~20件目を表示
怪物という蜃気楼
ガールズバーの入ったビルの火災を起点に、教室での子供の喧嘩、子供による教師の暴力の証言、学校の謝罪、そして嵐の日に2人の子供がいなくなるまでを、3つの視点から描く作品。
最初の母親視点のパートでは、学校関係者の態度が絵に描いたようにひどく見える。あまりにテンプレ的な描写なので、これは何か物語としての意図があるんだろうということは察せられる。
一方、序盤こそ母親の早織に同調しつつ見ていて、教師たちに対し言葉が荒くなるところくらいまではこんな教師相手ならしょうがないと思っていたものの、取り上げたファイルを投げつけるあたりでちょっと気持ちが引いて、彼女が受難の親とモンスターペアレントの境界線にいるように見えた。教師たちの姿は、早織の主観が入った描写なのかもしれないと思えてくる。
湊との会話の場面で彼女が言った、「湊が普通に結婚して子供をつくるまでは……」という言葉の、聞く人によっては引っかかるであろうかすかな無神経さも、下味のように効いている。
ちなみに、早織のこの言葉が早々に心に引っかかったのは、本作がカンヌでクィア・パルム賞を受賞したことを映画.comの紹介文で読んでいたからだ(クィア=既存の性のカテゴリーに当てはまらない人々の総称)。このことに関しては最後に余談を追記する。
次の、教師の保利視点のパート(何の説明もそれらしい区切りもなく火事があった日に戻るので、ちょっとわかりづらかった)から、早織パートで点々と撒かれた謎が少しずつ明かされてゆく。早織を通した視界で一面に立ち込めていた靄が徐々に晴れていくような、ミステリにも似たエンタメ感があった。
実は保利先生は、最初の印象よりは熱心なよい先生で、そんな彼が周囲の嘘により追い詰められていった、ということなのだが、それがわかってもちょっと危なっかしくて怪しげな雰囲気が残るのは、永山瑛太の演技の絶妙さだ。
ただ、本質的にそこまで真面目なら、最初の母親との面談がいくら不本意だとしても、その場で飴をなめるか?そこはちょっとキャラのブレを感じた。それ以外の挙動も早織のパートとは若干印象のずれがあったが、それは早織から見た保利と保利自身の視点からの描写という違いのせいなのかもしれない。
女児が猫の死体について嘘をついたのはどういう動機だったんだろう?それだけがわからなかった。
最後は、湊のパートだ。ここで、細かい謎は概ね明らかになる。水筒の泥水や、片方だけのスニーカーから、それまで学校の場面で遠くに響いていた管楽器の音まで。
是枝監督はやはり子供の撮り方が上手い。今回は、従来のような現場で口伝えに台詞を伝える方法ではなく、事前に子役に台本を渡して覚えてもらったそうだが、子供たちの自然な姿を捉えていることに変わりはなかった。
廃電車の中で依里の転校の話をする場面などは、あの年代特有の色気まで感じた。
このパートでは、校長の善性も垣間見える。早織の目を通した校長の姿も、管楽器を介して湊を慰めた校長の姿も、同じ人間の一面だ。
最後に2人が楽しく駆けてゆくシーンは、どこかこの世ならぬ雰囲気もあった。彼らは嵐で命を落としたのかもしれない。
人間には多くの側面があり、そこには必ず善も悪もある。そしてその側面を見る者の置かれた状況によって、見え方も変わる。誰が怪物なのか、そもそも怪物は本当にいるのか、自分の主観だけでは真実が見えないことの方が、想像よりはるかに多いのだろう。
誰かの人間性を安易に決めつけること、自分から見える風景だけで善悪を断定することの危うさを思った。私たちが誰かを疑う時、卑近な例ではネットで炎上するような事案に遭遇した時、自分から見えているものが全てだと、つい信じたくなる。
その時立ち止まって、他の立場からの見え方を想像する。そうすることで初めて、この物語のように少しずつ、物事の本当に正確な姿が見えてくるのではないか。そんなことを考えた。
余談:
映画ライターの児玉美月氏のツイートによると、試写会の時の資料に「(クィアの要素がある作品であることは)ネタバレなので触れないでほしい」といったことが書いてあったそうだ。
一方、是枝監督は会見で、「性的少数者に特化した作品ではなく、少年の内的葛藤の話」と言っている。なので試写会資料の注意文はちょっと謎だが、クィア・パルム賞を受賞したことで、注意文を入れた製作サイドからしたら受賞の報道自体がネタバレのようになった形だ。
ただ個人的には、クィア要素があると事前に聞いていても物語の感動はきちんとあり、知ってがっかりするようなネタバレとは思わなかった。なお、児玉氏はクィア要素をネタバレ禁止のネタにすることを批判している。当事者性の高い観客への配慮に欠けるから、とのこと。
試写会資料の是非は置いておいて、やはりマイノリティ要素があると受け止められた作品は海外で賞を取りやすいという面があるのかな、とひねくれた私は思った。最近そういう作品が本当に多い(否定ではない)。
怪物探し・・・。そうなりましたね、監督の思惑通り(?)ハマりました。
辛気臭そうな映画だから、観るのを避けていたってのもありますが、AmazonPrimeで観れる内にみないと、せっかくの作品が有料になったら、また観る機会が遠のくかな、と鑑賞。
ボタンの掛け違いが、大きな歪になって悲劇になっていくというストーリー。監督の思惑通り(?)、2人目の目線が始まった段階で、怪物探しをしてしまっている自分がいる。ストーリーが進むにつれて、信じていたものが逆転して不信につながる。物事の見方によって正義が変わっていく、という戦争がなくならない理由を表しているような、そんな作品に感じました。
最後、あの二人は亡くなっちゃったんでしょうね・・・。僕はそう感じたのですが、いかがでしょう。そういう意味で、やっぱり辛気臭い映画だったと思います。説教がましい、というか。それでもいいのですよ、全然。でも、この手の映画は、心が強い時にみないと折れちゃいそうで。要注意、というか。
恐怖映画に勝るとも劣らない恐ろしさ
モンスターペアレント、学校の事なかれ主義、児童虐待、イジメ、同性愛、等々現代の小学校問題をこれでもかと詰め込んだ問題作です。
伏線がいろいろあって、ボーッとみていると理解が追い付かないです。
ただただ、人間の恐ろしさや愚かさをまざまざと見せつけられた気がします。
秘密基地の廃棄車両や廃線跡でのシーンがすごく印象的で、ラストシーンがとても美しくて救われた気がしました。
世界はそれをLGBTとゆうんだぜて話
中、高と自分に置き換えてもそれらしき同級生はいたなあと。
個性なのか、病気なのか
作品では怪物と表現され
私としては病気
だからこそ向き合っていかなあかんのでは無いかと感じた。
切なくて美しい話でした
主人公二人の笑顔に胸が締め付けられました。私にも、子どもが二人いますが、ただただ自由に生きて、幸せになって欲しいと思いました。
ラストシーンは映画史に残る美しさを感じました。主人公二人が、幸せに生きて行ける世界に変わったと信じたいです。
素晴らしい映画でした。
怪物=思い込み
安藤サクラ演じる、夫と死別したシングルマザーは、お母さんになんでも言わなくなってきた小5の息子の湊と全身全霊向き合って生きている。
その湊に不可解な鼻血や怪我や物の紛失などなどが起こりはじめ、母は学校での先生からのいじめを疑う。
状況から、まぁわかる気もするけれど、
児童がいる=先生が授業をされている時間帯に何度も通い詰め、口調も教師を信用できないのはわかるが、タメ語。非常によろしくない。なぜ、先生が意味もなく体罰をするはずがないので、まずうちの子がどんな言動をしたからなんだろう?という発想にならないのか見ていて非常に不可解だった。
信任教師の保利先生もまた、作内では噂で先に、火事があって全焼した建物に入っていたガールズバーに保利先生がいたという先行情報を基に保利先生が登場するため、母親は一層保利先生への先入観不信感を強めて接し、保利先生が息子に暴力をふるったに違いないと断定的に罵倒する。
ミスリード役、湊と同級生の母親役野呂佳代に、どこからそれ聞いたの?と聞かない母親がまた、不可解。
それでも、安藤サクラのクリーニング店員役は万引き家族でも非常に板についていたし、ラグビー選手だった夫に顔向けできるように息子を真剣に育てようとクリーニングの仕事を夕方までこなしながら育児に奮闘している姿は応援したくなる。
その応援に含まれた、
「湊が普通に結婚して子供を持つまではお母さん頑張るってお父さんと約束してるんだ」
が、湊の苦しみの元凶だとは。
息子湊はチャッカマンを部屋に持っていたり、山に入ったり、車から転がり落ちて耳を怪我したり、様々おかしな行動を見せ、それは先生のせいだとは思えないものの、実は保利先生が勘違いしていたように湊がいじめっ子側なのか?チャッカマンで放火までしているのか?豚の脳と人間の脳の入れ替えと称して猫殺しまでしているのか?なんせ表題が怪物なものだから、頑張ってるお母さんの心子知らずで、実は息子は少年Aのような闇を抱えてしまっているのかと考えながら見進めていく時間には脅かされた。
どうか母親の知る湊像と著しく乖離、逸脱した本性ではありませんようにと願う。
それでも、湊から、凶悪な感じはしてこない。
真相はなんなのか?
学級内には、鏡文字を書く、おそらく発達障害の依里くんがいた。依里くんはいつもにこにこしていて感じの良い優しい子だが女の子にも見間違うかもしれないくらいあどけない可愛い雰囲気。
しかし、中村獅童演じる父親は酒にだらしなく、実は母親は依里を置いて出て行っており、父親は依里は豚の脳だと担任の保利先生にも言うほど息子を人間の脳にしなければなどと傷つける発言をするだけでなく、依里に激しいDVをしている。
息子は浴びた言葉を素直に信じて自分はそういうものだと思い、クラスの中ではエイリアンなどと呼ばれいじめを受けているが、笑って対応していた。
湊はそのいじめにできるだけ加担したくないと感じていた。学校の中で依里と仲良くすると、キスキスなどと囃し立てられて自分もいじめの対象になるから学校では依里に話しかけないでなどと子供ゆえの残酷すぎるお願いをしたりするが、実は下校後お互い親の帰りが遅いため、2人で仲良く遊んでいて、おそらく3.11で土砂崩れにより使われなくなったと思われる旧列車を秘密基地のようにして、「怪物だーれだ」の合言葉で人狼ゲームをしたり、列車を宇宙に飾り付けたり、2人だけの世界で将来の夢を話したり、友情を育んでいた。
湊は学校では依里へのいじめを止めるために、他の子達の防災頭巾を散らかして暴れたり、感情コントロールが効かない素振りを見せるが、優しく止めようとした保利先生の手がたまたま当たって鼻血が出ただけで、湊も誰もいじめていないし、保利先生も誰にも体罰をしていないのが実態だった。
湊の怪我は全て、依里くんを公に守りたいのにそれはできない葛藤と、なぜできないかというと依里くんに恋愛感情が芽生えている自覚があり、同性愛では子を持てないとわかるので、母親が軽く発した結婚や家庭を持つまで湊のために頑張るという言葉から、自らを幸せになれない存在と思い、悩んでいた。
学校では、母親の言葉を発端に保利先生が体罰教師として謝罪して新聞に載り辞職、校長先生その他先生は母親を刺激しないようとにかく本質よりも謝罪を繰り返す対応に走る大事態となっていたが、5年生の湊には保利先生が全てをかぶり湊の将来を思い周りの思惑通りに謝罪し仕事を失い、記者に追われ、結婚したい彼女にも逃げられている深刻さを知らない。
それでも保利先生が悪いと嘘をついてしまった罪悪感はあり、校長先生に打ち明けた。
校長先生もまた、孫を亡くした経緯を、実は校長が轢いた等と噂されて先入観のもと教師達から見られたりしていたが、幸せになれないと話す湊に答えをくれる。
「誰かにしか手に入らないものは幸せとは言わない。みんなが手にできるものが幸せ。」
抱えていることは楽器を吹いて吹き飛ばしてしまいなさいと助言してくれる。
ある日暗くなるまで秘密基地に依里といた湊には、血相を変えて母親が車で迎えに来たが、依里を心配し助けに行くべきと車から転がり落ちて怪我していた。
その後依里を心配して家に行くと、依里の父親は依里に、「祖父母のもとに好きな子がいるから転校するので今まで遊んでくれてありがとう」と玄関先で嘘をつかせるが、もう一度出てきて、「実は嘘!」と話した依里が家に引き摺り込まれお仕置きの暴行を加えられている声を耳にする。
嵐の前の日には、家では母親と窓に段ボールを貼ったり準備が進むが、依里を心配して家に行くと、依里は全身に暴力を振るわれ浴槽でぐったりとしていた。
助け出して2人で山に向かい、列車内に台風が近づくのを、生まれ変わりへの出発だ!と称して遊んでいた。
豚の脳と親に言われクラスでも虐められる依里も、植物好きなため品種改良の夢を持ちながらも、死んだら生まれ変わる輪廻転生に希望を感じていた。
父親を亡くし、母親を心配させたくないが、同性愛の悩みを抱えた湊もまた、輪廻転生に希望を感じていた。
猫の死体を学校で見つけた時も、依里から場所を教えて貰い見ていた湊を、女子は目撃して保利先生に報告しているが、その後依里と湊は猫の死体を山に運び、生まれ変われるように依里の持っていたチャッカマンで燃やして、山火事にならないように湊が水筒の水を川から運び火消していた。
チャッカマンはおそらく、依里が父親に火傷の虐待をされた時に手に入れたと思われる。
駅前の建物の火事は、父親がガールズバーに通うのをよく思わない依里が、知的判断がつかずにチャッカマンで放火した模様。
提出した将来の夢の作文を休職中に添削した保利先生が、2人の作文にある横文字、みなととよりに気が付き、過去に依里やみなとに、男らしくないなどと軽く発した言葉など全てに気がついて湊の家に台風の中謝罪に来た時、母親は怒っていたが不在の湊を探しに行くところだった。
保利先生と母親が山にたどり着くと、土砂崩れは既に起きて封鎖されていたが、無理やり中に入り列車に湊と依里がいるか探しに行く2人。
泥まみれの窓からなんとか中を覗くと、2人の姿はないが、2人の着ていたレインコートが見えた。
作中では、2人は列車の車体の下の線路の下に潜り込んで雨風を凌ぎ、生まれ変わりなんてないと湊は言いつつも、台風一過後、転生完了として2人で晴れてから山を駆け回る描写がある。
果たして湊も依里も本当に助かったのかはわからない。発達障害や同性愛の自我を受け入れて、子供達だけの世界の一瞬だけを切り取って判断するしかない先生や親が真相に気付いたとしても、依里の父親は変わらないだろうし湊の母子家庭も変わらない。
子供達は時に親に気を遣いながら、大人の言葉や環境で浴びる辛辣な言葉ひとつひとつを、大人が思うよりはるかに真剣に心に溜めて、傷付き悩んでいる。
5年生の、親とは異なる自我の尊重を求め秘密を持ったりもする月齢への接し方の親の揺れ、
親ではなく断片的に子供を見て責務に支障がないようにするのが仕事の教師、
親の言葉の影響を受けてものの見方が変わってしまう子供達、
その全てに居場所を見出せない時、子供の毎日は地獄である。
子供が話してくれる大人で居続けるためにも、先入観で話をしたり広めたりしないこと、それをよくわかっているからこそ、校長はスーパーで躾なき親が店内を走り回らせている子供の足を引っ掛け転ばせたのかもしれない。
是枝監督の、子供が大人に理路整然とは説明できないが日々感じている心情や時系列で出来事と整理すると子供が日々起こる事象に対して大人や周囲の影響を受けながら思考し判断し行動している様子の描き方がとても丁寧でリアルで好きだ。
作文のとこ
先生が作文の横文字で2人が仲が良かった事に気付いたとされるシーン。
あれ見てる側置いてけぼりで展開早すぎて意味不明でした。
観客に理解してもらうつもりならもぅ少しゆっくりのコマ回しかセリフが欲しかった。
女生徒が猫に対して先生からの再確認では知らないと言い張った所ももぅ少し分かりやすく伝えて欲しかったなぁ。
先生のセリフは猫を殺しただとかの言い回しに対して女生徒は猫をいじってただと言っただけだったので先生の言う殺した、とは言ってないと言った形だったらしい。
後はまぁラストはそれぞれ2パターンで観客の好きな方を選べばそれぞれに値する作品には仕上がってたと思う。
私は2人ともダメだったんだと解釈しましたが。
何を伝えたいかはそれぞれの視点で理解はしたけど先生ターンの時に飴を舐めたシーンは取り入れるべきだったとは思う。
既に彼女が落ち着くために飴をって伏線も張ったんだからと。
まぁそんな感じで私は生徒2人の気持ちには遠い昔すぎて感情移入も出来なかったのでイマイチな感じになりました。
誰が怪物だったのか、誰にも決められないと思う
あらすじ
郊外の町で暮らすシングルマザーの早織は、息子の湊の様子がいつもと違うことに気づく。
学校で何かあったのではと問いただすが、担任の説明と子どもの言葉は食い違い、何が真実なのか分からないまま事態はこじれていく。
親、教師、学校、それぞれの思惑が絡まり合う中で、大人には見えない子どもたちの世界が少しずつ顔を出す。
誰が「怪物」だったのかははっきりしないまま、問いだけが残される。
感想
いろんな問題が詰め込まれていて、どれも誰かにとっての正しさで、誰かにとっての苦しさだった。
親は子どもを守ろうとして、担任の先生は自分を守ろうとして、学校は学校を守ろうとしていたんだと思う。
子どもたちは、分からないまま、不安なまま、それでも最後にはお互いの気持ちをちゃんと大事にしていた気がする。
全部がはっきりとは見えないままだったけど、大人の正しさでは触れられないものが確かにあった。
誰が怪物だったのかは分からないけれど、それぞれが守りたいものの形だけは残っていて、そこにこの映画の問いがあったように思う。
怪物はいなかった
ポスターの「怪物だーれだ」という記述から、怪物を探しながら観たが、怪物なんて存在しなかった。
たしかにそれぞれの視点では、「母親」や「教師」は怪物だった。けれど、全ての視点を見た時、怪物なんていなかったのだということがわかった。同じ事件なのに、それぞれの視点ごとに全く違う解釈になるのがすごかった。
オチは子どもたちは死んだのか?
おもしろかったが難解な部分もあり個人的に分かりずらかったのでこの評価。
うーん
ラストまではものすごく良かった。子育てしてる人にぜひみてほしい!
でも、最後の着地がなんかなー。
謎解きまではほんと見入るものー。
誰も何も悪くないのに、、、、ここまで事件になっちゃうんだーって言う、人に嘘はついてはいけないし、言葉って言うのは、言ってしまったら取り返しのつかないことになるというのを、自覚させられる映画でした。
でも、最後がなー。もっとこうなんかなー惜しい。
浅はかな考え方でした。
国宝みて、喜久夫の子役が気になって気になって、
みました。
公開した時に予告の情報が無くて気になっていましたが、劇場で見れませんでした。
3つの構成で描かれます。
・母親・教師・子ども
偏見や噂に惑わされる。大人も子どもも。
嘘が事実になってしまうのは最も怖いことだと思います。
子どもは放火したのか、校長は本当の犯人なのか、
最後瀕死の依里くんはなんですぐ走り回れたのかな。
もうだめだったのかな。
男だから、女だから、男らしく、女らしく
そんなのなくなればいいね。
わからないことが多かったので、
解説の動画を見させていただきました。
シネマリンさんです。
正直私は博識ではないため、
銀河鉄道の夜やノアの方舟などが出てきて感心しました。難しかったです。
怪物はいなかった
あまりあらすじを知らずに観たのですが、思いがけない展開でした。
「みんなが怪物」という意見もあると思いますが、自分の結論は、「怪物はいない」です。面白かった。
母親の気持ちには共感できますし、盲目なモンスターペアレントというほどでもなく。校長の嘘も理解はできます。社会的にはダメだけど、夫婦で納得できているなら個人的にはよいです。
ただ、いくつか引っかかる点もあります。序盤の教師達の口先だけの謝罪のシーン。何だかコントのようでした。いくら周りに仕向けられたからと言っても、保利先生があんな風に謝罪するでしょうか。飴を食べたのは何だったのか。校長の棒読み謝罪は面白すぎます。
いじめについては、あれだけあからさまにやっているのに子供は誰も本当のことを言わない、大人は誰も気付かない。違和感があります。
また、子供達の「保利先生を陥れる嘘」は自分を守るためだと思いますが、ちょっと理由が弱い気がしてます。色々ありましたが、中でも湊と猫の件を話した女の子…納得できません。
それから、あのくらいの年齢で本当に同性愛を自認するものなのでしょうか。これは知識が無さすぎて分かりませんでした。そもそも、個人的にはその設定は無い方が良かったと思っています。
と、いくつか挙げましたが、それでもよくできた映画で観て良かったと思います。スタンドバイミーを思い浮かべながら観ていました。みんな子供だったはずなのに、大人になると忘れてしまいますが、子供だけの特別な世界ってありますよね。
依里の放火の罪もあるので、この結末になってしまうのは仕方がないと思いました。線路につながる柵が無くなったように、湊と依里が苦しいしがらみや生きにくさから解き放たれて天国で幸せになってほしいです。
最後になりますが、高畑充希さんの演じる彼女の軽薄さにはもう清々しささえ感じました。保利先生、周囲の人に恵まれなさすぎです。
3者の視点、そして真実とは?
怪物ってタイトルがどんな内容かも想像もしないで視聴。
只、宣伝の些細な事から子供を思う親、教師の話かな?って観てました。
3つの視点で一つの出来事を描いていて、シングルマザーの視点、一生懸命仕事をする担任、最後に子供の視点から真実を描いている。
「怪物」と言う題名で、学校が描かれているので、怪物=モンスターペアレント?って観始めて思いましたが、途中、子供達がする怪物ゲームで「かいぶつはだーれ?」でこの作品の誰が怪物なのかを考える話なんだと分かりました。
始めの母親パートでは母親が正義で、責任逃れの仕事の学校に母親同様に怒り心頭。
しかし、担任視点になると、少し発達障がいぽい担任は担任なりに一生懸命やっている。
子供視点で、実は母親も担任も事実を見ておらず、イジメはシングルマザーの子供がシングルファーザーの子をイジメていた訳ではなく、クラスの複数の子供からイジメられていた事が解る。しかもいじめられっ子が同性愛者で、その事をシングルファーザーの父から「頭が豚の脳みそ」と虐待され、父を殺す為にビルに火を点けた事が解る。
シングルマザーの子供ももしかしたら自分が同性愛者かも?と思いつつ、亡き父がラガーマンで父の様に生きる事を母親から強要され、その憧れの父も不倫中に亡くなった事を母親は隠しているが知っているので、母親の言葉に走っている車から飛び出してしまう。
秘密基地で遊ぶ子供達だが、嵐の中に担任と母親が土砂崩れの中に助けに行くが、最後のシーンで嵐が治まった所を二人で駆けて行くが、他の人のレビューでは二人共死んであの世の描写との見方があるが、私はそのまま嵐の中を生き抜いたと思って観ていた。
最初から流れる吹奏楽器の音も伏線として回収されていて、納得した。
いじめられっ子が同性愛者である事がその雰囲気でイジメられるのか分からなかったが、現実としてありそうだし、シングルファーザーの頭の固い父親がそれを矯正しようと暴力に訴えるのも解る気がした。
それぞれが自分の視点でしか事項を見ておらず、最後に子供の視点で真実が明るみになるのは推理小説のタネあかしの様で驚きだった。
怪物は誰?
そんな問いを鑑賞中ずっと考えながらしていた自分がいた。
その答えは「皆怪物だ」ということ。
誰だって弱い部分もあるし、隠したい過去も意地汚い部分もある。
それでいいし、「こうあれ」と矯正する事そのものが悪だし、決めつけや偏見は必ず良い結果を産まない。
ただしいじめっ子のクソガキ共と事勿れ主義の教師陣、中村獅童演じる依里パパてめぇらだけは許さん。
邦画は暗いものが多くて見るに堪えないし、実際前半は苦痛だったけど、全てが明らかになるとこうも印象が変わるものかと思うし、終わり方が鮮やかで心地良かった。
大半の方は2回目を見たくなるのだろうけど、1回でいいかな。
また気が向いたら見る。
もう一度見るべきかも
・友達へのいじめを告発出来ない事
・好きな人への愛を他人に話せない事
・事実を話せずに退職させられる事
・本心で謝りたいのに学校を守らなければならない事
・父からの暴力を訴えられない事
どれもが理不尽であるが、何かを突き破る必要があり、なかなか実行に移せない。それは自分の保身だったり、父親との関係だったり、組織に潰される自分だったりする。大人たちはそれで失敗してしまうが、最後に子供達はキチンと羽ばたいてくれる。子供にはこれから先チャンスがいくらでもあるのだから、自分に嘘などつかずに羽ばたいて欲しいというメッセージなのか。全くその通り。子供達よ、頑張って生きて欲しい。
いい作品です。ほんとうに。
いじめのシーンが幾度もありますが、首謀者が糾弾されることなく終わるのは残念でした。このままだと、虐められるのは仕方ない事のように取られかねませんよね。残念です。
鑑賞後の後味が思ったものと違う
この映画が話題になった当初受賞した事でLGBT関連の映画だとネタバレしたという話が出ていたけどそれで最後が分かるとか見なくても別に良いとか言えるような映画じゃなかった。
怪物の気配がずーっと映画の中に蔓延していて重たい気持ちで進んでいくのに最後の清々しさにもう涙が…
この映画のタイトルは怪物しかありえない。
CMのミスリードもとても効いている。
怪物は無邪気な噂話や囁き声の中にいる。あなたと私、2人だけの時の私と、私とあなた達の時の私。
どのアングルで物事に向き合い考えるか、他者の視点に立つためにはどうしたら良いのか、自分以外の事は点で物事を見ることしか出来ない私達は知らない事と知っている事を間違えないようにしないといけない。他者視点で見るなんて事は本当の意味では出来ないことだから。
一対一の親密な時間と他者のいる世界の見せ方と温度感がとてもうまかった。染みる。
希望がないように見えて、この世の中にあって暗いところから希望を見せてくれているように思う。
面白かったけど
一番納得いかないのは母親目線からのストーリーのとき。どう考えても担任の先生との面談の際、1)先生が保護者の面前で飴舐める 2)「シングルマザーのあるある」発言 3)校長先生の木で鼻をくくった(今まで生きてきて、この慣用句が初めてしっくりくくる場面と感じた)対応。(それにしてもこのシーン、安藤サクラが田中裕子の鼻に指突っ込んで。面白すぎ)
担当の先生のストーリーの時、この飴舐める場面と「シングルマザーのあるある」発言についての回収は無かった。一生懸命やってる先生って感じなのになぜ、あの行動と発言になったのかの場面がなく、最後までモヤモヤが残った。
校長先生についてもスーパーで走り回ってる子供に足を引っかけるところを母親が目撃する。そのため、校長先生の「素」が垣間見えるような場面となっているのだけど、これについても回収は無かった。悪い先生ではないのは少年を楽器を一緒に吹いて交流するところを見るとわかる。
作品を見る前に芥川龍之介の「藪の中」を彷彿とさせる、みたいな書評を読んでいたのでなるほど、面白い構成だな、とは思ったけど、どう考えても上のモヤモヤが解決されなかったので、そこが納得いかない。ラストの二人をどう解釈するかよりも気になる。
難しい
同じ時系列を3部構成でまとめている映画。
1部目はその異様さに疑問を多く抱き、2部目でそれが誤解であり間違いだとわかり一体怪物はだれなのか?と考える、3部目に種明かしをするのだが結局怪物とはなんだったのか。本筋はわかっても回収されない部分が多すぎて結局疑問が多く残ってしまう。
物語の3割以上が視聴者の想像に委ねられているような作品だった。
ラスト子供達はどうなったのか...生まれ変わりという言葉を取るならそうなのか...モヤモヤした気持ちで終える。
この全ての答えを出さないところが評価を得れているのだろうか...
視点と解釈の迷宮、そこに潜む「怪物」とは
観る者の視点と解釈を揺さぶる、奥深い作品だ。
美しい風景と共に織り成す湊と依里の場面では、私自身の少年時代の体験が蘇る。秘密基地やそこで過ごす誰にも邪魔されない時間、そして言葉にできない感情。それは、大人になるにつれて失われていく、かけがえのない宝物のような時間だ。しかし、同時に、子どもであるがゆえの無力さ、大人たちの無理解に苦しんだ記憶も蘇る。
物語は一見すると、いじめやDV、モンスターペアレント、教育現場における事なかれ主義など、現代社会にありふれた問題を扱う映画のように見える。しかし、湊と依里の関係がクローズアップされるにつれ、物語に潜む場面や何気ないセリフが、彼らへの苦悩や抑圧を生んでいたことに観客は気づかされる。
「お父さんみたいになれないよ」「豚の脳みそに入れ替わる」「ぼく、もう病気が治ったよ」「生まれ変わり」…これらのセリフは、二人の関係への社会の無理解や偏見が生んだものだったと気づき、観客の心を深くえぐる。
湊と依里の関係を安易に恋愛だったと決めつけてしまうことや依里の父親の暴力の原因、ラストシーンの湊と依里の生死など、それらを詮索すること全てが、観客自身の「怪物」性を浮き彫りにし問いかけてくる。
湊と依里が追い求める「生まれ変わり」は、社会的抑圧からの逃避だけではなく、もう一度過ぎた時間を戻し、あの楽しい時間を二人でまた過ごしたいという切実な願いだ。だからこそ二人は、二人だけの場所だった廃電車を「出発」の場所として選び、あの場にいたのだと私は思う。
この映画は、見返せば見返すほど観客を永遠の間違い探しに誘い込む。視点を変えるたびに、物語の解釈が変わり、観客は何度も立ち止まり、考えさせられる。それは、保利先生の趣味である「誤植探し」にも似ている。細部に目を凝らし、わずかな「ずれ」や「間違い」を見つけ出すことで、初めて見えてくる「気づき」がある。
「怪物」は、観る者の数だけ解釈が存在し、観るたびに新たな発見がある作品だ。安易な決めつけや偏見を捨て、多角的な視点から物語を読み解くことで、初めて見えてくる真実がある。この映画は、観客自身の「怪物」性を問いかけ、私たちに永遠の間違い探しを強いる。そして、物語に潜む社会的メッセージに気づいた時、観客は深い衝撃と同時に、少年たちの「生まれ変わり」に託された願いを感じるだろう。
全320件中、1~20件目を表示