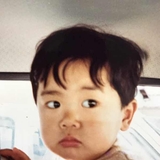怪物のレビュー・感想・評価
全696件中、61~80件目を表示
素直に感動だが…
怪物は誰の中にも棲んでいる。じっと存在を潜めて深く静かに・・・
男の中に女が棲み女の中に男が存在している。それは無意識の中だけれど確かに存在し人それぞれに潜在する意識下から顔を出しパニックを起こさせる。自我と自己を理解せずに野放図に飼い慣らしてしまうと周りの人間を巻き込み奈落の底へ導く。それは人間にしか起こりえない事象なのか症状なのか病気なのかまるで見当がつかない。この映画を観て怪物探しをしても無意味だろう。怪物は登場人物一人一人なのだから。
映画がはじまり安藤サクラ以外の人々がすべて狂っている人のように思わせる。しかし映画が進行するに従いみんな良い人に思えてくる。それはおかしなことはす訳が用意されているように作られている。その理由がなんとも幼稚だ。だから映画がダレてしまう。観ている者が容易に思いついてしまう。もしくは先読みをしてしまうからだ。しかしひとつだけ解き明かせないと感じさせるよう意図されているのがひとつのこされている。男が男を恋する気持ち。少年は子供ではない。とっくに子供たちは気づいている。ただ認めたくないだけ。そんな気持ちを大人は解ろうとしない。辛抱が足りない親や教師は短時間で理解しようとする。人の気持ちなんてわかるはずがない。そう断定してもいいのだろう。今は・・・・待ちきれない大人たちは子供を不幸にするだけなのに。本当は夜空や雨や風の匂いや諏訪湖の湖面の変化について一晩中でも話しあっていたら、多分とても幸せな気分のひとときが味わえたろうに。
初見ではよく分からなかったけど…
僕たちの愛
教育現場
是枝裕和×坂元裕二×坂本龍一
あなたの中の怪物
是枝裕和監督作品の中で物語が
一番ちゃんとしてるというか、上手いと思った。
脚本が坂元裕二が担当したからかもしれない。
それぞれの視点から観ていくと、皆、勘違いし合ってる。
ただ一部を除いては。
それは依里の父親と依里をイジメていた生徒達。
彼等立ちが「怪物」なのでは?と、個人的には思った。
でも、イジメを知りながら傍観していた湊とクラスメートも
ある意味「怪物」だったのかも?
でも本当は「あなたの中にも怪物がいませんか?」
というのが真のテーマなのだと思う
安藤サクラは相変わらず上手い!絶対に裏切らない女優
永山瑛太も上手い俳優だと常々思っていたし、今回も良かった
ラストは観た人それぞれの解釈に任せるという感じで
個人的には、二人が死ぬ寸前に観た「理想の世界」だと解釈しました。
⭐︎4.3 / 5.0
子役の演技は印象に残ったが...
始まって40分くらいは興味津々だったが、そのあとは釈然としない。
そこらのエンタメ映画とは違うんだぜ、と言わんばかりの純文学風の内容だが、そのわりには、わざとらしい漫画チックな演出が散見される。例えば、母親が学校に文句を言いに行ったときの学校側の対応なんて、まるで漫画に出てくるような、これでもかと言うぐらい過剰に憎たらしく描いている。また、中村獅童演じる父親は、教師の安月給を馬鹿にしたり、息子に「お前の脳は豚の脳。病気を治してやる」と言ったり、これも漫画に出てくるような性格の悪いサイコパスっぽく描いている。他にも、他の方も指摘しているが、問題の教師が母親に謝罪するとき急に飴を舐めだしたり逆切れしたりするが、これはのちの展開でその教師の本当の姿が180度変わることをカモフラージュするため、わざと「嫌な教師」の演出をしたのだろうが、単に不自然で矛盾する演出となってしまった。
内容は、ある出来事に関して次々に視点が変わり、見る者が思っていた真実も変わっていくという凝った作りになっている。でも結局これが導きだすのは、実はこれこれが真相でした、ということだけの話で、作者が本当に言いたいことはいろんな視点を行ったり来たりするのでぼやけてしまっているように見える。もし、「人は誰でも見方によっては怪物になりうるのだ」あるいは「信じているものは本当に真実なのか」と言いたいのだとしたら、先生視点のパートや子供視点のパートのエピソードはもっと短くていいはずで、あれだけ長いのなら他に何か言いたいことがありそうだが、よくわからない。特に、終盤の子供視点のパートは長くて2人の友情(怪しい関係?)が育まれる物語に変わってしまい、もはや「怪物だーれだ?」とは関係ない展開になっている。そういう意味で、色々なエピソードを詰め込んでいるため焦点が定まっていないように見える。結局なんの物語だったんだろうというモヤモヤした気持ちだけが残った。こういう映画は、いくらでも勝手な解釈で深読みできるので、「いやいや、君は分かっていない」と言われそうだが。
してやられた
普段自分たちが実際目で見てないもの、
子どもの学校の事だけじゃなくて、
SNSやネット記事もどれだけ先入観で良い悪いを決めてるかをまざまざと見せつけられた。
瑛太さんのあの先生の謝罪、あれは謝罪の態度は明らかに
ヤバいやつでしかなかったけども、
それでも悪い奴だと決めつけてしまった自分がいて、
恥ずかしいと同時にしてやられた!手玉に取られた!と
その手法と演出に感動すらしました。
自分で見たもの以外は信じない。と思って生きて来たけど
見て来たものも疑え!と言うのが、
この映画で一番思った事。
子どもの世界は大人が思ってるより複雑で、
悪気もなく言った言葉が、心を壊して行く可能性がある
と言うのもよく分かった。
怪物は一体何だったか、何が怪物を作ったのか?
やはり、それは言葉だったのかなと思う。
完全な悪人などいなく、また完全な善人もいない。
飴を舐めたのが、
怪物だーれだ?
❇️『瑛太さんは何故飴を食べたのか?マジ一番笑うところ😅』
怪物
❇️『瑛太さんは何故飴を食べたのか?マジ一番笑うところ😅』
🇯🇵長野県諏訪市
🔵かーるくあらすじ。
シングルマザーの息子が虐められてるのか?
靴が無くなったり、水筒に泥水、先生に殴られた事を母親に伝える。母親は学校に抗議する。
しかし見方の角度を広げて見ると、おかしいのは学校だけではなかった!いろんな種類の怪物達が現れる青春クライムドラマ。
◉70点。
★彡ややこじつけや過剰な演出も、あった様な気がするが、角度を変えて見るとこんなに真相は違う事に驚きました。
🟢感想。
1️⃣🔺『怪物とは言い難い!』
★彡怪物の表現には見合わないと思いました。
2️⃣⭕️『学校の対応ってあんなに酷いのか?』
★彡瑛太さんも飴を途中で舐めるとか普通ないでしょう😅ちょっとコメディーの雰囲気ありました。
3️⃣⭕️『スタンドバイミーぽくて良かった。』
★彡秘密基地的な環境は癒されるな。
4️⃣⭕️『一筋縄では行かないイジメの実態』
★彡誰でも瑛太さんの様になりうる。
見た時の状況だけでは判断が難しいですね。
👩🏻👦🏻🚃🏞️🧑🏻🏫
苦しくて辛い
火事を起点に少しずつ事実がわかっていくところが、時系列の記憶が追いつかず
もう一度確認のために観たくなるのかもしれないけど、もう一度は辛い
ずっと胸の奥がザワザワして
「かいぶつだーれだ」 が突き刺さってきます
最後の最後になって もしかしてもうラストを迎えているのか?と不安になったところでエンドロール
こんなラストなんだーー岩井俊二作品だから??
とか思いました。ファンタジー
子供を愛している 日々の暮らしがある
なんかおかしい
こうありたいと思うがどうにもならない
モヤモヤする
気づけない 気づいても私ができることは?
なんでこんなに忙しいのだろう
忙しいふりをして本当は煩わしいのかな
モヤモヤする………
とにかくキメツケルのはやめよう
推測や憶測での話は控えよう
認知のズレ
全696件中、61~80件目を表示