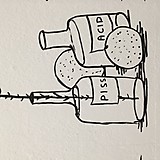ガール・ピクチャーのレビュー・感想・評価
全25件中、1~20件目を表示
エマ役リンネア・レイノのフィギュアスケート演技が美麗。国際的な活躍を大いに期待
日本に届いてきたフィンランドの最近の話題と言えば、2019年に34歳で首相になったサンナ・マリン(当時世界で最も若い在職中の国家指導者だという)が、今月2日の総選挙で所属するフィンランド社会民主党が後退した責任を取り辞任することや、マリン首相が在任中に申請したNATOへの加盟が4日に正式決定したことなど。同国の女性首相は3人目だったそうで、男女平等の目安となるジェンダー・ギャップ指数の2021年調査でフィンランドは世界第2位になっており、女性に開かれた社会のイメージがあるが、意外にも同国の映画では若い女性を主体的な主人公として描く作品が少ないとか。
そんなフィンランドで作られた「ガール・ピクチャー」は、比較的最近の映画でいえば「ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー」のように、ハイティーン世代の登場人物たちが友情をはぐくんで絆を固めたり、性的なことを含む大人の世界に足を踏み入れたりといった要素が中心になっている(「ブックスマート」のプールのシーンで流れていたPerfume Geniusの楽曲「Slip Away」が、「ガール・ピクチャー」のある印象的な場面でも使われている)。登場人物3人のうち、母親をはじめとする家族との関係に問題を抱えるミンミと、フィギュアスケートの欧州選手権出場を目指すエマとの関係性は、パルムドール受賞作「アデル、ブルーは熱い色」やセリーヌ・シアマ監督作「水の中のつぼみ」を想起させもする。
もう一人のキャラクター、ロンコはミンミの親友で、出会いと性的な体験に前向きなのだが、言動が(男性目線からすると)微妙にずれていて、相手と良好な関係をなかなか築けない。ロンコの性的なこと、ミンミの家族とのこと、エマのスケートという3人それぞれの事情に、ロンコとミンミ、そしてミンミとエマという2組の関係性のストーリーがからみ、3度の金曜のパートで綴られていく。
ロンコ役とミンミ役の女優2人は20代前半、エマ役のリンネア・レイノは20代後半で、役の年齢よりも実年齢のほうがかなり上なのだが、それぞれに性的な演技が必要なシーンがある事情を考慮すれば、適切なキャスティングということになるだろう。ちなみに、監督のアッリ・ハーパサロと共同脚本の2人はみな女性で、インティマシー・コーディネーターも参加している。
本作を特別なものにしているのは、何と言ってもリンネア・レイノによるフィギュアスケートの演技だ。あまりの見事さに経験者を起用したのかと思ったが、プレス資料によると3カ月の特訓でものにしたとか。特技にダンスとダウンヒルスキーを挙げていることから、もともと優れた身体能力の持ち主なのだろうが、それにしても数カ月であの表現力は驚異的だ。トリプルルッツのような高難度技のシーンはダブルのアスリートを使っている可能性もあるが、ゆっくりと滑りながらのパフォーマンスは間違いなくレイノ本人。さらに母国語のほかにも、フランス語、イタリア語、英語、スウェーデン語を話せるとか。天から二物も三物も与えられたリンネア・レイノが、サンダンス映画祭で観客賞を受賞した本作をきっかけに、国際的な座組の映画に出演する機会が増えることを大いに期待する。
入り込めそうで入り込めない
ガールズフッド溢れる一本
ミンミとロンッコが仲良しなのは、同じアルバイト先で深めた関係性なのでしょうか。
否、仲良しだったから、同じアルバイト先で働いているのでしょうか。
一方で、なかなか思う通りの演技(フィギアスケート)ができないエマには、ヨーロッパ代表選手権のプレッシャーが、容赦なく彼女を襲うー。
かてて加えて体重管理のためのカロリー制限の故でしょうか、飲み物ひとつ選ぶのにも気を遣わなければならない。
ミンミ・ロンッコも知り合ったときのエマは、本当に、精神的にはボロボロの状態だったことでしょう。
出会うことで、エマはミンミとロンッコという、いわば「心の支え」を得ることができたし、他方のミンミ・ロンッコにしても、無二の親友を新たに得ることができた。
フィンランド語での原題は『Tyt,t tyt,t tyt,t』で、「女の子たち、女の子たち、女の子たち」という意味のようです。
そのタイトルのとおりに、少女から大人の女性へと、今まさに脱皮しようとしている若い女性の心情の揺れ動きを見事に描き切ったという点で、「ガールフッド溢れる作品」ということでは、邦画で例えれば、『私をくいとめて』や『勝手にふるえてろ』、『甘いお酒でうがい』などをものしている大九明子監督などの作風にも親和性がありそうだと、評論子は思いました。
ネットで公開されている監督インタビューによれば、本作を観た多くのレビュアーからは「自分が10代だった頃に観ておきたかった映画」という評が数多く寄せられているとも聞き及びます。
評論子も、まったく、その通りと思います。
充分な佳作だったとも思います。
(追記)
もちろん、本作のストーリーからいえば、決してキーになるような台詞ではないのですけれども。
ミンミとロンッコが働いている軽食スタンド(?)は、いったいどんな店なのでしょうか。
見かけるところ、日本でいえば大型ショッピングセンターの片隅によく出店しているファーストフードのコーナーのようでもありますけれども。
しかし、そこで提供している飲み物の名前が、まったく不可解なものばかりなのは、いったい全体いかなることなのでしょうか。
「呼吸」だの「あなたは完璧」だの「ライムの情熱」だの「緑は最高」だの「ピーチラブ」だの「もちろんメロン」だの、そして「二人でマンゴ」だの…。
前菜は「愛は打ち寄せる波」でした。
いずれにしても(少なくとも日本人には)およそ食欲、購買意欲をそそりそうなネーミングではないとも思われます。
初めて店を訪れて困惑するエマを尻目にミンミは注文の決定を迫るのですけれども。
しかし、この店で注文を速断即決できるのは、余程の常連でもない限り無理だと思ったのは、果たして評論子、独りだったでしょうか。
(追記)
<映画のことば>
生姜ジュースはいかが?
寝たきりの人も飛び起きる味よ。
亡母が好みでなかったからか、子供の頃から評論子の家庭では食卓にあまり乗らなかったようで、長じても評論子はいわゆる香味野菜があまり得手ではなく、お好み焼きや焼きそばに紅しょうがを添えるようになったのも、その実、ここ数年のうちのことでした。
そんな評論子であってみれば、「飛び起きる」どころか、「あの世に直行」かも知れないと思うと、ちょっと可笑(おか)しくて、笑ってしまいました。
(追記)
評論子は、英語が得意という訳ではないのですけれども。それでも乏しい知識を振り絞って考えれば、邦題の『ガール・ピクチャー』は、「少女たちの肖像」くらいの意味合いでしょうか。
女性と女性(少女と少女)の間ではどうなのか、男性の評論子にはよくは分かりかねますけれども。
少なくとも日本では、男女の間では、こんなにも赤裸々に「性」が語られることはないこともあり、「映画は異体験」と常々は考えている評論子には、まさに「異体験」で、そういう意味では「新鮮な一本」でもあったとも思います。
上記のとおり、原題の『Tyt,t tyt, tyt,t』は、フィンランド語で「女の子、女の子、女の子」を意味するそうですけれども。
ときに、日本よりは男女の平等が徹底していると思われるフィンランドの社会でも、この言葉は、女の子らしくない行動について、「女の子なのに」というトーンで使われることが多いと聞きます(監督インタビュー)。
そうすると、本作は、彼(か)の国フィンランドでも、かなり実験的な作品だったのかも知れません。
(飽くまでも、フィンランドを知らない評論子の印象ということで、ここはお納め願います)
【性に奔放で寛容な国フィンランドで生きる3人の少女の物語を描く自由でジェンダークィアな青春映画。三人の少女が、自身の想いを自由を獲得する方法を学んでいく姿が素敵な作品である。】
■クールで皮肉屋なミンミと、素直なロンコ。
親友の2人はいつでも恋愛やセックスの不安や期待にまつわるおしゃべりを楽しんでいた。
出会いを求めてパーティにやってきたロンコ。一方、付き添いで来たミンミは、フィギュアスケーターのエマと急接近する。
◆感想
・東洋の日いづる国に住むオジンサンにとっては、可なりドキドキする作品である。
ー えーっと、私が遅れているんでしょうか? けれどもオイラが高校生時代に付き合っていた女の子から、クン二リングスを指導された経験は、胸を張って言うが全くなし!-
・フィンランドの人達にとっては、若い頃から人生=セックス(変な意味ではない。)と言うのが普通なんだろうな。
■この作品が、沁みるのはミンミと、ロンコの性にまつわる言葉の遣り取りや、ミンミが出会ったフィギアスケートの選手で行き詰まっているエマとの出会いであろうな。
ミンミが、自分達とは違うフィギアスケートの頂点に立とうとするエマの姿を見て、彼女がルッツが巧く出来ず悩む姿を見て、抱きしめる姿。
<今作は、子供と大人のはざまにいる3人の少女が“こうあるべき自分”を思い描き、つまずき、失敗しながらも誰かと寄り添い、自由を獲得する方法を学んでいく姿が素敵な作品である。>
フィンランド、オープンだなぁ
同じ学校に通っているミンミとロンコは放課後スムージー店でアルバイトしながら、恋愛、セックス、などを語り合ってた。そんなある日、恋愛がうまくいかないと悩んでいたロンコは、出会いを求めて、ミンミとパーティへ参加することにした。そこで、ミンミは、ジャンプがうまく飛べなくなったフィギュアスケーターのエンマと出会い、お互いを好きになり・・・てな話。
ミンミは母が再婚し愛情に飢えていて、ロンコは頭でっかちでセックスの際注文が多く男が逃げていき、エンマはスケートだけの生活で遊ぶことを知らずミンミと出会い弾けてしまう。10代の少女3人が3様の悩みを持つのが面白い。
年齢設定が定かじゃないが、学校は高校っぽかったが、それにしては酒も飲んでたし、大学生になったばかりくらいの設定なのかな?フィンランドのティーンエージャーってすぐにセックスになるのかな?オープンだなぁ、って思った。
それと、スムージー1杯が7.9ユーロ(1200円以上)とは、高っ!て思った。
精子のマグカップ、理解できなかった。それと、邦題はなんだかピンと来なかった。
ミンミは眉毛が金髪だから一瞬眉毛剃ってるのかという外見で、母の愛に飢えた少女を好演してた。エンマ役のリンネア・レイノは背が高くスタイル抜群で綺麗だった。
辛かった
爽やかな読後感(のような)に浸れる青春映画!
ムーミンのマグカップで精液採取の意味がわかりません
活き活きフィンランド映画
くじけるな、若者!
きわめて評価の高い映画。2023年のベスト10入りはほぼほぼ確定かなぁ。
今年134本目(合計785本目/今月(2023年4月度)29本目)。
日本ではあまり見ることができないフィンランド映画で、その中でもいわゆる「シスターフッド」を描いた映画です。その「シスターフッド」の性質上主人公を1人に定めるのは難しく(3人セットととらえるのが妥当?)、表現としてやや厳しいところはありますが(性的表現の一部。PG12ですが、PG12を若干超えているように思える)、それでも良い映画ではあります。
過去作でこの手のシスターフッドの映画で見たものといえば趣旨が同じ(アクションものではない、など、一定で絞りをかけることしかできない)映画だと、2021年の「プリテンダーズ」等があるかなと思いますが、展開は似ているところもありますが違います。
映画として明確にストーリーの中の発言として「フェミニスト・フェミニズム」という単語が出たもの良かったし、登場人物の大半は女性なので(残りの5%は大人の営みのシーンでちらっと出るだけに過ぎない)、その「シスターフッドとしての映画の在り方」はこちらの映画はかなり強く感じられます。
一方でこの映画は性自認やアセクシュアル(他人に恋愛関係を描かない、ということ)といったテーマも入ってくるのが新鮮でした。これだけの内容を100分ちょっとでおさめたのはとてもよかったです。
大阪市内では放映されている映画館が1つ(シネリーブル梅田さん)しかないのですが、ぜひぜひ見ていただければ、と思います。
評価に関しては以下の通りです(5.0を超えられないのでここで記載)
(加算3.0/シスターフッドを描く映画について)
・ 男女同権思想やシスターフッドを描くような映画は、趣旨が妥当であり、女性の人権の尊重をうたったりするなどのテーマ性がある限り、一律3.0の加算を行っています。
(減点0.3/字幕がわかりにくい部分がある)
・ フィンランド映画なので、固有名詞などでも何を指しているかわからないか理解に支障をきたす部分があります。序盤かパーティに行くシーンで「カレはどこ?」のセリフは「彼氏」か「「カレ」という人物」(男女は不明)か、パーティなので「「カレ」という食べ物(はどこか)」等いくつかの解釈ができます。
ほか、これらにこっそり混じってフィンランドの地名や、アイススケートに関する語(主人公の一人はアイススケートの教室に通っています)等が出てくるなど、固有名詞が「何を指すのか」「属性がわかりにくい」点は言えると思います。
(減点0.3/「腕をねじ折ってテレビに投げる」って何?)
・ あまりにも珍妙な字幕だったので鮮明に覚えています。厳密な表現は違うかもしれませんが、「腕をテレビに投げる」という点においては同じです。ただこのあとそのような行為を行っている様子もなく(暴力的行為だし、そもそも物理的にできない)、何を指すのかよくわかりませんでした(フィンランドのことわざか慣用表現??)
見ると元気になる。自分の10代の頃を思い出す。10代は、時代や地域を問わず、自分の感情と正面から向き合って組んずほぐれず大騒ぎ。
フィンランド発、10代女子の青春の物語。よくある話だが、おやっと思ったのは、アセクシャル、バイセクシャル、レズビアンであることで、悩んだり、隠したり、変な目で見られたりする描写がないところだ。アセクシャルの子は悩んでいるのではなく、色々とチャレンジ中だ。これが日本映画なら、LGBTに関する葛藤の描写が入る。
しかし、この映画では例えばレズビアンであることが一般的な話題と変わらない。 「女性が好き」ということが、「好きな色は青」 「ウドンよりソバが好き」 「わりと暑がり」なんてのと変わらない。
ヨーロッパ、特に北欧では性的指向で差別はしないという考え方が社会に広く浸透しているのだろう。だから映画にもそれが反映されて、LGBTを特別なこととして描かないのだと思う。
2023/4/21(金),5/2(火) 吉祥寺uplink
いかにも自然な
2022年。アッリ・ハーパサロ監督。フィンランドの女子高生3人の青春の一コマ。母の再婚のショックから立ち直れず感情の起伏が激しい人、性に興味津々だがうまくいかずに焦っている人、フィギュアスケートの国際大会を前にスランプに陥っている人。家族、恋、将来。万国に共通の若者特有のテーマ。
よくあるといえばよくある話で、主人公の二人が自然に同性愛カップルになっていくことを除けば、既視感満載。これが例えばカナダの女子高生といわれても違和感なく受け入れてしまうだろう。現代社会は(若い世代はなおさら)そのように画一化が進んでいるといえばそれまでだが。だからこの映画の物語に異文化的なものを求めてはいけない。
映像表現としても、ドライブの解放感(と恋の絶頂感)を表現するのに窓から片手をつき出す、という「ボヴァリー夫人」からやりつくされていることが再演されている。「ボヴァリー夫人」を想起させようとしているわけではないだろうが。そういえば「ドライブ・マイ・カー」では、たばこを持った手を二人同時に上にあげるという変わったことをやっていたよなあ。この映画にはあのような異例なことが出てくることはない。
つまり、かつての物語で描かれていたこと(親の再婚、同性愛、女性の性欲など)が現代社会ではいかにも自然なこととして実際に生起するようになっており、それをどこかで見たことがある表現手法(窓から手を突き出す類の)を参考にしていかにも自然に撮るとこうなるということなのかもしれない。
バイトテロはいけませんね
フィギュアスケートは情念であった
全25件中、1~20件目を表示