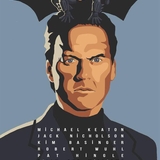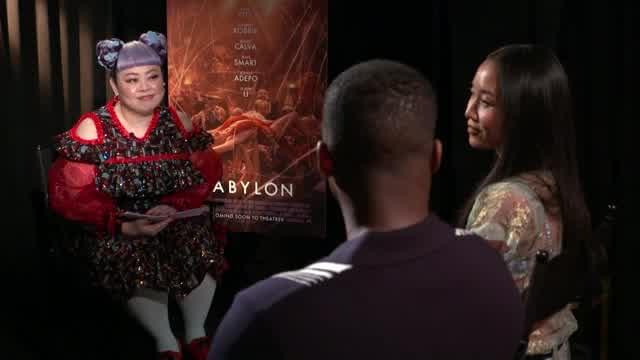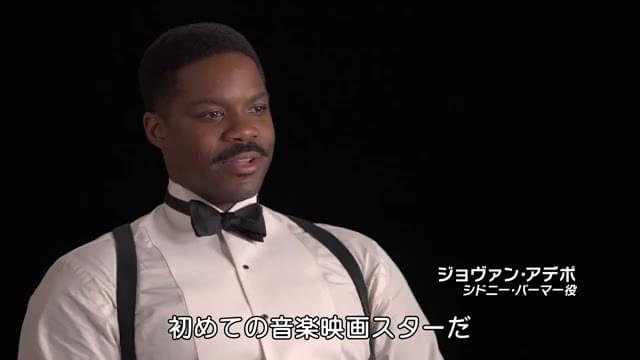バビロンのレビュー・感想・評価
全318件中、201~220件目を表示
「映画愛」に震える物語。
かくも「映画」というものは愛しいものなのだろうか。デミアン・チャゼル監督の眼差しは<創造するものたちへの限りない愛>に溢れ、狂乱の20年代ハリウッドを、このうえなく魅力的な祝祭空間として描いた。サイレントからトーキーへの移り変わりの悲喜こもごもは、これまで様々な映画作品でモチーフとされてきたものの、それは高みから見下ろして語る歴史であった。しかしこの『バビロン』は血を流し苦悩する、虚飾に生きるしかない<映画屋>の物語。時代から取り残される役者というのは『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(クエンティン・タランティーノ監督 2019年)で70年代に落ちぶれた往年の西部劇俳優をディカプリオが演じ、その友人でありダブルであるブラピが**を**してマルチバースなハリウッド史を表現していたのが記憶に新しい。ともあれ、トーキーに対応できなかった様々な人々と、生き残り切れなかった有象無象が、悲しくも消え去っていく残酷なら必然。しかし、連綿と続く「映画」という夢の世界は、そんな者たちさえ<歴史の一部>として現在まで続いているという、チャゼル監督の鎮魂の物語である。
冒頭の30分近く描かれる、狂乱淫靡な即物的享楽だけが<正義>であったギョーカイに、破裂しそうな野心を持ってチャンスを得ようと潜入する主人公たちに、189分続く悦楽を鷲掴みされる。そしてラスト10分の、130年にわたる映画史に残る古今の名作が、眩暈を呼び起こすフラッシュカットで提示される。これらの編集はチャゼル組のトム・クロス。16ビートの疾走する勢いで、作品全編の緩急自在なリズムと、冒頭の狂乱とクライマックスの映画史で観客の血圧をぐいぐい押し上げる。
まことに映画という愉悦に浸らせてくれる、見事なお点前であった。
時代はいつも猛スピードで進化します。21世紀の今だけではなく、いつも、です。時代の要求に自分を合わせ続けなければ生きられない。それが人間社会の残酷さだよというのが、この映画の主張なのかも知れません。
映画が出現してからトーキーに進化する、わずかな期間が、この映画の舞台です。その進化の異常な速さを念押すように、映画の中で「西暦年」がこれでもかと強調されます。
当初は、砂漠地帯の、屋根もない、オープンでチープなセットで映画が撮影されていた時代でした。
無声映画だったから、隣のセットから聞こえる声や騒音も、監督の声も、撮影の邪魔にはならなかった。
そこでの撮影で独特の才能を見い出され、一気に「スタア」の一端に名前を連ねるようになったのが、マーゴット・ロビー演じるヒロインです。
しかし、翌年には無声映画はトーキーへと進化し、撮影時の雑音をシャットアウトすることが求められ、本格的なスタジオ撮影に切り替わり、マーゴットが発揮していた才能の数々は封殺されていきます。
多くのスターたちが、自分だけが持っている「輝く才能」によって一瞬のうちにスターダムにのし上がり、しかし時代の変化があまりに急すぎて、映画が求める才能は次々に移り替わり、瞬時に上り詰めたスターはまた瞬時に使い捨てになり、二度と浮上できないという残酷な真実を突きつけるお話でした。
時代の進化に追いつくため、絶えず努力し、常に自分を変化させ続けた、たった一人、謎の中国人だけが生き残り、ほかの全員が一気に消え去ったのです。
時代の変動は残酷すぎる。
時代が激動することに気づくのが始めの第一歩ですが、それはしかし、なまじ成功を掴んだ人間に突きつけられる要求として、残酷すぎる現実なのです。
そういうことに対する、警鐘を鳴らす映画だったのでしょうか。
あるいは、ここまでの感想って、監督の意図を深読みしすぎかも知れませんが。
ストーリーは、凄いです。
ほんとうに凄いの一言。
まったく一瞬先が予想できない、天才の作品だと思います。
ストーリーのジェットコースター状態を車酔いしながら楽しむのが、いちばんの楽しみ方ではないかと思いました。
映画そのものは、映画業界人のツボに、見事にはまるように造られているので(これは駄作「ラ・ラ・ランド」も同じ構造ですが)、アカデミー賞だとか、あっち系の人たちには受けるのだろうと思います。
でも一般人たる私たち、つまり自分でお金を払って映画館に観に行く観客にとっては、どうなんだろうかなと思うのでした。
一般人だろうが誰だろうが、栄光の一瞬はあったでしょ、だからこの映画も刺さるでしょという、映画人の押しつけがましいメッセージに思えてしまうんですよね。
ブラッド・ピットは、「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」でも、まったく同じ役柄(一気に落ち目を迎える映画スター)を演じていましたが、今作と前作の、どちらの演技に、彼自身は満足していたのだろうか、なんて雑念も沸くのでした。
マーゴット・ロビーは謙虚さのかけらもないヒロインで、「まだ一本も映画には出てないけど私はスターなのよ」と威張る設定のお蔭で、感動話に進む方向も摘み取られてしまっていて、これは一体どうするつもりなんかねぇ、と思いながら観ていたのですが、そのなかで考えうる一番安易なストーリーを監督が選んでしまったのが、返す返すも残念でした。
下品さの裏に重厚的な物語が隠れている
「酒、ドラッグ、セックス」という3拍子揃った狂乱的映画は今まで散々あるが、うまくコミカルに描かれておりクスッと笑えるシーンが多かった。
そして開始数分後からスピーディーに展開していくのが心地よかった。「セッション」や「ラ・ラ・ランド」と同じ監督と誰もが納得できる、音楽にのせて演技が進行していく感じが興奮を呼び寄せる。
鑑賞後何よりも思うのが、マーゴット・ロビーがとにかく輝いている映画だということ。彼女にしかこの役はできないであろう。
絶対実現不可能だが、映画館で誰も他に人がいない中で強めのお酒をちびちびと呑みながら観たいものです。家族やパートナーと観るものではない。「映画」へ対する愛と敬意が大きければ大きい人ほど、この映画は刺さりそうだなと思いました。
マーゴット・ロビーを通してハリウッドを楽しむ
1920年代のハリウッド黄金時代に、夢を追いハリウッドへやって来た青年マニーと新進女優のネリー(マーゴット・ロビー)が大物俳優ジャック(ブラッド・ピット)と出会い、それをきっかけに、怖いもの知らずのネリーはスターになっていった。そして、時代はサイレント映画からトーキー(発声映画)に移って行き・・・てな話。
サイレント映画の時は美しければ声なんてどうでも良かったのが、トーキーになり、声が変で潰れていった女優が居たのは何かの作品で観て知っていたし、大変革だが時代の流れで仕方なかったのだから、合わせていかないといけないと思う。しかし、酒を飲み、薬に手を出し、オッパイ出しまくりの乱交もどきが当時のハリウッドの裏側だったのだろうか?
バックに流れる音楽はとても良くて、目を閉じても楽しめるくらい素晴らしかった。
ネリーのハチャメチャぶりは、ハーレイクイーンに通じるものがあり、マーゴット・ロビーしか出来ないだろうと思わせる素晴らしさだった。
特に、トーキー初期のテイクを重ねる時、乳首をわざと立たせての熱演はエロくて可愛かった。
破綻した映画。
期待以上の面白さ
あまり期待してなかったけど予想以上だった。
糞尿、ゲロ、毎晩パーティ、酒、ドラッグ、人前でセックス、裸体、マフィア…
開始10分で『お下品』だと言われるもの全て出てくる。
制作中、人が死んでもお構い無し。
R15で公開されていい作品ではない 笑
ブラッド・ピットは、流石、ハリウッドのトップ層にいるという納得の演技力。見るだけで心動かされる。
マーゴット・ロビーは、あまり好きではなかったが、
だんだんと惹き込まれていった。あんなに魅惑的なダンスと表情ができるのかと思った。
終盤でやはり、マーゴット・ロビーだなって感じだったけどもう苦手意識は私の中でなかった。
サウンドミュージックも最高。
あとで知ったが「ラ・ラ・ランド」の監督だとか。そりゃ音楽に力いれててミュージカル風なんだなと実感。
初代スパイダーマンで有名なトビーマグワイアは 終盤あたりで出てくるレベル。私は出てくると知らなかったので見た時ビックリした。 スパイダーマンのイメージしか無かったから。
イカれ狂ってんのに最高に面白かった
汚いし、裏の世界満載の物語なのに楽しかった。
テーマはgood
派手!刺戟的!音楽良し!ただし胸焼けするかも。
欲望が人間をドライブする
ハリウッドによるハリウッドな作品
デイミアン・チャゼルという監督は正統派な作品を撮る監督だと思う。冒頭の乱痴気パーティーのシーン、ヴィスコンティの「山猫」の舞踏会シーンのオマージュだと思うのだが、頽廃的な要素が目一杯であるにもかかわらず、何故か明るく乾いた感じがした。暗さと陰湿さと変態さに欠けているのだ。ヴィスコンティが撮ると美しい舞踏会のシーンも何故か頽廃し、秘め事を盗み見する後ろめたさがある。チャゼルには後ろめたさがない。マーゴット・ロビーも明るい、底抜けに明るい。この作品自体が燦々と降り注ぐ陽光の中で撮られた全く後ろめたさのない青春映画のように思える。ハリウッドという場所がそうさせるのか?人間が本来持っている暗さにもスポットが当てられ、明るく照らし出されているのだ。度肝を抜かせるための汚らしく、際どいシーンも幾つかあるのだが、後ろめたさに欠けるため、ありきたりのシーンに私は思えた。ハリウッド黎明期から黄金期へと向かう歴史譚の中の悲惨な要素さえも明るく照らし出された大掛かりな青春映画だというのが私の忌憚のない感想だ。
デイミアン・チャゼルとは気が合わない。
デイミアン・チャゼルとは気が合わない。
ラ・ラ・ランドも苦手だし、ちょっと気が進まいと思いつつマーゴット・ロビーが素晴らしい演技をしてると聞き劇場に向かったが、やっぱり合わない。
確かにマーゴット・ロビーは見応えあるし3時間の長尺も別に良いが
マーゴット・ロビー、ブラッド・ピットを起用し
過去のハリウッドを描くとゆう共通点からどうしてもワンハリと比べてしまうが個人的にはワンハリの圧勝で。
映画のマナーを、映画オタクのマナーで塗り替えたのがタランティーノだと考えると
チャゼルは映画のマナーもオタクのマナーも無視して
好きなものを直列繋ぎで並べるぜって感じな気がするんだけど、たしかに映画は好きなんでしょうね。とは思うが、いろんな映画の直接的なオマージュ?パロディ的なシーンは全て下位互換な印象しか感じなく、映像としてもモサァっとしてみえるんですよね。
例えばラ・ラ・ランドのOPダンスもロシュホールの恋人達のOPダンスの方が圧倒的に気分が湧き立ち感動する。露悪的とも感じる馬鹿騒ぎダンスシーンもバズ・ラーマンの映画のわけわからんが圧倒的に上がる!みたいな混沌としたエネルギーが溢れてくるみたいなエモーショナルはないし…みたいな
ちょっと残念なオマージュを重ねられると、チャゼルが自分の好きな映画に雑に唾つけてるのを観てる感覚になって気分が下がっていく。今回の最後は尚更ですね。
私はオタク的映画好き世代なので、映画の引用って知ってる人が、あっコレはあの映画のあのシーンだなって目配せしあってニヤっと笑うぐらいの塩梅がクールだと思ってるからチャゼルの大胆オマージュはどうしても好きになれません。
しかも、チャゼルってけっこうゴリゴリの白人男性ヘテロセクシャルな感じなのに、クィア文脈に近い映画好きだよねって感じで
今回のバビロンは特にレズビアンや有色人種を題材に取り込んでるけどこのオマージュの仕方だと、とても表層的で文化盗用的とも感じることもできる気がして…余計にチャゼルよ…とゆう気持ちになるんですよ。
ただ、映画の引用が正しい正しくないとかはないと思うので好き嫌いの問題だと思う。
世界一魔法がかかった場所だからこそ、必ず魔法がとける…
ハリウッド黄金期、煌びやかな世界時代に抗えない人間の無力さと儚さを描いたちょっぴり切ないエンターテイメント作品。
いきなり⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎プレイの描写から始まるカオスでド派手な幕開け、煌びやかなパーティー。
ドラッグに裸で踊る女性や男性、人前で乱れて、交えてめちゃくちゃ。初めこそ頭が混乱するけど、いつしかこの世界観に夢中になっている自分がいる。
まるで魔法がかかったような場所・ハリウッド。この夢の地に憧憬を抱いてやってきたディデコ演じるマニーや、ブラピ演じる名優・ジャック、マーゴット演じる魅力的なネリーなど、それぞれの人生が回り出す。
夢中で追いかけた夢や希望、共に過ごした仲間、場所、そして愛した女性…
かつてあった物や人は時と共に消えてゆくけど、思い出とフィルムは色褪せることはない…。
ラ・ラ・ランド同様、ラストのシーンは目の奥が熱くなり、号泣。
こうして時代は繰り返されてゆくのだ。
栄枯盛衰、人生も映画も常々変わりゆくのだと。
記者がブラピに話すシーンでの記者のセリフが名言だらけだった(メモっとけば良かった)!
音楽がとにかく最高!ラ・ラ・ランドらしい音楽で、スカやジャズをベースにした曲に体が自然と波を打つ。この場で踊りたくなるほどに素晴らしい曲ばかり。
面白いの?
繁栄と衰退
映画が好きな人全てに観てほしい
1920年代のハリウッドを舞台に、
映画が無声から音ありに変わる転換期を
生きる人たちの話。
ド派手でクレイジーな演出・キャラクターと
素敵なジャズ音楽で3時間あっという間でした!
序盤のカオスっぷりは最高でした。
それだけで観る価値のある作品ですが、
1番よかったのは当時の映画業界を知れたこと。
どこまで忠実に描いてるいるかは謎ですが
撮影現場は、ルールや手続きなど全くない
めちゃくちゃな場所でした。
とにかく全員がむしゃらに映画に全力を注ぐ姿は
かっこよくもあり怖さも感じるくらい。
当時の人たちの熱がすごく伝わりました。
無声映画のスターたちが
声あり映画で苦悩を強いられる展開は
かなり驚きました。
よく考えれば分かることですが、
今まで声を出さなくてよかったのに
声の演技も必要になるのはかなりしんどい。
同じ俳優でも全く別の業界に転職するようなもの。
順応するものもいれば
順応できずリタイアするものもいる。
かなり厳しい世界だと思いました。
それだけでなく、映画の作り方も時代とともに
変わっていったのが興味深かったです。
映画を作るってものすごく大変だなと
改めて感じました。
シリアスなテーマではありましたが、
豪華なキャストと軽快な音楽で
素敵なエンタメ作品になってました。
映画が好きな全ての人に観てほしいです。
ラストの映像は圧巻です。
たとえ俳優、女優が生涯を全うしても映画の中に生き続ける。
ハリウッド版『カメラを止めるな』(打ち上げあり)
現場あるあるの物量、規模はハリウッド版『カメラを止めるな』
(打ち上げがハンパねーー)
とも言えなくもない。
さまざまな作品で描かれてきた、
社会、時代のアップデートの変革期に翻弄される登場人物たち。
サイレントからトーキーへ。
うまく適応していくジャックと、
適応どころか自由過ぎて、
ルールも守れないネリー。
その狭間の主人公マニー。
マニーはチャゼル本人の、
悩みや映画に対するスタンスも、
反映されているのかもしれない。
コンプライアンス等、
現場での周りの理不尽さ、
一歩先のアイデアなんて理解されないのは、
現場あるある。
映画にしたい事、
撮りたい事なんて、
ギャングの城の地下のように、
現代では映画にできない事ばかり。
トランペッターの顔に靴墨を塗る背景(当時は白人が顔に靴墨を塗ってパフォーマンスしていた。それにしてもアフリカ系の人に靴墨塗る!?ありえねー!これもコンプライアンス!って言われたんだろう。チャゼルはこのおかしなシーンをカットしないで、あえて残したのでは?)
象からの、豚への◯◯、
ネリーが発射する大量の吐瀉等、
観客が悲鳴をあげればあげるほど、
汚物から目を背ければ背けるほど、
大量の汚物が腹に溜まったチャゼルはスッキリするのだろう。
そんな言いたい事の数々を、
現場あるある風に数々の作品へのオマージュと共に無いようである物語は進んでいく。
ワンスアポンのハリウッド、
反コンプライアンスへの挑戦はソドム、
グッドモーニングバビロン、
スパイディーの顔の白塗りはベニスに死すか、、、
カメラを止めるな、、
そして・・・。
just singin' singin' in the rain
現実の周囲からの、
汚物の雨霰に降られながら、
時計じかけの、、、
いや、
キューブリックへのオマージュ、
そして、
ザッツ・エンタテインメント、
への、
リスペクトなのかもしれない。
薄い酒池肉林の表面だけはカメラに収めても、
酒の池の底に澱む人間の業や、
肉林の皮膚に蠢く匂いのようなものを、
描けない、
ハーバード出のボンボンが、
社会や時代にそんなに興味もなく、
MCUやDCEUのような凡庸な(ジャック曰く)作品(音楽やリズムでごまかせない、緻密なイメージ、技術が必要)のオファーにも乗れない、PTアンダーソンや、イニャリトゥのようになりたくない現状への嘆き。
それはまるで、
イニャリトゥにとって、
バルドが、
偽りの記録と一握りの真実であるように、
バビロンは、
チャゼルにとって、
偽りの記録と一握りの真実なのかもしれない。
以下鰐足、、、蛇足。
50年後、100年後を意識して、
映画の神様原理主義に走るか、
そこはジャックのようにならないよう、
ブラッド・ピットと、
よく話し合って、
『アリゲーター』とか
撮るのはどうだろう。
大傑作を期待!
アリゲーターなめんなよ。
噛まれるのはもっといや。
冒頭に出てた、
権利処理の関係で一部字幕無し、
というのは珍しい。
おそらく、
singin' in the rain。
作品自体はパブリックドメインなのに、
日本語訳が権利発生するかもしれない、、、
問題。
権利元がMGMのみで、
明らかだと権利処理すれば良い。
一般的に、こういうケースは、
権利元が不明とか、
権利元は明快だがグレーな組織とか、
契約書を交わしてないとか、
手が出せない問題が多い。
今回は、
パブリックドメインで、
作詞家との契約が不明、
作曲家とは問題なし?
やっぱりアリゲーター!
全318件中、201~220件目を表示