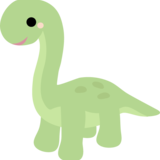ヒトラーのための虐殺会議のレビュー・感想・評価
全99件中、21~40件目を表示
ナチス(国民社会主義ドイツ労働者党)の支配下で結果ユダヤ人1100...
ほんまにしたんや。
我が我
恐ろしい映画
第二次世界大戦中に実際に行われたバンゼー会議の映画。こんな会議が行われていたなんて知らなかった。会社での会議のように、ユダヤ人を殺す方法を話し合う。ユダヤ人の命をまるでゴミのような扱い。参加者たちは殺されるユダヤ人よりも、処刑を行うドイツ兵の精神を心配している。銃殺は精神的苦痛が大きい。ならガス室なら一度で沢山殺せる。でも片付けが大変では?それはユダヤ人にやらそればいいではないか?どういう神経してるんじゃ!殺された仲間を運び出すユダヤ人達はどれほどの精神的苦痛があると思うんだ?まあ、ユダヤ人のことをゴミ扱いだからそんなことはお構いなし。「サウルの息子」を思い出す。
ナチスドイツの大虐殺は、「シンドラーのリスト」「サウルの息子」などなど、数多くあり、大量殺戮の場面や死体の山など観るのが辛いシーンは沢山ある。でも、この「ヒトラーのための虐殺会議」はそんな場面は一切なく、ひたすら話し合いの場面。殺し方を淡々と話し合う大人達。なのにものすごく恐ろしい。とても怖い。一度は観るべき映画だと思う。
事務会議に驚く
映画の役割の一つなのだろう
映画は、恋や夢、未来を語るときもあるが、歴史上の出来事を後世に残す役割を負うこともある。
『ユダヤ人問題の最終的解決』
と邦訳されている人類史上に残る汚点のキーイベント「ヴァンゼー会議」について、実に淡々と再現されている。
身の毛もよだつような会話が、高級将官、高級官僚たちにより繰り広げられる。
「労働力の維持」
「公民権剥奪」
「特別処理」
「ユダヤ人資産のアーリア化(略奪のこと)」
「疎開」
「強制断種」
「先の大戦(第一次世界大戦)の功労者の扱い」
「奴隷」
「人道的な方法」
「ドイツ人の精神の健康が心配」
「ユダヤ人は自業自得」
第二次世界大戦の終結から78年、ようやく、この歴史的愚行を描く″時″が訪れたのだろう。
この映画が公開された年に、パレスチナが戦場になったのは単なる偶然なのか??
この会議については、完全な議事録が残されていてニュルンベルク裁判でも貴重な証拠として機能したという。
会議に参加していたのは、狂人だったのか?
自分がその場にいたら、どうしただろうか?
多くの人に見ていただきたい作品だが、
見たことを後悔する人もいるだろう。
観る人に同情も共感も感動も求めない強烈な反ユダヤ主義、優性主義批判
このドイツ語の映画で、タイトルにあるヒトラーは登場しないし、現れる気配すらない。それでも登場人物の心を完全に支配しているヒトラーという圧倒的な存在感が終始作品の中に漂う。
さらにこのタイトルにあるユダヤ人虐殺(銃殺・毒殺)のシーンも連行のシーンなどの描写も全くない。それでもユダヤ人の強制収用や虐殺の残虐な実態が想像させられる。
この映画の舞台は、会議(ヴァンゼー会議)が開かれた邸宅(ヴァン湖畔)とその周辺数十メートル四方と驚くほど狭い地域だ。それでもユダヤ人問題と呼称する舞台の射程がヨーロッパ全土に広がっていたことを露わにする。
参加者は、ヒトラーを支える軍、親衛隊、主要省庁(国家保安部、内務省、外務省)の重鎮たちか。ユダヤ人迫害に対する良心の呵責が議論の中に垣間見られる程度のことを筆者は期待していた。しかしながらそんなせめてもの希望を見せることはなかった。若干ではあるが、前の大戦で祖国ドイツに貢献したユダヤ人に対する敬意が垣間見られた。その微かな人間味さえも、会議参加者ではなく、そうした気持ちを持つドイツ国民への考慮でしかなく、ユダヤ人に対するものではなかった。
会議は、戦争指導が必ずしもヒトラーの思い通りに進んでいる訳ではないことを伺わせる。実際に開催された1942年は東部戦線(独ソ戦)開戦後である。会議参加者の中からヒトラーに対する忠誠に動揺が見られることも期待したが、その期待も外される。程度の差はあれ、参加者の心は完全にヒトラーに支配されている。
この会議で静かながら意識的に強調されているのが書記の女性の存在である。参加者の発言を議事録として記録させる場面が再三入る。つまりこの女性は議事録の存在を象徴するものか。議事録はこの会議が歴史に刻まれたという証人になったが、参加者にとっては、この議事録を録っていることが会議におけるヒトラーを意識させる監視装置なのだ。会議のための静かな環境や豪華な食事が却ってその圧力の強さを引き立てる。全てが軍や親衛隊が経済的、心理的、時間的に効率的な方法で最終的解決を進めることに同意を取り付けるお膳立てなのである。
それでも参加者は、それぞれの異なる立場から時に穏やかに時に激しく議論をぶつけるが、欧州におけるユダヤ人問題の最終的解決 、すなわちユダヤ人を世界から完全に抹殺するという巨大な目標を達成することが、人類繁栄のために不可欠であり、その使命を誰も果たせていないし、果たそうとしないから、自分たちアーリア人(ドイツ人)が仕方なく実現に向けて行動していると思っている。彼らが議論しているのは、その遂行に当たって、さまざまな問題が噴出したからであって、円滑にそれぞれの管轄領域を相互に侵害せずに調整しているのである。
虐殺遂行に当たっての問題の捉え方も人道主義という言葉が出てくるが、遂行する軍や親衛隊のドイツ人の精神的苦痛に対する向けられるものであって、ユダヤ人に対して向けられてはいない。根底にあるのは揺るぎないドイツ人の優性思想とユダヤ人に対する差別意識だ。今もドイツにこうした思想を持つネオナチや極右と呼ばれる人たちがいる。こうした人たち目には、この会議は賞賛の対象として映ってしまうと危惧するのは、筆者の思い過ごしか。
この映画の舞台となる時期は、ヒトラーが出現した時代という特殊な環境が作り出したものだったと捉えるべきではないと筆者は考える。我々日本人のなかにも、周辺のアジアの国々とは日本は根本的に違うという考えはないか。かつて著作「学問のススメ」のなかで福澤諭吉は下記の有名な冒頭の主張から議論を展開する。
「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」といえり。(中略)されども今、広くこの人間世界を見渡すに、かしこき人あり、おろかなる人あり、貧しきもあり、富めるもあり、貴人もあり、下人もありて、その有様雲と泥どろとの相違あるに似たるはなんぞや。(中略)人は生まれながらにして貴賤・貧富の別なし。ただ学問を勤めて物事をよく知る者は貴人となり富人となり、無学なる者は貧人となり下人げにんとなるなり。
ところが、著作「脱亜論」のなかでは次の主張をしている。
「我日本の國土は亞細亞の東邊に在りと雖ども其國民の精神は既に亞細亞の固陋を脫して西洋の文明に移りたり然るに爰に不幸なるは近隣に國あり一を支那と云ひ一を朝鮮と云ふ」
つまり、いち早く西欧化に舵を切った日本は、中国や朝鮮とは違う、と断じている。この脱亜論がその後の日本の歴史にどれほどの影響を与えたかについての議論は他に譲るものとするが、優性思想が隠れていないか。
技能実習生として来日して、低賃金で過酷な労働を強いられていたり、高度な技術を要する仕事をさせずその技術の習得をさせようとしなかったり。近い将来に人口減少が予想ではなく、確定しているにもかかわらず、移民や難民の受け入れに高いハードルがあり、変わらない現状の根底に日本人の純血の防衛という優性思想は隠れていないか。
グローバルな人の流れは今では当然のこととして捉えられるが、そもそも人の流れは古代からグローバルであった。我が国も例外ではなかった。ただ徳川幕府の間、極端にその流れを断ち切った例外的時期が近代にあったことも事実である。このインパクトが過大評価され「独自性」が強調されすぎて来なかったか。
筆者を含めて日本人は歴史の教育の中で仏教、儒教、律令制、稲作などなど、政治・思想・文化のあらゆる分野で多くのことが大陸からもたらされたことを教わってきた。それは間違いでは無かろう。かつて、人やモノの交流が一方的な流れであるかのように認識されてきたが、今は双方向であったという捉え方をする方が自然になってきている。すなわち、遣隋使、遣唐使その他の交易などで大陸に渡った人たちも現地の政治・思想・文化に影響を与えてきたはずだ、という捉え方だ。
アーリア人という遺伝子の優性を盲信していたナチス政権下のドイツ人と移民・難民というグローバルな人々の交流という現実を未だ受け入れることに躊躇している日本人は、本質的に異なると明確に断じることはできるのであろうか。
意欲作ではあると思うけど…。
<映画のことば>
問題解決には悲劇も伴いますが、避けられないでしょう。ユダヤ人問題を解決するのに機は熟しました。後の世代には決断力も「本能の覚醒」もないでしょう。我々が重荷を背負うことで、あとの世代が幸せになるのです。
映画を観る立場からは、登場人物の会話からストーリーを読み取り、その場の雰囲気に入っていかなければならない作品ということでは、本作も、一種の「会話劇」と言えると思いました。
評論子は決して歴史問題には明るくはないのですが、作品の全体から察するに、この会議は、ナチス党側がドイツ第三帝国の官僚側との間でユダヤ人問題の「最終解決」について、その方針には理解を示しつつも、必ずしも乗り気ではない官僚側と最終的な合意形成を図るべく、ナチス党側が主導して開催されたもののようです。
ナチス党の方針には賛同しつつも、政治的な野心のない官僚側としては、自分の管轄範囲には余計な「厄介ごと」を持ち込んでほしくなかったというのがホンネだったのでしょうか。
そのような「温度差」を埋めて、最終的な合意形成を図ることが、ナチス党側としての、この会議の至上命題だったように、評論子には思われました。
もしそうだったとしたら、脚本の上で、そのような「色づけ」(脚色というほどの大袈裟なものでなくとも)がもっともっと前に出ていた方が、映画の観客としては、この会議にあたかも同席していたかのように、作品の中に入り込んで、会議の進行をリアルに体験することができたようにも思います。
<映画のことば>
「我が国の可能性は拡大の一途。下手に怖がって萎縮せよと?致命的な誤りです。さらなる飛躍を目指し勇気を持たねば。」
「戦争は障害ではなく好機です。戦争だから入れる場所もあり、個々の人間の悲劇に紛れ、事実を作ることも可能です。徹底的に介入し、壮大な構想で社会を形作る。シャベルを土に差さないと、農民も畑を耕せません。」
こういうふうに、政治的な野心で気持ちがいっぱいになってしまい、それ故に近視眼的な倒錯に陥ってしまった軍国主義者が、国民を戦争に駆り立て、敗戦という結末と国土の焦土化を招いたことは、同じだったように思われました。評論子には。ドイツでも、日本でも。
9歳でアイヒマン裁判を見たゲショネック監督の遺言でしょうか
見る人をものすごく選ぶのですが、良く練られた脚本で、緻密に撮られた群像会話劇(つまり会議劇)です。
会議の前から描くことで、職務上の地位、人となり、人間関係を説明しています。人数が多すぎて、それにドイツ人の名前が頭に入りにくくて、ハイドリヒやアイヒマンくらいしか結局分からないのですが、2度見ると、そのさりげなさから覗く巧みさに、ようやく気付けます。実際の議事録を元にした、という謳い文句はありますが、会議の上座下座をこっそり入れ替えるなんていうことは明らかな創作で、そんな些細な描写も、利己心が会議を動かしていることを象徴しているように感じます。
アイヒマンは言います。「私は、銃殺もガストラックも見ましたが、食欲がうせます」有能な官僚で、冷徹、非情なアイヒマンですら、食欲がうせるんだ、と驚きました。この人たち、議題に上がる法的な解釈や、効率性ばかりにとらわれて、全体像、つまり人殺しに関して話し合っていることを忘れているんじゃないの、なんて解釈もできなくはないのですが、それは違います。食欲がうせる惨状を、分かった上で議論を戦わせているんです。
私たちは、感情を理屈でコントロールします。また、慣れれば感情は摩耗します。そして、敵という言葉でくくれば、共感の対象から外せます。
その時代時代の価値観に基づき、合理性や理知的な判断を重ねた冷静な議論が、狂気を生み出しさえする。過去を振り返り、断罪することは簡単です。しかし、今の私たちがそうした誤った選択をしないようにするための確実な思考方法や、合意形成の方法を私は知りません。
平和と戦乱のきわどい均衡にある今の時代に、御年70歳のゲショネック監督がこの作品を問うたことを、私たちは重く受け止めなくてはいけないのではないでしょうか。
人間の怖さ。密室の怖さ。
人を人と思わない異常さ
第2次世界大戦時の1942年1月20日正午、ベルリンのバンゼー湖畔にある大邸宅にナチス親衛隊と各事務次官が集められ、「ユダヤ人問題の最終的解決」を議題とする会議が開かれた。最終的解決とはヨーロッパにいるユダヤ人を計画的に抹殺することで、国家保安部代表ラインハルト・ハイドリヒを議長とする高官15名と秘書1名により、移送、強制収容、強制労働、計画的殺害などの方策が異論なく淡々と議決され、1100万人ものユダヤ人の運命がたったの90分で決定づけられた、という史実に基づく話。
出席者たちがユダヤ人問題と大量虐殺について、まるでビジネスのように話し合う光景が異様なんだけど、会議の参加者全員がユダヤ人を人と思ってなくて、殺されるユダヤ人の事を心配する人は皆無。銃殺にしたら1,100万発の弾がもったいないとか、殺すドイツ兵の精神が心配だとか、酷い話だと思った。
作品自体は面白くもないが、史実を知る事の重要さを再認識出来る作品だと思う。
キリスト教徒にとってイエスを磔にしたユダヤ人は何年経っても許しがたいという事が背景にあるのだろうとは思うが。
静寂な事実
会議とはクソである
世の中の会議とは、ほぼすべてが苦痛であり、つまらんものだ。しかも物凄い金がかかる。
高給取りの高官や軍人の時間とその時間に見合う給料を考えたら、そりゃ凄いことになる。わざわざド田舎のヴァン湖のほとりの豪邸にお歴々がたくさんの部下を引き連れ、高級な旨い物とたくさんの雑用係を用意し、最低最悪の議題について話し合う。言葉に困ることだが、これほどのクソ会議がつまらないはずはない。クソであるがゆえに異様なスペクタクル性を備えたものだったに違いない。
クソ会議中のクソ会議、ヴァンゼー会議とはいかなるものだったのか?どんなクソ会議だったのか?
あのアイヒマンがまだ禿げる寸前の若かりし頃をロボコップのファーストのボスみたいな役者が演じており、まるでロボコップにちなんだかのようにロボットのように上官のいうことを素直に受け入れながら、会議は始まる。
出席者のなかには、文官がおり、ナチス政権以前の時代から、文官としての能力を買われ、ナチス政権後も権力をもっている人たちがいる。その人たちが、いろいろユダヤ人殲滅計画に突っ込みをいれる。ドイツの国益を考え、ユダヤ人の味方にみえる。ここが最大の見どころ。
人間の中にはまともな人もいると誰もが思いたいし、実際にそういう状態がぎりぎり維持されているから、ぎりぎり正常を維持できている。
そして、それら文官を応援したくなるし、頑張っているようにみえる。が、結果は誰もが知っている。この人たちに一体何があったのか?殺されたのか?
会議とはそれぞれが部分最適を目指す権力争いである。自分の利益やシマをあらされないように部分最適をそれぞれが図ろうと躍起になる。それは、このヴァンゼー会議でも変わらない。
やはり、会議とはクソ以外のなにものでもない。
官僚制や政治機構についての強力な著作を残した偉大な社会学者マックス・ヴェーバーがなぜドイツから出たか?行政や司法権力・官僚機構の病を小説にしたカフカが、なぜドイツ語圏から出たか?彼らはナチス以前からドイツの官僚や政治家が病んでいるとわかっていたに違いない。
目的と手段
目的と手段というのはなかなか簡単なようでいて、実は結構難しいものをはらんでいるように思います。大きな目的(ミッション・ビジョン・バリュー)のために、戦略が立案され、個別目標が決定され、その個別目標を阻害する要素があれば、それを洗い出し、それを効率的に解決する方策を探し出し、模索し、論議して決定する。
この映画で再現された会議を見ると、整然とした秩序のもとで、それらがある意味優れた形で、達成されていることに気づきます。例えばその労働力が目的の達成のために必要不可欠であるユダヤ人達の扱いをどうするのか?女性や子どもを含め一晩中大勢のユダヤ人を拳銃で銃殺したドイツ兵や将校の中に、精神に異常をきたす実例が出ている事を踏まえ、その精神的負担や物理的負担を軽減する「人道的」対応をどうするのか?そんな阻害要因が一つ一つ論議され、シュミレーションされ、理路整然と最適解を探すように、解決されてゆきます。(前者は利用しつくして最終処理する。後者はガス室に送り込む。)
問題はひとつ。
それは「大きな目的」がどうしようもなく誤っているということ。
「世界支配の権利を持っているのは疑いなくドイツ民族であるが、その最大の障害がユダヤ人であり、『アーリア人の勝利か、しからずんばその絶滅とユダヤ人の勝利か』の二つの可能性しかあり得ないとしている」ナチズムの思想(WIKIより)です。生物学的には差がないのに関わらず、フィクションのうえに壮大な人種の物語を作り上げるその醜い思想なのだと思いました。
「大きな目的」を誤ると、何が起こりうるのか?
そのことを、この作品は雄弁に物語っているように思うのです。
企業でも「パーパス経営」が叫ばれている昨今、「何が大切なのか」を改めて感じさせる作品ではありました。
組織の方針だから、、、
上の決定だからしかたない、、、
会社の方針だから従うしかない、、、
アウシュビッツ強制収容所を実際に見学に行った。
現地に行って初めてわかった事があった。
収容所ではなく、
列車で運ばれてきてそのまますぐに悲惨な事になるという事。
1時間に1000人の人を動かしていく、、、そんなノウハウが、現在の世界的人気企業の礎になっている事。
毒ガスのもとの顆粒が入っていた空き缶の膨大な数、
犠牲者の持ち物、髪の毛が、
そのまま残されている。
他にも衝撃的な事がたくさんあった。
そこでも思い出した。
自分は反対だけど、、、、
自分はおかしいと思うけど、
トップがGOを出しているので、
与えられた目の前の仕事を、
たんたんと進めるだけ。
効率的なアイデアを提案するぞ!
歴史は繰り返す、、、ではなく、
継続中。
蛇足
字幕に安易な酷い日本語を使わないプライドを感じました。
有能で凡庸な「悪」による戦略会議中継
本作にエンタメ性は微塵もなく、淡々と議論が進行していく。
おそらく当時のドイツでもっとも優秀な官僚、軍人たちによるトップの会議。テーマはユダヤ人の今後のホロコーストについて。
彼らの議論があまりにもビジネスライクなので、ホロコーストの恐怖感が全く伝わってこない。議論する彼らも目標の使命感に囚われ、立ち止まっての倫理観はそこにはない。人間としての想像力と共感力の喪失。
工程の分業化と不可視化によって、人間の道徳や尊厳よりも目標遂行の達成度合や効率化が重視されていく。リソース(弾薬)の確保と全ヨーロッパでの目標達成(約1千万人)の観点から、任務執行は銃殺からガス室処置へと大きく転換する。
そしてアイヒマンの冷徹な軍事官僚としての有能さが光る。まさに凡庸な悪の極み。
大昔のよその国だけでおこなわれた史実と捉えては、そこから何も学ばない。
全99件中、21~40件目を表示