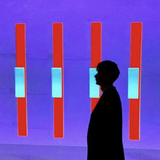ボーンズ アンド オールのレビュー・感想・評価
全88件中、21~40件目を表示
骨の髄まで僕を愛して
平凡な18歳の少女、マレン。
父親と二人暮らし。引っ越しが多く、この地も引っ越して来たばかり。
友達も居なかったが、親しくなった同世代の女子らに誘われ、父親に内緒でこっそり家を抜け出し、お泊まりへ。
楽しい時間も束の間、マレンが信じられない行動をする。
自分でも分からぬ衝動に駆られ、一人の少女の指に食らい付いたのだ…!
事情を知った父親はマレンを連れてすぐさま引っ越し。
一体、自分は何者…?
やがて父親にも捨てられ、残された出生証明書やカセットテープから初めて知る。
マレンは幼い頃から人食の嗜好があった…!
“カニバリズム”を題材にした衝撃作。
ホラー映画ではたまにある題材だが、本作もホラーテイストでありつつ、異色作。
父親に捨てられ(娘を育てるのに失敗したと自責の念から)、存在を知った母親を探す旅に出る。
一人の少女のアイデンティティーや彷徨を描いたロードムービー仕立て。
行く先々で出会ったのは…
ある町で声を掛けてきた一人の初老の男、サリー。
彼も人食者。初めて出会った自分以外の自分と同じ人。
人食者は普通の人や同族も食らう事あるが、自分は同族は食しないという。
マレンに同族の匂いや他にも同族がいる事、血の匂いなどを教える。
招かれた屋敷で瀕死の老婆を食らうサリー。
生きている人を食らう事に抵抗を感じるマレン。絶命してからはその衝動を抑えられず…。
食べた相手の髪の毛をコレクションしているサリー。
その異様さや不気味さに不快感を感じ、マレンは去る。
そんなマレンを見つめるサリー…。
また別の町。スーパーで店員の目を見計らって万引き中、横柄な態度の男の相手をする一人の青年。
スーパーから出た人目に付かぬ所へ。やがてその青年は口や身体中に血が。
この時マレンは“匂い”で分かった。彼も人食者。リーと名乗る。
彼と共に行動。
自分に近しい世代。彼も何処か自分と同じく、孤独や彷徨を感じる。
そんな二人の間に芽生え始めていく感情…。
この二人の出会いが本作の主軸と言っていい。
カニバリズム・ホラー×ロードムービーに、同じ秘密を抱える若い男女のラブストーリー。
ルカ・グァダニーノ監督とティモシー・シャラメの『君の名前で僕を呼んで』タッグが、まさかカニバリズム題材の作品を撮るとは…!
確かに際どい題材でグロい描写もあるが、それ見世物のゲテモノホラーなどは撮らない。(それが見たかった人には期待外れだろうが)
あの繊細な作品を手掛けた二人だけあって、本作も若者の葛藤や内面を瑞々しく描き取る。
そして今回も一筋縄ではいかない愛の物語。
美しい映像やセンスのいい楽曲も。
意外過ぎる題材ではなく、ちゃんとこのタッグならではの作風。通じる点もあり。
所々退屈や冗長も感じ、題材やグロ描写から好き嫌いは分かれそう。
多くの方はティモシーくん目当てだろう。またまた難しい役所を、色気や魅力、儚さや実力たっぷりに魅せる。
実質主役は、マレン。孤独や苦悩、複雑な内面…。リーに心惹かれる一人の少女として。己の運命と相対する。
これまた難しい役所を、注目株テイラー・ラッセルが熱演。大躍進。
若い二人の難演もさることながら、マーク・ライランスが不穏さと圧倒的存在感の怪演。出番は序盤だけではなく、終盤でも印象放つ。
道中、またまた人食者と出会う。サリーの言葉ではないが、同族は多くはないが思っている以上にいる。
その青年ジェイクから人食の中でも“フルボーンズ”の存在を聞かされる。人肉だけではなく、骨の髄まで食べ尽くす事。
人食に中毒なりつつあるリーにその傾向あると危惧。
旅の目的であるマレンの母親の元へ。そこは施設で、母親も人食者だった。自分で自分の腕を食らい、気も触れ、娘さえも食らおうとする。
ショックを受けるマレン。リーと思わず口論。
リーも家族との関係でぎくしゃく。
すれ違いから別れる。
リーは父親や妹と改めて対し…。
マレンもまた一人に。
その後再会。普通の人々と同様穏やかに暮らそうと始めた時、マレンの前にサリーが現れ…。
ずっとマレンを追っていたサリー。孤独だった自分に安らぎを与えてくれたマレンに横恋慕し、異様に執着。
襲い掛かられ、そこをリーが助けに入り、サリーを殺すも、リーも重傷を負う。
あまりにも深手。助かる見込みも薄い。
意識が遠退く中、リーは言う。
僕を食べて。骨の髄まで。愛しているなら。
一般の思考や常識では分かり得ない。
でももし、我々の常識を越える存在があるとしたら…?
我々の思考や常識では計り知れない形もあるかもしれない。
食らう。骨の髄まで。
それによって、君とずっと一緒。永遠に。
究極極限の愛の形。
これは狂愛か、激愛か、純愛か…?
彼の想いを受け止め、彼を我が身へ。
マレンのその後に思いを馳せられる…。
原作読み終わり
原作は父親探しの旅。旅の途中で出会う男2人組は出てこない。サリーはもっとマレンに影響を与えてくる存在。リーが決して主役じゃない、小説はマレンの青春物語といった感じ。最後は喰うことに躊躇しなくなる…喰いまくる。映画のマレンは喰うことに最後まで葛藤があるように見えた。映画はシャラメのリーを引き立たせて、たとえ喰われてもキラキラ青春純愛物に仕上げたといった感じ。
骨まで愛して
RAW少女のめざめ(2018)やぼくのエリ(2008)を思わせる。
世間から隠れ、人と違う体質に葛藤している。
人食はしたいが非道はしたくない。
とてもそういうものを描いているとは思えない語り口でもっていく。
同情しにくいが人食をとったら自分探しのロードムービーになっていた。
マレン役テイラーラッセルはジェナオルテガに似ていた。
サリー(ライランス)やリー(シャラメ)と道連れになったり離反したり、人食と自分の出自に納得のいく答えを見つけようとする。
思春期らしく乱れる心象が描かれ、なぜこれが食人ネタのホラーになっているのか不可解なほどの逃避と恋愛と青春のドラマになっている。
ふたりの無頓着な気配がいちばんの魅力。着のみ着のままであちこちを巡る。からだが訴えるフリーダム。適当な服装とぼさぼさの髪とシャラメのだらしない英語。New Orderがかかって眺望がひらける。謳歌される若さ。
さすがルカグァダニーノだと思った。
とはいえ食人と青春はアンバランスだった。
が、ラストでようやく腑に落ちた。
なるほど「骨まで愛して」と言いたいために恋愛を描いたのか、と。
まったく気づかなかったがこれは城卓矢の1966年のヒット曲「骨まで愛して」を映像化したものだった。
すなわち、愛する彼氏をフルボーンズしちまった少女の悲哀の物語。
愛しているからあなたを食べる──という究極を描いていることでRAWやぼくのエリというより大島渚の愛のコリーダに近い映画になっている。
──と考えたら笑うところじゃないのだがなんか笑えた。サスペリアもそうだがグァダニーノの何がすごいって与太話を壮大に語ってしまうところじゃなかろうかw。
思春期とカニバリズム
思春期とカニバリズムを合わせて描いた作品として、近年の「RAW少女のめざめ」と少し比較して観てしまったのだけど
(以下RAWの内容に触れるので注意してください)
両者とも、食人の衝動を血筋や遺伝的な継承があるように暗示されてるんだけどRAWはそのあたりがめちゃくちゃ上手くて(一人に焦点を当て切っているのもあるかもしれない)。遺伝的するとゆうことに納得度があったけど、ボーンアンドオールは、いまいち納得ができない部分があったり、食人が食欲なのか愛情の衝動と関連してるのか、何故同族は食べてはいけないのか(それが彼らの論理なのか、本能なのかみないなことが分からない)カニバリズムを扱ってるのに
何となくそのあたりがフワフワしてるのが気になる。
吸血鬼ものなのに、性質の設定があやふやだとなんか嫌だなってゆう感じに似てる。
遺伝することに感しての納得度が得られないのは、親子感の確執のメタファーとして食人を描いてる様に見えてたり
思春期もので、ロードムービーで、食人もあって、親子や家族の確執もあってなどなど盛り込み過ぎた結果、物語の強度が低い感じに仕上がってしまっている印象。
サリーの存在も少し意味わからなかったな、狂人的ピエロの様な存在なのは分かるし、行動に論理的な説明ができない人物として描かれてるんだろうけど話を無理矢理進める為に無理矢理いる存在のように見えて、何だかなとゆう感じ。だから落ちもね、なんだかな〜って感じ。
文字通り"骨まで愛して"のロマンチックな感じにしたかったんだろうなぁみたいな感想。
君の名前で〜のときも思ったがこの監督は
物語より気持ちいい決め絵や、空気感でいい感じに観せるのが上手くて
結果中身がやや薄くみえる作風なのかもと思う。
主人公のテイラー・ラッセルさんの世界に納得してない様な目や、少女と大人の間のような素朴なたたずいや、服のスタイリングと
80年代の様なノスタルジーのある風景が良かった。
シャラメもセクシー。
美しいぞ、これは。
俳優も雰囲気も悪くないのに、色々と残念
原作既読した者としての感想。
予告編の絵面や雰囲気、俳優は、原作の魅力をいい感じで体現してくれていそうだと期待したんだけど。観終わって残ったのは残念感のほうが強かった…
普通の人間の中に、なぜか生まれてしまうイーター=人喰いという忌まわしい存在。その人喰いである少女マレンが主人公だけれど、本作は、マレンと、同じく人喰いの少年の恋を中心に描いたが故に、恋愛ものとしてもホラー?としてもどっちつかずになったように思う。
原作は、マレンが人喰いであるため実の母(映画ではなぜか父に変換されてる)にも疎まれて見捨てられ、ひとりで生きていかざるを得なくなる。その設定は映画でも変わらないが、何が違うといって、マレンが人を食べるのは、自分に対し好意や愛情を寄せてくれて、かつ、自分もその人に惹かれた相手に限られる、という重要な設定が映画では失われている。つまり、自分が誰かを好きになればきっと人喰いの衝動を抑えきれず殺してしまうから、マレンは人と親密な関係が築けない。この上ない孤独を抱えてしか生きられない少女なのだ。
その彼女が、人喰いの少年と出会って惹かれあい、いったんは別れてもまた二人でいることを選んだ時に起きる出来事が、マレンの生き方を定める。つまり原作は恋物語ではなく、マレンの辛い成長と自立の物語なわけで。美しくも哀しく、恐ろしい捕食者として歩き出すマレンを、映画でも描いてほしかったなあ。そうすれば、少年リーを演じるティモシー・シャラメの繊細な美貌は、マレンへの供物としていっそう輝いただろうに。
原作と映画は別もの、とわかってはいても、やっぱり残念なものは残念だし、たとえ違うものになるとしても、違う魅力を見せてほしいと思うのですよ。
人を喰って愛を貫く二人
人喰い族というホラー映画然とした要素が売りの作品であるが、本作はただそれだけの作品ではないように思う。そこにはマイノリティの苦悩が隠されているような気がした。
マレンやリーのカニバリズムの衝動がどこから来るものなのか。それは映画を観終わっても良く分からなかった。ただ、遺伝が関係していることは明確に示唆されており、そこには抑圧されながら生きる被差別民の姿が投影されているような気がする。
また、食人の衝動はここでは恋愛の衝動に似た意味で語られているような気がした。
例えば、それは同族を匂いで感知するという彼らに特有の本能からもよく分かる。これはオスとメスが放つ”フェロモン”に近い生理的現象なのかもしれない。
また、彼らは生きていくために我々と同じように普通に食事をするが、人肉を喰うと特別な興奮と快感が得られるということだ。これはセックスの快感に割と近いものなのかもしれない。
こうしたことを併せ考えると、マレンとリーが惹かれあっていく今回の物語には”性的少数者”の苦悩が何となく透けて見えてくる。
人種差別やLGBTQ等、本作は深読みしようとすればいくらでもできる作品であり、単にホラー映画という外見だけで捉えてしまうには惜しい作品のように思う。物語の根底に忍ばされたメッセージを汲み取りながら観ていくと大変歯ごたえが感じられる作品である。
ただ、寓話としては面白く読み解ける作品なのだが、このカニバリズムという設定はやはり余りにもインパクトが大きい。それゆえ、どうしてもその意味については解明を試みたくなる。
しかして、本作はその本質に迫れているか?と言えば、自分はそこまでの深淵さが感じられなかった。どうしてカニバリズムなのか?その真意が読み解けなかった。
本作にはヤングアダルト小説の原作があるようだが(未読)、そちらにはマレンたちが食人になった経緯などは書かれているのだろうか?
監督はルカ・グァダニーノ。展開で首を傾げたくなる個所が幾つかあったのと、マレンの父親が残したカセットテープが余り上手く活用されていないことに不満を持ったが、演出は概ね安定しているように思った。リメイク版「サスペリア」に続き奇しくもホラー付いているが、見せ場となるようなビジュアル・シーンは前作ほどの刺激性はないものの、作品のテーマとしては十分に野心的で先鋭的で、改めてこの監督の独特な作家性には魅力されてしまう。
キャスト陣では、どうしてもリーを演じたティモシー・シャラメに目が行ってしまうが、サブキャラにも魅力的な俳優が揃っている。
特に、マレンが最初に遭遇する同族のサリーを演じたマーク・ライランスは印象に残った。自己の中に人喰いの自分とそうでない自分を抱えた精神分裂症気味な怪演がインパクト大である。
また、マレンたちに骨まで喰う恍惚感を嬉々として語るマイケル・スタールバーグ、マレンの母親を演じたクロエ・セヴィニーも少ない登場ながら印象に残る演技を見せている。
咀嚼するのに時間がかかる
稀に、咀嚼しきれない映画を見る事がある。まさに今回の映画はその類のものだった。想像しやすいストーリー、演技派ぞろいのキャスト、観客の情感を煽る数々の旋律。計算されつくされた美しさは、一見チープとも言えた。けれど、飲み込めない。心のどこにもつっかえないままに、映像は流れていった。
もちろんそれだけと言えばそれだけなのだけど。同じ監督の映画を見た際に似たような感情を抱いたので、少しこの気持ちを解きほぐしてみようと思い文字に書き起こしている。
人をくらうという事を軸としたこの映画は一体観客に何を投げかけているのか。正解のない日々にもがきながらも微かな幸せを、大切に大切に抱きかかえながら過ごす日々。その刹那の瞬きの中に何が隠されていたのだろう。
人は常に何らかの欠陥を伴い、孤独というものに鈍感であり、敏感だ。
一度自らの不足分を知ってしまったら、孤独に気づいてしまったら、あっという間に均一だったはずの世界は崩れてしまう。もう過ぎ去りし日々の思い出は散々に砕かれて、かき集めた愛しい日々はどろりどろりと指の隙間から滴り落ちていく。
脆くて愚かな人間は、ここでどうしようもない矛盾を抱える。
美しく生きたい。醜く生きたい。それは生に対するどうしようもない憧れと執念が生み出した魔物だ。誰しもの心に巣くうおどろおどろしく、気高い魔物。
私達はその片鱗を映画の中に垣間見たのではないだろうか。
骨ごと食いつくしてしまうことで得られる恍惚感。後には何も残らない。
白いシーツは真っ白で、風で柔く揺れる草原はおぼつかない。それが幻であれば。それが私の一部であれば。私はもっと強く生きていけるだろうか。この矛盾を愛しいものであると認めれば、もっともっと、私は美しくあれるだろうか。
これが私なりの映画の解釈だ。
最後の自問に対する答えはない。それは、これから生きていくうえで見つけていきたいことだ。
hungry like the wolf
これは好きだった
凄い役者揃い
骨の全てまで
結構好きだった。
この監督が映し出す"人"は本当に綺麗。
アメリカの田舎町に映る、社会からはみ出た2人の逃避行。その随所で切り取られる2人の表情が凄く印象に残ってる。
テイラーラッセルの現実を知った哀しみやときたま見せる本能的な表情。ティモシーのどこか幼さを感じさせつつも、重たいものを経験した上でのやるせなさ。
そんな負の感情の中で、2人が惹かれ合うなかで見せるあどけなく光を感じるような瞬間。
そのときどきで見せる表情が、背景と音楽と(あとだいたい車と)合わさってグッと心に何か訴えかける。
社会の中で孤独感を感じ、それでも生きていく。
背負ったもの・経験したものの重さはけっして1人ではかかえきれない。サリーや母親のように。
お互いを補完するかのように惹かれあって、
骨まで全て愛してる。
人肉食というかなりハードなテーマだけれど、
移り行く心情変化と、純愛の中で、ホラーにはし得ないどこか爽快感をも感じる、そんな後味がした。
ティモシーシャラメ
本能から
普通ってなんだろう?
ヴァンパイヤや人狼のアレンジかな
ティモシー・シャラメを観に行っただけなので、内容への賛否両論云々はどうでもよくて、「もうちょっとシャラメのカッコいいシーンを増やして欲しかった」という感想がまず真っ先にw
基本、世の中に受け入れられないマイノリティとして「人喰い一族」の設定を出しているのかなと。
ヴァンパイヤや人狼と変わらない、人間の命を糧に生きる魔物みたいな扱いですが、それらは現代ではもはやファンタジーとして定着してしまい陳腐さすらあり、ホラーになりにくいので、こういう風にアレンジしたのかと理解しました。
そして、この設定だと、「死んだ相方を食べること」がセックス以上の「一つになる恍惚感」をもたらせるわけで。
いろいろあざとさも感じてしまいました。
まさかカニバル映画で感動するとは…
ホラーではなく人食いによる純愛ロードムービーといったストーリー。
R18でゴア描写もしっかりあるが、ティモシー・シャラメの美しいビジュアルによって緩和されているのか鑑賞していて苦にはならなかった。
この作品は人食いを社会的マイノリティーとして描いていて面白い。
人を食べたいと思う衝動や食べることに対する苦悩が丁寧に描かれているので、だんだんと人を食べる人もいるのかと途中からうっかり受け入れてしまった。
ラスト リーがマレンに向けて言った「骨まで全部食べて」という台詞でタイトル回収。
ラストでしっかりタイトルの意味を回収し、またその行為が人食いにとって愛情表現の最上級の行為だと気づいたとき、妙に感動してしまった。
同族は食べないとタブーにしていた行為を最愛の人にしなければならないマレンのつらさ。最愛の人にだったら食べられてもいいと思うリーの愛。
マレンが泣きながらリーを食べるシーンはおぞましいのに、確かな愛がある感動シーンになっていた。
全88件中、21~40件目を表示