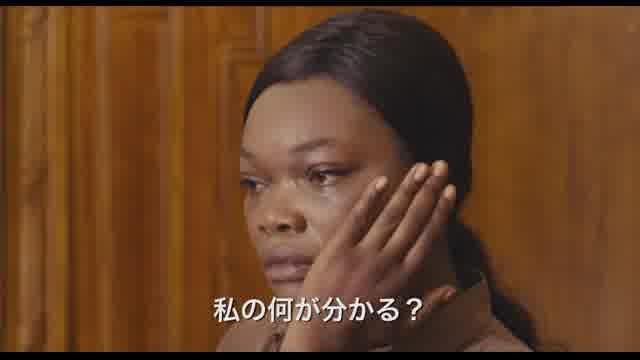サントメール ある被告のレビュー・感想・評価
全32件中、21~32件目を表示
個人的には今年上半期ダントツのヘビーな作品
行間のものすごく広い散文みたいな,観るものの想像力を試す作品。
様々な少数派・非主流派に対してさりげなく居場所を提供するのが成熟した社会だと思うが、多くの国で異端者排除が無くならない、という現状を突きつけられる。この社会を構成する人々は自分たちが期待しているほどはオトナではないということか。
ロランスは当初から出身・人種・性別の異端三重苦を負わされているだけでなく,毒親の(無自覚な)圧力,パートナーからのあの仕打ち,そして味方だと思っていた人の裏切りを受けた挙句,あの病的な無表情や一貫性のない主張,さらにもちろんあの凶行に逃げ込まざるを得なかった痛々しさはちょっと比類がないかもしれない。居場所が与えられなかった故の悲劇。
観たい度◎鑑賞後の満足度◎ 裁判も終盤に差し掛かる頃静かに感動が込み上げ涙が出てきた。何故だ?頭ではまだ理解しようと奮闘中だったし、母と娘なんて分からない事だらけ…きっと心が先に感動したのだろう…
①本作における映画の中の“映画の記憶”としては『ヒロシマモナムール(邦題:二十四時間の情事)』と『王女メディア』。この2作を観ることで本作を完璧に理解することは出来ないだろうけど、映画大好き人間としては観なくては!(恥ずかしながら2作とも未見)
②嬰児しかも我が子殺しなのだから本人も認めている以上、法治国家としては有罪になるのは当然。(フランスの法制度も知っとくべきだろうけど)
それ故本作は有罪か無罪かを争う法廷劇ではない。判決さえ示されない。
本作の肝は、どのような罪に問われるかということではなく、あくまで何故「我が子を殺めなくてはならなかった」のか、真実は何だったのか、ということ。
ところが、その真実も示されない。観ている者の想像・推理・解釈に委ねられている。
弁護士の最終弁論がそれを語っているようにも思えるし、それを聞いて被告は泣き崩れるが、あくまであれが本作の結論だとは思えない。
弁護士の弁論の中に、母親と子供の結び付きの不思議さの論拠として“胎児から母親に移る”キメラ細胞(正確には「マイクロキメリズム」というらしい)に触れているが、まだ現時点では医学的にはそこまでの証左にはなっていないみたいだし。
③弁護士だから被告に有利なことを言うのは当然だから、弁護士の弁論を鵜呑みにするのはどうかとも思うし、被告自体が証言をコロコロ変えるうえ“記憶にありません”とかしょっちゅう言う(まあ、弁護士が言わせているのかも知れないし、前言を翻したり証言を変えるのはよく有ることだし、某国の国会議員の先生方もしょっちゅうしているし)
被告台で“何故娘を手にかけたのか分からない。この裁判でそれを知りたい”と言ったのもある意味真実かもしれない。
優秀な彼女ですら(いや、だからこそ?)自分のなかで整理できてはいなかったのかも知れないし、本当は分かっていても認めたくなくて他の原因(になるかもしれないものを)を心の中で必死で探していたのかも知れない(これは実体験から)(まあ、彼女のしたことは取り返しのつかないことだけれども)。
それより被告席の被告が傍聴席にいるラマに向かってうっすらと笑みを漏らしたところが気になる。
まるでそれを目撃させる為にラマというキャラクターが必要だったみたいに。
それを目撃した後ラマは取材を放り出しそうになるくらい取り乱すし。
ラマ(とその姉妹たち)と母親との関係についても映画は明快な描き方はしていない。
全編まるで母と娘、女性にしかわからない暗号が張り巡らされているようだ。
④母国では高い教育を受け、それに値する優秀な人材だった被告。また、それ故に両親の期待が高く、それが重荷となっていた被告。
その重荷から逃れるためにフランスに来たのに、最初に頼った叔母さんとは間もなく上手くいかなくなり、親からの送金も途絶え(重荷から逃れても自立を目指した訳ではなかったようだ)、子守りを始めたが(雇い主は優秀な子守りだったと言うし、本人も子守りは合っていたと言うが、自ら勉強も出来て優秀だと言う被告にとっては屈辱的な仕事だった筈)やがて雇い主とも上手くいかなくなり(人間関係はあまり上手ではないようだ)、そのうち妻子のある男の愛人となり妊娠してしまう。
優秀な筈の勉学でさえ大学に行かず試験も受けず修士号も取れなかった。
誰もが言うように正しいフランス語を完璧に話せるということはかなり優秀な証拠だが、一方大学の教師の証言では書く方は話す程には完璧ではなかったようだ。
フランスに来てからは屈辱・恥辱まみれになり自分は呪われていると思いたくなるのも分からなくはない(日本で言えば前厄・厄年・後厄だと言っているようなものか?)。
妊娠したのも本当に偶々だったかも知れないし、本当にその時は相手の男の子供が欲しかったのかも知れないし、男が「陥れられた」と言うように欲得ずくだったのかもしれない。
相手の男も“愛していた”と言うかと思えば彼女の存在を隠していたし、“三人でいた時が一番幸せだった”という割には子供は認知していないし、随分胡散臭いけれど。
⑤裁判での色々な証言を聞いていると『王女メディア』のように不実な男への腹癒せに子供を殺したようには思えないけれども、「大きくなると邪魔になるから死なせた」という被告の言う通りかも知れないとも思える。
異国で知り合いもなく頼るものもなく、大きくなっていく一方の子供を抱えて生きていくのは確かに悪夢かもしれない。
一方彼女には自分は優秀だと言うプライドもあり、これ以上屈辱と恥辱にまみれた人生は送りたくないという思いか、或いは絶望の末最も恥辱に満ちた選択を敢えしたのか?(彼女くらい優秀であれば子殺しをすればどの様な罪に問われるか分かる筈だし)
⑥本当に母や女性というのは男にとっては死ぬまで分からないものかもしれない。
それでも魂を打つものがここには確かにある。
⑦アメリカのスタンダードナンバー(いわゆる懐メロ)である『Little Girl Blue 』が流れてきたのには少々驚いた(初めは何かのシャンソンかと思ったくらい)。
座って自分の指の数を数えるしかない、自分に降りかかってくる無数の雨粒を数えるしかない“Little Girl Blue”は被告の事なのか、広く女性の事なのか?
歌詞の最後:
“No use old girl
You might as well surrender
‘Cause your hopes are getting slender and slender
Why won’t somebody send a tender blue boy
To cheer up little girl blue”
をどんな想いで聴けば良いのだろう…
リトル・ガール・ブルーが心地よく流れる
子殺しと言えば、
ギリシャ悲劇王女メディアとなり、
マリア・カラスが忘れられない。
この女性心理が分からないと、
女性ばかりの法廷で、
男性ばかりの参審員と言えど真理は審判されないのが欧米か?
でも、その決め手はキメラで決まったか?
完璧なおフランス語が出来ても、
中味はセネガルの未体験の孤独な女の子。
それにしても、
リトル・ガール・ブルーはいい歌だった。
そう言えば、
主演の女の子は、ニーナ・シモン似だなぁ
( ^ω^ )
我が子を殺した罪に問われた女性の裁判の行方を実話を基に描き、
2022年・第79回ベネチア国際映画祭で銀獅子賞(審査員大賞)と新人監督賞を受賞した法廷劇。
フランス北部の町サントメール。
女性作家ラマは、
生後15カ月の娘を海辺に置き去りにして死亡させた容疑で逮捕された若い女性ロランスの裁判を傍聴する。
セネガルからフランスに留学し、完璧なフランス語を話すロランス。
被告本人や娘の父親である男性が証言台に立つが、真実は一体どこにあるのかわからない。
やがてラマは、偶然にも被告ロランスの母親と知り合う。
「私たち」などのドキュメンタリー作品で国際的に高く評価されてきたセネガル系フランス人監督アリス・ディオップがメガホンをとり、
作家マリー・ンディアイが脚本に参加。
「燃ゆる女の肖像」のクレール・マトンが撮影を手がけた。
ブルー
生後15ヵ月の娘を殺した女性の裁判の様子をみせる法廷劇…かと思ったら浮かない顔をした傍聴人の女性作家ラマの話?
確かに法廷での供述の様子が8割ぐらいを占めているけれど、コリーを見せたいのならラマは余計だし判決やその後の字幕すらないのは訳わからんし、ラマを見せたいのなら回りくどいし結局はっきりしないし、まあ両方見せたかったんだろうけれど中途半端でボケ捲り。
都合の悪いことは語らなかったり平気で嘘をついたり翻したり、後悔も反省もなく胸クソ悪い感じは良かったけれど。
科学じゃなく詩に感じる自分にはその演説も響かず、淡々としたコリー1本に絞ったら良かったのにという印象で、いずれにしても参審員の抽選や紹介はいらんかったなと。
呪われた血?負の連鎖?
一定の法律の知識は要求されるので注意(映画内で触れられていない結末等、補足入れています、ネタバレあり扱い)
今年240本目(合計891本目/今月(2023年7月度)26本目)。
(参考)前期214本目(合計865本目/今月(2023年6月度まで))。
※ おことわり: 本映画の趣旨として、「描写が中途半端で終わる」という事情があるため、大阪市立図書館等で調べた内容を追記しているものであり、個人攻撃(特に、被告の女性に対するもの)を意図したものではない点は書いておきます。
さて、こちらの映画です。
ほぼほぼ9割裁判所での話になりますし、そこで交わされる内容は、ある罪に問われた(この点、あとで補足)女性との第一審を描いた映画です。
その結果、一定程度(日本の刑事ドラマ等を超える程度)の法律の知識(ほぼ、刑法と刑事訴訟法)の知識が要求されるのが厳しいです。映画内では明確に法律ワードこそバンバン飛んできませんが、暗黙のうちに出てきたり前提にされている部分もあります。ただこれを学習する機会があるのは司法試験(予備)だけで、そこまでの知識があるリアル視聴者は超レアで、どういっても行政書士資格持ち(行政事件訴訟法のみ学習。要は、裁判所の手続きに関するルールの一類型を把握している、というもの)が事実上上限になるんじゃないかなぁ…といったところです。ただ、「深い理解」をするならそれが必要であるだけで、法律ワード「それ自体」はほとんど飛んでこないので、理解うんぬんを別にすれば、一応にも「みやすい」映画ではあります(これが「極端に」厳しかったのが「シャイロックの子供たち」で、抵当権抹消だの何だのマニアすぎる語が飛んできてビビった…)
映画の描写としては、どうしても存命している人物である以上、あまり深くあれこれあることないことかけず、妙なところで終わる事情もあり、その事情を知らないと、本当に珍妙なところで終わるので???な展開になりかねず、ここはうーむといったところです。最低限必要な知識だけは後に入れておきます。
採点対象として気になったのは以下の通りです。
------------------------------------------------
(減点0.3/タイトルがやや不正確)
・ 「日本でみる場合」、民事訴訟の相手方は「被告」、刑事訴訟の相手方は「被告人」であり、この2つは違います(「人」のありなし)。本当に細かい点なのですが、日本で見る場合、刑事訴訟法を想定してみるしかないため、この違いは民事で争うのか刑事で争うのかの理解のハマりにつながるので(ただ、展開的に民事でないことは明らか)、少し工夫が欲しかったです。
------------------------------------------------
(減点なし/参考/映画のそのあとのお話) ※ 情報ソースは大阪市立図書館ほか
映画内ではおそらく個人の尊厳を尊重して結末がぼかされていますが、当時のニュース報道、新聞報道(日本ではほとんど放映されていない)によると、2016年6月に「心理プログラム受講を義務付ける懲役20年」の判決となっています(海外の新聞ほか)。
※ 日本では、同じ類型の事件は、主に保護責任者遺棄致死になりますが、この類型で無期懲役になることが考えられず(ただ、フランスでは無期懲役がありえたとのこと。当時の刑法)、そこは日仏の違いなのかな、とは思えます。
判決文(第一審で確定?)は読もうと思えば読めるようですがフランス語なので当然厳しいです。ただ海外でも注目を集めた事案で、「アフリカからの渡仏者で、支援を得ることができなかった」「被告人の発言に多少なりとも不自然な点があり、弁護士が主張するように何らかの教育的プログラムを受けさせるのが適切」という点が判決に考慮されたようです。
また、第一審の裁判所等の判断によれば、「渡仏した事情があり、会話において、会話で使う語彙とレポート等で使用する語彙の区別がついておらず、裁判官も一般市民(いわゆる、日本でいう裁判員制度のそれ)も理解が困難だった」(このことは、渡仏に限らず、日本語学習者でも生じえます)といった「裁判において正常な主張ができなかった可能性がある」点が考慮された一方、「フランスの地域ごとの潮の満ち欠けの表(日本では、理科年表等が該当)を所持していた」点が認定されていて、上記のような判決になったようです。
なお、映画と実際の裁判では当然登場人物が異なり、映画内では女性の方が妙なまでに多いのですが、この点は「たまたまであり、何らかの意図があるものではない」ようです(仏版公式サイト等に言及あり)。
【”仏蘭西の中に厳然として有る意図せぬ黒人差別を描いた作品。そして、母と娘の本質的な関係性を描いた静的な法廷劇をメインにした作品でもある。そして、そこから見えてくる現実を考えさせられる。”】
ー 印象的なのは、今作の法廷に登場する人物は、生後15か月の娘の殺人罪に問われた若き女性ロランスと、彼女の母。そして、女性作家ラマ以外は、裁判長、弁護人、検察官や聴衆を含めて全て白人であることである。
これは、アリス・ディオップ監督による意図的なキャスティングであると思う。
更に、資料によるとアリス・ディオップ監督の母親が、事件を新聞で知り、サントメールで開かれた裁判を傍聴した際に、白人たちから背を向けられた経験も取り入れているそうである。ー
◆感想
・裁判シーンが8割を占めるが、ロランスを含めた証言者たちの証言内容がコロコロ変わる事に、やや戸惑う。
・ロランスは、殺害理由を問われ
”娘を海岸に置いた。けれど、私に責任があるとは思えない”と言い放つし、ロランスの夫の歳の離れた初老の”白人男性リュック”は”娘が出来て嬉しかった。”と言うが、ロランスは”彼は、大切な場にも私を連れて行かず、紹介もしなかった。”と述べる。
ー 推論だが、ロランスの夫リュックは、ロランスを内縁の妻として扱っていたのではないかと思う。故に、世間体を考え、親類に正式に結婚したと紹介をせず、娘が生まれた時も”本当に私の子か?”などと狼狽して言ってしまったのではないか。-
■仏蘭西の中に有る意図せぬ黒人差別
・いろいろなシーンで感じられるが、一番分かり易かったのは、ロランスがセネガルから希望を持ってやってきたのは、ウィトゲンシュタインの哲学を学ぶためであった。
だが、ある女性大学教授は笑いながら
”セネガルから哲学を学びにやってきた?あり得ないでしょ。”
と証言台で宣うのである。極、自然に・・。
ー これも、推論だがロランスは仏蘭西に来てから、あらゆる文化の壁、黒人差別を経験し、更に望まぬ妊娠をし、全てに絶望していたのだろうと思う。
セネガルからの仕送りも途絶えて・・。
故に、女性弁護人が彼女に掛けた言葉を聞いて、法廷で初めて泣き崩れたのであろう。-
・証言者の中には”フランス人化が成功の鍵。彼女のフランス語の発音は完璧だが、筆記が未熟”と答える女性もいる位である。
・今作では、女性作家ラマとロランスの母親との関係性もキーである。法廷で初めて会ったにも拘らず、翌日には一緒にランチをし、ラマは”妊娠しているでしょ”と誰にも言っていなかった事をズバリと言われて、うろたえる。
更に、裁判中、常に不機嫌な表情だったロランスが、ラマと目が合った時だけ笑いかけるのである。
<今作は、容易な作品ではないが”仏蘭西の中に有る意図せぬ黒人差別”の数々を暗喩させるとともに、母と娘の複雑な関係性も描き出している。
ラスト、ラマがソファで寝ているロランスの母親の寝顔を見ながら、優し気に手を握っているシーンが印象的でも有った作品である。>
苦手
繊細なテーマを力技で繋げた一作
すべての娘と母親へ
母親が重たい。娘に向けられる期待、抑圧、敵意、嫉妬、疲労感、鬱。そんな重圧に苦しんだ娘たちはそういう母親にだけはなりたくないと思う。にもかかわらず自分の中に大嫌いな母親のひと切れを感じて娘は絶望する。もし母親からの重圧を一切感じなかった娘がいたらその人は幸せだ。
マルグリット・デュラスの「ヒロシマ・モナムール」は知らなかったからデュラスの「ラ・マン」を思い出した。フランス領だった頃のベトナムで白人フランス人の少女と中国人男性との愛人関係を描いた小説。
ラマが素っ気ないホテルの部屋で自分のノートブックで見るのはパゾリーニの「王女メディア」の一部。王女メディアは自分が生まれ育った土地の宝である金羊皮を愛する男に渡す。でもその宝を男はないがしろにする。メディアは全てを失う。自分の王女としてのアイデンティティも男からの愛も失いよその土地で孤立し悲しむ。孤独に陥ったメディアは、その夫との繋がりを全部捨てることにした。だから愛する子も殺す。その子ども二人とも息子だったからと私は思った。娘だったらどうだったろう。
インテリのロレンス被告。母親も父親も叔母も母国セネガルもロレンスをもはや受け入れない。希望に胸をふくらませて向かった留学地フランスで自分が見えない存在にされていることにある時気がつく。同棲相手のフランス人白人男性からも大学からも。大学教授の法廷でのことばに私は怒りを覚えた。アフリカ人だから、肌が黒いから、女性だから?なぜウィトゲンシュタインの研究をしてはいけないのか!親たちからは法律を学べと言われていた、なぜ哲学を専攻してはいけないのか!
法廷の中の裁判官や弁護士の大半が女性であることに驚いた。医師も教師もヨーロッパでは女性の職業だ。いつになったら日本もそうなるのか。
疲れた・・・
リアルながら法廷を再現しようという意図・演出で、被告、弁護側・弁護側、裁判官、それぞれの主張や語りが長回しでつながれいるため、かなり根気が要りました。参審員の選出などもあるので・・・でもそこの部分はかなり根気興味深く見入りました。
内容も非常につらくどんよりとしているので、正直集中力が続きません。
終わり頃には意識を失いかけていたのですが、ニーナ・シモンの歌声に救われました。その部分だけ、なんか異様に演出が違っていて、ものすごく吸引力があって・・・もっとこういった演出があっても良かったのになぁなんて思ったり・・・
ちょっと話はずれるけど、ニーナ・シモンのドキュメンタリーとかを見ていたせいで不思議と彼女の過酷なる人生と重なるところを垣間見て、勝手にぐっときていましたが、それも意図があっての演出なのかどうかは分かりません。
非常に真摯で誠実な作品で、敢えて堅く・難しく作られている印象でした。後半のようなソフトに感覚的に響いてくる演出がもっとあったら、見やすかったような気がするのですけど、それでは作家魂が許さないといったところでしょうか─あくまで夢想です。
全32件中、21~32件目を表示