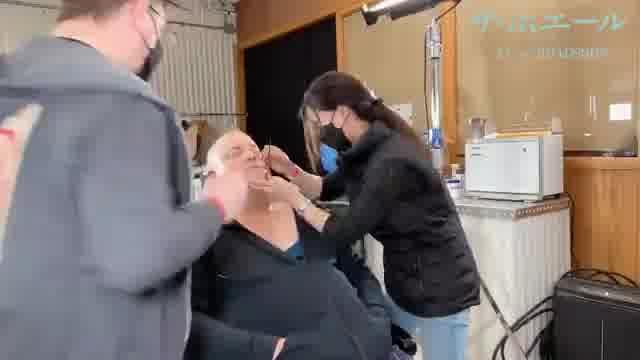ザ・ホエールのレビュー・感想・評価
全257件中、121~140件目を表示
どう捉えれば良いんだろ?
登場人物が少なくてシーンの展開が少ない点が非常に見やすくて良かった。昨今のMCU映画ばかり見ていたので、シークエンスが少なくて本当助かりました。あとストレンジャーシングスのマックスが出てビックリしました!「あれっ!?•••マックスじゃん!」って叫びました。
そんな中で、現実のストーリーと白鯨の物語が並列して進んで行きます。鯨はおそらく主人公の巨漢ニキだろう。それは自分も理解でしました。
無茶苦茶なことやって生きたチャーリーが、家族を裏切って不摂生をしてるのに、みんな捨てきれず寄ってくる。「人間は美しい」と言っていたが、人間臭い矛盾に満ちたこの巨漢ニキの生き様が、人を惹きつけてるのでしょうか?
自分でも抑えられない食欲、家族、世間体などを捨てボーイフレンドと恋に落ちるなど、自分の欲望にまっすぐなことと、それをエッセイに求めるところ、この映画はそれを伝えたかったのかもしれない、とこの文章を書いてて思いました。
でも何でこの映画を作ろうと思ったんだろ?巨漢ニキの演技、マックスの演技は最高でした。
だれだって、誰かを気にかけずにはいられないんだ。
これは映画ではない。とある人生だ。
かなり泣きました。デロデロに泣きました。
私自身も食で心を埋めるタイプである故、あらすじを見たときから他人事とは思えず視聴しましたが、予想外にキリスト教への辛く悲しい怒りのメッセージもあり深く共感。かなり没頭できました。
もしかしたら大衆が映画に求めるようなストーリーではないかもしれません。
人によっては鬱映画とも感じるでしょう。
しかし、さりげない伏線やそこはかとなくラブロマンスを感じるシーンに友愛もあり、シリアスではありますがキラキラと輝くドラマが散りばめられた良作です。
最後、主人公は救われたのだろうか?
救いとはなんでしょう。
愛する恋人に会えること?
娘の口で詩を読んでもらえたこと?
まさか神の元へでも行くのだろうか?
私は、ラストシーンを踏まえて、「あの時は本当に幸せだったなぁ」と過去になっても光り続ける思い出こそが救いだと感じました。
ほんの短い間だとしても、心から幸福を感じられる思い出があるなら、その人生は良きものだ。さらに愛する人にまで出会えたなら、最高の人生だ。
いいじゃないか。そんなもんで。
魂の救済、とは
レスラー、ブラックスワン、などで名をあげているDアロノフスキー作
もとは舞台劇というだけあり、物語はほぼ室内で進む。場面展開、転換も少ない。
にも関わらず、圧倒的なダイナミズムで心を打たれる。
つまりはシナリオの重要性があり、俳優の演技、がそれだけ試される作品でもある。
まずはキャスティングの妙にもつきる。主演のBフレイザー。
プライベートなどでの問題から、メンタルヘルスに支障をきたし長らく表舞台から遠ざかっていた。
彼を支える看護師役のホンチャウの演技もよい。
人間の心理描写で、物語にここまでの強弱をつけられる。ということは派手なアクション、激しいカット割り、スピーディーな展開、などだけが映像作品の肝というわけではないのだな、ということだ。
冒頭から物語に入り込み、どのようなラストで終わらせるのか、と思いつつ。
鑑賞後の深い余韻。しばらく席を立てなかった。
死を前にする人間の肉体が、幸福であったという時間、記憶を凌駕するその瞬間を最後にみた。
涙とともに。自身忘れることのできない映画。
そういえばレスラーでもそうだったか。
そう生きることしかできない男の、死を前にした肉体の躍動を映し出したラスト。自身の幸福、栄光につながる破滅への跳躍。
Dアロノフスキーの、人間に対する深いまなざしがつきささる傑作です。
果たして自分は、過ちなく生きているのか、幸福に生きているのか、正しいとされる生き方なんてあるんだろうか。
"やっぱり一筋縄では行かなかった…"な映画
ダーレン・アロノフスキーの作品が苦手だ。
改めてわかった。
やっぱり、苦手だ。
テーマが深過ぎる…というか、宗教に絡めたストーリーが出て来た瞬間に、「あっ、もうダメだ!」となる。
ネタバレは見たくないけども、何の話なのか、ほぼほぼ分からない笑
ブレンダン・フレイザーは熱演だけれども…
だから、どうした?
*人生の終わりに気付いて後悔すること…山ほどあるわ!そんなもん!
死に際にジタバタしても、到底救われるとは思わない。
やり直せるものならやり直したいわっ!
きれいに死ねると思うなよっ!笑
*もしそんなのがテーマと言うなら、くだらない作品だわ…。ん?違うってか?笑
エレファントマンよりは明るい
終末で人は救われない
すごく面白かった。
ある男の最期の五日間の物語。
登場人物は少ないが、1人1人が深く掘り下げられていて、人生について考えさせられる。
主人公を中心に、主人公と関係する人々が一人ずつ現れ、死に際の主人公と対話していく。
でもこの映画の隠れた主人公は、死んだ主人公のパートナーなのだと思う。この映画のほとんどの人物はパートナーとも深く関係している。
映画に登場しない人物を中心に物語が展開している様は、「ゴドーを待ちながら」を連想させる。たぶんあの話のゴドーはキリストの暗喩だと思うのだけど、本映画も「信仰」をテーマにしているのではないか。
そういえば、どこで聞いたか忘れたけど、「人生には誰にでも2つの奇跡が起こる。それは、生まれることと死ぬことだ」という話を思い出した。そこに存在しなかった生命が新しく出現することは確かに奇跡に違いないけど、同じくらい不思議なことは、そこに確かに存在していたものが消えてしまうこと。死とは神秘的なことでもあるのだと思う。
最後に主人公が娘に向かって歩くシーンは、ぼくは主人公が死に際に見た夢ではないかと思う。死の神秘と救いを表現していると思う。
この映画の人物はみんな、単なる善人でもなく、単なる悪人でもなく、どうしようもない人間的弱さをもちながら、互いを傷つけあい、同じ人を強く愛したり憎んだりする矛盾した感情を持っている。
主人公自身も娘を含めみんなにひどいことをしていてその罪悪感にさいなまれているが、悪人というわけではない。人間関係だけでなく、様々なものが実は善悪を簡単に決めることができないものだということが示される。
たとえばニューライフ(原理主義的なキリスト教)により主人公のパートナーは信仰に悩み自殺してしまったけど、一方でこの自殺は主人公への愛を貫いた証拠でもあった。
主人公の喘息呼吸は主人公の死が近いことを表すものだけど、一方で主人公が確かに今生きていることを示すものでもあった。
主人公の娘が宣教師の罪を暴露したことはおそらく娘の悪意からの行動だったけど、その結果かえって宣教師は救われることになった。
主人公の異常な過食行動と肥満体は、主人公が苦しみと罪を背負い続けたことを肉体的に表現したものだと思うのだけど、この映画全体が、「人間の罪」を大きく肯定しているんじゃないかと思う。
ニューライフの教義として、「終末」が訪れたあとでは汚れたものがすべて浄化される、というような話をしていたけど、この映画は、「そういうことじゃないんだよ」と言っている気がしてならない。
人間は弱さのために罪を犯し、そして苦しむけど、それらの中にこそ人間の素晴らしさがあるように思う。
<追記>
ラストシーンで、主人公の娘が、自分に渡されたレポートの文章が、自分が昔書いたものだということに気づく。
娘は「自分は父に愛されておらず、見捨てられた」とずっと考えていたが、実はずっと父に愛されていた、ということに気づく感動的なシーン。
このシーンに何か既視感があると感じていたが、その正体に気づいた
「砂の上の足跡」というクリスチャンの間で有名な詩だ。調べてみると、作者不詳らしい。
この詩の内容をざっと要約すると以下のようなものだ。
神に対して、「私が一番苦しかった時、あなたは私を見捨てたのはなぜなのか?」となじる男に対して、神は、「私はあなたを見捨てたことは一度もない。あなたが苦しかった時に足跡が一列しかなかったのは、私があなたを背負っていたからだ」と答える。
してみると、この映画でみじめで醜くて弱く罪深いおろかな人間の代表のような主人公は、「無垢に愛する」というただ一点において神の立ち位置にいるということになる。
主人公の娘は客観的には邪悪で、娘を盲目的に肯定する主人公は単なる愚か者に見えるが、一方で、理性的判断をはさまずただ信じるということによってしか、娘の心を動かすことはできなかっただろう。
もう一つラストシーンで気づいた事がある。主人公の最期のとき、ふわっと身体が浮き上がり、足が地面を離れたように見えるシーン。1つの解釈としては、主人公が死により肉体の重さから解放された、というようによめる。でも、キリスト教の教義に「空中携挙」というものがあったなあ、とあとで気づいた。調べてみると、終末論を掲げるプロテスタントの教義らしいので、たぶん当たりだろう。神に不死の身体を与えられ、空中に引き上げられた、というような宗教的なシーンではないか。
看護師のリズが主人公と最後に交わした言葉も意味深だ。「下で待ってる」とリズは言った。これが最期だと分かっているはずなのに。
主人公のパートナーは宗教によって殺されたということを考えると、この映画が宗教的なモチーフで構成されているのが奇妙に感じる。でも、この映画のテーマが「本当の信仰とは何か?」ということなのだとしたら納得できる。
ニューライフの宣教師は、「人を救いたい」という強い気持ちをもっていたけど、実はそれは「人を救うことで自分が救われたい」という動機だったことがあばかれる。
彼は決して悪人ではないけれど、彼にとっての信仰とは、自分の弱さから逃れるための依存の対象のようなものなのだと思う。主人公にとっての「過食」と変わらない。
人を愛し、信じて、前向きでいること
「おぞましい姿」をした主人公のチャーリーが、自らの死期を悟り、8年ぶりに娘と再会し向き合っていく1週間を描く室内劇。
最愛の人の死をきっかけに引きこもり、歩行も困難な程肥満化してしまったチャーリーに対し、序盤に感じるのは同情や哀れみでした。しかし、次第に明らかになっていく彼の心情や行動の根底にあるものを知るうちに、彼がとても前向きで、人を信じることを恐れず、愛に溢れた人なのだということを知り、ラストシーンは幸せに満ちた表情に感じました。
エリーの言動は客観的に見ると「邪悪」に見えます。それが真実なのかもしれません。
それでもチャーリーにとっては紛れもなく、優しく思いやりに溢れた聡明で美しい子なのだと、そう言うチャーリーの気持ちに嘘はないということが、エリーにも伝わったのだと思います。彼の愛が、彼女の未来に光を与えたと信じたいです。
たくさんの感情で涙が溢れましたが、まだ整理が仕切れていません。これからしっかり、噛み締めていきます。
デブの葛藤
40代のチャーリーはボーイフレンドのアランを亡くして以来、過食と引きこもり生活を続けたせいで太り過ぎ、体重272キロとなり、健康を損なってしった。アランの妹で看護師のリズに助けてもらいながら、オンライン授業の講師として生計を立てているが、心不全の症状が悪化しても病院へ行くことを拒否し続けていた。自身の死期が近いことを悟った彼は、8年前に家庭を捨ててから疎遠になっていた娘エリーに会いに行くが、彼女は学校生活や家庭に多くの問題を抱えていた。さて結末は、という話。
ほとんどチャーリーの家の中だけの会話劇で、そのチャーリーに共感も出来ずただ退屈だった。
娘の事は気になるし・・てな葛藤も有るのだが、自己管理も出来ないデブに共感も興味も湧かない。
フレイザーの演技が素晴らしいと評価が高いようだが、ストーリーが合わない作品だと名演だとしても個人的にはダメだった。
欲に勝てない、優しく哀れな男の物語
元は舞台劇との事なので、主人公チャーリーの自宅でのシーンが大半です。8年も会ってなかった娘が亡くなる直前の5日間に頻繁に訪ねてきたり、パートナーと同じ宗教の勧誘が偶然やって来たり、まぁまぁご都合主義的なところはありますが、割り切ればいい感じにひっかからずに観られました。
退屈するかなと思ってましたが「立ち上がる」「笑う」「食事する」等、普通の人ならなんて事ない動作も彼にとっては命に関わるので、いちいち緊張感が走ってハラハラしました。
A24ですが、グロい描写はほぼなし、代わりに食事シーンは鬼気迫るものがあり、理性ではどうにもならない過食症の恐ろしさを感じました。
不安や悲しい気持ちになると、命が危なくても過食を止められない。リズだって食べ物を渡したくないし、彼もよりによって看護師の彼女を加担させたくない筈なのに、結果的には自殺ほう助させてしまう。
こうなる前に心のケアができていたら、身体も健康でいられたのに。
過食症、アル中、貧困、格差、宗教問題等々、特にアメリカが抱えているシビアな問題が一気に描かれているので、暗い印象ではありますが、最終的には観て良かったと思える不思議な映画でした。★3.7
詰め込みすぎの鯨
おそらく現代アメリカ人にとって「救い」とはなにか、が主たるテーマなんだろう。しかし設定にあれこれぶち込みすぎてぼやけてしまった。
肥満、宗教2世、同性愛、家族の離別、金、生きる意味 などなど、アメリカ(だけではないが)が抱える問題がてんこもりなのである。てんこもりすぎてどれもこれも中途半端になり、結局どの登場人物にも感情移入できないまま予定調和で終わるという、最悪にちかいシナリオだった。
特に宗教2世の配分がおかしい。偶然現れた宣教師も親身な看護師も死んだ恋人もみんな同じ宗教の2世というのはいかがなものか。不自然だ。
さらにこの映画最大の「ウリ」である肥満も、その必然性がわからない。醜い外見の人間への救いを描きたかったのか? たしかに特殊メイクはすごかったものの、ブレンダン・フレイザーはハンサムなので醜いとは言い切れないし、ピザの配達人に姿を見られたショックもあまり伝わってこない。これは演技力の問題なのだろうか。(なのにアカデミー賞主演男優賞)
加えて、繰り返される「白鯨」の感想文のどこがすばらしいのかさっぱりわからない。 アメリカ人ならピンとくるのか? 鯨のイメージ映像を挟むとかすれば関連もわかりやすかっただろう。
舞台向けの設定なのかもしれない。
照明などで肥満はシルエットで表現でき、物語を進めていく会話に集中できる。窓の外の雨が最後に晴れるのも、ありふれてはいるが舞台なら一定の効果はあるだろう。
映画ならではの迫力やイメージの拡張もなく、つまらない作品。
あのハムナプトラで考古学者だった男が
20年前の映画「ハムナプトラ」でイケメンの考古学者を演じた後、いろいろあって、表舞台から遠ざかっていたブレンダン・フレイザーが、余命いくばくもない巨漢を演じる映画。
レビューでは、「椅子から立てなかった」ほど感動した人もいたが、自分はそこまでならなかった。
家庭をぶっ壊したのも、肥満体になってしまったのも、自分が欲望の赴くままに行動したからじゃないのかと。娘が可愛かったら、ちょっとはブレーキを踏むだろうと。まあ、あのきついかみさんじゃ、逃げ出したくもなるかなあと。
自分は日本人だからかもしれないが、赦す(その結果として救いがもたらされる)のはあくまでも人であって、神じゃないだろうと。神が赦しても、人(ここでは妻や娘)から赦してもらえなかったら、それは結局救いにはならないだろうと思った。
この映画で描かれなかったこと、描かれたこと
(完全ネタバレですので必ず鑑賞後にお読み下さい)
この映画は、(個人的に)描かれていないことと描かれていたことがある映画のように思われました。
私はこの映画の鑑賞後に、素晴らしく深い映画であると感じましたが、一方で大きな感銘や大感動の傑作とまでは思えないという感情もありました。
その理由は、この映画『ザ・ホエール』は、主人公のチャーリー(ブレンダン・フレイザーさん)が(私が字幕など見落としていない限り)なぜ娘や妻を捨て、ボーイフレンドのアランの方に行ったのか、チャーリー自身の理由動機が明確に描かれていないところにあると思われました。
加えて、チャーリーの妻であるメアリー(サマンサ・モートンさん)も、なぜゲイであるチャーリーと結婚したのか、その明確な理由が(私が字幕など見落としていない限り)描かれていないように思われました。
この映画の主人公チャーリーは、その後ボーイフレンドのアランが亡くなってから、引きこもり過食によって体重を増加させ、自らの足では歩行器なしに立つことさえ出来ない「醜い」姿になってしまいます。
私はこの怠惰な主人公チャーリーに心からの共感は正直出来ないままでした。
その理由は、(チャーリーの外見の「醜さ」というより)娘や妻を捨てボーイフレンドのところに行った、チャーリーの本当の意味での行動理由が描かれてないところにある、と思われました。
それが、この映画の鑑賞後に大傑作や大感動との思いが湧き上がって来ない理由にも感じました。
ではこの映画『ザ・ホエール』はダメな作品だったのでしょうか?
私はしかし大傑作や大感動の感情がなかったにもかかわらず、この映画はしかし人間の深淵をえぐってもいる別の意味の感銘を受ける映画になっていると一方では思われました。
その理由は、(主人公チャーリーや妻のメアリーとは違い)他の4人の主要登場人物の全員が、なぜそんな行動をしているのか、その理由が明確に描かれていたところにあると思われました。
チャーリーの娘であるエリー(セイディー・シンクさん)は、学校を停学になりSNSに犬の死体を載せたり大麻を吸ったりしています。
その理由は、娘エリー本人も言っているように、父チャーリーが自分と母を捨て、ボーイフレンドのアランの方に行ったのが根本理由だと暗に明かされています。
過食で身動きが難しくなっている主人公チャーリーの身の回りの世話を、訪問介護士のリズ(ホン・チャウさん)が時折訪ねて行っています。
リズがチャーリーの身の回りの世話をしているのも、彼女の兄がチャーリーの亡くなったボーイフレンドのアランだったことが理由として明かされます。
チャーリーのボーイフレンドだったリズの兄のアランは、新興宗教のニューライフ教会の父に決められた結婚から逃れ、チャーリーとパートナーになったことがリズから話されます。
しかしアランは、ニューラーフ教会の家族との精神的な断絶から命を落とすことになることが明かされます。
主人公チャーリーの家を訪ねて来たトーマス(タイ・シンプキンスさん)はニューライフ教会の宣教師で、チャーリーを救いたいとチャーリーの家を訪れています。
後に明かされるように、チャーリーの亡くなった元ボーイフレンドのアランがニューライフ教会の教えを家族から受けていて、チャーリー自身もニューライフ教会の教えを深く知っていたからこそ、トーマスを度々家に入れていたことが暗に明かされます。
また、トーマス自身は宣教活動でチャーリーの家に来たというのは実は嘘で、宣教活動に疑問を持ったトーマスが、教会の金を盗んで逃げて来たということが後に明かされます。
チャーリーや妻のメアリーと違って、娘のエリー、訪問介護士のリズ、ボーイフレンドのアラン、ニューライフ教会宣教師のトーマスの、行動の理由は明確に示されているように感じました。
そしてそこで描かれているのは、ゲイと新興宗教にまつわる世間と家族に引き裂かれた人々の濃縮された関係性だと思われます。
そしてその出会いは、一方で偶然の要素もあるのだと思われます。
さらにこの映画ではもう一つ重要なことが描かれていると思われます。
それはチャーリーが最後に(オンラインでの大学授業での生徒や、娘エリー対して)伝えていた「正直に」生きるという言葉です。
娘のエリーは、ニューライフ教会の宣教師のトーマスの、教会の金を盗んでここに来たとの告白を録音し、トーマスの家族にその録音を送り付けます。
おそらく娘のエリーは、トーマスの罪を家族に罰せさせようとしてトーマスの告白録音を送り付けたのだと思われます。
しかしトーマスの家族は、教会の金を盗んだことを大した話ではないと許し、トーマスに家に帰っておいでと伝えます。
このことは以下のことを表現しているように感じました。
チャーリーはボーイフレンドのアランを選択し、娘のエリーや妻のメアリーを捨てます。
しかしそのことによってチャーリーは娘のエリーと疎遠になってしまいその後に苦しみます。
もちろん冷たい言い方をすればこれはチャーリーの自業自得です。
しかし一方でここでは、私たちが何かを選択した時に、選択しなかった事柄についてからも影響を受けてしまうという普遍的な感情も描いているように思われました。
そしてその影響は、自分が何かを選択した時には思いもしなかった感情や事柄で成されることが多いと思われるのです。
娘エリーは自分の感情から「正直に」(おそらく)トーマスをトーマスの家族から罰してもらおうと彼の告白録音を送り付けたのだと思われます。
しかし結果は真逆の、トーマスは彼の家族から許されるという帰着を迎えます。
このことは、私達は例え一見自身の欲望に「正直な」選択をしたとしても、その選択をしたことにより(それ以外を選択しなかったことにより)別の思いもかけない影響を受けることになるのだということを伝えているように感じました。
だから例え犬の死体の写真をSNSに載せたりといった一見世間に反するように「正直に」生きたとしても、(逆に「正直に」生きたからこそ)さまざまな思いもかけない別の(傷を含めた)感情に出会うことになる、だから「正直に」生きて大丈夫なんだと、この映画は伝えているように思われました。
私は、この映画『ザ・ホエール』は、主人公チャーリー(あるいは妻メアリー)の行動理由が明確に描かれていないから大感動の大傑作になり得ていないと感じながら、一方で、偶然も相まって引き寄せられるように出来てしまう凝縮された人間関係と、人生での選択における思いもかけない選択しなかった方からの(内面外面含めた)影響のされ方について、人間を深く描いた作品になっていると思われました。
そしてこの映画の「正直に」生きるという到達は、その厳しさも含めた運命の受け入れにも通じる私達への励ましや勇気づけにも感じました。
思えば、人は周りのことは客観理解出来ても、自分のこと(あるいは妻のようなまだ存命の愛憎交わる最も近い人のこと)は客観視出来ないことも多いだろうと思われます。
そんな自分の(あるいは存命の近しい人の)行動理由は明確になんて分からないということも、「正直に」描かれていた映画なのかもしれないなとも思われたりもしました。
人間誰しもが過ちを犯す
かつて大学の教え子と恋に落ち、妻子を捨てて彼と一緒になったチャーリー。しかし恋人は数年前に死んでしまい、その喪失感から200キロを超える巨体になってしまい、ソファーから動くこともままならない。しかも太り過ぎることが原因で病気になり、後数日で死ぬことがわかる。
もう命がもたないと知ったチャーリーは、8歳の時に捨てた娘との再会を望み、距離を縮めようとするがーー。
全て彼の自業自得だ。
普通に考えると、なんて身勝手な男なんだろうと思うだろう。娘のエリーだってそりゃあんな態度をとっても不思議ではない。
だけど本作が伝えたいのは、人間は誰しも完璧ではないし過ちを犯す。クソッタレだけど、結局誰かを気にかけ、誰かを愛す……これが人間なんだと。
そこに宗教、LGBTQもテーマに組み込まれている。
物語としては、ツッコミどころが多くそんなに魅力を感じなかった。
だけど、本作の最も評価すべき点と見どころは、特殊メイクを施したチャーリー演じたブレンダーの渾身の演技だろう。
あの鯨とはチャーリー自身のことだったのだろう🐳
ピザ屋の兄ちゃんちょっとどうかって位にドン引きし過ぎ
アロノフスキー監督作品の殆どに共通するモチーフとして、キリスト教的な霊肉二元論でいう霊の追求、そして魂の解放があげられる。しかしそこに到達するために、主人公たちは宗教や信仰、つまり縦の力をあまり信用しないか無関心であり、むしろ横への水平移動、デスパレートなまでの体の酷使によって、ワンチャン恩寵の顕現を狙う逆張りの賭けに出る。彼ら彼女らの行動原理は、正に意味よりも強度優先であり、正しいか正しくないかなどどうでもいいのである。
今回の『ザ・ホエール』も、主人公チャーリーのこじれ具合が一目で分かるファーストショットからつかみはOKだし、他の登場人物も一様にこじれていて、特にトーマスのバックグラウンドには非常に興味深いものがあった。舞台脚本が原作なので基本スタティックな会話劇に終始するが、チャーリーが正に縦の力を獲得するに至る瞬間まで飽きさせなかった。
弱い人間たちの保身の生贄
元が舞台劇とのことで、舞台劇らしいつくりでした。
チャーリーの娘に対する親バカっぷりが切ない。
8歳から会っていなければ仕方ないかもだが、元妻に娘の実態を知らされても直視しない。
チャーリーは現実から逃避する。辛い現実を突きつけられると過食に逃げて身を守る。酷い言い方かもしれないけれど、恋人の死の現実から逃避して過食に走りあの巨体になったのだ。
宗教の嫌な部分の一つは、教義に外れると罪だの罰だのと信者を脅すところだ。「教え」は洗脳に近いと思う。
キリスト教は同性愛者にとっては救いどころか害だ。
本人たちに酷い罪悪感を押し付けるだけでなく同じ信仰を持つ人々を、彼らに対して白い目を向け迫害するよう仕向ける。チャーリーの恋人も信心深かったが故に罪悪感に苦しみ、さらに家族やコミュニティーから孤立した孤独感から、ああいうことになってしまったんだろう。チャーリーがそうならなかったのは、過食に逃げこんだから。(結果的にそれが緩慢な自死になってしまったが。)「救い」ってなんだろう。
チャーリーにキリスト教の、特にニューライフの「救い」は不要というのにしつこい宣教師トーマスは、真面目な青年だからこそ信念の押し付けになるんだろうが、チャーリーのためといいながら自分のためにしていることで、思いやりが欠如しているのは育てられ方のせいだろうと思う。
どんなに問題のある家族でも、そこから一人反旗を翻して離脱するのは大変なことだ。
「家族」全員、さらには親戚一同、コミュニティ全体から敵視されたら、肚をくくった心の強い人でも孤独感や寂寞感は半端ないだろうし、そこまでの決心のない人ならなおさら、人によっては罪悪感にも苦しむかもしれない。だから意を決して離れたものの、戻ってしまうことも多かろうと思う。トーマスが家族やコミュニティーに許されたとわかったときの晴れ晴れとした表情がそれを物語っている。毒家族から逃げられない真理はそういうものだと思う。
甲斐甲斐しくチャーリーの世話をするリズはあからさまなイネーブラーで、彼女も家族から孤立、唯一の仲間の兄に逝かれてチャーリーを自分に縛り付けて孤独から身を守っていたのだろう。
登場人物の、チャーリーの娘も含むほぼ全員(チャーリーの元妻は除けるかも)が弱い人間で、精神的に自立できない彼らがそれぞれ自分を守り正当化する行動をする。多分自覚はないのだろうがそのためにチャーリーを犠牲にしている。チャーリーはそれを一身に受けた吹き溜まりだった。おそらく彼はそれを知っていた。でも、孤独な彼には利用されつつも拒めない弱さがある。精神的な面だけでなく、身動きできない身体を持った物理的な不自由さからも。
自分の死期が見えてこれ以上他人に頼らなくていいとなったときに、ようやく周囲の思惑を振り切って自分の意思のみに従うことができたんだと思う。
生贄が去った後、遺された登場人物たちはどう生きて行くのだろうか。
全257件中、121~140件目を表示