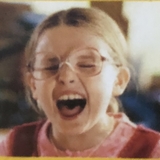ホワイトバード はじまりのワンダーのレビュー・感想・評価
全20件を表示
心に光が有れば相手の心が闇に包まれていても照らし出せる
「ワンダー 君は太陽」という映画のアナザーストーリー映画なんだけれど、そちらは観ていません。
スピンオフの位置付けになる映画なのでしょう。
文句無しに素晴らしい映画でした。
特に主役のサラ役のヘレン・ミレン(老サラ)とアリソン・グレイザー(少女サラ)の演技が良かった。
物語の構造は全く違うのだけれど、エピソードのそこかしこに何故か「タイタニック」を思い出しました。
「闇を払うのは闇ではなく光」だとか何とかのキング牧師の言葉と、サラの父の「心に光が有れば、相手の心が闇に包まれていても照らし出せる」だか何だかの言葉が心に染みました(染みた割にはちゃんと覚えていないけれど)。
フランス人が終始一貫して英語を喋るのはいつものハリウッド映画だけれど、色々と考えさせられる映画であったかな。
ナチスに追われたユダヤ人少女を守り抜いた、気高き少年騎士とその家族の戦いの記録。
『ワンダー 君は太陽』は未見。
とにかく、ポスターのヒロインが可愛いという「だけ」の理由で鑑賞。
総じてとても面白かったけど、若干、細部にはひっかかりもあったかな。
『ワンダー』のほうは、たぶん観ていなくても、ほとんどのパートが前作とは関連のない話なので、あんまり問題はなかったような。
ナチス傀儡のヴィシー政権下のフランスで、ユダヤ人の少女が納屋に匿われる『アンネの日記』のような話なのだが、基本的に匿う側がすがすがしいまでの「善意」に満ちた家族で、そこは最後まで一貫していて、サスペンスが「ない」というのが、逆に珍しいタイプの物語だった。
今年、やはりフランスが舞台のホロコーストもので、ヴィシー政権下の農村部でユダヤ人を匿う話を観たけど、あれはなんだったっけと記憶をたどったら、クロード・ルルーシュ版の『レ・ミゼラブル』(95)だった。あれは匿ってくれていた家族に「裏切られる」話だったが、神父様の経営する学校によってヒロインがユダヤ人狩りから守られる展開はまったく一緒で、もしかすると「同じフランスの学校」がモデルになっているのかもしれない。
前半のあたりはちょっと眠たくなる部分もあったが、学校にナチスが抜き打ちユダヤ人狩りに押しかけてきてからは、手に汗握る展開が待っていた。
そのあと、好きな女子を守って戦う少年の話に入ってからは、初期宮崎アニメ(『コナン』『カリオストロ』『ラピュタ』)の好きな僕のようなオッサンには、まさにこたえられない展開だった。結論からいえば、ラストまでどきどきわくわくしながら観ることができた。
映画のなかで動いているヒロインの少女は、ポスターよりは垢抜けない感じで、田舎娘ぽくはあったが、やはり可愛くて思わず守ってあげたくなるタイプ。
むしろ、ユダヤ人だからって急にバカにできる感覚が僕にはわからない(僕はルッキズムの奴隷なので、顔さえよければ人種も出身も性格もほぼ関係なくなんでも応援しますw)
対する過去篇のジュリアンも、歩くのこそ難儀しているが、秀才で、美形で、性格がよく、決して自分からは女に手を出したりしない究極のナイスガイで、これでくっつかなかったらウソみたいなくらいのグッドルッキング・カップル。
ただ、なんとなく違和感を感じた部分として、果たして『ワンダー』のスピンオフとして、このノリで問題なかったのかな? という疑念はうっすらあった。
『ワンダー』は(よく知らないけど)それこそルッキズムに一石を投じる話だったっぽいのに、スピンオフの本作で明らかな「美少女」「美少年」の物語にしてしまってよかったのかな、と。
もちろんその代わりに、今回は「ユダヤ人」と「障碍者」という、ナチスによって迫害される二大要素を持ったヒロイン/ヒーローだったわけだが、明らかにこの役者さん二人を主役に抜擢した場合、両名の見た目が「可愛らしい」から観客が自然と応援してしまう部分は否めない。それで本当によかったのかな?
それから、「いじめっ子」だったジュリアンのその後を描くことで、『ワンダー』の物語を完結させる意図があったと原作者自身が主張しているわりに、じゃああの少年兵ヴィンセントのおぞましい最期は、あんな終わらせ方で良かったんかい? ってのはすごく思った。
人まで死なせちゃったら、もう救いがないよって話なんだろうか。
主人公がただただひどい目に遭うだけのよくあるホロコースト話だったら、なんの引っかかりもなく観られる勧善懲悪の展開なんだけど、人の善意の大切さを問う物語――「現代のほうのジュリアンのその後を描いて、改心までさせて救済する」のが目的の話で、新しく出てきたいじめっ子が、闇落ちして、ろくでなしぶりを悪化させて、なんの反省もないまま最後まで悪行を積み重ねて、罰のように狼に食われておしまいって、なんかえらくイヤな対比だなあ、と。
それと最近、リドリー・スコットの『ハウス・オブ・グッチ』やマイケル・マンの『フェラーリ』など、古参監督が「ヨーロッパを舞台に英語で映画を撮る」ケースはあるが、若手監督の映画で、現地の言葉を使わずに英語で撮るケースは減っているので、まあまあ珍しいと思った。出演者ももっぱら英米豪の英語圏からキャスティングしているし、必ずしもユダヤ人ではない人間にもユダヤ人を演じさせている。
僕自身はそこまで気にしないが、リベラル寄りの作品のスタンスを考えると、エクスキューズなしで英語の映画として撮っていることに、とやかく言う人もいそうな気がする。
あと細かい不満ばかり言い募って、感じが悪いのは承知のうえなのだが……
●サラが学校から命からがら逃げ出したあと、どうやってジュリアンがサラを見つけ出せたのかは、ちょっとわからなかった。あと、軍が犬を使っているのにサラが逃げ切れた理由とか、ジュリアンはあの足でサラの隠れている階まで音を立てずに上がれたのかとか、雪の中でジュリアンの足跡はかなり目立つのではとか、前に親と潜ったからって下水施設を通って迷わずに家まで帰れるものなのかとか、いろいろ考えたけど、あまり深く考えないほうがいいのかもしれない。
●近くに密告者がいるといって警戒しているわりには、毎日毎日納屋に通って、そこそこ大きな声で談笑し、ライトを点けて壁にできる影の動きにも無頓着で、あげくに歌ったり踊ったりしていて、まあまあ恐れ知らずな連中だなと思ったが、途中からもう気にしないことにした。
●そうしたら比較的さらっとナレーションで「1年が経った」とか言ってたけど、幽閉状態に対する拘禁反応とか、ずっと閉じ込められていることで生じる身体的影響とかをまるで感じさせない、単なる穏やかな避難所生活のように描かれていて、さすがに若干描写が軽いかなあと。「女の子が1年間、風呂も入れず、トイレもないような納屋で、一度たりとも外に出ることを許されないまま暮らす」のって、結構なストレスだと思うんだけどね。
●あと、これだけ献身的かつ全身全霊の庇護を一方的に受けておきながら、サラのほうにあんまり申し訳なさそうな描写がないことも、ちょっと気になった。心の底からの感謝を三人に示すシーンとか、あまりの幸運に感極まって泣き暮れるシーンとか、いろいろしてもらえていることへの返礼として、何かしらの労働や内職で報いようとする姿勢とか、将来的な恩返しについての言及とか、そういうのがほとんど出てこないのって、どうなんだろう。
ボーミエ家の人たちはもちろん、別段何の見返りも求めてなんかいないのだろうが、サラのほうに「御恩」に対するリアクションが薄いのがどうにもひっかかる。
●で、サラの誕生日にボーミエ一家が総出で祝ってくれるのだが、「隣の夫婦には牛乳に入れて睡眠薬を盛ったから心配しなくても大丈夫」みたいなことを言っている。おいおい、そんなことしてええんかいな(笑)。しかも後からわかる事実から考えると、隣家の夫婦が寝こけているあいだ、匿われていたラビはどうなっていたのだろう? 結果的に彼らをかなり危険な目に遭わせていたことになるのでは?
●ナチスの青年隊に入ってレジスタンスと銃の撃ち合いをしている青年たちが、コウモリが怖くて逃げだす展開には、若干無理があるような気がする。ノリがそこだけ書き飛ばしのチープな少年向け小説みたいなんだよね。あのあと、ナチス青年隊の連中が報復に来ない理由もよくわからないし、学校でジュリアンが復讐されない理由もわからない。
●サラをヴィンセントがついに見つけ出して、森に追いつめるシーンも、途中からのモンタージュで結末がどうなるかはたいてい推測できるんだけど、さすがにそんな御伽噺みたいな展開でいいのかな、と、個人的にはちょっと引いてしまった。
●終盤のあの流れで「ジュリアンの死体が見つからない」理由もよくわからない。
軍が収容してどこかに持って行ったってこと? お母さんの目の前で撃たれていて、倒れた場所はかなり明確だった気がするけど……。
総じて、重たいテーマを扱っているわりに、若干リアリティを欠くというか、映画というよりは「テレビドラマでも見ているような」軽さと安易さが目立つ気がするんだよね。
好きなジャンルで、好きなタイプの物語だっただけに、どこか子供だましっぽいテイストがあちこちでひっかかるというか。
それと、前作の『ワンダー』を観ていないからそう思うんだろうけど、前後に挿入されている「今のジュリアン」と「今のサラおばあちゃん」の話は、あんまりピンとこない。
これがあることで、映画として面白くなっているかといわれると、たんに邪魔をしているようにしか思えない。
だいたい、転校先で煮詰まっている孫に、この話を一晩語って聞かせただけで、劇的に改心して生まれ変わったりするものだろうか。おばあちゃんが受けた善意の話を自分なりに消化して、自分が過去に成した凄絶ないじめを悔いて、真の反省を経たうえで新たな価値観のもとに新しい一歩を踏み出すまでには、けっこうな段階を踏まないといけない気がするんだけど。
そもそも、なんでこの話をおばあちゃんは一度もしたことがなかったの? 後ろめたかったり、知られると困るような話だったら別だが、ぜんぜん孫に語り聞かせて問題のない「良い話」だよね? どうやら古いほうのジュリアンが孫の名前の由来になっていることを考えると、むしろ「もっと昔にちゃんと伝えておかないといけない」話なのでは?
で、改心したジュリアンがやることというのが、「ワシントンDCまで行進する」と宣言して、校内でビラを配っている政治的な学生活動サークルに入ることってのも、ええええ? なんだかなあ、といった感じ。
それなの? やること? マジで??
もっと身近なところ――人に親切にすることや、なにかのボランティアをやることから始めるのが筋じゃないのか? あるいは、まずは前作で行った自分の悪行を自分なりに総括するところから入るべきじゃないのか?
最後のおばあちゃんのやたら政治的な演説も含めて、せっかく「個の物語」として説得力をもって提供してきた重みのある話を、最後はリベラリズムの宣伝ビラみたいな内容につなげちゃってる印象。なんだかお里が知れる感じで、個人的にはとてももったいない気がした。
ラスト、街の上を飛んでいくCGの白い鳥が、なんだか「張り子」のような作品の象徴みたいに思えてねえ……。
最初に書いたとおり、自分にとって、少年が全力で少女を助けるボーイ・ミーツ・ガールものはそもそも大好物だし、主演の二人は文句なしに応援できるキャラクターだし、満天の星空のもとブルーベルの咲き誇る森でジュリアンが告白するシーンの美しさと言葉の真摯さには心底感動したし、二人を助けようとする善意の家族や隣人に対しても全幅の共感を持って観られるような映画なだけに、もっと「本格的に」そういう映画としてちゃんと仕上げてくれていれば、もっとこっちだってハマれたのにと、残念に思う。
あと、往年のハリウッド女優のような風格でヴィヴィアンを演じている女性が、『Xファイル』のスカリー捜査官だったことを、観てからパンフで知ってびっくり。
ヘレン・ミレンも、僕が『第一容疑者』にはまって観ていたころから考えると、ずいぶんと歳を寄せた。
最後に悪口を書きすぎた反省に、ひとつ、心から感動したシーンを書いておく。
ジュリアンが尾行されたせいで危機が訪れたとき、ボコボコにされたジュリアンを心配してロフトから降りてきたサラに対して、ジュリアンが怒鳴り散らすシーン。
あそこには、間違いなく「真実」があった。
サラを心から心配する、胸を締め付けるような不安。
自分のやらかしを許せない、強烈な自罰感情。
いざというときに自分の身体ではサラを守れないという虚無的な無力感。
自分たちの家族の犯している危険の大きさを、サラに理解してほしいという切実な想い。
それでも絶対にサラを守り抜くという「騎士」としての誇りと決意。
あれは、複雑なジュリアンの想いがあふれた名シーンだったと思う。
なんにせよ、若き二人の俳優の未来に道が開けることを心から祈りたい。
ジュリアンの為のジュリアンの話
「Wonder 君は太陽」の続編と思っていたら
アナザーストーリーでした。
前作で嗚咽どころじゃなかったので
構えて行ったけど、本作も案の定号泣。
ユダヤ人と言うだけで迫害を受ける。
ヴィンセント、サラに恋してたんじゃないの?
そんな簡単に恋心は憎悪に変わるの?
サラを匿う為とはいえ、軟禁状態の彼女に
動かない車に乗って、2人だけの妄想フランス旅行は
本当に旅行を楽しんでいるような景色が見えてきて
幸せな気持ちになります。
ジュリアンだけではなく、ジュリアン両親の
暖かく優しい深い愛情。「あなたは私のママよ」
もう涙腺崩壊。
「人間万歳」
ナチス占領下のフランスを舞台にした見応えある作品だけどあの狼はいったい‥?
ナチス占領下のフランスを舞台に人間の愚かさ残虐さ、対し勇気や優しさを描いた見応えのある素晴らしい作品と思います。ただワンダーを見ると、サラの子供(孫ジュリアンの親)はなんであんな変なの(孫に教育はしても子供にはしなかったのかな)?ってのが気になってしまいましたが。あとサラを助けてくれたジュリアンこそ狼に助けてほしかったかな‥そもそもあのファンタジーめいたくだりは必要だったのかな‥
最高の彼氏😭
ハンカチ必要なほど泣いた。だいぶ良かった。
ジュリアーン!!と私も心中で叫んだ。
ワンダー君は太陽のほうのジュリアンも
今作できちんとフォローしているところに人間愛を感じた。
対照的に、改心しようのない奴はあっさり見捨てるところとかディズニー式でわかりやすいなと思う。
良い人達過ぎる
これまでもユダヤ人がナチスに迫害されていく作品は観てきたが、実話ベースも多くて、いろんなタイミングで難を逃れ生き延びたというのは大袈裟ではなく本当にあったのだろうと。
サラがギリギリのところで逃げ、隠れて生き延びたというのもフィクションだが、実際にありえた話だと思う。
ジュリアンの両親の懐の深さに感動する。
隣の家の人達も。
「ワンダー君は太陽」の内容はすっかり忘れていたが、特に問題なし。
孫に聞かせるおばあちゃんの話としてではなくても成立しそうだし。
ジュリアン、両親が非常にかわいそうだった。
ナチスドイツのことは後世に伝えられるべきで、私達もきちんと作品を観ていきたいと思う。
人類の未来を照らす光と人間のエゴをただす勇気の翼をください
有名な芸術家のユダヤ人のおばあちゃん役のヘレン・ミレンが弱いものイジメで高校を退学処分になり、転校を繰り返す孫に対して、ナチス統治下のフランスで中学生時代に苛められっ子の親子に助けられた実体験を話すことで、真の勇気とはなにか、人をみる目を養うことの大切さを伝えようとするお話。
周囲から絵の才能は認められてはいたが、気ままに少女時代を過ごしていたサラのピンチを救ったポリオで跛っこのイジメられっ子の優等生のジュリアン。相手の立場になって考えられない未熟さを指摘され、はっと気づいたサラが涙を流す場面に、人間の罪深いエゴについてワタシもハタと気付かされました。曇った心で勇気を持てない者は人をみる目も養われず、未来を語る資格もないんだと。
汚れのない白い鳥たちが自由に羽ばたき、この腐った世界を変えて欲しいと切に願う映画。
差別的なあだ名で呼ばれるジュリアン役は2019年の映画「トゥルーヒストリー オブ ザ ケリー·ギャング」ではラッセルクロウについて行くとても賢い子役でした。美しい青年になりました。井浦新の若い頃になんとなく似ていました。
納屋の軽トラでふたりが見る映画仕立てのシーンに胸がキュンキュン。
ジュリアンの親切な両親さえ、二階の夫婦を先入観から誤解していたことも、とてもショックだった。物語のはじまりが1942年。1945年の終戦にあとちょっとで届きませんでした。
ジュリアンの家の納屋で2年を過ごしたサラ。おしっこやうんちはどうしていたんでしょう。生理のことなんかもジュリアンの優しくて聡明なお母さんがうまく処理してあげたんでしょうか?気になってしまいました。
サラのスケッチブックを取り戻したジュリアンが招いた不幸を咎めたり、責めたりしないジュリアンの両親はほんとに立派でした。
CGの狼がサラのピンチを救うシーンは「ゴールデンカムイ」みたいでしたけど、海外の映像作家たちに対する「もののけ姫」の影響は非常に大きいんだなと思いました。
映画の原題は「ホワイトバード」
翼をくださいを歌ったのは「赤い鳥」
音楽の教科書にも載っています。
素朴な感じのエンドロールがよかった。
生きていた人間の数だけドラマがある
流れとしてはタイタニックを彷彿させる。
ユダヤ人だけでなく優生思想により精神疾患、病人、障害者なども処刑されていたのよね。
そうゆう意味では何故彼がと思うところもある。確かに体は不自由だが、数学は飛び級ですよ。成績優秀者は対象から除外されないの?
所詮は体力あるもの、権力のある者が選ばれしものってことよね。
納屋でのドライブシーンが前後の悲劇を救う唯一の心温まるシーン。外には出たいし、隠れているのも嫌だが、ずっと一緒に過ごしたい時間でもあるは分かる。
幻想的な夜の森のシーン。お互いの気持ちを言葉にせず、伝わるお互いを思う気持ち最高に幸せな気持ち。しかし、前日の幸せと戦争が終わると言う気持ちからなのか、ついいつもと違う行動をとってしまい…ありがちではあるが何とも苦しい気持ちになる。それが彼の運命なんだとしても辛いシーンである。
どうして息子ではなく孫に同じ名前がついているのか、までは描いて欲しかった
2024.12.11 字幕 TOHOシネマズくずはモール
2024年のアメリカ映画(121分、G)
原作はR・J・パラシオ『White Bird: A Wonder Story』
『ワンダー 君は太陽』にて主人公オギーをいじめて退学になったジュリアンの祖母サラの過去を描いたヒューマンドラマ
監督はマイク・フォースター
脚本はマーク・ボンバック
原題の『White Bird』は劇中で登場するサラが見る白い鳥のこと
物語は、前作にてビーチャー校を退学になったジュリアン・アルバンス(ブライス・カイザー)が、ニューヨークにあるナーテ校に通う様子が描かれて始まる
パーカーを目深に被って、周囲を気にしながら学校に向かうジュリアンは、食事の際に空いている席に座った
そこに女生徒のラミヤ(Priya Ghotane)がやってきて、彼はジュリアンは彼女が座ることを気にも留めなかった
だが、母同士が知り合いということで声をかけるように言われた同級生のディロン(Teagan Booth)は、「そこは負け犬の席だ」と言い放ち、「明日からは俺たちのグループのところに来い」と告げた
その後、帰宅したジュリアンは、メトロポリタン美術館にて個展を開くことになっていた祖母のサラ(ヘレン・ミレン、15歳時:アリエラ・ブレイザー)と再会する
両親が外出していたために、サラと夕食を共にすることになったジュリアンは、学校で起こったことを話すことになった
だが、彼の言葉に違和感を覚えたサラは、自身の過去を話し始めた
時は1942年、ナチス占領下のフランスの田舎村にてサラは両親と共に暮らしていた
パリが陥落し、安全のために非占領地域に身を委ねていたサラは、そこにあるエコール・ラファイエット校に通っていた
友人のソフィー(Mia Kadlecova)、マリアンヌ(Selma Kaymakci)たちと普通の日常を過ごし、クラスメイトのヴィンセント(ジェム・マシューズ)に想いを寄せていく日々
彼女は絵を描くことが好きで、授業中でもノートに描いていて、ある日、担任のプティジャン先生(Pasty Ferran)に見つかってしまう
先生は怒ることもなく、「才能があるから続けなさい」とアドバイスを送った
また、学校には、ポリオの影響で松葉杖歩行をしている少年ジュリアン・ボーミエ(オーランド・シュワート)がいたが、彼は「カニ」を意味する「トゥルトー」と呼ばれいじめられていた
ある日のこと、授業中にも関わらず校長のリュック牧師(Stuart MacQuarrie)に呼び出されたサラは、クラスメイトのルース(Beatrice Holdingova)と共に学校の外へと連れ出される
案内人のアントワーヌ(Mac Clemons)の指示にて森へ逃げようとするものの、ヴィンセントが来訪したドイツ軍にチクったために追われることになった
何とか逃げ延びたサラは、彼女を追いかけてきたジュリアンに助けられる
彼の家の離れにある納屋に匿ってもらうことになり、彼の父ジャン=ポール(ジョー・ストーン=フューイングス)と母ヴィヴィアン(ジリアン・アンダーソン)の協力を得ることになった
物語は、反省していないジュリアンに対して、サラが過去を語る物語になっていて、特に「普通でいること」に反応してのものになっていた
ジュリアンがサラの話のどの部分に感化されたかは何とも言えないが、普通でいることを選べるという時代性の中において、自分のやりたいことを見つける意味は見出せたのかもしれない
サラは絵を描き続け、そして画家になった
ジュリアンに何ができるのかはわからないが、まずは同じ過ちは2度としないと誓えただけでも良かったのだろう
映画は、ほぼサラの回想録で、彼女がいかにしてホロコーストから逃げ延びたのかを描いているが、かなり脚色されている部分があるのだと思う
メルニュイの森におけるオオカミの立ち振る舞いはおそらくメタファーで、彼は何らかの要因で撃ち殺されたのだろう
それを描く意味はないのだが、唯一モヤっとする部分だったかな、と感じた
いずれにせよ、『ワンダー 君は太陽』の続編だと思って観に行ったらダメな作品で、ほぼ観ていなくても成立する物語になっていた
祖母の話を聞いてあっさり心を入れ替えるとは思えないのだが、彼自身が変わる可能性があるとしたら「恋愛」のような激烈なものではないだろうか
その相手が彼女かどうかは置いておいて、人が動くための力として最も強いのは愛に他ならないと思う
ジュリアンの両親も彼のその想いを感じていたと思うので、それゆえに協力的だったのかもしれない
ラストでは、個展にてスピーチをするサラが描かれ、彼女自身も孫に話を聞かせたことで何かを取り戻していた
おそらくは、「君は身勝手な人間だ」というジュリアンの言葉だと思うが、その言葉を思い出したことで個展への向き合い方も変わったのだと思う
そう言った意味において、本作は過去の愛の物語が今を生きる二人を生き直させる力があったということを描いているかな、と感じた
オーランド シュヴェルトくんが好きになった
ものすごく期待して観たので、シアターがガラガラだったのにまず驚いた。個人的にはとても楽しめたし、終始ハラハラドキドキでのめりこめたし、泣ける場面も多かった。
ユダヤ人のヒロインを助けるいじめられっ子のジュリアンを演じた「オーランド シュヴェルト」くんの演技が素晴らしいと思った。情報をいろいろ知りたいのだけれど、分からないのが悔しい。ヒロインに恋心があったから命懸けで助けたのかもしれないけれど、二人の切ない儚い恋愛が描かれていたからこそ、私には綺麗で素晴らしい映画に思えた。二人の空想のドライブのシーンやジュリアンのチャプリンになり切っていた場面も好きです。
あなたに伝えたいこと
人生の過ちを経験し〝ただ普通に生きることにした〟と言う孫に祖母が「あなたのために」と伝え始める過去。
ここから広がる世界は終戦前のフランス郊外。
吸いこむ空気までたちまち変えながら物語は幕をあける。
ちいさな町にも及んでいたユダヤ人への迫害になす術もなくトラックに詰め込まれていく人々。
その傍らで人間が人間を分断するという不条理に抵抗する正義はひとかけらの尊厳も無く生命の重みとともに打ち砕かれた。
銃声が響きわたる山の斜面、雪の純白を散らしてごつごつした黒い樹々の間を転がるように逃げる赤い靴の少女サラ。
突然の絶望の淵に追われた彼女は同級生のジュリアンに助けられなんとか納屋に匿ってもらえたのだ。
あの状況においては奇跡的なラッキーだったには違いないが、罪もなく息を潜める暮らしや家族との離散、度重なる恐怖と不安に晒された少女の気持ちを考えるだけでどうにかなりそうだ。
そんなサラにとって、納屋に差し込む太陽の光の筋は生きる希望を、穴から見える鳥にはひとときの安心や父母と歌った唄にある勇気を、ジュリアンや彼の両親の無償の思いやりは自分の命を守ることにつながったのだろう。
ささやかなたのしみを見出しながら信頼で結ばれた二人はほのかな恋心も育む。
そう導かれたのはサラとジュリアンに共通する他に流されない心の強さと機転、豊かな想像力の結果だったのかも。
絵を描くのが大好きな少女の未来があのラストに繋がりそっと触れた木彫りの小鳥が映った時、静かな感動が満ちた。
同時に、サラが過去に心で受けとったものたちが後の人生を一緒に越えてきたこと、今後もそれらが彼女を見守るように在るのだろうという確信も。
また、祖母サラの話に耳と目と心を傾けて聴くspecial name=もう1人のジュリアンの姿をみてほっとし、真心が伝える言葉とそのぬくもりには計り知れない力があると信じている私の気持ちを温めた。
華やかで美しいあの石の道にも誰かの深い悲しみや喜びの歴史が幾重にも重なっていることに彼は気づき、きっとまた違う未来を一歩ずつ動かしていける。
時空を自由に旅する。
感じたままを浴びながらあらたな発見もする。
「果てしない空想の世界」はやっぱりいい。
またここにも映画の魅力がとくとくと溢れているかのようだった。
修正済み
小鳥よ、小鳥 〜 心の中の光よ
1942年、ナチス占領下のフランスで、家族と平穏な日々を送るユダヤ人の美しい少女サラをアリエラ・グレイザーが、サラを手助けするクラスメイトの脚の不自由な少年ジュリアンをオーランド・シュワートが熱演。
ナチスから身を隠す為、納屋に匿われて生活を送るサラにとって、小さな希望の光となるジュリアンと過ごすひと時。僅かに明かりの灯された納屋でのシーンが、愛おしい程に美しい。
若き2人の透明感あるルックスが、この作品をより切なく魅力的にしている。
本作の導入とラストに登場する祖母サラを演じたヘレン・ミレン。年齢を重ねて尚知的で美しい彼女が語る言葉が心に響く。
多くの方々に観て頂きたい作品。
- 空想の世界は果てしない
映画館での鑑賞
「ワンダー 君は太陽亅を観ていなくても楽しめる
本作は「ワンダー 君は太陽亅のアナザーストーリーという位置づけではあるが、ワンダーを観ていなくても充分に楽しめる作品だった。
主人公を命懸けで助けたいじめられっ子の少年と同じ名前をつけられた孫が、退学になるレベルのいじめっ子であるという設定には妙なリアリティがある。
スケッチブックや鳥の木彫り等を伏線として巧みに使っている一方で、狼が都合良く助けてくれる点や、恩人の少年が命を落とす際の不運の重なり方など、展開の廻し方には緻密と安直が併存しているように思える。
全体的には優れた演技・演出と素直に感動できるストーリーを持つ良作であり、観て良かったと思える作品だった。
【”人間万歳!”今作は自らの苛めの行為で退学になり人との関係を断つ決意をした少年にユダヤ人の祖母が語る辛き過去の中で経験した”人間の真の勇気”を描いた、琴線に響く涙を堪えるのが難しき作品である。】
ー 今作は、名作「ワンダー 君は太陽」の6年後を描いた作品との触れ込みだが、27回遺伝的要因で成形したジェイコブ・トレンブレイ演じるオギー君は冒頭チラッと写真が映るだけで、ほぼ8割はジュリアン(ブライス・ガイザー)のユダヤ人である祖母サラ(ヘレン・ミレン)が語る、過酷なナチスがフランスを占領した際の出来事が、描かれている。-
■1942年。ナチスに占領された仏蘭西。ユダヤ人の一斉摘発で学校に捜査に来たナチスから逃げる少女サラ。必死に逃げる中、助けの手を差し伸べたのは、サラの隣の席に5年座っていたポリオに罹患したために、片足が不自由でクラスメイトから苛められていた”ジュリアン”だった・・。
◆感想
・”ジュリアン”と、その両親の人間の善性溢れる姿が非常に心に響く。サラを納屋に匿っている事がナチスに見つかれば、彼ら自身がユダヤ人であるので危ういのに・・。
・”ジュリアン”と対比的に描かれる、イケメンでサラが好きだった少年の、ナチスの手先になってユダヤ人を探し出そうとする愚かしき姿。
絵が得意なサラは自分のノートに、彼の似顔絵を描いていたが”人間を見る眼がないね。”と”ジュリアン”の前でその頁を破くシーンと、その後”ジュリアン”の似顔絵を描くシーン。
・少年が、サラを探しに納屋にやって来て銃弾を撃ち込んで行くシーンは、”自分は、権力を持った。”と勘違いしている愚かしき人間の姿として、象徴的に描かれている。
だが、彼は森に逃げ込んだサラに、尚も銃を打ち乍ら追いかけるが、それを自分達を狩に来たと思った狼たちに襲い掛かられ、絶命するシーンは正に”自業自得”であろう。
■苛めをした事で退学になり人との関係性を断つ決意をしたジュリアン少年に、祖母のサラが勇気ある少年の名を、”ジュリアン”と語ったのは、サラお婆さんの粋な創作ではなかったかな、もしかしたらジュリアンの名付け親はサラお婆さんかな、とも思いながら鑑賞続行。
とにかく、サラが納屋などに隠れるシーンはハラハラしっぱなしなのである。
・”ジュリアン”とその両親がサラの誕生日をケーキで祝ってくれたり、ジュリアンとサラがお互いの想いを打ち明けるシーンなどは、もう涙腺が可なり緩くなってきている・・。
そして、ジュリアンがサラの想いを知って、いつもの遠回りではなくナチスが居る道を通ってしまった事で起きるジュリアンと母に振りかぶる悲劇のシーンは、キツカッタナア。
・けれども、ナチスの密告者と考えられていた夫婦が、実はユダヤ人のラビを匿っていたシーンなどの設定は、ムネアツであったよ。
<今作は、自らの苛めにより学校を退学になり、新しい学校で人との関係性を断つ決意をしたジュリアンに、祖母サラが語った数々のナチス支配下でのユダヤ人たちの”人間万歳!”のシーンがムネアツで、最初は黒人の少女が渡そうとした”人権の集い”のチラシを受け取らずにいたのが、その話を聞いた彼が黒人の少女が落としたチラシを拾い、誘いに乗るシーンや名優ヘレン・ミレンが、自身の絵画展覧会で行った崇高なスピーチと観衆の中で、彼女の姿を誇らしげに観る彼女の命を助けた”ジュリアン”の表情は、熱いモノが込み上げて来てしまったシーンである。
今作は、不寛容で差別的思想が蔓延る現代に、とても大切なメッセージを送っている素晴らしき作品であると、私は思います。>
君との空想ドライブ。
転校したばかりで学校に居場所のない孫のジュリアンの元を訪れた祖母サラの話。
1942年ナチス占領下のフランス、学校に押し寄せてきたナチスに連行されそうになるユダヤ人のサラ、クラスでは冴えなくいじめられっ子のジュリアンに助けてもらい、自宅近くの納屋で匿ってもらうことになるが…、孫ジュリアンへ語る祖母サラの学生時代。
鑑賞前はナチスとか個人的苦手なジャンルと期待はせずに観に行ったものの、結果から書いてしまうととても良かった!
当時サラの通う学校内の同級生のイケメンに惚れては授業ノートに描く彼の似顔絵…、その忘れた授業ノートをサラへ届けるジュリアン。
その惚れたイケメン君のリークでナチスから追われる羽目になるサラだったけれど、そこへ優しく手を差し伸べてくれて助けてくれるジュリアンの姿、優しさ、真っ直ぐな目には涙で。
納屋で行われる勉強、カードゲーム、置かれてる車に乗っては“エンジンの掛かってない車で深夜のパリの街を走る空想ドライブ”、そのドライブシーンを楽しむ二人が素敵すぎて涙が止まらない。
匿ってる事がバレれば殺されると分かっていながらも、ジュリアン、ジュリアンの両親の優しさ、近隣住人の実は優しい人だったにも涙で。
ドラマティックで切なくてラストのジュリアンの展開は悲しかったけれど、サラの愛したジュリアン、その好きな彼の名前を孫へ付けてたってのも感動的で良かった。
前作とは対照的に受ける優しさ
前作のワンダーは優しさを周囲に与える陽の存在とは対照的に、今作は相手から無償の優しさを受ける立場。
親切、優しさを受ける喜び幸福を存分に楽しめ、感動を受け心温まる作品だった。
特に今作の優しさは自分の命を危険に晒してでも相手を思いやる優しさは最上級の優しさだからグッとくる。
ストーリーとしては前作のいじめっ子ジュリアンがワンダーに対するいじめで退学し心に穴が空いた状態で始まる。自分の悪い部分を認めつつもそこから前に進めない状態。
それを祖母がしっかり否定し受け止め、自身がユダヤ人迫害の際に受けた苦しみとそこで受けた優しさをしっかり対比させ、ジュリアンにどうあるべきかを促していく姿がとても美しかった。ジュリアンという名前の偉大さ重たさも気づけて良かった。
一応続編物ではあるがワンダーを見てなくても十分楽しめる。続編を見た身としては前作で醜態晒した両親の存在が少しは改善してる事を期待したが特に両親は描かれなかった。
勇敢とは何か? を観ることができます。
'Darkness cannot drive out darkness; only the
light can do that.
サラのセリフはここまで、でもキング牧師は続ける。
Hate cannot drive out hate; only love can do that. ' ...と
最初は、"white bird" をこのように捉えていた。
カラドリウスCaladriusというローマ神話に登場する霊鳥
病人がこの鳥を直視できれば生き永らえうるといわれた。この霊鳥は患者の目から病魔を吸い取り,太陽まで飛んで行ってそれを捨て去るという。例えば、映画『グリーンマイル』のコーフィの不思議な力のようなものなのか? それとも
平和の証なのか?
そして、
映画の始まりは...
Julian: Just ... be normal.
Grand-mère: And this is what you've learned? To be normal?
Julian: What's wrong with normal?
Grand-mère: Nothing. And everything. I, too, wanted to be
normal when I was your age, but...
Julian: But what?
Grand-mère: I'm sure your father has told you stories about
what happened to me when I was a young girl.
Julian: Some. He says you don't really like to talk about it.
Grand-mère: I don't. But now, I think, for your sake, I must.
サラは、Julian(英語名にしたのは意味があります。)の父親、つまり自分の息子にも話さなかったことを孫の為に過去に起こった出来事を話し始める。
ドイツが1940 年 5 月にフランスを陥落した後、大戦中ドイツから比較的制限を受けない "The Free Zone(フラ語 zone libre )" という場所が次第にナチスによって統治され町自体が、またそこに住む人自体が変わり、それによってサラを含むユダヤ人が迫害されるようになる背景をこの映画はバックボーンとして描いている。 "The Free Zone" という言葉は、映画を見終えてから考えるとその呼び方が個人的には不適切に思える。
映画サイトなどを見ると概ね評価は高い。それは、原作に沿いながら、サラとJulienの二人の世界に焦点を当てて、ぶれていないストリー展開にしたことで、閉塞感のある納屋というワンシチュエーションなのに飽きさせないものとなっているところかもしれない。付け加えるなら、有能で、それを上回る人への優しさを与えるこころを兼ね備えているJulien に対して人として名前を呼ばない、ある動物として呼ぶ者に憤りを覚え、またそれ以上に強く嫌悪を抱いてしまう。
原作のグラフィックノベルにはセリフとしてラストに少しだけ出てきていたサラの想いが、彼女の日記の一文として載っていた。それは...
The entry that Sara wrote on her birth was written, "28 May, 1944 - Such a beautiful night, with beautiful people! How blessed am I to have the Beaumiers in my life! Thank you, life, for all you have given me. Mostly, the belief I now have that all human beings in this world are somehow connected to each other. Maybe I always knew this, but from my little window inside my little barn, I can actually hear the secrets of the world in the still of the night. I swear there are even times when I can hear the planet spinning! I can hear in the flutter of bat wings, the quickened heartbeats of the maisquards hiding in the mountains. I can hear in the soft cooing of the night owls, my papa, somewhere, calling my name. Funny, I used to be so afraid of the night. But now, I see it as my time for listening to the soul of the world telling me its secrets. And tonight it whispers, over and over again like a song: "You love Julien" Yes, I answer, I know. I love Julien."
観終わって...
white bird とは?
自由の証なのかもしれない... でも原作では、white hummingbird とより特定が出来て具体的になっている。
その象徴的意味合いは、"Hope and healing" もあるけども彼女の日記を紐解くとAIの解説より
Hummingbirds can have a spiritual significance and mean
the spirit of a loved one is near.
原作と一番違うところは、エピローグの部分を原作にはないサラとJulianのシーンに変えることでとても見やすくなっているところかもしれない。ただ、撮影場所として現在の場面はニューヨークで第二次大戦中のシーンはフランスでなくチェコ共和国がロケ地となっている。その自然豊かなチェコの美しい自然を背景にCGIで補てんしているシーンが素人目でも分かるので本作の質をいくぶん落としているようにも感じる。それとエピローグを別の話に変えたことで、見やすくなり、万人が感動を呼ぶ作品にはなったけれども...そうはなったけれども、ある超が付くほどの有名な日記を基に作られた過去の映画と包括的印象が似通ってしまうのが、目に見えない後悔というジレンマとなってしまう。
主演を演じた若い二人の役者さんは、映画とのマッチングが凄く良かったのが映画をよりよく見れる救いであり、癒しなのかもしれない。そして "white bird" のおかげで悲しい話だけどあまりシメッポクはありませんでした。
最後に一言
Vive l'humanité!
全20件を表示