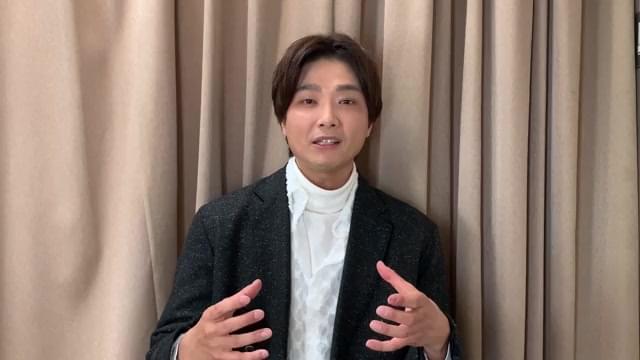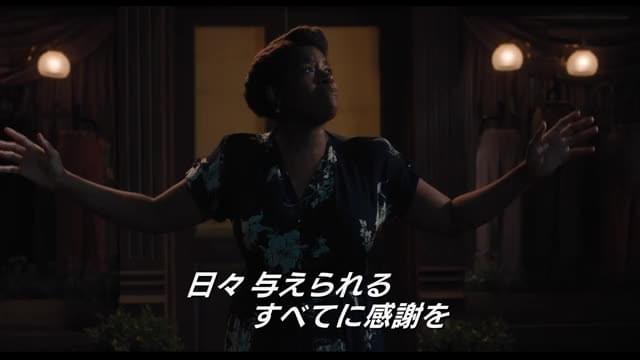「過酷な環境下で、尚も“正しさ”を見失わずに生きられるか?」カラーパープル 緋里阿 純さんの映画レビュー(感想・評価)
過酷な環境下で、尚も“正しさ”を見失わずに生きられるか?
【イントロダクション】
20世紀初頭のアメリカ南部を舞台に、1人の黒人女性の波乱に満ちた人生を描いたヒューマンドラマ。
アリス・ウォーカー原作の同名小説を、ブロードウェイでミュージカル化した作品を基にミュージカル映画としてリメイク。1985年には巨匠スティーヴン・スピルバーグ監督がウーピー・ゴールドバーグ主演で映像化しており、スピルバーグは本作では製作を務める。
監督にブリッツ・バザウレ、脚本にマーカス・ガードリー。
【ストーリー】
1909年アメリカ、南部ジョージア州。アフリカ系アメリカ人の街に暮らす14歳の少女セリーは、妹のネティと共に高圧的な父アルフォンソ(デーオン・コール)の下、姉妹で支え合いながら生活していた。セリーはアルフォンソとの間に2人の子供を儲けており、2人とも出産後すぐに彼の一方的な判断で子供のいない家庭に売り渡されてしまっていた。
ある日、ネティは農夫の“ミスター”ことアルバート(コールマン・ドミンゴ)に見初められ、ミスターはアルフォンソに「嫁にくれ」と願い出る。しかし、父親は美人で教養もあり、教師になる夢を持つネティを手離すことを拒み、代わりにセリーを牛一頭と卵と引き換えに嫁に出した。
セリーは反論すら許されず、その日の内にミスターの家に嫁に出された。ミスターの家は荒れ放題で、先妻との間に儲けていた3人の子供達の世話、家事全般を押し付けられる。ミスターは少しでもセリーの働きに不満を抱くと、容赦なく彼女を責め立てた。
過酷な日々を過ごすセリーのもとに、アルフォンソから身体を求められたネティが家を飛び出してやって来た。だが、本命であったネティに対してミスターが何もしないはずもなく、ネティに拒否されるとミスターは激昂して彼女を土砂降りのなか家から追い出した。セリーとの別れ際、ネティは手紙を出す事を約束するが、ミスターはセリーが手紙を受け取る事を許さず、毎週届いていたネティからの手紙は隠されてしまっていた。
1917年。成長したセリー(ファンテイジア・バリーノ)は、相変わらず過酷な日々を送っていた。ある日、ミスターの息子ハーポ(コーリー・ホーキンズ)は、気が強く快活な女性ソフィア(ダニエル・ブルックス)と結婚した。ハーポはミスターの家の近くの沼地に家を建て、セリーはソフィアと友人になる。だが、ソフィアは自らを服従させようとするハーポに抵抗し、生まれたばかりの赤ん坊を連れて出て行ってしまう。
1922年。ハーポは沼地の自宅を酒場に改装し、人気歌手のシュグ(タラジ・P・ヘンソン)を街に招いた。シュグは、ミスターが長年想いを寄せていた人物であり、彼女の滞在場所として自宅に招き入れる事を喜んだ。やがて、セリーはシュグと親しくなり、シュグが居る間は、セリーはミスターの暴力から解放されていた。店は繁盛し、万事上手くいくかと思われたが、シュグは巡業の為にしばらく街を離れるという…。
【感想】
スピルバーグ版の同名作は未鑑賞。
掴みの上手さ、つまりはキャラクターへの容赦のなさが素晴らしい。
セリーの人権や女性としての尊厳をひたすらに無視された前半の展開は観ていて辛いが、彼女への抜群の感情移入を促している。
家父長制による圧力、近親相姦と産まれた我が子を取り上げられる理不尽さ、自身を「ブサイク」と評した男の元に突然嫁がされ、彼の子供の世話や家事、性欲の捌け口にされる日々。
序盤は特に、アルフォンソとミスターのネティを巡るやり取りに、男性優位社会における女性の“モノ扱い”ぶりが顕著に現れている。
「(ネティの代わりに)セリーはどうだ?ブサイクだが男並みに働く」
「“あれ”か?要らねえ」
「子供達(の世話)はどうする?」
と、互いにまるでセリーをモノかのように捉え、召使いとして酷使しようとする。その身勝手さと傲慢さ、また1人の女性の人生を牛一頭と卵で簡単に引き換えてしまう残酷さは筆舌に尽くしがたい醜悪さ。
そんなセリーの姿を描いているからこそ、終盤の形勢が逆転していく展開はカタルシス十分だし、彼女とは対照的なソフィアとシュグの自らの意思で生きていく逞しさと奔放さには勇気づけられる。
特に、ソフィアの物怖じせず何事にもキッパリと「NO!」の意思を示す姿は見ていて清々しい。だからこそ、そんな彼女ですら抗う事の出来なかった“白人至上主義社会”の残酷さが際立つ。彼女をメイドとして雇おうとする市長夫人の傲慢さ、投獄の果てに自由意思を奪って使役する姿は、ともすればミスター以上の悪かもしれない。
街の醜聞のネタにされながらも、歌手としての人生と奔放な性生活を謳歌するシュグの「ありのままであり続ける」という姿は、作中最も現代的な人間像かもしれない。だからこそ、彼女はセリーを助ける事も、良き友人として接し続ける事も出来たのだろう。
スピルバーグ版はミュージカル映画ではなかったそうだが、本作をミュージカル映画として再び世に放ったその英断に拍手を贈りたい。
作品を彩る楽曲の素晴らしさ、エモーショナルな歌詞が突き刺さる。
【クライマックスに見る“赦すこと”の意義】
セリーがアルフォンソの葬儀後、彼との間に血縁関係の無いことを知り、母親名義だった店の土地を相続し、培ってきた裁縫の才能を活かして自立する。
セリーが自分自身を、そして自分の人生を肯定出来るようになった姿に感動し、同時に勇気づけられる。なぜなら、それらは全て彼女がどんな苦境に立たされても正しく在り続けた事に対する結果だからだ。神は彼女の清廉さの中にこそ宿っていたのだ。
ラスト、ミスターは自らのセリーへの行為の償いとして、農園の土地の一部を売却し、ネティ達が帰国出来るように手配して、復活祭に招く。
ネティとの再会、そして息子と娘との再会、更には初めて孫の存在を知り、彼らの頬に触れる。正しく生きてきたセリーの人生が報われ、彼女の全てが肯定されたかのようなあの瞬間は、目頭が熱くなった。
ところで、ミスターのこの贖罪は、これまでのセリーとネティに対する仕打ちを帳消しに出来るものだったのだろうか?人によっては、この行為が十分な贖罪とは感じられず、不満を抱く人もいるだろう。しかし、ミスターがネティを追い出す事をしなければ、彼女はセリーの子供達と再会して旅をするという人生は歩めなかったはずだし、結果として、セリーは想像以上の幸福を手にする。運命とは、タイミングの巡り合わせで形作られているのだろう。
また、ミスターの贖罪はこの先も続いていくべきであり、決してこれで終わったわけではない。彼はこの先も、セリーに対する償いを続けていくべきだし、改心した彼ならば、それが出来るのではないかと思う。
大事なのは、ミスターを復活祭に招き、“友人”として在る事を選択したセリーの姿だ。
昔、TVで被害者と加害者の和解について、心理学者の教授がコメントしていた事を覚えている。それによると、心理学的な観点から見ても、被害者が先に進むために1番重要なのは“許す”という行為なのだそうだ。
つい最近、Xで《幼稚園時代や小学生時代に、教師から「××ちゃんも謝ったから、○○ちゃんも許してあげてね」と言われる事が苦痛だった》という投稿が反響を呼んでいた。確かに、まだ判断力も自分の意思表示もままならない中で、納得のいかない“許し”を相手に与えるよう強要される事は、被害者にとっては「大人の欺瞞」であったことだろう。
しかし、成人して判断力や意思表示の仕方を学び、身に付けた人ならば、この“許す・赦す”という行為について、また違った視点から判断出来るのではないかと思う。それは、「自分が前に進むため」にこそ行って良いのだという事だ。断言するが、それは決して、相手のためである必要はない。あなたは被害者であり、受けた傷と記憶を完全に消し去る事は出来ないかもしれない。しかし、あなたが自身の人生の駒を前に進め、よりよき人生を手にする為ならば、許してみる事も重要なのではないだろうか。あなたが幸せになる為ならば、100%の利己的な理由から許して良いはずだ。
勿論、物事によって程度の差はあるし、一生許す事が出来ないこともあるだろう事は理解しているつもりである。これはあくまで、一つの解決策としての提案である。
セリーは、ミスターの改心を受け入れ、“赦した”事で更なる幸せを得た。その姿に、現実の私やあなたがこの先の人生で誰かを許した先に、同じく幸福が待ち受けていてほしいと願うのだ。
【総評】
過酷な人生の中で、それでも正しさを見失わずに生きた女性が最後に幸福を掴み取る姿は、現実の我々の背中を後押ししてくれる。優れたフィクションとは、我々が過酷な現実に立ち向かう為の勇気を与えてくれるものなのだ。
それらを豊かな色彩や楽曲でエモーショナルに表現したスタッフに感謝の拍手を贈りたい。