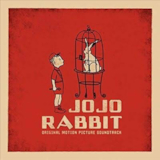ドント・ウォーリー・ダーリンのレビュー・感想・評価
全104件中、41~60件目を表示
良質のスリラー映画
【鑑賞のきっかけ】
本作品は、予告編の不穏な雰囲気に興味を惹かれ、劇場鑑賞を決めました。
【率直な感想】
<違和感のある空間>
主人公アリスは、夫と優雅な生活を送っていた。
ところが、あることをきっかけに、悪夢とも幻想ともつかないものを見るようになっていく…という、いわゆる「スリラー」映画です。
アリスの暮らす町というのは、同じ企業らしきものに勤めている人たちの言わば、社宅。
社宅と言っても、日本のような集合住宅ではなく、庭付きの一軒家が並んでいる。
毎朝、その家の夫は、妻が見送る中、乗用車を運転して、出勤していく。
アリスを含め、家に残っている妻は、専業主婦らしく、家事をこなし、余暇はダンスを習ったり、隣近所の奥さんと会話をしたり…。
私が、この世界に最初に感じた違和感は、「スマホ」がないことでした。
電話は、旧式の有線のダイヤル式のもの。
そういう目で見てみると、使っている掃除機やテレビも何だか古めかしい。
時代で言うと、1960年代くらいの風景です。
そこで思ったのが、妻たちが全員、「専業主婦」ということ。
現代なら、例え夫が高収入でも、妻が働きに出るというのは珍しいことではありません。
これも、1960年代だから?
ストーリーは、どこを紹介しても、ネタバレになってしまうので触れませんが、主人公アリスの前に現われる事象がとにかく奇妙なものが多く、彼女のいる世界にはどんな秘密が隠されているのか、という興味で、物語にどんどん引き込まれていきました。
その「秘密」というのは、それほど斬新なものではないけれど、2時間という物語を十分に引っ張っていくだけの魅力に満ちた作品だと感じました。
【全体評価】
大抵の映画がそうなのですが、物語が終了すると、タイトル「Don't Worry Darling」が画面に映し出されます。
それまで、タイトルを余り意識しないで鑑賞していたのですが、物語の全てを知ったうえで、このタイトルを見ると、妙に納得してしまうのですよね。
そんな意味でも、印象的なスリラー映画でした。
どうなるどうなる、と。
クローズワールドの妙味
安心して家にいて良いんだよ
広い家、イケてる車に乗って毎日仕事に向かう稼いでそうな夫、それを毎朝見送り家事をこなす妻。完璧に見える住宅街に何かおかしなところを感じ始める主人公アンナの話。
最近こういう、幸せに思えるのになぜか家に閉じ込められてるような気がする、怖い!って感じのスリラー多くて、逆に笑えてくる。奥さんが文句ひとつ言わず家事して幸せそうなんて絶対何かある怖い!ってすごく現代の感覚だよね(笑)この感覚分からなくても全世界全員コロナを体験してずっと家にいる恐怖(?)を味わってるから男性でも共感できるはず。
タイトルが実は『ドント・ウォーリー・ダーリン』というすごく優しいタイトルだったということを2時間不穏な雰囲気を見せられすぎて忘れる。でも、ほとんど終盤幻想のジャックが表れて「ここにいよう」と言われた後に何かを悟ったようにアンナは世界から抜け出すシーンからタイトルが表れて、急に優しい気持ちになれたような皮肉が効いていて爽快なような気分になった。
妻が家から出て仕事をしに行っても何も心配いらないんだよ、安心して家にいて良いんだよ?っていう優しさと捉えるか皮肉と捉えるか(笑)
ただ、結何かがおかしい、気持ち悪い、主人公が狂ってると思われるシーンが7割なので結構長く感じたしイライラした。良い意味でアンナは等身大の女性だから上手く駆け引きができないのが結構ヘイト溜まった。
まさにカオス😆
その後が気になる
絵作りも世界観も演技も良いのだが・・・
この手の映画で女性の自立につなげる勇気
住んでいる家やコミュニティが少し変って映画はたまに出てくる。広い意味では「マトリックス」もその1つ。だから、この手の映画が出てくるとどんな話なんだろう?ということが1番気になってしまう。
本作も気になっていたのはそこ。この作りものっぽいコミュニティがなんなのか?ってところが1番気になっていた。いろいろとミスリードも仕掛けてきていたし。これはなんなの?と思っていたら、後半なるほどそれね!って感じ。
後半の怒涛の展開は悪くない。カーアクションもショボいし、全然ドキドキしないけど。何より終わり方がよかった。あの音だけで表現するかー!って感じだった。
何より音楽がよかった。「古き良き時代」って意味の50年代〜60年代を表現するのに最適だし、BGMとしてかかる不穏な雰囲気の不協和音のサウンドもかなり印象に残った。
で、テーマは女性の自立ってのもなかなか興味深い。こんな描き方もアリだ。男は未だに「妻を守る夫」と「夫を支える妻」って構図を追い求めてしまうのだろうか。男どもは本当の意味で妻を守れやしないのに。でも、こんなエンタメ作品でそんなことを考えさせただけでもオリビア・ワイルド監督の目的は果たしたのかもしれない。たしかに、「ブックマート」も全然違う種類の映画なのにそんなテーマだったかも。侮れないな、オリビア・ワイルド!
大作に隠れた秀作
オリビアワイルドにこれだけの力量があったとは、と思わされる一作。今回女優としても重要な役割を担う彼女だが、映画監督としての才能も素晴らしい。
1950年代のアメリカ。ユートピアを築くビクトリー社のビクトリータウンに住む幸せな若夫婦。飛行機の墜落事故を目撃した若妻が、立ち入り禁止の会社本部に行ったことから歯車が狂い始める。
フローレンス・ピューはアニャテイラーと双璧をなす若手実力女優だが、今回は彼女の真価が十二分に発揮されている。ロマンティック、サイコホラー、スリラー、アクション様々なシーンを見事演じきった。
SEの多用はやや耳障りだが、声のサウンドは気味悪く世界観をよく表している。全体的に没入感のある作品に仕上がっている。見せ場も数多く、印象的なカットも多いため、見応えがある。
贔屓目
違和感と妖艶さが首筋をなぞるユートピア
フローレンスピュー、ハリースタイルズの2人が誘うどこか様子のおかしいアメリカンユートピアをひたすら不穏に描いた本作。
雰囲気、キャラクター大好物なのにあまりハマらなかった。
日常を描くことがテーマであるのは理解できたが、少し冗長だと感じた。
オリビアワイルド監督が描く女性の逞しさは凄まじく現代のジェンダー観のトップを直走っていると思う。
前作のブックスマートとも大分毛色が違う作品でオリビア監督の懐の深さを垣間見た気がした。
主演のフローレンスピューの得体の知れない恐怖に対しての演技はいつも通り圧巻で、ハリースタイルズのセクシーで正統派の紳士かと思えばかつ狂気じみた湿った気持ち悪さも出せることに驚いて見入った。
中毒感のある不気味さ
この世界は・・・
白いウサギではなく墜落する飛行機を追いかけて覚醒する専業主婦版『マトリックス』もとい『不思議の国のアリス』
舞台は1950年代のカリフォルニアにある砂漠の中に造られた小さいながらも美しい街ヴィクトリー。夫ジャックと何不自由ない暮らしを送っていたアリスだったが、突然起こったある事件をきっかけにその理想的な街を覆う巨大な謎の存在に気づき始める。
プロット的にはM・ナイト・シャマランが好きそうな感じ、すなわち星新一のショートショートの一編にありそうな物語。ここで痛烈に槍玉に上がっているのは旧態依然とした男性優位社会。それが揺るがないシステムとして機能する世界へのノスタルジーに縋る男性達に対する強烈なアッパーカットになっています。そんな“不思議の国”で覚醒するアリスを演じるのはフローレンス・ピュー。日常が少しずつ崩れていく焦燥を見事に体現しています。クリス・パイン、ジェンマ・チェン、ハリー・スタイルズ等の怪演もキラキラと怪しく輝いていますが、やはりアリスの親友メアリーを演じるオリヴィア・ワイルドが頭一つ抜きん出ています。常に優雅な笑顔を絶やさない彼女に『マトリックス』のサイファーを思い出した人も少なくないでしょう。
ネタバレに留意するとこの程度のことしか書けず歯痒いですが、2作目にして確固たる作家性を確立したオリヴィア・ワイルドの快挙に惜しみない拍手を捧げたことは付け加えておきます。
アメリカの荒地の新興住宅地、時は60年代あたりか。絵に描いたような...
結末が分かりません
「ユートピア・スリラー」という触れ込みに関心を持ち、都合の良い時刻に上映時間が合ったので、観ることにしました。
何か怪奇的な現象が起きるのだろうか?と思っていたのですが、物語の流れは「夫婦のきわどいラブ・シーン」→「ややSFがかった展開」→「ややスリラーがかった展開」→「ややアクションがかった展開」という風に自分には思え、結末がどうなったのか分からず仕舞い(制作費が尽きたのでしょうか?)でした。
この作品の見所は、私には、合間に登場するダンサーたちの脚線美を生かした、華麗なダンスのように思えました。
ユートピアと信じられていた街が、実は虚構であったというストーリーは、21世紀の映画作品としては、ずいぶんと古めかしいように思いましたが、観る人によって、感想が大きく分かれると思いました。
全104件中、41~60件目を表示