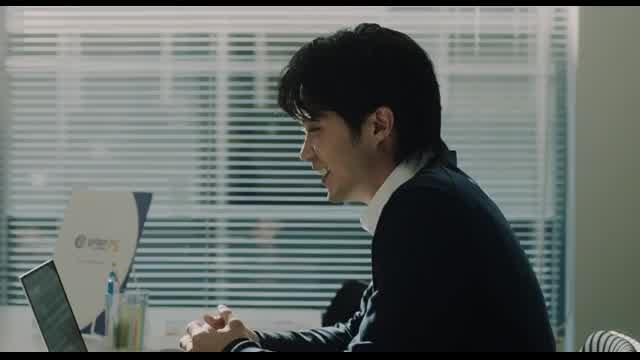PLAN 75のレビュー・感想・評価
全94件中、81~94件目を表示
滅んでいっても良いではないか
最近、BSで倍賞さんの映画(遥かなる山の呼び声、駅STATION)を見たばかりなので、どうしても”その後”が知りたくて、劇場までわざわざ足を運んだ。改めて、戦後の日本および日本人の足跡そして行く末を暗示していたと思う。結局、そうなんだね、やっぱりね、と。「楢山節考」もそうだけど、フランスの人ってこういったテーマ設定がえらくお気に入りなのだと改めて感心。さて、根底にあるものは、、、?映画的にはカタルシスが不足していて、ややモヤモヤが残りました。
タイトルなし(ネタバレ)
長編デビューとなった早川千絵監督が描いたのは、75歳以上が自分で生死を選択できる制度「PLAN75」がある近未来の世界。数年後には、5人に1人が75歳以上になるとされる日本で、この問題はもはや他人事ではない。そう感じざるを得ないリアルな内容に胸が抉られた。
磯村勇斗演じるヒロムが優しい役所職員を演じているが、この世界においての処刑人、死神にすら見えるダークなテイスト、そんな中に人間としての感情が垣間見える役を熱演していた。
河合優実演じる成宮が個人的に一番好きなキャラクターで、死をいかに辞退させないか、そしてそれは正しいのか?、という難しい役を若いが故に揺れ動く感情を電話越しの声、表情で見事に演じていた。スクリーン越しに目があった時、あなたならどうするか、問われた気がした。
相当重いテーマ
少子高齢化が進んだ近未来の日本では、満75歳から生死の選択権を与える制度、プラン75、が国会で可決された。これは、超高齢化社会の問題解決策として世論に受け入れられたためだった。夫と死別し、ひとりで暮らす78歳のミチは、ホテルの清掃員として働いていたが、ある日高齢を理由に解雇された。家賃も払えなくなり、住む場所を失いそうになった彼女は、プラン75、の検討を始めた。一方、市役所の、プラン75、申請窓口で働くヒロムや、死を選んだお年寄をサポートするコールセンターの瑶子らは、プラン75、の在り方に疑問を持つようになった。 、という話。
倍賞千恵子が歳とったなぁ、というのが第一の感想。寅さんでサクラを演じてた印象が強く、今でも寅さんシリーズで若かりし頃のサクラを観ることが有るから、余計にそう思うのかも。
最後に、倍賞千恵子は死ななかったが、家も無くなるし、どうするのだろうと、少し気になった。
75歳から安楽死の選択が出来るようになるシステムを導入する、というのが少子高齢化対策で、それを65歳に引き下げるようなアナウンスも有ったが、いくらなんでも、年金を一切払わないなんて有り得んでしょう、って感じた。
しかし、近未来、人口が6000万人になるとの予測も有り、現実問題として年金が出せない世の中になるかもしれないと、本気で少子高齢化対策を考えるべきであり、相当重たいテーマだと思った。
ミチ役の倍賞千恵子も良かったが、磯村勇斗と河合優実が自然な演技で素晴らしかった。
個人的には大賛成の制度
75歳以上が生死を選択出来る制度があったら
貴方はどうしますか?
個人的には大賛成です。
65歳とか55歳でもいいです。
何故なら幸せと感じられるうちに死にたいから。
自らゴールを決めることによって
生き方は大きく変えられます。
ゴールが見えないから不安になる。
そもそも今の与党は利権関係者には
惜しみ無く税金を使うけど困窮する国民に対しては
経済制裁レベルの厳しさ。
多くの先進国がコロナ禍で減税を推し進める中
頑なに消費税を下げない理由は?
来年からはインボイス制度という地獄も。
社会保障にのみ使うと明言した消費税は
大企業の法人税減税の穴埋めに。
今年から高齢者医療費は倍増し
年金カット法案まで始まる。
財源がないと繰り返すのに
防衛費は幾らでも増やせる不思議。
老後資金に2000万貯蓄が必要と
有識者が言えば岸田総理は投資に回せと。
飽くまで政策より自己責任。
それでもそれなりの幸せもあります。
それなら幸せと感じられる
タイミングで人生を終えたい。
だから倍賞千恵子さん演じるミチの最後の行動に
何故?と思ってしまいました。
【”深刻な高年齢化社会に対し、哀しき警鐘を鳴らす作品。”早川千絵監督の作品制作の意図は、現代日本社会の不寛容な哀しき実態を、強烈な設定を敢えてする事で訴えかけているのだ、と思った作品。】
ー 今作は社会に対するメッセージと共に、”自分の死の在り方を考える”作品である。ー
◆感想
・冒頭の青年が老人ホームを襲撃する強烈なシーン。そして、彼が自身の行動をモノローグで述べた言葉に、怒りが沸騰する。
ー ”日本の高度経済成長期を支えてきたのは、70代以上の方々だぞ!何だ、その不寛容で身勝手な思い違いの思想は!”-
・そして、高齢者を社会衰退の原因と捉えた殺傷事件多発を受け、政府が”PLAN75"という75歳を迎えた国民一人一人が自ら死を選択出来る制度を導入した事がTVで流れる。
そのニュースをやや哀し気な表情で聞くミチ(倍賞千恵子)。彼女も”PLAN75"に該当するのだな・・、と言う事が分かる。
・ミチはホテルの客室清掃の仕事をしているが、同じく高齢の仲間の女性が倒れたために、馘首される。
ー ホテル側の言い分は”高齢者を働かせて可哀想だ・・、という電話が入ったからという理由だが、”何を言っている。交通整理や、公共・民間施設のトイレ掃除(とても、尊崇な仕事だと思っている。)などは殆ど、高齢者の方々がやっているではないか”と再び、不寛容な社会に対し、イライラが募る。-
・そして、倒れた女性は自宅で独り孤独死しているのを、ミチが発見してしまう。
ー 仕事も中々見つからず、ミチは”PLAN75"に申し込みをし、加入者に配られる10万円を手にする。人生の総括の値段が10万円?しかも、”共同火葬”だと?ー
・心臓病の5歳の子供を母国フィリピンにおいて、出稼ぎに来ているマリア(ステファニー・アリアン)は政府直轄の”PLAN75"を運営する会社で働き始める。理由は時給がとても良いから・・。
ー 彼女ともう一人が行っている遺品整理のシーン。アウシュビッツのナチスを想起してしまった。”PLAN75"等という愚かしき制度は、何のことはない、民族粛清を行ったナチスの行為を通じるところがある事に、気づく。-
・ミチが、”PLAN75"のコールセンタースタッフの揺子(河合優実)にお願いして、一緒にボーリングに興じるシーン。
ー 良いのか?情が移るのではないか?違和感を感じたシーンである。-
・”PLAN75"の職員ヒロム(磯村勇斗)が20年振りに叔父(たかお鷹)と出会うシーン。叔父は音信不通であったが、身なりから推測するに零落しているようだ。
だが、叔父は誇らしげに言う”日本中の橋を作って来たんだぞ!”
ー この叔父も又、日本の高度経済成長期を支えてきた事が分かるシーンである。-
・そして、ミチと叔父は偶然”その日”を隣同士のベッドで迎える。
だが、ミチは自分で死に誘う呼吸機を外し、叔父はそのまま息を引き取る。
ー このシーンでのミチの心象が、もう少し分かればなあ・・。
一方、ヒロムは、叔父を”共同火葬”させまいと、叔父の遺骸を車に乗せ猛スピードで火葬場に向かうが・・。-
<ラスト、暮れ行く夕陽を眺めるミチの表情の解釈は、観る人によって違うだろうと思う。
私は、”自分の人生を”その時”が来るまで生きてみよう・・”ミチが思い返したように見えた作品である。>
■追記<2022.6.26>
拙レビューの中で、致命的な固有名詞ミスが幾つかあり、御指摘を受け修正しました。
ご寛恕願います。ドラムスコさん、有難うございました。
念願の寿命が伸びて人類は、、、
アインシュタインの基礎理論が原爆に利用されたように、先人が長い歴史の中で知力を尽くして生み出した、医療や食糧生産技術、そして資本主義が、意図せぬ大問題を呈してしまった現代社会。カルネアデスの板のような哲学的思考に陥り、悶々と矛盾を反芻しながら鑑賞。
命の選別という重いテーマにも関わらず、この映画では誰も泣き叫んだりしない。そして絶対悪も登場しない。だから尚更、登場人物の内なる慟哭が伝わってきて辛い。
結局、献身性を制度設計のベースに置くと、みちさんの様な善良で真面目で周囲への気遣いをする人が犠牲になる。
自由意志とは、定義が難しいのだが。監督が、生きているという事、それだけで素晴らしいこと、と仰っていましたが、私も、人は生きている限り、生きているべきだと思う。病気による安楽死問題は、また別次元として。
生命への冒涜は、許されないと思う。
倍賞千恵子さん、主人公の人となり、感情を、抑えた演技で見事に好演。歌声が伸びやかで素敵でした。磯村勇斗さんも、仕事とパーソナルな感情の狭間で揺らぐ心情を上手く表現。
カンヌの報道直後のせいか、いつもスカスカなミニシアターがほぼ満席でした。それだけ少子高齢化問題への関心が高いって事だし、実際街も映画館も高齢者だらけ。
いろいろ考えさせられる映画で、学校教育の教材としても良いんじゃないかと思いました。
意欲は認める
鑑賞後に残念感が充満する。ラスト20分、多くの何故を残しながら、早川監督は登場人物の決断の瞬間や行動のディテールを描かないことを選択した。マタゾウ的には物足りず、せっかくのテーマが浮いてしまった。
技術的には、撮影は素晴らしかったし、役者も皆さん適切だった。スター倍賞千恵子、その朝の痩せた指が印象的。磯村勇斗、マリア役(失礼)、たかお鷹、それに出番は少ないが泣かせるシーンを担当した河合優実。
カンヌで何らかの賞を得られ、世界で公開されるチャンスが得られているとのこと、なにはともあれおめでとうございます。他国の評価を見てみたいです。
新宿ピカデリーの舞台挨拶回を鑑賞。倍賞千恵子、磯村勇斗、マリア役の方、監督の4名が登壇。お互いの絡みについてあまり語らないなあと思っていたが、劇中もほとんど絡まず事後納得。そして舞台挨拶終了後映画を見ずに出ていかれる前列の女性陣が結構多数で驚いた。
淡々と丁寧に
わたしは基本的に死も選べることに(安楽死も含め)
肯定派なので、こういう制度は否定はしません。
が、選んでるのか選ばざるをえないのかは
正直なんとも...。
ただミチさんの慎ましく、凛と生きる姿は美しくて
夕方は荒れるという天気予報のなか
夕日を眺めるミチさんの最後のシーンは
未来を感じて力強く清々しかったです。
言葉で語るというより
表情や間、空気感で表現していて
本当に実力派の演者さんたちが見事でした。
辛い映画だ
結局、倍賞千恵子は死にきれなくて、磯村勇斗は叔父を送り出せなかった。
誰もが中途半端で終わってしまう本作。
それでも、明日が来て、それでも生き続けなければならない現実。
それは、どんなに綺麗事を語ってみても、納得のいく人生なんか存在しないと言っているような気がする。
誰もが年をとる
ラストシーンが朝陽なのがわからない。
そこを抜け出しても待っているのは、ある意味地獄。
人生という迷路の中、踠きながらも懸命に生きてきた。
それが老いというだけで、出口が見えないまま、排除
されて行く。孤独に苛まれ、選んだのは死。だが生へ
の渇望が芽生える。
だらだらと尺を廻し、意味のないカットを織り混ぜ、
3つのエピソードも中途半端に終わる。
星3つは出演者の素晴らしい演技。
私はフランス人の感性がわからない。
ただ単に、私がついていけないだけかもしれませんが。
(余りに長すぎるので便宜上のネタバレあり/ネタバレなし。法律的な観点や他の方の疑問点など)
今年171本目(合計447本目/今月(2022年6月度)18本目)。
まず、過去に3.5評価した映画は、2021年度の「樹海村」(極端にグロテスク、食事ができないような発言をする)、「DAUナターシャ」(モロに本番行為)だけです。
また、私自身が行政書士合格者で、やや法律的な観点で見たというのも採点上関係するかもしれません。そこは人によって異なるので…(とはいえ、合格者(未開業者)含めて、弁護士~行政書士まで14万人しかいないとされるので、どうしてもレアなんでしょうね…)。
さて、映画の内容。
といっても、多くの方が書いているし、「なぜか」カンヌ国際映画祭で取り上げられたという事情もあれば、ここの特集でも書かれているように「75歳以上の高齢者に安楽死の権利を与える日本がやってきたら」というifを描く映画。
…と考えるだけなら、「いわゆる人権枠の映画」(個人的には「憲法枠」と呼んでます)なのでは?というところですが、一応には13条(幸福追求権)が該当しえるし、リアル日本でも安楽死の導入に賛否両論ある点は知ってはいますが、それを超えても内容が支離滅裂です。
また、映画内で「明示的には描写はされるが、なぜか表立って問題的されない」点についても傷が大きく(正直、ボランティア団体等から苦情が殺到しそう)、正直「配慮のなさ」がすごいです。どうするとこういう映画になるんだろう…。
…と思ったらこの映画、「日仏合作」(実際には、フィリピンも登場する。登場人物の一人が、フィリピンからの出稼ぎ(?)という扱いであるため)という事情なのか「日本の福祉行政まであまり考慮しなかった」のではないか…と思えるフシもあります。どうしても他国の細かい制度なんて知っている方は少ないですからね…。
とはいえ、これはさすがにブチ切れる内容です。
--------------------------------------------------
(減点1.5) 結局、下記に書きますが、「配慮のなさ」がとにかくすごく、ある程度の「耐性」が必要な映画です。映画って何らかの意味で娯楽枠なら娯楽枠、こういう映画のように「考えさせる枠なら考えさせる内容」というのはあるはずで、この映画は後者のほうにあたるはずなのですが、あれこれ珍妙な描写やら不愉快にさせる表現やら出てきて、さすがにブチギレラインです。
--------------------------------------------------
▼(不愉快なシーン) ホームレス排除?
→ この映画には「ホームレス」という語は一切出ません。出ませんが、ホームレスを想定する描写は2回存在します。一つは、ホームレスの方がベンチ等で横に「なれない」ようにベンチ等に仕切りを作るシーン(福祉行政では俗に「排除アート」という)、もう1つは「(制度が変わって)住民票がない方でも対象になります」という看板が出る(ここに卵か何かを投げつけられるシーンも存在する)ところ。
この映画はそもそも「国による安楽死はありかなしか」を問う趣旨の映画だったはずですが、「語句としては登場はしないが、ホームレス排除を想定した描写になっている」ところがあります(これらの点について予告は一切存在しないし、かといって、ホームレスの方に人権があるとかないとかという話も一切されない)。
これはさすがにどうなのか…というレベルで、映画の作成・公開に表現の自由・言論の自由があるように、ホームレスの方やその支援団体も、明らかな「趣旨違いのクレーム」でない限りこれについて意見を述べる権利はあるのであり、明示的に出ないとはいえ、なぜにこのような描写を2回も入れたのか正直謎な上に不愉快です(映画側 vs 支援者グループでバトルでも始まったらどうするんでしょうか…)。
▼(趣旨不明なシーンその1) 他の法律との関係
・ 単に最初に「いわゆるplan75、75歳以上の高齢者に安楽死の機会を与える趣旨の法律が可決され…」となっていますが、この法律は当然、他の既存の法律とバッティングします。一番の代表例は年金に関する法でしょう(これに応募して亡くなった場合、未支給年金は受け取れるかどうか等)。
ほか、映画内では「ギリギリ出るか」というだけですが、生活保護法との関係もあり、この法を「本気で」発動させると行政は「いや、生活保護を申請するならplan75を申し込め」とか言い始めることになるのは当然のことなので、福祉行政とも矛盾・抵触します。
さらには、民法上の不法行為責任(消極的な名誉棄損から、積極的な交通事故まで)についても、訴訟(民訴)になったときに「あなたはplan75に申し込んでいて、賠償する部分が存在しない」(原則として将来の逸失利益の賠償になるため。原則。例外あり)と言い始めると「不法行為祭り」です。換言すれば、このような法律のもとでは「高齢者は轢きたい放題」と化するのであり(もちろん、申し込んでいない人との間では、通常通り不法行為責任で賠償の問題になる)、倫理的に支離滅裂です。
※ 不法行為に基づく賠償が金銭賠償が基本で相殺が禁止されている理由が「不法行為の誘発の防止」である以上(最高裁判例)、それとも矛盾します。
▼(趣旨不明なシーンその2) 悪用される恐れ等に関する注意事項、描写がない
・ この年齢(75歳)にもなると、認知症が始まる可能性もあります。そのような場合には成人被後見人制度などがあります(ほか、保佐人・補助人という制度もあります)。特に「分別すらつかない」最も重いのは「成人(被)後見人」であり(面倒を見る人のことを「後見人」といいます。主には司法書士の方が担当しますが、法に触れない限り行政書士の方や、そもそも親族の方が任命されることがあります(家裁が担当)。
すると、そうした人が勝手に悪用すること自体は容易に想定がつきますが、これに関する描写は一切なし。
また、いわゆる「だまされたパターン」((民法上の)詐欺)など、つまり、
・ 心裡(しんり)留保(93) → する気もないのに「やるよ」という「うそつき」パターン
・ 錯誤(95) → 相手とのやり取りで思い違いがあり勘違いを起こすパターン
・ 詐欺・強迫(96) → 相手をだましたり、おどしたりするケース。
・ 無権代理、表見代理(110以下) → 勝手に相手の代理人になりすます、被害にあうなど。
----------
(※参考) 「きょうはく」は、民法上では「強迫」、刑法上では「脅迫」と漢字が違います。
----------
…などとの関係で完全に破綻をきたします(かつ、映画内では一切これらは出ないが、これらが絡んだら、命を奪うという行為であるが故に(単にお金をだまし取られた、などとは違う)、誰が責任を取るのか、というのが、完全に現行民法の想定する範疇を超越している)。完全に「何とでもなってしまう」、換言すれば「法の支配がない何でもありムチャクチャワールド」となってしまっているわけです。
※ わかりやすいのが「第三者の詐欺」のケースで、CがA(申込者)に詐欺を働いて、AがB(コールセンター)に電話をした、というようなケースでは、複雑になってしまいます。
まぁ、この映画はおそらくそれでも「もし日本で安楽死が合法化されていたら?」という趣旨の映画であり、法律云々をどうこういう論じる趣旨の映画ではないことは重々承知もしているのですが、「ホームレス排除?」と思えるようなシーンなど、明らかに配慮不足なところもあり、「ブチギレ度合い」はかなり高いです。
---------------------------------------------------------------
▼ (ここから、6月20日追加、他の方が書かれていた疑問点など)
※ 行政書士合格者レベルの回答です。
・ 「もし翻意した場合、手渡したお金はどうするのか?」
→ これは、リアル日本で、ハローワークを利用したときに早期に就職が決まったときにいわゆる「再就職手当」(昔は祝い金的に言われていたし、今でもその側面はある)と実質同じです。このあと、入った会社が余りにブラックですぐに離職したからといって、再就職手当を返せ、とは(客観的証拠があれば)言われないのと同じ話です。
※ リアル日本で少し前にお騒がせした、中国四国地方の某事件(誤入金事件)の「不当利得」とは扱いが違います。
・ 「私企業があんなことをやっていいの?」「勝手に会っていいの?」
→ 国も地方自治体もすべて、行政がすべての活動をやっているのではなく「民間委託」というものがあります(大阪市だって、ごみ収集は表向き大阪市ですが、実態は民間)。
その場合でも、国が行うべきことを代わりに行っているのですから、いわゆる「みなし公務員」の適用を受けます(この手の法律では、みなし公務員の規定は必ずあります。つまり、勝手に情報を漏らすななどは法律でカバーされます)。
ただ、このように「ほとんど死刑執行に近い行為」を民間委託するというのが実際上倫理的に変で(人違い等があった場合に国家賠償を提起されると恐ろしく面倒なことになる)ためかなり奇妙です(奇妙というより、「どこの国ですか?」状態)。
・ それだと、「意思表示すらできない寝たきり老人はどうするのか?」
→ まさにその通りで、映画内でこの点に関する描写がないのが非常に不自然かつ、複雑な論点を「逃げた」と言われても仕方がないでしょう。
要は、要介護4~5や重度身障1級の寝たきりの方は対象にならないが、75歳でも元気な人は対象になるという「妙な逆転現象が発生する」(映画の趣旨でいう「高齢者にかける税金の削減」「だけ」を考えれば、前者を対象にしたほうが良いのは明らか)という論点です。
・ 国民はこの変な法律に対して裁判を起こすことができるか?
→ そもそも支離滅裂すぎて「ここは日本ですか?」という状況ですが、いかに倫理的に変な法でも、具体的な事件が起きたとき、その事件を争うなかで法が憲法に違反する、という主張しかできません(付随的違憲審査制)。つまり、具体的な事件とは別に「この法は憲法に違反する」という主張(抽象的違憲審査権)は認められていないのです。
まぁ、この映画、本当にどこが舞台なんでしょうねぇ。
---------------------------------------------------------------
桜桃の味を思い出したり
私も自分自身の死について、ずっと考えているので公開を首を長くして待っていた。
解雇されロッカー整理の辺りから悲しくて仕方なかった。
河合優実さん演じる成宮さんがこちらを見た時にドキッとした。
GUNDAグンダのお母さんブタのような鋭い視線で
『あなたは傍観者のつもり?』と問いただされたような
ヒロムのおじさんの選択も間違ってるとは思わないし、
ミチのように生きたい人には何歳だろうと身体が不自由になろうと優しい社会であってほしい。
他人を死に誘導するようなことはあってはならない。
そういう気持ちを忘れないようにしたい。
強い作家性やメッセージもなく世にも奇妙な物語の一編を丁寧に2時間かけてリメイクしただけみたいな映画
是枝裕和もカンヌもこの監督の何に期待したのか不明ですけど、世にも奇妙な物語の一編を丁寧に2時間かけてリメイクしただけみたいな映画でした
そこに強い作家性やメッセージも一切ありません
雑な偶然で主人公は生き残るというラストでただ終わりでした
キャラクターたちの感情を丁寧に描くのはいいですが、そこには意外性も何も無いのでさっさと次いってくれの連続なんですよね
こっちの予想を上回ることのない展開がずっと続くのでひたすら退屈な映画でした
磯村勇斗や河合優実や東南アジア人女性のパートも倍賞千恵子とそんなに絡みがないし、倍賞千恵子のキャラクターに変化を与えられてないからカットして良かったぐらいです
そうしたら本当に世にも奇妙な物語の30分ぐらいの話です
けど、その脚本を世にも奇妙な物語に持ち込んでもネタが通らないぐらいのレベルでつまらないです
倍賞千恵子はまだ映画に出て主演して欲しいです
この駄作を遺作にしてはいけません
それぞれの年齢、感情、立場で観てしまう
日本初上映の試写会で観せて頂きました。
観る前は磯村さんサイドで観ていましたが、
51才という自分の年齢に照らし、いつの間にか
倍賞さんの所作が気になり始め、自分ならどうするか考えていました。数年経ってみたら違う感情で
観ることになると思いました。ラストシーンがとても好きです。
全94件中、81~94件目を表示