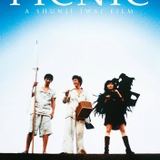すずめの戸締まりのレビュー・感想・評価
全1288件中、101~120件目を表示
新海誠は宮崎駿なのか?
いやね、マ王は宮崎駿も新海誠もどちらの作品も好きだよ😘
別に悪口を書くとかではないんだけど、クリエーターってどうしても変態が多いみたいでさぁ😅
どっちの監督も少女趣味が丸出しで気持ちが悪くなるのはマ王だけ?
そもそも日本人て変態率が多いと思う(100%に限りなく近い)←マ王はド変態のサディスト
さてカミングアウトはこれくらいにして映画の内容は新海誠にしては守りに入ったようなストーリーに少し驚いた😳
まさかの東日本大震災ネタ!!
まぁ10年以上経ってるけど少しばかり勇み足じゃないかなと💦
そしてマ王は「10年以上」という言葉を使ったけど被災者はまだ震災の真っ只中にいると思われるので(心身ともに)どんな形でも表現の一部に現実を取り込むのは早すぎると感じました😑
マ王はアマプラで2024年に観たけど、それでも気分が滅入ったからなぁ🤢
それに加えて大学生と高校生の恋愛でしょ(青春なんて言葉ではマ王は騙されない)
災害の設定は面白い表現方法だったけど物語としては厳しいね←有り得ないでしょ、あんな恋愛は普通
そしていい加減、RADWIMPSは止めてくれないか🙃
映画館での鑑賞オススメ度★★★☆☆
RADWIMPS度♪♪♪♪♪
新海誠の変態度❤️❤️❤️❤️♡(宮崎駿はMAX)
スズメの子供になりたかった
なんだちみの名は
実家閉じ師
この映画を見てから特に家の戸締りを気をつけようと思った。賃貸からミミズ出たら絶対大家さんに怒られるし、敷金も返ってこなさそう。あと実家の玄関とかよく開けっぱなし遊び行って帰ったらいつも閉まってたけど、あれ母さんじゃなくて閉じ師が閉めてくれてる可能性あった?
とにかく主人公の行動力に脱帽。宮崎→神戸→東京→宮城と桜前線に負けない勢いで北上してた。
なんとなく明日が楽しみなる作品。
動機は恋です。
端的に言うと、すずめという女の子が蒼太という男に出会って、日本中の地震を防ぐ話です。
暗い気持ちになれば僕達は、明日も、そしてずっとこうなのかなと憂鬱になります。
でも、そんなことはただの今がそうにすぎ無くて、きっと大丈夫だと思えるような、明日がどんな日になるか分からないけれど、なんだかほんの少し楽しみになる映画です。
作画は安定の素晴らしさ。それと、タイトルコールへの繋がり方が逸材。この完成度は今後数十年作れないと思う。
見終わったあとの爽やかさだけでもう充分傑作だと分かる。
思ったよりも
地上波放送で観ました。
映像と声優さんの演技は素晴らしかったです。
ただ、脚本が酷いです。(個人的な感想)
イケメンと通学途中に突然の出会い。
突然追い掛けて巻き込まれていくのですが、いきなり戸締まりやら、要石やら
説明があまりないまま話が進んでいきます。
話の展開が早いのもいいですが、
視聴者がきちんと理解できるような説明をして欲しいと思います。
最後まで見ましたが、
盛り上がっていたのは映画の中だけで、
こちらは何のこっちやという印象でした。
地震もネタのように使われて、
何がしたいのかわからない。
絵は綺麗
うーーーーん!
新海誠監督は描きたいことが壮大すぎるんだと思う その割に伝えたいことがシンプルなのでそこに段差があって見てて違和感が残るのかなぁ
それ、なんで?てポイントがたくさんあって、見終われば分かるのかなぁと思いつつ見終えたけど分からなかった
ファンタジー要素入れた作品こそ整合性というか違和感のない納得感、状況への納得感て大事だと思うんだけど、足りないんだよねぇ
その割にオチとして描きたいことだけハッキリしてて盛り上がらない 盛り上がるのは絵と音楽のおかげ 物語として興奮が足りない
泣きじゃくる4歳の子どもにあんな長々説明して一体何を納得させられると言うのか あれで希望持って扉をくぐったの違和感だった 良いセリフだと思うけど、明らかに観客に向けて語られててちょっと萎え
唯一、スズメとおばさんがお互い言い合ったシーンは良かった
言ってはいけないけど思ってしまったことがあって、絶対言う気はなかったけど言ってしまったことに、取り憑かれてたから〜とか説明するんじゃなく「それだけじゃない」だけだったのはすごく良かった
これまでの二人の生活が、ただその一言で分かり合える良き関係だったことがすごく伝わってきた
新海誠節
すごくよかった!
ジブリ愛が随所に散りばめられていて、本題の「扉」という意味でも、ハウルを連想させる。
すずめ役の原菜乃華ちゃんがとっても素晴らしくて、すずめが彼女で良かったと思った。
ほっくんはほっくんって感じで、スト担の自分には、草太というよりも松村北斗がずっと喋ってるという感覚。(良いのか悪いのかよくわからん笑。)
内容はちょっと重めなのかな。
時空系の話は頭がこんがらがってしまい苦手なのだが、考察は他の方にお任せするとして、その辺がよく分からなくても面白い。
また、地震国の日本だからこそ作れる作品だと思った。
扉を開ければそこは死の世界で、自然には抗えない、常に死と隣り合わせの国で生きている。
それでも、私たちは、好きな人と一緒に生きたい。平凡な日常を送りたい。
その切実な思いが感じられた内容だった。
個人的には、扉は潜在意識とか、記憶のことだと思った。
すずめの記憶が呼び覚まされた、みたいな。それを整理しに行く旅。
臭いものには蓋をする、ではなく、一度向き合って、記憶の扉に鍵をかけて、また前に向かって行ってきます、と。
忘れるのとは違う感覚。
でも、好きな人ができたというのも、辛い経験を乗り越えることができた要因の一つかなと。
愛の力って偉大!(アホっぽいよな。笑 いやでも割と真剣に。)
あと、環さんとすずめの喧嘩するシーンはかなり辛かった。
いくらなんでも言いすぎやん!と。短いシーンなのにダメージがすごい。
きっと、実際に地震の被害に遭った方々も観ると思うけど、新海さんなりに伝えたいメッセージが明確で、
決して軽い気持ちでこの題材を扱ったのではない気がした。
本当に閉じ師がいてくれたらな、と思わずにはいられない。
謎が多く、もう一回観たいと思う作品でした。
P.S. 新海さんは女の子が男物のブーツを履いてるのが好きなんだろうな。笑
3.11使うなら100年後で
右大臣?
新海誠監督は戦略家
100点
映画評価:100点
新海誠作品で間違いなくベスト1
そして、この作品を世に放ってくれて感謝します。
正直舐めていました。
冒頭の雰囲気や設定、展開を見て魔女の宅急便のオマージュくらいにしか思っていなかったです。
要石を再び封印するまでのスズメの成長秘話くらいにしか思ってなくて、まさかファンタジーじゃなくリアリティーショーだったとは…
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3・11を題材にしたお話しは多くあります。
そのどれも、中途半端に記憶を逆撫でする程度の腹立つ作品ばかりでした。
わざわざ現実に起きた悲しい出来事を思い出させ、辛かったね分かるよ~みたいな顔をして近づいてきて、そのくせ大した中身(内容)もなく、こちらの心を適当に傷つけるだけの………そういう作品ばかりでした。
でも、この作品は違いますっ!
私は違うと感じました。
【震災】という人ではどうにも出来ない存在を神と称し、その出来事によって埋もれてしまった人々の思いを【浄化】させていく
クライマックスに常世で垣間見た風景は、
そこに人が住んでいて、そこに様々な未来や思いがあって、そのかけがえのない一瞬を閉じ込めていました。
その当たり前だった日常が
たった数時間で壊される
当日の記憶と共に、そこに生きていた人たちの思いが私の心に入り込み涙が出ました。
スズメが忘れよう、諦めようとしていた
置いてきた(封印した)悲しい記憶。
そのせいで漠然と生きてきてしまった…
「死ぬのは怖くない」
そう自分の心に蓋(黒塗り)をして、
まるで死に場所を探しているかの様に儚い。
でも、鎮魂の儀式(戸締まり)を通して
今度はちゃんと理解し、お別れし、自らの意思で戸締まりをし、
「いってきます」
と進み出す。
そこに置いてある思いを胸に、
あった出来事を無理に忘れず、しっかりと振り返りながら明日の歩いていこうとしている。
そんなスズメの姿を見て、
私も1日1日を、もっと意識して生きたいと思えました。
《無念》という言葉で済ますのは簡単ですが、
人の心はそんなに単純ではないです。
複雑に絡み合う感情と念と共に
一歩ずつ地に足つけて
自分らしく生きていきましょ!
この作品を作ってくれて、本当にありがとうございました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
という訳で内容は割愛します。
実際に見て、それぞれが感じとって下さい。
参考にならないかもしれないですが、
私の場合はこんな感じでした(笑)
ps.芹澤推しです
【2024.4.10観賞】
すずめさん、何故標準語?
つい先ほど5日に渡ってぶつ切りで観終わりました。
オープニングの魅せかたは『もののけ姫』がオーバーラップし、一気に引き込まれました。確かに皆さんが仰っておられる通り、鈴芽の不可解な行動に「!?!?」になりましたが、120分超えには少ない、中弛みを感じず集中して観られました。日常の表現の美しさやリアリティは、「さすが新海監督!」と唸りました。
ダイジンを追って遠方を旅するモンタージュや、大学生の車に乗って東北地方へ行くモンタージュは、昭和歌謡を交え、この辺りでも新海監督らしい表現に釘付けになりました。
そしてクライマックスの“戸締まり”の場面、実際に起きた様々な災害や震災が脳裏に浮かび、同時にポジティヴな思いに共感し、涙腺が緩んでしまいました。イケメンとヒロインのロマンスは見たくありませんでした。世間様はああいうシーンがないと納得しないのでしょうか。
いわゆる“悪者”がいない作品ですが、スリリングで大迫力で感動的な作品です。是非ご覧下さい‼️
既視感
まず映像や音楽に関しては文句なく素晴らしかったな。
でももののけ姫とキミの名はからくる既視感を感じて残念だった。
それから現実に起きた災害を題材にしてたけど、悲惨な出来事をエンタメにしたって感じがして興ざめしたね。
地上波で流れた意味がわからない
シナリオ構成が…
全1288件中、101~120件目を表示