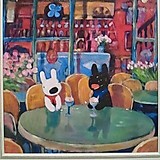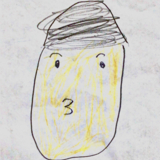コーダ あいのうたのレビュー・感想・評価
全732件中、81~100件目を表示
メインのストーリーは良いが、余計なエピソード挿入のせいで気持ち悪かった
ヒロインのルビーは高校生の女の子
両親と兄との4人家族
自分以外の家族は聴覚に障害があり耳が聞こえないため
(ルビーは聞こえる)
家業の漁船を手伝い、家族の通訳も務める
合唱クラブへ入部すると
顧問の教師がルビーの才能に気付き、バークリー音楽大学への進学を進める
自分のために実家を出て音大に進学するか
家に残り、障害を持つ家族を支えるかで悩むルビー
という物語
家族は耳が聞こえないために
歌で癒されたり、音楽で感動した経験が無いのだろう
バークリーへの進学を勧められるということのすごさを知らない
ルビーに家に残って仕事を手伝って欲しいと願う
物語はとてもいい
ただ、なんであんなにセックスの話が出てくるのだろう
歌の練習のために訪れた友達に
父親がコンドームをつけるしぐさをして見せたシーンはハッキリ言って気持ち悪かった
終盤で父親が娘の喉に手を当てて
振動で娘の歌を感じ取ろうとするシーンがあって
普通なら感動ものなのだが・・・・・
セックスの話が無ければ評価4.5だった
音が消えるシーンに注目
聴覚障害の俳優達が演じているからか、家族の会話はカナリ迫力のある手話シーンでした。娘の声が聞こえないってこういうことね、と分かるシーンは周りの人の表情で理解するしかないのだけど、なかなか感動しちゃいます。
いい映画だと思うから星4つにするけれど面白味はない
巷の評判はいいし、まあいい映画だとは思うけれど全く面白味のない作品だった。
二度の歌うシーンの演出が、あまりにもあざといとしてもなかなか良かったので、ギリギリ星4つにするけれど、単純に楽しめたかといえば星は2つでもいいくらい。
号泣とかいう言葉を事前に耳にしていたが、割とすぐに泣いてしまうタイプの自分でも号泣どころか涙の一滴も流れなかった。なんていうか、特にどのキャラクターも大して悩んだりしてないんだよね。秘められた想いとか変化がほとんどない。
ろう者の物語という意味ではなくて、この手の物語の場合、主人公が羽ばたく前に抱えた羽ばたけない悩みがあるものだが、基本的にそれがない。彼女は最初から羽ばたきたいと願っているのだ。
彼女の枷になるのが家族だという意味では斬新と言えなくもないが、家族間の溝が映画にするにはちょっと浅すぎる。
要は、この家族は最初から愛のあるいい家族で、漁についてうまくいかないことはあっても家族内にトラブルがほとんどない。それで最後に感動しろと言われてもちょっと無理。そんなんで泣けるなら街で家族連れを見かけるたびに泣くことになる。
娘に歌の才能があることを家族が直接理解出来ないこと、彼女が大学に行きたがっていることを後押しするのが兄貴で、母親はどちらかといえば反対する側だというところに目新しさは感じた。
娘が主人公の場合、大概は母親が理解者ポジションだからね。
本当に良かったのはここくらい。
久しぶりに傑作に出会えた
こんなに美しい作品をよく作ってくれた。
“歌”と“聴こえない”。その間にある愛。
演者たちの迫力がいい。そしてそのために撮影的な余計な演出を入れていないのがまたいい。
父だけに歌うシーンは心が震えた。
願わくば、さいごのオーディションは最後まで歌う姿を見たかった。たぶん永遠に見れたと思う。
久々に映画館に足を運ばせた
感動
さすがハリウッド
家族愛
歌唱指導の教師からバークレイ行きの話が出てきた時点で、結末は家族のためにバークレー行をあきらめるか、それとも自分の意志を貫き通してバークレイに行くのかが関心の中心になっていく。結果的には想定範囲内となるが、決め手となったのが、父親が彼女が歌っているときに喉に手を当てて、多分振動で彼女の歌声を感じとったのであろうが、いちばん感動したシーンであった。
涙ビダビダ
めっちゃ泣きました
最初から最後までお兄ちゃんが好きです(T . T)
他の家族は少なからずルビーに通訳として聴者との橋渡し役を期待している中、「家族の犠牲になるな」「俺たちは無力じゃない」とルビーの人生を尊重にし、自分たちを卑下せず強くいるお兄ちゃん…(T . T)(T . T)
耳が聞こえないから、という理由で漁を禁止になったシーンは最初は納得がいきませんでした。しかし後から考えてみると、緊急時の無線や他の船との衝突など安全面でも問題がありそうですし、他の人たちと違う、特別扱いをするのは逆に不平等なのではないかと感じました。
「無線は無視したらダメ」と同じ扱いをした上で、耳が聞こえないというハンディキャップに対応するために公的な制度(通訳ボランティアや無料で通訳を派遣できるサービスなど)が必要になるのではないかと思います。
ほかにも印象に残ったシーンとか考えさせられたシーンたくさんあるけど書ききれん〜〜〜トータル面白かったし歌と景色と人間美しすぎたそれだけでも価値がとてもあるみて〜〜〜
久しぶりに良い映画を見た。
音楽がとてもいい。爽やかに感動する映画。
2022アカデミー賞作品賞、脚色賞、助演男優賞を受賞。
遅ればせながら、やっと見ることができた。2014年のフランス語映画『エール!(フランス語版)』の英語リメイクであったことから、見るのを先送りにしていた。が、爽やかに感動する映画であった。ただ、下ネタが多いのでご注意を。
主人公(エミリア・ジョーンズ)が合唱部に入ると聞いて日本のクラシック的な合唱部かなと思いきや、ソウルフルな歌が続く。音楽教師はメキシコ出身でとてもハイテンションでポジティブ。彼女の才能を見抜いて熱く指導する。実際に役者もメキシコ出身のエウヘニオ・デルベス。スペイン語的な英語もいい。歌うことの基礎と厳しさを伝えてくれた。
印象に残った曲は、原曲でいうと
You're All I Need To Get By
(マーヴィン・ゲイ & タミー・テレル)
Both Sides Now(ジョニ・ミッチェル)
私も若い頃に聞いた馴染みの曲を、若いエミリア・ジョーンズ & Ferdia Walsh-Peeloが歌う。これがいい感じに仕上がっている。何度か出てくるのもいい。
ろうあ者のファミリーに一人だけ聴覚を持って生まれた娘(エミリア・ジョーンズ)。彼女が生まれたことは両親にとって必ずしも喜ばしいことではなかった。兄もろうあ者であるが、妹が生まれる前までは家族三人で幸せだったと。
兄が将来の妹を思う気持ちと、ろうあ者でも無力ではないと兄は力強く前向きに生きようとする。
私には、この音楽教師と兄の後ろ盾が心に響いた。
ギャガ・アカデミー賞受賞作品特集上映で見る。
良いストーリー
離別
良い話だった。
自分以外は聴覚に障害のある家族。
彼女は家族と健常者を繋ぐ唯一の手段だった。
幼い頃から通訳を務め、思春期の女の子には訳し難い言葉も飛び交う。なかなかにハードな人生だ。
そんな特殊な環境下だが、彼女は普通の女子高生で、恋に落ちる。
「歌」に出会うプロセスが微笑ましい。
その歌が、彼女と家族を変えていく。
彼女の歌声は美しく、とても豊かだ。
だけど、その環境が彼女の才能を阻む。
それと同時に健常者ではないない者だちの苦悩も描かれる。父親はコンプレックスを抱いてるし、母親は保守的だ。兄貴は反骨精神の塊のようだ。
母親は「理解してもらえない」と嘆く。
家族でありながらも、それほどの溝があるのだろう。
彼女は自分の才能に背を向けて、家族の犠牲になっていくかなような展開に。
それに反発する兄は、おそらく自分が出来なかった事を出来るのにやらない妹が歯痒いのであろう。
発表会の夜に、娘の歌をどうにか聞こうとする父親に胸が締め付けられる。
彼女は結局、家族から巣立つ。
今は苦しくとも、お互いが自立していく為の試練でもある。必要ならばやるしかないのだ。
そこから新たな仕組みが出来上がる。
あいのうたなんて副題が付いてるけど、その歌は聞こえてはこない。発表会の時の無音のシーンに哀しくなってくる。賞賛される娘の歌声を聴く事が出来ないのだ。
こんなにもどかしい事などない。
彼女が世界的な歌い手になっても、その声を聴く事が出来ないのだ。
オーディションの時、手話を交えて歌う彼女はとてもとても素敵だった。
とあるシーンに息を飲む
本作は名作です。見たこと無い人は是非見てください。
とくに学校の発表会のシーンでは両親の視点になると”ある演出”が起きるのですが、そこに息を飲みました。
(ああ…今まで映画を見てきたけどこの人たちには世界がこう見えていたのか…)
と思い知らされました…
名作です。
愛情表現の多様性
いよいよ歌が聴ける!というシーンで無音になる演出には驚いた。普通に歌が聞こえれば感動の場面になるはずが、無音の演出により不安感が引き出される。そして、娘の歌を聴きたい、娘の歌を感じたい、と願う父の思いに感情移入させられる。
登場人物がそれぞれ、独自の手法で愛情表現しており対比が面白い。
全732件中、81~100件目を表示