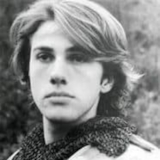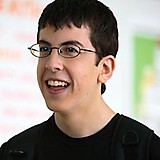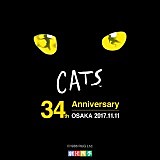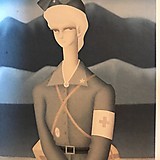コーダ あいのうたのレビュー・感想・評価
全732件中、581~600件目を表示
ルビーは「SOHO」に行かないでね😜
予告編で心掴まれました。
これは観なければならない‼️
健気なルビー。
家族唯一の健聴者として家業を手伝い、
学校で魚臭いと虐められても、
歌が好き♫
そして彼が好き♥️
V先生との出逢い。
彼女の才能が溢れ出す。
今度犬のマネしてから歌ってみよ👍
そして彼とのデュエット。
家での練習シーンvery good‼️
ギター弾きたくなりました❗️
そして仲直りからの・・・サイコー‼️👍
難聴の家族と、自分の将来。
彼女の背中を押したのは・・・ココですわ‼️😭
ここで泣けない人は人でない‼️
終始ルビーが可愛くて、
しかも歌上手くて大好き❤
他で好きになったのは、
やっぱり兄レオかな👍
正直、まあ想定内でした😅
でも涙は止まりませんでした😭
直近で観たのが、
「Lastnight in SOHO」なので、
色々境遇がダブりましたが、
こっちはアメリカ❓カナダ❓の話でしたね😅
温かい映画
佐久間P絶賛の作品。 いい映画。 ドキュメンタリーを見ているようだ...
大分バージョンアップしてます
エール!に比べると大分バージョンアップしており楽しめました。キャストも魅力的でファミリー全てが個性的です。私はお母さん以外はとても素敵に感じました。お母さんはあまりに利己的でせめて最後は理解を示すシーンが欲しかったです。
先生もエール!より魅力的でオーディションの時もよりリアルな流れになってました。歌のセレクトも練られており、歌詞に深い意味が含まれていた。ルビーの歌も感動的で心に響きました。物語のそこかしこに対比を取り入れているのも巧いと感じました。
が、もう少しルビーが去った後のプランを示したり、事業が好転してる事を分かりやすく描いてもよかったのでは?それと特にこのリメイクでは恋愛要素が無くても成立したのではないかな。その方がもう少し本質を濃く描けたのではないだろうか。
期待し過ぎていたけど、とてもウェルメイドな良い作品でした。泣きはしませんでしたが。
笑って、考えて、泣く…最高の映画
家族の中で唯一の健聴者である女子高校生の物語。予告編を観ただけで泣いてしまう映画だってことがわかる。聴覚障害者が抱える問題、家族愛、進学、恋、そして音楽。期待感しかなかった。
4人家族で自分だけが健聴者という状況は思った以上に過酷だし、しかも仕事が漁師。彼女が進学することの難しさを際立たせている。
でも、聴覚障害のある両親と兄の明るさ、そして何よりルビーの自然な感じがあるから全然説教くさくない。映画なんだから、あんな下世話な感じの障害者の描き方もいい。そして、ルビーを演じたエミリア・ジョーンズの歌声。これがこの映画を素晴らしいものにしている。しかも選曲もいい。あんな合唱でスターマンを歌うとは思わなかった。
聴覚障害のある家族がルビーの歌をどのように感じるのか、密かに気にしていた点なのだが、あんな演出があったか!と驚き、不思議と涙がこぼれてしまった。そして車の荷台で父親とルビーのシーンでも。あー、あれはダメだ、我慢できなかった。最高の映画だ。
ちなみにタイトルのCODAは最後に書かれる楽譜のこと(今までの家族のあり方の終わりを描くという意味)だと思っていたが、Children of Deaf Adultsのことだったんだな(ダブルミーニングだと思うけど)。知らなかった。そして、フランス映画のリメイクだということも。
なにげに母親を演じているのは「愛は静けさの中に」のマーリー・マトリンだったことにも驚いた。あの家族3人は実際に聴覚障害のある俳優らしいが、とてもいい演技だった。
これからいろんな人に勧めていかなければ!
エミリア·ジョーンズの切れのある演技
エミリア・ジョーンズの歌声が心に染み渡る
ジョニ・ミッチェルの名曲“青春の光と影”を荒削りながらも伸びやかな声で唄うシーンは凄く良い。
本家のジュディ・コリンズの繊細な歌声とはまた違った魅力がある。
宮本亜門風のV先生のアツい指導もウザさは無く、むしろ心から応援している姿が好印象。
聾唖の両親と兄も貧しいながらも卑屈になることなく、日々を明るく楽しく過ごしているのも素敵な感じ。
下品な表現も多いのだが、明るい家族の笑顔がいやらしさを吹き飛ばしてくれている。
娘にとっては一番の理解者であってほしい母が家族の中で最も娘の進学に否定的だというもどかしさもあったりするが、最終的には応援してくれるのも何かホッとする。
そして、何よりも印象的だったのは、クライマックスの発表会での1分間もの無音のシーン。
観客にも難聴者と同じ光景を伝えようとするこのシーンがこの作品を心に残る物にしてくれている。
星空の下、父が娘の歌声を感じ取ろうと喉元に手を添えながら、目の前で歌ってもらう場面。
歌い終えた娘・ルビーが父に「どうだった?」とばかりに目で問いかけるところもジーンときた。
鑑賞前は宣伝文句の『アカデミー賞最有力』というのは大袈裟だと思っていたが、作品賞はともかく、何がしかの賞は取るんじゃないかと思う秀作。
やはり、さすがGAGA。今回も良い作品を持ってきてくれた。副題の『あいのうた』も敢えて平仮名にしたところにこの作品へのこだわりを感じる。
希望あるヤングケアラー
明るい希望を持たせたヤングケアラーの家族の話だと思った。
自分以外は聾唖者の家族たちの通訳者となって生活している高校生ルビー。家族は結束力が強くとても仲良し。その中にあって、ルビーは家族にとって とても良い子。いい子ってのは、誰かにとって都合の良いいい子にもなる。
そう、家族にとって自分達の言葉を担う者としてルビーは、必要な良い子なのだ。ルビー自身家族という狭い世界に生きているため、自分の役割、自分の位置は家族の為にあるとして生活していた。そんな彼女の目を外に向けさせてくれたのは、音楽の先生だった。
ルビーには運良く『声』『歌』という特性が有りその事が認められる、けれどもその『声』を仲良しの家族は聞くことが出来ない悲しみ。でもそれを 彼女の第二の特性でもある手話を使って歌う姿を家族に見せるシーンや父親が骨伝導でルビーの歌を感じとる所は、この映画の最高感動シーンだった。
その後 家族達はようやく、ルビーを聾唖者の自分達の元から羽ばたかせる決心をする。ルビーと家族たち自身の自立をも描いていた。
本来なら、住んでいる地域コミュニティでこの家族のサポートをする人があっても不思議ではないが、その姿はなく、ただ遠巻きに軽んぜられている状況があるのはどうなんだろうと思った。
感動的に作ってあるからこそ、ルビーに『声』『歌』という特性が無かったらこの映画は成立しないのだ。私から見れば、いわゆる障害者に寄り添う下地があるアメリカでさえ本来は、そういうものなの?とちょっと考えさせられた。
歌唱シーンの演出に大号泣
ルビーの心に響かせる"音"や"言葉"、それを越えた体感型の豊かな歌声、台詞以上に体全身で表現をするキャストの演技力に強く胸を打たれました。
中盤コンサートの歌唱シーンの演出で私の涙腺は崩壊しました。
一件理解し合えない聾唖者の家族とその通訳係で健聴者の少女、けれど彼女の成長と共に変化する生活や関係性をユーモアも交えながら苦しい現実を乗り越え、そして家族の愛に満ちた逸品もの。
個人的には歌唱部顧問の先生が大胆かつ魅力的で、彼無しではルビーの明るい未来は無かったかもしれない、劇中を何度も盛り上げてもくれた。
そしてお兄ちゃんの役どころもまた素敵だった。
時折下品な場面や台詞があるのは両親の個性の一つ、多くの方に知って鑑賞して頂きたいお薦めの一作です。
『サウンド・オブ・メタル』と併せて観たい一作。
絆の深い家族だからこそ、胸に刺さるような一言を発することもある、それを痛切に理解させてくれる一作。
才能ある若者が、優れた指導者に見出されて未来を切り拓く。そんな物語はこれまで多く作られてきたけど、本作の主人公ルビーの持つ歌唱力という長所を、耳の聞こえない彼女の家族は直接体験することができません。そのもどかしさを抱きつつ、それぞれがどのように人生の決断をしていくのかが丁寧に描かれます。
漁業を営むルビーの家族は、時にかなりの憎まれ口を(手話で)叩くものの、深い愛情と絆で結ばれていることが、仕草の端々に伝わってきます。その一方で、漁船には必ず聴者が一人乗り込まなければならないという規則、そして仕事上の交渉の際に手話通訳が必要、といった現実上の要請もあり、学業と仕事の両方をルビーに背負わせざるを得ない状況にあります。さらに子どもを手放したくないという愛情、そして彼女の才能を理解してやれないという苛立ちがないまぜになって、ルビーが音楽の道に進みたい、という願いにも簡単には同意しません。諍いの時に交わされる言葉は、それが偽りのない心情に裏打ちされていることが分かるだけに、一層鮮烈です。
ルビーの家族を演じた3人の俳優はもちろん、本作のために手話を猛練習したというエミリア・ジョーンズの演技は素晴らしく、本当に家族のようです。彼女の才能を見出す音楽教師を演じるエウヘニオ・デルベスは、出身の設定からして彼そのもので、エキセントリックな指導場面を非常に生き生きと演じていました。一生懸命覚えたと思われる手話で対話する下りは、短いけど爆笑。
最初は軽薄に見えていたルビーの兄が、父と共に逆境を跳ね返していく姿は頼もしく、ルビーを産んだ時を回想する母の言葉の重さは深く胸に突き刺さります。そして終盤の、音にかかわるある演出に、『サウンド・オブ・メタル』を思い起こし、スクリーンを通してだけど、彼らの中に”入り込んだ”ような気がしました。
いい塩梅で爽やかに感動できます。
リメイク元の作品「エール!」は未見です。人間の内面や闇をぐりぐりとジリジリと炙り出すような・・・ヒリヒリしてゲロ吐きそうになるヒューマンドラマが好きな捻くれ者の私でも、さわやかなカンドー話は大好きなんですよ。
本作は家族愛っす!離れることのない心。伝わり合う愛情。嫌いだけど好き、好きだけど嫌い。だって家族なんだもん、大切なんだもん!聾唖の家族を歌声が繋技、そして未来の道を照らす・・・なんとまぁグッド・ストーリー!!!
いー塩梅の波風立ちます。
いー塩梅のスポ根、成長物語。
いー塩梅のユーモア。
いー塩梅の涙腺刺激。
いー塩梅の結末。
濃すぎず薄すぎずベタすぎずの感動エンタメ。ホント、いー塩梅(拍手)
本作のキーとなているであろう歌声の聴かせ方(見せ方かな?)は「ずるいっ!」って心で叫んじゃいましたよ。泣いちゃいますよ、これ。もー。やるなぁ。クライマックスの演出が良いのです。お父さん目線の一連の展開はマジでずるいよ。でもって、ラストのお父さん・・・なんだよ。なんだよー!です。
みなさん、最後の最後のお父さん、大注目ですよ。私はここで涙腺のダムは最大の決壊です。見せ方がいいんだよなぁ。普通で。それがいい。(ネタバレっぽく書いちゃってすみません)
これ見よがしの感動を大上段に構えた映画ではありませんが、爽やかな後味で劇場を出られます。おすすめですねー。
たくさんの人に観てほしい
久しぶりに映画館で観賞しましたが、この作品を選んで良かったです。
常に一緒だった家族が、ルビーの夢によって変化していく。自立においての葛藤は、子どもだけでなく大人にも言えることで、成長の過程でどれだけ互いに愛情があったのか窺えます。歌はやはり声だけで伝えるものじゃないことが分かる。なにより無音シーンが心に響きました。
PG-12なのがもったいないです。家族で、また若い方にも観ていただきたいので。夫婦仲が良すぎたせいでしょうか。合唱の先生も癖があって面白かったです。ルビーの友達も奔放のようでいて優しいのが分かる。
たくさんの人に観てほしいです。
君の声に恋してる
はい。よく私の馬鹿レビューを覗きに来て頂きました。
ありがとうございます。
いきなり映画の感想ですが、良かった❗️泣いた❗️笑った❗️こんな映画を待ってました。
脇道に逸れます。
割と最近の事です。知人のカナダ人のピアニストと話しをしていた時です。彼の知人が帰る時。突然・・・
♪さよなら さよなら さよーなら
えっ‼️カナダ人が何故、オフコースを知ってるの?
彼は言いました。日本に来て22年だよ。
なるほどね。
最近雑誌で知ったんですが・・・オフコースの「さよなら」にインスパイアされた名曲って知ってますか。誰でも知っています。それは・・・
山下達郎の「クリスマス・イブ」
「さよなら」の最後は
🎵 外は今日も雨 いつか雪になって僕らの心の中に
降り積もるだろう
かたや「クリスマス・イブ」の冒頭は
🎵 雨は夜更け過ぎに雪になって Silent night Holy night
ねっ?おんなじでしょ?達郎さんはこれなら俺にも作れると感じて作りました。
いやね・・・オフコースも山下達郎も大好きなのに気づかなかったのか‼️私は。ほんとに馬鹿だ‼️
それで、カナダ人のピアニストに聞いたんですよ。山下達郎は知ってる。彼曰く・・・
声が素晴らしい。
嗚呼・・・流石です。声は国境を越える。時代を越える。
コンサートは割と行ってますが、声に感動して泣いたのは達郎さんだけ。君の声に恋してる。
さて映画の感想ですが。私は主役のエミリア・ジョーンズの声に恋したようです。
この映画は家族、お仕事、青春、恋愛、色々な要素がありました。しかし着地点は音楽です。名曲を散りばめていましが・・・
Both Sides Now (青春の光と影 ジョニ・ミッチェル)
そうなんだよな。物事は一面からみちゃダメ! 上からも下からもね。オーディションのシーンね。先生、ミスタッチはグッドジョブ‼️
なんかねテーマが違うのは百も承知ですが、「天使にラブソングを」を思い出しましたよ。日本人は大体好きな映画です。
あと、フランス映画の「エール!」がベースらしいんですが、関係ないです。良い映画です。だってサザンオールスターズの「勝手にシンドバッド」だってパロディだったはずなのに、元歌より数段上の知名度。
もう一回言いますが エミリア・ジョーンズの歌声が本当に素晴らしい。いや多分、泣く映画じゃ無いんですが、頰を濡らしました。恥ずかしい。後ろの人も鼻をすすってました。同じ気持ちかな?
帰りは鼻歌で、青春の光と影。
大満足です‼️
読んで頂きありがとうございした。
全732件中、581~600件目を表示